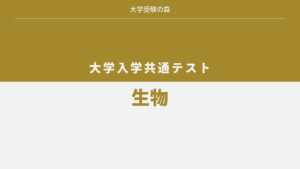解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
細胞におけるエネルギー代謝の全体像、特に解糖系、発酵、クエン酸回路、電子伝達系におけるATP、NADH、二酸化炭素の生成や消費に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
解糖系では、グルコース1分子を分解する過程で、前半のエネルギー投資期に2分子のATPを消費し、後半のエネルギー回収期に4分子のATPを合成します。したがって、全体としては2分子のATPが合成(純増)されるため、「消費される量のほうが多い」という記述は誤りです。
②【誤】
アルコール発酵は、解糖系でグルコースからピルビン酸が生成された後、ピルビン酸がエタノールと二酸化炭素に分解される過程です。この過程の目的は、解糖系で生じたNADHを酸化して$NAD^+$に戻し、解糖系を継続させることにあります。この過程でATPは合成されません。発酵全体で合成されるATPは、解糖系で得られる2分子のみです。
③【正】
クエン酸回路は、解糖系で生じたピルビン酸がアセチルCoAとなって取り込まれ、完全に分解される反応系です。この回路の反応過程では、脱水素酵素の働きによって多くのNADHやFADH2が生成されるだけでなく、基質レベルのリン酸化によってATP(動物細胞では多くの場合GTPが生成され、ATPに変換される)も合成されます。
④【誤】
呼吸の電子伝達系は、NADHやFADH2から電子を受け取り、最終的に酸素に電子を渡して水を生成する過程です。この過程で形成されるプロトンの濃度勾配を利用して、大量のATPが合成されます。二酸化炭素は、解糖系でできたピルビン酸がクエン酸回路に入る前(アセチルCoAになる際)や、クエン酸回路の過程で生成されるものであり、電子伝達系では生成されません。
問2:正解①
<問題要旨>
細菌が2種類の糖(グルコースとキシロース)を利用する際の優先順位と、それに伴う遺伝子発現調節(オペロン説)の仕組みについて、実験結果のグラフを読み解き考察する問題です。また、異なる条件下での増殖速度を比較し、集団内での競争の結果を予測する能力も問われています。
<選択肢>
空欄を含む文章を、図1と図2のグラフに基づいて論理的に考察します。
・アの考察
図1の野生株の培養結果を見ると、培養開始直後からグルコース濃度(破線)が減少し始め、約250分でほぼ消費し尽くされています。一方、キシロース濃度(点線)は、グルコースが消費されている間はほとんど変化せず、グルコースがなくなりかけた頃から減少し始めます。このことから、細菌Nはグルコースとキシロースの両方がある場合、グルコースを優先的に利用することがわかります。よって、アには「グルコース」が入ります。
・イの考察
キシロースオペロンは、キシロースの代謝に関わる酵素群の遺伝子です。図1を見ると、グルコースが存在する間(約0~250分)、キシロースオペロンの発現量(一点鎖線)はほぼ0に抑えられています。オペロン説において、遺伝子発現が抑制されている状態は、リプレッサーが遺伝子の発現を調節する領域であるオペレーターに結合している状態です。したがって、このときリプレッサーはオペレーターに結合していると考えられます。よって、イには「に結合して」が入ります。
・ウの考察
野生株(図1)と変異株M(図2)の増殖を比較します。培養開始600分後の細胞数(相対値)を見ると、野生株は約400に達しているのに対し、変異株Mは約200です。同じ時間でより多く増殖していることから、この混合糖培地の条件下では野生株のほうが増殖が速いと判断できます。増殖速度の速い方が集団内での競争に有利なため、両者を混ぜて培養すると、野生株が集団内で優勢になると考えられます。よって、ウには「野生株」が入ります。
以上の考察から、アに「グルコース」、イに「に結合して」、ウに「野生株」が入る②が正解となります。
問3:正解②
問3:正解2
<問題要旨> 科学的探究における仮説検証のための実験計画を立案する能力を問う問題です。「キシロースオペロンの発現は、キシロースによる誘導とグルコースによる抑制の両方で制御される」という仮説に対し、「グルコースのみによって制御される」という対立仮説の可能性を検討するために、どのような実験条件を比較すべきかを論理的に考える必要があります。
<選択肢> 提示された2つの仮説を整理します。 ・仮説A: キシロースが存在し、かつグルコースが存在しない場合に発現が誘導される。 ・仮説B: グルコースが存在しない場合に発現する(キシロースの有無は無関係)。
この「グルコースのみによって制御される」という仮説Bの可能性を検討するためには、まず、制御因子と疑われるグルコースとキシロースが、それぞれ単独で存在する場合にどのような影響を及ぼすかを確認することが、科学的探究の基本的なステップとなります。
・**「グルコースのみを含む培地」で培養する実験:この条件で発現が抑制される(OFFになる)ことを確認できれば、グルコースに抑制効果があることが示されます。 ・「キシロースのみを含む培地」**で培養する実験:この条件で発現が誘導される(ONになる)ことを確認できれば、キシロースに見かけ上の誘導効果があることが示されます。
この2つの実験結果を比較することで、「グルコースは発現を抑制し、キシロースは(少なくとも単独では)発現を誘導する」という基本的な情報を得ることができます。この情報があって初めて、「では、キシロースは本当に誘導に必須なのか?」あるいは「グルコースがないだけですべて説明できるのか?」という、より詳細な仮説の検討に進むことができます。
したがって、「『グルコースのみによって制御される』という可能性を検討するために」まず比較すべき実験の組合せとして、②「グルコースのみを含む培地」と「キシロースのみを含む培地」が最も適当です。
①【誤】
「キシロースのみを含む培地」と「どちらも含まない培地」の比較は、キシロースが誘導に必須かどうかを直接検証するための鋭い実験ですが、まずはそれぞれの糖の単独での効果を確認する②のステップが先立つのが適切と考えられます。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
生体膜における物質輸送に関わる様々なタンパク質(チャネル、担体、ポンプ)の機能や、輸送様式(受動輸送、能動輸送)の基本的な性質に関する理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
選択的透過性とは、特定の物質だけを選択して透過させる性質のことです。この性質は、輸送タンパク質が介在する輸送に共通してみられます。輸送タンパク質が関わる受動輸送(促進拡散)でも、能動輸送でも選択的透過性は見られるため、この記述は誤りです。
②【誤】
チャネルは、イオンなどを濃度勾配に従って輸送する受動輸送に関わります。担体(輸送体)は、グルコーストランスポーターのように受動輸送(促進拡散)に関わるものと、ナトリウムポンプのように能動輸送に関わるものの両方が存在します。したがって、「担体は受動輸送に関わらない」という記述は誤りです。
③【正】
水分子は比較的小さいため、脂質二重層を直接通過(単純拡散)することもできますが、その透過性は高くありません。細胞膜にはアクアポリンと呼ばれる水分子専用のチャネルタンパク質が存在し、これによって生体膜の水透過性は著しく高められています。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
ポンプは、ATPなどのエネルギーを利用して、濃度勾配に逆らって物質を輸送する「能動輸送」を担う輸送タンパク質です。ナトリウムポンプなどがその代表例です。したがって、「濃度勾配に逆らって物質を輸送することができない」という記述は誤りです。
⑤【誤】
アミノ酸は水溶性であり、また分子サイズも比較的大さいため、疎水性の脂質二重層を自由に透過することはできません。アミノ酸は、それぞれに対応した担体(輸送体)を介して細胞内に輸送されます。したがって、この記述は誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
気孔の開閉メカニズムに関する実験結果を読み解き、そこから導かれる正しい考察を選択する問題です。実験条件(明暗、K+の有無)と結果(孔辺細胞の膨張)の関係を正確に整理することが求められます。
<選択肢>
①【正】
実験1で、K+を含む溶液中で明所に置くと孔辺細胞が膨張し、K+を含まない溶液では明所でも膨張しなかったことから、細胞内へのK+の流入が膨張の原因であると考察できます。細胞内にK+が流入すると浸透圧が高まり、水が流入して細胞が膨張(膨圧が上昇)します。
②【誤】
実験1で、K+を含む溶液中でも暗所では形態が変化しなかったことから、孔辺細胞は「明所」でK+を取り込むと考えられます。
③【正】
K+があっても暗所では膨張せず、明所でもK+がなければ膨張しなかったことから、気孔の開口(孔辺細胞の膨張)には光とK+の両方が必要であると結論付けられます。
④【誤】
実験1では、孔辺細胞以外の表皮細胞はK+を含む溶液中で明所に置いても形態が変化しなかったとあります。暗所での変化についてはこの実験からはわかりません。
以上の考察から、適当な記述はaとcであり、その組合せである②が正解となります。
問3:正解③
<問題要旨>
ニューロンの興奮発生における膜電位の変化(静止電位と活動電位)と、それに関わるイオンチャネルやポンプの働きについての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
静止電位は、主にカリウムイオン(K+)が細胞内から細胞外へ漏出することで生じます。この電位を維持するため、細胞内は常に細胞外よりもK+濃度が高く保たれています。これはナトリウムポンプの働きによります。
②【正】
ニューロンの興奮は「全か無かの法則」に従います。刺激が一定の強さ(いき値)に達すると最大の大きさの活動電位が発生し、それ以上に刺激を強くしても活動電位の大きさは変わりません。
③【誤】
活動電位の発生時、膜電位が急激に上昇(脱分極)するのは、電位依存性ナトリウムチャネルが開き、細胞外から細胞内へナトリウムイオン(Na+)が「流入」するためです。選択肢は「流出する」とあるため誤りです。
④【正】
活動電位が最大値に達すると、次に電位依存性カリウムチャネルが開き、細胞内から細胞外へK+が流出することで、膜電位は静止電位に向かって下降(再分極)します。
⑤【正】
ナトリウムポンプは、ATPを消費して細胞内からNa+を3分子汲み出し、同時に細胞外からK+を2分子取り込む働きを持つ輸送タンパク質です。
問4:正解⑤
<問題要旨>
ニューロンにおける興奮の「伝導」と、シナプスにおける興奮の「伝達」のメカニズムに関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
⑤【正】
一度興奮した部位の電位依存性ナトリウムチャネルは、しばらく不活性化状態となり、新たな興奮を受け付けない「不応期」に入ります。このため、興奮は逆流せず、【イ】「一定方向に伝わる」ことになります。よって【ア】は「興奮しにくい」となります。
興奮が軸索末端のシナプスに到達すると、シナプス小胞が細胞膜に融合し、内部の神経伝達物質がシナプス間隙へ【ウ】「細胞外に放出される」ことによって、次のニューロンへ情報が伝達されます。
以上の組合せから、⑤が正解です。
第3問
問1:正解①②(順不同)
<問題要旨>
骨格筋の収縮メカニズム(滑り説)に関する基本的な知識を問う問題です。サルコメアの構造変化や、カルシウムイオン、ATPの役割を正確に理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
筋収縮が起こると、アクチンフィラメントがミオシンフィラメントの間に滑り込むため、サルコメア全体の長さと明帯(I帯)、H帯の長さは短くなります。しかし、ミオシンフィラメント自体の長さは変わらないため、暗帯(A帯)の長さは変化しません。
②【正】
通常時、トロポニンとトロポミオシンがアクチンフィラメント上のミオシン結合部位を覆っています。運動神経からの刺激で筋小胞体からカルシウムイオン(Ca2+)が放出され、これがトロポニンに結合すると、トロポミオシンの構造が変化して結合部位が露出し、アクチンとミオシンが結合できるようになります。
③【誤】
動物の筋細胞では、無酸素状態では解糖が進み、乳酸発酵によって乳酸が蓄積します。エタノールが蓄積するのは、酵母菌などが行うアルコール発酵です。
④【誤】
ATPが結合するのはアクチンではなく、ミオシンの頭部です。ATPがミオシン頭部に結合し、加水分解されるエネルギーを利用してミオシン頭部が動き、アクチンフィラメントを滑り込ませます。その後、別のATPが結合することでミオシン頭部はアクチンから離れます。
⑤【誤】
筋収縮は、アクチンフィラメントとミオシンフィラメントが互いに「滑り込む」ことで起こります。フィラメント自体が短くなるわけではありません。
⑥【誤】
単収縮が短い間隔で連続して起こると、収縮が重なり合ってより大きな収縮(強縮)が生じます。強縮の大きさは、単収縮の大きさよりも大きくなります。
問2:正解⑦
<問題要旨>
グリセリン筋(筋原繊維のみ)とスキンド筋(細胞膜以外は正常)を用いた実験結果から、筋収縮に必要な条件を考察し、新たな実験の結果を予測する問題です。それぞれの試料の構造の違いと役割を理解することが鍵となります。
<選択肢>
⑦【正】
実験5:グリセリン筋は筋原繊維のみでミトコンドリアを含まないため、グルコースからATPを合成できません。筋収縮には直接ATPが必要なので、グルコースを加えても収縮は起こりません(×)。
実験6:グリセリン筋は筋小胞体を持たないため、カルシウムチャネルを開く薬剤を加えても、Ca2+の供給源がありません。したがって、収縮は起こりません(×)。
実験7:スキンド筋は筋原繊維、ATP、筋小胞体など収縮に必要な要素をすべて含んでいます。実験1と同じ溶液(ATPと高濃度のCa2+)に浸せば、Ca2+が直接トロポニンに作用するため、筋収縮が起こります(○)。
以上の結果の組合せは⑦となります。
問3:正解①
<問題要旨>
ニワトリ胚の移植実験の結果から、体節の分化(特に皮筋節の形成)を制御する組織(誘導のシグナルを出す組織)の働きを解釈し、新たな実験(実験10)の結果を予測する問題です。発生における「誘導」の概念を正しく理解し、実験結果を論理的に考察する力が求められます。
<選択肢>
①【正】
まず、実験8と実験9の結果から、皮筋節の分化を制御するシグナルについて考察します。
・実験8では、本来は腹側にある脊索を体節の背側に移植すると、皮筋節が分化しなくなっています。このことから、脊索は皮筋節の分化を抑制するシグナルを出すと考えられます。
・実験9では、神経管の背側部分を移植すると、体節のほぼ全体が皮筋節に分化しています。このことから、神経管の背側は皮筋節の分化を誘導(促進)するシグナルを出すと考えられます。
これらの結果は、体節の各部分の運命が予め決まっているのではなく、周囲の組織からのシグナルによって決まること(誘導)を示唆しています。
次に、この考察を実験10に適用します。
・実験10では、体節を背腹逆になるように移植しています。
・これにより、移植された体節の**「元々の腹側だった部分」が背側に位置し、神経管の背側に近接します。
・逆に、「元々の背側だった部分」は腹側に位置し、脊索に近接**します。
誘導の原則に従うと、細胞の運命はその新しい場所のシグナルによって決まります。
・神経管の背側(誘導シグナル)に近接した「元々の腹側部分」は、新たに皮筋節へと分化します。
・脊索(抑制シグナル)に近接した「元々の背側部分」は、皮筋節への分化が抑制されます。
したがって、移植された体節では、その背側(元々は腹側だった領域)に皮筋節が形成されると予測できます。左側の正常な体節でも同様に背側に皮筋節が分化するため、結果として①の図が最も適当となります。
②【誤】
右側の移植された体節で皮筋節が全く分化しないという結果ですが、神経管背側からの誘導シグナルを無視しているため誤りです。
③【誤】
右側の移植された体節の腹側に皮筋節が分化するという結果です。これは、体節の運命が移植前に既に決定されており、場所を移動してもその運命を維持した場合に相当します。しかし、実験8・9の結果は、運命が周囲の環境(シグナル)によって決まる「誘導」が起きることを強く示唆しているため、この予測は実験結果と矛盾します。
④【誤】
右側の移植された体節で複数の皮筋節が分化する理由が、実験結果からは説明できません。
⑤【誤】
右側の移植された体節全体が皮筋節に分化するという結果ですが、これは実験9のように強力な誘導シグナルが全体にかかった場合であり、脊索からの抑制シグナルを考慮していないため誤りです。
第4問
問1:正解⑤
只今準備中です。しばらくお待ちください。
問2:(13)正解④ (14)正解⑤
<問題要旨>
短日植物であるジャガイモの塊茎形成における光周性のメカニズム、特に光受容体であるフィトクロムの関与を検証する実験計画を考察する問題です。暗期中断実験と、赤色光・遠赤色光の拮抗作用についての知識が問われます。
<選択肢>
(問13 ア)
ジャガイモは短日植物であり、塊茎の形成には限界暗期よりも長い連続した暗期が必要です。
実験1(短日条件)で形成され、実験2(長日条件)で形成されないことから、この性質が確認できます。
実験2では、長い暗期の途中に光を照射(光中断)すると、塊茎が形成されなくなっています。これは、光中断によって連続した暗期が分断されたためです。
フィトクロムは赤色光を吸収すると遠赤色光吸収型(Pfr型)に、遠赤色光を吸収すると赤色光吸収型(Pr型)に変化します。短日植物の花芽形成(この場合は塊茎形成)を抑制するのはPfr型です。
したがって、暗期を中断して塊茎形成を抑制する効果が最も高い光は、Pfr型を生成する【ア】「赤色光」です。実験3の条件は、赤色光による光中断で形成が抑制されることを示しています。
(問14 イ)
実験4では、実験3の赤色光照射の直後に別の光を照射することで、塊茎が形成される(抑制効果が打ち消される)結果が予測されています。これは、赤色光によって生成されたPfr型を、直ちにPr型に戻すことで光中断の効果をなくす操作です。Pfr型をPr型に戻す光は【イ】「遠赤色光」です。このような赤色光と遠赤色光の作用が可逆的である現象を、光可逆性といいます。
問3:(15)正解② (16)正解⑧
<問題要旨>
「塊茎形成が誘導されると、より多くの同化物が地下茎に分配される」という仮説を検証するための実験計画を立てる問題です。何を測定し、どのように計算して比較すれば仮説を検証できるかを論理的に考える必要があります。
<選択肢>
(問15 測定項目)
同化物は光合成によって生産された有機物(主に炭水化物)です。植物体に含まれる有機物の総量を比較するためには、水分量の影響を受けない「乾燥させた後の重量(乾燥重量)」を測定するのが最も適しています。生の重量では水分量が異なると正しく比較できません。デンプンは主要な貯蔵物質ですが同化物全体ではなく、灰は無機物、DNAはごく微量であるため不適切です。よって測定項目は②です。
(問16 計算式)
仮説は「地下茎に分配された同化物の比率」を比較するものです。
一定期間(試料1から試料2または3まで)に植物全体で増加した同化物の総量(=乾燥重量の増加分)のうち、どれだけの割合が地下茎の増加分になったかを計算します。
・栽培期間中の植物全体の乾燥重量増加量 = (x2+y2)-(x1+y1)
・栽培期間中の地下茎の乾燥重量増加量 = x2-x1
したがって、短日条件(塊茎形成条件)での分配比率は、x2-x1 / (x2+y2)-(x1+y1)となります。
同様に、対照となる長日条件での分配比率は、
x3-x1 / (x3+y3)-(x1+y1)
となります。
仮説が正しければ、短日条件での比率の方が長日条件での比率より大きくなるはずです。この比較を行っているのが⑧の計算式です。
第5問
問1:正解⑦
<問題要旨>
森林と牧草地という異なる植生の構造(生産構造図)と、それに伴う光環境(相対照度)の垂直的な分布の特徴を理解し、正しいグラフの組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
⑦【正】
森林の生産構造図:森林は、光合成を行わない幹や枝などの非同化器官の割合が大きく、高さがあります。光合成を行う葉(同化器官)は、主に光の当たる上層部(林冠)に集中します。問題文に「林床の草本層が発達した」とあるため、地表近くにも同化器官の層が見られます。これらの特徴に合致するのはグラフⓐです。(グラフⓑは同化器官が地表近くに集中しており、牧草地の特徴を示しています。)
森林の相対照度:光は上層の葉(林冠)によって大きく遮られるため、林冠から林床に向かうにつれて急激に暗くなります。林床の照度は非常に低くなります。このような光環境の変化を最もよく表しているのはグラフⓔです。
したがって、正しい組合せはⓐとⓔである⑦となります。
問2:正解②
<問題要旨>
表1のデータに基づいて、森林と農耕地の生態系について述べた記述の中から、考察として適当でないもの(誤っているもの)を一つ選ぶ問題です。数値を正確に読み取り、比較したり、生態学の基本的な知識と照らし合わせたりする力が必要です。
<選択肢>
①【誤】
この記述は「現存量と土壌有機物量の合計に占める現存量の割合」を比べています。計算してみましょう。
・熱帯の森林: 12 ÷ (18 + 12) = 12 ÷ 30 = 0.40 (40%)
・温帯の森林: 15 ÷ (13 + 15) = 15 ÷ 28 ≒ 0.54 (54%)
・亜寒帯の森林: 21 ÷ (9 + 21) = 21 ÷ 30 = 0.70 (70%)
計算結果から、この割合が最も高いのは「亜寒帯の森林」です。したがって、この記述は表の数値と合致せず、誤りです。
②【誤】
この記述は、亜寒帯の森林で土壌有機物量が多い「理由」について考察しています。亜寒帯では、低温のため分解者(微生物など)の活動が不活発です。そのため、有機物の分解速度が非常に遅く、生産された有機物が分解されずにどんどん蓄積していきます。これが土壌有機物量が多い最大の理由です。記述にある「年間の炭素固定量が少ないから」というのは、蓄積量が多い理由としては不適切です。したがって、この考察は生態学的に誤っています。
③【正】
森林から農耕地への変化による現存量の変化を見てみましょう。
・熱帯: 森林(12) → 農耕地(6)
・温帯: 森林(15) → 農耕地(7)
どちらの場合も現存量が大きく減少していることが、表のデータから読み取れます。したがって、この記述は正しいです。
④【正】
現存量と土壌有機物量の合計値を計算します。
・熱帯の森林: 18 + 12 = 30 (kg/m²)
・亜寒帯の森林: 9 + 21 = 30 (kg/m²)
両者の合計値は30で全く同じです。したがって、「ほとんど変わらない」という記述は正しいです。
問3:正解⑤
<問題要旨>
森林を農耕地に転用した際の、炭素循環への影響を考察する問題です。有機物の「分解」と「供給(純生産)」という二つの側面から、土壌有機物量が減少する理由を考えます。
<選択肢>
⑤【正】
森林が伐採され農耕地になると、地表が太陽光に直接さらされるため地表温度が高くなりやすく、土壌中の微生物の活動が活発になります。これにより、土壌有機物の【ア】「分解」が促進されます。
また、森林に比べて農耕地の【イ】「純生産」量(年間の有機物生産量)は一般に小さく、さらに収穫によって多くの有機物が農耕地の外に持ち出されるため、土壌への有機物の供給は森林だったときよりも【ウ】「少なく」なります。
分解は促進され、供給は減少するため、結果として土壌有機物量は減少していきます。この組合せは⑤です。
第6問
問1:正解⑥
<問題要旨>
生物学における「動物」というグループを定義する、普遍的な特徴は何かを問う問題です。多様な動物門全体に共通する性質を選ぶ必要があります。
<選択肢>
a【誤】
発生の過程で外胚葉・中胚葉・内胚葉の三つの胚葉が形成されるのは「三胚葉性動物」の特徴です。海綿動物や刺胞動物(イソギンチャクなど)は、それぞれ胚葉の分化が見られないか、二胚葉性であり、全ての動物に当てはまるわけではありません。
b【正】
動物は、植物のように光合成によって自ら有機物を生産する独立栄養生物ではなく、外部から有機物を取り込んでエネルギー源とする従属栄養生物です。これは全ての動物に共通する特徴です。
c【正】
動物界に属する生物は、アメーバなどの原生動物(現在はプロチスタ界などに分類)とは異なり、全て多数の細胞から構成される多細胞生物です。
したがって、全ての動物に当てはまるのはbとcであり、その組合せである⑥が正解です。
問2:(21)正解④ (22)正解② (23)正解⑤
<問題要旨>
与えられた生物(カメノテ、ウメボシイソギンチャク、ムラサキウニ)の特徴から、それぞれが動物の系統樹のどの分類群に属するかを同定する問題です。動物の系統分類に関する知識が問われます。
<選択肢>
(問21 カメノテ)
ノートの記述から、「節のある器官を持つ」「脱皮する」という特徴は、節足動物門に典型的です。節足動物門は、線形動物門などとともに脱皮を行う「脱皮動物」のグループ(系統樹のY)に分類されます。よってカメノテはYに含まれ、正解は④です。
(問22 ウメボシイソギンチャク)
「刺胞(刺細胞)を持つ」というのは、刺胞動物門(クラゲ、イソギンチャクなど)を特徴づける形質です。刺胞動物門は、海綿動物門よりは体制が複雑ですが、旧口動物や新口動物が分かれるよりも前に分岐したグループです。系統樹ではWの位置に相当します。よって正解は②です。
(問23 ムラサキウニ)
「原口は口にならない」という記述は、発生過程で原口が肛門になり、口は反対側に新しくできる「新口動物」の特徴です。ウニは棘皮動物門に属し、棘皮動物門は脊索動物門とともに新口動物のグループ(系統樹のZ)に分類されます。よってムラサキウニはZに含まれ、正解は⑤です。
問3:(24)正解④ (25)正解③
<問題要旨>
遺伝的浮動を模擬したシミュレーションの結果を読み取り、会話文の空欄を埋める問題です。図に示された系図を正確にたどり、各世代の個体の由来や数を数える必要があります。
<選択肢>
(問24 ア)
ハルさんの結果(図4)を完成させます。世代7を親としてサイコロを振った結果は「1, 1, 2, 3, 5, 6」です。世代7の個体は左から順に、C, C, C, F, F, F の系統に由来します。
サイコロの目に従って世代8の子を描くと、
・1番目の個体(C由来)が子を2個体残す。
・2番目の個体(C由来)が子を1個体残す。
・3番目の個体(C由来)が子を1個体残す。
・4番目の個体(F由来)は子を残さない。
・5番目の個体(F由来)が子を1個体残す。
・6番目の個体(F由来)が子を1個体残す。
結果として、世代8の6個体のうち、4個体がC由来、2個体がF由来となります。
会話文は「ア 個体が世代1の個体Ⓒに由来し、それ以外は個体Ⓕに由来しました」となっているので、【ア】には4が入ります。正解は④です。
(問25 イ)
アキさんの結果(図5)で、世代2の*印の個体で突然変異が起こったと仮定します。この変異遺伝子を持つ個体数を世代ごとに数えます。
・世代2:1個体(*印の個体)
・世代3:2個体
・世代4:2個体
・世代5:3個体
・世代6:2個体
・世代7:1個体
・世代8:0個体(この系統は途絶える)
したがって、一つの世代中に存在した最大の個体数は、世代5の3個体です。【イ】には3が入り、正解は③です。
問4:正解②
<問題要旨>
シミュレーションの結果も参考にしながら、実際の生物集団で起こる遺伝的浮動(偶然による遺伝子頻度の変動)に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
a【正】
シミュレーションの結果からもわかるように、ある個体の系統が子孫を残せずに途絶えることは頻繁に起こります。同様に、新しく生じた突然変異も、その変異を持つ個体が偶然子孫を残せなければ、集団に広まることなく失われてしまいます。これは特に有利でも不利でもない中立な変異で顕著です。
b【誤】
生存や繁殖に影響しない中立な突然変異でも、遺伝的浮動によって偶然その頻度を増し、やがては集団全体に広まる(固定される)ことがあります。アキさんのシミュレーション結果(図5)では、最終的に世代1の個体Aの系統だけが生き残っており、これは中立な遺伝子が偶然固定される例と見なせます。
c【正】
ある世代の全ての個体が、ある一つの対立遺伝子を持っている(その遺伝子が集団に固定された)ということは、その世代の全ての個体は、元々その対立遺伝子を持っていた一個体の祖先に系図をさかのぼることができる、ということを意味します。つまり、共通の祖先を持つことになります。
d【誤】
遺伝的浮動は、偶然による遺伝子頻度の「ゆらぎ」です。その影響は、サンプリングされる個体数が少ないほど、つまり集団サイズが小さいほど大きくなります。巨大な集団では、偶然による影響は相対的に小さくなります。
したがって、適当な記述はaとcであり、その組合せである②が正解です。