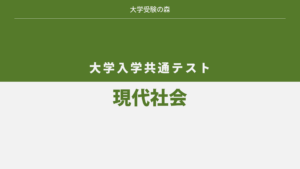解答
解説
第1問
問1:正解⑤
<問題要旨>
国籍取得の原則である血統主義と出生地主義を理解し、具体的な事例において重国籍や無国籍が発生する条件を正しく判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
イ、ウが誤りです。
②【誤】
ウが誤りです。
③【誤】
イ、ウが誤りです。
④【誤】
ウが誤りです。
⑤【正】
(ア、エに「A国」が入る)
・重国籍になるケース
A国籍(血統主義)とB国籍(出生地主義)の両方を取得する条件を考えます。
A国籍を取得するには、父または母がA国民である必要があります。
B国籍を取得するには、B国で出生する必要があります。
したがって、問題文の「B国民と【ア:A国】民との間の子Xが【イ:B国】において生まれた場合」、子はA国籍とB国籍を得て重国籍となります。よって、アには「A国」が入ります。
・無国籍になるケース
A国籍もB国籍も取得できない条件を考えます。
A国籍を取得できないのは、父も母もA国民でない場合です。
B国籍を取得できないのは、B国以外で出生した場合です。
したがって、問題文の「B国民と【ウ:B国】民との間の子Yが【エ:A国】において生まれた場合」、子は両親がB国民のためA国籍を取得できず、出生地がA国のためB国籍も取得できず、無国籍となります。よって、エには「A国」が入ります。
以上より、「A国」が入るのはアとエです。
⑥【誤】
イが誤りです。
⑦【誤】
イが誤りです。
⑧【誤】
アとエに「A国」が入ります。
問2:正解③
<問題要旨>
国家や国際社会に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
共通の言語や文化をもつ民族を基盤として構成された国家は「国民国家」あるいは「民族国家」と呼ばれます。積極国家とは、国民の福祉の向上のために、経済や社会へ積極的に介入する国家のことです。
②【誤】
主権国家を構成単位とする国際社会(主権国家体制)の成立の契機となったのは、三十年戦争の講和条約であるウェストファリア条約(1648年)です。ヴェルサイユ条約は第一次世界大戦の講和条約です。
③【正】
国際法の基本原則の一つに「主権平等の原則」があります。これは、国家は領土の大小や国力の強弱にかかわらず、法的に平等な権利と義務を持つとする考え方です。
④【誤】
国際法は、国家間の合意によって明文化された「条約」だけでなく、長年の国家間の慣行が法として認められた「国際慣習法」や、多くの国で認められている国内法の共通原則である「法の一般原則」も法源とします。
問3:正解④
<問題要旨>
民族や文化に関する用語や国際的な宣言についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
2007年の国連総会で「先住民族の権利に関する宣言」が採択されました。この宣言は、先住民族の自決権や、独自の文化・言語を保持し発展させる権利などを認めています。
②【正】
1960年の国連総会で「植民地独立付与宣言」が採択されました。これを契機に、特にアフリカでは多くの国が独立を果たし、この年は「アフリカの年」と呼ばれています。
③【正】
対抗文化(カウンター・カルチャー)とは、社会の主流となっている文化や価値観に異議を唱え、それに対抗しようとする文化のことです。1960年代のアメリカで、既存の体制や文化を批判した若者文化などがその典型例です。
④【誤】
記述の内容は「文化相対主義」の説明です。文化相対主義とは、文化に優劣はなく、それぞれの文化は固有の価値を持つとして互いに尊重し合うべきだという考え方です。エスノセントリズム(自民族中心主義)は、自らの文化を基準として他文化を評価し、優劣をつける考え方を指します。
問4:正解④
<問題要旨>
ステレオタイプに関する実験結果の表を正確に読み取り、データに基づいた正しい記述を選択する問題です。
<選択肢>
・表のデータの確認
ステレオタイプの強さ:A(6.8) > B(5.4) > C(4.4)
肯定的な印象の程度:C(6.8) > B(5.8) > A(5.2)
ア【誤】
「ステレオタイプの強さ」について、Aグループ(6.8)はBグループ(5.4)よりも高い数値を示しています。したがって、この記述は誤りです。
イ【正】
「肯定的な印象の程度」について、Cグループ(6.8)はBグループ(5.8)よりも高い数値を示しています。したがって、この記述は正しいです。
ウ【正】
CグループとAグループを比較します。「ステレオタイプの強さ」はCグループ(4.4)の方がAグループ(6.8)よりも低く、「肯定的な印象の程度」はCグループ(6.8)の方がAグループ(5.2)よりも高くなっています。したがって、この記述は正しいです。
以上より、正しい記述はイとウです。
問5:正解⑥
<問題要旨>
ルネサンス期から現代に至るヒューマニズム(人間中心主義)の思想の変遷に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
・アの判断
ルネサンス期のヒューマニズムは、中世ヨーロッパの神中心の考え方から脱却し、人間本来のあり方や理性を尊重しようとする思想です。したがって、「B 人間の自由な意思を尊重し、人間の罪深さを強調しない」が適切です。Aは中世キリスト教の人間観に近い記述です。
・イの判断
ルネサンス期のヒューマニズムは、古代ギリシャ・ローマの古典文学や哲学の研究を通じて人間性を探求したことから「人文主義」と呼ばれます。したがって、「C 人文」が適切です。「実存」主義は20世紀に広まった思想です。
・ウの判断
ガンディーが提唱した非暴力・不服従の思想の根底には、インドの宗教思想に由来する「アヒンサー(不殺生)」という考え方があります。したがって、「F アヒンサー」が適切です。「超人」は哲学者ニーチェの思想の中心概念です。
以上の組み合わせから、ア-B、イ-C、ウ-Fとなる⑥が正解です。
問6:正解⑤
<問題要旨>
ジェノサイド条約や国際人権制度に関する事実認識を問う問題です。各記述の正誤を正確に判断する必要があります。
<選択肢>
ア【正】
ジェノサイド条約は、第二次世界大戦中におけるナチス・ドイツによるユダヤ人等の組織的な大量虐殺(ホロコースト)への反省から、このような悲劇を二度と繰り返さないという国際社会の決意のもと、1948年に国連で採択されました。
イ【誤】
「存在していない」という部分が誤りです。国際人権規約(自由権規約)の個人通報制度など、人権条約で保障された権利を侵害された個人が、国連の規約人権委員会のような国際的な機関に通報し、救済を求めることができる制度が存在します。
ウ【誤】
日本はジェノサイド条約に署名はしていますが、2024年現在、まだ批准はしていません。批准とは、条約に法的に拘束されることへの国家の最終的な同意を示す手続きであり、日本国内ではその手続きが完了していません。
以上のことから、正しい記述はアのみであるため、⑤が正解となります。
問7:正解④
<問題要旨>
国連、特に安全保障理事会(安保理)の機能や権限に関する正確な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
安保理の議決において、常任理事国5か国の同意投票(拒否権が行使されないこと)を必要とするのは「実質事項」に関する決定です。「手続事項」については、常任理事国の拒否権の対象外であり、9か国以上の理事国の賛成で可決されます。
②【誤】
安保理は、核不拡散や核軍縮に関する決議を採択しています。例えば、2009年にはオバマ米大統領(当時)が議長を務め、「核兵器のない世界」の実現に向けた決議1887を全会一致で採択しました。
③【誤】
1990年のイラクによるクウェート侵攻に対し、安保理はイラクに即時無条件撤退を求める決議を採択しました。イラクがこれに応じなかったため、安保理は決議678を採択し、加盟国にあらゆる必要な手段(武力行使を含む)をとることを許可しました。これに基づき、多国籍軍が武力行使を行いました。
④【正】
「平和のための結集」決議は、朝鮮戦争の際にソ連が拒否権を行使し安保理が機能不全に陥ったことを契機に、1950年に国連総会で採択されました。これにより、安保理が機能しない場合に、総会が国際の平和と安全の維持について勧告できるようになりました。
問8:正解⑤
<問題要旨>
国連憲章に基づく軍事的措置(国連軍)と、国連平和維持活動(PKO)の基本原則との違いを正しく対比させる問題です。PKO三原則は「紛争当事者の同意」「中立・公平」「自衛のための必要最小限の武器使用」です。
<選択肢>
・アの判断
「国連の軍事的措置」が侵略国の意向にかかわらず「強制的に」実施されるのに対し、PKOは紛争を平和的に解決するための活動であり、その展開には紛争当事者すべての同意が必要です。したがって、アには「C 紛争当事国の同意に基づき、平和維持活動が展開される」が入ります(同意の原則)。
・イの判断
「国連の軍事的措置」が侵略国と被害国を明確に区別し、侵略国に対して行われるのに対し、PKOは特定の当事者に加担せず、中立・公平な立場で活動します。したがって、イには「A 紛争当事国の一方を利するまたは害する行為を控え、すべての紛争当事国を公平に扱う」が入ります(中立・公平の原則)。
・ウの判断
「国連の軍事的措置」が侵略を鎮圧するために本格的な「兵力が使用され」るのに対し、PKOの武器使用は、活動の妨害を排除したり、要員や保護対象者を守るための自衛的な場合に限定されます。したがって、ウには「B 平和維持部隊の要員およびその保護下にある者に対する攻撃に対処するために限り、必要最小限の武器を用いることができる」が入ります(武器使用の制限)。
以上の組み合わせから、ア-C、イ-A、ウ-Bとなる⑤が正解です。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
戦後から現代に至る日本の農業政策の変遷についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
高度経済成長期の1961年に制定された農業基本法は、農業従事者の所得向上などを目指しましたが、食生活の変化や国際化に対応できなくなり、1999年に廃止されました。代わって、食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的発展、農村の振興を基本理念とする食料・農業・農村基本法が制定されました。
②【誤】
米の生産調整(減反政策)は長年続けられてきましたが、国が生産数量目標を配分する方式は2018年産米をもって廃止されました。
③【誤】
日本が米の輸入を部分的に受け入れる(ミニマム・アクセス)ことになったのは、1993年に合意したガット(GATT)のウルグアイ・ラウンド交渉の結果です。東京ラウンドは1970年代の交渉です。
④【誤】
企業の農業への参入を促進するために改正されたのは、主に農地法です。新食糧法(1995年施行)は、食糧管理制度を廃止し、米の生産や流通を市場原理に委ねることを目的とした法律です。
問2:正解②
<問題要旨>
1990年代後半から2000年代初頭にかけて行われた橋本龍太郎内閣を中心とする行政改革についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
政治主導を強化するため、従来の政務次官制度が廃止され、新たに「副大臣」と「大臣政務官」が設置されました。
②【正】
縦割り行政の弊害などを是正し、内閣機能を強化するため、中央省庁等改革基本法に基づき、2001年1月に1府22省庁が1府12省庁(内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛庁(当時)、国家公安委員会)に再編されました。
③【誤】
小泉純一郎内閣で導入された構造改革特区制度は、地域限定で規制を緩和し、地域の活性化を図るものです。その対象事業は、教育、医療、農業、まちづくりなど多岐にわたり、社会福祉に限定されていません。
④【誤】
国家公務員の幹部人事を政府が一元的に管理する目的で設置されたのは、2014年の内閣人事局です。国家公務員倫理法(2000年施行)は、贈収賄事件などを背景に、公務員の職務執行の公正さに対する国民の信頼を確保するために制定されました。
問3:正解④
<問題要旨>
日本の租税制度の仕組みや機能に関する基本的な理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、国民一人ひとりに番号を付与し、社会保障、税、災害対策の分野で情報を一元管理することで、行政の効率化や国民の利便性向上などを図る仕組みです。
②【正】
環境税とは、地球温暖化対策の推進などを目的として、環境に負荷を与える行為(化石燃料の使用など)に対して課される税の総称です。日本では「地球温暖化対策のための税」が導入されています。
③【正】
ビルト・イン・スタビライザー(景気の自動安定化装置)とは、財政制度に組み込まれている、景気の変動を自動的に緩和する機能のことです。例えば、好況期には所得が増えるため累進課税によって税収が自動的に増え、景気の過熱を抑えます。逆に不況期には税収が減り、失業給付などが増えるため、景気の落ち込みを和らげます。
④【誤】
日本国憲法第84条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と定めています。これを「租税法律主義」といい、国民の代表である国会が定めた法律によらなければ、政府は租税を課すことはできません。
問4:正解④
<問題要旨>
日本の財政法、国債発行の現状、および憲法上の財政民主主義に関する理解を問う問題です。
<選択肢>
・アの判断
財政法第4条は、国の歳出は原則として公債(国債)以外の歳入で賄うことを定めており、例外として公共事業費などの財源となる建設国債の発行のみを認めています。しかし、グラフ1を見ると、歳入不足を補うための「赤字国債」が毎年発行されています。これは、財政法上の原則が形骸化し、毎年度「特例法」を制定することで赤字国債の発行が続けられている現状を示しています。したがって、「B 財政法上の原則にもかかわらず、一般的な経費に充てるための国債が毎年発行されている」が正しい記述です。
・イの判断
日本の憲法は、財政の運営について国民の代表である国会のコントロールを及ぼす「財政民主主義」を原則としています。予算を作成・提出する権限は内閣にありますが、その予算を審議し、承認する権限は国会にあります。これを「予算の議決権」といいます。したがって、「D 予算を議決する」が適切です。
以上の組み合わせから、ア-B、イ-Dとなる④が正解です。
問5:正解⑦
<問題要旨>
日本の国債発行残高の保有者構成の変化と、それを引き起こした金融政策に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
・Xの判断
グラフ2を見ると、2012年頃までは市中銀行が国債の最大の保有者でしたが、それ以降、日本銀行の保有比率が急激に上昇し、2022年時点では圧倒的な最大の保有者となっています。したがって、Xには「イ 日本銀行」が入ります。
・Yの判断
日本銀行が行う金融政策の主要な手段の一つに、金融市場で国債などの有価証券を売買することにより、市場の資金量を調整する操作があります。これを「公開市場操作(オープン・マーケット・オペレーション)」といいます。したがって、Yには「エ 公開市場操作」が入ります。
・Zの判断
日本銀行の国債保有が急増した直接的な契機は、2013年4月に導入された「量的・質的金融緩和」政策です。この政策では、2%の物価安定目標を達成するために、日本銀行が市中銀行から大量の長期国債を買い入れることで、市場に大規模な資金供給を行いました。したがって、Zには「オ 量的・質的緩和政策の採用」が入ります。
以上の組み合わせから、X-イ、Y-エ、Z-オとなる⑦が正解です。
問6:正解⑦
<問題要旨>
日本国憲法が定める政教分離原則に関する最高裁判所の判例についての正確な知識を問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
空知太神社訴訟で最高裁は、町が神社に町有地を無償で提供していたことは、特定の宗教団体への特別な便益提供にあたり、政教分離原則に違反するとの判断を示しました(違憲判決)。
イ【誤】
愛媛玉ぐし料訴訟で最高裁は、県知事が靖国神社などに公金から玉串料を支出したことは、特定の宗教団体との関わり合いが社会通念上相当とされる限度を超えており、政教分離原則に違反するとの判断を示しました(違憲判決)。
ウ【正】
津地鎮祭訴訟で最高裁は、市が体育館建設の際に神道式の地鎮祭を行い、公金を支出したことについて、その目的は工事の安全を祈願するという世俗的なものであり、その効果も神道を援助・助長するものとはいえないとして、政教分離原則には違反しないとの判断を示しました(合憲判決)。
以上より、正しい記述はウのみです。
問7:正解⑥
<問題要旨>
国の財政収支モデルを分析し、「プライマリー・バランス」と「累積債務残高の増減」という二つの指標の意味を理解して、各モデルを正しく評価する問題です。
<選択肢>
・プライマリー・バランス(基礎的財政収支)の計算
プライマリー・バランスは、国債の元利払いを除いた歳出(政策的経費)を、税収などで賄えているかを示す指標です。(計算式:税収など - 政策的経費)
A:75 – 70 = +5兆円(黒字)
B:85 – 70 = +15兆円(黒字)
C:70 – 70 = 0兆円(均衡)
よって、ア「プライマリー・バランスが均衡している」のはモデルCです。
・累積債務残高の増減の判断
累積債務残高が増えるか減るかは、その年度の新規国債発行額と、過去の国債の元本返済額を比較します。
新規発行額 > 元本返済額 → 累積債務は増加
新規発行額 < 元本返済額 → 累積債務は減少
A:新規発行 25 = 元本返済 25 → 残高は変わらない
B:新規発行 15 < 元本返済 20 → 残高は減少
C:新規発行 30 > 元本返済 25 → 残高は増加
よって、イ「国の累積債務残高が減少する」のはモデルBです。
以上の組み合わせから、ア-C、イ-Bとなる⑥が正解です。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
再生医療分野におけるiPS細胞とES細胞の違いを正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
・アの判断
2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授の業績は、人工多能性幹細胞、すなわち「iPS細胞」の作製です。したがって、アには「Q iPS細胞」が入ります。ES細胞(胚性幹細胞)は、iPS細胞より先に作製されていましたが、受精卵(胚)を壊して作るため倫理的な課題がありました。
・イの判断
iPS細胞は、人間の皮膚や血液などの体細胞に、数種類の遺伝子を導入することによって作製されます。これにより、受精卵を使うことなく、様々な細胞に分化できる多能性を持った細胞を作ることが可能になりました。したがって、イには「S ヒトの体細胞に特定の遺伝子を導入して」が入ります。「R 受精卵の初期段階の胚を壊して」作るのはES細胞です。
以上の組み合わせから、ア-Q、イ-Sとなる④が正解です。
問2:正解②
<問題要旨>
女性の社会進出や労働環境に関連する日本の現行法制度についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
労働基準法の改正により、かつて存在した女性の時間外労働・休日労働・深夜業の規制(女子保護規定)は、妊産婦などを除いて原則として撤廃されています。
②【正】
男女雇用機会均等法は、募集・採用、配置・昇進などにおける男女差別を禁止するとともに、事業主に対して職場におけるセクシュアル・ハラスメントを防止するための措置(相談窓口の設置など)を講じることを義務づけています。
③【誤】
育児・介護休業法は、性別にかかわらず、子どもを養育したり家族を介護したりする労働者が休業を取得する権利を保障しています。男性も育児休業を取得できます。
④【誤】
男女共同参画社会基本法は、男女間の事実上の格差を改善するため、国や地方公共団体、事業主が必要な範囲内で行う積極的改善措置(ポジティブ・アクション)を認めています。
問3:正解②
<問題要旨>
子どもの権利、教育に関する国民の義務、法律上の少年の定義に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
ア【正】
1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」は、子どもを権利の主体として位置づけ、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利などを保障しています。第12条では、子どもが自分に関係のある事柄について自由に意見を表す権利(意見表明権)を定めています。
イ【正】
日本国憲法第26条第2項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めています。これは、勤労、納税と並ぶ国民の三大義務の一つです。
ウ【誤】
日本の少年法第2条第1項で、「少年」とは「二十歳に満たない者」と定義されています。2022年に民法が改正され成年年齢は18歳に引き下げられましたが、少年法の適用対象年齢は20歳未満のままです。
以上より、正しい記述はアとイです。
問4:正解③
<問題要旨>
生命倫理をめぐる近年の法制度や国際的なルールに関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
日本では「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(クローン技術規制法)」により、ヒトのクローン個体を作製することは禁止されています。
②【誤】
胎児の染色体異常などを調べる出生前診断は、日本では禁止されておらず、一定の条件下で実施されています。ただし、命の選別につながる可能性など、倫理的な課題が指摘されています。
③【正】
ヒトゲノム(人間の全遺伝情報)の解析が進む中で、遺伝情報に基づく差別や人権侵害が懸念されるようになりました。こうした背景から、1997年にユネスコ総会で「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」が採択され、ヒトゲノム研究における人権擁護の原則が示されました。
④【誤】
遺伝子組換え生物等の使用による生物多様性への悪影響を防止するための国際的な議定書は「カルタヘナ議定書」です。「モントリオール議定書」は、オゾン層を破壊するフロンガスなどの化学物質の規制に関する議定書です。
問5:正解③
<問題要旨>
日本の国会(衆議院・参議院)の権限や、国会議員の持つ特権についての正確な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合、衆議院が「出席議員の3分の2以上」の多数で再び可決すれば、その法律案は法律となります(衆議院の優越)。「過半数」では成立しません。
②【誤】
内閣不信任を決議する権限は「衆議院のみ」に認められています。この決議が可決された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければなりません。
③【正】
日本国憲法第50条は、国会議員の「不逮捕特権」を定めています。これにより、国会議員は、国会の会期中は、院外での現行犯逮捕などを除き、その議院の許諾がなければ逮捕されません。
④【誤】
国会議員の「免責特権」(憲法第51条)は、議員が議院で行った演説、討論又は表決について、「院外で」民事上・刑事上の責任を問われないとするものです。議院の内部における懲罰などの責任(院内の責任)まで免除されるわけではありません。
問6:正解④
<問題要旨>
障害の捉え方に関する「医学モデル」と「社会モデル」の違いを理解し、具体的な支援策を分類する問題です。
<選択肢>
・医学モデル:障害を個人の心身機能の問題と捉え、医療的な治療やリハビリテーションによって個人を社会に適応させようとする考え方。
・社会モデル:障害は個人の機能だけでなく、社会にある物理的・制度的・文化的な障壁によって作り出されるものと捉え、社会の側がその障壁を取り除くべきだとする考え方。
ア【「医学モデル」に近い】
補聴器が合っているか検査を勧めるのは、個人の聴覚機能の改善に焦点を当てたアプローチであり、医学モデルの考え方に近い支援です。
イ【「社会モデル」に近い】
板書が読み取れないという困難に対し、大学という社会環境の側が「学生支援員を配置する」という形で障壁を取り除こうとする支援であり、社会モデルの考え方に基づいています。
ウ【「社会モデル」に近い】
図書館の段差という物理的な障壁に対し、市という社会の側が「スロープを設置する」ことで環境を改善しようとする支援であり、社会モデルの考え方に基づいています。
以上より、「社会モデル」に基づく支援に近いものはイとウです。
第4問
問1:正解①
<問題要旨>
経済学者のリカードが提唱した「比較生産費説」の基本的な考え方(機会費用の計算)を理解し、表のデータから正しい結論を導き出す問題です。
<選択肢>
・まず、各国が各財を1単位生産するための「機会費用」(ある財を1単位多く生産するために諦めなければならない、もう一方の財の量)を計算します。
【X国】
・毛織物1単位の機会費用=ぶどう酒 (50人 / 40人) = 1.25単位
・ぶどう酒1単位の機会費用=毛織物 (40人 / 50人) = 0.8単位
【Y国】
・毛織物1単位の機会費用=ぶどう酒 (80人 / 160人) = 0.5単位
・ぶどう酒1単位の機会費用=毛織物 (160人 / 80人) = 2単位
①【正】
「毛織物1単位の生産を取りやめたときに増産できるぶどう酒の生産量」とは、毛織物1単位の機会費用のことです。X国は1.25単位、Y国は0.5単位なので、X国の方がY国よりも大きくなります。
②【誤】
「ぶどう酒1単位の生産を取りやめたときに増産できる毛織物の生産量」とは、ぶどう酒1単位の機会費用のことです。Y国は2単位、X国は0.8単位なので、Y国の方がX国よりも大きくなります。
③【誤】
労働者一人当たりの生産量は、生産に必要な労働者数の逆数で比較できます。毛織物(X国:1/50 > Y国:1/80)、ぶどう酒(X国:1/40 > Y国:1/160)ともに、X国の方がY国よりも生産性が高い(労働者数が少なくて済む)ため、一人当たりの生産量は大きくなります。
④【誤】
比較生産費説では、各国は機会費用が小さい財(比較優位を持つ財)の生産に特化すべきです。毛織物の機会費用はY国(0.5)の方が小さく、ぶどう酒の機会費用はX国(0.8)の方が小さいです。したがって、Y国が毛織物、X国がぶどう酒に特化するのが効率的です。問題文の特化方法は非効率です。
問2:正解①
<問題要旨>
世界の紛争や核兵器をめぐる国際情勢に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
第二次世界大戦後、1948年にイスラエルが建国を宣言したことをきっかけに、周辺のアラブ諸国との間で第一次中東戦争が勃発しました。このパレスチナの地をめぐるアラブ人とユダヤ人の対立は、現在に至るまで続くパレスチナ紛争の根幹となっています。
②【誤】
ダルフール地方で激しい紛争が起きたのはスーダンです。2011年に南スーダンが分離独立しました。ソマリア内戦は別の国で起きた紛争です。
③【誤】
包括的核実験禁止条約(CTBT)は1996年に国連で採択されましたが、発効するためには核開発能力を持つ特定の44か国すべての批准が必要です。しかし、アメリカ、中国、インド、パキスタン、北朝鮮などが未批准のため、現在も発効していません。
④【誤】
核兵器保有国の増加を防ぐことを目的とする核拡散防止条約(NPT)は、1995年の再検討・延長会議において、無期限で延長されることが決定しました。
問3:正解②
<問題要旨>
南北問題の解決に向けた取り組みの一つである「フェアトレード」の目的と仕組みを正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
A【正】
フェアトレードは、開発途上国の小規模生産者や労働者が生産した原料や製品(コーヒー、カカオ、綿製品など)を、公正な価格で継続的に購入することを通じて、生産者の生活向上を支援する貿易の仕組みです。
B【正】
公正な取引を保証することで、開発途上国の生産者が経済的に自立し、貧困から脱却することを目指す取り組みです。
C【誤】
関税を引き上げるのは、国内産業を保護するための保護貿易政策であり、フェアトレードの考え方とは異なります。フェアトレードは、自由貿易の枠組みの中で、より倫理的で公正な取引を実現しようとする民間の運動です。
以上より、正しい記述はAとBです。
問4:正解③
<問題要旨>
GDP(国内総生産)の計算に含まれるものと含まれないものを、与えられたルールに基づいて判断する問題です。
<選択肢>
A【含まれる】
農家が生産した農産物を市場で販売せず、自家消費した場合、その分は市場価格で評価され、GDPに加算されます。これは「帰属計算」の一例です。条件③に該当します。
B【含まれない】
親が同居の子どもに渡すおこづかいは、生産活動の対価ではなく、家族内での所得の移転にすぎないため、GDPには計上されません。条件②に該当します。
C【含まれる】
工場が公害防止のために排水処理施設を建設した場合、その建設費用は企業の設備投資としてGDPに計上されます。公害というマイナス要因への対策費がGDPを押し上げることは、GDPの限界の一つとして指摘されますが、計算ルール上は含まれます。条件①に該当します。
以上より、GDPに含まれるのはAとCです。
問5:正解④
<問題要旨>
所得格差を示すジニ係数の表を読み解き、各国の格差の状況と、所得再分配政策の種類を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
・まず、表の数値を整理します。ジニ係数は0に近いほど格差が小さいことを示します。
【当初所得(再分配前)の格差】
B国(0.34) < A国(0.46) < C国(0.51)
【再分配後の所得の格差】
C国(0.26) < B国(0.29) < A国(0.39)
【所得再分配による格差是正効果(当初 – 再分配後)】
C国(0.25) > A国(0.07) > B国(0.05)
・説明文の空欄を埋めます。
ア:当初所得の格差が最も小さいのは「B国」。
イ:再分配後の所得の格差が最も大きいのは「A国」。
ウ:格差是正効果が最も大きいのは「C国」。
・政策を判断します。
A国(イ国)が格差是正を行うための政策を考えます。
I:B国(ア国)のように、当初所得の格差そのものを小さくする政策。これは、雇用機会の創出や賃金格差の是正など、市場メカニズムへの介入を意味します。「Q 最低賃金を引き上げる」は、低所得層の賃金を底上げするため、当初所得の格差を縮小させる効果があります。
II:C国(ウ国)のように、再分配後の所得の格差を小さくする政策。これは、税制や社会保障制度を通じて、所得の再分配機能を強化することを意味します。「P 資産課税を強化する」は、富裕層からより多く税を徴収し、再分配の原資とするため、再分配機能を強化する政策です。
問題ではイ、ウ、Iの組み合わせが問われているので、「イ:A国」「ウ:C国」「I:Q 最低賃金を引き上げる」となります。これに合致するのは④です。
問6:正解②
<問題要旨>
福沢諭吉、新渡戸稲造、夏目漱石という日本の近代思想家の文章を読み、それぞれの思想的特徴から誰の文章かを特定する問題です。
<選択肢>
ア【新渡戸稲造】
文章中に「武士道」という明確なキーワードがあり、知識が実践と結びついて初めて価値を持つという考え方が述べられています。これは、新渡戸稲造が著書『武士道』で論じた中心的な思想です。
イ【福沢諭吉】
「天は富貴を人に与えずしてこれをその人の働きに与うる」「人は生れながらにして貴賤貧富の別なし」という部分は、福沢諭吉の『学問のすゝめ』の有名な一節「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」の精神と合致します。生まれや身分ではなく、個人の学問や努力が重要であるという近代的な人間観を示しています。
ウ【夏目漱石】
西洋の評価を鵜呑みにするのではなく、「私が独立した一個の日本人として」自分の意見を持つべきだという主張は、夏目漱石が講演「私の個人主義」などで説いた「自己本位」の思想を反映しています。他者の価値観に流されず、自己の内面から発する考えを大切にする姿勢を説いています。
したがって、新渡戸稲造はア、夏目漱石はウとなり、その組み合わせである②が正解です。
第5問
問1:正解④
<問題要旨>
在留資格別の在留外国人数に関する統計表を正確に読み取り、特に「増加率」の計算も含めて、記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
「専門的・技術的分野」と「技能実習」の人数を比較すると、2019年には技能実習(411千人)が専門的・技術的分野(408千人)を上回っています。したがって、「一貫して上回っている」という記述は誤りです。
②【誤】
2019年から2020年にかけて、「身分又は地位」(1,185→1,194千人)と「専門的・技術的分野」(408→428千人)の人数はどちらも増加しています。したがって、「減少している」という記述は誤りです。
③【誤】
2013年から2014年の増加率を計算します。
・留学:(215 – 193) / 193 ≒ 11.4%
・技能実習:(168 – 155) / 155 ≒ 8.4%
・専門的・技術的分野:(214 – 205) / 205 ≒ 4.4%
「留学」の増加率は、他の二つよりも高くなっています。したがって、「低い」という記述は誤りです。
④【正】
2018年から2019年の増加率を計算します。
・技能実習:(411 – 328) / 328 ≒ 25.3%
・留学:(346 – 337) / 337 ≒ 2.7%
・専門的・技術的分野:(408 – 351) / 351 ≒ 16.2%
「技能実習」の増加率が、他の二つよりも明らかに高くなっています。したがって、この記述は正しいです。
問2:正解①
<問題要旨>
異文化接触における移住者の態度を4つの類型(統合、同化、分離、周縁化)に分類し、それぞれの定義に合致する具体的なインタビュー事例を特定する問題です。
<選択肢>
・各類型の定義
A【統合】:自文化を維持し、移住先の文化との関係も求める。
C【分離】:自文化を維持し、移住先の文化との関係は望まない。
・インタビュー事例の分析
ア:母国の料理を作る(自文化の維持)一方で、移住先の国の料理も作って楽しみたい(移住先文化との関係を求める)と考えており、これはA【統合】の事例です。
イ:母語や母国のテレビ番組に触れ、母国出身者と交流する(自文化の維持)一方で、移住先の国の人との交流の必要性を感じない(移住先文化との関係を望まない)としており、これはC【分離】の事例です。
ウ:母国の風習を避ける(自文化を維持しない)一方で、移住先の伝統行事にも参加しない(移住先文化との関係も望まない)としており、これはD【周縁化】の事例です。
したがって、Aに当てはまるのはア、Cに当てはまるのはイとなり、その組み合わせである①が正解です。
問3:正解⑧
<問題要旨>
「ボルダルール」という特殊な選挙制度の仕組みを理解し、具体的な投票結果から当選者を計算するとともに、一般的な選挙制度(単記式)との違いや戦略について考察する問題です。
<選択肢>
・ボルダルールでの得点計算
1位に3点、2位に2点、3位に1点が与えられます。
X候補:(4万票×3点) + (3万票×1点) + (2万票×1点) = 12 + 3 + 2 = 17万点
Y候補:(4万票×1点) + (3万票×3点) + (2万票×2点) = 4 + 9 + 4 = 17万点
Z候補:(4万票×2点) + (3万票×2点) + (2万票×3点) = 8 + 6 + 6 = 20万点
最高得点はZ候補なので、アには「c Z候補」が入ります。
・単記式での当選者の計算
1位に投票された票数のみを比較します。
X候補:4万票
Y候補:3万票
Z候補:2万票
最多得票はX候補なので、イには「a X候補」が入ります。
・ウの判断
単記式では1位票をいかに多く集めるかが重要ですが、ボルダルールでは2位、3位の票も得点になります。今回の結果でZ候補が当選したのは、1位票は最下位でも、全ての有権者から2位または3位として支持され、極端に低い評価(3位)を受けなかったためです。このことから、ボルダルールで当選するためには、一部から熱狂的に支持されるだけでなく、「e 3位候補として投票されないように、すべての有権者に配慮する」戦略が有効だとわかります。
以上の組み合わせから、ア-c、イ-a、ウ-eとなる⑧が正解です。
問4:正解③
<問題要旨>
多様な文化集団が共生する社会(多文化主義)を実現するための公的な取り組みとして、適切な事例を選択する問題です。問題文の「それぞれの文化集団が元々継承してきた文化を尊重するため公的支援を行う」という趣旨に合致するかを判断します。
<選択肢>
ア【適切】
各文化集団の子どもたちが自らの文化への理解を深めるための教材作成を公的に助成し、公立学校で配布することは、文化の尊重と公的支援という趣旨に合致する多文化主義的な取り組みです。
イ【不適切】
生活習慣の変更を求め、集団移住を推進するのは、文化の尊重ではなく、むしろ多数派の価値観(この場合は自然保護)を少数派に押し付ける同化主義的な政策であり、問題文の趣旨とは異なります。
ウ【適切】
国内に住む様々な文化集団の伝統行事の維持・継続を、予算措置や法制定によって公的に支援することは、それぞれの文化を尊重し、その継承を助ける多文化主義的な取り組みです。
以上より、取り組みとして考えられるものはアとウです。