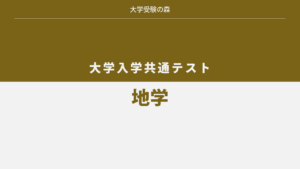解答
解説
第1問
問1:正解①
<問題要旨>
気象衛星の可視画像と赤外画像からわかる雲の性質を理解し、画像の特徴から雲の種類を推定する問題です。
<選択肢>
①【正】
まず、空欄アについて考えます。問題文に「対流圏は高度が高くなるほど気温が低い」とあり、図1からは「赤外画像で白い」ほど「雲頂温度が低い」ことがわかります。この二つを組み合わせると、赤外画像で白く見える雲ほど、雲頂の高度が高いということになります。したがって、アには「高い」が入ります。
次に、空欄イについて考えます。領域Aの雲は「可視画像では白く、赤外画像では黒く見える」とあります。可視画像で白く見えるのは、雲が太陽光を強く反射していることを意味し、雲粒が密であったり、雲が厚いことを示します。一方、赤外画像で黒く見えるのは、図1から雲頂温度が高いことを意味します。雲頂温度が高いということは、雲頂の高度が低いということです。
以上のことから、この雲は「高度が低く、太陽光をよく反射する雲」であり、これは下層雲(層雲や層積雲など)の特徴と一致します。上層雲や積乱雲は雲頂高度が高いため、赤外画像では白く映ります。
よって、アに「高い」、イに「下層雲」が入るこの選択肢が正解です。
②【誤】
アは正しいですが、イが誤りです。領域Aの雲は赤外画像で黒く見える(雲頂温度が高い)ため、雲頂高度が高い上層雲ではありません。
③【誤】
アは正しいですが、イが誤りです。積乱雲は雲頂高度が非常に高いため、赤外画像では明るい白に映ります。
④【誤】
アが誤りです。赤外画像で白い雲は雲頂温度が低く、高度は高くなります。
⑤【誤】
アが誤りです。また、イも領域Aの雲の特徴と一致しません。
⑥【誤】
アが誤りです。また、イも領域Aの雲の特徴と一致しません。
問2:正解④
<問題要旨>
プレートの沈み込みに伴う地殻変動について、地震発生前のひずみの蓄積と、地震発生時のひずみの解放(弾性反発)の様子を正しく理解できているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
西向きの変位を示しており、地震発生前のひずみが蓄積していく方向です。地震発生時のひずみの解放とは逆の動きです。
②【誤】
東向きの変位を示していますが、震源域から遠い内陸部ほど変位量が大きく、近い沿岸部で小さくなっており、実際の現象とは逆です。
③【誤】
西向きの変位を示しており、地震発生前の動きです。
④【正】
問題の図3では、太平洋プレートの沈み込みにより、陸側のプレートが西向きに引きずられてひずみが蓄積している様子が示されています。東北地方太平洋沖地震では、この蓄積されたひずみが解放され、陸側のプレートが元に戻ろうとする東向きの動き(弾性反発)が起こりました。この変位は、プレート境界に近い太平洋沿岸で最も大きく、そこから離れるにつれて小さくなります。この選択肢の図は、太平洋沿岸部で最も変位が大きく、全体として東~南東方向へ移動しており、弾性反発の様子を正しく示しています。
問3:正解①
<問題要旨>
金属資源が生成される熱水鉱床について、その成分と、日本に特徴的な鉱床の種類についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
熱水鉱床は、マグマの熱水に溶けやすい金、銅、鉛、亜鉛などの金属元素が沈殿・濃集して形成されます。したがって、ウには「金、銅、鉛」が入ります。また、「過去の海底の熱水噴出によって形成された」「日本の代表的な鉱床」という記述は、秋田県などで産出された黒鉱鉱床の特徴と一致します。黒鉱鉱床は、銅、鉛、亜鉛などを豊富に含みます。よって、この組み合わせは正しいです。
②【誤】
エが誤りです。ボーキサイト鉱床は、アルミニウムに富む岩石が熱帯気候下で風化して生成される残留鉱床であり、熱水鉱床ではありません。また、日本では産出しません。
③【誤】
ウが誤りです。アルミニウムはボーキサイト鉱床の主成分であり、熱水鉱床の主成分ではありません。
④【誤】
ウ、エともに誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
地球全体のアルベド(太陽放射の反射率)の平均値と、地表面の状態の変化がアルベドに与える影響について問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
オ、カともに誤りです。地球のアルベドは約0.3(30%)です。また、アルベドの高い氷床が減り、アルベドの低い森林が増えると、全体のアルベドは低くなります。
②【誤】
オが誤りです。地球のアルベドは約0.3(30%)です。
③【誤】
カが誤りです。アルベドの高い氷床や雪原が減少し、アルベドの低い森林が増加すると、地球全体が反射する太陽放射の割合は小さくなるため、アルベドの平均値は低くなります。
④【正】
地球が太陽放射を反射する割合であるアルベドの全球平均値は、約0.3(30%)です。したがって、オには「0.30 (30%)」が入ります。次に、地表面の状態とアルベドの関係を考えます。氷床や雪原は白色に近いため太陽光をよく反射し、アルベドが高い(0.8程度)です。一方、森林は濃い緑色で太陽光をよく吸収するため、アルベドは低い(0.2程度)です。問題のように、アルベドの高い氷床・雪原が減り、アルベドの低い森林が増えると、地球全体の平均アルベドは低くなります。したがって、カには「低く」が入ります。
問5:正解③
<問題要旨>
年周視差を用いた天体の距離計算と、セファイド型変光星の性質(周期-光度関係)に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
キ、クともに誤りです。
②【誤】
キが誤りです。また、セファイド型変光星の距離推定に用いられるのは、周期と光度の関係です。
③【正】
まず、キの距離を計算します。年周視差p(秒)とパーセク単位の距離rには、r=1/p の関係があります。年周視差が0.001秒なので、距離は 1/0.001=1000パーセクとなります。1パーセクは約3.26光年なので、光年に換算すると 1000×3.26=3260光年です。選択肢の中で最も近い数値は3000光年です。
次に、クについてです。セファイド(ケフェウス座δ)型変光星には、変光周期が長いものほど絶対的な光度が大きい(明るい)という「周期-光度関係」があります。この関係を使うと、見かけの明るさと変光周期を観測することで、その天体までの距離を精度よく推定できます。これは、より遠方の銀河までの距離を測る「距離はしご」の重要な指標となります。よって、この組み合わせは正しいです。
④【誤】
クが誤りです。スペクトル型と表面温度の関係は、ヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図)で示される恒星の基本的な性質ですが、セファイド型変光星を用いた距離測定に直接使われる関係ではありません。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
地球内部の熱源に関する記述のうち、適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
地球が誕生する過程で、微惑星が衝突した際の運動エネルギーや、重い物質が中心に沈むことで解放された重力エネルギーが熱に変わりました。この「地球形成時に蓄えられた熱」は、現在の地球内部の熱源の主要な一つです。
②【正】
地殻やマントルに含まれるウラン、トリウム、カリウム40などの放射性同位体が、放射性崩壊する際に放出する熱エネルギーは、地球内部のもう一つの主要な熱源です。
③【誤】
花こう岩は大陸地殻を構成する岩石で、ウランやカリウムなどの放射性同位体を比較的多く含んでいます。そのため、他の岩石に比べて単位質量あたりの発熱量が多いのは事実です。しかし、その熱源は「放射性同位体の崩壊による熱」であり、「地球形成時に蓄えられた熱エネルギー」を特に多く含むためではありません。したがって、この理由付けは誤りです。
④【正】
熱は温度の高い方から低い方へ移動する性質があります。地球は中心部が非常に高温で、地表に向かうにつれて温度が低くなるため、熱は常に内部から地表に向かって移動しています。
問2:正解⑤
<問題要旨>
ブーゲー重力異常と地下の密度構造の関係を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
bとdも正しい関係を示しています。
②【誤】
aも正しい関係を示しています。
③【誤】
a、b、dも正しい関係を示しています。
④【誤】
cは誤った関係を示しています。
⑤【正】
ブーゲー異常は、地下の岩石の密度分布を反映します。基準となる密度よりも大きい(重い)物質が地下にあるとその部分の重力が強くなり、ブーゲー異常は正(プラス)になります。逆に、密度が小さい(軽い)物質があれば重力が弱まり、ブーゲー異常は負(マイナス)になります。
a:深部の密度の大きい領域(灰色部)がへこんでおり、その分だけ密度の小さい物質が相対的に多くなっています。そのため重力が弱くなり、ブーゲー異常は負になります。図の関係は正しいです。
b:周囲より密度の大きい物体が地下に存在するため、その真上では重力が強くなり、ブーゲー異常は正になります。図の関係は正しいです。
c:深部の密度の大きい領域が浅い位置に食い込んでいます。これは密度の大きい物質が地表に近づいていることを意味するため、重力は強くなり、ブーゲー異常は正になるはずです。しかし、図では負になっているため、この関係は誤りです。
d:深部の密度の大きい領域が盛り上がっており、cと同様に重力は強くなるため、ブーゲー異常は正になります。図の関係は正しいです。
したがって、a、b、dが正しく示されています。
⑥【誤】
cは誤った関係を示しています。
問3:正解③
<問題要旨>
世界の震源分布図から、プレート境界の種類(収束境界、発散境界)を読み取る問題です。
<選択肢>
①【誤】
文eが誤りです。
②【誤】
文eが誤りです。
③【正】
e:太平洋西岸(日本海溝など)では、震源が深さ100kmより深い地震が多数発生しており、プレートが沈み込む「収束境界」であることがわかります。一方、大西洋東岸(ヨーロッパ・アフリカ沿岸)では、深い地震はほとんどなく、顕著なプレート境界はありません。したがって、「大西洋東岸には、プレート収束境界がある」という記述が誤りであるため、文eは全体として誤りです。
f:太平洋南東部(東太平洋海膨)や大西洋中央部(大西洋中央海嶺)では、震源が深さ100kmより浅い地震が線状に連なって発生しています。これは、プレートが新たに生成・拡大している「発散境界」の特徴です。したがって、文fは正しいです。
よって、eが誤、fが正の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
④【誤】
文fが正しいです。
問4:正解①
<問題要旨>
地球内部の深さによる、P波速度、S波速度、密度の分布を示したグラフを正しく読み解く問題です。
<選択肢>
①【正】
P波(縦波)は固体・液体を伝わり、S波(横波)は固体しか伝わりません。また、同じ媒質中では常にP波の方がS波より速いです。
Aの線は、全体で最も速度が速く、深さ約2900kmで急に速度が落ちています。これはP波が固体のマントルから液体の外核へ入ったことを示しています。したがってAはP波速度です。
Bの線は、Aより速度が遅く、深さ約2900kmで速度が0になっています。これはS波が液体の外核を伝わらないことを示しています。したがってBはS波速度です。
Cの線は、深くなるにつれて基本的に増加し、マントルと外核の境界(約2900km)、外核と内核の境界(約5100km)で不連続に大きく変化しています。これは密度の分布を示しています。
したがって、AがP波速度、BがS波速度、Cが密度の組み合わせが正しいです。
②【誤】
BとCの対応が逆です。S波は外核で速度が0になります。
③【誤】
AとBの対応が逆です。P波はS波より常に速いです。
④【誤】
A, B, Cすべての対応が誤っています。
⑤【誤】
A, B, Cすべての対応が誤っています。
⑥【誤】
A, B, Cすべての対応が誤っています。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
示準化石の活動時代と、その殻の化学的性質に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ヌンムリテス(カヘイ石)は古第三紀の示準化石で、殻の主成分は炭酸カルシウム(CaCO₃)です。
②【正】
問題の条件は「三畳紀」の地層から発見された「二酸化ケイ素(SiO₂)の殻を持つ」化石です。放散虫は、古生代から現在まで生息する単細胞生物で、その殻は二酸化ケイ素でできています。特に中生代(三畳紀を含む)の示準化石として重要です。したがって、この選択肢が正解です。
③【誤】
フズリナ(紡錘虫)は古生代の石炭紀からペルム紀にかけて繁栄した示準化石で、三畳紀には存在しません。殻の主成分は炭酸カルシウムです。
④【誤】
筆石(グラプトライト)は古生代の示準化石で、三畳紀には存在しません。殻はキチン質です。
問2:正解②
<問題要旨>
火成岩の薄片スケッチから鉱物同定を行い、岩石名を特定し、その化学組成(SiO₂含有量)を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
SiO₂含有量が誤りです。花こう岩はSiO₂含有量が66%以上の酸性岩です。
②【正】
図3のスケッチには、石英、カリ長石、斜長石、黒雲母といった鉱物が確認できます。これらの鉱物組み合わせ、特に石英とカリ長石を多く含むこと、そして鉱物が互いに大きく成長した等粒状組織を示すことから、この岩石は深成岩である花こう岩と判断できます。花こう岩はSiO₂の含有量が多い酸性岩に分類され、その含有量は一般に66質量%以上です。選択肢の中では「約70質量%」がこれに該当します。したがって、この組み合わせは正しいです。
③【誤】
岩石の名称が誤りです。閃緑岩は主に斜長石と角閃石からなり、石英やカリ長石はほとんど含みません。
④【誤】
岩石の名称とSiO₂含有量の両方が誤りです。
問3:正解③
<問題要旨>
地質図から、ある岩石がどのような作用を受けてできた変成岩かを判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
結晶片岩は、広範囲に圧力と熱がかかる広域変成作用でできる変成岩です。
②【誤】
結晶質石灰岩(大理石)は、石灰岩が変成作用を受けたものです。元の岩石が石灰岩である必要があります。
③【正】
地質図を見ると、地点Rを含む接触変成岩Cは、火成岩Bが堆積岩Dに貫入した際に、その境界部に形成されています。これは、マグマ(火成岩Bのもと)の熱によって周囲の堆積岩Dが変成(接触変成作用)を受けたことを示しています。接触変成作用によってできた硬く緻密な変成岩をホルンフェルスと呼びます。地点Qの礫層Aに含まれる黒っぽい礫が、このホルンフェルスであったと考えられます。
④【誤】
片麻岩は、結晶片岩よりもさらに高い温度・圧力の広域変成作用でできる変成岩です。
問4:正解②
<問題要旨>
地質年代測定法について、測定対象の年代に適した方法と試料の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
ルビジウムーストロンチウム法は半減期が約488億年と非常に長く、数千万年~数十億年という古い年代の測定に用いられ、数万年前の年代測定には適しません。
②【正】
測定対象は「数万年前より新しい」土石流堆積物です。この年代の測定には、半減期が約5730年である炭素14を用いる炭素14法(放射性炭素法)が適しています。炭素14法は、生物の遺骸(木片、骨、貝殻など)に含まれる炭素14の量を測定する方法です。土石流が発生した当時に取り込まれたと考えられる「木片」を試料とすることで、土石流の年代を推定できます。したがって、この組み合わせが最も適当です。
③【誤】
測定方法が不適切です。
④【誤】
測定方法が不適切です。炭素14法は、黒雲母のような無機物の鉱物には適用できません。
問5:正解④
<問題要旨>
マグマの結晶分化作用において、晶出した結晶が沈積してできる「沈積層」の化学組成が、元のマグマや残りのマグマの組成と比べてどうなるかを考察する問題です。
<選択肢>
①【誤】
沈積層はSiO₂含有量の低い結晶Pが主成分なので、液AよりもSiO₂含有量は低くなります。
②【誤】
沈積層は結晶Pが主成分であり、液Bは隙間を埋める少量にすぎないため、液Bと同じにはなりません。
③【誤】
沈積層はSiO₂含有量の低い結晶Pが多く集まったものなので、元の液AよりもSiO₂含有量は少なくなります。
④【正】
レポートの条件から、晶出する結晶PのSiO₂含有量(40%)は、元のマグマである液Aや残りのマグマである液BのSiO₂含有量(60%)よりも低いです。沈積層は、このSiO₂含有量の低い結晶Pが主に集積し、その隙間を少量の液Bが埋めているものです。したがって、沈積層全体の平均的なSiO₂含有量は、結晶Pの40%よりはわずかに高くなりますが、元のマグマである液AのSiO₂含有量(問6の計算により56%)よりは明らかに低くなります。
問6:正解④
<問題要旨>
マグマの結晶分化作用のモデルにおいて、与えられた条件から分化前のマグマのSiO₂含有量を計算する問題です。
<選択肢>
①【誤】
計算が誤っています。
②【誤】
これは液Bに含まれるSiO₂の質量(液Aを100とした場合)であり、含有率ではありません。
③【誤】
計算が誤っています。
④【正】
液A、結晶P、液Bの関係は、質量保存の法則に基づき計算できます。液Aの全体の質量を100と仮定します。結晶Pと液Bの質量比が20:80なので、結晶Pの質量は20、液Bの質量は80となります。
それぞれのSiO₂の質量を計算すると、
・結晶Pに含まれるSiO₂の質量: 20×(40/100)=8
・液Bに含まれるSiO₂の質量: 80×(60/100)=48
分化前の液Aに含まれていたSiO₂の総質量は、この二つを合計したものなので、8+48=56 となります。
液Aの全体の質量を100としたので、SiO₂含有量は56質量%です。
問7:正解②
<問題要旨>
顕生代における生物の科の数の変動グラフから、大量絶滅の時期を読み取り、その時期に起こった出来事に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
グラフを見ると、a〜eで示された5回の顕著な大量絶滅以外にも、科の数は常に変動しており、減少している時期は他にも見られます。これは正しい記述です。
②【誤】
三葉虫は古生代を代表する生物ですが、絶滅したのは古生代の終わりであるペルム紀末の大量絶滅(グラフのc、約2.5億年前)の時です。グラフのbは約3.7億年前のデボン紀後期の大量絶滅を示しており、この時期ではありません。したがって、この記述は誤りです。
③【正】
グラフのcは、約2.5億年前のペルム紀末に起きた、顕生代で最大規模の大量絶滅です。この原因の一つとして、大規模な火山活動に伴う地球環境の激変が挙げられ、その結果として海洋の酸素濃度が極端に低下する「海洋無酸素事変」が起こったと考えられています。これは正しい記述です。
④【正】
グラフのeは、約6600万年前の白亜紀末の大量絶滅です。この時、巨大隕石の衝突が原因で恐竜が絶滅したことは有名ですが、同じく中生代の海に広く生息していたアンモナイトもこの時に絶滅しました。これは正しい記述です。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
北半球における地衡風の向きと、それにはたらく力の向きを正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
コリオリの力の向きが異なります。
②【正】
地衡風は、気圧傾度力(気圧の高い方から低い方へ向かう力)とコリオリの力(転向力)がつりあった結果、等圧線に平行に吹く風です。
まず、風の向きを考えます。北半球では、地衡風は進行方向に対して右側に高圧部を見るように吹きます。図では高圧部が北側、低圧部が南側にあるため、高圧部を右に見る風の向きは西向き、つまりAの方向となります。
次に、力のはたらく向きを考えます。気圧傾度力は高圧部から低圧部へ向かうので、南向きにはたらきます。地衡風が吹いている定常状態では、コリオリの力は気圧傾度力とちょうどつりあうため、北向きにはたらきます。
しかし、選択肢には「A、北向き」の組み合わせがありません。このような場合、問題の意図を解釈する必要があります。風を吹かせる直接的な原因は気圧傾度力です。設問が、地衡風の向きと、その風を駆動する力の向き(気圧傾度力の向き)の組み合わせを問うていると解釈すると、「地衡風の向き:A(西向き)」と「力の向き:南向き」の組み合わせが考えられます。この解釈に基づくと、この選択肢が正解となります。
③【誤】
地衡風の向きが異なります。
④【誤】
地衡風の向きが異なります。
問2:正解③
<問題要旨>
地表付近で吹く風が、上空の地衡風とどのように異なるかを、地表摩擦の影響から理解する問題です。
<選択肢>
①【誤】
地衡風より弱くなりますが、向きは同じではなく、低圧部側にずれます。
②【誤】
弱くなりますが、逆向きにはなりません。
③【正】
地表付近では、地面との摩擦によって風速が地衡風よりも遅くなります。風速に比例してはたらくコリオリの力も、その結果として弱まります。気圧傾度力は変わらないため、「気圧傾度力>コリオリの力」となり、力のつり合いが崩れます。その結果、風は気圧傾度力に引かれる形で、等圧線を斜めに横切り、低圧部側に吹き込むようになります。したがって、北半球では、低気圧の中心に向かう風の成分が生じます。
④【誤】
高気圧からは風が吹き出しており、中心に向かうことはありません。南半球の高気圧では、時計回りに、中心からやや外側にずれて風が吹き出します。
問3:正解④
<問題要旨>
風浪と津波について、その速さと波長、水深の関係を示したグラフを正しく読み解く問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア、イともに異なります。グラフの傾きと線の位置関係を読み取ります。
②【誤】
アが異なります。風浪は波長が長いほど速くなります。
③【誤】
イが異なります。津波は水深が深いほど速くなります。
④【正】
ア(風浪):グラフの左側「風浪」の範囲を見ると、3つの水深の線(50m, 200m, 1000m)がほぼ1本に重なっており、右上がりの直線になっています。これは、風浪の速さが「水深によらず」、かつ「波長が長いほど速く」なることを示しています。したがって、アには「速く」が入ります。
イ(津波):グラフの右側「津波」の範囲を見ると、3つの水深の線がはっきりと分かれており、水深1000mの線が最も速く、50mの線が最も遅くなっています。これは、津波の速さが「水深が深いほど速く」なることを示しています。また、それぞれの線はほぼ水平であり、波長による速さの変化はほとんどないことがわかります。したがって、イには「速く」が入ります。
問4:正解①
<問題要旨>
海洋の熱塩循環のスケールと、大西洋の表層における塩分の特徴を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
ウ:海洋の深層水が世界中の海洋をゆっくりと巡る熱塩循環は、一周するのに1000年~2000年かかると言われています。選択肢の中では「1500」年が適当です。
エ:図3の塩分分布を見ると、表層(水深0m付近)の塩分は、深層に比べて全体的に高い値を示しています(35‰~37‰程度)。特に亜熱帯域で高くなっています。これは、表層では日射による蒸発が盛んで、水分が奪われて塩分が濃縮されるためです。したがって、エには「高い」が入ります。
②【誤】
エが誤りです。表層の塩分は深層より高いです。
③【誤】
ウのスケールが大きすぎます。
④【誤】
ウのスケールが大きすぎ、またエも誤りです。
問5:正解②
<問題要旨>
海洋の熱塩循環における、北大西洋で沈み込む深層水(X)と、南極周辺で沈み込む底層水(Y)の水温・塩分の特徴を比較し、図から正しい位置を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
AはYよりも塩分・水温ともに高く、密度が小さい海水を示します。
②【正】
問題文に、Xを形成する海水(a)は北緯60°付近から沈み込み、Yを形成する海水(b)は南極付近から沈み込み、(b)の方が(a)より密度が大きいとあります。
図3を見ると、Xの水塊は、Yの水塊よりも上の中層に位置しています。これは、Xの方がYよりも密度が小さいことを意味します。
図4は、右下に行くほど密度が大きくなることを示しています。XはYより密度が小さいので、図4ではYより左上に位置するはずです。
また、XはYに比べて、より低緯度の暖かい海域から運ばれてきた水が冷却されて沈み込んだものであるため、南極で直接形成されるYよりも、水温・塩分ともに高い特徴があります。
これらの条件(Yより密度が小さい、Yより水温・塩分が高い)を満たすのは、点Bです。
③【誤】
CはYよりも水温が高いですが塩分が低く、Yとほぼ同じ密度曲線上にあります。
④【誤】
DはYよりも塩分が低いですが水温が低く、Yよりも密度が大きい海水を示します。
第5問
問1:正解③
<問題要旨>
銀河系の中心部を観測する方法と、銀河系の構造に関する用語の知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア、イともに誤りです。紫外線は星間物質に吸収されやすく、銀河中心の観測には使えません。
②【誤】
アが誤りです。
③【正】
ア:銀河系の中心方向は、濃い星間ガスや塵(星間物質)に覆われているため、可視光線や紫外線は通り抜けることができず、直接観測することができません。しかし、波長の長い赤外線や電波は星間物質を透過しやすいため、銀河中心の観測には赤外線望遠鏡や電波望遠鏡が用いられます。
イ:銀河系の中心部にある、恒星が密集した球状の膨らんだ領域を「バルジ」と呼びます。
したがって、この組み合わせが正しいです。
④【誤】
イが誤りです。ハローは、銀河系の円盤部やバルジを球状に取り囲むように希薄に広がっている領域です。
問2:正解②
<問題要旨>
星間物質の組成や観測方法に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
星間物質は、約99%が希薄なガス(水素やヘリウムが主成分)で、約1%が塵と呼ばれる固体微粒子からなります。「豊富な液体」は含まれません。
②【正】
高温の恒星(O型星やB型星など)の周辺では、星から放射される強力な紫外線によって、周囲の星間ガス(主に水素)が電離(電子が原子から離れること)しています。このような領域は電離水素領域(HII領域)と呼ばれ、輝線星雲として観測されます。
③【誤】
星間雲が近くの恒星の光を反射して見えるのが散光星雲(反射星雲)ですが、背景の星の光を遮ることで黒い影のように見える暗黒星雲としても観測されます。また、星間ガス自体が放つ電波を観測することでも、その存在を知ることができます。
④【誤】
星間物質が密集した分子雲では、水素は分子状態(H₂)で存在しますが、H₂分子は電波をほとんど放射しないため直接観測が困難です。そのため、分子雲の中に比較的多く含まれ、特徴的な電波を放射する一酸化炭素(CO)分子を観測することで、分子雲の分布や動きが調べられています。
問3:正解②
<問題要旨>
銀河系内に存在する星団(散開星団と球状星団)の特徴と、それに含まれる恒星の元素組成について問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
エが誤りです。散開星団の星の重元素量は太陽とほぼ同じです。
②【正】
ウ:恒星の集団である星団には、主に銀河系の円盤部に分布し、数十~数百個の比較的若い星が集まった散開星団と、主にハローに分布し、数万~数百万個の年老いた星が球状に集まった球状星団があります。銀河の円盤部内で円軌道を描いて運動しているのは散開星団です。
エ:銀河系では、星の世代交代(星の誕生と死)を繰り返すことで、超新星爆発などによって合成された重元素(ヘリウムより重い元素)が星間空間に供給され、徐々にその割合が増えてきました。太陽や散開星団を構成する星は、比較的最近の材料から生まれたため、重元素の割合が太陽とほぼ等しいです。一方、銀河系の初期に誕生した球状星団の星々は、重元素がまだ少なかった時代のガスからできているため、重元素の割合は太陽より小さいです。
③【誤】
ウが誤りです。球状星団はハローに分布し、銀河中心を長楕円軌道で運動しています。
④【誤】
ウ、エともに誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
宇宙膨張による赤方偏移が、遠方銀河のスペクトルにどのような影響を与えるかを理解する問題です。
<選択肢>
①【誤】
これは青方偏移した場合のスペクトルであり、波長が短くなっています。
②【誤】
これは赤方偏移していない、元の銀河のスペクトルです。
③【誤】
輝線の波長が元の2倍になっていません。
④【正】
赤方偏移 zは、元の波長を λo、観測される波長を λとして、z=(λ−λo)/λoと定義されます。これを変形すると、λ=λo (1+z) となります。
問題では、z=1 なので、λ=λo (1+1)=2λoとなり、観測される光の波長は、元の波長のちょうど2倍になります。
図1の元のスペクトルを見ると、特徴的な強い輝線が波長600nm付近にあります。したがって、赤方偏移 z=1 の銀河を観測した場合、この輝線は波長 600×2=1200nm の位置に観測されるはずです。また、スペクトル全体の形も、波長軸方向に2倍に引き伸ばされた形になります。例えば、300nm付近の立ち上がりは600nm付近に移動します。この条件に合うスペクトルは、この選択肢の図です。
問5:正解①
<問題要旨>
宇宙背景放射について、ウィーンの変位則を用いて、宇宙の晴れ上がり当時と現在のスペクトルの違いを考察する問題です。
<選択肢>
①【正】
宇宙背景放射は、約138億年前に「宇宙の晴れ上がり」が起こった時の光が、宇宙膨張によって波長が引き伸ばされ、現在では温度約3Kの黒体放射として観測されているものです。晴れ上がり当時の宇宙の温度は約3000Kでした。
ウィーンの変位則は、黒体放射のエネルギーが最大となる波長$λ_{max}$は、その黒体の温度$T$に反比例する (λmax∝1/T) という法則です。
したがって、温度が高かった晴れ上がり当時(約3000K)の放射は、現在(約3K)よりも、エネルギーが最大となる波長がずっと短くなります。
図2のスペクトルを見ると、Bが現在の約3Kの放射です。AはBよりもピーク波長が短く、より高温の黒体放射スペクトルを示しています。CはBよりもピーク波長が長く、より低温であることを示します。Dは黒体放射の形とは異なります。したがって、晴れ上がり当時のスペクトルとして最も適当なのはAです。
②【誤】
Bは現在の宇宙背景放射のスペクトルです。
③【誤】
Cは現在よりもさらに低温の黒体放射を示しており、誤りです。
④【誤】
Dは黒体放射スペクトルの形ではありません。
問6:正解④
<問題要旨>
プランク衛星が観測した宇宙背景放射の温度ゆらぎについて、その観測が明らかにしたことに関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
この宇宙背景放射の温度の「ゆらぎ」の大きさや空間的なパターンを詳しく解析することで、宇宙の年齢、膨張率、組成などが非常に高い精度で求められました。その結果、宇宙の年齢は約138億年であることがわかっています。
②【正】
同様に、このゆらぎの解析から、宇宙全体のエネルギーのうち、我々が直接観測できる通常の物質は約5%に過ぎず、残りは正体不明の暗黒物質(ダークマター)が約27%、暗黒エネルギー(ダークエネルギー)が約68%を占めるという、現在の宇宙の組成が明らかになりました。
③【正】
宇宙背景放射の平均温度は約2.73Kですが、図3に示されている温度の「ゆらぎ」は、平均温度に対して10万分の1程度の非常にわずかな差です。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
宇宙背景放射の温度は約3Kであり、その放射エネルギーのピークはミリ波やサブミリ波といった電波の領域にあります。プランク衛星もこの波長帯の電波を観測する衛星です。波長の短い紫外線で観測されたものではありません。したがって、この記述は誤りです。