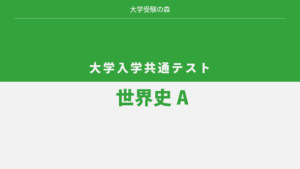解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
1867年のパリ万国博覧会が開催された時期のフランスの君主、すなわち皇帝ナポレオン3世(在位1852~1870年)の治世における政策を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
バタヴィア(現在のジャカルタ)を拠点に東南アジアで植民地支配を広げたのはオランダです。フランスではありません。
②【正】
ナポレオン3世は、工業家や金融資本家の支持を得て、産業革命を推進し、積極的に対外進出を行いました。その一環として、1861年にメキシコ出兵(メキシコ干渉)を行いました。これはナポレオン3世の治世における代表的な対外政策の一つです。
③【誤】
三国同盟は、1882年にドイツ・オーストリア・イタリアの間で結ばれた軍事同盟です。フランスを孤立させることを目的としており、ナポレオン3世の時代よりも後の出来事です。
④【誤】
国立作業場は、1848年の二月革命後のフランス第二共和政において、臨時政府が失業者救済のために設立したものです。ナポレオン3世が皇帝に即位する前の出来事であり、彼が主導した政策ではありません。
問2:正解①
<問題要旨>
ナポレオン3世がイギリスと共に勝利し、中国進出を強化する契機となった戦争、すなわちアロー戦争(第二次アヘン戦争、1856~1860年)に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
文「あ」は、アロー戦争がイギリスとフランスの共同出兵であったことを述べており、正しいです。文「い」は、アロー戦争の講和条約である北京条約(1860年)で天津の開港などが定められたことを述べており、正しいです。したがって、「あ」と「い」が共に正しいとするこの選択肢が正解です。
②【誤】
文「い」は誤りではありません。
③【誤】
文「あ」は誤りではありません。
④【誤】
文「あ」、文「い」ともに正しい記述です。
問3:正解①
<問題要旨>
文章の内容から、野中元右衛門がパリ万博に関わった理由を推論し、ジャポニスムに影響を与えたフランス印象派の画家の作品を特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
理由について、本文に「肥前の地の大半は佐賀藩だった」「佐賀藩や薩摩藩なども幕府とは別に独自に出品した」とあることから、肥前の豪商であった野中は佐賀藩の関係者として万博に関わったと推測するのが最も自然です(理由「う」)。絵画について、Xはルノワールの『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』であり、印象派を代表する作品です。一方、Yはレンブラントの『夜警』であり、17世紀オランダのバロック美術の作品です。したがって、印象派の絵画はXです。「う」と「X」の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
②【誤】
絵画Yは印象派の作品ではありません。
③【誤】
野中は肥前(佐賀藩)の商人であり、薩摩藩の関係者とする理由「え」は本文の内容と合いません。
④【誤】
理由「え」、絵画Yともに誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
下線部③「朝鮮王朝は中国から冊封を受けていた」に関連して、歴史上の中国と周辺諸国との関係(冊封・朝貢関係)について、正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
新羅は、隋ではなく唐と連合(唐・新羅の連合軍)して、百済(660年)と高句麗(668年)を滅ぼしました。
②【正】
琉球王国は、明、そして明を継承した清の時代に至るまで、中国皇帝の臣下として朝貢を行っていました。これは冊封・朝貢関係の典型的な例です。
③【誤】
邪馬台国の女王卑弥呼が使いを送ったのは、後漢ではなく、三国時代の魏(239年)です。このとき「親魏倭王」の称号と金印を授けられました。
④【誤】
豊臣秀吉の朝鮮侵略(文禄・慶長の役、1592~1598年)の際、朝鮮に援軍を送ったのは明です。元は14世紀に滅亡した王朝です。
問5:正解⑤
<問題要旨>
韓国の独立門がどの国からの独立を意図したものかを文脈から読み取り、朝鮮の固有文字であるハングルについての正しい説明を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
ウ(独立の意味)とX(ハングルの説明)の組み合わせが正しいです。
②【誤】
ウは「清からの独立」が正しく、Y(ハングルの成立時期)は誤りです。
③【誤】
ウは「清からの独立」が正しいです。
④【誤】
ウは「清からの独立」が正しく、Yは誤りです。
⑤【正】
空欄ウについて、独立門が中国皇帝の使者を迎える「迎恩門」の跡地に建てられたという文脈から、これは「清からの独立」を意味していると判断できます(語句「う」)。下線部④ハングルについて、ハングルは子音と母音を表す字母(文字)を組み合わせて一つの音節を表す表音文字です(文「X」)。日本の仮名文字は平安時代(9~12世紀)に成立しましたが、ハングルは李氏朝鮮の世宗によって15世紀半ばに創られました。したがって、「Y」は誤りです。「う」と「X」の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
⑥【誤】
Yは誤りです。
問6:正解①
<問題要旨>
下線部⑤「大韓帝国」が存在した時期(1897年~1910年)に朝鮮半島で起こった出来事を特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
日本の統監府は、第二次日韓協約(1905年)に基づき、1906年に設置されました。これは大韓帝国の存在した時期(1897~1910年)にあたります。
②【誤】
甲午農民戦争(東学党の乱)は、1894年に起こった出来事であり、大韓帝国成立以前の出来事です。
③【誤】
李承晩が初代大統領となったのは、第二次世界大戦後の1948年に大韓民国が成立したときです。
④【誤】
三・一独立運動は、日本の植民地支配下にあった1919年に起こった民族運動であり、大韓帝国が併合された後の出来事です。
第2問
問1:正解②
<問題要旨>
資料は1973年の第一次石油危機(オイルショック)について述べています。下線部ⓐ「忘れられない事件」とは、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)による石油禁輸措置のことです。その契機となった歴史的出来事を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
バルフォア宣言は、第一次世界大戦中の1917年にイギリスがユダヤ人の民族郷土建設を支持したもので、石油危機とは時代も内容も異なります。
②【正】
1973年10月、エジプトなどが、占領されていたシナイ半島などを奪還するためにイスラエルを攻撃し、第四次中東戦争が勃発しました。この戦争の際に、OAPECはイスラエルを支持する国々への対抗措置として石油輸出の制限・禁止を行い、第一次石油危機を引き起こしました。
③【誤】
インティファーダは、パレスチナ人によるイスラエルへの抵抗運動で、第一次は1987年から始まりました。石油危機の後の出来事です。
④【誤】
イラクのクウェート侵攻とそれに続く湾岸戦争は、1990~1991年の出来事です。
問2:正解②
<問題要旨>
下線部ⓑ「1920年代に開始された」に関連し、1920年代に起こった出来事を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
イランでパフレヴィー朝が成立したのは1925年です。エジプトではありません。
②【正】
ドーズ案は、第一次世界大戦後のドイツの賠償金支払い問題を緩和するため、1924年に成立した案です。これによりアメリカ資本がドイツに流入し、ドイツ経済は安定しました。これは1920年代の出来事です。
③【誤】
ピカソがスペイン内戦を主題に『ゲルニカ』を描いたのは1937年であり、1930年代の出来事です。
④【誤】
ソ連で第一次五か年計画が開始されたのは1928年ですが、これはフランスの出来事ではありません。
問3:正解①
<問題要旨>
1970年代の石油危機後のアメリカ合衆国で見られた変化について、正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
1970年代の石油危機による経済の混乱(スタグフレーション)などを背景に、1980年代に就任したレーガン大統領は、「レーガノミックス」と呼ばれる経済政策を推進しました。これは、政府による経済規制の緩和や減税を柱とする「小さな政府」を目指すものでした。
②【誤】
ニューディール政策は、1929年の世界恐慌を克服するために、1930年代にフランクリン=ローズヴェルト大統領が推進した大規模な経済政策です。石油危機以前の出来事です。
③【誤】
ドルを基軸通貨とする国際経済体制(ブレトン・ウッズ体制)は、第二次世界大戦末期の1944年に成立しました。石油危機以前の出来事です。
④【誤】
「金ぴか時代」は、南北戦争後の19世紀後半、工業化が急速に進展した経済成長期を指します。
問4:正解②
<問題要旨>
タイのアユタヤ朝で信仰された宗教とその伝播ルートを特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
伝播ルートが異なります。
②【正】
アユタヤ朝をはじめとするタイの歴代王朝では、上座部仏教(語「あ」)が信仰の中心でした。東南アジアへの上座部仏教の伝播は、インドから直接ではなく、セイロン(スリランカ)を経由して広まったとされています(文「Y」)。したがって、「あ」と「Y」の組み合わせが正しいです。
③【誤】
タイで信仰されたのは主に上座部仏教であり、伝播ルートも異なります。
④【誤】
タイで信仰されたのは主に上座部仏教です。
問5:正解④
<問題要旨>
文章中の空欄イに入る国、すなわち19世紀にタイの東側(ラオス、カンボジア、ベトナム)を植民地化した国、フランスの対外進出に関する正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
アンボイナ事件(1623年)は、モルッカ諸島をめぐってオランダがイギリスの商館員を殺害した事件です。
②【誤】
南アフリカ戦争(ブール戦争、1899~1902年)は、イギリスがオランダ系移民(ブール人)の国を征服した戦争です。
③【誤】
ポトシ銀山は、現在のボリビアにあり、16世紀にスペインによって開発されました。
④【正】
フランスは、19世紀半ばから太平洋地域への進出を強め、1880年にタヒチを植民地としました。
問6:正解②
<問題要旨>
本文と図1~3を参考に、タイにおける地図の歴史的変化について正しく述べた文を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
図1の18世紀の地図では、仏教世界とタイの地名が一体となって描かれており、国境線によって区切られてはいません。
②【正】
本文には「西洋の技術を取り入れて近代化を進めたタイも対抗して地図を作った」とあり、19世紀のラタナコーシン朝(チャクリ朝)の時代に、タイが西洋の地理学や測量技術を受け入れて近代的な地図を作成したことがわかります。
③【誤】
タイは、周辺国が欧米の植民地となる中で、独立を維持した数少ない国の一つです。植民地化されたわけではありません。
④【誤】
図3は冷戦期のもので、隣接する社会主義国を「鎌と槌」のシンボルで描き、異質な他者として認識している様子を示しています。同質性を強調しているわけではありません。
問7:正解③
<問題要旨>
映画『アンダーグラウンド』の第一章の舞台である空欄ウの時期、すなわち第二次世界大戦中のユーゴスラヴィアに関連する出来事を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
フランコが人民戦線内閣に対して反乱を起こし、スペイン内戦が始まったのは1936年で、第二次世界大戦の直前の出来事です。
②【誤】
サライェヴォ事件は、オーストリアの皇位継承者夫妻が暗殺され、第一次世界大戦のきっかけとなった事件で、1914年の出来事です。
③【正】
1940年にナチス=ドイツがフランスに侵攻し、パリを占領した後、南フランスのヴィシーにドイツへの協力政府が樹立されました。これは第二次世界大戦中の出来事であり、ユーゴスラヴィアでティトーがパルチザン闘争を展開していた時期と重なります。
④【誤】
ブレスト=リトフスク条約は、第一次世界大戦中の1918年に、ドイツとソヴィエト政権との間で結ばれた講和条約です。
問8:正解①
<問題要旨>
映画の第二章の時代背景である空欄エ(冷戦期)と、その時期のユーゴスラヴィアの動向である空欄オに当てはまる内容を特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
映画の第二章は、ティトーの葬儀(1980年)までを描いており、これは冷戦期(語「あ」)にあたります。ティトー政権下のユーゴスラヴィアは、ソ連と距離を置き独自の社会主義路線を歩むとともに、インドのネルー、エジプトのナセルらと非同盟運動を主導し、1961年には首都ベオグラードで第1回非同盟諸国首脳会議を開催しました(文「X」)。したがって、「あ」と「X」の組み合わせが正しいです。
②【誤】
文Yのボスニア・ヘルツェゴヴィナ併合は、1908年にオーストリアが行ったもので、第一次世界大戦前の出来事です。
③【誤】
空欄エは冷戦期が適切であり、両大戦間期(1919~1939年)ではありません。
④【誤】
空欄エも文Yも誤りです。
問9:正解③
<問題要旨>
下線部ⓕ「地図上から消えてしまった国」の例として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
ベルリン会議(1878年)で独立が認められたルーマニアは、現在も国家として存在しています。
②【誤】
消滅したのは東ドイツであり、1990年に西ドイツに吸収される形で統一されました。記述が逆です。
③【正】
ポーランドは、18世紀後半(1772年、1793年、1795年)に、ロシア・プロイセン・オーストリアの3国によって分割され、第一次世界大戦後まで地図上から国家としては消滅しました。
④【誤】
バルカン同盟は、オスマン帝国に対抗するために1912年に結成された軍事同盟であり、国ではありません。また、同盟を構成した各国は現在も存在しています。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
メモに登場する河川ア、すなわちガンジス川流域の歴史について正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
モエンジョ=ダーロなどのインダス文明の遺跡があるのは、インダス川流域です。
②【正】
紀元前1500年頃、アーリヤ人がパンジャーブ地方からガンジス川流域に進出し、多くの都市国家を形成しました。これはガンジス川流域の歴史に関する正しい記述です。
③【誤】
マウリヤ朝はガンジス川流域に成立した王朝ですが、アクバルは16世紀のムガル帝国の皇帝です。時代が全く異なります。
④【誤】
扶南は、1世紀頃にメコン川下流域(現在のカンボジア・ベトナム南部)に建国された国です。
問2:正解③
<問題要旨>
イギリスがインドのベンガル地方の民族運動を分断するために1905年に発布したベンガル分割令に対し、高揚した民族運動の内容(空欄イ)を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
ガンディーによる「塩の行進」は、イギリスの塩の専売に反対して1930年に行われた運動であり、ベンガル分割令(1905年)よりも後の出来事です。
②【誤】
ウラービーの反乱は、1881年にエジプトで起こった反乱であり、インドの出来事ではありません。
③【正】
ベンガル分割令に反対して、インド国民会議派はカルカッタ大会(1906年)で、英貨排斥(スワデーシ)・民族教育・自治獲得(スワラージ)・民族教育の4綱領を採択し、反英闘争を激化させました。これが空欄イに当てはまります。
④【誤】
ネルーが指導した国民会議派が完全独立(プールナ=スワラージ)を決議したのは1929年のことであり、後の出来事です。
問3:正解②
<問題要旨>
下線部ⓑ「ベンガル地方はさらなる大変動に見舞われた」とは、1947年のイギリスからのインド・パキスタン分離独立を指します。この時、宗教対立を背景にベンガル地方がどのように分割されたかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
東ベンガルはイスラーム教徒が多いためパキスタン領(東パキスタン)に、西ベンガルはヒンドゥー教徒が多いためインド領になりました。記述が逆です。
②【正】
ヒンドゥー教徒が多数を占める西ベンガルはインドの西ベンガル州となり、イスラーム教徒が多数を占める東ベンガルはパキスタンの飛び地(東パキスタン)として独立しました。
③【誤】
東ベンガルが東パキスタンとして独立した後、さらにパキスタンから独立してバングラデシュとなったのは1971年のことです。1947年の時点ではパキスタンの一部でした。
④【誤】
西ベンガルはインドの一部となりました。バングラデシュになったのは東ベンガルです。
問4:正解①
<問題要旨>
19世紀初頭にギリシアを領有していた国、すなわちオスマン帝国で、19世紀に起こった出来事を特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
オスマン帝国では、1876年に宰相ミドハト=パシャらの尽力により、アジアで最初の近代的な憲法であるミドハト憲法が発布されました。これは19世紀のオスマン帝国における重要な出来事です。
②【誤】
タバコ=ボイコット運動は、19世紀末にイラン(カージャール朝)で起こった反外国運動です。
③【誤】
ローザンヌ条約は、第一次世界大戦後にトルコ共和国が連合国と結んだ条約で、1923年の出来事であり、20世紀に入ってからです。
④【誤】
トルコマンチャーイ条約は、1828年にロシアとイラン(カージャール朝)との間で結ばれた条約です。
問5:正解④
<問題要旨>
イギリスの詩人バイロンの詩から、エルギン卿の行為に対する彼の考え(空欄エ)を読み取り、その背景にある当時のヨーロッパの思潮を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
バイロンの考えも、社会背景も誤りです。
②【誤】
バイロンの考えが誤りです。
③【誤】
社会背景の記述が誤りです。「平和に関する布告」は1917年のロシア革命の際にレーニンが発表したもので、時代が異なります。
④【正】
バイロンはエルギンの行為を「略奪」「強奪者」と非難しており、持ち帰るべきではないと考えていたことがわかります(文「い」)。彼がギリシアの独立戦争に参加しようとした行動の背景には、19世紀前半のヨーロッパで広まっていたロマン主義の思潮があります。ロマン主義は、民族の個性や文化、歴史的伝統を重視する考え方であり、ギリシアの文化遺産や独立への共感を育みました(文「Y」)。したがって、「い」と「Y」の組み合わせが正しいです。
問6:正解②
<問題要旨>
下線部ⓓ「自分たちのルーツを古代のギリシアやローマに求め、憧れる傾向」に関連して、古代ギリシア・ローマ文化とその後の時代への受容について、正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
ラファエロがルネサンス期に描いた『アテネの学堂』には古代ギリシアの学者が描かれていますが、これを描いたのはボッティチェリではありません。
②【正】
古代ギリシアのアリストテレスなどの著作は、イスラーム世界でアラビア語に翻訳されて研究が続けられました。そして、12世紀頃から、イスラーム勢力下のイベリア半島(スペイン)などで、それらの文献がラテン語に翻訳され、ヨーロッパのスコラ学などに大きな影響を与えました。
③【誤】
アクロポリスは古代アテネの城山で、パルテノン神殿などがある宗教的中心地です。剣闘士の闘技場としては、古代ローマに建設されたコロッセウムなどが有名です。
④【誤】
イタリア=ルネサンスの経済的基盤となったのは、地中海貿易(東方貿易)で得た富です。大西洋三角貿易が本格化するのは、ルネサンス期より後の大航海時代です。
問7:正解④
<問題要旨>
メモ1に書かれている運動、すなわち1919年に北京の学生から始まった五・四運動の背景について問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
五・三〇事件は、1925年に上海で発生した反帝国主義運動であり、五・四運動より後の出来事です。
②【誤】
第一次国共合作は、1924年に成立しました。五・四運動がきっかけの一つにはなりましたが、直接の背景ではありません。
③【誤】
抗日民族統一戦線の結成が呼びかけられたのは、日中戦争が本格化する1930年代後半のことです。
④【正】
五・四運動の思想的背景として、陳独秀らが中心となって展開した新文化運動がありました。この運動は、儒教などの古い道徳や思想を批判し、民主主義と科学をスローガンに掲げて、中国の近代化を目指しました。
問8:正解①
<問題要旨>
メモ2に書かれている運動、すなわち毛沢東が権力奪還のために起こした文化大革命(プロレタリア文化大革命、1966~1976年)の期間中に起こった出来事を特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
米中関係の改善を目指したアメリカのニクソン大統領が中国を訪問したのは1972年です。これは文化大革命の期間中の出来事です。
②【誤】
イギリスから中国へ香港が返還されたのは1997年です。
③【誤】
中ソ友好同盟相互援助条約が締結されたのは1950年で、文化大革命より前の出来事です。
④【誤】
中国が朝鮮戦争に義勇軍を派遣したのは1950年で、文化大革命より前の出来事です。
問9:正解③
<問題要旨>
メモ3で言及されている民主化運動(1989年の天安門事件)のきっかけとなった経済政策(空欄オ)を推進した指導者と、その政策の内容を示す資料を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
指導者も資料も誤りです。
②【誤】
指導者が誤りです。資料Yは毛沢東の大躍進政策(人民公社)に関するものです。
③【正】
天安門事件につながる経済発展と格差拡大をもたらしたのは、1970年代末から鄧小平(名「い」)が主導した改革開放政策です。資料Xは、「社会主義にも市場はある」「証券、株式会社」といった市場経済の導入を肯定する内容であり、これは鄧小平の考え方(社会主義市場経済)を明確に示しています。したがって、「い」と「X」の組み合わせが正しいです。
④【誤】
資料Yは改革開放政策ではなく、その前の大躍進政策に関するものです。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
ナポレオンのエジプト遠征の目的(空欄ア)と、スエズ運河を建設した人物(空欄イ)を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
人物が異なります。
②【正】
ナポレオンは、宿敵イギリスと、その植民地であるインド(語「あ」)との連絡を断つことを目的に、1798年にエジプトへ遠征しました。スエズ運河は、フランスの外交官・企業家であったレセップス(人物「Y」)が中心となって建設を進め、1869年に開通しました。したがって、「あ」と「Y」の組み合わせが正しいです。
③【誤】
人物が異なります。ゴードンはアロー戦争や太平天国の乱で活躍したイギリスの軍人です。
④【誤】
目的も人物も異なります。
⑤【誤】
目的が誤りです。
⑥【誤】
目的も人物も異なります。
問2:正解④
<問題要旨>
下線部ⓐ「世界の東西を結ぶ交通の大動脈」、すなわち1869年に開通したスエズ運河を通過したと考えられる事例を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
ペリーが日本に来航したのは1853年であり、スエズ運河開通前の出来事です。艦隊は太平洋を横断して日本に到達しました。
②【誤】
大黒屋光太夫は、ロシアに漂着した後、18世紀末にシベリアを横断し、ヨーロッパ経由ではなく陸路と海路で日本に帰国しました。
③【誤】
クックの探検は18世紀後半に行われ、スエズ運河開通前の出来事です。
④【正】
岩倉使節団は、欧米を歴訪した後、1873年に帰国の途につきました。その際、ヨーロッパからアジアへ向かう航路でスエズ運河を通過しています。これは運河開通後の出来事であり、地理的にも自然なルートです。
問3:正解④
<問題要旨>
下線部ⓑ「スエズ戦争」と、文「う」「え」の出来事を年代の古い順に並べる問題です。
<選択肢>
①【誤】
時系列が異なります。
②【誤】
時系列が異なります。
③【誤】
時系列が異なります。
④【正】
各出来事の年代は以下の通りです。
・え:エジプトでナセルらの自由将校団がクーデタを起こし、王政を打倒した(エジプト革命)のは1952年。
・下線部ⓑ:ナセルがスエズ運河の国有化を宣言したことをきっかけに、スエズ戦争(第二次中東戦争)が勃発したのは1956年。
・う:パレスチナ解放機構(PLO)が結成されたのは1964年。
したがって、「え→下線部ⓑ→う」の順が正しいです。
⑤【誤】
時系列が異なります。
⑥【誤】
時系列が異なります。
問4:正解②
<問題要旨>
アヘン戦争以前、ヨーロッパとの貿易が限定されていた港(空欄ウ)、すなわち広州の歴史に関する正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
北宋の都は開封(かいほう)です。
②【正】
1926年、蒋介石が率いる国民革命軍は、軍閥打倒と中国統一を目指して、広州を拠点に北伐を開始しました。
③【誤】
南京条約によってイギリスに割譲されたのは香港島です。
④【誤】
玄奘がインドから持ち帰った仏典を収めるために大雁塔が建てられたのは、唐の都、長安(現在の西安)です。
問5:正解④
<問題要旨>
グラフから読み取れる事柄と、グラフの最終年(1915年)を含む下線部ⓐの時期(第一次世界大戦期)に起こった出来事を組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【誤】
事柄「あ」も出来事「X」も誤りです。
②【誤】
事柄「あ」が誤りです。
③【誤】
出来事「X」が誤りです。
④【正】
事柄について、清仏戦争が勃発した1884年のイギリスへの輸出量は約90万担です。グラフ最終年の1915年のイギリスへの輸出量は約15万担であり、明らかに2分の1以下です。したがって、「い」は正しいです。(ちなみに「あ」の武昌蜂起は1911年で、グラフを見るとロシア、アメリカへの輸出は増加しており、誤り。)
出来事について、下線部ⓐの時期(1880~1915年)のうち、グラフの輸出量が10万担以下に落ち込んだ時期は1904~1905年に見られます。これは、遼東半島を主戦場として日本とロシアが戦った日露戦争(1904~1905年)の時期と一致します。したがって、「Y」は正しいです。「い」と「Y」の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
問6:正解③
<問題要旨>
下線部ⓑ「アフリカ大陸」において、グラフの期間(1880~1915年)に起こった出来事を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
二度のモロッコ事件(1905年、1911年)は、ドイツがフランスのモロッコ支配に対抗して起こしたものであり、イタリアではありません。
②【誤】
アフリカ統一機構(OAU)が結成されたのは、多くのアフリカ諸国が独立を果たした後の1963年です。
③【正】
スーダンでは、エジプト・イギリスの支配に対し、ムハンマド=アフマドが自らを救世主(マフディー)と称して反乱(マフディーの反乱)を起こし、1885年にハルツームを占領しました。これは1880~1915年の期間内の出来事です。
④【誤】
「アラブの春」は、2010年末から中東・北アフリカ地域で発生した民主化運動であり、チュニジアの政権崩壊は2011年の出来事です。