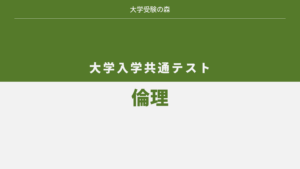解答
解説
第1問
問1:正解①
<問題要旨>
様々な宗教や思想における、人間の望みや欲望についての理解を問う問題。ア・イ・ウそれぞれの記述の正誤を判断する必要がある。
<選択肢>
①【正】
アは正しく、イとウは誤りである。したがって、アのみを正しいとするこの選択肢が正解となる。
②【誤】
イが誤りであるため、この選択肢は誤り。
③【誤】
ウが誤りであるため、この選択肢は誤り。
④【誤】
イが誤りであるため、この選択肢は誤り。
⑤【誤】
ウが誤りであるため、この選択肢は誤り。
⑥【誤】
イとウがともに誤りであるため、この選択肢は誤り。
⑦【誤】
イとウがともに誤りであるため、この選択肢は誤り。
(各記述の詳細解説)
ア:【正】旧約聖書のモーセの十戒では、9番目に「隣人の家を欲してはならない」と定められており、他者のものを欲しがることを明確に禁じている。したがって、この記述は正しい。
イ:【誤】イスラームでは、俗世を完全に離れる出家のような制度は原則として存在しない。信者は現世においてアッラーの教えを守り、信仰を深める生き方が求められる。欲望を完全に消し去るのではなく、教えの範囲内でコントロールすることが重要とされる。したがって、この記述は誤りである。
ウ:【誤】荀子は、人間の本性(性)を欲望に満ちたもの(性悪説)と捉えたが、その欲望に基づく行為そのものを「人為的」と批判したわけではない。むしろ、人間が後天的な努力(偽)によって礼を学び、欲望をコントロールすることを肯定的に評価した。記述中の「人間の欲望に基づく行為を人為的だと批判し」という部分が、荀子の思想と整合しない。したがって、この記述は誤りである。
問2:正解④
<問題要旨>
仏教の基本的な教えである四苦八苦のうち、いくつかの「苦」についての説明の正誤を判断する問題。
<選択肢>
①【誤】
愛別離苦(あいべつりく)は、愛する者と別れなければならない苦しみを指す。選択肢にある「万民と平等な関係を築けなくなる」という説明は、愛別離苦の本来の意味とは異なる。
②【誤】
怨憎会苦(おんぞうえく)は、怨み憎んでいる相手に会わなければならない苦しみを指す。選択肢にある「人と会うことが難しくなる」という説明は、怨憎会苦が意味する内容とは逆である。
③【誤】
求不得苦(ぐふとっく)は、求めているものが手に入らない苦しみを指す。選択肢にある「特定の身分でなければ解脱への道は得られない」という説明は、仏教の教えではなく、求不得苦の正しい意味でもない。
④【正】
五蘊盛苦(ごうんじょうく)は、人間の心身(五蘊)そのものが無常であり、思うがままにならないことから生じる苦しみを指す。私たちの心と身体が活動し、存在していること自体が苦の源であるという根本的な苦を示す。したがって、この記述は正しい。
問3:正解③
<問題要旨>
キリスト教における原罪思想について、アダム、パウロ、アウグスティヌスに関する記述の正誤を判断する問題。
<選択肢>
ア:【正】旧約聖書「創世記」には、アダムとエヴァが神の命令に背いて禁断の果実を食べ、楽園を追放された物語が記されている。このアダムの罪が全人類に受け継がれた根源的な罪(原罪)であると解釈されるようになった。したがって、この記述は正しい。
イ:【誤】パウロは、律法を守ろうとしても守れず、望まない悪を行ってしまう自己の罪深さを自覚した。しかし、その罪からの救いは、人間の努力や「隣人愛の実践」によって贖われるのではなく、イエス・キリストの贖罪を信じる「信仰によってのみ」義とされる(信仰義認)と考えた。したがって、「隣人愛を実践することを説いた」が救済の手段であるかのような記述は誤りである。
ウ:【正】教父アウグスティヌスは、人間は原罪を負っているため自力では救われず、神の一方的な恩寵(恩恵)によってのみ救済されると説いた。そして、その恩寵を仲介するのが教会であるとし、カトリック教会の権威を理論的に基礎付けた。したがって、この記述は正しい。
以上のことから、アが正、イが誤、ウが正であるため、③が正解となる。
問4:正解④
<問題要旨>
資料1のエピクロスと資料2のブッダの思想を読み取り、両者を比較した文章として最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
エピクロスは「快楽から解放されて生きる」のではなく、「快楽のある生」を目的としている。彼は、魂の動揺のない静的な快楽(アタラクシア)を理想としたのであり、快楽そのものを否定したわけではない。したがって、この記述は誤りである。
②【誤】
エピクロスは、ぜいたくや性的享楽を「快楽ではない」と断定しているわけではなく、それらが魂の動揺をもたらす種類の快楽であるため、避けるべきだと考えた。また、ブッダは喜びを「錯覚」と断じているのではなく、喜びも憂いも執着から生まれると指摘している。したがって、この記述は誤りである。
③【誤】
ブッダは「執着を捨てずに憂いのみを断つ道」を探求しているわけではない。むしろ、憂いの原因である執着そのものを断つこと(解脱)を目指した。したがって、この記述は誤りである。
④【正】
エピクロスは、魂の平静を乱す肉体的・瞬間的な快楽ではなく、分別の知によって得られる魂の平静(アタラクシア)という「別の快楽を追求するべきだ」と考えた。一方、ブッダは、資料2で示されるように、所有や執着から生まれる世俗的な喜び(とそれに伴う憂い)そのものを問題視し、執着から離れることを示唆している。両者の思想の違いを的確に捉えているため、この記述は正しい。
問5:正解①
<問題要旨>
様々な思想における「人間の理想的な生き方」についての説明の正誤を判断する問題。
<選択肢>
①【正】
プロティノスは新プラトン主義の思想家であり、万物は至高の存在である一者(ト・ヘン)から流出(emanatio)したものであり、人間は思惟や修行を通じて再びその一者へと還帰し、合一(ヘノーシス)することを理想とした。したがって、この記述は正しい。
②【誤】
梵我一如は、古代インドのウパニシャッド哲学の中心思想であり、宇宙の根本原理であるブラフマン(梵)と個人存在の本質であるアートマン(我)が同一であることを悟る境地を指す。ブッダが理想としたのは、煩悩の炎が吹き消された涅槃(ニルヴァーナ)の境地であり、梵我一如ではない。
③【誤】
「天地自然と一体となり、物事にとらわれない絶対的に自由な境地に遊ぶ」という思想は荘子のものだが、その理想像は「真人」や「至人」と呼ばれる。「大丈夫」は、儒教、特に孟子が用いた言葉で、高い道徳性を備えた人物を指す。
④【誤】
三位一体は、父なる神・子なるイエス・聖霊が、三つの位格(ペルソナ)でありながら本質において一つの神であるとする、神のあり方についてのキリスト教の中心的教義である。信者が目指す理想の生き方そのものを指す言葉ではない。
問6:正解③
<問題要-旨>
イスラームの聖典クルアーンについての説明と、資料として示された章句の内容の解釈として、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
資料には「信仰を拒む者たちの諸国での活躍がおまえを惑わすことがあってはならない。わずかな享楽であり、それから彼らの棲家は火獄である」とあり、不信仰者も現世では「わずかな享楽」を得ることが示唆されている。したがって、「現世の享楽も…得られない」という記述は誤りである。
②【誤】
クルアーンは、「神の教えをムハンマドが説明したもの」ではなく、神(アッラー)が天使ジブリール(ガブリエル)を通じて預言者ムハンマドに伝えた「神の言葉(啓示)」そのものであるとされる。したがって、記述の前半部分が誤りである。
③【正】
イスラームにおいて、クルアーンは神から人類への「最後の啓示」と位置づけられている。また、資料には来世の楽園の様子が「下に河川が流れる」「妻たちと木陰で寝台にもたれかかる」「果物がある」など、現世の物質的な快楽から類推しやすい形で描写されている。したがって、この記述は正しい。
④【誤】
資料は現世の享楽と来世のそれを比較し、来世のものが「一層良く、一層残る」と述べているが、「現世の一切の享楽を拒否すれば」来世の快楽が得られる、というような極端な禁欲主義を説いているわけではない。したがって、この記述は誤りである。
問7:正解②
<問題要旨>
資料(『朱子語類』)を読み、孔子の「己の欲せざる所は人に施すなかれ」という恕の精神を、朱子がどのように解釈しているかを理解する問題。
<選択肢>
①【誤】
資料の中で朱子は、罪人に刑罰を加えないことを「その場限りの上辺だけの行いとなる弊害がある」と批判的に論じている。したがって、それを「思いやりのある行為である」とするこの選択肢は、資料の趣旨と反対である。
②【正】
資料で朱子は、「忠」(自分の真心を尽くすこと)に基づいて「恕」を考えるべきだと説く。そして、罪人自身も、その真心においては、罪を犯せば刑罰を受けて当然だと承知しているはずだと論じている。したがって、この記述は資料の内容と合致する。
③【誤】
資料は、「忠を理解できずに恕を行おうとする」ことが問題であると指摘している。「相手の私心と自己の私心とを区別できない」ことが問題であるとは述べていない。
④【誤】
資料では、「真心」(まごころ)を尽くすことの重要性が説かれており、「私心」(私的な欲望)を尽くすことについては述べられていない。むしろ、刑罰を欲しないのは私心の働きであるとされている。したがって、「私心を尽くせない」という記述は誤りである。
問8:正解②
<問題要旨>
一連の会話の流れを踏まえ、登場人物Aの考えの変化を最もよく表す記述を空欄に補充する問題。Bの応答「自分の利益や楽しみに還元されない価値を認めつつも、快楽の概念を再考するってこと?」が重要なヒントとなる。
<選択肢>
①【誤】
Aが「人とのつながりを自分の楽しみとして追求する」と結論づけてしまうと、それは結局「自分の利益や楽しみ」に還元されることになり、Bの言う「還元されない価値を認めつつも」という部分と矛盾する。
②【正】
「人と生きることの中にある善も、自分(の快楽)のためではないにしても人間としての一種の快楽と捉えてみよう」という考えは、当初の利己的な快楽観を乗り越え、「快楽の概念を再考」し、より広い意味で捉え直そうとする姿勢を示している。Bの応答とも完全に一致しており、会話全体の文脈に最も適合する。
③【誤】
Bは「快楽を吟味してそれを人間の理想とした思想家はいない」という指摘はしていない。むしろ、会話の冒頭で「快楽の内容を厳しく見つめ直すことを通して、人間の理想的な生き方を探し求めた思想家もいたんだね」と述べており、この選択肢は会話の内容と矛盾する。
④【誤】
「自分にとって快楽と感じられなくても、友人とともに生きることも快楽とみなしてみよう」という表現は、②と似ているが、やや無理やり言い聞かせているようなニュアンスがある。②の「人間としての一種の快楽と捉えてみよう」という表現の方が、快楽の概念自体を積極的に拡張・再考しようとするAの知的な変化をより的確に表している。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
近代日本の民衆の生活や社会に向き合った思想家についての説明として、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【正】
南方熊楠は、粘菌の研究などで知られる博物学者・生物学者であると同時に、民俗学にも深い知見を持ち、神社合祀令に反対して鎮守の森の保護運動を展開したことで知られる。したがって、この記述は正しい。
②【誤】
安部磯雄は、日本における社会主義の先駆者の一人であり、キリスト教の牧師でもあった。彼の思想はキリスト教的人道主義と社会主義が結びついたものであり、社会主義を捨ててキリスト教に転じたわけではない。
③【誤】
柳宗悦は、民芸運動の創始者であり、名もなき職人の手による日常的な工芸品の中に「用の美」、すなわち実用性と結びついた健全な美しさを見いだした。「実用を離れた装飾美」を評価したとする記述は、民芸運動の趣旨とは逆である。
④【誤】
植木枝盛は、自由民権運動の思想家であるが、その思想はイギリス流の穏健なものではなく、フランスのルソーなどの影響を受けた急進的なもので、抵抗権(革命権)を認めるなどした。
問2:正解④
<問題要旨>
『古事記』などに見られる古代日本の神々や天地に関する思想についての説明として、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
『古事記』によれば、イザナギとイザナミは、日本の国土(大八島国)や様々な神々を産んだ(国生み・神生み)とされるが、神々の住まう高天原そのものを産み出したわけではない。高天原は、天地開闢の際にすでに出現している。
②【誤】
古代の神々も、神意を問うために占い(太占)を行ったと『古事記』などには記されている。神々が占いなしに他の神の意志を認識できたわけではない。
③【誤】
古代日本の神道(古神道)では、神々は山や川、木や岩といった現実世界の具体的な事物や事象に宿り、その働きとして現れると考えられていた。現実世界から切り離された超越的な存在として祀られたわけではない。
④【正】
『古事記』の冒頭では、天地が初めて分かれたとき、高天原に造化三神(天之御中主神など)が次々と「成りませる」、すなわち自然に出現したと記されており、それらの神々を創造したさらに上位の絶対神のような存在は想定されていない。したがって、この記述は正しい。
問3:正解②
<問題要旨>
資料として提示された安藤昌益『統道真伝』の一節と、彼の思想についての説明として、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
安藤昌益は、誰もが自ら土地を耕す「万人直耕」の自然世を理想とし、農作物の商品化や貨幣経済を批判した。したがって、「農作物の商品化を奨励した」という記述は誤りである。
②【正】
安藤昌益は、人間と自然が互いに助け合って万物を生み出す関係(互性)にあると考え、農耕を自然の働きに参加する神聖な営みと捉えた。資料で「人間や動植物は、全て食から生じ食を行う」と述べられている通り、万物が食という営みにおいて平等であると考えていた。したがって、この記述は正しい。
③【誤】
安藤昌益は儒教や仏教を、人々を支配し搾取するための「法世」の教えとして厳しく批判したが、それに代わるものとして「社会の法制度の拡充と徹底」を訴えたわけではなく、むしろそうした人為的な法制度のない「自然世」への復帰を主張した。
④【誤】
安藤昌益は、資料中で聖人や釈迦を「みずから食物を作らずに他人の作物を搾取している」と厳しく批判しており、彼らを「食に関わる必要がない例外的存在」とは全く考えていない。
問4:正解③
<問題要旨>
資料(『南方録』)の内容を正確に読み取り、そこに示されている茶道の思想(わび茶の精神)を説明したものとして、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
資料では、花や紅葉(華やかな茶)を経験した先に、苫屋(質素なわびの境地)の良さが見いだされると説いている。「粗末な家のように貧相にしないことに努めるべき」という記述は、資料の趣旨と逆である。
②【誤】
資料は、花や紅葉を知らない人が「初めから苫屋には至れない」と述べている。つまり、華やかな美を経験することも、わびの境地に至るためには必要であるとしている。単に華美を否定し、侘しいものをよしとするだけではない。
③【正】
資料は、「花や紅葉をじっくり眺め尽くしてみると、それは無一物の境界、浦の苫屋である」と述べ、さらに「花や紅葉を知らない人が初めから苫屋には至れない」と説明している。これは、華やかさや豪華さを知悉した上で、その先にある質素で静かな境地(わび)に至ることこそが茶道の本質である、という考え方を示している。したがって、この記述は資料の内容と完全に合致する。
④【誤】
資料は、花や紅葉(立派な茶)を「じっくり眺め尽くす」必要があると述べており、それらに関心を向けるなとは言っていない。華やかな世界を経由することの重要性を説いている点で、この選択肢は誤りである。
問5:正解③
<問題要旨>
日本の仏教思想史における肉食についての考え方をまとめたノートの空欄a、bに入る思想家の組合せとして、正しいものを選ぶ問題。
<選択肢>
空欄aは不殺生戒を説く人物、空欄bは悪人でも救われるという他力思想を説く人物が入る。
bには、人間は他の命を奪わねば生きられない罪深い存在(悪人)であるが、そのような者こそ阿弥陀仏の救いの目当てであると説いた親鸞が最も適合する。これにより、選択肢は①か③に絞られる。
次にaを検討する。
①のaは道元。道元も不殺生を説いたが、③のaは空海。空海は密教の教主である大日如来を宇宙の真理そのものとみなし、あらゆる事象はその働きであると説いた。この万物肯定の思想から、生命を尊び肉食を戒める考えが導かれると解釈できる。
bに入る親鸞の説明として、①の記述も正しいが、③の「どんなに努めても自力では煩悩を振り切ることはできないと自覚し、阿弥陀仏の本願他力を信じるべきである」という説明は、親鸞思想の核心である絶対他力の考えをより正確に示している。
総合的に判断すると、③の組合せが最も適当である。
問6:正解⑤
<問題要旨>
『養生訓』の著者とその思想の説明の正しい組合せを選ぶ問題。
<選択肢>
まず、『養生訓』を著し、日常の食事を通じた心身の健康を説いたのは、江戸時代の儒学者・本草学者である貝原益軒である。したがって、思想家はイとなる。
次に、貝原益軒の思想の説明を選ぶ。
エ:古学を提唱したのは、山鹿素行や伊藤仁斎などであり、貝原益軒ではない。
オ:貝原益軒は、朱子学の合理主義的な精神を受け継ぎ、実証的な博物学(本草学)研究に励んだが、晩年には理気二元論などの朱子学の教説に疑問を抱くようになった。この説明は貝原益軒の思想と経歴に合致する。
カ:身分秩序を理の表れとして重視するのは、林羅山など幕府に仕えた朱子学者の典型的な思想である。
したがって、正しい組合せはイとオであり、⑤が正解となる。
問7:正解③
<問題要旨>
資料として示された宮沢賢治の『ビヂテリアン大祭』の一節を読み、その内容に合致する説明を選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
「やむを得ない場合には肉食も許される」という点は正しいが、資料は「もしその一人が自分になった場合でも敢て避けない」という、自己犠牲をも覚悟する命の連鎖への視点に言及している。この重要な点が欠けているため、不十分である。
②【誤】
資料は、「もしたくさんのいのちの為に、どうしても一つのいのちが入用なときは、仕方ないから泣きながらでも食べていい」と述べており、いかなる場合も動物の命を奪わないという絶対的な立場ではない。したがって、「徹底するべきである」という記述は資料の内容と異なる。
③【正】
資料は、多くの命を救うために一つの命を犠牲にせざるを得ない場合があることを認めつつ、「そのかわりもしその一人が自分になった場合でも敢て避けない」と述べている。これは、自分自身もまた、他者のために犠牲になりうる命の連鎖の中にいるという自覚を促すものである。したがって、この記述は資料の内容を最も的確に捉えている。
④【誤】
資料は「ふだんはもちろん、なるべく植物をとり、動物を殺さないようにしなければならない」と明確に述べており、「肉も野菜も分け隔てなく大事に食べる」ことを推奨しているわけではない。
問8:正解④
<問題要旨>
柳田国男の資料と、CとDの会話文の両方を踏まえて、ノートの内容として最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
柳田国男の資料は、子どもの「ままごと」が、かつてのハレの日の特別な共同の食事の「名残」であり「模倣」であると述べている。ハレの日の食事がままごとの再現であったかのように書かれているこの選択肢は、因果関係が逆である。
②【誤】
柳田国男の資料は、集団での食事が「ハレ」という「非日常」の特別な快楽であったと述べている。「日常生活の中で」楽しもうとしてきた、という記述は資料の趣旨と異なる。
③【誤】
CとDの会話の中で、食の生産者に言及した安藤昌益の思想が話題に上っている。しかし、過去の思想家に「生産者への意識が欠けていた」と断定しているわけではなく、またそれが会話の主題でもない。
④【正】
柳田国男の資料から、「皆で集まって食事することは、日常では得られない特別な感情を伴ってきたこと」が読み取れる。また、CとDの会話では、Cが「神人共食」の考えに触れ、「食を通じた自分と他の様々な人やものとの結び付きを意識できた」と述べている。このことから、「食や共食の思想は、人間の日々の生のあり方を律しつつ、神に対する人の向き合い方にも繋がっている」というまとめは、資料と会話の両方の内容を的確に踏まえている。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
16世紀の宗教改革と、それに対するカトリック側の対抗宗教改革に関する説明として、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
ウィクリフやフスは宗教改革の先駆者とされる人物であり、教皇の権威や教会の腐敗を批判した。教皇の権威を「正当化する主張を展開した」という記述は誤りである。
②【正】
ルターが「万民司祭説」を唱え、全ての信者は神の前で平等であるとしたように、宗教改革は身分や聖職者といった階級的な権威を否定し、個人の内面的な信仰を重視した。この精神は、近代における個人の尊厳や人権、平等思想の基盤の一つとなった。したがって、この記述は正しい。
③【誤】
「福音主義」(信仰のみによって義とされる)は、ルターなど宗教改革側の中心的な立場である。カトリック教会が改革運動に対抗して行った対抗宗教改革(反宗教改革)で成立した立場ではない。
④【誤】
イグナティウス=デ=ロヨラは、対抗宗教改革の中でイエズス会を設立し、教皇への絶対的服従と厳格な規律を掲げてカトリックの勢力回復に努めた。「神を信じる者は等しく司祭である」というのは、ルターの万民司祭説であり、イグナティウスの考えとは異なる。
問2:正解④
<問題要旨>
資本主義を批判的に論じた思想家(ドゥルーズとガタリ、レーニン、ハーバーマス)についての説明のうち、適当なものを全て選ぶ問題。
<選択肢>
ア:【正】ドゥルーズとガタリは、『アンチ・オイディプス』などで、人間が持つ欲望を肯定的に捉え、資本主義体制や国家、家族といった既存の制度が、その欲望の自由な流れを抑圧していると批判した。したがって、この記述は正しい。
イ:【正】レーニンは、マルクス主義を発展させ、資本主義が最終段階である帝国主義に至ると分析した。そして、帝国主義段階のロシアでは、労働者(プロレタリアート)と農民の同盟を基盤とする前衛党が革命を指導し、社会主義を実現すべきだと考えた。したがって、この記述は正しい。
ウ:【誤】ハーバーマスは、権力や貨幣といったシステムが、人々の対話的なコミュニケーションによって成り立つ「生活世界」を侵食する「植民地化」を批判した。しかし、彼がその対抗手段として重視したのは、合理的な対話を通じて合意形成を目指す「コミュニケーション的理性」であり、効率や計算を重視する「道具的理性」は、むしろシステム側の論理である。したがって、この記述は誤りである。
以上より、アとイが正しいため、④が正解となる。
問3:正解④
<問題要旨>
アダム・スミスの『道徳感情論』における「共感」についての資料を読み、スミスの思想と資料の内容を踏まえた事例の説明として、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
資料では、他者の感情を「見るだけで」共感が生じる場合と、想像力によって共感が生じる場合の両方が述べられている。「みてはじめて…できる」という記述は、資料の一側面しか捉えていない。
②【誤】
スミスは、個人の利己的な利益追求が結果的に社会全体の利益につながると考え(神の見えざる手)、私益の追求を否定していない。また、資料は、相手が自身の振る舞いを不適切だと感じていなくても、こちらが共感(この場合は羞恥心)を抱くことがある、と述べている。
③【誤】
スミスは、人間の利己心を否定せず、むしろ経済活動の原動力として肯定的に捉えた。したがって、「人間の利己心を認めず」という前提が誤りである。
④【正】
スミスは、人間が法や正義のルールを守る「フェア・プレイ」の精神を持つべきだと考えた。資料では、他者(賄賂を贈った人)が恥じていなくても、その人の立場を想像することでこちらが恥ずかしくなる(共感する)ことがあると説明されており、この選択肢の事例は資料の内容と完全に合致する。前提となるスミスの思想の説明も正しい。
問4:正解①
<問題要旨>
ヘーゲルの分業に関する文章を読み、その思想と資料の内容の説明として最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【正】
ヘーゲルは、精神が自己を展開していく過程を「弁証法」として捉え、歴史もその法則に従うと考えた。資料では、分業によって労働が抽象化・機械的になることで、「機械によって人間の労働を置き換えることが可能となる」と結論づけている。この記述は、資料の内容を正しく要約している。
②【誤】
「人間は衝動に促されて苦の世界を生きている」という思想は、ヘーゲルではなくショーペンハウアーのものである。
③【誤】
資料は、分業によって労働が「抽象的と」なり、「単調さゆえに」生産が増大すると述べている。生産量が増大するから労働が容易になる、という因果関係ではない。
④【誤】
ヘーゲルは、個人の自由な利益追求の場である「市民社会」の対立は、より高次の共同体である「国家(人倫)」において統合され、真の自由が実現されると考えた。「市民社会の中で最高の形で実現される」としたこの記述は誤りである。
問5:正解②
<問題要旨>
ドイツとイギリスにおける社会民主主義の源流となった思想家や団体(ベルンシュタイン、フェビアン協会)に関する説明として、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
ベルンシュタインは、マルクスの予測に反して資本主義は崩壊せず、労働者の生活は改善されつつあると現実を分析し、マルクス主義の修正を試みた(修正主義)。「マルクスの予測どおりに現実が進行していると考え」たわけではない。
②【正】
ベルンシュタインは、革命による社会変革ではなく、議会制民主主義の枠内で、労働者階級の代表が議会活動を通じて社会政策を前進させ、漸進的に社会主義を実現していくべきだと主張した。したがって、この記述は正しい。
③【誤】
共同生活の村(理想社会の実験)を試みたのは、ロバート・オーウェンなどの空想的社会主義者である。フェビアン協会は、議会を通じた漸進的改革を目指した。
④【誤】
フェビアン協会は、ローマの将軍ファビウスの持久戦術にその名を由来するように、「急進的」ではなく「漸進的」な社会改革を志向した。
問6:正解③
<問題要旨>
哲学者カール・ポパーの科学哲学や社会思想についての説明として、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
人間の思考や行為を支える構造を抽出し、人間の主体性を問い直すのは、レヴィ=ストロースなどの構造主義(ストラクチュラリズム)の思想である。ポパーの思想ではない。
②【誤】
これは、ポパーが批判した論理実証主義などが取る「検証」の考え方である。ポパーは、科学理論は検証によって証明されるのではなく、反証(=誤りであることの証明)に耐えることによってその確かさを増していくと考えた。
③【正】
これは、ポパーの科学哲学の中心概念である「反証可能性」を的確に説明している。科学的理論とは、どのような実験や観察によってその理論が誤りであると証明されうるか(反証されうるか)が明確な理論のことであり、いかなる理論も、新たな反証によって覆される可能性を常にはらんでいるとした。したがって、この記述は正しい。
④【誤】
ポパーは、社会全体を一度に変革しようとする全体主義的な社会計画(ユートピア的社会工学)を批判し、社会の問題を一つずつ漸進的に修正していく「漸次的社会工学(ピースミール・エンジニアリング)」を提唱した。「社会全体の漸次的な変革を目指した」のは、ポパーが批判した対象ではなく、彼自身が提唱した方法である。
問7:正解①
<問題要旨>
資料1(イリイチのシャドウ・ワーク)と資料2(キテイの依存労働)の内容を踏まえ、会話の空欄a、bを埋めるのに最も適当な語句の組合せを選ぶ問題。
<選択肢>
空欄aは、賃金の支払われない「シャドウ・ワーク」の具体例を問うている。
空欄bは、ケアする側とされる側の不平等な関係から生じる「依存労働」の問題点を問うている。
①のa「家族のために食事の準備をすること」は、家事労働でありシャドウ・ワークの典型例である。b「家庭で介護に携わる人は、介護される高齢者に援助を求められたとしたら、その要求を拒むことが難しい状況にある」は、資料2が指摘する依存労働者の脆弱性(vulnerability)を的確に説明している。
②のbは、介護者が「対等な個人としてその報酬を得ることができる」としており、資料2が問題にする不平等な関係性とは逆の内容である。
③④のaは、教師の職務(テストの採点、出欠確認)であり、賃労働の一部であって、イリイチの言うシャドウ・ワークにはあたらない。
したがって、aとbの両方が正しいのは①のみである。
問8:正解②
<問題要旨>
一連の会話と資料を踏まえ、登場人物Eの労働観の変化をまとめたノートの空欄a、bを埋めるのに最も適当な記述の組合せを選ぶ問題。
<選択肢>
①のb「賃金の支払われる労働が、賃金の支払われない労働から切り離されている」という記述は、むしろ両者が補完関係にあるというイリイチの指摘と異なる。
②のa「労働についての視野を広げるためには、労働の多様なあり方や労働者の置かれた社会的立場に目を向けることが大事だ」は、当初の画一的な労働観から、資本主義下の労働、シャドウ・ワーク、依存労働など多様な労働形態へとEの視野が広がったことを的確に示している。b「人間の労働には経済活動以外の側面があるということ」は、資料1、2が示す家事や育児、介護といった、経済活動を支える非経済的な労働の重要性を指しており、これもEの気付きと合致する。
③のa「人間が労働において平等な関係に置かれているという現状に目を向ける」という記述は、マルクスやキテイが指摘する搾取や不平等な関係性といった議論と矛盾する。
④のa「賃金の支払われない労働では常にやりがいが度外視される」という記述は、E自身が例に出した「文化祭の準備」というやりがいのあった無償労働の経験と矛盾する。
したがって、aとbの両方がEの学びを的確に反映しているのは②である。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
人と自然の関わりに関する「スチュワードシップ」という考え方の説明として、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
これは、科学的な不確実性があっても、重大な損害の恐れがある場合には予防的な対策を取るべきだという「予防原則」の説明である。
②【誤】
これは、将来世代のニーズを損なうことなく現代世代のニーズを満たす開発を目指す「持続可能な開発(サステイナブル・ディベロップメント)」の説明である。
③【正】
スチュワードシップは、聖書に由来する考え方で、人間は自然の所有者ではなく、神からその管理(stewardship)を委ねられた「管理人(steward)」であるとする。そのため、自然を搾取するのではなく、責任をもって管理・保護すべきだと考える。したがって、この記述は正しい。
④【誤】
これは、多くの人が利用できる共有資源が、個人の利益追求によって枯渇してしまう問題を指す「コモンズの悲劇」の説明である。
問2:正解①
<問題要旨>
教育や人間の知性について論じた思想家(デューイ、ジェームズ)の説明として、最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【正】
プラグマティズムの思想家デューイは、知性を、人間が環境との相互作用の中で生じる問題に対処し、よりよく生きていくための「道具」として捉えた。そして、子どもが自ら試行錯誤しながら問題解決に取り組む経験(なすことによって学ぶ)を重視した。したがって、この記述は正しい。
②【誤】
知識の発展を「神学的段階」「形而上学的段階」「実証的段階」の三段階で捉えたのは、コントである。
③【誤】
人間を「シンボルを操る動物」と定義し、言語や神話、芸術といったシンボル的活動を通じて世界を理解するとしたのは、カッシーラーである。
④【誤】
神や価値に関する形而上学的な問いは、客観的に真偽を確かめられず、言語表現の限界の外にあるとして退けたのは、ウィトゲンシュタイン(前期)などの論理実証主義の思想である。
問3:正解⑤
<問題要旨>
充実した人生と関係する心的状態を論じた人物(神谷美恵子、マズロー、アドラー)についての説明のうち、適当なものを全て選ぶ問題。
<選択肢>
ア:【正】精神科医の神谷美恵子は、ハンセン病患者との交流を通じて、「自分には果たすべき使命がある」という使命感や、「自分が誰かから必要とされている」という感覚が「生きがい」の中核をなすと論じた。したがって、この記述は正しい。
イ:【誤】マズローは、欲求を階層構造で捉え、生理的欲求、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求といった低次の欲求(欠乏欲求)が満たされて初めて、自己実現の欲求という最高次の欲求(成長欲求)が現れると考えた。「自己実現の欲求といった欲求が満たされてはじめて現れる」という部分が、自己実現欲求を低次の欲求と誤解しており、誤りである。
ウ:【正】心理学者のアドラーは、人間は誰もが「劣等感」を持っており、それを克服しようとする「優越性の追求」が、人間の努力や成長の原動力になると考えた。したがって、この記述は正しい。
以上より、アとウが正しいため、⑤が正解となる。
問4:正解④
<問題要旨>
心理学者レヴィンの青年期に関する資料を読み、その思想と資料の内容の説明として最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
人間の発達を8段階のライフサイクルとして捉えたのは、エリクソンである。レヴィンではない。
②【誤】
資料では、青年は「大人から完全に受け入れられていないことは分かっている」と述べられており、「大人の集団に受け入れられたことを自覚して」いるわけではない。
③【誤】
人間の発達を8段階のライフサイクルとして捉えたのは、エリクソンである。レヴィンではない。
④【正】
レヴィンは、葛藤(コンフリクト)の類型化などで知られる。彼は、青年期を、子ども集団にはもはや所属していたくないが、大人集団にも完全には所属できない境界的な状態にある「マージナル・マン(境界人)」として特徴づけた。資料では、この青年期のあり方と、マイノリティ集団の境界にいる成員のあり方が似ていると指摘している。したがって、この選択肢は資料の内容を正しく説明している。
問5:正解②
<問題要旨>
資料と図で示された心理学実験の結果を読み解き、考察の空欄に入る記述として最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
考察の趣旨は、「人々が実際には見知らぬ人に話しかけないのはなぜか?」という理由を、図から説明することである。
人々が行動を選択する際は、その行動が成功したとき(達成条件)の快さよりも、その行動を試みるとき(トライ条件)に予測される快さや不快さに基づいて判断する傾向がある。
図を見ると、「会話トライ条件」(0.22)の快さの予測値は、「会話達成条件」(1.00)よりも著しく低い。つまり、「話しかけようとすること」は、「話しかけてうまくいっている状態」に比べて、ずっと快くない(むしろためらわれる)と予測されている。この予測が、人々が話しかけるのをためらう原因だと考えられる。
②の記述は、この「会話トライ条件」と「会話達成条件」の得点差に着目し、「話しかけようとする場面は、うまく会話できている場面ほどには快くないだろう」と人々が予測しているからだ、と説明している。これは、図から読み取れる合理的な推論である。
①③④は、比較する条件が不適切であったり、結論が考察の趣旨とずれていたりするため、誤りである。
問6:正解②
<問題要旨>
社会学者アルヴァックスの記憶に関する資料を読み、その内容の説明として最も適当なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
資料の冒頭でアルヴァックスは、心理学が人間を「孤立した存在として考察していることにとても驚く」と述べており、個人に対象を限定するアプローチを批判している。したがって、この記述は資料の趣旨と逆である。
②【正】
資料には、「私が過去を思い出すのは、他の人々が自分に過去を想起するように促し、他の人々の記憶が自分の記憶を助け、自分の記憶は他の人々の記憶に支えられるからである」と明確に書かれている。これは、個人の記憶が、その人が属する集団(家族、友人、社会など)によって支えられ、形成されるという「集合的記憶」の考え方を示している。したがって、この記述は資料の内容に合致する。
③【誤】
資料は、「過去の思い出は、外部から呼び起こされたものだからである」と述べ、記憶が個人の脳内に完結しているという考えを否定している。「自己の力で過去を思い起こす」という記述は、資料の主張と反対である。
④【誤】
資料は、「自分が所属している諸集団に関心を向け、少なくとも一定の間、そこでのものの考え方を取り入れさえすれば」思い出を再構成する手段が得られると述べており、単に所属しさえすればよい、という無条件な話ではない。
問7:正解①
<問題要旨>
キング牧師、マザー・テレサ、マララ・ユスフザイという、困難な状況にある人々に寄り添った人物に関する説明の正誤を判断する問題。
<選択肢>
ア:【正】マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは、アメリカの公民権運動の指導者であり、インドの独立運動を率いたガンディーの非暴力思想に深く影響を受け、黒人差別に対する非暴力・不服従の抵抗運動を展開した。したがって、この記述は正しい。
イ:【正】マザー・テレサは、カトリックの修道女として、インドのコルカタ(カルカッタ)を拠点に、貧しい人々や病人、孤児など、社会から見捨てられた人々のためのホスピスや児童養護施設を設立し、その救済活動に生涯を捧げた。したがって、この記述は正しい。
ウ:【正】マララ・ユスフザイは、パキスタンの女性活動家であり、武装勢力による女子教育の抑圧に屈せず、教育の重要性を訴え続けた。ノーベル平和賞を受賞し、現在も世界中のすべての子どもが教育を受けられる権利を求めて活動している。したがって、この記述は正しい。
以上より、ア、イ、ウ全てが正しいため、①が正解となる。
問8:正解③
<問題要旨>
障害のある人もない人も、社会の中で当たり前に生活できるように環境を整備するという「ノーマライゼーション」の考え方の具体例として、適当でないものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
デパートがスロープを設置するのは、ベビーカー利用者や車椅子利用者などが段差という障壁(バリア)なく移動できるようにする環境整備であり、ノーマライゼーションの具体例として適当である。
②【誤】
病院が案内を多言語表示するのは、日本語を母語としない人々が情報という障壁なくサービスを受けられるようにする環境整備であり、ノーマライゼーションの具体例として適当である。
③【正】
適正な価格で製品を購入し、途上国の生産者の生活向上を支援するのは、「フェアトレード」の説明である。これは、南北間の経済格差という課題に取り組むものであり、障害の有無などにかかわらず誰もが共に生きる社会を目指すノーマライゼーションの理念とは直接の関連性が薄い。
④【誤】
自治体が障害のある人とない人が共に参加できるスポーツ大会を実施するのは、両者の交流を促し、社会的な障壁を取り除く試みであり、ノーマライゼーションの具体例として適当である。
問9:正解②
<問題要旨>
70ページの文章と、GとHの会話文を踏まえて、会話の空欄a、bを埋めるのに最も適当な記述の組合せを選ぶ問題。
<選択肢>
①のaは、住民の行動を優先し、行政を二次的なものと位置づけており、本文の「まずは政府や行政が…支援を行う」「行政の取組みだけでは支援が十分に行き届かないことがある」という記述のニュアンスと異なる。
②のa「行政の取組みも重要だけど、それでは不十分なこともあり、地域住民も積極的に行動しないといけない」は、70ページの文章が示す、行政の支援と住民のボランティア活動などが協力し合う関係性を的確に表現している。b「地域社会での交流が深まり、社会的なつながりができれば、新しい住民も地域社会の文化を受け入れやすくなる」は、Hが感じている新しい住民との居心地の悪さに対し、文章にある「地域住民と交流し、社会的なつながりを築くことができれば、…地域社会固有の文化に参加しやすくなる」という解決策を提示するものとして、文脈に完全に適合する。
③のa「行政に頼らず、地域住民だけで責任をもって解決すべきだ」は、本文が行政の役割を明確に述べている点と矛盾する。
④のb「交流の機会がなくとも、時間が経てば自然に慣れる」という楽観的な見方は、本文が交流や参加の重要性を積極的に説いている点と矛盾する。
したがって、aとbの両方が本文と会話の文脈に最も適合するのは②である。