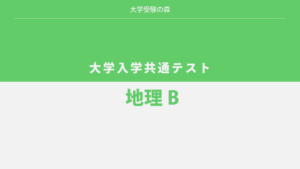解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
自然現象を時間的・空間的な規模(スケール)で整理した図を見て、モンスーン(季節風)に該当するものを選ぶ問題です。それぞれの現象が、どのくらいの期間、どのくらいの範囲で起こるのかを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
これは低気圧・台風を示します。台風は、空間的には数百~千km程度(10²~10³km)の規模で、時間的には数日間で発生から消滅まで至ります。図の①は、このスケールによく合致します。
②【正】
これがモンスーンです。モンスーンは、大陸と海洋の温度差によって生じる季節的な風系の交替で、夏と冬で風向きが大きく変わります。アジア大陸やインド亜大陸など、数千km(10³~10⁴km)にわたる非常に広大な範囲に影響を及ぼし、その期間は季節ごと、つまり数か月から1年単位となります。図の②は、このスケールに該当します。
③【誤】
これはエルニーニョ・ラニーニャ現象を示します。この現象は、太平洋赤道域の広い範囲(数千km以上)で海水温が平年より高くなったり低くなったりする現象で、数か月から1年以上続くことがあります。図の③が示すスケールと一致します。
④【誤】
これは地球温暖化を示します。地球温暖化は、地球全体(10⁴km以上)に影響が及ぶ現象であり、その変化は数十年から数百年(10¹~10²年)という非常に長い時間スケールで進行します。図の④が示すスケールに合致します。
問2:正解①
<問題要旨>
サンゴ礁とマングローブの分布図を見分け、図に示された海流の向きと正しく組み合わせる問題です。それぞれの生育条件の違いと、海流の基本的な流れを理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
マングローブは河口付近の汽水域(海水と淡水が混じる水域)に生育し、河川が運ぶ土砂が堆積した濁った環境を好みます。図イは、アマゾン川など大河川の河口周辺に分布が集中していることから、マングローブの分布図と判断できます。一方、サンゴ礁は温暖で透明度の高いきれいな浅い海を好むため、河口付近は生育に適しません。したがって、マングローブはイです。海流の向きについては、図3に示される海流には、AからBへ向かう流れ(ブラジル海流など)と、BからAへ向かう流れ(ペルー海流、メキシコ湾流、カリフォルニア海流など)の両方が存在します。選択肢では「BからA」が示されており、これは図3に存在する海流の向きとして正しい記述です。したがって、この組み合わせは正しいです。
②【誤】
マングローブの分布図はイです。アはサンゴ礁の分布を示します。
③【誤】
マングローブの分布図はイです。アはサンゴ礁の分布を示します。
④【誤】
海流の向きとして「AからB」も図3には存在しますが、正解の組み合わせは①です。
問3:正解②
<問題要旨>
東京の月別・時間別の気温分布図を参考に、パース、ヤクーツク、ラパスの3都市の同様の図を特定する問題です。各都市の気候特性(南半球か北半球か、緯度、標高など)から気温の季節変化や日較差を推測する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【正】
・カ:等温線が全体的に緩やかで、最も気温が高くなるのが1月頃、低くなるのが7月頃です。これは南半球の季節変化を示しています。気温の変化も比較的穏やかであることから、地中海性気候のパース(オーストラリア)と判断できます。
・ク:1月の平均気温が極端に低く、7月に向けて急激に気温が上昇しており、年較差が非常に大きいことが読み取れます。これはシベリアに位置し、厳しい冬と短い夏が特徴のヤクーツク(ロシア)の気候と一致します。
・キ:1年を通して気温の変動が非常に小さい(等温線がほぼ水平)一方、1日の中での気温差(日較差)は大きいことが読み取れます。これは、赤道に近く季節変化が少ないものの、標高が約3600mと非常に高いために起こる、ラパス(ボリビア)の気候特性です。
以上のことから、パースがカ、ヤクーツクがク、ラパスがキの組み合わせが正しいです。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問4:正解①、⑤
<問題要旨>
J「火山の災害」とK「熱帯低気圧の災害」について、両方が当てはまる地域と、Jのみが当てはまる地域を地図中から選ぶ問題です。プレートテクトニクスと世界の気候区分の知識を統合して考える必要があります。
<選択肢>
JとKの両方:
①【正】
カリブ海周辺は、カリブプレートと周辺のプレートがぶつかり合う境界にあたり、火山活動が活発な地域です(Jに該当)。また、大西洋で発生するハリケーン(熱帯低気気圧)の常襲地帯でもあります(Kに該当)。したがって、①はJとKの両方が当てはまります。
Jのみ:
⑤【正】
イタリアなど地中海周辺は、アフリカプレートとユーラシアプレートが衝突する場所に位置し、ベスビオ火山やエトナ火山など活発な火山が存在します(Jに該当)。一方で、この地域は熱帯低気圧の発生域ではなく、その影響を頻繁に受けることはありません(Kに該当しない)。したがって、⑤はJのみが当てはまります。
(その他の選択肢)
②【誤】
ブラジル高原は安定陸塊に位置するため、火山活動はほとんどありません。また、熱帯低気圧の影響も受けにくい地域です。
③【誤】
アフリカ大地溝帯の周辺であり、火山は存在しますが(Jに該当)、熱帯低気圧の被害を頻繁に受ける内陸地域ではありません。
④【誤】
サハラ砂漠周辺は安定陸塊であり火山はなく、熱帯低気圧の影響も受けません。
問5:正解⑤
<問題要旨>
日本の3つの地域(P, Q, R)の断面における地震の震源分布図(タ, チ, ツ)を正しく組み合わせる問題です。日本のプレートテクトニクス、特に沈み込み帯で発生する地震の深さの傾向(和達-ベニオフ帯)を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【正】
・P(東北地方):日本海溝から太平洋プレートが西向きに深く沈み込んでいます。そのため、震源は東の沖合で浅く、西の内陸に向かうにつれて深くなる明瞭な「和達-ベニオフ帯」が形成されます。図チは、東から西へ震源が深くなり、600kmに達する深い地震もみられることから、Pの断面図と判断できます。
・Q(中部・近畿地方):南海トラフからフィリピン海プレートが北西方向に沈み込んでいます。太平洋プレートに比べると、沈み込む角度が浅く、地震が発生する深度も比較的浅いのが特徴です。図ツは、東から西(南東から北西)へ震源が深くなっているものの、チほど深くはなく、この特徴と一致します。これがQの断面図です。
・R(九州地方):南海トラフから続く琉球海溝からフィリピン海プレートが沈み込んでいますが、同時に内陸部には活断層が多く存在します。図タは、明瞭な沈み込み帯が見られず、西側(内陸部)と東側(海側)にそれぞれ浅い地震が集中しています。これは九州内陸の活断層による地震と、沈み込み帯の浅い部分の地震を示していると考えられ、Rの断面図と判断できます。
したがって、タがR、チがP、ツがQという組み合わせが正しいです。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問6:正解④
<問題要旨>
都市化によって河川の降雨後の水位変化(ハイドログラフ)がどのように変わるか、またその主な要因は何かを問う問題です。都市化が水循環に与える影響についての理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
理由(ミ)の選択が誤っています。
②【誤】
変化の方向(マ)と理由(ミ)の選択が両方とも誤っています。
③【誤】
変化の方向(マ)の選択が誤っています。遊水地などの整備は洪水を抑制する方向(XからYへ近づける)に働きます。
④【正】
都市化が進む前(Y)は、森林や田畑が多いため、雨水が地面に浸透しやすく、ゆっくりと川に流れ込みます。そのため、水位の上昇は緩やかでピークも低くなります。一方、都市化が進んだ後(X)は、地面がアスファルトやコンクリートで舗装されるため、雨水が浸透せずに速やかに下水道などを通じて川に流れ込みます。その結果、短時間で水位が急上昇し、ピークも高くなります。したがって、都市化による変化は「YからXへ」です(マ)。その主な要因は、選択肢nの「森林や田畑が減少し、地表面が舗装された」ことです(ミ)。
第2問
問1:正解②
<問題要旨>
中世ヨーロッパの荘園(村落)の模式図を見て、その特徴について正しく述べている文を選ぶ問題です。当時の農業システムである三圃制についての知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
図からは、集落が防御用の濠で囲まれている様子は読み取れません。川や池はありますが、集落全体を囲んではいません。
②【正】
図には耕作地が「春耕地」「秋耕地」「休閑地」の3つに明確に分けられています。これは、耕地を3分割し、①秋耕(小麦・ライ麦)→②春耕(大麦・燕麦・豆類)→③休閑、というサイクルで土地をローテーションさせて地力の消耗を防ぐ「三圃制農業」が行われていたことを示しています。
③【誤】
耕作地が短冊状に分割されているのは、荘園内の農民たちが、質の異なる土地を公平に利用できるように、各耕地にそれぞれ細長く分散した土地を割り当てられたためです。土壌侵食の防止が主目的ではありません。
④【誤】
図の中央付近に教会や領主館があり、その周りに「集落」が形成されています。農民たちは耕作地から離れた場所に集まって住む「集村」の形態をとっており、分散して居住していたわけではありません。
問2:正解③
<問題要旨>
4つの地域(アフリカ、中央・西アジア、東アジア、ヨーロッパ)について、「耕作地に占める灌漑面積の割合」と「1ha当たりの穀物収量」の散布図から、東アジアに該当するものを選ぶ問題です。各地域の農業の特色を理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
これはアフリカです。灌漑面積の割合が低く、伝統的な農業が中心で化学肥料の使用も少ないため、土地生産性(収量)も低い水準にあります。
②【誤】
これはヨーロッパです。灌漑面積の割合は低いですが、混合農業や酪農など、資本集約的な近代農業が発達しており、土地生産性は高い水準にあります。灌漑が少ないのは、比較的降水量に恵まれている地域が多いためです。
③【正】
これが東アジアです。東アジアはモンスーン気候の影響で稲作が盛んです。稲作は多くの水を必要とするため、灌漑施設がよく整備されており、「灌漑面積の割合」が高くなります。また、肥料の多投や品種改良などにより集約的な土地利用が行われているため、「1ha当たりの穀物収量」も非常に高い水準です。図の③は、両方の値が高いことから東アジアと判断できます。
④【誤】
これは中央・西アジアです。この地域は乾燥気候が広がっているため、農業には灌漑が不可欠であり、「灌漑面積の割合」が高くなります。しかし、オアシス農業や外来河川沿いの農業が主で、塩害などの問題もあり、地域全体の土地生産性は東アジアほど高くはありません。
問3:正解④
<問題要旨>
遺伝子組み換え作物に関する文章を読み、下線部①~④の中から最も適当なものを選ぶ問題です。遺伝子組み換え作物の現状や、それを取り巻く世界の状況について正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
遺伝子組み換え作物には、特定の除草剤に耐性を持つものや、害虫を殺す成分を自ら作り出すものなどがあります。これらは農薬(除草剤や殺虫剤)の使用量を「減らす」ことはあっても、「なくす」わけではありません。また、収量向上を目的としない遺伝子組み換え作物もあります。
②【誤】
図3を見ると、栽培面積上位5か国はアメリカ、ブラジル、アルゼンチン、カナダ、インドです。このうちOECD加盟国はアメリカとカナダのみで、発展途上国(ブラジル、アルゼンチン、インド)の方が多いです。全体的に見ても、発展途上国での栽培が広がっています。
③【誤】
栽培面積上位5か国のうち、インドは国土面積が広いものの、伝統的な小規模農家が多く、必ずしも「企業的な大規模農業が中心」とは言えません。他の4か国については当てはまりますが、「いずれの国でも」という記述が誤りです。
④【正】
ヨーロッパ諸国(EU)などでは、遺伝子組み換え作物の栽培や食品への利用に対して消費者の抵抗感が根強く、厳しい規制が敷かれています。食用以外の作物(飼料用、工業用など)に限定したり、栽培自体を禁止したりしている国や地域が多く存在します。したがって、この記述は正しいです。
問4:正解④
<問題要旨>
牛肉、鶏肉、羊肉のそれぞれについて、生産量に占める輸出量の割合を示した世界地図(A~C)を正しく組み合わせる問題です。各食肉の生産国、消費国、宗教的背景、そして国際的な流通の特色を理解しているかが鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【正】
・A(鶏肉):鶏肉(ブロイラー)は飼育期間が短く、生産コストが比較的安いため、世界中で広く生産・消費されています。アメリカ、ブラジル、中国などが主要生産国です。特にブラジルやアメリカは輸出量が多く、輸出割合が高くなっています。図Aはこれらの国々で輸出割合が高いことを示しており、鶏肉と判断できます。
・B(羊肉):羊肉は、乾燥帯での遊牧や、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどで企業的牧畜により生産されます。イスラム教徒や、ヨーロッパ、中東などで伝統的に食されますが、世界的な生産量や流通量は牛肉や鶏肉に比べて少ないです。特にオーストラリアとニュージーランドは人口が少ないため、生産の大部分が輸出に向けられ、輸出割合が極めて高くなります。図Bは、オセアニアで輸出割合が突出して高いことから羊肉と判断できます。
・C(牛肉):牛肉の生産は、アメリカ、ブラジル、EU、中国、インドなど人口大国や国土の広い国で盛んです。しかし、これらの国の多くは国内消費量も非常に多いため、生産量に占める輸出の割合は、一部の輸出国(オーストラリア、ブラジル、アルゼンチンなど)を除いて、比較的低くなる傾向があります。図Cは、主要生産国である中国やアメリカで輸出割合が低い(低位)ことから、牛肉と判断できます。
以上のことから、Aが鶏肉、Bが羊肉、Cが牛肉の組み合わせが正しいです。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問5:正解③
<問題要旨>
フランスとポルトガルのEU域外への輸送手段について、「輸出額」と「輸出量(重量)」の割合を示した4つのグラフ(①~④)の中から、「フランスの輸出額」に該当するものを選ぶ問題です。両国の地理的条件や産業構造から、輸送手段の構成を推測する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
これは「フランス」の「輸出量」を示します。アがフランス、Eが輸出量であるためです。
②【誤】
これは「ポルトガル」の「輸出量」を示します。イがポルトガル、Eが輸出量であるためです。
③【正】
この問題を解くには、まず国(ア・イ)と指標(E・F)を特定する必要があります。
国の特定(ア vs イ):フランス(ア)はヨーロッパ大陸に位置し、多様な輸送手段を持ちます。一方、ポルトガル(イ)は大陸の西端にあり、EU域外との貿易は海上輸送への依存度が極めて高くなります。グラフを見ると、イ(②、④)は海上輸送の割合が圧倒的に高い一方、ア(①、③)は海上、道路、航空輸送が比較的バランスよく利用されています。したがって、アがフランス、イがポルトガルと判断できます。
指標の特定(E vs F):航空輸送は、輸送コストが高いため、軽量で付加価値の高い製品(医薬品、精密機械、航空機部品など)の輸送に主に利用されます。そのため、重量ベースの「輸出量」に占める割合は低くなりますが、金額ベースの「輸出額」に占める割合は高くなります。グラフのE(①、②)とF(③、④)を比べると、Fの方がEよりも航空輸送の割合が高くなっています。したがって、Fが輸出額、Eが輸出量と判断できます。
以上のことから、「フランスの輸出額」に該当するのは、ア(フランス)の列とF(輸出額)の行が交差する③のグラフとなります。
④【誤】
これは「ポルトガル」の「輸出額」を示します。イがポルトガル、Fが輸出額であるためです。
問6:正解③
<問題要旨>
日本、アメリカ、カナダ、ドイツの4か国について、紙の原料となる「パルプ」と「古紙」の消費量を示したグラフから、ドイツとパルプの正しい組み合わせを選ぶ問題です。各国の森林資源の状況や環境政策の違いを考慮する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【正】
・国(カ~ク):
カ:X、Yともに消費量が突出して多い。これは世界最大の経済大国であり、紙の生産・消費量も世界一であるアメリカ合衆国と判断できます。
ク:Yの消費量が非常に少ない。カナダは広大な森林資源に恵まれ、木材パルプの生産が盛んな一方、人口が比較的少ないため国内で回収される古紙の量は限られます。したがって、クがカナダと考えられます。
キ:日本のグラフと似たような規模で、XとYのバランスが取れています。これがドイツです。ドイツは環境先進国として知られ、古紙の回収と利用が非常に進んでいます。
・原料(X、Y):
パルプは木材から作られる一次原料、古紙はリサイクル原料です。アメリカ(カ)やカナダ(ク)のような森林資源が豊富な国では、パルプの消費割合が高くなる傾向があります。一方、日本やドイツ(キ)のように国内の森林資源が限られ、環境意識が高い国では、古紙の利用率が高くなります。ドイツ(キ)のグラフを見ると、Y(灰色)の方がX(白色)よりも多くなっています。これは古紙利用が進んでいることを示唆します。したがって、Yが古紙、Xがパルプです。
・結論:ドイツはキ、パルプはXです。この組み合わせは③です。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
1960年と2018年における、四国・九州から三大都市圏への人口移動の内訳を示したグラフです。九州地方と東京圏の正しい組み合わせを選ぶ問題で、時代による国内の人口移動パターンの変化を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
・移動先(A, B):1960年(高度経済成長期)には、西日本の各地域から最も近い大都市圏である大阪圏(京阪神)への人口流入が盛んでした。その後、経済活動の東京一極集中が進み、近年では全国から東京圏への人口流入が主流となっています。グラフを見ると、1960年にはA・BともにBへの移動割合が高く、2018年にはAへの移動割合が逆転して最も高くなっています。この変化から、Bが大阪圏、Aが東京圏と判断できます。
・移動元(ア, イ):九州は四国よりも人口が多く、大阪圏(B)との地理的・経済的な結びつきが歴史的に強いです。1960年のグラフで、イよりもアの方が大阪圏(B)への移動割合が著しく高いことから、アが九州地方、イが四国地方と判断できます。
・結論:九州地方はア、東京圏はAとなります。
②【誤】
東京圏はAです。
③【誤】
九州地方はアです。
④【誤】
九州地方はア、東京圏はAです。
問2:正解⑤
<問題要旨>
1970年以降の東京都区部における3つの指標(工業地区の面積、住宅地の平均地価、4階以上の建築物数)の推移を示したグラフ(カ~ク)を正しく組み合わせる問題です。バブル経済とその崩壊など、戦後の東京の社会経済的変化に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【正】
・カ(住宅地の平均地価):1980年代後半から1990年初頭にかけて、日本の地価は異常な高騰を見せました(バブル経済)。その後、バブル崩壊により地価は急落しました。グラフカは、1990年頃に極端なピークを迎え、その後急落するという特徴的な動きを示しており、住宅地の平均地価と判断できます。
・キ(4階以上の建築物数):東京では都市化の進展と土地の高度利用に伴い、高層の建物が一貫して増え続けています。グラフキは、多少の変動はありつつも、長期的に右肩上がりの増加を示していることから、4階以上の建築物数と判断できます。
・ク(工業地区の面積):高度経済成長期以降、地価の高騰や公害問題などから、都心部の工場は郊外や地方、海外へ移転する傾向が続きました。そのため、都区部の工業地区の面積は一貫して減少し続けています。グラフクは、1970年を100として、一貫して減少を続けているため、工業地区の面積と判断できます。
したがって、カが地価、キが建築物数、クが工業地区面積という組み合わせが正しいです。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問3:正解⑥
<問題要旨>
ある地方都市の地図(図3)と、3つの地点(D, E, F)周辺の景観に関する会話文(サ~ス)を正しく組み合わせる問題です。地図から読み取れる情報(駅、市役所、幹線道路、土地利用など)と、都市の発展過程(中心市街地の空洞化、郊外化など)を結びつけて考える必要があります。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【正】
・地点D:鉄道の駅や市役所に隣接しており、格子状の道路網が見られることから、古くからの中心市街地であると推測されます。会話文スは「百貨店やスーパーマーケットがあってにぎわっていた」が「現在は人通りは少なく、シャッターが閉まったままの店舗もある」と述べており、これは中心市街地の空洞化(ドーナツ化現象)の様子を描写しています。したがって、Dがスです。
・地点F:市街地から離れた郊外に位置し、幹線道路沿いにあります。会話文サは「周辺には水田や畑が広がっていた」が「現在は、道路沿いに全国チェーンの店舗がみられる」「広い駐車場がある」と述べており、これは自動車社会の進展に伴う郊外のロードサイド店舗の発展(郊外化)の様子を示しています。したがって、Fがサです。
・地点E:中心市街地と郊外の中間に位置し、比較的新しい住宅地のように見えます。会話文シは「水田や畑が広がっていた」「近年は開発が進んで住宅が増えている」と述べており、宅地開発が進む郊外の様子を描写しています。したがって、Eがシです。
以上のことから、Dがス、Eがシ、Fがサの組み合わせが正しいです。
問4:正解②
<問題要旨>
日本の過疎化や高齢化に関する3つの地図と、それについての会話文を読み、下線部①~④の中から誤りを含むものを選ぶ問題です。地図から読み取れる傾向と、日本の人口問題に関する知識を照らし合わせて判断します。
<選択
①【正】
「過疎市町村の面積が都道府県面積に占める割合」の地図を見ると、東京、大阪、愛知などの三大都市圏では割合が低く(下位)、それ以外の中国山地や北海道、東北地方などで割合が高く(上位)なっています。したがって、「三大都市圏よりも三大都市圏以外の地域で高い傾向にある」という記述は正しいです。
②【誤】
「老年人口の増加率」の地図を見ると、三大都市圏(特に東京圏、名古屋圏)で増加率が高く(上位)なっています。この原因は、高度経済成長期に地方から三大都市圏へ移住した団塊の世代などが、そのまま三大都市圏で高齢期を迎えているためです。三大都市圏以外から「高齢者」が新たに大量に流入しているわけではありません。したがって、この記述は誤りです。
③【正】
農山村地域では、過疎化・高齢化により、食料品店が閉店するなどして日常の買い物が困難になる「買い物弱者」が問題となっています。その対策として、食料品や日用品を積んだ移動販売車が各地を巡回するサービスが行われています。したがって、この記述は正しいです。
④【正】
「老年人口に占める食料品へのアクセスが困難な人口の割合」の地図を見ると、三大都市圏である神奈川県などでも割合が高い(上位)地域が見られます。これは、1970年代前後の高度成長期に、駅から離れた丘陵地などが大規模なニュータウンとして開発され、そこに住んでいた住民が一斉に高齢化し、坂道が多いなどの理由で移動が困難になっていることが一因として考えられます。したがって、この記述は正しいです。
問5:正解①
<問題要旨>
日本、エチオピア、中国、フランスの4か国について、従属人口指数の推移と将来予測を示したグラフ(①~④)から、日本に該当するものを選ぶ問題です。各国の人口構成の歴史的変化(戦後のベビーブーム、急激な高齢化、人口爆発など)を理解しているかが鍵となります。
<選択肢>
①【正】
これが日本です。日本は、1950年代から1970年頃にかけて、出生率の低下により年少人口が減少し、従属人口指数が低下しました(グラフの谷の部分)。この時期は生産年齢人口の割合が高く、「人口ボーナス期」と呼ばれました。しかしその後、世界で最も速いペースで少子高齢化が進行し、老年人口が急増したため、従属人口指数は急激に上昇に転じ、将来的に非常に高い値になることが予測されています。①のグラフはこの特徴的なV字(あるいはU字)型の推移と将来の急上昇を明確に示しています。
②【誤】
これはフランスです。フランスは他の先進国と比べて比較的出生率が高く、高齢化の進行も緩やかであるため、従属人口指数の変動は日本ほど急激ではありません。比較的安定して推移しています。
③【誤】
これは中国です。中国は1979年から始まった「一人っ子政策」により急激に出生率が低下し、それに伴い従属人口指数も急速に低下しました。しかし、近年はその政策の影響で急激な高齢化が進んでおり、今後は指数が上昇に転じると予測されています。日本の後を追うような形で指数が変化するのが特徴です。
④【誤】
これはエチオピアです。エチオピアは発展途上国であり、高い出生率が続いているため、年少人口の割合が非常に高いです。そのため、従属人口指数は一貫して高い水準で推移しており、近年緩やかな低下傾向にあります。これは「多産多死」から「多産少死」への人口転換の初期段階を示しています。
問6:正解①
<問題要旨>
イギリスにおける外国生まれの人口の上位5か国(1990年、2005年、2019年)の表を見て、空欄マ~ムに当てはまる国(アイルランド、インド、ポーランド)を正しく組み合わせる問題です。イギリスとこれらの国々との歴史的・地理的な関係や、近年の国際的な人の移動の動向に関する知識が必要です。
<選択肢>
①【正】
・マ(アイルランド):アイルランドはイギリスの隣国であり、歴史的に非常に深いつながりがあります。長年にわたり、アイルランドからイギリスへの労働移住が続いてきました。そのため、1990年時点では1位を占めています。しかし、近年はアイルランド経済の発展などにより、その地位は相対的に低下しています。表では、マが1990年に1位で、その後順位を下げていることから、マがアイルランドと判断できます。
・ミ(インド):インドはかつてイギリスの植民地であり、イギリス連邦の一員です。そのため、独立後もインドからイギリスへの移住者は多く、常に上位に位置しています。表では、ミが3つの年代すべてで1位または2位を占めていることから、ミがインドと判断できます。
・ム(ポーランド):ポーランドは2004年にEUに加盟しました。EU域内では労働者の移動が自由であるため、加盟後に多くのポーランド人が高賃金を求めてイギリスへ移住しました。そのため、2005年には4位に急浮上し、2019年には2位にまで上昇しています。この急増パターンから、ムがポーランドと判断できます。
したがって、マがアイルランド、ミがインド、ムがポーランドの組み合わせが正しいです。
②~⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
インドと中国周辺の4つの地域(A~D)について、土地利用(耕地、草地・裸地、森林)の面積割合を示した表(①~④)から、地域Cに該当するものを選ぶ問題です。地図から各地域の地形や気候を読み取り、それに対応する土地利用を推測する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
これはA(華北平原)です。広大な平野が広がり、古くから農業が盛んなため、耕地の割合が96%と極めて高くなっています。
②【誤】
これはD(デカン高原)です。綿花などの畑作が盛んな地域であり、耕地の割合が高くなっています。
③【正】
これがC(四川盆地)です。盆地の周りを高い山脈に囲まれており、温暖湿潤な気候を生かして古くから農業が発達しています。盆地の底は耕地として利用されていますが、周辺の山地は森林に覆われています。表③は、耕地が約16%である一方、森林が72%と非常に高い割合を占めており、四川盆地の土地利用の特徴と一致します。
④【誤】
これはB(チベット高原)です。標高が非常に高く、寒冷で乾燥した気候のため、農業には適さず、森林もほとんど見られません。土地の大部分は草原や岩石・氷雪に覆われた裸地です。したがって、草地・裸地の割合が88%と突出して高い④がBに該当します。
問2:正解③
<問題要旨>
インドと中国の行政区を、米と小麦の作付割合によってa~dの4グループに分けた地図(図2)と、そのグループ分けの基準を示した三角グラフ(図3)があります。地図とグラフを対応させ、a~cとア~ウの正しい組み合わせを選ぶ問題です。両国の農業地帯の特色、特に「南米北麦」といった基本的な知識が鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【正】
・地域の農業特色の確認:
・中国:「秦嶺・淮河線」を境に、南部では温暖湿潤な気候を活かした米作(稲作)が中心(南米)、北部では冷涼・乾燥した気候に適した小麦作が中心(北麦)となります。
・インド:北西部のパンジャブ地方やガンジス川中・上流域では小麦作が、北東部のガンジス川下流域や沿岸部では米作が盛んです。
・地図とグラフの対応:
・a(地図):中国の東北地方や華北地方に分布しています。ここは中国の小麦地帯です。したがって、aは「小麦の割合が高く、米の割合が低い」グループです。三角グラフでは、横軸(小麦)の値が大きく、縦軸(米)の値が小さい領域である「ウ」がこれに該当します。
・b(地図):中国の長江流域から南部、インドの沿岸部やガンジス川下流域に分布しています。これらは両国の米作地帯です。したがって、bは「米の割合が高く、小麦の割合が低い」グループです。三角グラフでは、縦軸(米)の値が大きく、横軸(小麦)の値が小さい領域である「ア」がこれに該当します。
・c(地図):インドのデカン高原中央部やガンジス川中流域に分布しています。これらの地域は、米と小麦が混在して作付けされている地域です。したがって、cは「米と小麦の両方の割合が比較的高い」グループです。三角グラフでは、米と小麦の割合がともに20%以上である「イ」がこれに該当します。
・結論:aがウ、bがア、cがイの組み合わせが正しいです。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問3:正解③
<問題要旨>
インドと中国の行政区ごとの「1人当たり総生産」と「出生率」の関係を示した2001年と2018年の散布図を見て、それに関する文章中の下線部①~④から適当でないものを選ぶ問題です。経済発展と人口動態の関係(人口転換)や、両国の国内における経済格差についての理解が問われます。
<選択肢>
①【正】
2つのグラフを見ると、両国・両年代に共通して、横軸の「1人当たり総生産」が高い(右にある)地域ほど、縦軸の「出生率」が低い(下にある)という負の相関関係が見られます。これは、経済的に豊かになるにつれて、教育水準の向上や価値観の変化などから出生率が低下するという一般的な傾向を示しており、記述は正しいです。
②【正】
2001年のグラフでは、中国(黒丸)の1人当たり総生産は、ほとんどが5千ドル未満の範囲に集中しています。しかし2018年には、低い地域から20千ドルを超える高い地域まで、横方向に大きくばらついています。インド(白四角)も経済成長していますが、中国ほど地域差の拡大は大きくありません。したがって、「インドよりも中国の方が大きくなった」という記述は正しいです。
③【誤】
インドでも家族計画は推進されていますが、その浸透度は地域や社会階層によって差が大きく、特に農村部では高い出生率が維持されている地域も少なくありません。出生率の低下は主に都市部で進んでおり、「農村部を中心に出生率が大きく低下した」という記述は現状と異なり、適当ではありません。
④【正】
中国では、1980年代から沿岸部に経済特区が設置され、外国資本が集中しました。これにより沿岸部は急速な経済発展を遂げましたが、内陸部との発展のペースには大きな差が生まれ、深刻な国内経済格差が生じています。したがって、この記述は正しいです。
問4:正解②
<問題要旨>
インドと中国の産業別GDP割合の推移(2000年と2017年)を示したグラフです。国(J, K)と産業(サ, シ)を正しく組み合わせる問題です。両国の経済発展のパターンの違い、特に中国の「世界の工場」としての成長と、インドのITサービス業の発展を理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【正】
・国(J vs K):中国(J)は改革開放政策以降、外国企業を積極的に誘致し、工業製品の輸出を柱に「世界の工場」として急速な経済成長を遂げました。そのため、第二次産業(鉱・工業、建設業)の割合が非常に高いのが特徴です。一方、インド(K)は、近年IT関連などのサービス業(第三次産業)が著しく成長しています。グラフを見ると、Jは鉱・工業の割合がKよりも高く、2000年から2017年にかけても高い水準を維持しています。KはJに比べてサービス業や農林水産業の割合が高いです。したがって、Jが中国、Kがインドと判断できます。
・産業(サ vs シ):農林水産業(第一次産業)は、経済が発展するにつれてGDPに占める割合が低下していくのが一般的です。グラフを見ると、J・Kともにシの割合が2000年から2017年にかけて低下しています。これが農林水産業です。残ったサが運輸・通信業となります。インド(K)では、近年IT産業の発展が著しく、運輸・通信業を含むサービス業の成長が経済を牽引しています。
・結論:インドはK、運輸・通信業はサとなります。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
問5:正解④
<問題要旨>
インド、中国、オーストラリアの3か国間における、「輸出額」と「移民の送出数」の1995年から2019年にかけての変化を示した図です。国(タ, チ)と指標(P, Q)を正しく組み合わせる問題です。近年のアジア太平洋地域における経済関係と人的交流の拡大についての知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【正】
・国(タ vs チ):中国は「世界の工場」として急速に経済成長し、世界最大の輸出国となりました。オーストラリアにとって、中国は現在最大の貿易相手国です。インドも経済成長していますが、貿易規模ではまだ中国に及びません。図を見ると、1995年から2019年にかけて、タとオーストラリア間の矢印は細いままですが、チとオーストラリア、そしてチとタの間の矢印は劇的に太くなっています。この爆発的な増加は中国の経済成長を反映していると考えられます。したがって、チが中国、タがインドと判断できます。
・指標(P vs Q):
・P:1995年時点では3国間の関係は比較的細いですが、2019年にはチ(中国)を中心として全ての矢印が非常に太くなっています。これは、中国の経済成長に伴う貿易額の急増を示していると考えられます。
・Q:1995年時点では矢印が非常に細いですが、2019年には、タ(インド)とチ(中国)からオーストラリアへの矢印が特に太くなっています。オーストラリアは移民を積極的に受け入れている国であり、近年は特にアジアからの移民が増加しています。インドと中国は、オーストラリアへの主要な移民送出国です。
・結論:Pが輸出額、Qが移民の送出数と判断するのが妥当です。したがって、中国はチ、輸出額はPの組み合わせが正しいです。
問6:正解①
<問題要旨>
インドと中国周辺のPM2.5濃度分布図(S, T)が1月と7月のいずれかを示しているかを判断し(マ)、国境を越える環境問題の例(ミ)を正しく選ぶ問題です。モンスーンの影響や、冬季の暖房利用といった、大気汚染の季節的な要因を理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
・時期(マ):中国北部やインド北部では、冬(1月)に石炭などを使った暖房が多用されるため、PM2.5などの大気汚染物質の排出量が大幅に増加します。また、冬はシベリア高気圧の影響で大気が安定し、汚染物質が拡散しにくく滞留しやすいため、高濃度になりがちです。図Sは、中国北部やインドのガンジス川流域で特に濃度が非常に高くなっており、これは冬(1月)の特徴と一致します。一方、夏(7月)はモンスーンの影響で降雨が多く、大気中の汚染物質が洗い流されるため、濃度は比較的低くなります(図T)。したがって、Sは1月を示します。
・環境問題の例(ミ):PM2.5が風に乗って発生源から遠く離れた国へ運ばれ、影響を及ぼすように、原因となる物質が国境を越えて移動し、広範囲に影響を与える環境問題としては、他に「酸性雨」や「海洋ごみの漂着」などがあります。土地の塩性化は、不適切な灌漑などが原因で特定の地域で発生する問題であり、汚染物質が国境を越えて拡大していくタイプの問題ではありません。したがって、ミは海洋ごみの漂着が当てはまります。
②【誤】
ミの選択が誤っています。土地の塩性化は国境を越えて拡大する汚染問題の例として不適切です。
③【誤】
マの時期の判断が誤っています。Sは冬(1月)です。
④【誤】
マの時期の判断と、ミの選択が両方とも誤っています。
第5問
問1:正解⑤
<問題要旨>
利根川に関する文章の空欄(ア、イ)を補充する問題です。空欄アは利根川の現在の流域に含まれる地点を、空欄イは特定の区間の標高差を計算で求める必要があります。地図の読解力と基本的な計算力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
地点Aは利根川の流域に含まれないため、誤りです。
②【誤】
地点Aは利根川の流域に含まれないため、誤りです。また、標高差の計算も異なります。
③【誤】
地点Aは利根川の流域に含まれないため、誤りです。
④【誤】
地点Aは利根川の流域に含まれないため、誤りです。また、標高差の計算も異なります。
⑤【正】
空欄ア(流域の特定):図1の地図を見ると、利根川の本流(太い実線)とその支流(細い実線)が描かれています。
地点Aは、利根川とは別の水系である荒川の流域に位置しています。
地点Bは渡良瀬川、地点Cは鬼怒川の流域にあり、これらはどちらも利根川の主要な支流です。
したがって、現在の利根川の流域に含まれているのは**「BとC」**です。
空欄イ(標高差の計算):問題文に、取手から佐原までの河川の勾配が「1万分の1程度」であると書かれています。これは、水平距離が10,000m進むごとに、標高が1m低くなることを意味します。
次に、地図の縮尺を使って取手から佐原までの川に沿った距離を求めます。地図上のスケール(20km)を参考にすると、この区間の距離は**約40km(40,000m)**と読み取れます。
標高差は「距離 × 勾配」で計算できます。
40,000m × (1 / 10,000) = 4m
したがって、取手と佐原の標高差は**約「4m」**となります。
以上のことから、アに「BとC」、イに「4m」が入る⑤の組み合わせが正しいです。
⑥【誤】
標高差の計算が誤っています。
問2:正解②
<問題要旨>
利根川下流域の地形図(図2)と、4つの範囲(E~H)の土地利用割合を示したグラフ(①~④)を対応させ、範囲Fに該当するグラフを選ぶ問題です。地形図から土地の起伏(台地か低地か)を読み取り、それに応じた土地利用を推測する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
これはGです。利根川沿いの平坦な低地であり、大部分が水田として利用されていると考えられます。グラフ①は「田」の割合が80%以上と突出しており、Gに対応します。
②【正】
これがFです。Fは利根川の北側に位置する常総台地の一部です。比較的平坦な台地上では、畑作や果樹園、そして宅地開発が進んでいることが多いです。また、鉄道が通り市役所もあることから、市街地(建物用地)も広がっています。グラフ②は、「畑・果樹園など」と「建物用地」の割合が比較的高く、「田」の割合が低いことから、台地上の市街地とその周辺であるFの土地利用と一致します。
③【誤】
これはEです。Fと同様に台地上ですが、Fよりも市街地化が進んでいない地域と考えられます。グラフ③は建物用地の割合が②よりも低く、Eに対応すると考えられます。
④【誤】
これはHです。下総台地の一部で、起伏のある地形が見られます。このような台地では畑作や、谷津田と呼ばれる谷の部分での稲作、そして森林が混在します。グラフ④は「畑・果樹園など」「森林」「田」がバランスよく分布しており、Hに対応すると考えられます。
問3:正解⑤
<問題要旨>
1931年と2019年の佐原周辺の地形図と、利根川の渡船・橋の分布図を見て、会話文の空欄J(古くからの中心市街地)とK(1981年の橋の分布)に当てはまるものの正しい組み合わせを選ぶ問題です。新旧地形図の比較読解と、交通手段の変遷を読み解く力が必要です。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【正】
・空欄J:古くからの中心市街地を特定します。1931年の地形図を見ると、bの範囲は既に建物が密集し、市街地として形成されています。一方、aの範囲は佐原駅周辺ですが、bに比べると建物の密度は低いです。佐原は江戸時代に利根川水運の中継地として、小野川沿い(bの周辺)が商業の中心地として栄えました。したがって、より古くから発達していたのはbです。
・空欄K:1932年と1981年の渡船と橋の分布を考えます。
・サ:非常に多くの地点に印があり、川を渡る手段が多数必要だったことを示しています。これは橋が少なかった時代の「1932年の渡船」と考えられます。
・ス:印の数がサよりも少なく、川幅が狭い場所などに限定されています。これが「1932年の橋」でしょう。
・シ:印の数はスより多いですが、サよりはるかに少ないです。自動車交通の増加に対応して、1932年以降に主要な地点に橋が架けられた結果と考えられます。また、橋ができたことで渡船はほとんど廃止されたはずです。したがって、これが「1981年の橋」の分布図です。
・結論:Jにはb、Kにはシが当てはまります。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問4:正解③
<問題要旨>
佐原周辺の水害の歴史と対策に関する資料を読み、会話文の空欄P(水門が設置された地点)とQ(現代の洪水対策)に当てはまるものの正しい組み合わせを選ぶ問題です。地図から河川の流れる方向を読み取り、治水の基本的な考え方を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【正】
・空欄P:資料1には、八筋川や十六島で水害が発生したとあります。学芸員は「利根川の支流への逆流などにより、水害が発生」し、それを防ぐために水門が設置されたと説明しています。地図を見ると、利根川本流から八筋川が分流しています。利根川本流の水位が上昇した際に、水が八筋川へ逆流するのを防ぐためには、八筋川が利根川から分かれる地点に水門を設置する必要があります。地点チは、まさにその利根川と八筋川の分岐点に位置しています。したがって、水門が設置されたのはチです。
・空欄Q:大きな河川の下流域における洪水対策について述べています。
・f「決壊を防ぐため、堤防を補強する」:これは洪水対策の基本であり、下流域で堤防の決壊による浸水被害を防ぐために行われる重要な取り組みです。
・g「土砂の流出や流木を防ぐため、ダムを建設する」:ダムは主に河川の中・上流域に建設され、洪水調節や土砂の流出抑制の機能がありますが、下流域で一般的に行われる取り組みとしてはfの方がより直接的で適切です。
・結論:Pにはチ、Qにはfが当てはまります。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
問5:正解②
<問題要旨>
ウナギの供給量に関する資料と、河川環境に関する写真を見て、空欄に当てはまる記号や写真を正しく組み合わせる問題です。統計資料の読解と、生態系に配慮した河川改修(多自然川づくり)に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【正】
・供給量の推移(マ vs ミ):資料2の表を見ると、日本のウナギ供給量は1970年代以降、国内漁獲量が激減する一方で、合計量は増加・高止まりしています。これは、天然ウナギの不足を補うために、養殖や輸入が拡大したことを意味します。特に2000年には合計が約16万トンとピークに達しており、これは国外からの大量輸入によるものと考えられます。したがって、変動が大きく、時に非常に大きな値を示すミが「国外からの輸入量」です。一方、マは1985年にピークを迎え、その後は減少傾向にあり、これは「国内の養殖生産量」の推移と考えるのが妥当です。
・空欄X:資料2の文章では、近年の取り組みとして「ニホンウナギや川魚などの水産資源の回復に寄与することが期待されて」いるものがXであると述べられています。
・写真s:コンクリートや石材で固められた護岸です。これは治水を目的としていますが、生物の生息環境としては好ましくありません。
・写真t:川を横断する堰(せき)のそばに、魚が遡上できるように作られた別の水路(魚道)が写っています。堰は魚の移動を妨げますが、魚道を設置することで、ウナギなどが川を上り下りできるようになり、水産資源の回復につながります。
・結論:したがって、Xにはtの写真が当てはまります。国内の養殖生産量はマ、Xはtなので、この組み合わせは②です。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
問6:正解③
<問題要旨>
地域調査における新たな探究課題と、その調査方法の組み合わせの中から、適当でないものを選ぶ問題です。地理的な問いに対して、どのような調査手法が有効かを判断する力が求められます。
<選択肢>
①【適当】
「農地の分布の変化」という課題に対して、「撮影年代の異なる空中写真を入手し、年代別の土地利用図を作成する」ことは、過去と現在の土地利用を視覚的に比較できる非常に有効な方法です。
②【適当】
「橋の開通による住民の生活行動の変化」という課題に対して、「聞き取り調査により、周辺住民に生活行動の変化を尋ねる」ことは、統計データには表れない質的な変化(買い物先、通勤・通学路の変化など)を知るための非常に重要な方法です。
③【不適当】
「防災施設の整備により、住民の防災意識はどのように変化したか?」という課題は、住民の「意識」という内面的な変化を問うています。これに対して、「GISを用いて、防災施設から一定距離内に住む人口の変化を調べる」という方法は、人口という量的なデータを分析するものであり、「防災意識」そのものを直接調べることはできません。防災意識を調べるには、アンケート調査や聞き取り調査といった手法が適切です。したがって、この調査方法は課題に対して適当ではありません。
④【適当】
「環境の変化により、利根川流域の漁獲量はどのように変化したか?」という課題に対して、「図書館やインターネットで資料を入手し、漁獲量の推移を調べる」ことは、漁業協同組合の統計資料や自治体の報告書などを探し、客観的なデータに基づいて変化を把握するための基本的な調査方法です。