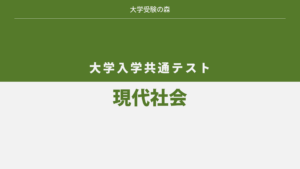解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
サービス貿易の4つの形態(越境取引、国外消費、商業拠点設置、人の移動)の定義を理解し、具体的な行動がどの形態に分類されるかを判断する問題です。これらはGATS(サービスの貿易に関する一般協定)で定められています。
<選択肢>
①【誤】
アがⅠ、イがⅡ、ウがⅢの組み合わせは誤りです。
②【誤】
アがⅠ、イがⅢ、ウがⅣの組み合わせは誤りです。
③【正】
ア:研修先の町の現地旅行会社が主催する観光バスツアーに参加した 。
これは、マツキさん(消費者)が海外(研修先)に移動し、現地でサービスを受けているため、サービス提供者(現地旅行会社)が自国にとどまり、他国から来た消費者にサービスを提供する「Ⅱ 国外消費」に該当します 。
イ:日本の運輸会社の現地支店を利用して日本の自宅に送った 。
これは、日本の企業が海外に支店という商業拠点を設置し、その拠点を通じてサービスを提供しているため、「Ⅲ 商業拠点設置」に該当します 。
ウ:日本から研修先の町を訪れて開催した単独コンサートを聴きに行った 。
これは、サービス提供者である日本人ピアノ奏者が海外に移動し、サービスを提供しているため、「Ⅳ 人の移動」に該当します 。
したがって、ア-Ⅱ、イ-Ⅲ、ウ-Ⅳの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
④【誤】
アがⅡ、イがⅣ、ウがⅠの組み合わせは誤りです。
⑤【誤】
アがⅢ、イがⅡ、ウがⅣの組み合わせは誤りです。
⑥【誤】
アがⅢ、イがⅣ、ウがⅡの組み合わせは誤りです。
⑦【誤】
アがⅣ、イがⅠ、ウがⅡの組み合わせは誤りです。
⑧【誤】
アがⅣ、イがⅠ、ウがⅢの組み合わせは誤りです。
問2:正解④
<問題要旨>
外国為替市場の仕組みに関する基本的な知識を問う問題です。円高・円安、為替レート決定制度、為替介入、外国為替の定義について、正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
1ドル=120円が1ドル=130円になることは、同じ1ドルを得るためにより多くの円が必要になることを意味するため、「円安・ドル高」です 。円高・ドル安はその逆の状態です。
②【誤】
外国為替市場における需要と供給によって為替レートが決まる制度は「変動為替相場制」です 。金・ドル本位制(ブレトン・ウッズ体制)は、ドルと金の兌換を保証し、各国通貨とドルの交換比率を固定する「固定為替相場制」の一種です。
③【誤】
急激な円高に対応するためには、円の価値を下げる(円安に誘導する)必要があります。そのためには、市場で円を売ってドルを買う「円売り・ドル買い介入」を行います 。記述は「ドル売り・円買い介入」となっており、これは円安に対応するための介入です。
④【正】
外国為替は、国際間の貸借関係を、現金を直接輸送することなく、金融機関などを介して為替手形などの信用手段によって決済する方法です 。貿易や資本取引などで生じる国際間の支払いに利用されます。記述は外国為替の定義として正しく、この選択肢が正解です。
問3:正解①
<問題要旨>
欧州連合(EU)を中心とした地域経済統合の歴史や仕組みに関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
1992年に調印され、1993年に発効したマーストリヒト条約(欧州連合条約)によって、それまでの欧州共同体(EC)から、経済統合に加えて共通の外交・安全保障政策や司法・内務協力などを含む、より幅広い協力を行う欧州連合(EU)へと発展しました 。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
②【誤】
ギリシャの財政危機は、ユーロという共通通貨の信認を揺るがし、ユーロの価値が下落する「ユーロ安」の要因となりました 。記述は「ユーロ高」となっており、誤りです。
③【誤】
EUでは、金融政策は欧州中央銀行(ECB)によって統一的に実施されていますが、財政政策は各加盟国が主権事項として個別に運営しており、統一されていません 。これがギリシャ財政危機のような問題の一因ともなりました。
④【誤】
第二次世界大戦後の欧州統合の起点は、1952年に発足した欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)です 。欧州経済共同体(EEC)と欧州原子力共同体(EURATOM)は1958年に発足し、これら3つが統合されて1967年に欧州共同体(EC)が成立しました。
問4:正解④
<問題要旨>
国際社会の仕組みに関する問題です。国家の領域、国連の主要機関、国際経済機関、人間の安全保障といったテーマについて、基本的な知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
国家の領域を構成するのは、領土、領海(沿岸から12カイリ)、領空(領土・領海の上空)です 。排他的経済水域(EEZ、沿岸から200カイリ)は、沿岸国が水産資源や鉱産資源に対する主権的権利を持つ水域であり、国家の領域には含まれません。
②【誤】
国際連合の六つの主要機関は、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所、事務局です 。人権理事会は経済社会理事会の下部組織でしたが、2006年に総会の下部組織に格上げされた重要な機関ですが、設立当初からの「主要機関」ではありません。
③【誤】
「関税と貿易に関する一般協定(GATT)」を発展的に解消し、自由貿易を促進する国際機関として1995年に誕生したのは、世界貿易機関(WTO)です 。国際復興開発銀行(IBRD)は世界銀行グループの中核機関であり、第二次大戦後の復興や開発途上国の開発支援を目的として設立されました。
④【正】
国連開発計画(UNDP)は、1994年の『人間開発報告書』において「人間の安全保障」という概念を提唱しました 。これは、国家の安全保障だけでなく、紛争、貧困、人権侵害といった様々な脅威から一人ひとりの人間を守るべきだという考え方です。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
問5:正解④
<問題要旨>
自由貿易協定(FTA)がもたらす貿易転換効果による利益と損失について、具体的な数値例を用いて計算し、理解度を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア、イ、ウの数値の組み合わせが誤りです。
②【誤】
ア、イ、ウの数値の組み合わせが誤りです。
③【誤】
ア、イ、ウの数値の組み合わせが誤りです。
④【正】
ア:A国がB国、C国とFTAを結んでいない場合、両国からの輸入品には40%の関税がかかります 。このとき、A国での販売価格はB国製が700円、C国製が840円となるため 、より安いB国から輸入します。関税がゼロの場合のB国製品の価格は500円なので、関税収入は700円 – 500円 = 200円となります。よってアは200です。
イ:A国とC国がFTAを結ぶと、C国からの輸入品に関税がかからなくなり、販売価格は600円になります 。これは、FTA締結前に輸入していたB国製品の価格700円よりも安いため、A国は輸入先をC国に切り替えます 。これにより、A国での製品Xの販売価格は700円から600円に下がるため、100円分下がることになります 。よってイは100です。
ウ:FTA締結によって、A国政府はそれまで得ていた1単位あたり200円(ア)の関税収入を失います 。一方で、消費者は価格が100円(イ)下がった分の恩恵を受けます 。この差額、200円 – 100円 = 100円が、A国全体の損失額となります 。よってウは100です。
ア=200、イ=100、ウ=100の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
⑤【誤】
ア、イ、ウの数値の組み合わせが誤りです。
⑥【誤】
ア、イ、ウの数値の組み合わせが誤りです。
問6:正解⑦
<問題要旨>
宗教上のヴェール着用禁止に関する三つの異なる立場(A, B, C)と、それぞれの立場を要約した記述(ア〜エ)を正しく結びつける問題です。文章の読解力と思想的な立場の理解が問われます。
<選択肢>
①【誤】
A, B, Cとア, イ, ウの組み合わせが誤りです。
②【誤】
A, B, Cとア, ウ, エの組み合わせが誤りです。
③【誤】
A, B, Cとイ, ア, エの組み合わせが誤りです。
④【誤】
A, B, Cとイ, ウ, アの組み合わせが誤りです。
⑤【誤】
A, B, Cとウ, イ, アの組み合わせが誤りです。
⑥【誤】
A, B, Cとウ, イ, エの組み合わせが誤りです。
⑦【正】
Aは、治安維持(公の秩序・安全の保護)のために個人の識別が必要な場合があるとしつつも、それをもってヴェールの着用を「包括的に(一律に)禁止する」ことの論証が必要だと述べています 。これは、エの「治安への脅威に対処しなければならないとしても、顔を隠すヴェールの公共の場での着用を一律に禁止することは、当然に正当化されるわけではない」という考え方と合致します 。
Bは、顔を隠すことが社会での相互活動(コミュニケーション)の障壁となり、「共生しやすい社会で生活するという他者の権利を侵害する」という意見に理解を示しています 。これは、アの「顔を隠すヴェールの公共の場での着用は、社会で共同生活を送る上でのコミュニケーションの妨げとなり、他人の権利と抵触する可能性がある」という考え方と合致します 。
Cは、ヴェール着用禁止が女性の権利保護の観点から主張されることに触れつつも、ヴェール着用は必ずしも従属の象徴ではなく、着用する女性自身の意見を聞くべきだと述べています 。これは、ウの「ヴェールの着用は、女性の自主選択に基づく場合があり、両性の平等に反するとして一概に断定はできない」という考え方と合致します 。
したがって、A-エ、B-ア、C-ウの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
⑧【誤】
A, B, Cとエ, ウ, イの組み合わせが誤りです。
問7:正解⑥
<問題要旨>
先進国と開発途上国間の医療格差、特に医薬品の特許をめぐる問題について、二つの異なる立場(マツキさん、スミスさん)の意見に合致する政策(X〜Z)を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【誤】
アとイに入る政策の組み合わせが誤りです。
②【誤】
アとイに入る政策の組み合わせが誤りです。
③【誤】
アとイに入る政策の組み合わせが誤りです。
④【誤】
アとイに入る政策の組み合わせが誤りです。
⑤【誤】
アとイに入る政策の組み合わせが誤りです。
⑥【正】
マツキさんは、開発途上国の人々が治療薬を使えることを最優先し、「特許権者の利益を害することにはなるが」と前置きした上で、高価な治療薬を自国で製造できない問題を解決する政策を主張しています 。これは、Zの「緊急時には、一時的に特許権の保護の対象外とする」という、特許の効力を強制的に停止させる政策(強制実施権の発動など)と合致します 。
スミスさんは、「特許権者の利益を害することなく」開発途上国を支援する政策を主張しています 。これは、Yの「国際機関が、先進国などから拠出された資金を用いて治療薬を購入し、開発途上国に供給する」という、市場メカニズムと特許権を尊重しつつ、資金援助によって問題を解決しようとする政策と合致します 。
したがって、ア-Z、イ-Yの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
青年期(思春期)の心理的・社会的な特徴に関する思想家の見解を問う問題です。各思想家が提唱した概念を正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
身体が性的に成熟し大人になっていくことは「第二次性徴」と呼ばれます 。第一次性徴は、生まれたときの男女の性器の違いを指します。
②【誤】
エリクソンが、青年が多様な自己を統合できず混乱した状態を指す言葉として用いたのは「アイデンティティ拡散(同一性拡散)」です 。モラトリアムは、社会的な責任や義務を猶予され、自己を探求する期間を指します。
③【誤】
青年が親や社会的権威に反抗することは「第二反抗期」と呼ばれます 。第一反抗期は、幼児期(2〜3歳頃)に見られる自我の芽生えに伴う反抗です。
④【正】
ドイツの心理学者レヴィンは、青年期を、子どもと大人のどちらの集団にも完全には所属できず、両者の境界にいる不安定な存在として「境界人(マージナル・マン)」と呼びました 。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
問2:正解④
<問題要旨>
統計資料(表)の読み取りと、会話文の空欄補充を組み合わせた問題です。資料を正しく解釈し、会話の流れに沿った適切な記述を選択する能力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
アとイの記述の組み合わせが誤りです。
②【誤】
アとイの記述の組み合わせが誤りです。
③【誤】
アとイの記述の組み合わせが誤りです。
④【正】
サトウさんは「日本の若者は『やさしさ』の回答割合が一番低いんだね」と発言していますが 、表を見ると、「やさしさ」の日本の値69.1%は、韓国79.5%、アメリカ93.0%、スウェーデン90.6%と比較して一番低いです 。これは「項目ごとに国際比較」した見方です。
一方、ヤマダさんは「日本の若者は『やさしさ』の回答割合が一番高いと思った」と発言しています 。日本の列を縦に見ると、「やさしさ」の69.1%は他の項目(明るさ52.7%、慎しみ深さ50.6%など)と比較して最も高い値です 。これは「国内の項目間で比較」した見方です。
したがって、アにはbの「私は項目ごとに国際比較したけど、ヤマダさんは国内の項目間で比較した」が入ります 。
次にイの記述を検証します。
c:「各国内の項目間で比較すると、日本以外の国では、『やさしさ』に次いで2番目に回答割合が高い項目が共通している」 。韓国では「まじめさ」(77.9%)、アメリカでは「正義感」(90.5%)、スウェーデンでは「正義感」(88.8%)が「やさしさ」に次ぐ高さであり、共通していません。よってcは誤りです。
d:「項目ごとに国際比較すると、日本は他の国よりもすべてにおいて回答割合が低い」 。表の各行(項目ごと)を見ると、日本の値は常に韓国、アメリカ、スウェーデンの値よりも低くなっています 。よってdは正しいです。
以上より、アにb、イにdが入る組み合わせであるこの選択肢が正解です。
問3:正解①
<問題要旨>
現代の企業活動や社会貢献活動に関連する用語の知識を問う問題です。社会的企業とCSR(企業の社会的責任)の定義を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
A:空き家問題の解決といった公共性の高い社会課題を、収益の得られる事業(ビジネス)の手法を用いて解決しようとする組織は「社会的企業(ソーシャル・エンタープライズ)」と呼ばれます 。
B:企業が法令遵守だけでなく、環境保全や地域貢献など、株主以外の様々なステークホルダー(利害関係者)の利益に配慮して貢献する活動は、「企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)」の一環として行われます 。
したがって、A-社会的企業、B-企業の社会的責任の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
②【誤】
Bの内部統制(コーポレート・ガバナンス)は、企業の不正を防ぎ、健全な経営を行うための社内管理体制のことであり、環境保全活動のような社会貢献活動を直接指すものではありません。
③【誤】
Aは、社会課題解決を主目的としているため、利益追求を第一とする「営利企業」とは区別されます。
④【誤】
Aが「営利企業」ではなく、Bが「内部統制」ではないため、この組み合わせは誤りです。
問4:正解⑤
<問題要旨>
日本の戦後経済史と有効求人倍率の推移を示したグラフを関連付ける問題です。各年代の経済状況(高度経済成長、石油危機、バブル経済、構造改革など)を理解し、それが雇用状況にどのように反映されたかを読み解く力が必要です。
<選択肢>
①【誤】
各時期と経済状況の説明の組み合わせが誤りです。
②【誤】
各時期と経済状況の説明の組み合わせが誤りです。
③【誤】
各時期と経済状況の説明の組み合わせが誤りです。
④【誤】
各時期と経済状況の説明の組み合わせが誤りです。
⑤【正】
ア:1965年~1970年代初頭は、いざなぎ景気などを含む高度経済成長期です 。企業の積極的な投資や旺盛な消費により人手不足となり、有効求人倍率が高い水準で推移しました。これはCの説明と合致します 。
イ:1973年~1975年頃、有効求人倍率は急激に悪化しています 。これは、1973年の第一次石油危機(オイルショック)により、原油価格が高騰し、狂乱物価と呼ばれる激しいインフレーションと深刻な不況が同時に発生(スタグフレーション)し、戦後初のマイナス成長を記録した時期です。これはAの説明と合致します 。
ウ:1970年代後半~1980年代前半は、石油危機を乗り越える過程で、省エネルギー化が進み、鉄鋼などの重厚長大産業から、ICやVTRなどの軽薄短小産業へと産業構造が転換した時期です 。有効求人倍率は低い水準で安定しています。これはDの説明と合致します 。
エ:2000年代前半から半ばにかけて、有効求人倍率は回復傾向にあります 。この時期は、小泉純一郎内閣による「聖域なき構造改革」が進められ、規制緩和や金融再生などを通じて景気が回復した時期です。これはBの説明と合致します 。
したがって、ア-C、イ-A、ウ-D、エ-Bの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
⑥【誤】
各時期と経済状況の説明の組み合わせが誤りです。
⑦【誤】
各時期と経済状況の説明の組み合わせが誤りです。
⑧【誤】
各時期と経済状況の説明の組み合わせが誤りです。
問5:正解②
<問題要旨>
社会参加や人間のあり方に関する西洋思想家の見解を問う問題です。各思想家の中心的な主張を正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
「人間は自由の刑に処せられている」と述べ、自由であることの責任と不安(アンガージュマン)を説いたのは、実存主義者のサルトルです 。ハイデッガーは『存在と時間』で知られる思想家です。
②【正】
ハンナ・アーレントは、著書『人間の条件』などで、古代ギリシャのポリスにおける市民の公的領域での活動(言論や討論)を理想とし、他者と関わる「活動」の重要性を論じ、公共性の意義を強調しました 。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
③【誤】
「死を待つ人の家」を運営し、貧しい人々への奉仕に生涯を捧げたのはマザー・テレサです 。シュヴァイツァーは「生命への畏敬」を説き、アフリカで医療活動に従事したことで知られています。
④【誤】
自由がもたらす孤独に耐えきれず、ナチズムのような権威主義に人々が服従していくメカニズムを分析し、それを『自由からの逃走』という著書で表現したのは、フロムです 。レヴィナスは「他者の顔」をめぐる倫理学で知られる思想家です。
問6:正解①
<問題要旨>
日本の財政や予算に関する基本的な仕組みについての知識を問う問題です。フィスカル・ポリシー、予算の種類、地方財政、三位一体の改革といったキーワードの正確な理解が必要です。
<選択肢>
①【正】
フィスカル・ポリシー(財政政策)とは、政府が公共事業などの政府支出を増減させたり、増税や減税を行ったりすることを通じて、経済全体の総需要をコントロールし、景気の安定化を図る政策のことです 。記述は正しく、この選択肢が正解です。
②【誤】
国が行う特定の事業(国有林野事業、特定の空港整備など)の収支を計上する予算は「特別会計」です 。財政投融資は、財投債の発行によって得た資金を元に、政策金融機関などを通じて民間の事業に投融資を行う仕組みです。
③【誤】
地方公共団体の財源は、自ら確保できる自主財源と、国から交付される依存財源に分かれます。地方税は自主財源ですが、地方交付税は国から交付されるものであり、依存財源に含まれます 。
④【誤】
小泉内閣で進められた「三位一体の改革」は、地方分権を推進するため、「国庫支出金(補助金)の削減」、「地方への税源移譲」、「地方交付税の見直し」を一体で行ったものです 。したがって、補助金は増額ではなく削減が図られました。
問7:正解⑤
<問題要旨>
心理学者マズローが提唱した「欲求階層説(自己実現理論)」について、具体的な欲求の内容が五段階のどの階層に当たるかを正しく判断する問題です。
<選択肢>
①~④【誤】
A, B, Cと欲求の階層の組み合わせが誤りです。
⑤【正】
マズローの欲求階層説は、低次から①生理的欲求、②安全の欲求、③社会的欲求(所属と愛の欲求)、④承認の欲求、⑤自己実現の欲求、の5段階で構成されます。
A:「人々との愛情に満ちた関係」や「所属する集団や家族においても居場所を切望する」という記述は、集団への所属や愛情を求める「③社会的欲求」に該当します 。
B:「音楽家は音楽を」「自分がなりうるものにならなければならない」「自分自身の本性に忠実でなければならない」という記述は、自らの持つ能力や可能性を最大限に発揮したいという最も高次な「⑤自己実現の欲求」に該当します 。
C:「法律や秩序や社会的権威が脅かされる」時に緊急に必要となるという記述は、身体的・経済的な危険から逃れ、安定した状態を求める「②安全の欲求」に該当します 。
したがって、A-3番目、B-5番目、C-2番目の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
⑥~⑨【誤】
A, B, Cと欲求の階層の組み合わせが誤りです。
第3問
問1:正解⑧
<問題要旨>
名目GDPと実質GDPの違いを、具体的な仮想例に基づいて理解しているかを問う問題です。物価変動の影響を取り除いて生産量の変化を見るのが実質GDPであるという基本がポイントです。
<選択肢>
①~⑦【誤】
A, B, Cの語句の組み合わせが誤りです。
⑧【正】
A:実質GDPは、物価変動の影響を取り除いた、生産量の変化をみるための指標です 。仮想例では「生産物と生産量が同じ」とされているため 、実質GDPは変化しません。よってAは「ウ 同じ」です 。
B:名目GDPは、その時点の市場価格で計算されます 。仮想例では「スマートフォンだけ価格低下(同時に、付加価値も低下)」とあるため 、生産量が同じでも、価格が下がった分だけ名目GDPは減少します。よってBは「イ 減少」です 。
C:経済成長、つまり一国全体の生産量がどれだけ増減したかを判断するには、物価変動の影響を除いた「実質GDP」を用います 。よってCは「キ 実質」です 。
したがって、A-ウ、B-イ、C-キの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
問2:正解①
<問題要旨>
日本政府による企業や市場への介入・規制に関する制度や法律についての知識を問う問題です。独占禁止法、公共財、労働基準監督機関、食の安全に関する制度がテーマとなっています。
<選択肢>
①【正】
メーカーなどの企業が、自社製品の販売価格を小売店に守らせる「再販売価格維持行為」は、自由な価格競争を阻害するとして、原則として独占禁止法で禁止されています 。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
②【誤】
公共財(警察、国防など)は、対価を払わない人を排除できず(非排除性)、多くの人が同時に利用できる(非競合性)という性質を持つため、市場メカニズムに任せると誰も費用を負担しようとせず、供給されないか「過少供給」される傾向があります 。そのため政府が供給する必要があります。
③【誤】
企業が労働基準法などの労働法規を守っているかを監督・指導する機関は「労働基準監督署」です 。労働委員会は、労働組合と使用者との間の労働争議の調整や、不当労働行為の審査などを行う行政委員会です。
④【誤】
食の安全のために、生産から消費までの情報を追跡できる仕組みは「トレーサビリティ制度」です 。食糧管理制度は、米などの主要食糧の需給と価格の安定を図るための制度で、1995年に食糧法に変わりました。
問3:正解③
<問題要旨>
日本とアジア諸国の経済・政治関係に関する知識を問う問題です。中国の「一国二制度」、貿易の形態、ASEANの経済統合、AIIBについて問われています。
<選択肢>
①【誤】
中国が社会主義体制を維持しつつ、経済面で市場経済を導入する政策は「改革開放」政策です。「一国二制度」は、香港やマカオに対し、中国の主権下で社会主義制度を適用せず、高度な自治と資本主義制度を認める統治方式を指します 。
②【誤】
日本とアジア諸国が、互いに競争力のある工業製品(部品や完成品)を輸出しあう貿易は、同一産業内での貿易であるため「水平貿易」に分類されます 。垂直貿易は、先進国が工業製品を輸出し、開発途上国が原材料や食料品を輸出するといった、異なる産業間の貿易を指します。
③【正】
東南アジア諸国連合(ASEAN)は、域内の貿易を活性化させるため、1992年にASEAN自由貿易地域(AFTA)を創設することに合意し、段階的に関税の引き下げを進めてきました 。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
④【誤】
アジアインフラ投資銀行(AIIB)は、アジア地域のインフラ整備を支援する国際金融機関であり、その設立交渉を主導したのは中国です 。日本やアメリカは参加していません。
問4:正解①
<問題要旨>
「財」と「サービス」の違いについて、板書で示された定義(無形性、生産と消費の同時性、非貯蔵性)を理解し、具体的な事例の中から「サービス」の取引に該当するものをすべて選び出す問題です。
<選択肢>
①【正】
A:理髪店で髪を切ってもらう行為は、物質ではなく(無形性)、カットという行為とそれを受けるという消費が同時に行われ(同時性)、在庫として作り置きできません(非貯蔵性)。したがって、サービスの取引です 。
B:コンビニが従業員を雇用し、働いてもらうことは、労働力の提供というサービスの取引です 。労働も無形で、提供と消費が同時であり、作り置きはできません。
C:鉄道に乗って移動することも、移動という便益を提供するサービスの取引です 。これも無形で、乗車(生産)と移動(消費)が同時であり、在庫はありません。
したがって、A、B、Cのすべてがサービスの取引に該当するため、この選択肢が正解です。
②【誤】
Cもサービスの取引に該当するため、誤りです。
③【誤】
Bもサービスの取引に該当するため、誤りです。
④【誤】
Aもサービスの取引に該当するため、誤りです。
⑤【誤】
B、Cもサービスの取引に該当するため、誤りです。
⑥【誤】
A、Cもサービスの取引に該当するため、誤りです。
⑦【誤】
A、Bもサービスの取引に該当するため、誤りです。
⑧【誤】
A、B、Cはすべてサービスの取引に該当するため、誤りです。
問5:正解④
<問題要旨>
プラットフォームビジネスに特徴的な「ネットワーク効果」と、それに伴う市場の独占・寡占化、そして競争がもたらす消費者への影響について、会話文の空欄を補充することで理解度を問う問題です。
<選択肢>
①~③【誤】
X, Y, Zの記述の組み合わせが誤りです。
④【正】
X:あるWebサイト(プラットフォーム)の利用者数が多いと、制作者も見る人も広告主もそこに集まります 。この状況で利用者は、より多くのコンテンツや交流相手がいる人気のサイトを利用し続けると考えられます。これを「ロックイン効果」とも言います。よってXには「ア 毎回同じ人気のある Web サイトを利用する」が入ります 。
Y:Xのようなメカニズム(ネットワーク効果)が働くと、利用者が多いプラットフォームがさらに多くの利用者を呼び込み、市場で圧倒的な勝者となる傾向があります。これを「ウィナー・テイク・オール(勝者総取り)」と言います。よってYには「キ 利用者数が多いプラットフォームに、さらに利用者が集まる」という結果になる、という記述が入ります 。
Z:一つのプラットフォームが市場を独占すると、価格をつり上げたりサービスの質を低下させたりする懸念があります。しかし、先生は「利用者は価格やサービスの面で得することが多い」と述べています 。これは、複数のプラットフォームが存在し、利用者獲得のために競争している状況を指しています。よってZには「シ 複数のプラットフォームが、競争しつつサービスを提供する」方が良い、という記述が入ります 。
したがって、X-ア、Y-キ、Z-シの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
⑤~⑧【誤】
X, Y, Zの記述の組み合わせが誤りです。
問6:正解④
<問題要旨>
現代社会における国家・政府の役割に関する問題です。国際会議、経済思想、地方分権、国家予算といった幅広い分野から、正確な知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
2008年の世界金融危機(リーマン・ショック)を機に、新興国を含む主要国・地域が経済問題を話し合う首脳会議として開かれるようになったのは、G20サミット(金融・世界経済に関する首脳会合)です 。G7サミットは、日・米・英・仏・独・伊・加の7か国(+EU)による会議です。
②【誤】
政府の市場への介入を重視する「大きな政府」を否定し、市場原理を重視して規制緩和や民営化を進める「小さな政府」を目指す考え方は、新自由主義(ネオリベラリズム)です 。修正資本主義は、ケインズ経済学に基づき、混合経済体制のもとで政府が市場に積極的に介入し、完全雇用や福祉国家を目指す考え方で、「大きな政府」につながります。
③【誤】
1999年に制定(2000年施行)された地方分権一括法により、地方公共団体の事務は、国から委託される法定受託事務と、それ以外の自治事務に再編されました 。一本化されたわけではありません。
④【正】
日本の国の予算(一般会計)は、社会保障費の増大などにより年々増加しており、2022年度の当初予算は総額で107兆円を超え、100兆円を大きく上回りました 。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
第4問
問1:正解④
<問題要旨>
日本の刑事司法制度に関する憲法の規定や法律の知識を問う問題です。検察審査会、裁判員裁判、自白の証拠能力、刑事補償制度について、正確な理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
検察官が不起訴とした処分に対し、検察審査会が2度「起訴相当」と議決した場合、裁判所が指定した弁護士が検察官役となって強制的に起訴します 。起訴を担当するのは検察官ではありません。
②【誤】
裁判員裁判の対象となるのは、殺人などの重大事件の「第一審」のみです 。控訴審(第二審)や上告審(第三審)に裁判員は関与しません。
③【誤】
日本国憲法第38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と定めています 。つまり、自白以外に証拠がなければ有罪にはできません。
④【正】
日本国憲法第40条は「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」と定めています 。これを刑事補償制度といいます。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
問2:正解⑥
<問題要旨>
刑罰の目的や性質に関する思想(応報刑論、一般予防論、特別予防論)と、それを説明した文章を正しく結びつける問題です。思想の核心を理解し、文章を読解する力が必要です。
<選択肢>
①【誤】
ア, イ, ウとA, B, Cの組み合わせが誤りです。
②【誤】
ア, イ, ウとA, C, Bの組み合わせが誤りです。
③【誤】
ア, イ, ウとB, A, Cの組み合わせが誤りです。
④【誤】
ア, イ, ウとB, C, Aの組み合わせが誤りです。
⑤【誤】
ア, イ, ウとC, A, Bの組み合わせが誤りです。
⑥【正】
ア:「犯罪を犯したがゆえに」科されるべきで、「別の善を促進する手段」ではない、としています 。これは、刑罰は犯罪に対する報復・報いであるとする「応報刑論」の考え方です。したがって、Cの「過去に行った犯罪に対する報い(応報)として科される」に合致します 。
イ:「他の人々の心にみせしめによってきざまれる威嚇」が目的だとしています 。これは、刑罰を社会一般の人々(他の人々)に示すことで犯罪を思いとどまらせる「一般予防論」の考え方です。したがって、Bの「他の人々に警告して犯罪を行わせないために科される」に合致します 。
ウ:「改善不能なものは無害化し、改善を必要とするものは改善する」ことが目的だとしています 。これは、犯罪者本人を改善・教育したり、社会から隔離したりすることで、その人が再び罪を犯すことを防ぐ「特別予防論」の考え方です。したがって、Aの「犯罪者が将来、再び罪を犯すことを防ぐために科される」に合致します 。
以上より、ア-C、イ-B、ウ-Aの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
問3:正解②
<問題要旨>
防犯カメラの設置をめぐる議論について、会話文の空欄に人権(プライバシー権、肖像権、表現の自由など)に関する適切な記述を補充する問題です。具体的な人権侵害の態様を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
イとウに入る記述の組み合わせが誤りです。
②【正】
ア:承諾なしに映像を撮影すること自体は、Bの「みだりに自己の容貌・姿態を撮影されない自由」(肖像権、プライバシー権の一種)を制約することになります 。
イ:撮影された映像が保存・管理されることは、その映像が外部に流出したり、防犯以外の目的で悪用されたりするリスクを生じさせます。これは、Aの「映像が流出したり、防犯以外の目的で利用されたりするリスクを発生させる」ことに繋がります 。
ウ:たとえ模型であっても、常に監視されていると感じることで、人々が自由な行動をためらうようになる可能性があります。これは、Cの「公共の場で意見を表明したり、その他の様々な活動をしたりすることを萎縮させる」(萎縮効果)という問題に繋がります 。
設問はイとウに入る記述を問うているため、イ-A、ウ-Cの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
③~⑥【誤】
イとウに入る記述の組み合わせが誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
基本的人権に関する日本の最高裁判所の判例についての知識を問う問題です。教科書検定、わいせつ文書、プライバシー権、私人間効力に関する重要な訴訟での最高裁の判断を正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
一連の家永教科書訴訟において、最高裁は、教科書検定制度そのものは教育行政として許される裁量の範囲内であり、合憲であるとの判断を示しています 。ただし、検定における国の裁量権の濫用を認めた例はあります。
②【誤】
チャタレー事件(1957年)の最高裁判決では、『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳書がわいせつ文書にあたるとし、それを頒布することを禁じた刑法の規定は、公共の福祉に適合するものであり、憲法が保障する表現の自由に違反しない(合憲である)と判断しました 。
③【正】
小説『石に泳ぐ魚』事件(2002年)において、最高裁は、小説のモデルとされた人物のプライバシーや名誉などが、公表によって重大かつ回復困難な損害を被るおそれがある場合には、表現の自由よりも優先されるとして、出版の差止め(事前抑制)を認める判断を下しました 。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
④【誤】
三菱樹脂訴訟(1973年)において、最高裁は、憲法の人権規定は国や地方公共団体と個人との関係を規律するものであり、原則として私人(企業)と個人の間に直接適用されるものではない(間接適用説)という判断を示しました 。
問5:正解②
<問題要旨>
日本の国会および国会議員に関する制度や慣行についての知識を問う問題です。国会の会期、政治献金、党議拘束、政府委員制度について、正確な理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
衆議院の解散中に、国に緊急の必要があるときに開かれるのは、参議院の緊急集会です 。臨時会は、内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集されます。
②【正】
政治資金規正法により、企業や団体が、政治家個人(候補者個人)に対して政治活動に関する寄附(政治献金)をすることは禁止されています 。献金は政党や政治資金団体に対して行う必要があります。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
③【誤】
政党に所属する議員が、党の決定(党議)に従って投票することを「党議拘束」といいます 。マニフェストは、政党が選挙に際して有権者に示す政権公約のことです。
④【誤】
政府委員制度は、各省庁の官僚が大臣に代わって国会で答弁する制度でしたが、国会審議の活性化と政治主導の確立のため、1999年の国会改革で廃止されました 。現在は副大臣・大臣政務官制度が導入されています。
問6:正解④
<問題要旨>
日本の選挙制度に関する公職選挙法の規定についての知識を問う問題です。在外選挙、選挙運動、選挙の原則、連座制について問われています。
<選択肢>
①【誤】
1998年の公職選挙法改正により、外国に居住する日本人でも、国政選挙(衆議院・参議院)において投票できる「在外選挙制度」が導入されています 。
②【誤】
公職選挙法により、選挙運動期間中の戸別訪問は、有権者への利益誘導や買収につながるおそれがあるため、禁止されています 。
③【誤】
財産や納税額にかかわらず、一定年齢以上のすべての国民が選挙権を持つ選挙は「普通選挙」と呼ばれます 。秘密選挙は、誰に投票したかを他人に知られないようにする原則です。
④【正】
候補者の選挙運動の総括主宰者や出納責任者などが、買収などの悪質な選挙違反で有罪となった場合、候補者自身が関与していなくても当選が無効となる「連座制」が公職選挙法で定められています 。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
問7:正解⑤
<問題要旨>
住民が地方自治に直接参加する方法(直接請求権など)について、会話の流れに沿って適切な制度を判断する問題です。議会の解散請求、条例の制定改廃請求、陳情といった制度の目的や手続きのハードルを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①~④【誤】
ア, イ, ウの記述の組み合わせが誤りです。
⑤【正】
アライさんは、条例を制定しない議会を信任できないとして、より強力な手段を提案しています。これは、Cの「議会の解散を請求する」ことにあたります 。
マエダさんは、議会の解散請求は住民投票で過半数の同意が必要など「ハードルが高い」と指摘し 、よりハードルが低く、目的(条例制定)に直接関連する方法として、イを提案しています。これは、Aの「市長に対して、条例の制定を請求する」ことにあたります 。条例制定請求は、有権者の50分の1以上の署名で請求できます。
さらにマエダさんは、議会に否決された場合に備え、署名も不要なさらにハードルの低い方法としてウを提案しています。これは、Bの「議会の議員に対して、条例の制定を陳情する」ことにあたります 。陳情や請願は、法的な拘束力はありませんが、議会に意見を伝える手段となります。
したがって、ア-C、イ-A、ウ-Bの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
⑥【誤】
ア, イ, ウの記述の組み合わせが誤りです。
第5問
問1:正解③
<問題要旨>
貧困(絶対的貧困、相対的貧困)の定義と、それに関する複数の統計資料(表1、表2)を正確に読み解く力を問う問題です。数値の比較や計算、そして統計の注釈を注意深く読むことが求められます。
<選択肢>
①【誤】
2018年の相対的貧困率15.4%は、等価可処分所得の中央値253万円の半分である「貧困線127万円」に満たない者の比率で算出されています 。記述は「253万円に満たない者」となっており、誤りです 。
②【誤】
表1より、2018年の子どもの相対的貧困率は13.5%です 。これは、100人に13.5人、つまり10人に1人以上の子どもが貧困線に満たない世帯で生活していることを意味します。「10人に1人未満」という記述が誤りです 。
③【正】
表2を見ると、アメリカの「大人が一人」の世帯の貧困率は45.7%、「大人が二人以上」は14.9%であり、その差は45.7 – 14.9 = 30.8ポイントで、30ポイント以上です 。デンマークでは、「大人が一人」が9.7%、「大人が二人以上」が3.5%で、その差は9.7 – 3.5 = 6.2ポイントであり、10ポイント以下です 。したがって、この記述は正しく、この選択肢が正解です。
④【誤】
表2より、日本の「大人が一人」の世帯の貧困率は48.3%であり、OECD平均の31.9%よりも16.4ポイント高く、10ポイント以上「高い」です 。記述は「低い」となっており、誤りです。
問2:正解③
<問題要旨>
子どもの貧困によって生じる問題(教育機会の不平等、社会的な孤立)に対して、官民が行う具体的な取り組みを正しく分類する問題です。各取り組みがどちらの問題に対応するものかを判断する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
イとエは「問題1」に対応するため、この組み合わせは誤りです。
②【誤】
イとエは「問題1」に対応するため、この組み合わせは誤りです。
③【正】
【問題1】は「教育の機会不平等」 、【問題2】は「社会的な孤立」です 。設問は【問題2】に対応するbの取り組みを問うています。
ア:ヤングケアラーが「友達や周囲の人との関係が疎遠になり、誰にも頼ることができない」状態は社会的な孤立であり、訪問相談はその支援にあたるため、【問題2】に対応します 。
イ:有料の補習による学力向上支援は、進学に関わるものであり、【問題1】の教育機会不平等に対応します 。
ウ:「旅行や遊園地に行ったことがない」といった生活上の経験不足や、キャンプなどの活動を通じて人とのつながりを創出することは、社会的な孤立の解消につながるため、【問題2】に対応します 。
エ:県外大学への進学を支援する給付型奨学金は、経済的理由による進学断念を防ぐものであり、【問題1】の教育機会不平等に対応します。
したがって、【問題2】に対応するのはアとウであり、この選択肢が正解です。
④【誤】
イとエは「問題1」に対応するため、この組み合わせは誤りです。
⑤【誤】
エは「問題1」に対応するため、この組み合わせは誤りです。
⑥【誤】
イ、エは「問題1」に対応するため、誤りです。
⑦【誤】
イは「問題1」に対応するため、誤りです。
⑧【誤】
エは「問題1」に対応するため、誤りです。
⑨【誤】
エは「問題1」に対応するため、誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
子どもの貧困問題の解決策について、二つの異なるアプローチ(所得再分配の強化、地域社会の役割)を提示し、それぞれの立場に合致する具体的な政策や考え方を選択する問題です。税制や社会福祉の担い手に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
Bの記述がフジタさんの立場と合致しません。
②【正】
A:フジタさんは、経済的不平等を是正するために政府の所得再分配機能が重要であり、その際に「低所得層にとって負担が大きくならない」方法が適切だと主張しています 。これは、所得が高いほど税率が高くなる「ア 所得税の累進性を高める」ことによって、高所得者から低所得者への所得再分配を強化するという考え方と合致します 。
B:ハヤシさんは、すぐに解決できない経済的不平等よりも、地域の人々が主体的に問題を解決することが大事だと主張しています 。これは、行政だけでなく「エ NPOや学生、高齢者などの多様な担い手が、福祉活動に参画することで、子どもの社会参加を促進する」という、地域の多様な主体による支え合いを重視する考え方と合致します 。
したがって、A-ア、B-エの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
③【誤】
Aの記述がフジタさんの立場と合致しません。消費税は所得にかかわらず同じ税率がかかるため、低所得者ほど所得に占める負担率が高くなる「逆進性」という課題があります 。
④【誤】
Aの記述がフジタさんの立場と合致しません。
⑤【誤】
AとBの記述が、それぞれの主張と逆になっています。
⑥【誤】
AとBの記述が、それぞれの主張と逆になっており、かつAの記述がフジタさんの立場と合いません。
⑦【誤】
AとBの記述が、それぞれの主張と逆になっています。
⑧【誤】
AとBの記述が、それぞれの主張と逆になっており、かつAの記述がフジタさんの立場と合いません。