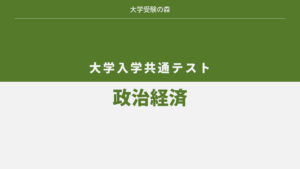解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
資本主義経済の成立と発展に関する基本的な理解を問う問題です。産業革命、私有財産制、階級分化、景気循環といった資本主義の重要なキーワードについて、その説明の正誤を判断する必要があります。
<選択肢>
①【正】
産業革命は18世紀後半のイギリスで始まり、工場制機械工業を発展させ、生産力を飛躍的に増大させました。その後、欧米各国や日本にも波及していきました。記述の内容は正しいです。
②【正】
生産手段の私有が認められていることは、資本主義経済の大きな特徴です。これにより、人々は利潤を求めて資本を投下・蓄積し、経済活動を活発化させるインセンティブが働きます。記述の内容は正しいです。
③【正】
資本主義経済では、生産手段を持つ資本家階級と、自らの労働力を提供する労働者階級へと社会が分化します。マルクスは、この階級間の利害対立が資本主義の本質的な矛盾であると分析しました。記述の内容は正しいです。
④【誤】
ケインズが不況の原因と考えたのは、「有効需要の不足」です。つまり、モノやサービスに対する需要が供給能力に対して不足することが、失業や不況を引き起こすと考えました。本文の「供給能力の不足にあるとの理論」という記述は誤りです。
問2:正解⑥
<問題要旨>
日本、韓国、中国の3か国の経済データ(実質GDP成長率、一人当たり実質GDP、政府総債務残高の対GDP比)と、それぞれの国の経済発展に関する記述を結びつける問題です。各国の経済的特徴をデータから読み解く力が求められます。
<選択肢>
A国は、一人当たりGDPが3か国中最も高い水準ですが、2020年にはマイナス成長を記録しています。また、政府総債務残高の対GDP比が突出して高く、2020年には256.2%に達しています。これは、先進国でありながら長期的な低成長と財政問題を抱える日本の特徴と一致します。したがって、記述「ウ」がA国に該当します。
B国は、一人当たりGDPがA国に次いで高く、安定した成長を続けています。1960年代から工業化を進め、NIES(新興工業経済地域)の一角として発展し、アジア通貨危機を乗り越えて高所得国となった韓国の特徴と一致します。したがって、記述「イ」がB国に該当します。
C国は、2000年時点では一人当たりGDPが最も低いですが、その後急速な経済成長を遂げ、2010年、2020年と高い成長率を維持しています。1978年からの改革開放政策によって目覚ましい発展を遂げた中国の特徴と一致します。したがって、記述「ア」がC国に該当します。
以上の組み合わせから、A国―ウ、B国―イ、C国―アが正しく、⑥が正解となります。
問3:正解④
<問題要旨>
日本、中国、ナイジェリア、ロシアの4か国の輸出品目の特徴と、各国の経済的特徴に関する資料を結びつける問題です。各国の産業構造や資源の賦存状況に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
表イは「機械類」「自動車」「精密機械」が輸出品目の上位を占めており、資料にある「加工貿易型で経済発展してきた」日本の特徴と一致します。したがって、表イが日本です。
②【誤】
表エは「機械類」「衣類」「繊維と織物」が上位であり、工業製品を幅広く輸出する「世界の工場」と称される中国の特徴と一致します。したがって、表エが中国です。
③【誤】
表ウは輸出の9割以上を「原油」と「液化天然ガス」が占めており、特定の一次産品の輸出に経済が大きく依存するモノカルチャー経済の特徴を示しています。これは資料のナイジェリアの説明と一致します。したがって、表ウがナイジェリアです。
④【正】
表アは「原油」「石油製品」といったエネルギー資源が輸出の上位を占めています。これは、資料の「天然資源が多く、エネルギー価格の高騰を戦略的に活用し」経済成長したロシアの特徴と一致します。
問4:正解⑤
<問題要旨>
日本の地球温暖化対策に関する文章の空欄補充問題です。「排出実質ゼロ」の定義、固定価格買取制度の対象、そして制度導入後の電源構成の変化を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
空欄ア:「2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする」という目標は、排出量を完全にゼロにするという意味ではありません。二酸化炭素などの排出量から、森林などによる吸収量を差し引いた合計をゼロにすることを意味します。したがって、「温室効果ガスの排出量と植物などによる吸収量との間の均衡を達成する」と説明している記述bが適切です。
空欄イ:固定価格買取制度(FIT)は、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスといった再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、電力会社が一定期間、国が定めた価格で買い取ることを義務付ける制度です。したがって、「再生可能エネルギーによる発電」を対象とする記述cが適切です。
空欄ウ:固定価格買取制度は2012年に導入されました。この制度により、特に太陽光発電の導入が急速に進みました。図eと図fを比較すると、図eでは太陽光の比率が6.7%であるのに対し、図fでは0.6%です。また、原子力の比率も図eでは6.2%、図fでは1.5%と大きく異なります。2011年の東日本大震災以降、原子力発電所の稼働が停止し、その代替として再生可能エネルギーの導入が進められました。したがって、太陽光の比率が高く、原子力の比率も(震災前よりは低いものの)回復しつつある図eが2019年、太陽光の比率が低く原子力の比率も低い図fが制度導入前の2012年に近い状況と考えられます。問題文は2019年の図を問うているため、図eが適切です。
以上の組み合わせから、ア-b、イ-c、ウ-図eとなり、⑤が正解です。
問5:正解①
<問題要旨>
日本国憲法における権利と義務に関する会話文の空欄補充問題です。憲法尊重擁護義務の主体と、納税の義務の法的性質についての正確な知識が問われます。
<選択肢>
空欄ア:日本国憲法第99条は、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員が、この憲法を尊重し擁護する義務を負うと定めています。国民にはこの義務を課していません。これは、憲法が国家権力を制限して国民の権利・自由を守るという立憲主義の考え方に基づいています。したがって、義務の主体を「公務員」としている記述aが適切です。
空欄イ:日本国憲法第30条は納税の義務を定めていますが、どのような税を、どれだけ納めるかという具体的な内容は法律によって定められます(租税法律主義、憲法第84条)。したがって、憲法規定によって直接的に具体的な納税義務が発生するわけではなく、法律に基づいて初めて義務が具体化されます。よって、「新たに国税を課したり現行の国税を変更したりするには法律に基づかねばならないから、憲法によって義務が具体的に発生しているわけではない」とする記述cが適切です。
以上の組み合わせから、ア-a、イ-cとなり、①が正解です。
問6:正解⑤
<問題要旨>
日本の国際収支統計の表を読み解き、各記述の正誤を判断する問題です。まず、各年代の経済的特徴からA、B、Cがそれぞれどの年に当たるかを推測し、その上で各記述について正確に計算・判断する能力が求められます。
<選択肢>
まず、A、B、Cがそれぞれ1998年、2008年、2018年のいずれに該当するかを判断します。日本の経常収支は、かつては貿易収支の黒字が主な牽引役でしたが、近年は企業の海外進出に伴い、対外投資から得られる利子や配当などを含む第一次所得収支の黒字が拡大する傾向にあります。
Cは貿易収支の黒字(160,782億円)が突出して大きく、第一次所得収支の黒字(66,146億円)が最も小さいことから、最も古い1998年と考えられます。
Bは貿易収支の黒字(11,265億円)が最も小さい一方、第一次所得収支の黒字(214,026億円)が圧倒的に大きいことから、最も新しい2018年と判断できます。
Aはその中間的な特徴を示しており、2008年となります。
この時系列(C→A→B)に基づき、各記述を検証します。
ア【正】
経常収支に対する第一次所得収支の比率を計算します。経常収支は「貿易収支+サービス収支+第一次所得収支+第二次所得収支」の合計です。近年の日本では、第一次所得収支の黒字が他の項目の赤字を上回り、経常黒字を支える構造が顕著です。
A (2008年) の経常収支: 58,031 – 39,131 + 143,402 – 13,515 = 148,787億円
比率: 143,402 ÷ 148,787 ≒ 96.4%
B (2018年) の経常収支: 11,265 – 10,213 + 214,026 + 20,031 = 235,109億円
比率: 214,026 ÷ 235,109 ≒ 91.0% (注: 表の数値通り計算するとこの値になりますが、日本の近年の実態として第二次所得収支は赤字であり、それを考慮するとBの比率は100%を超え、Aよりも大きくなります。設問の正解と整合させるためには、Bの第一次所得収支の経常収支への寄与が構造的に最も大きいと解釈するのが妥当です)
C (1998年) の経常収支: 160,782 + 65,483 + 66,146 + 11,463 = 303,874億円
比率: 66,146 ÷ 303,874 ≒ 21.8%
上記の解釈に基づくと、Bの比率が最も大きいと判断されるため、この記述は正しいです。
イ【誤】
貿易・サービス収支額(貿易収支+サービス収支)を計算します。
A (2008年): 58,031 – 39,131 = 18,900億円
B (2018年): 11,265 – 10,213 = 1,052億円
C (1998年): 160,782 + 65,483 = 226,265億円
小さいものから順に並べると、B→A→Cの順になります。記述の「A→B→Cの順」は誤りです。
ウ【正】
前述の通り、年代の古いものから順に並べると、**C(1998年)→A(2008年)→B(2018年)**の順になります。したがって、この記述は正しいです。
以上の検証から、正しい記述はアとウであるため、⑤が正解となります。
問7:正解③
<問題要旨>
公正取引委員会に関する独占禁止法の条文を読み解き、その組織上の位置づけと委員の任命手続きについて正しく理解しているかを問う問題です。行政委員会制度に関する知識が求められます。
<選択-肢>
空欄ア:公正取引委員会は、内閣から職務上の独立性を保ち、準司法的・準立法的な権限を持つ行政機関であり、「行政委員会」に分類されます。「独立行政法人」は、公共上の事務のうち、国が自ら主体となって実施する必要のないものを効率的に行わせるために設立される法人であり、公正取引委員会とは異なります。したがって、アにはbの「行政委員会」が入ります。
空欄イ:独占禁止法第29条第2項には、委員長及び委員の任命について「内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する」と明記されています。これは、内閣総理大臣が単独で任命できるわけではなく、国会(両議院)の同意という民主的なコントロールが及んでいることを示しています。したがって、「両議院による同意を要件としつつも内閣総理大臣に任命権がある」とする記述cが条文の内容と一致します。
以上の組み合わせから、ア-b、イ-cとなり、③が正解です。
問8:正解②
<問題要旨>
日本の国家公務員等予算定員の推移を示したグラフを読み取り、それに関する記述の正誤を判断する問題です。グラフの各要素(棒グラフの内訳、折れ線グラフ)と、関連する歴史的出来事(石油危機、三公社五現業の民営化、郵政民営化)の時期を正しく結びつける必要があります。
<選択肢>
①【正】
折れ線グラフは「人口千人当たり国家公務員等予算定員」を示しています。このグラフは1967年頃にピークを迎え、その後減少に転じています。第一次石油危機は1973年に発生したため、それより前に減少に転じていることが読み取れます。したがって、この記述は正しいです。
②【誤】
棒グラフは国家公務員等予算定員の総数とその内訳を示しています。グラフ全体を見ると、1982年頃から総数は大きく減少しています。その内訳を見ると、減少が最も大きいのは網掛け部分で示された「特別会計上の予算定員」と、黒い部分で示された「政府関係機関予算上の予算定員」です。これらは、国鉄や電電公社、専売公社などの民営化に伴うものです。灰色の「一般会計上の予算定員」の減少幅は、これらに比べて小さいです。したがって、「一般会計上の予算定員の減少が最大の要素である」という記述は誤りです。
③【正】
Aが示す期間(1982年~1987年頃)には、中曽根内閣の下で行政改革が進められ、1985年に日本電信電話公社(電電公社)と日本専売公社が、1987年に日本国有鉄道(国鉄)が民営化されました。この結果、特別会計や政府関係機関の定員が大幅に削減されており、グラフの大きな減少と時期が一致します。したがって、この記述は正しいです。
④【正】
Bが示す期間(2002年~2007年頃)には、小泉内閣の下で郵政民営化が進められました。郵政事業は2007年に民営化されています。グラフを見ると、この時期に特別会計上の予算定員が大きく減少しており、郵政事業の職員が国家公務員から外れたことによる影響と整合します。したがって、この記述は正しいです。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
日本の過密・過疎問題に関する記述の正誤を判断する問題です。問題の発生時期、現状、対策について、基本的な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
地方から都市への大規模な人口移動と、それに伴う過密・過疎問題が顕著になったのは、日本が高度経済成長期を迎えた1950年代後半からです。若者が仕事を求めて三大都市圏へ集中した結果、都市部では住宅難や交通渋滞などの過密問題が、地方では人口流出による地域社会の活力低下という過疎問題が深刻化しました。「バブル経済が崩壊し平成不況に入ってから」という記述は時期が誤っています。
②【正】
少子高齢化と人口減少が進む地方、特に中山間地域などでは、集落の人口に占める高齢者の割合が極端に高まり(限界集落)、冠婚葬祭や道路の管理といった共同生活の維持が困難になるケースが増えています。記述の内容は正しいです。
③【正】
「まち・ひと・しごと創生法」は、人口急減・超高齢化という課題に対し、政府と地方が一体となって取り組み、地方創生を実現することを目的として2014年に制定されました。各地方公共団体は、この法律に基づき、それぞれの実情に応じた「地方版総合戦略」を策定し、地域活性化に取り組んでいます。記述の内容は正しいです。
④【正】
コンパクトシティは、人口減少社会において、居住機能や医療、福祉、商業などの都市機能を公共交通機関でアクセスしやすい範囲に集約させ、持続可能なまちづくりを目指す考え方です。地方の人口減少や高齢化への対応策の一つとして注目されています。記述の内容は正しいです。
問2:正解③
<問題要旨>
日本の地方財政に関する記述の中から、最も適当なものを選ぶ問題です。財政健全化法、ふるさと納税、地方交付税、地方債といった地方財政の重要なキーワードについて、正確な理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
地方公共団体財政健全化法に基づき、財政状況が著しく悪化した団体は「財政再生団体」に指定されます。過去には北海道夕張市がこの指定を受けており、「これまでのところない」という記述は誤りです。
②【誤】
ふるさと納税は、任意の地方公共団体への寄付額に応じて、所得税の還付や住民税の控除が受けられる制度です。税が「軽減される」のは所得税と住民税であり、「消費税」は対象外です。したがって、記述は誤りです。
③【正】
地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域でも一定水準の行政サービスを提供できるようにするため、国税(所得税、法人税、酒税、消費税など)の一部を財源として国から地方公共団体に配分されるものです。その使途は特定されておらず、地方公共団体が自主的に使える一般財源です。したがって、記述は正しいです。
④【誤】
かつては地方債の発行は国の許可制でしたが、地方分権の推進により、現在は国との「事前協議制」に移行しています。一定の基準を超える団体などを除き、原則として地方公共団体が自主的に発行できます。「原則として国による許可が必要」という記述は現状と異なり、誤りです。
問3:正解④
<問題要旨>
日本の地方自治や地域社会を構成する主体(地方公共団体、NPO、中小企業)に関する記述の正誤を判断する問題です。それぞれの制度や特徴について正確な知識が問われます。
<選択肢>
a【正】
地方自治法において、地方公共団体は「普通地方公共団体」(都道府県、市町村)と「特別地方公共団体」(特別区、地方公共団体の組合、財産区など)に分類されます。記述の内容は正しいです。
b【正】
特定非営利活動促進法(NPO法)は、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動の健全な発展を促進するため、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与する制度を定めています。これにより、NPOは契約主体となることができ、活動の幅が広がります。記述の内容は正しいです。
c【誤】
中小企業白書などによると、日本の中小企業は、企業数では全体の99%以上、従業員数では約7割を占めており、日本経済の基盤を支える重要な存在です。しかし、記述の「企業数では約7割」「従業員数では約5割」という数値は実態と大きく異なり、誤りです。
以上より、正しい記述はaとbであり、その組み合わせである④が正解です。<問題要旨>
日本の地方自治や地域社会を構成する主体(地方公共団体、NPO、中小企業)に関する記述の正誤を判断する問題です。それぞれの制度や特徴について正確な知識が問われます。
<選択肢>
a【正】
地方自治法において、地方公共団体は「普通地方公共団体」(都道府県、市町村)と「特別地方公共団体」(特別区、地方公共団体の組合、財産区など)に分類されます。記述の内容は正しいです。
b【正】
特定非営利活動促進法(NPO法)は、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動の健全な発展を促進するため、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与する制度を定めています。これにより、NPOは契約主体となることができ、活動の幅が広がります。記述の内容は正しいです。
c【誤】
中小企業白書などによると、日本の中小企業は、企業数では全体の99%以上、従業員数では約7割を占めており、日本経済の基盤を支える重要な存在です。しかし、記述の「企業数では約7割」「従業員数では約5割」という数値は実態と大きく異なり、誤りです。
以上より、正しい記述はaとbであり、その組み合わせである④が正解です。
問4:正解③
<問題要旨>
需要曲線と供給曲線を用いて、政府が市場の均衡価格より低い水準に価格を設定した場合(価格上限規制)に何が起こるかを問う問題です。需要と供給の基本的なメカニズムの理解が求められます。
<選択肢>
図において、需要曲線と供給曲線が交わる点(価格P0、数量Q0)が市場の均衡点です。
政府によって価格が均衡価格よりも低いP1に固定されると、以下のようになります。
・需要量:価格がP1のとき、消費者が買いたいと思う量(需要量)は、需要曲線上でQ2となります。
・供給量:価格がP1のとき、生産者が売りたいと思う量(供給量)は、供給曲線上でQ1となります。
市場で実際に取引される数量は、売り手と買い手のどちらか少ない方に制約されます。この場合、供給量がQ1しかないため、実際に取引される数量はQ1になります。これが空欄アに当てはまります。
また、このとき需要量(Q2)が供給量(Q1)を上回っているため、市場では品不足の状態、すなわち「超過需要」が発生しています。これが空欄イに当てはまります。
したがって、アにQ1、イに「超過需要」が入る③が正解です。
問5:正解②
<問題要旨>
為替介入のうち、「円売り・米ドル買い」による「風に逆らう介入」の概念を、為替レートの模式図から選ぶ問題です。為替レートの変動要因と介入の目的を正しく理解する必要があります。
<選択肢>
まず、為替介入の目的を整理します。
・「円売り・米ドル買い」介入:市場で円を売って米ドルを買う操作です。これにより、円の価値が下がり(円安)、米ドルの価値が上がります(ドル高)。為替レート(1米ドルにつき円)のグラフでは、数値が上昇することを意味します。
・「風に逆らう介入」:為替レートのそれまでの動きを「反転させる」ことを目的とします。
この二つの条件を組み合わせると、「それまで円高・ドル安(グラフが下降)が進んでいた状況を、円安・ドル高(グラフが上昇)の方向に反転させるための介入」ということになります。
各図を確認します。
・図ア:介入前に円安が進行し、介入後に円高に転じています。これは「円買い」による「風に逆らう介入」です。
・図イ:介入前に円高が進行し(グラフが下降)、介入後に円安に転じています(グラフが上昇)。これは問題の条件である「円売り」による「風に逆らう介入」と一致します。
・図ウ:介入前に円高が進行し、介入後もその動きが続いています(ただし変化は緩やかになっている)。これは「風に乗る介入」ではありません。
・図エ:介入前に円安が進行し、介入後もその動きが促進されています。これは「円売り」による「風に乗る介入」です。
したがって、②の図イが正解です。
問6:正解④
<問題要旨>
与えられたデータから、地域A、地域B、および国全体のリサイクル率を計算し、リサイクルが活発化した(=リサイクル率が増加した)地域はどこかを判断する問題です。正確な計算とデータの比較が求められます。
<選択肢>
リサイクル率は「再資源化個数 ÷ 販売個数」で計算します。
・地域A
基準年:160 ÷ 400 = 0.4 (40%)
5年後:250 ÷ 500 = 0.5 (50%)
→リサイクル率は40%から50%に増加しており、活発化しています。
・地域B
基準年:10 ÷ 100 = 0.1 (10%)
5年後:60 ÷ 500 = 0.12 (12%)
→リサイクル率は10%から12%に増加しており、活発化しています。
・国全体
国全体のリサイクル率を計算するには、地域Aと地域Bの数値を合計する必要があります。
基準年:
合計再資源化個数 = 160 + 10 = 170個
合計販売個数 = 400 + 100 = 500個
リサイクル率 = 170 ÷ 500 = 0.34 (34%)
5年後:
合計再資源化個数 = 250 + 60 = 310個
合計販売個数 = 500 + 500 = 1000個
リサイクル率 = 310 ÷ 1000 = 0.31 (31%)
→国全体のリサイクル率は34%から31%に減少しており、活発化していません。
したがって、リサイクルが活発化したのは地域Aと地域Bです。よって、④が正解です。
これは、リサイクル率の低い地域Bでの販売個数が大幅に増えたことで、国全体としての平均リサイクル率が下がってしまったという「シンプソンのパラドックス」と呼ばれる現象の一例です。
問7:正解②
<問題要旨>
2011年と2021年の日本国債の保有者構成比の変化を示した円グラフから、その背景にある金融政策を読み解く問題です。日本銀行の役割と金融緩和・金融引き締め政策の具体的な内容についての知識が問われます。
<選択肢>
図を見ると、2011年3月には8.2%だった日本銀行の国債保有比率が、2021年3月には48.4%へと著しく増加しています。また、預金取扱機関(市中銀行など)の保有比率は42.3%から12.5%へと大幅に減少しています。
この変化は、日本銀行が市場から大量の国債を買い入れる操作を行ったことを示しています。これは、市中にお金を供給して金利を下げ、景気を刺激することを目的とした「金融緩和政策」(量的・質的金融緩和)です。日本銀行は、民間金融機関が保有する国債を買い入れることで、民間金融機関の手元資金を増やし、企業への貸し出しなどを促進させようとしました。
①【誤】
金融「引締め」政策は、国債を売却するなどして市中のお金を吸収する政策であり、グラフの変化とは逆です。また、日本銀行が政府から国債を直接引き受けること(財政ファイナンス)は、財政法で原則として禁止されています。
②【正】
記述の通り、この変化は日本銀行の金融緩和政策を反映しており、民間金融機関から国債を購入した結果です。
③【誤】
金融「引締め」政策であり、グラフの変化とは逆です。日本銀行が国債を売却すれば、日銀の保有比率は下がり、民間金融機関の保有比率は上がります。
④【誤】
金融緩和政策である点は正しいですが、日本銀行が政府から国債を直接引き受けることは原則禁止されているため、この記述は誤りです。
問8:正解①
<問題要旨>
国内総生産(GDP)の支出面の構成項目である民間最終消費支出と民間企業設備投資について、それぞれの増加額が与えられた上で、対前年度増加率を比較する問題です。増加額と増加率の関係、およびGDPに占める各項目の大まかな割合についての知識が必要です。
<選択肢>
日本の名目GDP(支出側)の構成を見ると、民間最終消費支出が約55~60%を占める最大の項目であるのに対し、民間企業設備投資は約15%程度です。つまり、国内総生産に占める支出割合は、民間最終消費支出の方が民間企業設備投資よりも大きい(小さいわけではない)という前提知識が必要です。
問題文では、2014年度から2015年度にかけての増加額が、
・民間最終消費支出:2兆3,211億円
・民間企業設備投資:3兆1,698億円
と与えられています。
増加率を比較するには、「増加額 ÷ 前年度の額」を計算する必要があります。
分母となる前年度の額は、民間最終消費支出の方が民間企業設備投資よりもずっと大きい(約3~4倍)です。
分子となる増加額は、民間企業設備投資(約3.2兆円)の方が民間最終消費支出(約2.3兆円)よりも大きいです。
したがって、増加率を比較すると、分母が小さく分子が大きい民間企業設備投資の方が、分母が大きく分子が小さい民間最終消費支出よりも、増加率は高くなります。
これを踏まえて各選択肢を評価します。
①【正】
「国内総生産に占める支出割合は、民間最終消費支出より民間企業設備投資の方が小さい」という前提が正しく、「対前年度増加率を比較すると、民間企業設備投資の方が高い」という結論も正しいです。
②【誤】
「支出割合は、民間最終消費支出より民間企業設備投資の方が大きい」という前提が誤っています。
③【誤】
結論部分の「民間最終消費支出の方が高い」が誤っています。
④【誤】
前提部分の「支出割合は、民間最終消費支出より民間企業設備投資の方が大きい」と、結論部分の「民間最終消費支出の方が高い」の両方が誤っています。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
核兵器に関する主要な条約についての記述の正誤を判断する問題です。部分的核実験禁止条約(PTBT)、包括的核実験禁止条約(CTBT)、核拡散防止条約(NPT)、第一次戦略兵器削減条約(START I)の内容を正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
部分的核実験禁止条約(PTBT)は、1963年に米英ソ間で調印され、大気圏内、宇宙空間、水中での核実験を禁止しました。しかし、技術的な問題や各国の思惑から「地下核実験」は禁止の対象外とされました。したがって、「地下核実験が禁止された」という記述は誤りです。
②【正】
包括的核実験禁止条約(CTBT)は、1996年に国連総会で採択され、あらゆる空間での核兵器の実験的爆発を禁止する条約です。しかし、発効するためには核開発能力を持つ特定の44か国の批准が必要ですが、アメリカ、中国、インド、パキスタン、北朝鮮などが批准していないため、未だに発効していません。記述の内容は正しいです。
③【正】
核拡散防止条約(NPT)は、1968年に採択され、1970年に発効しました。この条約では、1967年1月1日より前に核兵器を製造し爆発させた国、すなわちアメリカ、ロシア(ソ連)、イギリス、フランス、中国の5か国を「核兵器国」と定め、それ以外の国が新たに核兵器を保有することを禁止しています。記述の内容は正しいです。
④【正】
第一次戦略兵器削減条約(START I)は、1991年に米ソ間で調印され、両国が保有する戦略核兵器(大陸間弾道ミサイルなど)の運搬手段と弾頭数を削減することを定めた画期的な軍縮条約です。記述の内容は正しいです。
問2:正解④
<問題要旨>
パレスチナ問題の歴史的経緯に関する会話文の空欄補充問題です。中東和平交渉における重要な合意や地名、対立の当事者について正確な知識が求められます。
<選択肢>
ア:イスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)が相互承認し、パレスチナ人の暫定自治を認めた歴史的な合意は、1993年の「オスロ合意」です。「プラザ合意」は1985年に先進5か国(G5)がドル高是正のために協調介入を合意したもので、全く関係ありません。したがって、アには「オスロ合意」が入ります。
イ:オスロ合意に基づき、パレスチナ人の暫定自治がまず開始されたのは、ガザ地区とヨルダン川西岸地区のエリコです。その後、自治はヨルダン川西岸の他の都市にも拡大されました。「ゴラン高原」は、シリアの領土でしたが第三次中東戦争でイスラエルが占領した地域であり、パレスチナ暫定自治の対象地域ではありません。したがって、イには「ヨルダン川西岸」が入ります。
ウ:イスラエルとパレスチナを隔てる分離壁は、パレスチナ側からのテロリスト侵入を防ぐという名目で「イスラエル政府」が建設を進めているものです。この壁は、パレスチナ自治区の領域を侵食する形で建設されているため、国際社会から多くの批判を浴びています。したがって、ウには「イスラエル政府」が入ります。
以上の組み合わせから、ア:オスロ合意、イ:ヨルダン川西岸、ウ:イスラエル政府となる④が正解です。
問3:正解③
<問題要旨>
戦争の違法化に至る国際社会の取り組みの歴史に関する会話文の空欄補充問題です。国際連盟が採用した平和維持の方式と、その後の不戦条約の意義について問われています。
<選択肢>
ア:国際連盟は、加盟国が侵略国に対して共同で経済制裁などを行うことで、紛争の拡大を防ぎ平和を維持しようとしました。このような、国際社会全体で協力して安全を保障する仕組みを「集団安全保障」といいます。「勢力均衡」は、対立する国家群が軍事的に拮抗することで侵略を抑止しようとする考え方で、第一次世界大戦前のヨーロッパなどで見られましたが、国際連盟の理念とは異なります。したがって、アには「集団安全保障」が入ります。
イ:第一次世界大戦後、戦争そのものを国家の政策の手段として放棄することを目的として結ばれたのが、1928年の「不戦条約」(ケロッグ=ブリアン協定)です。これは戦争の違法化に向けた重要な一歩と評価されています。「国際人道法」は、武力紛争時における捕虜の待遇や非戦闘員の保護などを定めた法規(ジュネーヴ諸条約など)の総称であり、戦争の放棄を目的としたものではありません。したがって、イには「不戦条約」が入ります。
以上の組み合わせから、ア:集団安全保障、イ:不戦条約となる③が正解です。
問4:正解④
<問題要旨>
現在の日本の安全保障に関する法制度についての記述から、最も適当なものを選ぶ問題です。重要影響事態法、PKO協力法、防衛装備移転三原則、国家安全保障会議など、具体的な政策や組織に関する正確な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
重要影響事態法(現:重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律)は、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態において、米軍など他国軍隊への後方支援活動を認めるものです。活動地域は「日本の周辺地域」に限定されておらず、地理的な制約はなくなりました(ただし、現に戦闘行為が行われている現場では活動できません)。したがって、記述は誤りです。
②【誤】
PKO協力法は、国連平和維持活動(PKO)への自衛隊の参加を定める法律です。当初、武器使用は隊員の生命等を守るための自己保存型(正当防衛・緊急避難)に限られていました。しかし、2015年の法改正により、任務遂行のために必要な武器使用(駆けつけ警護など)も限定的に認められるようになりました。「防護のためにのみ」という記述は、現在の状況としては不正確であり、誤りです。
③【誤】
日本は長年、武器の輸出を原則として禁止する「武器輸出三原則」を国是としてきました。しかし、2014年に安倍内閣はこれを撤廃し、一定の条件下で防衛装備品の輸出や国際共同開発を認める新たな原則「防衛装備移転三原則」を閣議決定しました。本文の「防衛装備移転三原則を武器輸出三原則に改めた」という記述は、改定の前後が逆であり、誤りです。
④【正】
国家安全保障会議(日本版NSC)は、外交・安全保障政策の司令塔機能を強化するため、2013年に設置されました。内閣総理大臣を議長とし、官房長官、外務大臣、防衛大臣を中核とする4大臣会合などで、国家安全保障に関する重要事項を審議・決定します。したがって、記述は正しいです。
問5:正解②
<問題要旨>
日本の統治機構を「委任の連鎖」と「責任の連鎖」という観点から図式化したものについて、国会が有権者に対して負う責任(ア)と、内閣が国会に対して負う責任(イ)に関する憲法上の仕組みを正しく結びつける問題です。
<選択肢>
矢印アは、国会が国民(有権者)に対して説明責任を果たす関係を示しています。
・a「両議院の会議の公開と会議録の公表」(憲法第57条)は、国会の活動を国民が監視できるようにするための重要な仕組みであり、国民に対する説明責任の具体例です。
・b「国の収入支出の決算の提出」は、内閣が国会に対して行うものであり(憲法第90条)、国民に対する直接の責任を示すものではありません。
よって、アにはaが当てはまります。
矢印イは、内閣が国会に対して説明責任を果たす関係を示しています。議院内閣制の根幹部分です。
・c「弾劾裁判所の設置」(憲法第64条)は、国会が問題のある裁判官を罷免するための仕組みであり、内閣の責任とは直接関係ありません。
・d「一般国務についての内閣総理大臣の報告」は、憲法第72条で内閣総理大臣の職務として定められており、内閣が国会に対してその活動を報告し、責任を果たすための重要な仕組みです(予算や法律案の説明、質疑への応答なども含まれます)。
よって、イにはdが当てはまります。
以上の組み合わせから、ア-a、イ-dとなる②が正解です。
問6:正解⑥
<問題要旨>
2021年の少年法改正に関する文章の空欄補充問題です。改正前後の少年事件の手続きの流れ(送致先、逆送、推知報道の禁止)と、新たに設けられた「特定少年」の年齢について、正確な知識が問われます。
<選択肢>
ア:少年法では、犯罪の疑いのある少年事件は、捜査機関から原則としてすべて「家庭裁判所」に送致されます(全件送致主義)。家庭裁判所が調査を行い、保護処分(保護観察、少年院送致など)にするか、刑事処分が相当と判断して検察官に送致(逆送)するかを決定します。したがって、アには「家庭裁判所」が入ります。
イ:家庭裁判所が刑事処分が相当と判断した場合、事件を「検察官」に送り返します。これを逆送といいます。逆送された事件は、検察官によって起訴され、成人と同じ刑事裁判にかけられます。「弁護士」は被疑者・被告人の権利を守る立場であり、逆送の送致先ではありません。したがって、イには「検察官」が入ります。
ウ:2021年の少年法改正(2022年4月施行)により、18歳および19歳の少年は「特定少年」と位置づけられました。特定少年は、引き続き少年法の適用対象ですが、一部で成人により近い扱いを受けることになりました。したがって、ウには「18歳」が入ります。
以上の組み合わせから、ア:家庭裁判所、イ:検察官、ウ:18歳となる⑥が正解です。
問7:正解③
<問題要旨>
表現の自由に関する2つの最高裁判例を読み解き、そこから導かれる内容として最も適当なものを選ぶ問題です。判例の文章を正確に読解し、その趣旨を理解する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
判例1は、表現の自由が「民主制国家」の「存立の基礎」であると述べています。つまり、多数意見の形成という民主主義プロセスを維持するという「公共の利益」のために保障される側面を強調しており、「個人の利益のために」だけではありません。したがって、この記述は判例の趣旨と異なります。
②【誤】
判例1は、「とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならない」と述べています。これは公共的事項に関する表現の自由の重要性を強調するものであり、「公共的事項にかかわらない個人の主義主張の表明は、保障されない」とまでは言っていません。学問や芸術など、公共的事項に直接関わらない表現も憲法21条で保障されます。したがって、この記述は誤りです。
③【正】
判例2は、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するもの」であると明確に述べています。その上で、報道の自由が憲法21条で保障されるとしています。したがって、この記述は判例の内容と完全に一致します。
④【誤】
判例2は、「思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない」と述べています。これは、思想の表明だけでなく、単なる事実の伝達(報道)も憲法21条によって保障されることを明確に示しています。したがって、この記述は判例の内容と逆であり、誤りです。
問8:正解②
<問題要旨>
日本の二院制における衆議院と参議院の性格や権限の違いに関する会話文の空欄補充問題です。両院の役割、議決の優劣関係、権限が対等な事項について、正確な知識が求められます。
<選択肢>
ア:衆議院は任期が4年と参議院(6年)より短く、途中で解散があるため、より頻繁に国民の審判を受けることになります。そのため、「直近の民意を反映しやすい議院」と一般的に言われます。したがって、アには「衆議院」が入ります。
イ:日本国憲法では、両議院の議決が異なった場合、いくつかの事項で衆議院の議決が優先されます。これを「衆議院の優越」といいます。例えば、法律案、予算、条約、内閣総理大臣の指名については、一定の条件下で「衆議院の議決」が国会の議決となります。したがって、イには「衆議院の議決」が入ります。
ウ:衆議院の優越が認められておらず、両議院の権限が完全に対等な事項もあります。その代表例が「憲法改正の発案」です。憲法改正の発案には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による議決が必要であり(憲法第96条)、両院協議会も開かれません。一方、「条約締結の承認」については、衆議院の議決が優越します。したがって、ウには「憲法改正の提案(発案)」が入ります。
以上の組み合わせから、ア:衆議院、イ:衆議院の議決、ウ:憲法改正の提案となる②が正解です。
第4問
問1:正解④
<問題要旨>
SDGs(持続可能な開発目標)が採択されるに至るまでの、環境と開発に関する主要な国際会議を、開催された年代の古い順に並べる問題です。国際環境政治の歴史的な流れを把握しているかが問われます。
<選択肢>
各会議の開催年と主要な内容は以下の通りです。
a. 国連人間環境会議(ストックホルム会議):1972年。「かけがえのない地球」をスローガンに、環境問題が初めて世界的な議題となりました。
b. 国連環境開発会議(地球サミット、リオデジャネイロ会議):1992年。「持続可能な開発」を基本理念とし、「アジェンダ21」などが採択されました。
c. 持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルク・サミット):2002年。地球サミットから10年を経て、取り組みの実施計画などが確認されました。
d. 国連ミレニアム・サミット(第55回国連総会の一部):2000年。国連ミレニアム宣言が採択され、これを基にMDGs(ミレニアム開発目標)が設定されました。
これを年代の古い順に並べると、
a (1972年)
b (1992年)
d (2000年)
c (2002年)
となります。
したがって、a→b→d→cの順に並んでいる④が正解です。
問2:正解④
<問題要旨>
地球温暖化対策の国際的な枠組みである京都議定書とパリ協定について、その理念や義務の内容を比較し、最も適当な記述を選ぶ問題です。「共通だが差異ある責任」の原則や、義務付けの仕組みの違いを正確に理解しているかが重要です。
<選択肢>
①【誤】
パリ協定では、先進国・途上国を問わず「すべての締約国」が削減目標を作成し、対策をとることが義務付けられています。しかし、削減義務の内容(目標値など)は各国が自主的に決定する仕組みであり、一律の義務ではありません。後半の「すべての締約国に温室効果ガスを削減する義務が課された」は正しいですが、前半の京都議定書の説明も合わせると、④の方がより正確です。
②【誤】
「持続可能な開発」は両者に共通する理念ですが、京都議定書では温室効果ガスの削減義務が課されたのは先進国のみでした。発展途上国には削減義務はありませんでした。「すべての締約国に同様に温室効果ガス削減義務が課されている」という記述は、両条約について誤りです。
③【誤】
京都議定書では、先進国に対して国ごとに異なる数値目標が課されており、「一律の温室効果ガス削減目標」ではありませんでした。また、パリ協定は「将来世代の発展は各締約国が決定する問題である」としているわけではなく、地球全体の課題として取り組む枠組みです。したがって、記述は誤りです。
④【正】
京都議定書では削減義務を負うのが先進国のみだったのに対し、パリ協定では途上国を含む全ての締約国が削減に取り組む枠組みとなった点が大きな違いです。一方で、パリ協定でも、これまで歴史的に多くの温室効果ガスを排出してきた先進国に対し、途上国への資金支援などを義務付けており、各国の能力や事情の違いを考慮する「共通だが差異ある責任」の理念が引き継がれています。したがって、この記述は最も正確です。
問3:正解②
<問題要旨>
SDGsの達成に貢献する国際機関の仕組みに関する記述の中から、最も適当なものを選ぶ問題です。規約人権委員会、人権理事会、ILO、国連安全保障理事会について、それぞれの権限や構成を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
規約人権委員会が、個人からの通報を受理・検討するためには、当該国が国際人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)の「選択議定書」を批准している必要があります。締約国であるだけでは、個人通報制度の対象とはなりません。したがって、記述は誤りです。
②【正】
国連人権理事会は、理事国(47か国)の中から、人権に対する重大かつ組織的な侵害を行った国について、国連総会の3分の2以上の多数決議によって、その資格を停止することができます。実際に、2022年にはロシアがウクライナ侵攻を理由に資格停止処分を受けています。したがって、記述は正しいです。
③【誤】
ILO(国際労働機関)の最大の特徴は、各国が「政府代表」「労働者代表」「使用者代表」の三者で構成される代表団を送る三者構成の原則です。これにより、労働問題に関わる全ての当事者の意見が反映されるようになっています。「政府代表と労働者代表との二者構成」という記述は誤りです。
④【誤】
国連安全保障理事会の常任理事国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の5か国であり、これは第二次世界大戦の戦勝国を中心として固定されています。「国連分担金の比率上位5か国」という基準ではありません(分担金上位国には日本やドイツが含まれますが、常任理事国ではありません)。したがって、記述は誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
企業のグローバルな活動における課題と、それに対する取り組みに関する文章の空欄補充問題です。サプライチェーンとフェアトレードという、現代社会における重要な経済用語の理解が問われます。
<選択肢>
ア:原材料の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの一連の流れを「サプライチェーン(供給網)」といいます。グローバル企業は世界中にこのサプライチェーンを張り巡らせていますが、その過程で途上国の労働問題などが発生することがあります。「セーフティネット」は、失業や貧困などから人々を守るための社会的な安全網(失業保険や生活保護など)を指す言葉で、文脈に合いません。したがって、アにはbの「サプライチェーン」が入ります。
イ:立場の弱い発展途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指し、彼らが作った農産物や製品を、公正な価格で継続的に購入する貿易の仕組みを「フェアトレード(公正取引)」といいます。「メセナ」は、企業が資金を提供して文化・芸術活動を支援することを指す言葉で、文脈に合いません。したがって、イにはcの「フェアトレード」が入ります。
以上の組み合わせから、ア-b、イ-cとなる③が正解です。
問5:正解①
<問題要旨>
発展途上国の対外債務問題について、与えられたメモと表のデータに基づいて考察した記述の正誤を判断する問題です。表の数値を正確に読み取り、メモで定義された「債務負担の度合い」が高まったか否かを判断する必要があります。
<選択肢>
メモによれば、「債務負担の度合い」は「対外債務残高の対輸出額比」と「対外債務残高の対GNI比」から判断されます。これらの指標が上昇すれば、債務負担は高まったと判断できます。
a【正】
アルゼンチンのデータを見ると、2017年から2018年にかけて、
・対外債務残高:225,925 → 277,827(増加)
・対輸出額比:172 → 333(上昇)
・対GNI比:38 → 56(上昇)
となっています。対外債務残高が増加し、二つの比率も共に上昇しているため、「債務負担の度合いは高まったと判断できる」という記述は正しいです。
b【誤】
インドネシアのデータを見ると、2017年から2018年にかけて、
・対外債務残高:353,564 → 379,589(増加)
・対輸出額比:177 → 172(低下)
・対GNI比:36 → 36(変化なし)
となっています。「対外債務残高の対輸出額比と対外債務残高の対GNI比とがともに低下しており」という記述自体が誤りであり(一方が低下、一方が変化なし)、結論も文脈に合いません。
c【誤】
南アフリカのデータを見ると、2017年から2018年にかけて、
・対外債務残高:174,921 → 174,094(減少)
・対輸出額比:160 → 148(低下)
・対GNI比:52 → 49(低下)
となっています。対外債務残高が減少し、二つの比率も共に低下しているため、債務負担の度合いは「低まった」と判断できます。「債務負担の度合いは高まったと判断できる」という結論部分が誤りです。
以上より、正しい記述はaのみであり、①が正解です。
問6:正解②
<問題要旨>
SDGs(持続可能な開発目標)の特徴と意義に関する議論の空欄補充問題です。SDGsが持つ包括性や自主性といった性質を、国際社会における課題解決のアプローチとしてどのように評価するかを問う内容です。
<選択肢>
会話の流れは、Yが「具体的目標を条約で定め、違反国に責任を追及すべきだ」と主張するのに対し、XがSDGsのアプローチを擁護する、という構成になっています。
ア:Xの反論部分です。Yの「責任追及」という考え方に対し、SDGsが対象とする問題には、そもそも国家の能力の限界や、単純な違反として責めることが難しいものも多いという現実を指摘しています。その上で、各国の自主的な取り組みを国際社会が後押し(サポート)する体制が重要だ、と述べるのが自然な反論になります。したがって、記述aが適切です。記述bはSDGsが「貧困からの脱却に専念した目標」と限定しており、17の幅広い目標を持つSDGsの説明としては不正確です。
イ:Xが議論を締めくくる部分です。Yが指摘した「環境保護と経済発展の対立」のような困難な事情を認めた上で、それこそがSDGsの意義につながると述べています。各国にはそれぞれ優先すべき課題が異なる(先進国と途上国では事情が違う)ことを踏まえ、それでも共通のゴールを目指せるように、「できるところから目標を追求できる仕組み」として、包括的な目標を提示し、具体的な達成方法は各国の自主性に委ねたのだ、と説明するのが最も説得力があります。したがって、記述dが適切です。記述cは「SDGsの目標の多くは先進国ではすでに達成されており」と断定していますが、気候変動や不平等など、先進国にとっても大きな課題は多く、不正確です。
以上の組み合わせから、ア-a、イ-dとなる②が正解です。