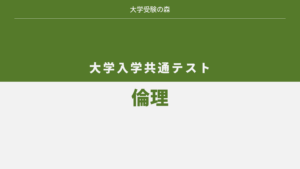解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
古代ギリシア思想と中国思想における宇宙観・世界観についての理解を問う問題です。それぞれの思想家の主張を正確に把握しているかがポイントになります。
<選択肢>
①【誤】
アのパルメニデスに関する記述が誤りです。パルメニデスは「あるものはあり、あらぬものはあらぬ」と述べ、万物の根源は永遠不変の「有」であると説きました。絶えざる生成消滅を説いたのはヘラクレイトスです。
②【誤】
アのパルメニデスに関する記述が誤りです。
③【誤】
アのパルメニデス、エの道家に関する記述が共に誤りです。エの道家は、万物の根源を「道(タオ)」とし、「無」から「有」が生じると考えました。『老子』には「天下の万物は有より生じ、有は無より生ず」とあります。
④【正】
イのエンペドクレス、ウの朱子に関する記述が共に正しいです。エンペドクレスは、火・空気・水・土の四元素が「愛」と「憎」の力によって結合・分離し、万物が生成されると説きました。朱子は、宇宙の根本原理である「理」と、物質的素材である「気」によって世界が構成されるとする理気二元論を大成しました。
⑤【誤】
エの道家に関する記述が誤りです
⑥【誤】
エの道家に関する記述が誤りです。
問2:正解③
<問題要旨>
古代インドの宗教、特に仏教とジャイナ教の戒律に関する理解を問う問題です。出家者と在家信者の戒律の違いや、仏教教団の歴史について正確な知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
仏教もジャイナ教も不殺生(アヒンサー)を重要な戒律としますが、仏教では在家信者に対しても五戒の一つとして不殺生戒を説きました。
②【誤】
ブッダの死後、教団は戒律を厳格に守ろうとする保守的な上座部と、戒律を柔軟に解釈しようとする進歩的な大衆部に分裂しました。この選択肢の記述は逆になっています。
③【正】
仏教では、出家者は厳しい禁欲生活を送る必要がありますが、在家信者は五戒の一つである不邪淫戒(不貞をしない)を守れば、結婚して家庭を持つことが認められていました。
④【誤】
六波羅蜜(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)は、大乗仏教の菩薩が実践すべき徳目であり、在家・出家を問わず、全ての修行者が目指すものです。したがって、在家者のための徳目ではないという記述は誤りです。
問3:正解④
<問題要旨>
『韓非子』の資料を読み解き、法家と儒家の思想的対立を理解する問題です。ノートにまとめられた内容の正誤を判断するため、両者の思想の核心を捉える必要があります。
<選択肢>
①【正】
法家は、国家の秩序を維持するために、君主が定めた法を絶対視します。躬の行動は、父子の情よりも国法を優先したものであり、法家の立場からは「君主に対する正直さ」として評価されうると言えます。
②【正】
儒家は、家族道徳、特に「孝」(親への敬愛)を社会秩序の基本と考えます。父を告発する行為は、この孝の精神に反するため、儒家の立場からは「父に対しては誤っている」と非難されます。
③【正】
資料文の最後に「楚では大臣が躬を殺してから、悪事が訴えられることはなくなった」とあり、ノートの記述はこの内容を正しく反映しています。
④【誤】
韓非子は法家の代表的思想家であり、個人的な情愛(私情)が法の支配を妨げると考えました。したがって、私的な情愛によって法の不備を補うべきだとは主張しません。むしろ、この話を通して、儒家的な「孝」のような私情が、国家の法秩序(公)にとっていかに有害であるかを示し、情に流されない厳格な法の支配の必要性を訴えています。
問4:正解①
<問題要旨>
新約聖書の記述を基に、キリスト教における宗教的義務と社会的義務の関係を理解し、それをイスラームの教えと比較する問題です。「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に」というイエスの言葉の解釈が鍵となります。
<選択肢>
①【正】
資料でイエスは、皇帝への納税(社会的義務)と神への信仰(宗教的義務)を区別し、両立するものとして示しています。これは、納税が信仰と矛盾しないことを意味します。一方、イスラームにおける喜捨(ザカート)は、宗教的義務(五行の一つ)でありながら、貧者救済という社会福祉的な機能も持ち、イスラーム国家においては税としての側面も有していました。両者の関係を的確に説明しています。
②【誤】
イエスは社会的規範を神への信仰より「優先する」とは言っていません。「神のものは神に」と述べており、両者を区別し、それぞれの領域を認めています。
③【誤】
イエスは皇帝への納税という社会的義務を「否定」しておらず、むしろ「返しなさい」と肯定しています。
④【誤】
イスラームでは、原則として政教一致であり、キリスト教世界のような聖職者階級は存在しません。ウラマー(イスラーム法学者)は存在しますが、彼らへの義務が神への義務に準ずるものとして制度化されているわけではありません。
問5:正解②
<問題要旨>
ヘレニズム時代の思想やインドの宗教における社会の捉え方について、その特徴を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ストア派は、理性をロゴスと呼び、全ての人間がロゴスの分有者であると考えました。そして、情念(パトス)に動かされず、自然に従って生きることを理想としました。情念を持つがゆえに世界市民になるという記述は誤りです。
②【正】
エピクロス派は、魂の平静(アタラクシア)を得ることを人生の目的としました。彼らは、公的な政治活動などが心の平安を乱すと考え、「隠れて生きよ」を信条とし、友人との私的な共同生活を重視しました。
③【誤】
バラモン教の司祭階級であるバラモンは、ヴァルナ制という社会秩序の頂点に立ち、その維持に深く関与していました。個人の救済のみを説いていたわけではありません。
④【誤】
ゴータマ・ブッダは、ヴァルナ制やバラモン教の権威を否定し、個人の社会的義務(ヴァルナごとに定められた業)よりも、八正道の実践による解脱を説きました。業(カルマ)は、行為とその結果の因果法則を指す言葉であり、ここでいう社会的義務とは意味合いが異なります。
問6:正解②
<問題要旨>
西洋思想および中国思想における「実践」に関する考え方の理解を問う問題です。各思想家の中心的な主張を正確に記憶しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
ソクラテスは、アテナイの法(ポリスの魂)に従うことが善く生きることだと考え、不正に逃亡することを拒んで死刑を受け入れました。「名誉のため」というよりは、自らの哲学(魂への配慮)を実践した結果です。
②【正】
アリストテレスは、倫理的徳(勇気や節制など)は、正しい行為を繰り返し習慣づけることによって身につくと考えました。その際、過剰と不足という両極端を避け、中庸(メソテース)を選択することが重要だと説いています。
③【誤】
孟子は、人間が生まれながらに持つ道徳性の芽生えである「四端(惻隠・羞悪・辞譲・是非の心)」を拡充することで、仁・義・礼・智の「四徳」が完成されると説きました。四徳を育てて四端を身につけるのではなく、順序が逆です。
④【誤】
王陽明は、知と行は本来一体であるとする「知行合一」を説きました。また、善悪是非を判断する心の本体(良知)を明らかにする「致良知」を主張しました。自分以外の事物に関する知識を学ぶ(格物致知)ことを重視したのは朱子であり、王陽明はそれを批判しました。
問7:正解⑤
<問題要旨>
旧約聖書における神とイスラエルの民との「契約」の概念を、預言者の活動と関連付けて理解する問題です。預言者エレミヤの時代背景と、契約違反に対する罰という考え方がポイントになります。
<選択肢>
①【誤】
a:アブラハムはイスラエルの民の始祖であり、神と契約を結んだ最初の人物ですが、この預言者ではありません。b:内容は正しいです。
②【誤】
a:アブラハムではありません。b:「贖い」ではなく、契約を破ったことに対する「罰」として苦難が与えられるという文脈です。
③【誤】
a:モーセはエジプト脱出を導き、シナイ山で神から十戒を授かった指導者ですが、この預言者ではありません。b:内容は正しいです。
④【誤】
a:モーセではありません。b:「贖い」ではなく「罰」です。
⑤【正】
a:エレミヤは、南王国ユダの滅亡とバビロン捕囚という国難の時代に活動した預言者です。資料の内容は、神との契約を破った民への裁きと国の滅亡を預言するエレミヤの言葉として合致します。b:イスラエルの民が神との契約に背いて偶像崇拝などに走ったため、その罰として王国の滅亡やバビロン捕囚という「災い」がもたらされた、と理解されています。
⑥【誤】
b:「贖い」ではなく「罰」です。
問8:正解③
<問題要旨>
イスラームにおける「啓典の民」(ユダヤ教徒・キリスト教徒)への対応について、クルアーンの記述やムハンマドの伝記からその思想的背景を読み解く問題です。
<選択肢>
①【誤】
cの「信仰に基づいた生活をしている」という共通点の指摘が、やや漠然としています。また、bの「ムスリム共同体の一員となる」という表現は、メディナ憲章における政治的な共同体を指すともとれますが、宗教集団としては別個の存在でした。
②【誤】
cの「ユダヤ教の神と共にアッラーも信仰している」という記述が誤りです。ユダヤ教徒はヤハウェ(エホバ)を唯一神としており、アッラーを信仰しているわけではありません。イスラーム側が、ユダヤ教の神もアッラーと同じ唯一神であると解釈しています。
③【正】
a:旧約・新約聖書は、アッラーからの啓示を記した書物ですが、クルアーンが最終かつ完全な啓示であるため「クルアーンと同等ではない」とするのがイスラームの正確な理解です。b:資料2(省略されていますが、メディナ憲章の内容と推測されます)では、ユダヤ教徒が独自の宗教共同体を維持することが認められていました。c:「神の言葉を信じ、その教義を守っている」という点は、同じ啓典宗教としての共通点として的確な表現です。
④【誤】
aの「クルアーンと同等の啓典」という記述が誤りです。クルアーンはイスラームにおいて絶対的な位置を占めています。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
江戸時代の思想家、鈴木正三の職業倫理についての理解を問う問題です。彼の「職分仏行説」の核心を捉えているかがポイントになります。
<選択肢>
①【誤】
鈴木正三は、家職に励むこと「そのもの」が仏道修行であると説きました(職分仏行説)。「余暇を活用して」仏道修行をするという考え方ではありません。
②【誤】
鈴木正三は、士農工商の身分秩序を否定せず、むしろそれを所与のものとして受け入れた上で、各身分がそれぞれの職務に専念することの重要性を説きました。
③【正】
鈴木正三は、武士なら武士の、農民なら農民の、商人なら商人の務め(職分)を一心に励むことが、すなわち仏の道の実践(仏行)であると説きました。これを「職分仏行説」といいます。
④【誤】
鈴木正三は、武士に対しても、主君への忠誠といった武士の職分を全うすることが仏道修行であると説いており、仏道修行を優先させるべきとは論じていません。
問2:正解④
<問題要旨>
国学者、本居宣長の思想、特に「もののあはれ」についての理解を問う問題です。彼の古道論や和歌論の要点を正確に把握している必要があります。
<選択肢>
①【誤】
宣長が理想としたのは、感情を抑制せず、ありのままに表出した古代人の姿であり、それを「ますらをぶり(益荒男ぶり)」や「たをやめぶり(手弱女ぶり)」と評しました。「感情を抑制しながら」という部分が誤りです。
②【誤】
宣長は、儒教や仏教的な道徳(漢意)による解釈を排し、古代人の心をありのままに理解しようとしました。『古事記』も道理や理屈で解釈するのではなく、素直に読み解くべきだと考えました。
③【誤】
宣長は、仏教や儒教が伝来する以前の日本固有の精神(古道)を理想としました。天皇が仏に祈ってきたことを日本の優れた点として主張するのは、彼の思想とは異なります。
④【正】
宣長は、物事に接した時に心で感じ、感動するありのままの心を「真心」と呼び、それが深くしみじみと現れたものが「もののあはれ」であるとしました。この「もののあはれを知る心」を持つ人だけが、他者の感情にも共感できると考えました。
問3:正解④
<問題要旨>
天台宗の開祖・最澄の思想と、彼が目指した社会のあり方を資料から読み解く問題です。大乗仏教の理念、特に大乗戒の重要性についての彼の主張を理解することが鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
最澄は、災厄を防ぐ力を持つのは、利他の精神で人々のために尽くす「菩薩」であると主張しています。「仏だけである」とした点が誤りです。
②【誤】
最澄が『法華経』を重視したのは正しいですが、「唱題の行」(南無妙法蓮華経と唱えること)を重視したのは、後の時代の日蓮です。
③【誤】
最澄は、資料中で大乗菩薩戒が「出家にも在家にも一貫して用いられるべきもの」と述べており、国の宝となる菩薩の役割を「出家した僧侶だけが担うべき」とは考えていません。
④【正】
最澄は、奈良の旧仏教が依拠していた小乗戒ではなく、大乗の精神に基づく大乗菩薩戒のみによって僧侶となる独自の制度(大乗戒壇の設立)を目指しました。資料にも「出家の菩薩も在家の菩薩も区別はなく」「出家にも在家にも一貫して用いられるべき」とあり、大乗戒が僧侶だけでなく在家者も守るべきものだと説いていることがわかります。
問4:正解⑤
<問題要旨>
日本における他界観に関する神話や民俗学の学説についての正誤を判断する問題です。記紀神話、柳田国男、折口信夫の説を正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
ア【誤】
記紀神話において、スサノヲの乱暴な行いを疑ったアマテラスに対し、スサノヲが自らの心の潔白(清明心)を示すために誓約(うけい)を行いました。アマテラスが禊を行ったのは、黄泉国から帰還したイザナキが穢れを祓う場面などです。
イ【正】
柳田国男は、日本人の死生観について、死者の霊は遠い世界へ行くのではなく、山の高みなど村落の近くにとどまり、時を経て祖先神(氏神)となって子孫を見守る存在になると考えました。
ウ【正】
折口信夫は、海の彼方の常世国(とこよのくに)から、定期的に村を訪れて人々に富や幸福(豊穣)をもたらす来訪神(まれびと)への信仰が、日本の神の原型の一つであると論じました。
以上のことから、アが誤り、イとウが正しいので、⑤が正解となります。
問5:正解②
<問題要旨>
日本の浄土信仰の展開に関わった僧侶たちの教えや活動についての理解を問う問題です。一遍、法然、源信、蓮如それぞれの思想の核心と違いを区別する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
一遍は、信・不信を問わず、また浄・不浄を嫌わず、ただ名号を称えれば誰でも往生できると説き、念仏札を配りました。しかし、「仏の救いを信じさえすれば」という部分は、むしろ親鸞の思想に近いです。一遍の思想は、信じる心さえも阿弥陀仏の働きとする、より徹底した他力思想でした。
②【正】
法然は、釈迦の死後、時代が下るにつれて仏の教えが形骸化していく末法思想に基づき、現代は教え(教)と実践(行)は残っているが、悟り(証)を得ることは困難な時代(像法末)であると考えました。このような時代には、自力による厳しい修行(聖道門)ではなく、阿弥陀仏の本願を信じ、念仏を称えることで救われる他力の道(浄土門)こそがふさわしいと説きました。
③【誤】
源信は『往生要集』で、地獄の恐ろしさと極楽浄土の素晴らしさを詳細に描き、極楽往生を願う方法として、心に仏や浄土を思い浮かべる観想念仏と、口で「南無阿弥陀仏」と称える口称念仏の両方を勧めました。口称念仏を否定してはいません。
④【誤】
蓮如は、浄土真宗の教えを分かりやすい言葉で説いた手紙である「御文(御文章)」を著し、民衆への布教に努めました。御文は、難解な教義の注解書ではなく、信仰の要点を平易に説くためのものです。
問6:正解③
<問題要旨>
白樺派の文学者・武者小路実篤の思想と、彼が描いた理想的社会の姿を資料から読み解く問題です。
<選択肢>
武者小路実篤は、トルストイの人道主義に深く影響を受け、個人の自我の肯定と調和を理想としました。その理念を実践するため、宮崎県に共同生活の場である「新しき村」を建設しました。したがって、説明は「イ」が正しいです。「ア」のトルストイ批判や、「ウ」のキリスト教・急進的社会主義は彼の思想とは異なります。
次に空欄aに入る記述について、武者小路は個性の尊重と発揮を重視したため、「エ」の「自己の趣味、自己の正しき要求、天職、個性を発揮出来るように」という記述が適切です。「オ」の「個性の発露を控え、全体の調和に資する」という考え方は、彼の思想とは逆です。
したがって、正しい組合せは「イ」と「エ」になります。
問7:正解③
<問題要旨>
江戸時代の儒学者、荻生徂徠の思想、特に彼が提唱した古文辞学と「先王の道」についての理解を問う問題です。資料文の読解と、徂徠の思想的特徴の把握が求められます。
<選択肢>
①【誤】
荻生徂徠は、朱子学や伊藤仁斎の古義学を批判し、孔子以前の古代中国の文献(古文辞)を直接研究することで、先王の道を明らかにしようとしました。孟子が説いた内面道徳の修養とは異なるアプローチです。
②【誤】
徂徠は、先王の道が天下を治めるための政治制度(礼楽刑政)であるとした点は正しいですが、資料では道が「先王たちが創造したもの」であり「天地自然に備わっているものではない」と明記されています。「天地自然に備わった道を発見した」という記述は誤りです。
③【正】
徂徠は、道とは先王が天下を安んずるために作り出した政治・社会制度(礼楽刑政)であると主張しました。そして、人々がその道に従うことで社会の秩序が保たれる(安天下)と考えました。資料にも、道は「多くの聖人の努力によって完成された」ものであり、孔子もそれを「学んでから道を知った」とあり、この選択肢の説明と合致しています。
④【誤】
徂徠は、学問(古文辞学)によって先王の道を学び、それを政治に活かす経世済民の学を説きましたが、「全ての人々が聖人となり」といった主張はしていません。
問8:正解⑧
<問題要旨>
桑原武夫のエッセイを題材に、「ユートピア」に対する近代的な考え方を読み解き、それを具体的な歴史的事例と結びつける問題です。文章の論理展開を正確に追う読解力が求められます。
<選択肢>
a:筆者は、ユートピアを「どこにもない場所」として空想するのではなく、世界人権宣言のような理想を、現実の努力によって一歩ずつ実現していくべき対象と捉え直しています。これは、実現不可能と諦めるのでも、空想するのでもなく、理想への向き合い方そのものを問い直す姿勢です。したがって、「ウ」が筆者の主張を最も的確に要約しています。
b:筆者の主張は「理想の実現に向けて堅実な努力を続けていくべき」というものです。この実例としてふさわしいのは、社会の不正や因習に対して、理想(男女同権や女性の解放)を掲げて変革を訴え、行動した事例です。「オ」の岸田俊子や景山英子らによる自由民権運動での活動は、まさにこの文脈に合致します。「エ」の北一輝は国家社会主義的な改造を唱え、「カ」の田山花袋は現実をありのままに描く自然主義であり、筆者の言う「堅実な努力」とは方向性が異なります。
したがって、正しい組合せは「ウ」と「オ」になります。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
16世紀フランスの思想家モンテーニュの思想的特徴について、その正誤を判断する問題です。懐疑主義、モラリストとしての側面を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
ア【正】
モンテーニュは古代ギリシアの懐疑主義(セクシスの思想など)に学び、独断的な判断を保留する態度(エポケー)を重視しました。彼は『エセー(随想録)』の中で、自らの経験を省察し、絶えず自己を探求する謙虚な生き方を説きました。
イ【誤】
「われ何を知るか(ク・セ・ジュ)」はモンテーニュの言葉であり、自己反省を促すものですが、「決定的回心を経て、キリスト教を擁護する著作の完成に努めた」のは、17世紀の思想家パスカルです。
ウ【誤】
モンテーニュは、宗教戦争の不寛容や狂信を批判しましたが、人間性の探求を内面的に行った思想家であり、「モラリスト」とは呼ばれるものの、「厳格な道徳に基づく政治の必要性」を積極的に訴え続けたわけではありません。政治的な改革よりも、個人の生き方を問う姿勢が中心でした。
したがって、アのみが正しく、④が正解となります。
問2:正解①
<問題要旨>
ドイツの合理論哲学者ライプニッツの思想についての説明として、最も適当なものを選ぶ問題です。彼の中心概念であるモナド論や予定調和説の理解が問われます。
<選択肢>
①【正】
ライプニッツは、宇宙は単一の実体であるモナドの集合体であり、モナド同士は直接相互に影響を及ぼしあうことはないですが(窓なきモナド)、神が宇宙を創造する際に、全てのモナドの運動や変化が全体として調和するようにあらかじめ定めていると考えました。これを予定調和説と呼びます。
②【誤】
事物を「永遠の相のもとに見る」ことによって神を認識できると主張したのは、ライプニッツと同じく合理論の哲学者であるスピノザです。
③【誤】
自然は神そのものの現れであるとする汎神論を説いたのは、スピノザです。
④【誤】
ライプニッツは、世界を構成する実体をモナドと呼びましたが、モナドは空間的な広がりを持たない、精神的な(表象能力を持つ)実体であると考えました。「空間的実体」という記述が誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
イギリス経験論の哲学者ロックの思想について、不適切な説明を選ぶ問題です。彼の認識論、社会契約説に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
ロックは、デカルトらの合理論(生得観念説)を批判し、生まれたばかりの人間の心は白紙(タブラ・ラサ)のようなもので、全ての知識は経験に由来すると主張しました。これは正しい説明です。
②【誤】
「存在するとは知覚されることである」と述べ、実体として存在するのは精神だけであるとする観念論(非物質論)を主張したのは、アイルランドの哲学者バークリーです。ロックは、精神の外に客観的な物体世界が存在することを認めていました。
③【正】
ロックは、人々が自然状態において持つ生命・自由・財産といった所有権(プロパティ)を、より確実に保障するために、相互の契約によって国家を設立すると考えました。これは正しい説明です。
④【正】
ロックは、政府が人々の信託に反して権力を濫用し、所有権を侵害する場合には、人民は政府に抵抗し、新たな政府を樹立する権利(抵抗権・革命権)を持つと主張しました。これは正しい説明です。
問4:正解④
<問題要旨>
カントの倫理思想における、人間と動物の扱いの違いについて、資料を基に理解する問題です。彼の義務論、特に人格を「目的」として扱う考え方が鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
カントは理論理性(自然を認識する能力)と実践理性(道徳法則を意志する能力)を明確に区別しました。また、資料によれば、動物に対する義務は人間自身に対する「間接的な」義務であり、「直接的な」義務ではありません。
②【誤】
カントは、理性的存在者である人間は、たんに手段としてだけでなく、同時に目的として扱われなければならないと説きました。資料でも、動物を虐待することは、人間自身の道徳性を損なうため避けるべきだと述べており、「どのように利用したとしても問題はない」わけではありません。
③【誤】
カントは、無条件に善いものは、ただ「善意志」のみであると主張しました。「数ある無条件に善いものの一つとして」という記述が誤りです。
④【正】
カントは、自らが立てた普遍的な道徳法則に自ら従うことを「意志の自律」と呼びました。資料では、動物は理性を欠き、自己を意識しないため「目的」とはなりえませんが、動物を残虐に扱うことは、人間が自己自身に対して持つ義務(=道徳性を鈍らせないようにする義務)に背くことになると論じています。これは、動物への配慮が、結果的に人間自身の義務に適うことになるという主張であり、選択肢の説明と合致しています。
問5:正解②
<問題要旨>
19世紀の進化論とその社会思想への応用に関する理解を問う問題です。ダーウィンとスペンサーの思想を正確に区別できるかがポイントになります。
<選択肢>
①【誤】
ダーウィンの自然選択説では、生物に生じる変異はランダム(偶然)であり、その中で環境に適したものが生き残り、子孫を残す(自然選択)と考えます。「生物が自ら環境に適応するよう変異していく」という部分は、獲得形質が遺伝するとしたラマルクの用不用説に近い考え方です。
②【正】
スペンサーは、ダーウィンの進化論を社会に適用し、自由競争を勝ち抜いた「適者」が生き残ることで社会は自然に進歩すると考えました(社会進化論)。そのため、国家が貧困層の救済などで市場に介入すること(弱者保護)は、社会の自然な進歩を妨げるとして批判しました。
③【誤】
ダーウィンの進化論が、キリスト教の伝統的な世界観に衝撃を与えたのは事実ですが、その世界観は「機械論的自然観」とは異なります。機械論的自然観は、デカルトに代表されるような、自然を法則に従って動く精巧な機械とみなす近代科学の考え方です。キリスト教の世界観は、神による天地創造と種の不変を前提とします。
④【誤】
スペンサーは、社会が闘争を中心とする「軍事型社会」から、自由な経済活動を中心とする「産業型社会」へと進化していくと考えました。この選択肢の記述は逆になっています。
問6:正解③
<問題要旨>
ハイデガーの哲学における人間(現存在)と動物の存在様式の違いを、資料(省略されていますが内容は推測可能です)を基に理解する問題です。彼の専門用語の正確な理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
ハイデガーは、人間が意識や選択とは無関係に、既に特定の歴史的・社会的な状況のうちに存在していることを「被投性」と名付けました。資料の趣旨(動物は衝動にとらわれているが、人間は存在者を存在者として関わることができる)から考えると、動物は衝動によって振る舞うため、あるものを「そのものとして把握している」とは言えません。
②【誤】
「対自存在」は、自己を対象化し、未来に向かって自己を形成していく人間のあり方を指すサルトルの用語です。ハイデガーの用語ではありません。
③【正】
ハイデガーは、自らの「存在」そのものに関心を持ち、その意味を問うことができる唯一の存在者を人間、すなわち「現存在(ダーザイン)」と呼びました。動物は周囲の刺激に衝動的に反応し、物事にとらわれる(本能に束縛される)のに対し、人間(現存在)は、物事をたんなる刺激としてではなく、「存在するもの」として認識し、それに関わることができます(世界内存在)。この選択肢は、ハイデガーの思想を正しく説明しています。
④【誤】
「限界状況」は、死・苦・罪責・争いといった、人間の力ではどうすることもできない壁のような状況を指すヤスパースの用語です。ハイデガーの用語ではありません。
問7:正解①
<問題要旨>
現象学の影響を受けた思想家についての説明のうち、適当なものを選ぶ問題です。ボーヴォワール、九鬼周造、サルトルの思想の要点を把握しているかが問われます。
<選択肢>
ア【正】
ボーヴォワールは、実存主義の立場から「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」と述べ、女性が社会的に作られた「女性らしさ」の役割から解放され、自らの生き方を主体的に選択すべきだと主張しました。彼女は現象学、特にサルトルの実存主義から強い影響を受けています。
イ【誤】
「間柄的存在」として人間を捉え、西洋と日本の思想を融合させようとしたのは、和辻哲郎です。九鬼周造は「いき」の構造などを分析した哲学者として知られています。
ウ【誤】
サルトルは、人間は自由な選択を運命づけられており(自由の刑)、その選択には全人類に対する責任が伴う(アンガージュマン)と説きました。他者と責任を分け合って重荷を軽減できるとは考えず、むしろ個人の選択の重さを強調しました。
したがって、正しいのはアのみです。
問8:正解④
<問題要旨>
ベンサムの功利主義的な動物観を資料から読み解き、それが現代の動物解放論に与えた影響や、倫理的な線引きの問題について考察する問題です。
<選択肢>
a:資料でベンサムは、人間と動物を区別する基準として、理性や会話能力を挙げることに疑問を呈しています。彼が最終的に重視する基準は「問題となるのは、…動物が苦しむことができるかということなのである」という一文に集約されています。つまり、快楽や苦痛を感じる能力(快苦感受能力)こそが、倫理的配慮の対象となるかどうかの境界線だと主張しています。したがって「④ 会話の能力の有無で…なく、苦痛を感じることができるかどうかを重視すべきである」が最も的確な要約です。
b:D君は、ベンサムの基準に共感しつつも、新たな線引きが新たな問題を生む可能性に気づき、「倫理では配慮の必要な対象とそうでないものとを分ける基準が必要なのか」と問い、最終的には「人間以外の動物も視野に入れた倫理」の必要性を述べています。この文脈に合うのは「④ 何をどこまで倫理的に配慮するのかという点にも注意して、人間以外の動物も視野に入れた倫理を考えていかなければならない」という、配慮の範囲や基準そのものを問い続ける姿勢を示す記述です。
したがって、正しい組合せは④となります。
第4問
問1:正解⑦
<問題要旨>
SNSへの投稿内容に関する日米比較調査の資料(図と文章)を正確に読み解き、そこから導かれる考察を完成させる問題です。データの解釈能力と論理的思考力が問われます。
<選択肢>
a:図の横軸(出現率)を見ると、アメリカ(□)ではPH(ポジティブで強い)の出現率が最も高いとは言えず、NL(ネガティブで穏やか)が最も高いです。一方、日本(○)ではPL(ポジティブで穏やか)とNL(ネガティブで穏やか)という「穏やか」な投稿が、「強い」投稿(PH, NH)よりも出現率が高い傾向にあります。また、アメリカではポジティブ(PH, PL)がネガティブ(NH, NL)より高いとは言えません。したがって、「イ」の「日本では強い感情表現よりも穏やかな感情表現を含む投稿の出現率が高い」という部分が、図から読み取れる正しい記述です。
b:影響度の定義は「そのタイプの感情表現を含む他者の投稿を見た際に、投稿者も同様の感情表現を含む投稿をする頻度が高まる度合い」です。図の縦軸(影響度)を見ると、アメリカ(□)で最も影響度が高いのはNH(ネガティブで強い)です。したがって、他人のネガティブで強い投稿を見た際に「エ それと同様のネガティブで強い感情表現を含む投稿」をする頻度が最も高まりやすいと言えます。
c:日米両国に共通する点を探します。図を見ると、日米ともに、最も出現率が高いNL(日)やNL/PL(米)の影響度は低く、最も出現率が低いNH(日)やPH(米)の影響度が高い傾向にあります。つまり、「オ 最も出現率が高い投稿の影響度が最も低く、最も出現率が低い投稿の影響度が最も高い点」が共通しています。
以上のことから、正しい組合せは「イ」-「エ」-「オ」となり、⑦が正解です。
問2:正解①
<問題要旨>
生命倫理をめぐる様々な事柄や法律についての説明のうち、適当でないものを選ぶ問題です。着床前診断、臓器移植、代理出産、パターナリズムに関する正確な知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
体外で受精させた受精卵(胚)を子宮に戻す前に、遺伝子や染色体を調べる「着床前診断(着床前遺伝学的検査)」は、重い遺伝性疾患を対象に日本でも実施されています。したがって、「体外で受精させた卵を女性の体に戻す前の段階では診断できない」という記述は誤りです。
②【正】
日本の「臓器の移植に関する法律」では、脳死は人の死とされていますが、それは本人が生前に臓器提供の意思表示をしており、かつ脳死判定がなされた場合に限られます。脳死判定の基準は「脳幹を含む脳全体の機能が不可逆的に停止」することです。これは正しい説明です。
③【正】
アメリカで起きた「ベビーM事件」では、代理母が出産後に子の引き渡しを拒否し、裁判となりました。裁判所は、子の福祉を最優先し、代理出産契約の無効を認めつつ、生物学的な父親に親権を与え、代理母には面会権を認めました。これは正しい説明です。
④【正】
パターナリズム(父権主義)とは、医師などが、本人の意思(自己決定権)よりも、本人にとっての利益を優先して意思決定を行う考え方のことです。これは正しい説明です。
問3:正解①
<問題要旨>
メディアと社会の関係についての思想や事象の説明として、最も適当なものを選ぶ問題です。マクルーハン、アンダーソンらのメディア論や、情報社会の課題に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
マクルーハンは「メディアはメッセージである」と述べ、メディアそのものが人間の感覚や思考様式を規定すると考えました。彼は、活版印刷技術(グーテンベルクの銀河系)の登場が、視覚優位の文化を生み出し、人々を共同体から切り離された個人として内面化させたと論じました。これは正しい説明です。
②【誤】
「想像の共同体」という概念を提唱したのはアンダーソンですが、彼がその形成要因として重視したのは、新聞や小説といった出版資本主義(プリント・キャピタリズム)です。彼は、同じ印刷物を読む人々が、顔も知らない互いを「国民」という共同体の一員として想像するようになったと論じました。インターネットの登場より前の時代の議論です。
③【誤】
情報通信技術(ICT)革命は、先進国と途上国の間の情報格差(デジタル・デバイド)をむしろ拡大させる側面があり、「解消された」とは言えません。また、国内においても、年齢や所得、地域などによって個人間の情報格差は存在します。
④【誤】
デジタル・データは、劣化することなく、容易かつ大量にコピー(複製)できるという特性を持ちます。そのため、著作権などの知的財産権の侵害が大きな問題となっています。
問4:正解③
<問題要旨>
多文化共生社会における対立や課題に関連する用語の理解を問う問題です。文化摩擦、ヘイトスピーチ、エスノセントリズム、同化主義の定義を正確に把握しているかがポイントになります。
<選択肢>
①【誤】
文化摩擦は、グローバル化が進んだ現代においても、移民問題や宗教的対立など、様々な形で見られる現象であり、「ほとんど見られない」というのは誤りです。
②【誤】
ヘイトスピーチとは、人種、民族、国籍、宗教、性的指向など、特定の属性を持つ個人や集団に対して、差別を助長・扇動するような憎悪表現を指します。マイノリティがマジョリティを批判する発言を指すものではありません。
③【正】
エスノセントリズム(自民族中心主義)とは、自分たちの文化の価値観や基準を絶対的なものとみなし、それを基準に他の文化を判断、評価する態度のことです。しばしば他民族への偏見や差別、抑圧的な行動につながることがあります。
④【誤】
同化主義とは、ある社会のマイノリティ(少数派)に対して、マジョリティ(多数派)の文化や生活様式を受け入れ、同化することを求める考え方です。マジョリティがマイノリティの文化に同化するのではなく、その逆です。
問5:正解①
<問題要旨>
青年期の発達課題や心理的特徴に関する説明として、最も適当なものを選ぶ問題です。役割実験、反抗期、若者文化、発達加速現象といった用語の正確な理解が求められます。
<選択肢>
①【正】
エリクソンが提唱した概念で、青年は社会的な責任を一時的に免除されたモラトリアムの期間に、様々な役割や活動を試みます(役割実験)。この試行錯誤を通して、自分は何者であるかという問いに答え(自我同一性の確立)、人格を形成していきます。これは正しい説明です。
②【誤】
親や大人に対して反抗的な態度をとるようになるのは、青年期に現れる「第二反抗期」の特徴です。「第一反抗期」は、自我が芽生える幼児期(2~3歳頃)に見られます。
③【誤】
若者文化(ユース・カルチャー)は、青年たちが大人社会の既成文化に対抗し、あるいはそれを批判・風刺する中で、仲間うちで共有される独自の文化(対抗文化=カウンター・カルチャー)として形成される側面を持ちます。「優れた部分を積極的に取り入れてさらに発展させる」とは限りません。
④【誤】
発達加速現象により、身体的な成熟は早まっていますが、社会人としての自立は遅くなる傾向にあります(心理社会的モラトリアムの長期化)。そのため、青年期の終了時期は早まるどころか、むしろ長期化しています。
問6:正解②
<問題要旨>
リップマンの『世論』からの資料を基に、「ステレオタイプ」の機能や性質について正しく理解しているか問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
資料(省略されていますがリップマンの議論)によれば、ステレオタイプは「我々の文化の中で既に与えられている」ものであり、個人が独自に作り上げるというよりは、社会や文化の中で共有されているものです。
イ【正】
リップマンは、複雑な現実世界を毎回いちから理解しようとすることは非常に骨が折れるため、人々はステレオタイプという簡略化された「決まりきった型」を用いて世界を認識すると考えました。これにより、認識の労力を節約できます。
ウ【誤】
資料では、ステレオタイプが認識の助けになる側面を認めつつも、それが現実を歪め、偏見につながる危険性を示唆しています。「互いに尊厳を配慮した付き合いを可能にする」のは、ステレオタイプに依拠するのではなく、むしろそれを乗り越えようとする姿勢です。
したがって、正しいのはイのみです。
問7:正解④
<問題要旨>
パーソナリティの理解の仕方の一つである「類型論」についての説明として、最も適当なものを選ぶ問題です。類型論の特徴と、他の理論(特性論)との違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
関心の方向が自己の内面に向かう「内向」と、外部に向かう「外向」によって性格を類型化したのは、ユングです。シュプランガーは、人々がどのような価値(理論的・経済的・審美的・宗教的・社会的・権力的)を重視するかに基づいて性格を6つの類型に分けました。
②【誤】
オルポートは、パーソナリティを少数の類型に分類する類型論ではなく、個人が持つ様々な「特性(トレイト)」の組み合わせによって理解しようとする「特性論」の代表的な論者です。
③【誤】
この説明は、複数の特性の程度によってパーソナリティを多次元的に捉えようとする「特性論」の考え方です。類型論は、代表的なタイプに個人を当てはめて全体像を把握しようとする考え方です。
④【正】
類型論は、いくつかの典型的なタイプ(例:内向型/外向型)を設定し、個人がどのタイプに当てはまるかを考えます。これにより、性格の全体像を直感的に把握しやすく、異なるタイプ間の比較が容易であるという利点があります。一方で、個人を無理やり型にはめてしまい、その人の多面性や個性を捉えきれないという欠点も指摘されています。
問8:正解④
<問題要旨>
現代の政治哲学における個人と社会(共同体)の関係をめぐる二つの対照的な立場を、代表的な思想家と結びつける問題です。リバタリアニズムとコミュニタリアニズムの思想を区別できるかが問われます。
<選択肢>
ア:個人の自由と権利を最優先し、国家の役割を最小限(夜警国家)にとどめるべきだと主張するのは、リバタリアニズムの立場です。特に、個人の財産権を絶対的なものとみなし、富の再分配を目的とした課税を「強制労働」に等しいとして否定したのは、ノージックです。
イ:近代の自由主義が、社会や共同体から切り離された孤立した個人を前提にしていると批判し、人間は特定の共同体の歴史や伝統の中で人格を形成し、その共同体が善しとするもの(共通善)を追求する中でよく生きることができると主張するのは、コミュニタリアニズム(共同体主義)の立場です。その代表的な論者がマッキンタイアです。
したがって、正しい組合せは「ア ノージック」「イ マッキンタイア」となります。
問9:正解②
<問題要旨>
友人との対話を通して、インターネットにおける発信者の責任についての考えを深めた人物の投稿を完成させる問題です。会話の流れを正確に踏まえ、登場人物EとFの考えの変化や共有点を読み解く必要があります。
<選択肢>
a:会話の後半で、友人Eは「相手の人格を尊重して、真摯に向き合う」「きちんと相手に応答するような姿勢を持っておく必要がある」と主張しています。Fも最終的にその考えに納得しています。これを要約しているのは「ア インターネット上でも、書き込みの対象となる相手を尊重し、応答の構えを持っておくことが必要だ」です。
b:会話の中で、Fは当初「受け取る人のリテラシーが重要」と主張していましたが、Eとの対話を経て「発信する人の問題でもあるか」と考えるようになりました。両者が当初から共有していたわけではありませんが、最終的に共有に至った考えは何かを考えます。会話の中でEは「偏見が増幅されていて、それにステレオタイプも関与している」と問題提起し、Fもステレオタイプの危険性を認識しています。したがって「エ インターネットは、自由に意見を発信できるメディアではあるけれど、自分の書き込みが、ステレオタイプとして受け取られ、偏見を助長する可能性があることに、注意しておくべきだという考え方」は、両者が共有できる認識と言えます。「ウ」のステレオタイプを一切用いない、や「オ」の受け取る人のリテラシーだけで解決するという考えは、会話の内容と一致しません。
したがって、正しい組合せは「ア」と「エ」になります。