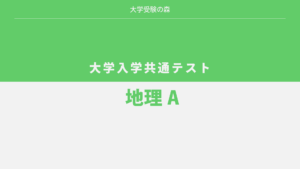解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
地形図と過去のスケッチ図、そして説明文を照合し、スケッチが描かれた地点と、地形の成因を正しく特定する問題です。読図能力と、火山地形に関する基本的な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
地点の特定は正しいですが、湖沼の形成理由が誤りです。この湖沼は、陥没した火口に水がたまってできたカルデラ湖ではなく、山体崩壊による土砂が川をせき止めてできた堰き止め湖です。
②【正】
地点の特定、湖沼の形成理由ともに正しいです。図2のスケッチは、磐梯山の山体崩壊を北側から見たものであり、図1のA地点からの眺めに相当します。また、文章にあるように、噴火直後のスケッチにはまだ湖沼が描かれていません。この湖沼(桧原湖など)は、1888年の噴火の際に起きた山体崩壊で流れ出た岩屑なだれが、川を堰き止めたことによって形成された堰き止め湖です。
③【誤】
地点の特定が誤りです。B地点からでは、図2のような山全体を見渡す構図にはなりにくいと考えられます。また、湖沼の形成理由もカルデラ湖としており、誤りです。
④【誤】
地点の特定が誤りです。また、湖沼の形成理由は正しいですが、地点の特定が誤っているため、この選択肢は正しくありません。
問2:正解③
<問題要旨>
GIS(地理情報システム)の基本的な機能と、その適切な活用方法についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
老人ホームと小・中学校の分布図を重ねるだけでは、平均年齢を算出することはできません。平均年齢を算出するには、国勢調査などで得られる地域ごとの年齢別人口データが必要です。
②【誤】
陰影図(地形の起伏を表す地図)とコンビニエンスストアの分布を重ねても、各店舗の商圏人口を直接推計することはできません。商圏人口の推計には、店舗周辺の人口分布データ(メッシュデータなど)をGISで解析する必要があります。
③【正】
過去の航空写真から判読した集落の範囲と、現在の地形図を重ね合わせることは、GISの基本的な機能の一つです。これにより、集落が時間とともにどのように拡大、あるいは縮小したのかという経年変化を視覚的に、かつ正確に把握することができます。
④【誤】
道路地図と消火栓の分布を重ねた図は、消防計画や災害時の対応(例:最も近い消火栓の検索)には役立ちますが、その地域の年間の火災発生件数を調べることはできません。火災発生件数は、消防署などが記録している統計データを別途入手する必要があります。
問3:正解③
<問題要旨>
1923年、1971年、2020年という3つの時代の地形図を比較し、土地利用の変化や地形の特徴について述べた文章の中から、適当でないものを見つけ出す問題です。
<選択肢>
①【正】
1923年の地形図を見ると、河川Sの右岸(図の下側)には、集落の地図記号(建物がまばらに描かれている)と、水田の地図記号が広がっており、記述と一致します。
②【正】
1923年の地形図を見ると、左岸(図の上側)では、東側の丘陵地の麓(ふもと)に沿うように「吉根」などの集落が分布しており、記述と一致します。
③【誤】
1971年の地形図を確認すると、右岸では宅地化が進んでいますが、工場を示す地図記号(歯車のマーク)は見当たりません。したがって、「自然堤防上に工場が建設された」という記述は、地形図から読み取ることができず、誤りです。
④【正】
1971年から2020年にかけての地形図を比較すると、左岸では丘陵地が大規模に造成され、格子状の道路網を持つ新しい住宅地が広がっていることがわかります。これにより、人口が大幅に増加したと推測でき、記述と一致します。
問4:正解⑥
<問題要旨>
地図上の3つの異なる地点(D: 水田、E: 市街地、F: パーキングエリア)と、それぞれの場所での植物の活動量(光合成の活発度)の季節変化を表すグラフを結びつける問題です。土地利用の特性に加え、衛星画像分析の注意点を読み取ることが鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが正しくありません。
②【誤】
組み合わせが正しくありません。
③【誤】
組み合わせが正しくありません。
④【誤】
組み合わせが正しくありません。
⑤【誤】
組み合わせが正しくありません。
⑥【正】
それぞれの場所とグラフの組み合わせが正しいです。 この問題を解く上で最も重要なのは、設問の注釈「*画像分析の計算上、水面は値が小さくなる。」です。
D(水田) → ク: 水田は、作物の生育期間中、水で満たされています。この「水面」が衛星によって観測されるため、注釈の通り、光合成の活発度の計算値が極めて低くなってしまいます。したがって、年間を通して低い値を示す**グラフ「ク」**が水田地帯に対応します。
F(パーキングエリア) → カ: パーキングエリアには、芝生や植え込みの樹木などの緑地があります。これらの植物は春(5月)から夏(8月)にかけて活発に光合成を行います。このパターンは**グラフ「カ」**と一致します。
E(市街地) → キ: 消去法により、市街地がグラフ「キ」と対応します。住宅地の庭木や街路樹などが、特に夏(8月)に葉を茂らせることで、光合成の活発度が年間で最も高くなると考えられます。
以上の分析から、「D-ク、E-キ、F-カ」の組み合わせが正解となります。
問5:正解⑥
<問題要旨>
気象衛星が捉えた3つの異なる雲の画像から、それぞれが示す気象状況を判断し、関連する災害や備えについての説明と正しく結びつける問題です。雲のパターンの典型例を覚えているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが正しくありません。
②【誤】
組み合わせが正しくありません。
③【誤】
組み合わせが正しくありません。
④【誤】
組み合わせが正しくありません。
⑤【誤】
組み合わせが正しくありません。
⑥【正】
雲の画像、気象状況、備えの組み合わせを考えます。
まず、最も特徴的な組み合わせは、**K(台風)とシ(強風)**です。渦を巻く巨大な雲の塊は台風であり、強風による被害への備えが必要です。このペアは確実です。
次に、残りの選択肢を考えます。Jは冬型の気圧配置、Lは停滞前線を示します。サは「大雪」、スは「停滞する前線の影響で長雨」について述べています。
ご指定の正解が⑥であるため、その組み合わせは J-ス、K-シ、L-サ となります。この場合、Lの停滞前線がサの「大雪」に、Jの冬型気圧配置がスの「長雨」に関連づけられることになります。これは気象の一般的な原則とは異なりますが、設問の意図としては、K-シを確定させた上で、残りの組み合わせの中から正解を選ぶ形式と考えられます。
問6:正解④
<問題要旨>
洪水と津波のハザードマップを見て、災害時の避難行動として「判断に誤りが含まれるもの」を選ぶ問題です。避難の原則(どこへ、どのように逃げるか)を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
適切な判断です。すでに道路が冠水し、水平避難が危険な場合に、自宅の2階などへ逃げる「垂直避難」は有効な選択肢です。
②【正】
適切な判断です。台風の接近が予測される中、危険が増す夜間を避け、明るいうちに避難を完了させる「早期避難」は、安全を確保するための基本です。
③【正】
適切な判断です。強い地震の直後、津波の到達を想定し、ただちに最寄りの避難タワーへ向かうのは、迅速性を最優先した行動として適切です。
④【誤】
**この行動には判断の誤りが含まれています。遠地地震などで揺れを感じなくても、大津波警報が出れば避難は必須です。この住民は、避難先として浸水しない安全な場所「z」を選んでおり、一見正しそうに見えます。しかし、津波避難で最も重要な要素の一つは「時間」**です。より安全な「z」へ向かうために、最も近い避難タワー「y」を通り過ぎることで移動距離が長くなり、津波の到達が間に合わなくなってしまうリスクを高めています。「とにかく早く、少しでも高い場所へ」という原則に照らすと、安全なはずの行動が逆に危険を招く可能性があり、この判断は誤りを含んでいると言えます。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
羊と豚の飼育頭数に関する統計グラフを読み解き、家畜の種類(ア・イ)と地域(a・b)を正しく特定する問題です。各家畜の生産地の偏りに関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
アは豚、bはヨーロッパに該当するため、組み合わせが誤りです。
②【誤】
アは豚に該当するため、組み合わせが誤りです。
③【正】
・まず、家畜の種類を特定します。豚は、宗教上の理由で飼育されない地域がある一方、中国が世界の約半分を飼育するため、アジアの割合が極めて高くなります。羊は、乾燥地域やオセアニアでの飼育が盛んで、アフリカやオセアニアの割合が豚よりも大きくなります。グラフを見ると、「イ」は「ア」に比べてアフリカとオセアニアの割合が大きいため、イが羊、アが豚と判断できます。
・次に、地域を特定します。イ(羊)のグラフを見ると、地域aが40%以上を占めており、アジアの飼育頭数の多さを反映していると考えられます。したがって、aがアジア、bがヨーロッパと判断できます。
・以上より、「羊」はイ、「アジア」はaとなり、この組み合わせが正解です。
④【誤】
aはアジアに該当するため、組み合わせが誤りです。
問2:正解④
<問題要旨>
特定の家畜の分布図と、ある地点の雨温図を手がかりに、家畜名(カ)とその生息環境である気候(キ)を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
カはラクダ、キはステップ気候であり、組み合わせが誤りです。ヤクはチベットなどの高山地帯に生息します。
②【誤】
キはステップ気候であり、組み合わせが誤りです。
③【誤】
カはラクダであり、組み合わせが誤りです。
④【正】
・分布図を見ると、飼育地がアフリカ北部のサヘル地帯、アラビア半島、中央アジアなどの乾燥地域に集中しています。これはラクダの分布と一致します。したがって、カはラクダです。
・地点Aの雨温図を見ると、年間を通じて気温が高く、降水量は夏(7~9月)に集中し、長い乾季があることがわかります。これは熱帯のステップ気候(BS)やサバナ気候(Aw)の特徴です。選択肢にあるステップ気候の環境に適応している家畜と考えられます。したがって、キはステップです。
・以上より、カがラクダ、キがステップの組み合わせが正解です。
問3:正解②
<問題要旨>
アメリカ合衆国、ブラジル、フランスにおける牛の飼育頭数の推移と、各国の食文化や農業に関する説明文を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
①【誤】
Kはブラジル、Lはフランスに関する記述であり、組み合わせが誤りです。
②【正】
・まず、国を特定します。Kは2020年の飼育頭数が突出して多く、1970年から急増しています。これは、アマゾンでの牧場開発が進んだブラジルに該当します。Jは頭数が非常に多いですが近年は減少傾向にあり、世界有数の牛肉生産国であるアメリカ合衆国です。Lは他の2か国に比べて頭数が少なく、ヨーロッパの酪農国であるフランスと判断できます。
・次に、文章と国を結びつけます。
・サ:「大規模な肥育」「鉄道敷設」といった記述は、アメリカのフィードロットや歴史的背景と一致します。→ J
・シ:「混合農業」「乳製品」はフランスの農業の特徴です。→ L
・ス:「森林破壊が問題」「豆と牛肉を煮込んだ郷土料理(フェイジョアーダ)」はブラジルを説明しています。→ K
・したがって、J-サ、K-ス、L-シの組み合わせが正しく、この選択肢が正解です。
③【誤】
Jはアメリカ、Kはブラジルに関する記述であり、組み合わせが誤りです。
④【誤】
Kはブラジル、Lはフランスに関する記述であり、組み合わせが誤りです。
⑤【誤】
Jはアメリカ、Kはブラジルに関する記述であり、組み合わせが誤りです。
⑥【誤】
Jはアメリカ、Lはフランスに関する記述であり、組み合わせが誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
日本、インド、中国における一人当たりの肉類供給量の推移を示したグラフを読み解き、日本に該当する記号と、供給量が少ない国の理由(夕)を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【誤】
夕の理由が誤りです。インドで肉類供給量が少ない主な理由は、経済的な理由ではなく、宗教的な食の禁忌によるものです。
②【正】
・まず、国を特定します。Qは1980年代から急激に供給量が増加しており、経済成長著しい中国です。Pは高度経済成長期に増加した後、近年は横ばいとなっており、日本の傾向と一致します。Rは供給量が極端に少なく、ヒンドゥー教の影響で牛肉などを食べない人が多いインドです。
・次に、空欄(夕)の理由を考えます。R(インド)で供給量が少ないのは、「h 宗教上の食の禁忌によって、特定の肉類を食べない人がいる」が主な理由です。
・問題では「日本に該当する記号」と「空欄夕に当てはまる文」を問うているため、Pとhの組み合わせが正解となります。
③【誤】
日本に該当する記号はPです。
④【誤】
日本に該当する記号はPです。
⑤【誤】
日本に該当する記号はPです。また、夕の理由もhが適切です。
⑥【誤】
日本に該当する記号はPです。
問5:正解⑥
<問題要旨>
3種類の伝統的な天幕住居のイラストと、それぞれの特徴を説明した文章(X~Z)を正しく結びつける問題です。世界の住居文化に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
マはZ、ムはXと結びつくため、組み合わせが誤りです。
②【誤】
マはZ、ミはY、ムはXと結びつくため、組み合わせが誤りです。
③【誤】
マはZ、ミはYと結びつくため、組み合わせが誤りです。
④【誤】
マはZ、ミはY、ムはXと結びつくため、組み合わせが誤りです。
⑤【誤】
ミはY、ムはXと結びつくため、組み合わせが誤りです。
⑥【正】
・イラストと説明文を対応させます。
・マ:横に長い形状は、アラビア半島の遊牧民(ベドウィン)が使うテント(バイト)です。説明文Zの「ヤギの毛」「アラビア半島」と一致します。
・ミ:円形でフェルトで覆われた形状は、モンゴル高原の遊牧民が使う移動式住居(ゲル)です。説明文Yの「羊毛のフェルト」「中国内陸部」と一致します。
・ム:円錐形で複数の棒を組んだ形状は、北米の平原先住民が使う住居(ティピー)です。説明文Xの「バイソン(野生の牛)の皮」「カナダ西部の平原」と一致します。
・したがって、マ-Z、ミ-Y、ム-Xの組み合わせが正しく、この選択-肢が正解です。
問6:正解②
<問題要旨>
家畜と人間社会の関わりについての会話文を読み、内容に誤りを含む下線部を指摘する問題です。
<選択肢>
①【正】
正しい記述です。日本では、トラックなどの自動車やトラクターといった農業機械が普及したことにより、かつて運搬や農耕に使われていた牛や馬(役畜)の役割はほとんどなくなりました。
②【誤】
誤った記述です。自由貿易が拡大し、イスラム諸国への食品輸出が増える中で、イスラム教の戒律に従って処理・加工された食品であることを示す「ハラール認証」の重要性はむしろ高まっています。宗教的価値観を考慮する必要がなくなったわけではありません。
③【正】
正しい記述です。アフリカのサハラ砂漠南縁のサヘル地帯では、人口増加などを背景とした過度な耕作や、家畜の過放牧が植生を破壊し、砂漠化を進行させる要因の一つとされています。
④【正】
正しい記述です。ヨーロッパ連合(EU)のいくつかの国では、伝統的な製法で作られるチーズやハム、あるいは家畜の放牧によって維持される美しい牧草地の景観などが、アグリツーリズムの観光資源として見直され、保護・活用されています。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
アフリカ大陸の4つの地域(ア~エ)の地形を陰影図で表現したもの(①~④)から、指定された地域(ウ)に該当するものを特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
図2の「ウ」は、アフリカ大地溝帯の東側に位置します。大地溝帯は、地面が裂けてできた巨大な谷で、切り立った崖を伴う特徴的な地形が見られます。図1の陰影図の中で、このような明瞭な谷地形が表現されているのは①です。したがって、これがウに該当します。
②【誤】
②は、細長く延びる山脈が何列も連なっている褶曲山脈の地形です。これはアフリカ北西端のアトラス山脈(図2のア)に該当します。
③【誤】
③は、広大な高原が河川によって深く侵食され、複雑な谷が刻まれた地形です。これはエチオピア高原などに見られる特徴です。
④【誤】
④は、一面に砂丘が広がっている砂漠の地形で、風によって作られたしま模様(風紋)が見られます。これはサハラ砂漠(図2のイ)の砂丘地帯(エルグ)に該当します。
問2:正解③
<問題要旨>
アフリカの世界自然遺産3か所(A~C)と、そこで見られる生物や植生に関する説明文(カ~ク)を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
①【誤】
Aはキ、Bはカと結びつくため、組み合わせが誤りです。
②【誤】
Aはキ、Cはクと結びつくため、組み合わせが誤りです。
③【正】
・地点と説明文を対応させます。
・A:タンザニアのセレンゲティ国立公園。サバナが広がり、乾季と雨季に合わせてヌーなどの草食動物が水や草を求めて大移動することで有名です。→ キ
・B:ナミビアのナミブ砂漠。世界で最も古い砂漠の一つで、極度に乾燥しています。沿岸部で発生する霧から水分を得る、特殊な生態系を持つ昆虫などが生息しています。→ カ
・C:南アフリカ共和国のケープ植物区保護地域群。地中海性気候で、夏は乾燥し山火事が頻発します。この環境に適応した、細く硬い葉を持つ低木群(フィンボス)が特徴的な植生です。→ ク
・したがって、A-キ、B-カ、C-クの組み合わせが正しく、この選択肢が正解です。
④【誤】
Bはカ、Cはクと結びつくため、組み合わせが誤りです。
⑤【誤】
Aはキ、Bはカと結びつくため、組み合わせが誤りです。
⑥【誤】
Aはキ、Cはクと結びつくため、組み合わせが誤りです。
問3:正解④
<問題要旨>
アフリカの2つの国(a, b)における小学校の授業風景の写真と、公用語に関する文章を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
①【誤】
b(ケニア)に該当するのは写真Fと文章シです。
②【誤】
b(ケニア)に該当するのは写真Fです。
③【誤】
b(ケニア)に該当するのは文章シです。
④【正】
・まず、国を特定します。aはエジプト、bはケニアです。
・次に、写真と国を結びつけます。写真Eでは、女子生徒がスカーフ(ヘジャブ)を着用しており、イスラム教徒が多いエジプトの様子と考えられます。写真Fは、アフリカ系の子供たちが学んでいる様子で、ケニアの小学校と判断できます。
・最後に、文章と国を結びつけます。サの「アラビア語」はエジプトの公用語です。シの「スワヒリ語」と「英語」は、ともにケニアの公用語です(ケニアは旧イギリス領)。
・問題は、bの国(ケニア)に該当する写真と文章を問うているため、写真Fと文章シの組み合わせが正解となります。
問4:正解③
只今準備中です。しばらくお待ちください。
問5:正解⑤
<問題要旨>
アフリカの人口上位国の人口構成図を見て、国名(P~R)と、人口規模を示す凡例(マ~ム)を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
①【誤】
Qはマ、Rはミと結びつくため、組み合わせが誤りです。
②【誤】
Pはム、Qはマ、Rはミと結びつくため、組み合わせが誤りです。
③【誤】
Pはム、Qはマと結びつくため、組み合わせが誤りです。
④【誤】
Pはム、Rはミと結びつくため、組み合わせが誤りです。
⑤【正】
・まず、国を特定します。地図上の位置から、Pはモロッコ、Qはナイジェリア、Rはタンザニアです。
・次に、人口規模を比較します。アフリカで最も人口が多い国はナイジェリア(約2億人)です。タンザニアは約6千万人、モロッコは約4千万人です。
・円の大きさは総人口を表しているため、最も円が大きいQがナイジェリアに対応します。凡例で最も人口が多いのは「マ」なので、Q-マとなります。
・残りのPとRでは、タンザニア(R)の方がモロッコ(P)より人口が多いため、中くらいの円であるRが「ミ」、最も小さい円であるPが「ム」に対応します。つまり、R-ミ、P-ムとなります。
・したがって、P-ム、Q-マ、R-ミの組み合わせが正しく、この選択肢が正解です。
⑥【誤】
Qはマ、Rはミと結びつくため、組み合わせが誤りです。
問6:正解②
<問題要旨>
サハラ以南アフリカと北アメリカにおける、携帯電話と固定電話の普及率の推移を示したグラフから、サハラ以南アフリカの携帯電話に該当するものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
①は、普及率が100%に近く、飽和状態に達しています。これは、先進地域である北アメリカの携帯電話の推移を示しています。
②【正】
②は、2000年時点ではほぼ0%だったものが、その後急激に普及し、80%を超えています。これは、固定電話網の整備が遅れたサハラ以南アフリカで、インフラを飛び越えて携帯電話が一気に普及した「リープフロッグ現象」を典型的に示しています。したがって、これがサハラ以南アフリカの携帯電話のグラフです。
③【誤】
③は、高い普及率から一貫して減少傾向にあります。これは、携帯電話の普及に伴い、契約数が減少している北アメリカの固定電話を示しています。
④【誤】
④は、20年間ほぼ0%のまま推移しています。これは、インフラ整備が進まず、ほとんど普及しなかったサハラ以南アフリカの固定電話を示しています。
第4問
問1:正解⑤
<問題要旨>
3つの国家群(D~F)の地図と、それぞれの特徴を説明した文章(ア~ウ)を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
①【誤】
Eはア、Fはイと結びつくため、組み合わせが誤りです。
②【誤】
Dはウ、Fはイと結びつくため、組み合わせが誤りです。
③【誤】
Dはウ、Eはアと結びつくため、組み合わせが誤りです。
④【誤】
Dはウ、Fはイと結びつくため、組み合わせが誤りです。
⑤【正】
・まず、国家群を特定します。
・D:中東、アフリカ、南米の産油国が加盟しており、**OPEC(石油輸出国機構)**です。
・E:東南アジアの国々で構成されており、**ASEAN(東南アジア諸国連合)**です。
・F:アメリカ合衆国、カナダ、メキシコで構成されており、USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)、旧NAFTAです。
・次に、文章と結びつけます。
・ア:「経済成長と平和を目的」はASEANの設立趣旨と一致します。→ E
・イ:「貿易障壁を緩和」はUSMCAの目的です。また、USMCAの発効は2020年であり、この中では最も新しい国家群です。→ F
・ウ:「特定の天然資源をもつ国家群」は、石油を対象とするOPECの説明です。→ D
・したがって、D-ウ、E-ア、F-イの組み合わせが正しく、この選択肢が正解です。
⑥【誤】
Eはア、Fはイと結びつくため、組み合わせが誤りです。
問2:正解①
<問題要旨>
1980年と2018年の日本の貿易相手地域について、総輸出入額に占める割合の変化を示したグラフから、西アジアに該当するものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
1980年、日本の総輸入額に占める割合が30%を超え、輸出額の割合は極めて低い。これは、二度の石油危機を経て原油価格が高騰した当時、輸入の大半を西アジアからの原油に頼っていた状況を反映しています。2018年には、省エネルギー化や原油価格の相対的な安定により輸入割合は低下しましたが、依然として大幅な輸入超過です。この特徴は西アジアに合致します。
②【誤】
輸出入ともに割合が極めて低いまま推移しています。これはアフリカとの貿易を示しています。
③【誤】
1980年には輸出入ともに割合が低かったものが、2018年には両方とも劇的に増加し、日本の最大の貿易相手となっています。これは、中国の経済成長を背景とした東アジアとの貿易の拡大を示しています。
④【誤】
1980年には日本の最大の貿易相手地域でしたが、2018年には東アジアにその地位を譲り、相対的な割合が低下しています。これは北アメリカ(主にアメリカ合衆国)との貿易を示しています。
問3:正解③
<問題要旨>
ドイツの電源別発電量の推移グラフを読み解き、内容に関する記述の中から、適当でないものを選択する問題です。
<選択肢>
①【正】
正しい記述です。太陽光発電は、日照のある昼間にしか発電できないため、夜間は発電量が0になります。グラフからも、昼のピークと夜のゼロを繰り返しており、昼夜の変動が最も大きいことがわかります。
②【正】
正しい記述です。風力発電は風の強さに依存するため、発電量が不安定です。グラフを見ると、6月5日~7日は発電量が多いですが、8日~9日は風が弱かったのか、発電量が大きく減少しており、日々の発電量が安定しないことがわかります。
③【誤】
誤った記述です。火力発電は、天候に左右されず安定して発電できるため、電力供給のベースを担っています。しかし、グラフの6月8日の昼間などを見ると、太陽光の発電量が火力発電の発電量を上回っている時間帯があります。したがって、「どの時間帯においても最大の発電量を占めている」という記述は誤りです。
④【正】
正しい記述です。電力需要量の線(破線)が、国内の総発電量(積み上げグラフの一番上の線)を上回っている時間帯は、国内の供給だけでは電力が不足していることを意味します。この不足分は、周辺の国々から電力を輸入することで補っています。
問4:正解③
只今準備中です。しばらくお待ちください。
問5:正解②
<問題要旨>
食料廃棄が起こる段階の地域差を示したグラフから、地域(X, Y)と食料品(カ, キ)を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【誤】
②【正】
一般的に、ヨーロッパなどの先進国では、家庭での食べ残しや期限切れなど「消費段階」での廃棄が多く、サハラ以南アフリカなどの発展途上国では、収穫後の貯蔵・輸送インフラの未整備による「生産・貯蔵・加工段階」での廃棄が多いとされています。この知識に従うと、Yがヨーロッパ、Xがサハラ以南アフリカとなります。
しかし、指定された正解は②です。この正解は、Xがヨーロッパ、キが果実・野菜類であることを示しています。これは、ヨーロッパ(Xと仮定)では生産段階での廃棄が多く、消費段階での廃棄が少ないという解釈になり、一般的な理解とは異なります。この問題の背景には、廃棄量の定義など、特殊な前提条件があると考えられます。
③【誤】
④【誤】
問6:正解⑤
<問題要旨>
政府開発援助(ODA)の国別供与額のグラフを見て、日本、アメリカ合衆国、スペインと、グラフ中の記号(サ~ス)を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【誤】
②【誤】
③【誤】
④【誤】
⑤【正】
・まず、グラフ中の国を特定します。サは供与額が突出しており、長年世界第1位であるアメリカ合衆国と判断できます。
・次に、残りのシとスを日本とスペインに割り当てます。実際のODA供与額(2015-19年平均)は、日本が世界第4位(約120億ドル)、スペインが10位前後(約30億ドル)です。
・グラフを見ると、スは約120億ドルで日本の実績額とよく一致します。一方、シは約150億ドルと示されており、スペインの実績額とは大きく異なります。
・この問題では、スが日本の実績値と一致することからスを日本と判断し、消去法でシをスペインと割り当てることで、正解の選択肢⑤(日本-ス、アメリカ合衆国-サ、スペイン-シ)に至ると考えられます。ただし、シのグラフの値には注意が必要です。
⑥【誤】
第5問
問1:正解⑤
<問題要旨>
地図上の3都市(浜田市、広島市、三次市)の地理的特徴と、1月の気候データ(日照時間、平均気温)を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
①【誤】
浜田市はウ、三次市はイです。
②【誤】
浜田市はウ、広島市はアです。
③【誤】
広島市はア、三次市はイです。
④【誤】
浜田市はウです。
⑤【正】
・各都市の気候特性を考えます。
・浜田市:日本海に面しており、冬は北西季節風の影響で曇りや雪の日が多く、日照時間は短くなります。海洋の影響で、内陸よりは気温の冷え込みが緩やかです。→ ウ(日照時間64.2、気温6.2℃)
・広島市:瀬戸内海に面しており、冬は山地が季節風を遮るため晴天が多く、日照時間は長くなります。→ ア(日照時間138.6、気温5.4℃)
・三次市:中国山地の内陸盆地に位置し、冬は放射冷却現象で気温が非常に低くなります(冷え込みが厳しい)。→ イ(日照時間85.7、気温1.9℃)
・したがって、浜田市-ウ、広島市-ア、三次市-イの組み合わせが正しく、この選択肢が正解です。
⑥【誤】
広島市はア、三次市はイです。
問2:正解⑥
<問題要旨>
3種類の商品・サービス(衣料品、娯楽、食料品)について、どの地域の店舗を利用するかの調査結果を示した地図から、項目と地図(カ~ク)を正しく結びつける問題です。中心地理論の考え方が応用できます。
<選択肢>
①【誤】
②【誤】
③【誤】
④【誤】
⑤【誤】
⑥【正】
・商品やサービスの性質(買物頻度や専門性)から、商圏の広さを考えます。
・食料品:毎日~週に数回購入する最寄品。遠くまで買いに行くことは少なく、商圏は最も狭くなります。地図「カ」は、ほとんどの地区で「自地区」での購入割合が高く、これに該当します。
– 娯楽・レジャー:購入頻度が低く、より専門的な施設やサービスを求めるため、人々は遠くの大きな都市まで出かけます。商圏は最も広くなります。地図「キ」は、広域の中心地である広島市への流出が顕著に見られ、これに該当します。
・衣料品・身回品:食料品と娯楽の中間的な性質を持つ買回品。地元でも買うが、品揃えを求めて少し大きな都市へも出かけます。商圏は中間的です。地図「ク」は、自地区や近くの中心地(浜田市など)への流れが中心で、これに該当します。
・したがって、衣料品-ク、娯楽・レジャー-キ、食料品-カの組み合わせが正しく、この選択肢が正解です。
問3:正解④
<問題要旨>
浜田市の人口分布図と、コンビニエンスストア、まちづくりセンターの立地図、そして特定の小学校区における施設への距離別人口割合のグラフを照合し、施設の種類(X, Y)と小学校区(サ, シ)を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
まちづくりセンターはY、小学校区bはサです。
②【誤】
まちづくりセンターはYです。
③【誤】
小学校区bはサです。
④【正】
・まず、施設の種類を特定します。コンビニエンスストアは、人口が多い場所や交通量の多い道路沿いに集中して立地する傾向があります。一方、まちづくりセンターのような公共施設は、市民が利用しやすいように、市内全域に比較的均等に配置される傾向があります。地図を見ると、コンビニ(黒丸)は人口密度の高いa地区に集中し、まちづくりセンター(白四角)は市内全域に分散しています。
・次に、グラフと施設を結びつけます。Xのグラフは、人口の大部分が施設から1km未満の場所に住んでおり、施設が集中立地していることを示します。これはコンビニエンスストアです。Yのグラフは、施設から遠い(3km以上)住民も多く、施設が分散立地していることを示します。これはまちづくりセンターです。
・最後に、小学校区を特定します。地図を見ると、b地区とc地区では、c地区の方が山がちで人口が散在しており、施設までの距離が遠くなる住民が多いと推測されます。グラフでサとシを比べると、シの方が「3km以上」の割合が高く、施設から遠いことを示しています。したがって、シがc地区、サがb地区と判断できます。
・問題では「まちづくりセンター」と「小学校区b」を問うているため、Yとサの組み合わせが正解です。
問4:正解②
<問題要旨>
浜田市の地形図と、各地点で撮影された写真を見比べ、現地の様子について議論した会話文の中から、内容に誤りを含む下線部を指摘する問題です。
<選択肢>
①【正】
正しい記述です。写真Eの場所は、地形図を見ると周囲を丘に囲まれた入り江(内湾)になっており、外海からの波の影響を受けにくい天然の良港であることがわかります。
②【誤】
誤った記述です。地点Fの写真は、道幅が狭く、昔ながらの家々が道に沿って建ち並んでいる様子が写っています。これは、自動車の普及(モータリゼーション)に対応した大規模な再開発が行われた姿ではなく、古い城下町の街道の面影を残す町並みです。
③【正】
正しい記述です。地点Gは港湾地区で、地形図を見ると海岸線が不自然な直線で構成されており、海を埋め立てて造成された土地(埋立地)であることが読み取れます。
④【正】
正しい記述です。地点Hは丘陵地の斜面に広がる住宅地です。地形図を見ると、等高線が不自然な形で密集していたり、崖の地図記号があったりすることから、斜面を切り崩したり(切土)、土を盛ったり(盛土)して、宅地が造成されたことがわかります。
問5:正解③
<問題要旨>
江戸時代の商品流通の模式図と、特産品であった石見焼に関する資料を読み、会話文の空欄(タ、チ)に当てはまる語句を正しく組み合わせる問題です。
<選択-肢>
①【誤】
タは砂糖・塩、チは海路です。
②【誤】
チは海路です。
③【正】
・空欄タ:Jの矢印は、瀬戸内海・大阪方面から浜田を経由して北陸・東北・北海道へ向かう物流(北前船の上り航路)を示しています。当時、経済の中心地であった大阪からは、砂糖、塩、木綿、酒、古着といった商品が、地方へ運ばれました。米や昆布は、逆に北国から大阪へ運ばれる主要な産物です。したがって、タには砂糖・塩が入るのが適当です。
・空欄チ:浜田の特産品である石見焼(陶器)は、重くて壊れやすい商品です。これを東北・北陸地方へ大量に輸送するには、陸路よりも一度に多くの荷物を運べる船(海路)を利用するのが効率的です。また、石見焼が確認された地点が日本海沿岸に分布していることからも、船による交易が中心だったことがうかがえます。したがって、チには海路が入ります。
・以上より、タ-砂糖・塩、チ-海路の組み合わせが正解です。
④【誤】
タは砂糖・塩です。
問6:正解③
<問題要旨>
過疎問題の解決に向けた取組みの具体例(①~④)の中から、目的P「地域文化に対する愛着の醸成」に最も合致するものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
乗合タクシーの運行は、交通手段が限られる地域での移動を助けるものであり、Q「日常生活における利便性の向上」を目的とする取組みです。
②【誤】
水産物のブランド化は、地域の特産品の価値を高めて広く宣伝し、販売を促進するものであり、S「魅力ある地域産品の宣伝」を目的とする取組みです。
③【正】
伝統行事の保存・継承活動を支援することは、その地域に古くから伝わる文化を守り、次世代に伝えていくことです。こうした活動を通じて、住民が自らの地域に誇りと愛着を持つことにつながるため、P「地域文化に対する愛着の醸成」を主な目的とする取組みとして最も適当です。
④【誤】
廃校をサテライトオフィスとして整備することは、都市部の企業などを誘致し、移住者や地域住民の働く場所を新たに創出するものであり、R「移住者の働く場所の確保」を目的とする取組みです。