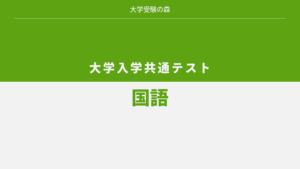解答
解説
第1問
問1:(ア)正解② (イ)正解③ (ウ)正解② (エ)正解② (オ)正解③
(ア):正解②
<問題要旨>
文脈に合う漢字を選ぶ問題です。傍線部(ア)「ケイサイ」は、「CDショップのウェブサイトにケイサイされている」という文中にあり、ウェブサイトなどに文章や写真を載せることを意味します。
<選択肢>
①【誤】
「啓発」は、人が気づかずにいるところを教え示し、より高い認識・理解に導くことを意味します。文脈に合いません。
②【正】
「掲載」は、新聞・雑誌・ウェブサイトなどに文章や写真を載せることを意味し、文脈に合致します。
③【誤】
「掲出」は、人々の目に触れるように、看板やポスターなどを掲げ出すことを意味します。ウェブサイトの内容について使われる語としては不適切です。
④【誤】
「契機」は、物事が起こる、あるいは変化する直接的な原因やきっかけを意味します。文脈に合いません。
(イ):正解③
<問題要旨>
文脈に合う漢字を選ぶ問題です。傍線部(イ)「カツヤク」は、「CDプレイヤーのプログラミング機能がカツヤクする」という文中にあり、機能などが十分に働き、めざましい成果を上げることを意味します。
<選択肢>
①【誤】
「ご利益」は、神仏が人間に与える恵みや幸運を意味します。文脈に合いません。
②【誤】
「倹約」は、費用を切り詰めて無駄遣いをしないことを意味します。文脈に合いません。
③【正】
「活躍」は、めざましく活動することを意味します。「機能が活躍する」というように、ものが活発に働く意味でも使われ、文脈に合致します。
④【誤】
「系図」は、一族の血統を書き記した図や記録を意味します。文脈に合いません。
(ウ):正解②
<問題要旨>
文脈に合う漢字を選ぶ問題です。傍線部(ウ)「モヨオし物」は、「このモヨオし物は『音楽』である以前に典礼であり」という文中にあり、人々を集めて行う催しを意味します。
<選択肢>
①【誤】
「採択」は、いくつかあるものの中から、よいものを選び取って用いることを意味します。文脈に合いません。
②【正】
「催し物」は、人々を集めて行う会や行事を意味します。文脈に合致します。
③【誤】
「催眠」は、眠気を催させることや、催眠術をかけることを意味します。文脈に合いません。
④【誤】
「負債」は、借金などの金銭的な負い目を意味します。文脈に合いません。
(エ):正解②
<問題要旨>
文脈に合う漢字を選ぶ問題です。傍線部(エ)「アクヘイ」は、「一九世紀的なアクヘイにすぎない」という文中にあり、悪い習慣や風習を意味します。
<選択肢>
①【誤】
「公平」は、判断や処理などが、かたよっていないことを意味します。文脈に合いません。
②【正】
「悪弊」は、悪い習慣や、それによって生じる害を意味します。文脈に合致します。
③【誤】
「疲弊」は、疲れ弱ること、経済的に困窮することを意味します。文脈に合いません。
④【誤】
「幽閉」は、人を特定の場所に閉じ込めて、外に出られないようにすることを意味します。文脈に合いません。
⑤【誤】
「横柄」は、人を見下した、いばった態度をとることを意味します。文脈に合いません。
(オ):正解③
<問題要旨>
文脈に合う漢字を選ぶ問題です。傍線部(オ)「マギれ」は、「オマギれもなく宗教行事であるには違いないが」という文中にあり、他のものと見分けがつかなくなる、はっきりしなくなる、という意味を持ちます。ここでは否定の「なく」を伴い、「紛れもなく」として「疑う余地もなく」という意味で使われています。
<選択肢>
①【誤】
「紛失」は、物がなくなることを意味します。文脈に合いません。
②【誤】
「噴出」は、内部のものが勢いよく吹き出すことを意味します。文脈に合いません。
③【正】
「紛れ」は、入り混じって区別がつかなくなることを意味します。「紛れもなく」の形で、疑いようもなく、はっきりと、という意味を表し、文脈に合致します。
④【誤】
「分別」は、物事の道理をわきまえていることを意味します。文脈に合いません。
⑤【誤】
「紛糾」は、物事がもつれて、乱れることを意味します。文脈に合いません。
問2:正解⑤
<問題要旨>
筆者が、ウィーンで行われたモーツァルトの《レクイエム》の演奏会について、「これが典礼なのか、音楽なのかという問題は、実はかなり微妙である」と述べる理由を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
本文には、この演奏会が「典礼の割り込み」を含むものであり、音楽部分だけを切り離して聴く聴き方が紹介されていますが、演奏会そのものが「典礼から切り離し」て行われたわけではありません。むしろ典礼という形式の中で行われたからこそ問題が「微妙」になっています。
②【誤】
これは、筆者が第3段落で紹介している「本末転倒だとする立場」の説明であり、筆者自身の見解ではありません。筆者は第4段落で、このような単純な二分法では片付けられないと述べています。
③【誤】
聖書の朗読や祈りの言葉が含まれることは第1段落に書かれていますが、それがこの問題を「微妙」にする理由の全てではありません。第5段落で述べられているオーケストラの規模や聴衆の様子といった、通常の典礼とは異なる要素が、問題を微妙にしている重要な点です。
④【誤】
CDを購入して鑑賞できることは第6段落で述べられていますが、それが問題を「微妙」にしている直接的な理由ではありません。問題の核心は、演奏会という「現場」そのものが、典礼と音楽の境界線上にあるという点です。
⑤【正】
第5段落の内容と合致します。筆者は、この催しが「追悼ミサであるという限りではオマギれもなく宗教行事」としながらも、「通常の典礼にはない大規模なオーケストラと合唱団」が参加している点や、聴衆が音楽自体を「鑑賞」の対象にしている様子を指摘しています。さらに第6段落で、この催しがメディアで販売される「音楽的なメディア・イヴェント」になっていることにも触れ、単純に典礼とも音楽とも言い切れない「微妙」な性格を説明しています。
問3:正解①
<問題要旨>
傍線部B「今『芸術』全般にわたって進行しつつある状況」がどのような状況かを説明する選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
第7、8段落の内容と合致します。筆者は、博物館の展示が「コンテクスト全体をみせ」るようになった結果、かつて博物館の内部に向けられていた「『鑑賞』のまなざし」が、「博物館の垣根をのりこえて、町全体に流れ込む」ようになり、「現実の時空もろとも、美術館や博物館という『聖域』の中に引きずり込まれた状況」であると述べています。これは、現実の空間までが鑑賞の対象になった状況を的確に説明しています。
②【誤】
関心が「博物館内部の空間よりもその周辺に関心が移り」という部分が不正確です。筆者は、博物館で培われた「まなざし」が外部に拡大していくことを述べているのであり、内部への関心が薄れたとは述べていません。
③【誤】
「施設の内部と外部の境界が曖昧になってきた」という点は本文の内容と合いますが、その理由を「地域全体を展示空間と見なす新たな鑑賞のまなざしが生まれ」たからだとする点が不正確です。筆者は、もともと内部にあったまなざしが「流れ込」んだ、つまり外部に拡大したと説明しています。
④【誤】
これは第7段落で述べられている、博物館の展示方法の変化の説明にとどまっています。傍線部Bが指すのは、その変化がもたらした、より広範な「博物館化」という現象(第8段落)であり、この選択肢は状況の一部しか説明していません。
⑤【誤】
「町全体をテーマパーク化し人々の関心を呼び込もうとする都市が出現してきた」というのは、筆者が挙げる具体例の一つに過ぎません。傍線部Bが指す「状況」とは、その背景にある、人々の「まなざし」の変化や、鑑賞対象が現実空間にまで拡大してきたという、より根本的な変化のことです。
問4:正解⑤
<問題要旨>
筆者が、「音楽」や「芸術」という概念を自明のものとして議論を始めることに対して、「なおさら警戒心をもって周到に臨まなければならない」と主張する理由を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
「概念化を促す原動力としての人々の心性を捉え損ねてしまうから」という理由が不適切です。筆者の懸念は、概念の形成過程を無視することの危険性、特にその概念が持つイデオロギー的な側面に無自覚になってしまう点にあります。
②【誤】
「『音楽で世界は一つ』などというグローバリズムの論理に取り込まれてしまう」というのは、筆者が危惧する結果の一例です。しかし、そうした事態に陥ってしまう根本的な理由、すなわち概念の「本質化」について言及されていないため、不十分です。
③【誤】
「あらゆるものが『音楽化』や『芸術化』の対象になってゆく状況を説明できなくなるから」という理由が不適切です。筆者の主張の力点は、状況を説明できるかどうかではなく、その状況の中で概念を無批判に受け入れることの危険性を指摘する点にあります。
④【誤】
「それらの周辺にはたらいている力学の変容過程を明確にすることができなくなるから」という点は本文(第9段落最終文)に即しており、非常に近い内容です。しかし、⑤で指摘されている「本質化」という、より核心的な問題に触れていない点で、最適とは言えません。
⑤【正】
第9、10段落の内容と合致します。筆者は、「音楽」や「芸術」という概念が特定の歴史的・文化的コンテクストの中で形成されたものであることを無視すると、それらがいつの間にか「本質化され」、もとから絶対的な価値があるかのように錯覚されてしまうと警告しています(第10段落)。この「本質化」こそが、筆者が最も警戒している点であり、その危険性を的確に指摘しているこの選択肢が最も適当です。
問5:正解③
<問題要旨>
文章全体の構成・展開に関する説明として、適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
適当な説明です。第1段落はモーツァルトの《レクイエム》演奏会という具体例を提示し、第2段落では音楽として聴く立場、第3段落では典礼として捉えるべきだという立場を紹介しています。
②【正】
適当な説明です。第4段落で、この問題は単純な二項対立ではないと提起し、第5、6段落で演奏会の具体的な様子を描写しながら、全体が「作品化」しているという議論の方向づけを行っています。
③【誤】
適当でない説明です。第7段落は、前段落までの議論(コンサートホール化)を、より一般的な事例である「博物館化」を通して検討し直していますが、これは「新たに別の問題への転換を図って」いるわけではありません。むしろ、「博物館化」という類似の現象を例に挙げることで、元々の問題をより深く、広い視野で捉えようとしています。問題の主題は一貫しています。
④【正】
適当な説明です。第9段落は、第8段落で示された「コンサートホール化」「博物館化」という観点に基づき、「音楽」「芸術」という概念が自明ではないという問題点を指摘します。そして第10段落は、その問題点を「『ある』わけではなく、『なる』ものである」と簡潔に言い換え、その概念を自明視することへの危惧(怪しげなグローバリズム)を示しています。
問6(1):(ⅰ)正解① (ⅱ)正解③
(ⅰ):正解③
<問題要旨>
Sさんの【文章】において、提示された一文を挿入するのに最も適当な箇所を(a)~(d)から選ぶ問題です。
<問題要旨>
挿入する文は、「それは、単に作品の舞台に足を運んだということだけではなく、現実の空間に身を置くことによって得たイメージで作品を自分なりに捉え直すということをしたからだろう。」というものです。この文は、「なぜ面白かったのか」「なぜ今までと違う見方ができたのか」という理由を説明する役割を果たします。
(a)は、体験について語り始める前なので不適切です。
(b)は、「面白かった」という感想の直後であり、理由説明として自然な流れです。
(c)は、「作品について自身の経験を基に考えたりするようになった」という、内面的な変化を述べた後です。この内面的な変化が起きた理由を、挿入する文が深く説明しています。「体験→感想→内面的変化→その理由付け→結論へ」という流れを考えると、(c)の位置で体験と思考の結びつきを明確にすることが、文章の論理性を高めます。
(d)は、現実世界の見え方が変わったという結論的な内容を述べた後なので、そこに理由を挿入すると文の流れが不自然になります。
(b)も候補になりますが、(c)に入れることで、「面白かった」という感想と、「考えるようになった」という変化の両方に対する理由となり、より説得力が増します。したがって、(c)が最も適当です。
(ⅱ):正解①
<問題要旨>
Sさんの【文章】の傍線部「今までと別の見方ができて」を、前後の文脈に合わせてより具体的に修正する表現を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
小説を読んだ後で、その舞台となった「なにげない町の風景」を実際に訪れた際に、小説の描写を思い出すことでその風景が「魅力的に見えて」くる、という状況を的確に表現しています。これは、作品世界(小説)が現実世界の認識に影響を与えるという、Sさんの体験の核心を捉えています。
②【誤】
「作品を新たな視点で読み解けて」は、現実の体験が作品解釈に影響を与えることを示しています。Sさんの文章は、まず現実の風景の見え方が変わったことを中心に述べているため、主眼が異なります。
③【誤】
「作者の創作意図が感じられて」という表現は、Sさんが述べた「別の見方ができた」という素朴な感想よりも、踏み込みすぎた解釈です。
④【誤】
「作品の情景と実際の風景のずれから時間の経過が実感できて」というのも、Sさんの体験の一側面かもしれませんが、「別の見方ができた」という全体的な感動を説明するには具体的すぎ、限定的です。
問6(2):正解②
<問題要旨>
Sさんの【文章】の主張をより明確にするための最終段落として、最も適当な方針を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
「作品理解は欠かせない」「作品世界と現実世界が不可分である」という結論は、Sさんの体験談から導き出すには断定的すぎます。また、Sさんの体験は作品→現実、現実→作品という双方向のものであり、「作品が現実を知るために不可欠」という一方的な関係ではありません。
②【正】
「作品世界と重ね合わせることで現実世界の見方が変わることがあり、それとは逆に、現実世界と重ね合わせることで作品の印象が変わることもある」という部分は、Sさんの体験(現実の見方が変わる)と、挿入文で示唆された内省(作品を捉え直す)の両方を反映しています。「作品と現実世界の鑑賞のあり方は相互に作用し得る」という結論は、この双方向の関係を的確にまとめており、Sさんの主張として最もふさわしいです。
③【誤】
「現実世界を意識せずに作品世界だけを味わうことも有効である」という内容は、Sさんの文章では触れられていません。新たな論点を持ち出すのは、結論として不適切です。
④【誤】
「作品世界を鑑賞するには現実世界も鑑賞の対象にすることが欠かせない」という結論は、①と同様に断定的すぎます。また、現実→作品という一方的な関係に焦点を当てすぎており、Sさんの体験の双方向性を十分に捉えられていません。
第2問
問1:(ア)正解④ (イ)正解④ (ウ)正解②
(ア):正解④
<問題要旨>
文脈における語句の意味を問う問題です。傍線部(ア)「うらぶれた」は、「うらぶれた男やもめ」という文脈で使われており、落ちぶれてわびしい様子を指します。
<選択肢>
①【誤】
「度量が小さく偏屈な」は、心が狭くひねくれている様子を指し、意味が異なります。
②【誤】
「だらしなく大雑把な」は、しまりがなく、細かいことにこだわらない様子を指し、意味が異なります。
③【誤】
「不満げで投げやりな」は、満足せず、物事をいい加減に扱う様子を指し、意味が異なります。
④【正】
「みすぼらしく惨めな」は、見た目が貧弱で、哀れな様子を指し、「うらぶれた」の意味と合致します。
(イ):正解④
<問題要旨>
文脈における語句の意味を問う問題です。傍線部(イ)「もっともらしい」は、「もっともらしい顔で言わないでよ」というイチナのセリフで使われており、いかにも道理にかなっているように見える様子を指します。
<選択肢>
①【誤】
「悪びれず開き直るような」は、悪いことをしたのに平気な顔で、逆に相手を責めるような態度を指し、意味が異なります。
②【誤】
「へりくだり理解を求めるような」は、自分を低くして相手の許しや同意を得ようとする態度を指し、意味が異なります。
③【誤】
「まるで他人事だと突き放すような」は、自分には関係ないという冷たい態度を指し、意味が異なります。
④【正】
「いかにも正しいことを言うような」は、うわべだけは正論を述べているように見える様子を指し、「もっともらしい」の意味と合致します。
(ウ):正解②
<問題要旨>
文脈における語句の意味を問う問題です。傍線部(ウ)「やにわに」は、祖父が「けやにわに弁解し、自分の領域を護ろうとするときがあった」という文脈で使われており、だしぬけに、急に、という動作の様子を指します。
<選択肢>
①【誤】
「多弁に」は、口数多く、よくしゃべる様子を指し、意味が異なります。
②【正】
「即座に」は、すぐその場で、という意味であり、「やにわに」の持つ「急に、すぐに」という意味と合致します。
③【誤】
「強硬に」は、自分の意見を強く主張して譲らない様子を指し、意味が異なります。
④【誤】
「半端に」は、中途半端な様子を指し、意味が異なります。
⑤【誤】
「柔軟に」は、状況に応じてしなやかに対応する様子を指し、意味が異なります。
問2:正解①
<問題要旨>
傍線部A「おばがいる限り世界は崩れなかった」がどういうことかを問う問題です。これは、おばが主宰する「ままごと」の場の性質を理解することが求められます。
<選択肢>
①【正】
本文には、ままごとの設定が凝っている一方で、子どもたちは「的外れなせりふを連発する」とあります。それでもごっこ遊びの世界が成立していたのは、おばが一人で何役もこなし、その演技力によって独特の雰囲気を作り出し、子どもたちの言動のずれを包み込んでいたからです。この選択肢は、その状況を的確に説明しています。
②【誤】
子どもたちが「的外れなせりふを連発する」とあることから、「完成度に達していた」という評価は不適切です。世界が崩れなかったのは、完成度が高かったからではなく、おばの演技力によるものです。
③【誤】
おばが子どもたちの「取るに足りない言動にも相応の意味づけをした」という記述は本文にありません。むしろ、子どもたちの言動とは無関係に、おばの力で世界が維持されていたと解釈するのが自然です。
④【誤】
子どもたちが「安心して物語の設定を受け入れることができた」かどうかよりも、傍線部が指しているのは、子どもたちの失敗があっても「世界」そのものが成立し続けたという点です。論点がずれています。
⑤【誤】
おばが「状況にあわせて話の筋をつくりかえる」という記述は本文にありません。おばは、その存在感と演技力で、設定された世界を維持していたのです。
問3:正解④
<問題要旨>
友人が、おばが自分の家にも居候していたことを打ち明けた後、「もう気安い声を出した」のはなぜかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
友人は打ち明ける前に「すばやい沈黙」があったり、「いや、これ言っていいのかな」とためらったりしており、「うれしくなった」という心情は読み取れません。
②【誤】
「罪悪感に耐えきれず」という表現は、友人のためらいの気持ちとしては強すぎます。また、隠し事をしていたこと自体が罪だという意識があったとは断定できません。
③【誤】
友人は、おばとの関係を「別にいいんだよ」「共同生活、悪くなかったよ」と語っており、イチナとの仲を気にして「安心させようとした」という意図は読み取れません。
④【正】
イチナから「おばさんと話すのは億劫?」と聞かれた友人は、何か言いにくいことがある様子でした。それは、イチナに話していなかった「おばが自分の家にも居候していた」という事実があったからです。その事実を打ち明けてしまえば、隠し事をしているという後ろめたさや気まずさから解放されるため、「気安い声」になったと考えられます。
⑤【誤】
おばがイチナに話してしまうことを「懸念して」自分から打ち明けた、という具体的な理由は本文から読み取れません。
問4:正解②
<問題要旨>
本文中で何度か描かれる、イチナが絨毯の上の糸屑を拾う様子の描写について、その説明として最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
イチナの衝撃は、「他人が割り込んでくること」という個人的な嫉妬のような感情よりも、知らなかったおばの行動や一面を知ったことによる驚きや戸惑いが中心です。
②【正】
一度目の描写では、友人宅におばが居候していたという「事実」に驚いて「動きがとまる」。二度目の描写では、友人が語るおばの「人物評」(虚勢を張らない、自然の側みたい、など)に心を揺さぶられ、動揺を抑えられないように「手をとめない。上手くとめられなかった」とあります。この選択肢は、二つの場面におけるイチナの心の動きを的確に捉えています。
③【誤】
友人の話によってイチナの「見方を覆された」ことは事実ですが、この描写は単に考えが変わったことだけでなく、それに伴う驚きや動揺といった内面のありようを表現しています。
④【誤】
友人と「おばとの関係が親密であったと告げられたことにうろたえ」たというよりは、おばの行動そのものに驚いています。また、「おばに懐いていた頃を思い返す」という記述は本文にはありません。
⑤【誤】
友人は共同生活を「悪くなかった」と評価しており、おばとの生活をはっきり思い出せないのは「なぜか」と付け加えている程度です。イチナが友人と「同じ思いを抱いていた」と気づいたというよりは、友人の話からおばの得体の知れなさを再認識させられたと捉えるべきです。
問5:正解②
<問題要旨>
傍線部C「私はごまかされたくない、とイチナは思う。」というイチナの思いを説明する問題です。
<選択肢>
①【誤】
この時点でのイチナの関心は、おばを「迷惑なものとして追及し続けたい」という非難の感情から、おばという人間の本質を「捉えたい」という知的な探求心へと変化しています。
②【正】
友人の話を聞き、イチナは、おばには「内面の輪郭が露わになる瞬間」がなく、「どこからどこまでがおばなのかよくわからない」と感じます。そして、母や友人も、おばのその「果てのなさ」に追いつけず、だからこそ暮らしをはっきり思い出せないのだ、と分析します。その上で「私はごまかされたくない」と思うのは、他の人のように煙に巻かれるのではなく、自分だけはおばという人間のあり方、本質をしっかりと見極めたい、という決意の表れです。
③【誤】
「記憶にとどめておきたい」という感傷的な思いではなく、「ごまかされたくない」という言葉からは、おばの本質を見誤らずに理解したいという、より強い意志が感じられます。
④【誤】
おばの「本心を解き明かして理解したい」という点では近いですが、友人や母が「どこまでが演技か見抜くことができなかった」という記述は本文にありません。
⑤【誤】
おばが「はぐらかすような答えしかしない」というのは事実ですが、イチナの思いは、単に居候の理由を知りたいというレベルを超え、おばという存在そのものの不可解さに向けられています。
問6:正解②
<問題要旨>
本文の表現に関する説明として、適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
適当な説明です。「ざくざく」「どすん」「すたすた」といった擬音語・擬態語は、読者が具体的な情景や行動を生き生きと思い浮かべる助けとなります。
②【誤】
適当でない説明です。「さまざまな遊具の影は誰かが引っ張っているかのように伸びつづけて、砂の上を黒く塗っていく」という表現は、夕暮れの公園の情景を描写したものです。これにより、ままごとの舞台に不思議な、あるいは少し不穏な雰囲気を加えていますが、直接的に「子どもたちの意識が徐々に変化していく様子」を表現しているとまでは言えません。
③【正】
適当な説明です。電話の場面では、受話器の向こうの友人から語られる、イチナの知らないおばの姿(友人の家に居候し、自然体で生きていた姿)と、階下から聞こえてくる日常的なおばの様子(母に料理のことで注意されている姿)が対比的に描かれ、おばの多面性が効果的に示されています。
④【正】
適当な説明です。イチナとおばが居候について言い合う場面は、地の文による描写を排し、会話文だけで構成されています。これにより、二人の間の緊張感や、イチナが畳みかけるように問い詰める様子が、テンポよく臨場感をもって伝わってきます。
⑤【正】
適当な説明です。「氷山の一角みたいに」という比喩(直喩)は、見えている部分はわずかであり、その大半はうかがい知れないという、おばの性質を的確に表しています。
問7:(ⅰ)正解④ (ⅱ)正解③
(ⅰ):正解④
<問題要旨>
教師と生徒の対話の空欄XとYに入る語句の組み合わせとして、最も適当なものを選ぶ問題です。
<問題要旨>
生徒Mは、イチナがおばを「X」と思っていたことと、【資料】の「Y」という欲求がおばには見られないことを結びつけています。
【資料】では、人間には「〈私〉を枠づけたいという欲求」があると述べられています。
イチナがおばに対して抱いていた思いは、「氷山の一角みたいに」「どこからどこまでがおばなのかよくわからない」というものでした。これは、おばに明確な「枠」がないと感じていることを示しています。
したがって、Xにはイチナがおばの「枠」のなさを感じていることを示す「どこからどこまでがおばなのかよくわからない」が入り、Yには【資料】にある「枠づけ」の欲求を示す「なに者かである者として〈私〉を枠づけ」が入るのが最も適切です。
(ⅱ):正解③
<問題要旨>
生徒Nのセリフの空欄Zに入る、イチナのおばに対する考え方の説明として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<問題要旨>
生徒Nは、イチナがおばのことを、日常生活において「Z」と考えていると述べています。その後の文で、イチナは役者としてのおばを「様々な役になりきることで自分であることから離れている」と捉えていると説明されます。
これは、イチナがおばを、【資料】が言うような「自分になる」ために演じるのではなく、むしろ特定の「自分」という「枠」を持たずに存在している人物だと考えていることを示します。
この考えに最も合致するのは、「自分は『これこれの者』だという一つの『枠』にとらわれないふるまいをしている」という選択肢です。これが日常生活におけるおばの「枠」のないあり方を示しており、それが役者としてのあり方にもつながっている、とイチナは考えているのです。
①は「枠」を隠している、②④は「枠」を実現・所有している、という考え方であり、イチナの認識とは異なります。
第3問
問1:(ア)正解③ (イ)正解② (ウ)正解⑤
(ア):正解③
<問題要旨>
古語「あからさまにも」の文脈上の意味を問う問題です。「桂の院つくりそへ給ふものから、『あからさまにも渡り給はざりし』」という文中にあり、否定の語を伴って「ほんの少しの間も」という意味を表します。
<選択肢>
①【誤】
「昼のうちも」という意味はありません。
②【誤】
「一人でも」という意味はありません。
③【正】
「あからさまなり」は「ほんのちょっと」「かりそめだ」という意味の形容動詞です。これを打ち消しているので、「少しの間も(お越しにならなかった)」という意味になり、文脈に合致します。
④【誤】
「完成してからも」という意味はありません。
⑤【誤】
「紅葉の季節にも」という意味はありません。
(イ):正解②
<問題要旨>
古語「とみのこと」の文脈上の意味を問う問題です。「とみのことなりければ、かくとだにもほのめかし給はず」という文中にあり、「急なこと」という意味を表します。
<選択肢>
①【誤】
「今までになかったこと」という意味ではありません。
②【正】
「とみなり」は「急だ、突然だ」という意味の形容動詞です。したがって、「とみのこと」は「急なこと、突然のこと」を意味し、「にわかに思いついたこと」という解釈は文脈に合致します。
③【誤】
「ひそかに楽しみたいこと」という意味ではありません。
④【誤】
「天候に左右されること」という意味ではありません。
⑤【誤】
「とてもぜいたくなこと」という意味ではありません。
(ウ):正解⑤
<問題要旨>
古語「けかたちをかしげなる」の文脈上の意味を問う問題です。「けかたちをかしげなる童の水干着たるが」という文中にあり、童の外見を描写しています。
<選択肢>
①【誤】
「格好が場違いな」という意味ではありません。「をかし」は肯定的な意味で使われます。
②【誤】
「機転がよく利く」は内面的な賢さを指しますが、「けかたち」は外見を指します。
③【誤】
「和歌が上手な」は才能を指しますが、「けかたち」は外見を指します。
④【誤】
「体を斜めに傾けた」は具体的な動作を指しますが、「けかたち」は容姿全体を指します。
⑤【正】
「けかたち」は「容貌、姿」を、「をかしげなり」は「趣がある、美しい、かわいらしい様子だ」を意味します。したがって、「見た目が好ましい」という解釈が最も適当です。
問2:正解②
<問題要旨>
波線部a~eの語句と表現に関する文法的な説明として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
a「うち興じたりしも」の「し」は、過去の助動詞「き」の連体形です。強意の副助詞ではありません。
②【正】
b「引き返さむも」の「む」は、助動詞「む」の連体形です。ここでは「もし引き返したとしたら」という仮定の状況を考えているので、「仮定・婉曲」の用法と解釈するのが適当です。
③【誤】
c「面変はりせり」の主語は、直前に述べられている「何がしの山、くれがしの河原」といった風景です。「人々の顔色が…変化してしまった」のではなく、「景色が一変した」という意味です。
④【誤】
d「興ぜさせ給ふ」の「させ」は、尊敬の助動詞「さす」の連用形です。尊敬の補助動詞「給ふ」と合わせて、主語である主人公への最高敬意を表しています。使役ではありません。
⑤【誤】
e「見給ふ」の「給ふ」は、尊敬の補助動詞で、動作の主語(この場合は和歌をご覧になる主人公)への敬意を表します。作者から大夫(動作の客体)への敬意を表すものではありません。
問3:正解④
<問題要旨>
源少将が贈った和歌Xと、それに対する主人公の返歌Yに関する説明として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
源少将は誘いを断ったわけではなく、主人公が急に出発したため、誘われなかった(取り残された)ことを恨んでいます。
②【誤】
和歌Xは、雪景色への同行から取り残されたことへの「恨み」を詠んだものであり、恋の歌ではありません。主人公がほほ笑んだのは、その大げさで巧みな恨み言の表現を面白がったからです。
③【誤】
主人公が返歌を松の枝に結びつけたのは、「松(まつ)」と「待つ(まつ)」を掛けた言葉遊びですが、和歌Yに詠まれているのは源少将を「待っていた」という内容であり、源少将が桂の院で「待つ」こととは直接関係ありません。
④【正】
和歌Y「尋め来やとゆきにしあとをつけつつも待つとは人の知らずやありけむ」では、「ゆき」に「雪」と「行き」の二つの意味が掛けられています。「あなた(源少将)が訪ねて来るかと期待して、雪道を行く私の車の跡をつけながら、待っていたとは知らないのでしょうか」という意味になり、源少将の恨み言に巧みに切り返しています。この解釈は適当です。
問4:(1)正解② (2)正解② (3)正解③
(1):正解②
<問題要旨>
解説文の空欄Ⅰに入る、和歌の解釈として最も適当なものを選ぶ問題です。
<問題要旨>
空欄Ⅰは、和歌「ここもまた月の中なる里ならし雪の光もよに似ざりけり」の後半「雪の光もよに似ざりけり」が、前半「ここもまた月の中なる里ならし」の理由となっていることを説明する部分です。「雪の光がこの世のものとは思えない(ほど素晴らしい)」から、「(月の世界である桂の里ではないが)ここも月の世界の里のようだ」と詠んでいるわけです。
したがって、空欄には「雪の光がこの世のものとは思えないほど美しいから」という趣旨の内容が入ります。②「雪がこの世のものとは思えないほど光り輝いているから」は、この解釈に完全に合致します。
(2):正解②
<問題要旨>
解説文の空欄Ⅱに入る、本文20~22行目の情景描写の要約として最も適当なものを選ぶ問題です。
<問題要旨>
空欄Ⅱは、本文の「さばかり天霧らひたりしも、いつしかなごりなく晴れわたりて、名に負ふ里の月影はなやかに差し出でたるに、雪の光もいとどしく映えまさりつつ、天地のかぎり、白銀うちのべたらむがごとくきらめきわたりて」という部分の要約です。
解説文の流れから、「名に負ふ里」が「月」を連想させる「桂の里」を指していることを踏まえる必要があります。
本文の描写は、「曇っていた空がすっかり晴れ、月の名を持つ桂の里にふさわしく、月の光が華やかに差し込み、その光で雪の輝きは一層増して、天地一面が白銀のようにきらめいている」という内容です。
②は、この情景を正確かつ過不足なく要約しています。
(3):正解③
<問題要旨>
解説文の空欄Ⅲに入る、本文の結び(23~25行目)における主人公の描き方の説明として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<問題要旨>
空欄Ⅲは、院の預かりや人々(従者)と対比される主人公の姿を説明する部分です。
院の預かりは、慌てて牛車の雪を払おうとして烏帽子を落としたり、美しい雪を踏み荒らしたりと、滑稽で無風流に描かれています。人々も「とく引き入れてむ(早く中に入ってしまおう)」とそわそわしています。
それに対して主人公は、「ここもなほ見過ぐしがたうて」と、目の前の美しい月と雪の景色に心を奪われ、その場を立ち去り難く思っています。
この対比から浮かび上がるのは、実務的・現実的な従者たちと、美を愛でる風流な心を持つ主人公の姿です。③は、この対比構造と主人公の「風雅な心」を的確に指摘しており、最も適当な説明です。
第4問
問1:正解⑤
<問題要旨>
漢詩の形式と押韻について、最も適当なものを選ぶ問題です。
<問題要旨>
この詩は、一句が七言(七文字)、全部で四句から構成されています。このような形式の詩を「七言絶句(しちごんぜっく)」と言います。
押韻(おういん)は、句の最後の文字の音をそろえることで、詩にリズムを生み出す技法です。漢詩では、原則として偶数句末で押韻し、第一句末でも押韻することがあります。この詩では、第一句末の「堆」、第二句末の「開」、第四句末の「来」が韻を踏んでいます。
したがって、形式は七言絶句で、押韻しているのは「堆」「開」「来」となります。
問2:(ア)正解① (イ)正解④ (ウ)正解①
(ア):正解①
<問題要旨>
漢文における語句の意味を問う問題です。波線部(ア)「百姓」は、【資料】Ⅰの「人馬多斃於路、百姓苦之」という文脈で使われています。
<問題要旨>
現代日本語の「百姓(ひゃくしょう)」は農民を指すことが多いですが、漢文における「百姓(ひゃくせい)」は、特定の職業を指すのではなく、「多くの人々」「人民」「民衆」といった意味で使われます。文脈は「多くの人や馬が道で倒れ、民衆はこれを苦しんだ」という意味なので、「民衆」が正しい解釈です。
(イ):正解④
<問題要旨>
漢文における語句の意味を問う問題です。波線部(イ)「膾炙人口」は、【資料】Ⅲの「杜牧華清宮詩尤膾炙人口」という文脈で使われています。
<問題要旨>
「膾」は生の肉を細かく刻んだもの(なます)、「炙」はあぶり肉を指し、いずれも当時ごちそうとされていました。「膾炙人口」は、「ごちそうが誰の口にも美味しく感じられるように、詩文などが多くの人々の話題に上り、もてはやされること」を意味する故事成語です。したがって、「広く知れわたっている」が正しい意味です。
(ウ):正解①
<問題要旨>
漢文における語句の意味を問う問題です。波線部(ウ)「因」は、【資料】Ⅳの「会南海献荔枝。因名荔枝香」という文脈で使われています。
<問題要旨>
「因」は、理由や原因を示す接続詞として使われることがあります。ここでは、「たまたま南海からライチが献上された。そのことによって(それが理由で)、(新しい曲を)『荔枝香』と名付けた」という文脈です。したがって、「そのために」という理由を示す意味が最も適当です。
問3:正解④
<問題要旨>
傍線部「窮人力絕人命、有所不顧。」の返り点の付け方と書き下し文の組み合わせとして、最も適当なものを選ぶ問題です。
<問題要旨>
この文は、「(皇帝は)人々の力を使い果たし、人々の命を絶っているのに、気にもかけないことがある」という意味です。「窮む」と「絶つ」がそれぞれ「人力」と「人命」を目的語にとる構造になっています。
書き下し文は「人力(じんりょく)を窮(きわ)め人命(じんめい)を絶(た)つも、顧(かえり)みざる所(ところ)有(あ)り」となります。「~も」は逆接の意を補っています。
返り点は、「窮(二)人力(一)ヲ」「絶(二)人命(一)ヲ」、「有(レ)所(ニ)不(レ)顧(一)ミザル(三)」というように付けられ、この書き下し文を導きます。④の組み合わせがこれに合致します。
問4:正解④
<問題要旨>
【詩】の第三句「一騎紅塵妃子笑」について、【資料】Ⅰ・Ⅱをふまえた解釈を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
ライチを手配したのは楊貴妃ではなく、彼女を喜ばせるための玄宗皇帝の命令によるものです。
②【誤】
早馬はライチの産地である南方から都へ「来る」のであり、「産地へと走りゆく」のではありません。
③【誤】
詩には早馬が「倒れて」という描写はありません。
④【正】
【資料】Ⅰ・Ⅱから、楊貴妃がライチを好み、玄宗皇帝がそれを南方から早馬で運ばせていたことがわかります。第三句は、そのライチを運ぶ一騎の馬が土煙を上げてやってくるのを見て、楊貴妃が喜んで微笑んでいる情景を描いたものと解釈できます。この選択肢は、背景情報を正しくふまえています。
⑤【誤】
ライチを運んでいたのは、玄宗皇帝の寵愛を得ようとする一個人の役人ではなく、国家の駅伝制度を利用した公的な輸送でした。
問5:正解⑤
<問題要旨>
【資料】Ⅲと【資料】Ⅳの関係性についての説明として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
【資料】Ⅲは、滞在時期とライチの旬が「一致」するのではなく、「不一致」であると指摘しています。
②【誤】
【資料】Ⅲは、滞在時期とライチの旬が「一致」するのではなく、「不一致」であると指摘しています。
③【誤】
【資料】Ⅲが「不一致」を指摘している点は正しいです。しかし、【資料】Ⅳは「『荔枝香』が果物の名ではなく楽曲の名である」と述べているわけではありません。「荔枝(ライチ)が献上されたことに因んで、新曲に『荔枝香』と名付けた」とあり、ライチが実際に献上されたことを前提としています。
④【誤】
【資料】Ⅳは、玄宗一行がライチを賞味した場所を「夏の南海郡」とは述べていません。「驪山」の「長生殿」で献上されたと述べています。
⑤【正】
【資料】Ⅲは、玄宗皇帝の驪山滞在は冬であり、ライチの旬である夏とは合わないため、杜牧の詩は事実に反すると指摘しています。これに対し、【資料】Ⅳは、楊貴妃の誕生日である夏(六月一日)に、玄宗一行は驪山に滞在しており、実際に南海からライチが献上されたという具体的な記録を挙げています。したがって、【資料】Ⅳは【資料】Ⅲの見解に反論する根拠となり得ます。
問6:正解②
<問題要旨>
【資料】をふまえた【詩】の鑑賞として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
【資料】Ⅳによれば、この詩は「事実無根の逸話」とは断定できません。また、詩の調子は直接的な「憤慨」というより、情景描写の中に批判を込めた、より技巧的で哀愁のあるものです。
②【正】
この詩は、長安を望む遠景から始まり(第一句)、山の上の宮殿(第二句)、馬煙と楊貴妃の笑顔(第三句)へと、映画のように視点が絞られていきます。そして最後の第四句で、その笑顔の理由が、民衆を犠牲にして(【資料】Ⅰ・Ⅱ)運ばれてきたライチであったことが明かされます。これは、玄宗皇帝が国政を顧みず、楊貴妃への私情に溺れたことへの批判や嘆き(慨嘆)を、巧みな構成で表現した作品と鑑賞できます。
③【誤】
この詩は、詳細を描き込む「写実的」な描写ではなく、鮮やかなイメージを提示して読者の想像を喚起する叙情詩です。「歴史的知識を提供」することが主目的ではありません。
④【誤】
詩の根底にあるのは、皇帝の権力への「感嘆」ではなく、その権力が私的に乱用されることへの批判的な眼差しです。
⑤【誤】
この詩は、二人の愛を「賛美」しているのではありません。むしろ、その愛のために多くの民が苦しんでいるという社会的な側面を浮き彫りにし、為政者のあり方を問うています。