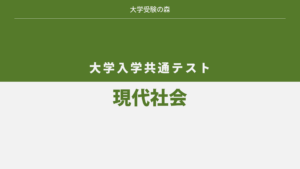解答
解説
第1問
問1:正解⑤
<問題要旨>
大日本帝国憲法と日本国憲法における、統帥権や文民統制、自衛権といった安全保障に関する中心的な条文や政府解釈についての理解を問う問題です。
<選択肢>
A【正】
大日本帝国憲法(明治憲法)第11条は「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と定めており、軍隊の最高指揮権である統帥権は、議会や内閣からも独立した天皇の大権とされていました。
B【誤】
日本国憲法第66条第2項は「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と定めています。これは文民統制(シビリアン・コントロール)の原則であり、軍人でない者が軍隊を統制するという考え方です。したがって、すべての国務大臣は文民である必要があり、文民でない者は国務大臣に就任できません。
C【誤】
かつて政府は、日本国憲法第9条の下では集団的自衛権の行使は許されないと解釈していましたが、2014年の閣議決定により憲法解釈を変更しました。現在の政府解釈では、日本の存立が脅かされるなどの「存立危機事態」においては、自衛のための必要最小限度の武力行使として、限定的な集団的自衛権の行使は許されるとしています。したがって、「全面的に禁じている」という記述は誤りです。
以上のことから、正しい記述はAのみであるため、⑤が正解です。
問2:正解⑥
<問題要旨>
冷戦後の日米安全保障体制の変遷について、主要な宣言、指針(ガイドライン)、そしてそれらに関連する国内法の制定時期を時系列で正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
まず、関連する出来事の年代を整理します。
・1996年:日米安全保障共同宣言(冷戦後の日米同盟の再定義)
・1997年:日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の改定
・1999年:周辺事態法(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律)の制定
・2015年4月:日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の再改定
・2015年9月:安全保障関連法(平和安全法制)の制定
この時系列に沿って、法律がどの時期に入るかを確認します。
・「日米安保共同宣言の発表」(1996年) と「指針の改定」(1997年) の間が【ア】です。
・「指針の改定」(1997年) と「指針の再改定」(2015年) の間が【イ】です。1999年に制定された「周辺事態法」は、1997年の指針改定を受けて、日本周辺有事における米軍への後方支援などを可能にするために制定された法律であるため、【イ】の時期に該当します。
・「指針の再改定」(2015年4月) より後が【ウ】です。2015年9月に制定された「安全保障関連法」は、2015年の指針再改定の内容を国内法として整備し、集団的自衛権の限定的行使などを可能にするものであるため、【ウ】の時期に該当します。
したがって、「周辺事態法」がイ、「安全保障関連法」がウに入る⑥の組合せが正解です。
問3:正解③
<問題要旨>
国際平和を実現するための歴史的な思想や構想について、提唱者とその内容を正しく結びつけられるかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
Aはカントの思想です。ヘーゲルではありません。
②【誤】
Aはカント、Bはウィルソンの思想です。ヘーゲル、F. ローズベルトの組合せは誤りです。
③【正】
Aの記述にある「目的の国(王国)」や「永久平和」という概念は、ドイツの哲学者カントが著書『永久平和のために』で提唱したものです。彼は、人間理性の尊厳に基づき、互いを手段としてだけでなく目的として扱うような社会を理想とし、そのような共和制国家による国際的な連合(平和連合)によって永久平和が実現されると考えました。
Bの記述にある「平和原則14か条」は、第一次世界大戦末期の1918年に、アメリカのウィルソン大統領が提唱したものです。この中で彼は、秘密外交の廃止や民族自決などと共に、国家間の紛争を平和的に解決するための国際平和機構(後の国際連盟)の設立を訴え、集団安全保障の考え方の基礎を築きました。
④【誤】
Bはウィルソンの構想です。第二次世界大戦時のアメリカ大統領であるフランクリン・ローズベルトは国際連合の設立に尽力しましたが、「平和原則14か条」の提唱者ではありません。
問4:正解⑥
<問題要旨>
公職選挙法におけるインターネットを利用した選挙運動のルールについて、具体的な事例がルールに適合しているかどうかを判断する問題です。ポスターに示されたルールを正確に読み取ることが求められます。
<選択肢>
ポスターから読み取れるルールは以下の通りです。
・選挙運動期間:公示日(7月13日)から投票日の前日(7月29日)まで。
・有権者ができること:ホームページ、ブログ、SNS、動画配信などでの選挙運動。
・有権者ができないこと:電子メール(メールアドレス宛、電話番号宛のメッセージ)を利用した選挙運動。
このルールに照らして、各行動を検証します。
A【誤】
7月16日は選挙運動期間内ですが、「メールアドレス宛てに一斉送信」する行為は、有権者に禁止されている電子メールを利用した選挙運動に該当するため、ルール違反です。
B【正】
7月25日・26日は選挙運動期間内です。「動画配信アプリを利用してライブ配信」することは、ポスターの例にある「動画共有サービス、動画中継サイト」を利用した選挙運動にあたり、有権者に許可されている方法です。したがって、ルールに適合しています。
C【誤】
7月30日は投票日当日です。選挙運動は投票日の前日までしか行えません。投票日当日にSNSで投票を依頼する投稿を行うことは、禁止されている投票日当日の選挙運動にあたるため、ルール違反です。
したがって、ルールに適合しているのはBのみであり、⑥が正解です。
問5:正解④
<問題要旨>
日本国憲法における司法権、特に裁判官の任命や身分保障に関する条文の基本的な知識を問う問題です。三権分立における司法の独立の重要性に関連する内容です。
<選択肢>
①【誤】
裁判官を訴追(罷免の訴追)に基づいて裁判するための弾劾裁判所は、国会に設置されます(憲法第64条)。最高裁判所内に設置されるわけではありません。
②【誤】
裁判官の罷免は、①公の弾劾による場合、②心身の故障のために職務を執ることができないと裁判によって決定された場合、に限定されています(憲法第78条)。「国会で議決されたとき」に罷免されるわけではありません。
③【誤】
最高裁判所の長官は内閣が指名し天皇が任命します。長官以外の裁判官は内閣が任命します(憲法第79条)。最高裁判所の長官が他の裁判官を任命する権限はありません。
④【正】
憲法第76条第3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と定めています。これは「裁判官の独立」を保障する規定であり、裁判官が内閣や国会など他の権力からの干渉を受けずに、憲法と法律に基づいて公正な裁判を行うことを保障するものです。
問6:正解②
<問題要旨>
司法権の限界を示す「統治行為論」について、砂川事件の最高裁判決を題材に、その判決の趣旨と、それに対する異なる立場からの批判を正しく理解し、結びつけられるかを問う問題です。
<選択肢>
まず、判決文の趣旨と各批判の立場を整理します。
・【判決文の趣旨】日米安全保障条約のような、国の存立に関わる高度な政治性を持つ問題について、裁判所は原則として違憲かどうかの法的判断をすべきではない。ただし、「一見極めて明白に違憲無効である」場合は例外とする。基本的には国会や内閣の判断、そして国民の政治的判断に委ねられるべき、という考え方です。これが統治行為論です。
・【より積極的に違憲審査すべきとの立場からの批判】統治行為論を理由に裁判所が判断を避けることは、憲法が裁判所に与えた違憲審査権の役割を放棄することになり、人権保障が脅かされるおそれがあるため、政治的な問題であっても積極的に憲法判断を行うべきだ、という立場です。
・【違憲審査を一切すべきでないとの立場からの批判】統治行為論をさらに徹底し、高度な政治性を持つ問題については、裁判所は一切関与すべきでなく、完全に国会や国民の判断に委ねるべきだ、という立場です。
次に、記述A~Cをそれぞれの立場に当てはめます。
・記述A:「一見極めて明白に違憲無効であると認められる場合を除いて、違憲審査をすべきでない」という内容は、判決文の趣旨【ア】を要約したものです。
・記述C:「違憲審査制の趣旨に反するから、違憲審査を回避すべきでない」という内容は、司法の積極的な役割を求める【イ】の立場からの批判に合致します。
・記述B:「明白に違憲無効と認められるかどうかの審査さえ行うべきでない」という内容は、司法の関与を完全に否定する【ウ】の立場からの批判に合致します。
したがって、アにA、イにC、ウにBが入る②が正解となります。
問7:正解①
<問題要旨>
「食料安全保障」という概念について、日本国内の文脈と、国連(FAO)などが推進する国際的な文脈における考え方の違い、および関連する政策や国際目標についての理解を問う問題です。
<選択肢>
まず、説明文中の各空欄に入る記述を論理的に特定します。
・前半は日本の食料安全保障に関する文脈です。食料の多くを輸入に頼る日本が、輸入途絶を危惧する状況を前提としています。
【ア】には、このような日本の状況を踏まえた考え方として「B. 国外の状況に左右されることなく食料を確保すべきこと」が入るのが最も自然です。
【I】には、特定の国・地域への依存を避けるための政策として「Q. 食料輸入先を分散させる」が入ります。
【II】には、輸入先の分散(I)だけでは対応できない、より広範な凶作などの事態に備えるための政策として、国内生産を重視する「P. 食料自給率を向上させる」が入ります。
・後半は国連の食料安全保障に関する文脈です。開発途上国の飢餓問題が背景とされています。
【イ】には、すべての人々の生存に関わる普遍的な理念として、国連食糧農業機関(FAO)が掲げる「A. すべての人が安全で栄養のある食料を入手する権利を有すること」という考え方が入ります。
【III】には、1996年の世界食糧サミットや2000年のミレニアム開発目標(MDGs)で掲げられた、2015年までの栄養不足人口に関する具体的な目標が入ります。この目標は「R. 半減させる」ことでした。(なお、「S. ゼロにする」は現在の持続可能な開発目標(SDGs)の目標です。)
問題では「イ・Ⅱ・Ⅲ に入るものの組合せ」が問われています。
以上の分析から、正しい組合せは イ=A、II=P、III=R となります。
①【正】
この選択肢は「イ-A」「II-P」「III-R」の組合せであり、上記の論理的推論と完全に一致します。
②【誤】
IIIがS(ゼロにする)となっています。これはMDGsではなくSDGsの目標であるため誤りです。
③【誤】
IIがQ(食料輸入先を分散させる)となっています。本文の文脈上、IIにはP(食料自給率を向上させる)が入るため誤りです。
④【誤】
IIがQ、IIIがSとなっており、両方とも誤りです。
⑤【誤】
イがB(国外の状況に左右されることなく食料を確保すべきこと)となっています。これは日本の文脈(ア)には適しますが、国連が掲げる普遍的な理念としてはAがより適切なため誤りです。
⑥【誤】
イがB、IIIがSとなっており、両方とも誤りです。
⑦【誤】
イがB、IIがQとなっており、両方とも誤りです。
⑧【誤】
イがB、IIがQ、IIIがSとなっており、すべて誤りです。
第2問
問1:正解⑤
<問題要旨>
社会調査の方法に関する基本的な用語と概念の理解を問う問題です。フィールドワーク、ブレインストーミング、帰納法といった、調査研究のプロセスで用いられる手法や考え方について問われています。
<選択肢>
・【ア】について:卒業生が働く職場を実際に訪ね、体験・見聞きしながら情報を収集する方法は、現地調査を意味する「フィールドワーク」(B)です。「ロールプレイ」(A)は、ある役割を演じることで問題解決などを図る手法であり、異なります。
・【イ】について:「ブレインストーミング」の説明として、「グループのメンバーで、お互いのアイデアを否定しないというルールで、自由にたくさんの意見を出し合う」(C)が適切です。これは、批判をせずに自由な発想を促し、多くのアイデアを出すことを目的とした会議手法です。「肯定側と否定側に分かれ、あるテーマについて討論」する(D)のは「ディベート」の説明です。
・【ウ】について:「個々の経験的事実から共通する事柄を取り出して、一般的な傾向を見出す方法」は、具体的な事例(個)から一般的な法則(般)を導き出す「帰納法」(E)の説明です。「演繹法」(F)は、一般的な原理(般)から個別の結論(個)を導き出す方法であり、逆です。
したがって、アにB、イにC、ウにEが入る⑤が正解です。
問2:正解②
<問題要旨>
日本の就労(働き方)に関連する制度や慣行についての基本的な知識を問う問題です。インターンシップや日本的雇用慣行、労働者派遣法など、現代の労働環境を理解する上で重要なキーワードが扱われています。
<選択肢>
①【誤】
政府が設置している総合的な就労支援機関は、ハローワーク(公共職業安定所)です。国民生活センターは、消費者問題に関する情報提供や相談を受け付ける機関です。
②【正】
インターンシップとは、学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行う制度のことです。職業意識の向上や、企業と学生のミスマッチを防ぐ目的で行われます。記述の通りです。
③【誤】
日本的雇用慣行の伝統的な特徴は、終身雇用や年功序列型の賃金体系です。成果主義型の賃金体系は、近年導入が進んでいる新しい考え方であり、伝統的な特徴とは言えません。
④【誤】
労働者派遣法は、1985年の制定当初は専門的な13業務に対象が限定されていましたが、その後の改正で対象業務は原則自由化されるなど、拡大する方向で改正が重ねられてきました。「対象業務数を減らす方向」という記述は誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
統計資料(表)を正確に読み取り、その内容を正しく説明している記述を選択する問題です。数値を比較し、傾向を把握する能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
「安定していて長く続けられる」の割合は、16~19歳では58.2%で最も高いですが、20~24歳では46.8%(1位)、25~29歳では46.7%で、「自宅から通える」(51.0%)に次いで2位です。「すべての年齢区分で最も高い」わけではないため、誤りです。
②【正】
「自分が身に付けた知識や技術が活かせる」の割合は、16~19歳(40.6%)>20~24歳(30.7%)>25~29歳(24.7%)です。
「能力を高める機会がある」の割合も、16~19歳(31.8%)>20~24歳(25.2%)>25~29歳(19.9%)です。
両方の観点とも、16~19歳が他の年齢区分よりも回答割合が高いため、この記述は正しいです。
③【誤】
「収入が多い」は、16~19歳(52.6%)→20~24歳(43.7%)→25~29歳(43.2%)と、年齢区分が上がるごとに減少していますが、「自由な時間が多い」は、16~19歳(35.0%)→20~24歳(35.9%)→25~29歳(31.3%)と、20~24歳で一度増加した後に減少しており、「回答割合は増加する」という記述は誤りです。
④【誤】
「自宅から通える」は、16~19歳(38.8%)→20~24歳(41.4%)→25~29歳(51.0%)と、年齢区分が上がるごとに増加していますが、「子育て、介護等との両立がしやすい」は、16~19歳(28.5%)→20~24歳(25.7%)→25~29歳(28.1%)と、20~24歳で一度減少しており、「ともに、回答割合が増加する」という記述は誤りです。
問4:正解⑤
<問題要旨>
心理学者エリクソンの提唱した「アイデンティティ」の概念、特にその構成要素である「斉一性」「連続性」などを正しく理解し、具体的なエピソードに当てはめることができるかを問う問題です。
<選択肢>
まず、各概念を整理します。
・斉一性:状況によって役割や振る舞いが違っても、それらを含めて「一人の自分」としてまとまっている感覚。
・連続性:過去の自分、現在の自分、未来の自分がつながっているという感覚。
・他者からの承認:自分が感じている斉一性や連続性を、他者も同じように認めてくれているという感覚。
次に、卒業生の発言ア~ウを分析します。
・発言ア:大学入学当初(過去)の自分と卒業時(現在)の自分を比較し、「この方法をずっと続けていこうと思う」(未来)と語っており、過去・現在・未来のつながりである【連続性】の感覚が表れています。しかし、異なる場面での自分を統合する【斉一性】については特に触れられていません。
・発言イ:幼い頃からの自分の特徴(心配性だが堅実)が就職後(未来)も強みになると考えており【連続性】の感覚が見られます。また、その特徴に加えて「相手や場面によって自分の振る舞いを変えられる柔軟性」も自分だと認識しており【斉一性】の感覚も見られます。さらに、親友から「私もその通りだと感じているよ」と言われており、【他者からの承認】も得られています。
・発言ウ:授業のグループワークでの自分と、ダンスサークルでの自分という、異なる場面での異なる役割を「違う役割をしている自分に違和感がなく」と語っており、これらを統合して一人の自分として捉える【斉一性】の感覚が表れています。しかし、過去から未来へのつながりである【連続性】については特に触れられていません。
設問のX、Y、Zに当てはめます。
・X(斉一性はあり、連続性はない):発言ウが該当します。
・Y(連続性はあり、斉一性はない):発言アが該当します。
・Z(斉一性と連続性の両方を他者が認めてくれている):発言イが該当します。
したがって、X-ウ、Y-ア、Z-イの組合せである⑤が正解です。
問5:正解⑤
<問題要旨>
心理学における欲求不満(葛藤)の類型の一つである「接近-回避」型を正しく理解し、具体的な事例の中から該当するものを選び出す問題です。
<選択肢>
葛藤の類型を整理します。
・接近-接近型:魅力的な目標が二つ以上あり、どちらか一つしか選べない状況。(例:旅行にも行きたいし、コンサートにも行きたいが、どちらかしか行けない。)
・回避-回避型:避けたいことが二つ以上あり、どちらかを選ばなければならない状況。(例:痛い注射も嫌だが、苦い薬を飲むのも嫌だ。)
・接近-回避型:一つの目標に、魅力的な側面(接近したい欲求)と、不快な側面(回避したい欲求)の両方が含まれている状況。
この定義に照らして、事例ア~ウを分析します。
・ア:「多くのことを指導したい」(接近したい欲求)が、それによって「新入社員との関係を悪くしたくない」(回避したい欲求)という状況です。これは、指導という一つの事柄に対してプラスとマイナスの感情が同時に存在するため、「接近-回避」型に該当します。
・イ:「友人と日帰り旅行に行きたい」(接近したい欲求)と、「親しい同僚の仕事を手伝ってあげたい」(接近したい欲求)という、二つの魅力的な選択肢の間で悩んでいるため、「接近-接近」型に該当します。
・ウ:「試験を受けたくない」(回避したい欲求)し、「現在の業務を続けるということもしたくない」(回避したい欲求)という、二つの避けたい選択肢の間で悩んでいるため、「回避-回避」型に該当します。
したがって、「接近-回避」型に当てはまるのはアのみであり、⑤が正解です。
問6:正解①
<問題要旨>
日本の思想家に関する問題です。それぞれの思想家が提唱した中心的な概念や思想の内容を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
和辻哲郎は、著書『人間の学としての倫理学』などで、人間は独立した個人として存在するのではなく、人と人との間柄(関係性)の中で初めて人間として存在しうる「間柄的存在」であると説きました。記述の通りです。
②【誤】
「忠信」の徳を日常生活で実践することを説いたのは、江戸時代の儒学者である伊藤仁斎です。賀茂真淵は江戸時代の国学者で、万葉集の研究などを通じて、古代日本人の精神(ますらおぶり)を明らかにしようとしました。
③【誤】
他人からの評価を行動基準にする現代人の性格類型を「他人指向型」と名付けたのは、アメリカの社会学者であるリースマンです。フランスの思想家サルトルは、人間は自由な選択を通じて自己を形成していく存在であるとする実存主義を唱えました。
④【誤】
公共的な事柄について、人々が対話を通じて合意形成を目指すことの重要性を説いたのは、ドイツの思想家ハーバーマスです。彼が提唱した概念は「対話的理性」や「コミュニケーション的合理性」と呼ばれます。アドルノは同じくドイツのフランクフルト学派の思想家ですが、主に近代の道具的理性を批判しました。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
日本の国会(衆議院・参議院)の議員の任期や選挙制度に関する基本的な知識を問う問題です。二院制の仕組みの違いを正確に理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
参議院議員の任期は6年ですが、3年ごとに半数が改選されます。6年に1度、すべての議員が改選されるわけではありません。
②【誤】
参議院の比例代表選挙は、全国を一つの単位とする非拘束名簿式で行われます。11のブロック単位で行われるのは、衆議院の比例代表選挙です。
③【正】
衆議院議員の任期は4年です。ただし、任期満了前に内閣不信任決議の可決や内閣総理大臣の判断によって衆議院が解散された場合は、その時点で議員の身分を失い、任期は終了します。記述の通りです。
④【誤】
選挙権年齢は満18歳以上に引き下げられましたが、被選挙権年齢は変更されていません。衆議院議員の被選挙権は満25歳以上、参議院議員の被選挙権は満30歳以上です。
問2:正解④
<問題要旨>
グラフを読み取り、各国の公務員の構成(中央政府・地方政府)の特徴を比較し、説明文の空欄を正しく埋める問題です。連邦制という政治体制と公務員の構成との関連性を理解することが求められます。
<選択肢>
グラフと説明文を照らし合わせて分析します。
・【ア】:アメリカ・ドイツは連邦制の国で、韓国は単一国家です。グラフを見ると、アメリカ・ドイツは韓国に比べて地方自治体や州政府に雇用される公務員(グラフの白抜き部分=地方)の割合が著しく大きいです。これは州政府が大きな権限を持つ連邦制の特徴を反映しています。したがって、アには「地方」が入ります。
・【イ】:日本のグラフを見ると、中央政府に雇用される公務員(斜線部分=中央)の割合が、他国と比較して特に少ないことが読み取れます。したがって、イには「中央」が入ります。
・【ウ】:政府の規模を「全雇用者に占める政府雇用者の割合」で測ると、日本の棒グラフの全長(合計の割合)は4か国の中で最も短いです。これは、政府の規模が相対的に「小さな」国であることを示します。したがって、ウには「小さな」が入ります。
以上のことから、アに「地方」、イに「中央」、ウに「小さな」が入る④が正解です。
問3:正解③
<問題要旨>
日本の地方自治制度について、議会、首長、住民(有権者)の関係や、住民が持つ直接請求権に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
地方議会は、首長に対して不信任決議を行うことができます。不信任決議が可決された場合、首長は議会を解散するか、自ら辞職するかを選択しなければなりません。
②【誤】
首長は、有権者による解職請求(リコール)の対象に含まれています。有権者の一定数以上の署名を集めることで、首長の解職を問う住民投票を実施することができます。
③【正】
日本の地方自治では、住民が地方議会の議員と、行政の長である首長(都道府県知事や市町村長)を、それぞれ別の選挙で直接選びます。これを二元代表制と呼びます。
④【誤】
事務の監査請求は、有権者が監査委員に対して行います。首長に対して行うものではありません。
問4:正解③
<問題要旨>
日本の刑事司法制度に関する憲法上の原則や、近年の制度改正についての知識を問う問題です。罪刑法定主義、推定無罪、被害者参加制度、一事不再理といった重要な概念が扱われています。
<選択肢>
①【誤】
憲法第39条は、事後法(実行の時に適法であった行為を、後から作った法律で処罰すること)の禁止を定めています。これは罪刑法定主義の原則の一つです。したがって、記述は認められません。
②【誤】
刑事裁判では、「疑わしきは被告人の利益に」という原則に基づき、検察官が被告人の有罪を証明する責任を負います。被告人は「無罪であると推定」されており(推定無罪の原則)、自ら無罪を証明する必要はありません。
③【正】
2008年から導入された被害者参加制度により、殺人や危険運転致死傷など一定の重大な事件の犯罪被害者やその遺族は、刑事裁判に参加して、被告人への質問や証人尋問、事実や法律の適用についての意見陳述(論告・求刑)などを行うことが認められています。
④【誤】
憲法第39条は、一度無罪(または有罪)判決が確定した事件について、再び同じ事件で裁判にかけられることはないという「一事不再理(二重の危険の禁止)」の原則を定めています。無罪が確定した後に新たな有罪の証拠が見つかっても、再び審理することは認められません。
問5:正解⑧
<問題要旨>
「法の経済分析」の考え方に基づき、損害賠償事案における「裁判」と「和解」の選択を、それぞれの費用と確率を考慮して計算し、当事者の合理的な判断を予測する問題です。
<選択肢>
まず、条件(X=100, Y=70)を代入して、それぞれの利得・損失額を計算します。
【裁判の判決で解決する場合】
・原告の予想利得額 = 0.6×200−X=120−100=20
・被告の予想損失額 = 0.2×200+X=40+100=140
【和解で解決する場合】
・原告の予想利得額 = 100−Y=100−70=30
・被告の予想損失額 = 100+Y=100+70=170
次に、この計算結果を基に説明文のア、イを判断します。
・ア(原告側の判断):和解の予想利得額(30)は、裁判の予想利得額(20)を「上回るので和解を選択する」(B)となります。
・イ(被告側の判断):和解の予想損失額(170)は、裁判の予想損失額(140)を「上回るので和解を選択しない」(C)となります。
この時点では、原告は和解を望むが、被告は裁判を望むため、和解は成立しません。
最後に、ウを考えます。和解が成立するためには、原告と被告の双方が和解を選択する必要があります。
・原告が和解を選ぶ条件:和解の利得額 ≧ 裁判の利得額
100−Y≥20⟹80≥Y
・被告が和解を選ぶ条件:和解の損失額 ≦ 裁判の損失額
100+Y≤140⟹Y≤40
両者がともに和解を選ぶためには、Yが80以下であり、かつYが40以下である必要があります。両方の条件を満たすのは Y≤40 です。
設問は「和解にかかる費用が ウ 未満まで下がることが条件となる」とあるので、Yが40未満であれば和解が成立します。したがって、ウには「40」(Q)が入ります。
以上のことから、アにB、イにC、ウにQが入る⑧が正解です。
(※問題の選択肢の構成上、アとイの判断だけでも正解は絞り込めます。)
問6:正解④
<問題要旨>
公害・環境問題における民事責任の原則と、その例外や救済制度についての会話文を読み、空欄に入る適切な法律用語や法律名を答える問題です。
<選択肢>
・【ア】について:民法上の損害賠償責任(不法行為責任)は、原則として加害者に「故意」または「過失」があったことを被害者が証明しなければ認められません。これを過失責任の原則といいます。公害事件では、被害者が企業の過失を証明することが困難であったため、被害者救済が難しいという問題がありました。文脈から、アには「過失」が入ります。
・【イ】について:裁判によらない救済制度として、汚染原因者(事業者)から金銭を徴収し、被害者に給付する仕組みを定めた法律は「公害健康被害補償法」です。この法律は、原因者(企業)に厳しい責任を課し、迅速な被害者救済を図るもので、「汚染者負担の原則(PPP)」に基づいています。「環境基本法」は、日本の環境政策の基本理念を定める法律であり、直接的な補償制度を規定するものではありません。
したがって、アに「過失」、イに「公害健康被害補償法」が入る④が正解です。
問7:正解③
<問題要旨>
情報公開や個人情報保護など、情報に関する日本の法制度についての基本的な知識を問う問題です。それぞれの法律が何を目的とし、どのような内容を定めているかを正確に理解しているかが試されます。
<選択肢>
①【誤】
情報公開制度では、国の安全や個人のプライバシーに関する情報など、開示しないことができる「不開示情報」が定められています。「いかなる場合も情報を開示しなければならない」わけではありません。
②【誤】
特定秘密保護法は、国の安全保障に関する特に秘匿性の高い情報を「特定秘密」に指定し、これを漏えいした公務員などに対して厳しい罰則を科すことを定めています。「罰則は設けられていない」という記述は誤りです。
③【正】
個人情報保護法は、個人情報を取り扱う民間事業者に対して様々な義務を課すとともに、本人(個人情報の主体)が事業者に対して自己の個人情報の開示、訂正、利用停止などを求める権利を認めています。
④【誤】
他人のIDやパスワードを無断で使用して、アクセス制限のあるコンピュータに不正にアクセスすることを禁止しているのは、「不正アクセス禁止法」です。「通信傍受法」は、犯罪捜査のために、裁判所の令状に基づき捜査機関が電話やインターネットなどの通信を傍受(盗聴)することを認める法律です。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
国際収支統計の項目に関する知識を問う問題です。経常収支を構成する「貿易収支」「サービス収支」「第一次所得収支」「第二次所得収支」のそれぞれが、どのような取引を計上するものかを理解しているかがポイントです。
<選択肢>
・【ア】について:海外からの配当・利子の受け取りは、対外的な投資によって得られる収益です。このような投資収益や、海外で働く人が本国に送金する給与などは「第一次所得収支」に計上されます。近年の日本では、この第一次所得収支の黒字が経常収支の黒字を支える大きな要因となっています。
・【イ】について:日本人が海外のホテルに宿泊する、といった旅行サービスに関する支払いは、サービスの輸入にあたります。このような、輸送、旅行、通信、金融などの国際的なサービスの取引は「サービス収支」に計上されます。
したがって、アに「第一次所得収支」、イに「サービス収支」が入る②が正解です。
問2:正解④
<問題要旨>
日本の政府開発援助(ODA)の特徴や内容に関する基本的な知識を問う問題です。ODAの形態や規模、対象分野について正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
日本のODAには、返済不要の資金協力である贈与(無償資金協力や技術協力)と、将来返済義務のある緩やかな条件での貸付(円借款)があります。「贈与に限定している」わけではありません。
②【誤】
日本のODA実績額の対GNI(国民総所得)比率は、近年0.3%台で推移しており、国連が目標とする0.7%や、先進国(DAC)平均を大きく下回っています。「1%を超えている」という記述は誤りです。
③【誤】
日本のODAは、医療や教育といった生活関連分野(基礎生活分野)の支援だけでなく、道路や港湾などの経済インフラ整備への支援も大きな割合を占めています。「生活関連分野の支援に限定している」わけではありません。
④【正】
日本のODAは、特定の開発途上国に対して直接行う「二国間援助」と、国連や世界銀行などの国際機関へ出資・拠出を通じて間接的に行う「多国間援助」から構成されています。記述の通りです。
問3:正解④
<問題要旨>
エネルギーや資源に関する基本的な用語の知識を問う問題です。エネルギー政策や環境問題を学習する上で重要な概念が扱われています。
<選択肢>
①【誤】
情報通信技術(ICT)を活用して電力の需給を効率的に管理するシステムは「スマートグリッド」と呼ばれます。「クリーン開発メカニズム」は、京都議定書に盛り込まれた制度の一つで、先進国が開発途上国で温暖化対策事業を行い、その結果得られた排出削減分を自国の削減目標達成に利用できる仕組みです。
②【誤】
主たるエネルギー源が石炭から石油に転換したことは「エネルギー革命」と呼ばれます。「オイル・ショック(石油危機)」は、1970年代に中東戦争をきっかけに原油価格が急騰し、世界経済が混乱した出来事を指します。
③【誤】
動植物に由来する有機物を原料とする再生可能エネルギーは「バイオマスエネルギー」です。「一次エネルギー」とは、石油、石炭、天然ガス、水力、原子力など、自然界から採取されたままの形態のエネルギーを指します。
④【正】
ある資源について、現在確認されている採掘可能な埋蔵量(確認可採埋蔵量)を、その年の年間生産量で割った値が「可採年数」です。これは、その資源があと何年採掘し続けられるかを示す目安となります。記述の通りです。
問4:正解③
<問題要旨>
国際連合(UN)の専門機関や関連機関の役割と名称を正しく理解しているかを問う問題です。それぞれの機関がどの分野で活動しているかを区別できるかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
国連環境計画(UNEP)は、1972年の国連人間環境会議で採択された「人間環境宣言」の理念を実現するための中核機関として設立されました。
②【正】
国際労働機関(ILO)は、労働者の権利保護、労働条件の改善、社会正義の促進などを目的とする国連の専門機関です。
③【誤】
南北格差の是正のために「援助より貿易を(Trade, not Aid)」というスローガンを掲げ、開発途上国の貿易促進と経済発展に取り組んでいるのは、国連貿易開発会議(UNCTAD)です。経済協力開発機構(OECD)は、主に先進国が加盟する国際機関で、「先進国クラブ」とも呼ばれます。
④【正】
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、紛争や迫害によって故郷を追われた難民・避難民を国際的に保護し、その生活を支援することを目的とする国連の機関です。
問5:正解①
<問題要旨>
地球温暖化対策の国際的な枠組みである「京都議定書」と「パリ協定」について、両者の違いや特徴を正しく理解しているかを問う問題です。特に、先進国と開発途上国の義務の違いが重要なポイントです。
<選択肢>
まず、空欄ア~ウに入る内容を考えます。
・【ア】(京都議定書が先進国のみに義務を課した理由):先進国が高い解決能力や歴史的責任を持つことに加え、「開発途上国に対して排出削減を求めると、その経済発展の妨げとなる」(P)という配慮がありました。これは「共通に有しているが差異のある責任」の原則に基づいています。
・【イ】(パリ協定が全参加国に義務を課した理由):現在では開発途上国の排出量が世界全体の半分以上を占めることに加え、「開発途上国と言われてきた国のなかには、既に経済発展を遂げた国もある」(Q)という現状の変化があります(例:中国、インドなど)。
・【ウ】(パリ協定が課す追加の義務):パリ協定では、途上国にも排出削減義務を課す一方で、「先進国が、開発途上国に対して、地球温暖化防止のための資金援助や技術提供を行う」(R)ことも義務づけています。これにより、途上国の温暖化対策を支援する仕組みになっています。記述Sの「排出枠を設定した上で…買い取る」のは、京都議定書で導入された排出量取引制度の説明です。
したがって、アにP、イにQ、ウにRが入ります。問題で問われているのはアとウの組合せなので、アにP、ウにRが入る①が正解です。
問6:正解⑤
<問題要旨>
ハイパーインフレーションが発生するメカニズムと、その収束策に関する会話文を読み解き、為替相場、金融・財政政策、為替制度に関する適切な用語を選択する問題です。
<選択肢>
・【X】(為替相場の変動):A国は経常収支が赤字で、米ドル建ての債務返済のために自国通貨「ルント」を売って米ドルを買う動きが強まります。これにより、ルントの価値が下がり、米ドルの価値が上がる「ルント安・ドル高」(イ)が進行します。
・【Y】(インフレ収束策):激しいインフレを収束させるためには、市中に出回るお金の量を減らし、全体の需要を抑える必要があります。これは「総需要を抑制する」(カ)政策(緊縮財政・金融引き締め)にあたります。「総需要を拡大する」(キ)政策は、不況対策として行われるもので、インフレをさらに加速させてしまいます。
・【Z】(新通貨の為替制度):中央銀行が信用ある外貨(米ドル)と新ルントの交換を保証し、外貨準備額以上の新ルントを発行しない、という仕組みは、為替レートを特定の水準に固定する「固定相場制」(サ)です。これにより通貨の信認が回復し、インフレが収束します。「変動相場制」(シ)では、このような強力な信認の裏付けは得られません。
したがって、Xにイ(ルント安・ドル高)、Yにカ(抑制)、Zにサ(固定相場制)が入る⑤が正解です。
問7:正解③
<問題要旨>
インフレーション(物価の継続的な上昇)が、人々の収入、資産、負債にどのような実質的な影響を与えるかを問う問題です。名目的な金額と実質的な価値の違いを理解することが重要です。
<選択肢>
・ア【正】
インフレになると、同じ金額で買えるモノやサービスの量が減るため、お金の価値(購買力)が実質的に下がります。年金の受給額が一定(名目額が同じ)であれば、その年金でできる生活の水準は下がってしまいます。
・イ【誤】
インフレでお金の価値が下がっている状況で、預金の金利が同じであれば、預金から得られる利子を含めても、資産全体の実質的な価値は目減りしてしまいます。預金の価値は実質的に「減少」します。
・ウ【正】
政府が過去に発行した国債は、将来、国民から借りたお金(負債)を返済する義務です。インフレが進行すると、返済する時点ではお金の価値が発行時よりも下がっています。そのため、政府が負う借金(国債)の返済負担は、実質的に軽くなります。
したがって、正しい記述はアとウであり、③が正解です。
第5問
問1:正解③
<問題要旨>
地域づくりにおける住民運動について、その要求の内容が「政策の内容そのもの」への異議なのか、それとも「政策決定のプロセス(過程)」への異議を含むのかを、具体的な事例から読み解く問題です。
<選択肢>
・ア:実施された環境アセスメントの調査が不十分であり、その「調査結果に基づいて計画を決定した進め方に問題がある」として、「やり直し」を要求しています。これは、政策決定のプロセス(過程)の不備を指摘しているため、該当します。
・イ:道路建設という「計画の撤回」を要求しており、これは政策の内容そのものへの異議です。公聴会に参加していますが、要求の主眼は内容の撤回であり、プロセスへの異議が主ではありません。しかし、住民の意見を聴取する公聴会というプロセスに参加しているため、プロセスへの関与も含まれていると解釈の余地はありますが、アやウに比べると弱いです。
・ウ:自治体が「住民の意見を聴取する機会を十分に確保しなかった」ことを問題視し、住民の意思を問う「住民投票の実施」を要求しています。これは、政策決定のプロセス(過程)が民主的でなかったことへの明確な異議表明であり、該当します。
問題文は「政策決定までの過程に対する異議の表明が含まれる事例」を全て選ぶよう求めています。アとウは明確にプロセスへの異議を表明しています。イは政策内容への異議が主ですが、公聴会への参加というプロセスへの関与はあります。しかし、より明確に「過程」そのものを問題にしているのはアとウです。選択肢を見ると「アとウ」の組合せが存在するため、これを最も適当なものとして選びます。したがって、③が正解です。
問2:正解③
<問題要旨>
二つの資料(グラフ・表)を正確に読み取り、その内容を要約した記述として正しいものを選択する問題です。地域づくりの担い手に関する意識調査(資料1)と、関係人口が地域との関わりを続ける理由(資料2)を分析する能力が求められます。
<選択肢>
・【Aに入る記述の分析】
・ア:「小都市」「町村」の「住民自身がもっと…」の割合(53.0%, 53.4%)は「全体」(58.1%)より低く、「外部人材の参加を…」の割合(21.4%, 23.0%)は「全体」(18.1%)より高い。この記述は正しいです。
・イ:「地域づくりは行政が中心に…」の割合は、「大都市」(30.3%)だけでなく「小都市」(33.0%)、「町村」(33.9%)も「全体」(32.7%)より低くはありません。「大都市だけが…低い」は誤りです。
したがって、Aにはアが入ります。
・【Bに入る記述の分析】
・ウ:「生きがいを感じる…」の割合は「直接寄与型」(20.2%)が最も高いですが、「家族の事情や…」の割合は「地縁・血縁型」(63.7%)以外でも「趣味・消費型」(22.8%)や「直接寄与型」(23.5%)など10%を超える型があり、「10人に1人にも満たない」は誤りです。
・エ:「収入源となっている」の割合は「就労型」(27.5%)が最も高いですが、「地域の良い変化を感じられる」の割合は「趣味・消費型」(8.8%)が最も低く、「地縁・血縁型」(5.6%)の方が低いため、誤りです。
・オ:「楽しい、リフレッシュできる」の割合は、全ての型で30%を超えており「5人に1人(20%)以上」を満たしています。「参加・交流型」において「いろいろな人との出会い…」(27.0%)と「同行者や滞在先の人が…」(24.5%)は、どちらも20%を超えており「5人に1人以上」です。この記述は正しいです。
したがって、Bにはオが入ります。
以上のことから、Aにア、Bにオが入る③が正解です。
問3:正解②
<問題要旨>
「関係人口」が地域にもたらす効果(A:地域資源の再発見、B:専門的能力の移転、C:運営体制の変化)を定義し、その3つの効果がすべて表れている具体的な事例を選択する問題です。
<選択肢>
各事例がA~Cのどの効果を含んでいるかを分析します。
・ア:
A: 関係人口との話で「古民家が商店街の活性化に活用できることに気付いた」→地域資源の再発見。
B: 関係人口から「古民家の利活用事業の仕組みを教えてもらい」→専門的能力の移転。
C: 「それまで連携が取れていなかった自治体や町内会、商店街が連携して役割分担をした」→運営体制の変化。
→A, B, Cすべてが含まれています。
・イ:
A: 関係人口が「地域の家庭料理が地域外の人にとっては珍しいものだと…伝えた」→地域資源の再発見。
B: 関係人口が「家庭料理の商品化のノウハウを地域に提供し」→専門的能力の移転。
C: 「商店街や自治体も商品を宣伝するために協力するようになった」→運営体制の変化。
→A, B, Cすべてが含まれています。
・ウ:
A: 「海岸林が劣化し始めていることに地域住民が気付いた」とあり、関係人口による再発見ではないため、Aは含まれていません。
B: 関係人口が「保全に関する情報を住民に提供し」→専門的能力の移転。
C: 「自治体や住民が共同で保全を行う仕組みをつくった」→運営体制の変化。
→B, Cは含まれますが、Aが含まれていません。
したがって、効果A~Cがすべて表れている事例はアとイであり、②が正解です。
問4:正解④
<問題要旨>
提示された「観点」に基づいて、地域づくりが進められていると考えられる具体的な事例を選択する問題です。観点の要素を分解し、各事例がそれらの要素を満たしているかを判断する必要があります。
<観点>
観点は、以下の3つの要素から構成されています。
地域内外の多様な担い手が連携していること。
地域内の諸資源(空き店舗、里山、伝統工芸など)を活用していること。
地域社会がもつ独自の文化(景観、祭り、歴史など)を振興していること。
この観点に照らして、事例ア~ウを分析します。
・ア:地域外の大手不動産会社が関わっていますが、「連携」ではなく、高層マンション建設によって「歴史的な景観が失われた」とあり、文化の振興とは逆の結果になっています。したがって、観点には基づいていません。
・イ:まちづくり組織(地域内)と、展示や販売を行う人(地域内外から募集)が「連携」し(要素1)、地域内の「空き店舗」という資源を活用し(要素2)、「古くから行われてきたお祭り」という独自の文化を再び盛り上げています(要素3)。したがって、観点に基づくと考えられます。
・ウ:地域住民と地域外のNPOが「連携」し(要素1)、地域内の「里山」や「伝統工芸品」といった資源を活用し(要素2)、地域通貨の仕組みを通じて「地域のもつ歴史や風土、自然を保存するための団体」が生まれるなど、地域の独自文化の振興につながっています(要素3)。したがって、観点に基づくと考えられます。
以上のことから、観点に基づくと考えられる事例はイとウであり、④が正解です。