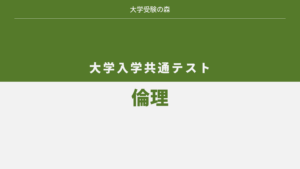解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
青年期における自己形成と、その過程で生じる心理的な課題や、それらを乗り越えるための他者との関わりの重要性について問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
本文には「他者との関わりの中で,その他者のうちに自分と共通するものを見いだしたり,あるいはその他者との相違を認めたりしながら,『自分はこういう人間だ』という,他ならぬこの自分についての意識」が形成されるとあります。他者と自己を切り離すのではなく、他者との関わりを通して自己を形成していくと述べられているため、この選択肢は誤りです。
②【誤】
本文では、青年期を「大人としての社会的役割や責任をすぐに引き受けなくてもよい『おとな猶予期間』」と述べており、社会的役割を引き受けることからの自由が保障されている期間としています。したがって、意識的に社会的責任を引き受けようとすることが自己形成の出発点であるとするこの選択肢は、本文の内容と一致しません。
③【正】
本文では、青年期を「『自分は何をしたいのか』『自分に何ができるのか』を真剣に悩み,模索する時期」と表現しています。これは、自分自身の生き方について、既存の価値観にとらわれず、主体的に問い直す時期であることを示しており、選択肢の内容と一致します。
④【誤】
本文には「自分らしさを自分で見いだそうとして自分自身の内面に深く沈潜していく」とあり、自己の内面を探求することの重要性が述べられています。しかし、それが「自己を客観的に見つめる冷静な態度」のみを意味するわけではありません。むしろ、内面への沈潜は、時に主観的な悩みを深める過程でもあります。また、本文は他者との関わりの重要性も強調しており、自己の内面への集中だけが自己形成の方法であるかのようなこの選択肢は不適切です。
問2:正解⑤
<問題要旨>
デカルト、パルメニデス、ヘラクレイトスの思想における「真理」や「実在」の捉え方について、それぞれの思想家の特徴を正しく理解できているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
「万物は流転する」と説いたのはヘラクレイトスです。彼は、絶えず変化する現象の世界こそが実在であると考えました。したがって、この記述はパルメニデスのものではありません。
②【誤】
「あるものはあり,あらぬものはあらぬ」と説き、感覚で捉えられる変化する世界を幻想とし、理性によってのみ捉えられる不変の実在を探求したのはパルメニデスです。デカルトは方法的懐疑を通じて「われ思う、ゆえにわれあり」という確実な真理に到達したのであり、記述の内容が異なります。
③【誤】
デカルトは、疑うことのできない確実な真理を探求するために方法的懐疑を用いましたが、それは真理の存在自体を否定する懐疑論とは異なります。彼は、方法的懐疑の末に「われ思う、ゆえにわれあり」という第一原理を発見し、そこから神の存在や物体の存在を証明しようとしました。したがって、真理は存在しないと断定したとするこの記述は誤りです。
④【誤】
パルメニデスは、感覚的な経験(感覚)ではなく、理性(ロゴス)によってのみ不変の実在を認識できると主張しました。したがって、感覚的な経験を重視したとするこの記述は誤りです。
⑤【正】
デカルトは、少しでも疑わしいものは全て偽として退ける方法的懐疑の果てに、疑っている自己の存在だけは疑いえないという結論に至りました。これが「われ思う、ゆえにわれあり(コギト・エルゴ・スム)」という彼の哲学の第一原理です。この記述はデカルトの思想を正しく説明しています。
問3:正解④
<問題要旨>
ソクラテス、プラトン、アリストテレスの知に関する思想の違いを問う問題です。それぞれの思想家が何を「知」と考え、どのようにそれを追求したかを理解しているかがポイントです。
<選択肢>
ア【正】
ソクラテスは、対話(ディアレクティケー)を通じて相手が無知であることを自覚させ、「無知の知」から真の知(徳)の探求へ導こうとしました。これは魂(プシュケー)を善く生きるように配慮すること(魂の世話)を意味します。したがって、この記述は正しいです。
イ【誤】
プラトンは、現実の個物はイデアの影にすぎないと考えました。そして、真の知とは、感覚の世界を超えたイデア界にある真・善・美といったイデアを、理性によって認識すること(想起、アナムネーシス)であると説きました。個物に内在する形相(エイドス)を観察し、知を探求したのはアリストテレスです。
ウ【正】
アリストテレスは、現実の個物に内在する本質(形相)を、感覚的経験に基づく観察を通じて捉え、そこから普遍的な知識を獲得しようとしました。彼は、師プラトンとは異なり、現実世界の中に真理があると考え、知的好奇心(知を愛すること)が哲学の始まりであるとしました。したがって、この記述は正しいです。
以上のことから、アとウが正しく、イが誤りであるため、正解は④となります。
問4:正解①
<問題要旨>
古代ギリシャの思想家プロタゴラスと、中国の思想家老子の思想における「道」の捉え方の違いを問うています。普遍的な真理の存在を認めるか否かが、両者の思想を比較する上での重要なポイントです。
<選択肢>
①【正】
プロタゴラスは「人間は万物の尺度である」と述べ、各人がそれぞれに感じ、判断することが真理であるとしました。これは、絶対的・普遍的な真理の存在を否定する相対主義の立場です。一方、老子は、人為的な知や価値を超えた、万物の根源であり宇宙の根本法則である「道(タオ)」の存在を説きました。この「道」は人知を超えた絶対的なものです。したがって、絶対的な真理の存在をめぐる両者の見解は対立すると言えます。
②【誤】
プロタゴラスは、人それぞれが真理の基準であると主張し、普遍的な真理を探求する必要はないと考えました。老子は、人為を超えた「道」に従う生き方(無為自然)を理想としましたが、これもまた、人間中心的な視点から真理を探求するものではありません。したがって、両者とも真理の探求は不要であると考えた点で共通するというこの記述は誤りです。
③【誤】
プロタゴラスの思想は、普遍的な真理を否定する相対主義であり、老子の思想は人為を排し「道」に従うことを説くものです。両者の思想が、普遍的な真理の存在を肯定する点で共通するという記述は誤りです。
④【誤】
プロタゴラスと老子の思想は、真理に対する考え方において根本的に異なります。プロタゴラスが相対主義を説いたのに対し、老子は絶対的な「道」の存在を説きました。両者の思想が対立しないというこの記述は誤りです。
問5:正解④
<問題要旨>
フランシス・ベーコンの経験論における「イドラ」の概念を正しく理解しているかを問う問題です。イドラが、真理の認識を妨げる偏見や先入観を指すことを理解しているかが鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
ベーコンは、真理の探求において、まずイドラ(偏見)を取り除く必要があると主張しました。そして、観察や実験といった経験を通じて得られたデータから、帰納法を用いて普遍的な法則を見いだすべきだと考えました。したがって、イドラを真理の探求の出発点とすべきだというこの記述は誤りです。
②【誤】
イドラは、正しい認識を妨げる先入観や偏見のことであり、ベーコンはこれらを排除すべきものと考えました。真理の探求に不可欠なものであるとするこの記述は誤りです。
③【誤】
ベーコンが探求しようとしたのは、自然界に潜む客観的な法則であり、イドラのような主観的な思い込みではありません。イドラは、むしろその探求の障害となるものです。
④【正】
ベーコンは、人間が陥りやすい先入観や偏見を「イドラ(幻影)」と呼び、これらが真理の認識を妨げると考えました。そして、正しい知識を得るためには、まずこれらのイドラを自覚し、排除しなければならないと主張しました。この記述はベー-コンのイドラに関する説明として正しいです。
問6:正解②
<問題要旨>
イギリス経験論のヒュームと、ドイツ観念論を確立したカントの認識論における「自己」や「認識」の捉え方の違いについて問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
Aはヒュームの説明として正しいですが、Bはカントの説明として誤りです。カントは、人間の主観が持つ認識の形式(カテゴリー)によって、外界からの情報(感性的素材)を整理・統合して世界を認識すると考えました。理性が感性に「従う」のではなく、理性が感性的な素材を構成する、と考えたのです。
②【正】
A:ヒュームは、自己とは絶えず変化する知覚(印象や観念)の束にすぎず、恒常不変な実体としての「自己」は存在しないと考えました。
B:カントは、人間は外界(物自体)をありのままに認識するのではなく、主観に備わった形式(感性の形式である時間・空間や、悟性の形式であるカテゴリー)を通して世界を認識すると考えました。これは、認識が対象に従うのではなく、対象が認識に従うという「コペルニクス的転回」と呼ばれます。
したがって、A、Bともに正しく、この組み合わせは適切です。
③【誤】
Aは、確実な知の出発点として「考える我」の存在を確立したデカルトの思想です。ヒュームの説明ではありません。Bはカントの説明として正しいです。
④【誤】
Aはデカルトの思想です。また、Bのカントに関する記述も、「理性が感性に一方的に従う」という部分が不正確です。
⑤【誤】
Aはヒュームの説明として正しいですが、Bはカントの説明として誤りです。カントは、認識されうる現象の世界と、認識不可能な「物自体」の世界を区別しました。人間の認識は現象の世界に限られると考えたため、この記述は誤りです。
⑥【誤】
Aはデカルトの思想です。Bもカントの思想として不正確です。
問7:正解③
<問題要旨>
17世紀フランスの思想家パスカルの人間観についての理解を問う問題です。彼の著作『パンセ』で展開された人間考察が中心となります。
<選択肢>
①【誤】
パスカルは、理性を司る「幾何学の精神」と、直観や感情を司る「繊細の精神」の二つを認め、後者の重要性も説きましたが、理性を全面的に否定したわけではありません。彼は理性の限界を指摘し、その上で信仰の必要性を説きました。
②【誤】
パスカルは人間を「考える葦」と表現しました。これは、人間が自然の中で葦のようにか弱い存在でありながら、思考する点において偉大であるという、人間の二面性を示した言葉です。偉大さのみを強調するこの記述は不正確です。
③【正】
パスカルは、人間を無限(神)と無(虚無)との間に位置する「中間者」と捉えました。人間は、偉大さと悲惨さ、全と無という両極の間で揺れ動く存在であり、その有限性と矛盾を自覚することが、神へと向かうきっかけになると考えました。
④【誤】
パスカルは「人間は天使でもなければ、獣でもない」と述べ、人間がそのどちらでもない中間的な存在であることを強調しました。天使に近い崇高な存在であると断定するこの記述は誤りです。
問8:正解⑥
<問題要旨>
レヴィナスとアーレントという、20世紀を代表する思想家の思想的特徴を問う問題です。レヴィナスの「他者」の倫理、アーレントの「公的領域」における活動の思想が問われています。
<選択肢>
ア【レヴィナス】
・自己の全体性から脱し、無限なる他者に応答すること(正)
レヴィナスは、自己中心的な世界観(全体性)を批判し、自己の理解を超えた存在としての「他者」の顔と向き合い、その呼びかけに無限の責任をもって応答することに倫理の根源を見いだしました。
・他者を自己の内に取り込み、全体性へと包摂すること(誤)
これはレヴィナスが批判した、他者を自己の理解の枠内に収めてしまう自己中心的な態度のことです。
イ【アーレント】
・他者と共に言論を交わし、活動する公的領域を重視した(正)
アーレントは、古代ギリシャのポリスを理想とし、人々が対等な立場で言論を交わし、共に行為する「公的領域」における「活動(ヴィータ・アクティーヴァ)」に、人間の卓越性の発揮を見いだしました。
・公的領域と私的領域を区別せず、社会的な領域を重視した(誤)
アーレントは、近代において経済活動を中心とする「社会的なもの」が公的領域を侵食し、公私の区別が曖昧になったことを批判しました。彼女は公的領域の自律性を重視しました。
以上の組み合わせから、ア、イともに正しい記述を選んでいる⑥が正解となります。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
古代中国の儒家思想における、孔子、孟子、荀子の人間観と政治思想の違いについての基本的な理解を問う問題です。
<選択肢>
ア【正】
孔子は、親兄弟に対する自然な愛情である「孝悌」が、人を愛する心「仁」の根本であると考えました。この家族道徳を社会全体に広げること(忠恕)によって、社会秩序が実現されると説きました。
イ【正】
孟子は性善説を唱え、人間には生まれながらにして「惻隠」「羞悪」「辞譲」「是非」の四つの心(四端)が備わっているとしました。この善性の芽を育て拡充することで、仁義に基づいた王道政治が実現できると考えました。
ウ【誤】
荀子は性悪説を唱え、人間の本性は利を好む欲望であるため、放置すれば争いが起こると考えました。そのため、後天的な学習や社会規範である「礼」によって欲望を矯正し、社会秩序を維持する礼治主義を説きました。欲望の充足を目標としたわけではありません。
したがって、正しい記述はアとイであり、③が正解となります。
問2:正解⑥
<問題要旨>
儒家に対抗した諸子百家のうち、墨家を創始した墨子と、法家思想を大成した韓非子の思想的特徴を問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
墨子は、儒家が家族や血縁を重んじる差別的な愛(仁)を説くことを批判し、すべての人々を分け隔てなく愛する「兼愛」を主張しました。家族愛を出発点とするのは儒家の考え方です。
イ【正】
墨子は、「兼愛」の思想に基づき、互いに利益をもたらし合う「交利」を説き、国家間の利益の奪い合いである侵略戦争(攻)を、最も不義で不利益なものとして「非攻」を唱え、強く否定しました。
ウ【正】
法家である韓非子は、徳治主義や血縁を重んじる儒家を批判し、君主が定めた客観的な法と厳格な信賞必罰によって臣下や人民を統制すべきだとする法治主義を主張しました。
したがって、正しい記述はイとウであり、⑥が正解となります。
問3:正解④
<問題要旨>
宋代から明代にかけての中国儒学(宋明理学)の二大潮流である、朱子学と陽明学の思想的特徴と、その違いを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
「性即理」を説き、人間の本性が宇宙の根本原理である「理」と一体であるとしたのは朱子の思想です。一方、「心即理」を説き、心の本体そのものが「理」であると考えたのは王陽明です。
②【誤】
一つ一つの事物に内在する理を探求していく「格物致知」を説いたのは朱子です。王陽明は、心に本来備わっている道徳知(良知)を最大限に発揮すること(致良知)を説きました。
③【誤】
知ることと行うことは表裏一体であり、分離できないとする「知行合一」を説いたのは王陽明です。
④【正】
王陽明は、人間の心には生まれながらにして善悪を判断する能力「良知」が備わっているとし、この良知を曇らせることなく、実践の中で発揮していくこと(致良知)が重要であると説きました。この記述は王陽明の思想を正しく説明しています。
問4:正解④
<問題要旨>
江戸時代の儒学の一派で、朱子学を批判し、孔子・孟子の原典に直接学ぶことを主張した古学派の代表的人物、伊藤仁斎と荻生徂徠の思想について問う問題です。
<選択肢>
ア【正】
伊藤仁斎は、朱子学の思弁的な「理」の思想を批判し、『論語』を最も重要な経典と位置づけました。そして、孔子の教えの中心である「仁」を、他者への具体的な愛情(忠信)の実践の中に求めました。
イ【誤】
荻生徂徠は、個人の内面的な道徳ではなく、古代の聖人(先王)が人民を治めるために制定した礼儀や音楽、制度といった客観的な社会規範こそが「道」であると考えました。道徳を社会制度から切り離したのではなく、むしろ道徳を社会制度そのものと捉えました。
ウ【正】
伊藤仁斎も荻生徂徠も、宋代の儒学者による解釈(朱子学)を通してではなく、孔子や孟子の時代の原典(『論語』や『孟子』など)に直接立ち返って、その本来の意味を解明しようとする「古学」という方法論を共有していました。
したがって、正しい記述はアとウであり、④が正解となります。
問5:正解③
<問題要旨>
仏教の根本的な世界観を示す四つの真理(四法印)についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
「諸行無常」は、この世のあらゆる事物や現象(諸行)は、絶えず変化し生滅し続け、永遠不変なものはないという真理です。永遠不変の実体があるという考えは、仏教が否定するものです。
②【誤】
「諸法無我」は、あらゆる存在(諸法)は、様々な原因や条件が相互に依存しあって成り立っており(縁起)、独立した不変の実体としての「我(アートマン)」は存在しないという真理です。
③【正】
「一切皆苦」は、この世のすべては、自分の思い通りにならない苦しみ(苦)に満ちているという真理です。生老病死などの根源的な苦しみ(四苦八苦)を直視することが、仏教の出発点となります。
④【誤】
「涅槃寂静」は、煩悩の炎が完全に消え去った、静かで安らかな悟りの境地を指します。これは仏教が目指す究極の理想であり、単に生きることを諦める虚無的な思想ではありません。
問6:正解④
<問題要旨>
部派仏教(小乗仏教)から発展した大乗仏教の中心的な思想である「空」の思想と、その実践としての「利他行」についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
大乗仏教で説かれる「空」とは、すべての存在には固定的な実体がなく、相互依存の関係性(縁起)の中でのみ存在するという意味です。虚しい、無価値であるというニヒリズム(虚無主義)とは異なります。
②【誤】
自分自身の悟りのみを追求するあり方は、大乗仏教の立場からは声聞(しょうもん)や縁覚(えんがく)と呼ばれ、利己的であるとして批判されました。大乗仏教では、自己の解脱(自利)と他者の救済(利他)の両方を目指す菩薩の生き方が理想とされます。
③【誤】
「空」の思想は、物事への執着から離れることを教えますが、それは他者や社会への関心を捨てることではありません。むしろ、すべての存在がつながっているという縁起の理を理解するからこそ、他者への慈悲の心が生まれるとされます。
④【正】
大乗仏教の理想像である菩薩は、自身の悟りを求めながら(上求菩提)、同時にこの世に留まって苦しむすべての人々(衆生)を救済するために尽くす(下化衆生)存在です。このような「利他」の精神が、大乗仏教の大きな特徴です。
問7:正解①
<問題要旨>
鎌倉時代に登場した新仏教の宗派のうち、浄土真宗の開祖である親鸞と、曹洞宗の開祖である道元の思想的特徴を問う問題です。
<選択肢>
ア【正】
親鸞は、煩悩が深く、自力での修行によって悟りを開くことができない人間(悪人)こそ、阿弥陀仏の絶対的な慈悲(本願)による救いの主要な対象であるとする「悪人正機説」を説きました。
イ【誤】
道元は、ひたすら坐禅に打ち込む「只管打坐」を説きましたが、それは悟りを得るための手段ではありません。坐禅をする姿そのものがすでに仏の姿であり、修行と悟りは一体である(修証一等)と考えました。
ウ【誤】
親鸞は阿弥陀仏の本願力という絶対的な他力によってのみ救われると説き、人間の側の「はからい」(自力)を徹底的に否定しました。一方、道元は只管打坐という自力の修行を重視しました。両者の救済観は大きく異なります。
したがって、正しい記述はアのみであり、①が正解となります。
問8:正解②
<問題要旨>
唯一神を信仰するアブラハムの宗教(ユダヤ教、キリスト教、イスラーム)における、神と人間との「契約」という概念の捉え方の違いを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ユダヤ教では、神がイスラエルの民を選び、預言者モーセを通じて律法(トーラー)を与えたというシナイ契約が信仰の中心です。民が律法を守ることで、神の祝福を受けるという契約関係にあります。神への絶対的服従を強調するのは特にイスラームの特徴です。
②【正】
キリスト教では、イエス・キリストが全人類の罪を背負って十字架で死に、復活したことによって、神と人類との間に「新しい契約」が結ばれたと信じられています。イエスを救い主として信じる信仰によって、神の恵みとして罪が赦される(贖罪)と考えられています。
③【誤】
イスラームでは、神(アッラー)が最後の預言者ムハンマドに下した啓示であるクルアーン(コーラン)に従うことが求められます。神への絶対的な帰依と服従が信仰の核心であり、イエスの贖罪による契約という考え方はありません。
④【誤】
三つの宗教は同じ唯一神を信仰の起源としますが、預言者の位置づけや啓示の内容、そして神との契約の理解において、それぞれ独自の内容を持っており、同じではありません。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
日本古来の自然観であるアニミズムと、そこから形成された神道の基本的な概念である「ケガレ」と「ハライ」についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
古代の日本人は、山や川、岩や木といった自然物や自然現象に霊的な力(カミ)が宿ると考えるアニミズム的な世界観を持っていました。自然は畏敬の対象であり、支配や克服の対象ではありませんでした。
②【誤】
神道における「ケガレ」とは、死、出産、病、罪などに触れることで生じる生命力の減退した状態を指します。これは、道徳的な悪というよりも、一種の不浄な状態と捉えられます。
③【誤】
「ハライ」は、神職が祝詞を奏上し、大麻(おおぬさ)を振るなどの儀式によって、「ケガレ」を祓い清めることです。内面的な反省よりも、儀礼的な浄化に重点が置かれています。
④【正】
神道では、人間は本来清らかな存在であり、日常生活の中で知らず知らずのうちに付着した罪やケガレは、「ハライ」や冷水で身を清める「ミソギ」といった儀礼を通じて取り除くことができ、元の清浄な状態に立ち返れると考えられています。
問2:正解②
<問題要旨>
江戸時代の国学者、本居宣長の思想についての問題です。儒教や仏教の影響を排し、日本古来の精神を探求した彼の思想のキーワードである「真心」や「もののあはれ」が問われています。
<選択肢>
①【誤】
宣長は、儒教や仏教の教えに影響された考え方を「漢意(からごころ)」と呼んで批判し、それらが伝来する以前の、古代日本人の純粋な精神(古道)を『古事記』などの古典に求めました。
②【正】
宣長は、人間が生まれながらに持つ自然な感情を「真心(まごころ)」として肯定しました。そして、平安時代の文学作品『源氏物語』を高く評価し、その主題は、物事に触れて自然に湧き上がるしみじみとした情趣を理解する心、すなわち「もののあはれを知る」ことにあると論じました。
③【誤】
宣長は、儒教的な道徳規範で人間の自然な感情を偽ることを「漢意」として批判しました。彼が重んじたのは、人為的な道徳ではなく、ありのままの自然な感情である「真心」です。
④【誤】
宣長は、神々の世界の出来事やこの世の理不尽な事柄は、人間の小さな知恵(さかしら)で理解しようとすべきではなく、あるがままに受け入れるべきだと考えました。合理的な精神で解明しようとする立場とは対極にあります。
問3:正解①
<問題要旨>
明治時代の啓蒙思想家、福沢諭吉の思想の中心である、学問による個人の自立と国家の独立についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
福沢諭吉は、主著『学問のすゝめ』の冒頭で「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」と述べ、人間は生まれながらにして自由平等であるという天賦人権論を平易に説きました。そして、個人が学問によって知性を磨き、精神的・経済的に自立する「独立自尊」の精神を持つことが、国家の独立にとって不可欠であると主張しました。
②【誤】
福沢は、旧来の身分制度を支える封建道徳を厳しく批判し、個人の自由と平等を基本とする近代的な倫理観を広めようとしました。
③【誤】
福沢は、西洋の学問の中でも、物理学、経済学、医学といった実生活の役に立つ「実学」の重要性を強調しました。西洋文化の無批判な導入を勧めたわけではありません。
④【誤】
福沢は、朝鮮や中国が旧態依然とした状態に留まっていることを憂い、日本はこれらアジアの国々と連帯するのではなく、西洋文明国の仲間入りをすべきだとする「脱亜論」を主張しました。
問4:正解④
<問題要旨>
近代日本を代表する思想家である、キリスト教思想家の内村鑑三と、哲学者である西田幾多郎の思想的特徴を問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
内村鑑三は、欧米の教会制度や神学に縛られず、聖書に直接基づく信仰を説く「無教会主義」を提唱しました。また、キリスト教を日本の伝統的精神である「武士道」に接ぎ木することで、日本人のためのキリスト教を確立しようとしました。
イ【正】
京都学派の創始者である西田幾多郎は、主観と客観が分かれる以前の、直接的で純粋な意識状態である「純粋経験」を哲学の出発点としました。これは、西洋哲学の論理と、日本の禅仏教の体験的思惟を統合しようとする独自の試みでした。
ウ【正】
内村はキリスト教と日本の伝統精神(武士道)の融合を、西田は西洋哲学と東洋思想(禅)の融合を試みました。両者ともに、西洋の思想・文化をたんに模倣するのではなく、日本の精神的風土に根ざした形で主体的に受容し、世界に通じる独自の思想を構築しようとした点で共通しています。
したがって、正しい記述はイとウであり、④が正解となります。
問5:正解⑤
<問題要旨>
日本の哲学者・倫理学者である和辻哲郎の倫理学の根本概念である「風土」と「間柄」についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
和辻は主著『風土』において、人間の文化や精神構造は、その土地の自然環境(風土)によって深く規定されると論じました。風土から独立した人間性を論じたわけではありません。
②【誤】
和辻は、西洋の倫理学が孤立した個人(実存)を前提としていることを批判し、人間は常に人と人との関係性(間柄)の中に存在する共同的な存在であると考え、倫理学を「人間の学」として捉え直そうとしました。
③【誤】
和辻は、世界の風土をモンスーン型、砂漠型、牧場型の三つに大別し、それぞれの類型が持つ特徴を分析しました。風土が人間のあり方を一律に規定すると考えたわけではありません。
④【誤】
人間存在を「死への存在」として特徴づけたのは、ドイツの哲学者ハイデガーです。和辻はハイデガーの思想に影響を受けつつも、その個人主義的な側面を批判し、人間を社会的な「間柄」的存在として捉えました。
⑤【正】
和辻は、人間存在が、個人としての側面(実存性)と、社会的な関係性の中にある側面(間柄性)との、二重の構造を持つと考えました。人間は、一人の個人であると同時に、常に社会的な関係の中で生きる存在であるという視点に立っています。
問6:正解①
<問題要旨>
戦後日本の思想界に大きな影響を与えた、思想家の吉本隆明と政治学者の丸山眞男の思想的特徴を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
吉本隆明は、知識人やエリートが作り出す文化や思想だけでなく、大衆の日常生活の中に根ざした文化や心情(共同幻想)に注目し、そこに思想の根源を見いだそうとしました。彼の思想は、大衆の視点を重視する点に特徴があります。
②【誤】
日本の近代化の過程で、個人の内面的な主体性や自律性が育たなかったことを批判的に分析したのは、丸山眞男です。
③【誤】
丸山眞男は、日本の伝統思想の中に、近代的な主体性の確立を妨げる無責任の体系や、権威への「古層」的な思考様式が存在することを見いだし、それを厳しく批判しました。
④【誤】
吉本隆明は、初期にはマルクス主義の影響を受けましたが、既存のマルクス主義理論を乗り越えようとし、文学、言語、文化など多岐にわたる領域で独自の思想を展開しました。
問7:正解③
<問題要旨>
インターネットの普及に代表される情報化社会が、現代人のアイデンティティ(自己同一性)の形成にどのような影響を与えているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
インターネット上の匿名性は、現実世界ではできないような自由な自己表現を可能にする一方で、他者への誹謗中傷など、無責任な言動を生み出す温床ともなり得ます。必ずしも責任感を高めるとは言えません。
②【誤】
インターネットでは、アルゴリズムなどによって自分の見たい情報だけが表示されやすくなる「フィルターバブル」や、自分と似た意見の人々の中だけでコミュニケーションが完結する「エコーチェンバー」といった現象が指摘されており、かえって視野が狭まる危険性があります。
③【正】
SNSやオンラインゲームなどの仮想空間(サイバー空間)では、現実の自分とは異なる人格(アバター)を演じたり、複数のアカウントを使い分けたりすることが容易です。こうした経験は、唯一無二の「本当の自分」という感覚を揺るがし、アイデンティティが多重的になったり、拡散したりする一因となり得ます。
④【誤】
SNSなどで他者の「キラキラした」生活を垣間見ることは、他者との比較による劣等感や自己肯定感の低下につながることがあります。また、「いいね」の数などで評価される承認欲求が、アイデンティティの不安定さを助長する場合もあります。
問8:正解④
<問題要旨>
グローバル化の進展に伴う文化の変容について、文化の均質化、多文化主義、文化の盗用といった現代的な課題に関する理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
マクドナルドのようなグローバル企業の商品が、世界各地の地域性(ローカル)に合わせてカスタマイズされて受容される現象(例:日本の「てりやきマックバーガー」)は、「グローカル化」と呼ばれます。これは、均質化とは異なる側面を捉えた言葉です。
②【誤】
異文化との接触は、自文化の伝統を見つめ直すきっかけとなり得ます。異文化の要素を主体的に取り入れ、自文化と融合させることで、新たな文化が創造されることも多く、伝統文化の価値を否定するものではありません。
③【誤】
多文化主義は、一つの社会の中に存在する複数の異なる文化の価値を等しく尊重し、その共存を目指す考え方です。自らの文化の基準で他文化を判断する自文化中心主義(エスノセントリズム)とは対立する理念です。
④【正】
ある文化圏に属する人々が大切にしてきた宗教的シンボル、伝統的な髪型、民族衣装などを、その文化的・歴史的背景への理解や敬意を欠いたまま、ファッションなどとして安易に借用・消費する行為は、「文化の盗用(カルチュラル・アプロプリエーション)」として近年批判の対象となっています。
第4問
問1:正解①
<問題要旨>
環境問題に対する倫理的アプローチである環境倫理の諸思想について、人間中心主義、生命中心主義、生態系中心主義などの違いを理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
アルド・レオポルドは、倫理共同体の範囲を人間社会から、土壌、水、植物、動物を含む生態系全体(土地)へと拡張すべきだとする「土地倫リ(ランド・エシック)」を提唱しました。これは、生態系全体を一つの共同体とみなし、その全体性や安定性を尊重する生態系中心主義(エコセントリズム)の立場です。
②【誤】
アルベルト・シュヴァイツァーは、「生きようとするすべての生命」に対する「畏敬の念」を持つべきだと説きました。これは人間だけでなく、動物や植物、微生物に至るまで、あらゆる生命を等しく尊重しようとする生命中心主義(バイオセントリズム)の立場です。
③【誤】
功利主義の立場から動物の権利を論じたピーター・シンガーは、快楽や苦痛を感じる能力(感応能力)を持つ存在を、道徳的配慮の対象に含めるべきだと主張し、「種の差別(スピーシシズム)」を批判しました。彼の議論は一部の動物にまで配慮を広げますが、生態系全体を対象とするものではありません。
④【誤】
人間中心主義は、自然を人間の利益のための資源や道具として捉える考え方です。この思想が環境破壊の一因となったという反省から、環境倫理では、人間以外の存在にも道徳的価値を認める非人間中心主義的なアプローチが探求されています。
問2:正解②
<問題要旨>
ドイツの哲学者ハンス・ヨナスが、現代の巨大化した科学技術時代に対応するために提唱した「責任倫理」についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ヨナスは、現代の科学技術が、将来の世代や地球全体の生存可能性に不可逆的な影響を及ぼす力を持つことを指摘し、倫理はまず「未来に対する責任」を考慮すべきだと主張しました。現在世代の利益を優先する考え方を批判したのです。
②【正】
ヨナスは、これまでの伝統的な倫理が、同時代に生きる人間同士の相互的な関係を前提としていたのに対し、現代では、まだ存在せず、私たちに応答することのできない「未来世代」や、人間以外の「自然」に対する、一方的な責任が問われると論じました。この非相互的な責任こそが、彼の「責任倫理」の核心です。
③【誤】
ヨナスは、科学技術がもたらすかもしれない未知のリスクに対して、楽観的な見通しを持つことを戒めました。むしろ、考えうる最悪の事態を想像し、そのような事態を避けることを優先するべきだという「危惧の発見法」を提唱し、慎重な態度を求めました。
④【誤】
ヨナスの思想は、科学技術の発展を無条件に肯定する技術楽観主義とは正反対の立場です。彼は、技術の持つ破壊的な可能性を直視し、それに対する倫理的な規制の必要性を強く訴えました。
問3:正解⑤
<問題要旨>
医療技術の進歩に伴って生じた、生殖補助医療、終末期医療、遺伝子技術などをめぐる生命倫理(バイオエシックス)の具体的な課題についての理解を問う問題です。
<選択肢>
ア【正】
第三者の女性が依頼者の夫婦のために妊娠・出産する代理出産(サロガシー)は、子どもを持つという願いをかなえる一方で、女性の身体を道具として扱うことにならないか(人間の商品化)、生まれた子の福祉や親子関係の複雑化など、多くの倫理的な問題をはらんでいます。
イ【正】
回復の見込みのない末期状態の患者が、自らの意思で延命のためだけの治療を差し控え・中止し、人間としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えることを「尊厳死」と呼びます。これは、患者の自己決定権を尊重する考え方に基づいています。
ウ【誤】
ヒトゲノム(人間の全遺伝情報)の解析は、病気の原因解明やオーダーメイド医療の発展に大きく貢献すると期待されています。しかし、同時に、個人の遺伝情報が就職や保険加入の際に差別につながる可能性や、プライバシーの侵害、優生思想への警戒など、解決すべき多くの新たな倫理的・社会的問題を生み出しています。
したがって、正しい記述はアとイであり、⑤が正解となります。
問4:正解⑥
<問題要旨>
現代の政治哲学における「正義」をめぐる議論の中心人物である、ジョン・ロールズとアマルティア・センの思想的特徴を問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
ロールズは、社会で最も恵まれない立場の人々(最も不遇な人々)の利益を最大化する限りにおいて、社会経済的な格差は許容されるとする「格差原理」を提唱しました。彼は完全な結果の平等を主張したわけではありません。
イ【正】
ロールズは、公正な社会のルール(正義の原理)を導き出すための思考実験として、参加者が自分自身の能力、社会的地位、価値観などを一切知らないという「無知のヴェール」を被った仮想的な状態(原初状態)を設定しました。この状態でなら、誰もが自己の利益のために偏った原理を選ぶことなく、公正な選択ができると考えました。
ウ【正】
アマルティア・センは、ロールズが所得や富といった「財」の分配に注目しすぎていると批判しました。そして、人がその財を用いて「何ができるか」「どのような状態でありうるか」といった、個人の実質的な自由や可能性、すなわち「潜在能力(ケイパビリティ)」の平等を保障することこそが重要だと主張しました。
したがって、正しい記述はイとウであり、⑥が正解となります。
問5:正解④
<問題要旨>
近代から現代にかけての思想家、ホッブズ、カント、ガンディーが、それぞれどのようにして「平和」が実現されると考えたかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ホッブズは、各人が自然権を自由に行使する自然状態を「万人の万人に対する闘争」であるとし、人々が契約を結んで絶対的な権力を持つ主権者(国家)を創設することで、国内の平和と安全が確保されると説きました。
②【誤】
カントは著書『永久平和のために』で、各国の国内体制が市民の自由と平等を保障する共和制となり、それらの自由な国家群が、戦争を放棄するための国際的な連合体を形成することで、永久平和が実現可能になると考えました。単一の世界政府の樹立を主張したわけではありません。
③【誤】
ガンディーが提唱した「サティヤーグラハ」は、「真理の把握」を意味する言葉で、暴力に訴えるのではなく、非暴力・不服従の抵抗によって相手の良心に働きかけ、正義を実現しようとする運動です。
④【正】
ガンディーは、インド独立運動の指導理念として「アヒンサー(不殺生・非暴力)」を掲げました。これは、いかなる生命をも傷つけないという徹底した非暴力の思想であり、彼の思想と行動の根幹をなすものです。
問6:正解④
<問題要旨>
現代社会における労働のあり方や、富の分配をめぐる経済格差の問題について、関連する思想や概念の理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ワーク・ライフ・バランスとは、「仕事と生活の調和」を意味し、過度な長時間労働を見直し、仕事と、育児や介護、個人の趣味といった私生活とを両立できる社会を目指す考え方です。
②【誤】
ベーシック・インカムは、政府がすべての人々に対して、生活に必要最低限の所得を無条件で給付する政策構想です。その目的は貧困対策や格差是正にあり、勤労意欲への影響については、むしろ低下を懸念する声もあります。
③【誤】
新自由主義(ネオリベラリズム)は、市場原理への信頼を基本とし、政府による経済への介入を極力減らす「小さな政府」を目指す思想です。規制緩和や民営化を推進しますが、その結果として格差が拡大したという批判も受けています。
④【正】
アダム・スミスは、個々人が自己の利益を追求する自由な市場経済が、神の「見えざる手」によって導かれ、意図せずして社会全体の富を増大させると考えました。しかし、現代のグローバル化した資本主義社会では、市場原理だけでは貧富の差が拡大するため、税制などを通じた政府による所得の再分配機能の重要性が指摘されています。
問7:正解①、②
<問題要旨>
現代社会を批判的に分析したドイツのフランクフルト学派の思想家、エーリヒ・フロムとユルゲン・ハーバーマスの思想についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
フロムは、主著『自由からの逃走』において、近代人が封建的な束縛から解放され「~からの自由」を得たものの、その結果生じた孤独と無力感に耐えきれず、ナチズムのような権威主義的体制に自ら服従したり、周囲の匿名の権威に無批判に同調したりすることで、自由から逃避してしまう危険性を分析しました。
②【正】
ハーバーマスは、効率性や利益追求を目的とする「道具的理性」が社会の隅々まで浸透することを批判しました。そして、それに対抗するものとして、人々が対等な立場で、言語を介して合理的な対話を行い、相互理解と合意形成を目指す「対話的(コミュニケーション的)理性」の重要性を主張しました。
③【誤】
社会の隅々にまで張り巡らされた権力(ミクロな権力)が、人々の身体や精神を監視し、規律に従わせる「生-権力」として作用していると分析したのは、フランスの思想家ミシェル・フーコーです。
④【誤】
現代の消費社会では、人々は商品の機能的な価値(使用価値)ではなく、それが示す社会的地位や他者との差異といった「記号」を消費していると論じたのは、フランスの思想家ジャン・ボードリヤールです。
問8:正解③
<問題要旨>
アラン、ラッセル、ヒルティという三人の思想家が論じる「幸福」についての文章を読み解き、その共通する考え方を指摘する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文章Cのヒルティは、神と共に働くことに幸福を見いだしており、宗教的な要素が強いですが、Aのアランは意志の力を、Bのラッセルは外界への関心を強調しており、必ずしも宗教的信仰を幸福の条件としているわけではありません。
②【誤】
Bのラッセルは、自己の内面への関心を外界に向けることを勧めていますが、三者ともに社会から離れて隠遁生活を送ることを幸福への道として推奨しているわけではありません。Cのヒルティはむしろ日々の「仕事」の中に幸福を見いだしています。
③【正】
Aのアランは「幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ」と述べ、幸福を意志的な努力の産物と捉えています。Bのラッセルは、関心の持ち方という心のあり方を説いています。Cのヒルティも、日々の仕事に意味を見いだすという精神的な営みを重視しています。三者ともに、幸福とは外部の条件によって受動的に与えられるものではなく、本人の能動的な心の持ち方や努力によって作り出されるものである、という点で共通しています。
④【誤】
三者の議論の中心は、心の持ち方や精神的な充足感にあり、物質的な豊かさが幸福の第一の条件であるとは考えていません。むしろ、そうした外面的な条件に左右されない幸福のあり方を示唆しています。