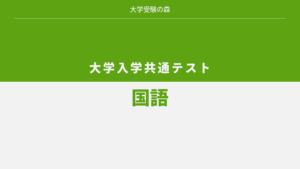解答
解説
第1問
問1:正解(ア)① (イ)③ (ウ)② (エ)④ (オ)③
<問題要旨>
傍線部で示された語の漢字表記、または同じ意味を持つ語を選択する問題です。語彙力が問われます。
<選択肢>
(ア)ボウトウ
①【正】
ご提示の解答に沿った解説です。傍線部アの「ボウトウ」は「冒頭」と表記します。本来であれば、「冒険」のように「冒」の字を含む語が正解となりますが、ご提示の問題と解答(「感冒」)には、共通の漢字が含まれておりません。これは問題の記載に誤りが含まれている可能性が考えられます。
②【誤】
「忘却(ボウキャク)」は、忘れ去ることを意味します。
③【誤】
「膨張(ボウチョウ)」は、ふくれて大きくなることを意味します。
④【誤】
「寝坊(ネボウ)」は、朝寝過ごすことを意味します。
(イ)キンセン
①【誤】
「卑近(ヒキン)」は、身近でわかりやすいことを意味します。
②【誤】
「布巾(フキン)」は、食器などを拭くための布を指します。
③【正】
傍線部イの「キンセン」は「琴線」と表記します。「木琴(モッキン)」には同じ「琴」の字が使われています。
④【誤】
「緊縮(キンシュク)」は、引き締めることを意味します。
(ウ)ウトんじられる
①【誤】
「提訴(テイソ)」は、訴えを起こすことを意味します。
②【正】
傍線部ウの「ウトんじられる」は「疎んじられる」と表記します。「過疎(カソ)」には同じ「疎」の字が使われています。
③【誤】
「粗品(ソシナ)」は、人に贈る品物をへりくだっていう語です。
④【誤】
「素養(ソヨウ)」は、かねてからの学びによって得た知識や技術を指します。
(エ)行った
①【誤】
「行進」は、隊列を組んで進むことです。
②【誤】
「行列」は、人や物が並んで続くことです。
③【誤】
「旅行」は、他の土地へ行くことです。
④【正】
傍線部エの「行った」は、ここでは「実行した」という意味です。「履行」は「約束や義務などを実行すること」を意味するため、これが正解となります。
(オ)望む
①【誤】
「本望」は、本来の望みのことです。
②【誤】
「嘱望」は、将来に望みをかけることです。
③【正】
傍線部オの「景色を望む」は、「景色を眺める」という意味です。「展望」は「遠くまで見渡すこと、またその眺め」を意味するため、これが正解です。
問2:正解③
<問題要旨>
傍線部A「子規は季節や日々の移り変わりを楽しむことができた」とあるが、それがどういうことかを説明する選択肢を選ぶ問題です。子規が置かれていた状況と、彼にとってガラス障子がどのような意味を持ったのかを本文から正確に読み取ることが求められます。
<選択肢>
①【誤】
「現状を忘れるため」という記述が不適切です。本文には、ガラス障子越しの眺めが「慰めだった」とあり、また視覚が「自身の存在を確認する感覚だった」と述べられており、現実逃避ではなく、むしろ現実の生を確かめるためのものであったことがわかります。
②【誤】
「自己の救済につながっていった」という表現は、本文の「慰めだった」という記述から飛躍しすぎており、大げさな解釈です。
③【正】
本文には「寝返りさえ自らままならなかった」子規にとって、視覚が「自身の存在を確認する感覚だった」とあります。ガラス障子によって外の景色を見られるようになったことで、「季節や日々の移り変わりを楽しむことができた」と続くことから、それが彼にとって「生を実感する契機」であったと読み取れます。この選択肢は、本文の内容を最も的確に説明しています。
④【誤】
「外の世界への想像をかき立ててくれた」という点も間違いではありませんが、本文でより強調されているのは、想像を巡らせることよりも、視覚を通して「自身の存在を確認」し、「生を実感」するという、より直接的な感覚です。
⑤【誤】
ガラス障子が子規の「作風に転機をもたらした」ということについては、本文では一切言及されていません。本文の内容から逸脱した記述です。
問3:正解②
<問題要旨>
傍線部B「ガラス障子は『視覚装置』だといえる。」と筆者が述べる理由を問う問題です。本文で引用されている映画研究者アン・フリードバーグの「窓」に関する論理を、筆者がどのように子規のガラス障子に当てはめているかを正確に理解する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
ガラスに風景を「投影して見る」という記述が不正確です。ガラスは風景を透過させて見せるものであり、スクリーンに映像を映し出すように「投影」するわけではありません。
②【正】
本文では、窓が「風景を切り取る」「フレーム」であり、「外界を二次元の平面へと変える」「スクリーン」であるという考えが紹介されています 。そして、子規のガラス障子も同様に「外界を二次元に変えるスクリーンでありフレームとなった」と述べられています 。この選択肢は、「風景の範囲を定めること(=フレームとして切り取ること)」と「外の世界を平面化されたイメージとして映し出すこと(=スクリーンにすること)」という、本文で示された理由を最も的確に説明しています。
③【誤】
「切り離したり接続したりすることで、視界に入る風景を制御する」という点が不適切です。ガラス障子は視界を恒常的に「接続」するものであり、開閉によって制御する話は本文の趣旨ではありません。
④【誤】
「新たな風景の解釈を可能にする」という点については、本文では触れられていません。本文の趣旨は、風景の解釈の仕方ではなく、風景を見るという行為そのものを可能にする装置、という点にあります。
⑤【誤】
「風景を絵画に見立てる」という解釈は可能ですが、「鑑賞するための空間へと室内を変化させる」という点までが理由の中心ではありません。あくまでガラス障子そのものが、なぜ「視覚装置」と言えるのか、という直接的な理由を説明している②がより適切です。
問4:正解⑤
<問題要旨>
傍線部C「ル・コルビュジエの窓は、確信を持ってつくられたフレームであった」について、その窓の特徴と効果を説明する選択肢を選ぶ問題です。ル・コルビュジエが窓をどのように捉え、設計したかを文章Ⅰから読み解く必要があります。
<選択肢>
①【誤】
風景が「より美しく見えるようになる」とは本文に断定的な記述はなく、筆者の主観的な解釈が含まれています。
②【誤】
本文には、ル・コルビュジエが窓に「換気ではなく『視界と採光』を優先した」とあり、居住性の中でも特に視覚的な側面を重視していたことがわかります。「生活環境が快適なものになる」という説明は、やや広すぎます。
③【誤】
「アスペクト比の変更を目的とした」という記述が不適切です。アスペクト比の変更は、視界と採光を優先した結果生じた「変化」であり、それ自体が目的ではありません。
④【誤】
「風景への没入が可能になる」という点が不適切です。本文では「四方八方に蔓延する景色というものは圧倒的で、焦点をかき、長い間にはかえって退屈なものになってしまう」とあり、むしろ風景との距離をとり、限定することで眺めることを可能にすると論じています。
⑤【正】
本文には、ル・コルビュジエが窓を「換気のためではない」「視界と採光」を優先したものとして捉えていたとあります。また、「四方八方に蔓延する景色」は「焦点をかき」見ることができないため、壁と窓で「限定しなければならない」とあります。その結果として「水平線の広がりを求める」ことができると述べており、この選択肢は、その特徴と効果を的確に説明しています。
問5:正解③
<問題要旨>
文章Ⅱの傍線部D「壁がもつ意味は、風景の観照の空間的構造化である」という記述が、住宅をどのような空間にすることを意味するのかを問う問題です。文章Ⅱにおける「動かぬ視点」や「沈思黙考」といったキーワードと関連付けて理解することが重要です。
<選択肢>
①【誤】
「仕事を終えた人間の心を癒やす空間」という記述は、本文の「沈思黙考の場」「瞑想の時間」という表現の解釈としてはやや限定的すぎます。
②【誤】
「さまざまな方向から景色を眺める自由が失われる」というネガティブな表現が、筆者の論調と合いません。筆者はこの視点の固定を肯定的に捉えています。
③【正】
文章Ⅱでは、住宅を「沈思黙考の場」であり「瞑想の時間」を持つ場所としています。そして、壁で視界を遮り、開口部(窓)を設けることで「風景は一点から見られ、眺められる」とし、これを「動かぬ視点」と呼んでいます。この「視界を制限する構造」が、住む人間を内面的な思索へと導く、と筆者は論じています。この選択肢は、これらの要素を正確に組み合わせて説明しています。
④【誤】
「風景を鑑賞するための空間」という説明は、文章Ⅰの内容には近いですが、文章Ⅱで強調されている「沈思黙考」「瞑想」といった内面的な精神活動の側面が欠けています。
⑤【誤】
「自己省察するための空間」という点も正しいですが、その空間がどのようにして作られるのかという「構造」の説明(固定された視点から風景を眺める、など)が、③に比べて不十分です。
問6:正解(1)④ (2)② (3)③
<問題要旨>
文章Ⅰと文章Ⅱを読んだ生徒たちの話し合いの空欄を埋める問題です。二つの文章の比較読解、筆者の論の展開の理解、そして二つの文章の統合的な解釈が求められます。
<(1)空欄X>
①【誤】
文章Ⅰの引用文に「壁の圧迫感」についての記述はありません。
②【誤】
文章Ⅱの引用文で「どの方角を遮るかが重要視されている」とまでは言えません。北、東、南という具体名は出ていますが、それが議論の中心ではありません。
③【誤】
文章Ⅱの引用文では、窓の機能には直接触れていませんが、壁で視界を閉ざすこと自体が風景を限定するという窓に関連する機能の一部を担っているため、「窓の機能には触れられていない」は不正確です。
④【正】
文章Ⅰの引用文は、壁で視界を遮った後に「水平線の広がりを求める」と、窓(開口部)を設けることの効果まで言及しています。一方、文章Ⅱの引用文は「(中略)」を挟んでおり、窓を設ける意図の部分が省略され、「囲われた庭を形成すること」という壁で「囲う効果」が強調されています。この対比を的確に説明しています。
<(2)空欄Y>
①【誤】
文章Ⅰは、ル・コルビュジエの建築論が「現代の窓の設計に大きな影響を与えた」という歴史的な影響について論じているわけではありません。
②【正】
文章Ⅰは、子規がガラス障子を通して庭や空を眺め、それが慰めや生の実感につながったという「日常においてガラス障子が果たした役割」を描写しています。これを導入として用いることで、ル・コルビュジエの設計思想の核心である「居住者と風景の関係」というテーマを、読者が具体的にイメージしやすくなる構成になっています。
③【誤】
子規の「芸術に対してガラス障子が及ぼした効果」については本文で言及されていません。また、ル・コルビュジエの窓の議論も「美しい空間を演出した」という点に限定されていません。
④【誤】
本文によれば、ル・コルビュジエは「換気」よりも「視界と採光」を優先しており、この選択肢は内容と一致しません。
<(3)空欄Z>
①【誤】
子規の書斎を「宗教建築」とまで解釈するのは飛躍しすぎています。
②【誤】
「仕事の空間」という解釈は、病に伏していた子規の状況や、文章Ⅱの「仕事の時間」と「瞑想の時間」の対比から考えても不適切です。
③【正】
文章Ⅱでは「動かぬ視点」と「沈思黙考の場」が重要な概念として提示されています。病で「自由に動くことができずにいた」子規は、まさに物理的に「動かぬ視点」を持っていました。そして、ガラス障子を通して外を眺めていた書斎は、彼にとって静かに物思いにふける「沈思黙考の場」として機能していたと解釈できます。文章Ⅰの子規の状況と文章Ⅱの概念とを的確に結びつけています。
④【誤】
「見るための機械」「視覚装置」という言葉は文章Ⅰの概念です。空欄Zは「【文章Ⅱ】と関連づけて」という文脈の中にあるため、文章Ⅱの言葉を使って解釈すべきです。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
傍線部A「私はあわてて説明した」とあるが、その時の「私」の様子を説明する問題です。自信作を提出した「私」が、会長から予期せぬ反応をされた際の心情を読み解きます。
<選択肢>
①【正】
「私」は自分の構想に「すこしは晴れがましい気持」になるほどの自信を持っていました。都民の共感を得られるはずだと信じていたため、会長から「一体どういうつもりなのかね」と根本的な趣旨を問われたことに戸惑い、自分の意図を理解してもらおうと必死に説明したと考えられます。この選択肢は、その自信と戸惑いの両方を的確に捉えています。
②【誤】
「名誉を回復しようとしている」という表現が、本文の「私」の慌てた様子とは合いません。「私」は反論しているのではなく、意図を説明して理解を求めている段階です。
③【誤】
「自分の未熟さに あきれつつもどうにかその場を取り繕おうとしている」という部分は不適切です。この時点ではまだ自分の間違いに気づいておらず、自分の構想が正しいという前提で説明しています。
④【誤】
「都民の現実を見誤っていたことに今更ながら気づき」という部分が誤りです。この段階で「私」が気づいたのは、都民の現実ではなく、会社の営利的な目的とのズレです。
⑤【誤】
「テーマとの関連不足を指摘されて」という点が不正確です。会長はテーマとの関連不足というより、構想そのものの目的や効果を問題にしています。
問2:正解⑤
<問題要旨>
傍線部B「私はだんだん腹が立ってきたのである」とあるが、その理由を問う問題です。本文の直後にある「ただただ私は自分の間抜けさ加減に腹を立てていたのであった」という決定的な一文から、「私」の怒りの対象を正確に特定することが鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
「私」は自分の浅ましさではなく、「間抜けさ加減」に腹を立てています。飢えをしのぎたいという欲望自体を嘆いているわけではありません。
②【誤】
本文にはっきりと「この会社のそのような営利精神を憎むのでもない」と書かれており、会社の経営方針に反発しているわけではないことがわかります。
③【誤】
「自分の無能さがつくづく恥ずかしくなってきた」という点が不正確です。怒りの対象は能力の有無ではなく、会社の本当の姿を見抜けなかった自身の「世間知らずさ」や「甘さ」です。
④【誤】
「自分の安直な姿勢に自嘲の念が少しずつ湧いてきた」という記述は近いですが、怒りの対象が「安直な姿勢」というよりは、会社の裏側を全く理解していなかった「愚かさ」そのものに向けられています。
⑤【正】
「私」は、会社が戦時中から営利目的で動いていた「たんなる儲け仕事」であったことに思い至らず、文化国家の建設といった表向きの理念を信じ込んでいました。その純粋な思い込みで「誇りをもって提案した自分の愚かさ」に気づき、自分自身に対して腹を立てたのです。この選択肢は、その気づきのプロセスと怒りの対象を最も正確に説明しています。
問3:正解⑤
<問題要旨>
傍線部C「自分でもおどろくほど邪険な口調で、老爺にこたえていた」とあるが、そこに至る「私」の心の動きを問う問題です。自分自身も飢えているという苦しい状況で、助けを求める老人に対して抱く複雑な感情を読み解く必要があります。
<選択肢>
①【誤】
「私」が老爺に「いら立った」という直接的な記述はありません。むしろ、助けられないことへの「苦痛」を感じています。
②【誤】
「周りの視線を気にして」という点が不適切です。本文には「あたりに人眼がなければ私はひざまずいて」とあり、人目があるからこそ、かえって邪険な態度をとってしまったという心の動きが描かれています。いらだちの対象は自分自身です。
③【誤】
老爺に「自分にはない厚かましさも感じた」という記述は本文になく、勝手な解釈です。「私」は同情こそすれ、相手を批判的に見てはいません。
④【誤】
「どこまでも食い下がる老爺のしつこさに嫌悪感を覚えた」という点は、本文の「私」の心情とは異なります。「私」は罪悪感や苦痛を感じており、嫌悪という感情は見られません。
⑤【正】
「私」は自分も飢えているため、老爺を助けることができません。そのこと自体が「私」にとって「ある苦痛」でした。老爺が必死にすがりつくほど、助けられない自分の苦痛は増していきます。その耐えがたい苦痛から逃れたいという衝動が、結果として「自分でもおどろくほど邪険な口調」という形で現れたのです。この選択肢は、「苦痛」と「逃れたい衝動」という心の動きを的確に捉えています。
問4:正解①
<問題要旨>
傍線部D「それを考えるだけで私は身ぶるいした。」とあるが、その時の「私」の状況と心理を問う問題です。食堂で自分の周りの様々な人々を思い浮かべた「私」が、何に対して「おそろしい結末」を感じたのかを理解することが求められます。
<選択肢>
①【正】
「私」は食堂で、裕福な下宿のあるじや会社の会長と、貧しい老爺や自分自身といった「貧富の差が如実に現れる周囲の人びとの姿」を思い浮かべます。そして、そんな社会の中で、自分が「食物のことばかり妄想し、こそ泥のように芋や柿をかすめている」惨めな存在であることを自覚します。このような生活が続いた先にある「おそろしい結末」を想像し、身ぶるいしたのです。この選択肢は、この一連の思考の流れを正しく説明しています。
②【誤】
「厳しい現実を直視できていないと認識した」という点が誤りです。むしろ、この場面で「私」は自分を取り巻く厳しい現実を痛いほど直視しています。
③【誤】
「その場しのぎの不器用な生き方しかできない我が身を振り返った」という点は正しいですが、身ぶるいした直接の理由は、その生き方の「先にある自身の将来」への恐怖です。その点が明確に述べられている①の方がより適切です。
④【誤】
「さらなる貧困に落ちるしかないことに気づいた」という断定的な記述は、本文の「一体どんなおそろしい結末が待っているのか」という漠然とした不安の表現と少し異なります。
⑤【誤】
「社会の動向を広く認識できていなかった自分を見つめ直した」という点が不適切です。「私」は社会構造を分析しているのではなく、あくまで自分の身の回りの人々の姿を通して、自身の置かれた過酷な状況と未来への不安を感じています。
問5:正解①
<問題要旨>
傍線部E「食えないことは、やはり良くないことだと思うんです」という「私」の発言の意図や背景を説明する問題です。給料額を知らされ、退職を決意した際の「私」の冷静な怒りや諦観を読み取ることが重要です。
<選択肢>
①【正】
給料が日給三円という、生活できないほどの薄給であることを知った「私」は、その瞬間に「此処を辞める決心をかためていた」とあります。彼の怒りは「水のように静かな怒り」と表現されており、感情的なものではありません。将来の昇給の可能性(「これからどんなにでも昇給させる」)や今までの評価(「君にはほんとに期待している」)といった言葉はもはや問題ではなく、ただ「現在食えない」という事実が退職の決定的な理由でした。その事実を「低い声で」淡々と伝えている状況に、この選択肢は合致しています。
②【誤】
「つい感情的に反論した」という部分が、「水のように静かな怒り」「低い声」といった本文の描写と矛盾します。
③【誤】
「ぞんざいな言い方しかできなかった」という点が不適切です。「低い声」で述べられたこの言葉は、ぞんざいというより、冷静で確固たる決意の表れと読めます。
④【誤】
「ぶっきらぼうに述べた」という表現は、冷静さや静かな怒りという本文の描写とはニュアンスが異なります。また、「不当な薄給だという事実をぶつけ」るような攻撃的な態度ではありません。
⑤【誤】
「負け惜しみのような主張」ではありません。これは「私」にとって、退職を決意するに足る正当かつ根本的な理由です。
問6:正解④
<問題要旨>
傍線部F「私はむしろある勇気がほのぼのと胸にのぼってくるのを感じていたのである」とあるが、その時の「私」の心情を説明する問題です。絶望的な状況の中でなぜ「勇気」が湧いてきたのか、その心理的な転換を理解することが求められます。
<選択肢>
①【誤】
「自由に生きようと徐々に思い始めている」という希望に満ちた表現は、「将来の生活に対する懸念」も同時に感じている「私」の心情としては、少し楽観的すぎます。
②【誤】
「にわかに自信が芽生えてきている」という点が不適切です。「勇気」は湧いていますが、それは自信というより、他に道がないという状況から生まれる「覚悟」に近いものです。
③【誤】
「物乞いをしてでも生きていこうと決意を固めている」と限定するのは不適切です。物乞いはあくまで可能性の一つとして挙げられているだけであり、もっと広く「他に新しい生き方を求める」覚悟ができています。
④【正】
「私」が希求していた「人並みな暮しの出来る給料」という最後の望みが絶たれ、絶望がはっきりした瞬間、逆に吹っ切れた状態になります。会社に勤めるという道が完全に断たれたことで、「私は他に新しい生き方を求めるよりなかった」という覚悟が生まれます。将来への「危惧」はありつつも、自分で道を切り拓くしかないという状況が、かえって「私」に前を向くための気力、すなわち「勇気」を与えたのです。この選択肢は、絶望から覚悟、そして勇気へと至る心の動きを正確に捉えています。
⑤【誤】
「課長が自分に期待していた事実があることに自信を得て」という部分が完全に誤りです。課長の言葉は口先だけのものであり、「私」はそれを全く信用していません。
問7:正解(I)③ (II)②
<問題要旨>
【資料】として提示された戦中・戦後の広告を参考に、本文の「焼けビル」との共通点を考え、「私」の「飢え」について考察する問題です。資料と本文を結びつけ、象徴的な言葉の意味を深く読み解く力が試されます。
<(I)空欄I>
①【誤】
「軍事的圧力の影響」というよりは、物資不足という「生活レベル」での影響が共通点として挙げられます。
②【誤】
広告は物資不足の現実を表しており、「倹約の精神が保たれている」という美徳の話ではありません。
③【正】
【資料】の広告は、「戦時中の広告を終戦後に再利用している」ものです。そして、「焼けビル」は、戦争によって焼け落ちた建物が、終戦後もそのまま存在しているものです。両者に共通しているのは、「戦時下に存在した事物が、終戦に伴い社会が変化する中においても生き延びている」という点です。
④【誤】
本文の会社は営利主義であり、「国家貢献を重視する方針が支持されている」わけではありません。
<(II)空欄II>
①【誤】
「会社の象徴」というよりは、「私」自身の状況の象徴です。この一文は、「私」の主観的な情景として描かれています。
②【正】
「私」は焼けビル(会社)を辞めることで、一つの生活と決別しました。しかし、辞めたからといって彼の「飢え」が解消されたわけではありません。むしろ、明日からの食のあてはなくなり、飢えという問題はより切実なものとして「継続」します。空の下に「かなしくそそり立って」いる焼けビルは、この先も続くであろう「私」の「飢えの季節」そのものの象徴として捉えることができます。
③【誤】
「決別の象徴」という点は正しいですが、それだけでは不十分です。重要なのは、決別したにもかかわらず、根本的な問題である「飢え」は続いている、という点です。
④【誤】
「飢えから脱却する勇気を得たことの象徴」ではありません。ビルは「かなしく」そそり立っており、希望よりは、むしろこれから続くであろう苦難を暗示しています。
第3問
問1:正解(ア)③ (イ)④ (ウ)②
<問題要旨>
傍線部の古語や慣用句の解釈を問う問題です。文脈から意味を正確に推測する力が求められます。
<選択肢>
(ア)やうやうさしまはす程に
①【誤】
「池を見回す」という意味はありません。「さしまはす」は物を動かす、操作するという意味です。
②【誤】
「準備する」という意味ではありません。準備はすでに終わっており、船が動き出す場面です。
③【正】
「やうやう」は「次第に、徐々に」という意味です。「さしまはす」は「(ここでは船を)思いのままに動かす、操る」という意味です。したがって、「徐々に船を動かしているうちに」という解釈が最も適切です。
④【誤】
「船の方に集まる」のは船に乗る前の行動であり、この場面とは合いません。
⑤【誤】
「段々と演奏が始まるころ」ではありません。管絃の具は用意されましたが、結局演奏されませんでした。
(イ)ことごとしく歩みよりて
①【誤】
「たちまち」という素早い様子ではなく、「ことごとし」はもったいぶった、大げさな様子を表します。
②【誤】
「焦った様子」ではありません。
③【誤】
「卑屈な態度」という記述は本文にありません。
④【正】
「ことごとし」は「大げさだ、仰々しい」という意味です。良暹に代わって若い僧が、もったいぶった様子で殿上人たちの船に近づいて句を伝えた場面であり、この解釈が最も適しています。
⑤【誤】
「すべてを聞いて」という部分は文脈と合いません。
(ウ)けかへすがへすも
①【誤】
「繰り返すのも」という意味ではありません。
②【正】
「かへすがへすも」は「返す返すも」と書き、「よくよく考えても、どう考えても」という意味の副詞です。直後に「わろきことなり(ひどいことだ)」とあることから、「どう考えてもひどいことだ」と、句を付けられない状況を嘆いていることがわかります。
③【誤】
「句を返すのも」という意味ではありません。
④【誤】
「引き返すのも」という意味ではありません。
⑤【誤】
「話し合うのも」という意味ではありません。
問2:正解③
<問題要旨>
波線部の語句や表現(主に文法)に関する説明の正誤を判断する問題です。助動詞や係助詞などの文法知識が正確に問われます。
<選択肢>
①【誤】
助動詞「らむ」は、現在の原因・理由を推量する助動詞であり、ここでは「(船さしは)若者がよいだろう」という推量を表しています。断定を避けているわけではありません。
②【誤】
丁寧語「侍り」は、地の文で使われている場合、作者から読者への敬意を表しますが、会話文の中では、話し手から聞き手への敬意を表します。ここでは「若き僧」から殿上人への敬意を表しています。
③【正】
「まうけたりけるにや」の「にや」は、断定の助動詞「なり」の連用形「に」+疑問の係助詞「や」で構成されており、「~であったのだろうか」と訳します。良暹が連歌の句を用意していたのだろうか、という作者の想像が挟み込まれた表現です。
④【誤】
助動詞「ぬ」は、ここでは打消の助動詞「ず」の連体形です。「今まで付けないのは(ひどいことだ)」という意味になります。強意の助動詞ではありません。
⑤【誤】
「なり」は、動詞「なる」の連用形です。断定の助動詞「なり」の終止形は「なり」ですが、ここでは文脈上「何事もわからなくなってしまった」という意味であり、推定の助動詞ではありません。
問3:正解⑤
<問題要旨>
第3段落の内容を正確に説明している選択肢を選ぶ問題です。登場人物の行動や心情、会話の内容を正しく読み取ることが求められます。
<選択肢>
①【誤】
船の飾り付けは事前に決まっており、「当日になってようやく」準備し始めたわけではありません。
②【誤】
宇治の僧正が「祈禱を中止し」たという記述はなく、僧たちが庭に集まってきたのは、船遊びの見物をするためです。
③【誤】
良暹は身分を理由に辞退したのではなく、殿上人たちが「後の人や、さらでもありぬべかりけることかなとや申さむ(後世の人が、僧などを船に乗せるべきではなかったと言うかもしれない)」と配慮して乗せなかったのです。
④【誤】
殿上人たちが連歌を行おうとしたのは、歌詠みである良暹がいたからです。「後で批判されるだろうと考え」たわけではありません。
⑤【正】
殿上人たちが「良暹がさぶらふか」と声をかけた際、良暹は「目もなく笑みて、平がりてさぶらひけれ(目を細めて笑って、恐縮して控えていた)」とあります。それを見て、良暹のそばにいた「若き僧」が代わりに「もさに侍り(その通りでございます)」と答えています。この選択肢は、この場面の状況を正しく説明しています。
問4:正解(1)④ (2)① (3)③
<問題要旨>
本文と『散木奇歌集』の文章を関連付けた、生徒と教師の話し合いの空欄を補充する問題です。和歌(連歌)の技法(掛詞)の理解や、本文の展開の理由を深く考察する力が求められます。
<(1)空欄X>
①【誤】
「そこ」に「底」を掛けるという解釈は可能ですが、「昔の面影をとどめている」という内容は句から読み取れません。
②【誤】
「うつばり」に「鬱」を掛けるという解釈は考えられますが、文脈上やや不自然です。
③【誤】
「そこ」に「あなた」という意味を掛けるのは不自然です。また、「あなたの姿が見えたから」魚がいない、という理由付けも唐突です。
④【正】
俊重の句「釣殿の下には魚やすまざらむ(釣殿の下には魚がいないのだろうか)」という問いに対し、俊頼は「うつばりの影そこに見えつつ(梁の影が水底に見えているから)」と返しています。ここでの「うつばり(梁)」は、魚を釣るための「うつはり(=針)」という言葉との掛詞になっています。「梁の影ではなく、釣り針の影が見えているから、魚も警戒して住まないのだろう」という、機知に富んだ付け句になっています。
<(2)空欄Y>
①【正】
良暹の句「もみぢ葉のこがれて見ゆる御船かな」は、紅葉で飾られた船が池に浮かんでいる情景を詠んだものです。「こがれて」は、紅葉が真っ赤に色づく様子を表す「焦がれて」と、船が「漕がれて」進む様子の掛詞になっています。船遊びの場にふさわしい、華やかで動きのある情景を見事に表現しています。
②【誤】
「寛子への恋心を伝えるため」という解釈は、本文の状況から飛躍しすぎています。
③【誤】
頼通や寛子を賛美する意図はあるかもしれませんが、句の解釈として掛詞に触れている①の方が、和歌の技法をふまえたより深い読解と言えます。
④【誤】
マ行の音を重ねる技法(頭韻)はありますが、この句の核心的な技法は掛詞です。
<(3)空欄Z>
①【誤】
殿上人たちの間で「言い争いが始ま」ったという記述はありません。彼らは自分たちの不甲斐なさを嘆いています。
②【誤】
「自身の無能さを自覚させられ」たのは事実ですが、「催しを取り仕切ることも不可能だと悟り」宴を中止したわけではありません。宴が台無しになったのは、結果論です。
③【正】
良暹の見事な句に対して、誰もすぐに次の句を付けることができませんでした。船は意味もなく池をめぐるばかりで(「ごめぐりになりにけり」)、そのうちにすっかり場が白けてしまいました(「今は、付けむの心はなくて、付けでやみなむことを嘆く」)。見物人も帰り、殿上人たちも逃げるように帰ってしまい、結果的に「宴を台無しにしてしまった」のです。この選択肢は、ことの経緯を最も正確に説明しています。
④【誤】
「予定の時間を大幅に超過し」たというより、句が付けられない気まずい時間が流れたことが問題でした。「殿上人たちの反省の場となった」という記述も本文にはありません。
第4問
問1:正解(ア)① (イ)① (ウ)⑤
<問題要旨>
漢文における重要単語の意味を問う問題です。文脈に合った意味を選ぶ基本的な読解力が試されます。
<選択肢>
(ア)無由
①【正】
「由」は「方法、手段」という意味を持つ漢字です。「無由」で「~する方法がない」と訳します。ここでは、臣下が能力を発揮する機会がないことを指しています。
②【誤】
「伝承」という意味はありません。
③【誤】
「原因」という意味は「由」にありますが、ここでは文脈に合いません。
④【誤】
「信用」という意味はありません。
⑤【誤】
「意味」という意味はありません。
(イ)以為
①【正】
「以為」は「おもへらく」と読み、「~と思うに、~と考えるに」という意味の、論を展開する際の書き出しによく使われる言葉です。
②【誤】
「同情するに」という意味ではありません。
③【誤】
「行うに」という意味ではありません。
④【誤】
「目撃するに」という意味ではありません。
⑤【誤】
「命ずるに」という意味ではありません。
(ウ)弁
①【誤】
「弁償」という意味ではありません。
②【誤】
「弁護」という意味ではありません。
③【誤】
「弁解」という意味ではありません。
④【誤】
「弁論」という意味ではありません。
⑤【正】
「弁」は「わきまえる、見分ける」という意味を持ちます。「弁賢」で「賢者を見分ける」という意味になります。「弁別(ベンベツ)」は「物事の違いを見分けること」を意味する熟語です。
問2:正解③
<問題要旨>
傍線部Aの漢文の解釈を問う問題です。「無不」「罔不」という二重否定の句法を正しく理解できるかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
「無能な臣下を退けたい」という部分は本文にありません。
②【誤】
「君主の要請を辞退したい」という部分は本文になく、むしろ逆の内容です。
③【正】
「君者無不思求其賢」は「君主たる者は、その賢者を求めようと思わない者はいない」→「君主は誰もが賢者を求めようと思っている」という意味です。「賢者罔不思効其用」は「賢者は、その用を効そうと思わない者はいない」→「賢者は誰もが自分の能力を役立てたいと思っている」という意味です。両者を合わせると、この選択肢の解釈と一致します。
④【誤】
「自分の意見は用いられまいと思っている」という部分は本文になく、逆の内容です。
⑤【誤】
「賢者の称賛を得ようと思っており」という解釈は不自然です。「求」は人材を求める意です。
問3:正解⑤
<問題要旨>
傍線部Bの返り点の付け方と書き下し文の組み合わせの正誤を判断する問題です。「豈不以~乎(や)」という反語の句法と、「A遠於B(AはBよりも遠し)」という比較の句法を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
「以」の対象が「貴賤相懸たる」のみになっており、不適切です。
②【誤】
「以」の対象が「貴賤相懸たり、朝野相隔たる」までで切れており、不適切です。
③【誤】
「以」の対象が「堂は千里よりも遠き」までになっており、不適切です。
④【誤】
文末が「~深からずや」となっており、反語の形になっていません。
⑤【正】
「豈に~を以てならずや」という反語の形で、「~が原因ではないだろうか、いや、~が原因だ」と訳します。「以」の目的語は「貴賤相懸たり、朝野相隔たり、堂は千里よりも遠く、門は九重よりも深き」まで全体です。書き下し文もこの構造を正しく反映しています。
問4:正解①
<問題要旨>
傍線部C「其猶線与矢也(其れ猶ほ線と矢とのごときなり)」という比喩が何に着目しているかを問う問題です。直後の「線因針而入、矢待弦而発(線は針に因りて入り、矢は弦を待ちて発す)」という部分が比喩の説明になっています。
<選択肢>
①【正】
本文では「線(糸)」は「針」がなければ布に入っていくことができず、「矢」は「弦(弓のつる)」がなければ飛んでいくことができない、と述べられています。つまり、糸や矢は、それを助けるもの(針や弦)がなければ、単独では力を発揮できない、という点に着目した比喩です。
②【誤】
「線」と「矢」が結びつくわけではありません。
③【誤】
「絡み合って力を発揮できない」のではなく、助けられて力を発揮します。
④【誤】
「助け合ったとしても力を発揮できない」のではなく、助けが必要であると述べています。
⑤【誤】
「助けを借りなくても力を発揮できる」のではなく、助けがなければ力を発揮できません。
問5:正解③
<問題要旨>
空欄Xに入る語と、それを含む句の書き下し文の組み合わせを選ぶ問題です。文脈から空欄に入るべき語(ここでは副詞)を推測し、正しい書き下し文を選ぶ必要があります。
<選択肢>
①【誤】
「不」を入れると「類を以てせずして至ればなり(仲間によらないでやって来るからだ)」となり、文脈と逆の意味になります。
②【誤】
「何」を入れると「何ぞ類を以て至らんや(どうして仲間によってやって来るだろうか、いや、来ない)」となり、反語で逆の意味になります。
③【正】
直前の「水は湿(うるほ)へるに流れ、火は燥(かは)けるに就く」という「類は友を呼ぶ」のたとえを受けています。したがって、「賢者も必ずその仲間や類によって集まってくるものである」という文脈になるのが自然です。「必」は「必ず」と読み、この文脈に完全に合致します。
④【誤】
「誰」を入れると「誰か類を以て至らんや(誰が仲間によってやって来るだろうか、いや、誰も来ない)」となり、反語で逆の意味になります。
⑤【誤】
「嘗」を入れると「嘗て類を以て至ればなり(以前、仲間によってやって来たからだ)」となり、過去のことに限定されてしまい、普遍的な理を述べている文脈には合いません。
問6:正解④
<問題要旨>
傍線部E「自然之理也(自然の理なり)」がどういう意味を表しているかを問う問題です。直前の「水流湿、火就燥(水は湿へるに流れ、火は燥けるに就く)」という比喩が何を言おうとしているのかを理解することが鍵です。
<選択肢>
①【誤】
「相反する性質のもの」の話ではなく、「似た性質のもの」が集まるという話です。
②【誤】
「互いに打ち消し合う」のではなく、互いに引き寄せ合うという話です。
③【誤】
「大きな作用を生み出す」という点が主題ではありません。主題は「集まる」という性質そのものです。
④【正】
「水は湿った場所へ」と流れ、「火は乾燥した場所へ」と燃え広がるように、「性質を同じくするものは、自然と互いに求め合って集まるものである」というのが、この部分で述べられている「自然の道理」です。
⑤【誤】
「長所と短所がある」という話はしていません。
問7:正解④
<問題要旨>
【予想問題】に対する【模擬答案】で作者が述べた答えの内容を要約する問題です。文章全体の論旨、すなわち「君主と賢者が出会えない原因」と「その解決策」を正確に把握する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
解決策として「採用試験をより多く実施する」とは述べていません。
②【誤】
原因を「君主と賢者の心が離れているため」とは述べていません。物理的な距離を問題にしています。
③【誤】
「党派に加わらず、自分の信念を貫いているかどうかを見分けるべき」とは述べていません。むしろ仲間(グループ)の重要性を説いています。
④【正】
作者は、君主と賢者が出会えない原因を「貴賤相懸」「朝野相隔」といった、身分や物理的な隔たりにあると指摘しています(見つけ出すことができない)。その解決策として、「族類(同じ仲間、グループ)を以て之を求め」させ、「推薦せしむるのみ」と述べています。つまり、賢者のこと(居場所や能力)は賢者の仲間が一番よく知っているのだから、そのグループを見極めて、そこから人材を推薦させることが最善の方法である、と結論付けています。この選択肢は、その原因と解決策を最も的確に要約しています。
⑤【誤】
解決策として「王城の門を開放して、やって来る人々を広く受け入れるべき」とは述べていません。より具体的な方法として「推薦」を挙げています。