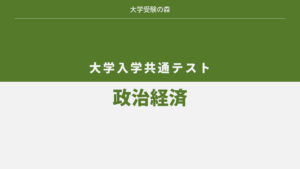解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
2022年4月からの成人年齢引き下げに伴う、18歳以上の若者に関わる日本の法制度についての理解を問う問題です。選挙権、国民投票、少年法、民法(契約)など、多岐にわたる分野の正確な知識が求められます。
<選択肢>
①【正】
公職選挙法では、選挙権を持つ18歳以上の者は、選挙運動期間中に電話をかけて特定の候補者への投票を依頼するなどの選挙運動を行うことが認められています。ただし、戸別訪問や買収などは禁止されています。
②【正】
日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)において、国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有すると定められています。
③【誤】
日本の少年法では、14歳に満たない者の行為は、刑事罰の対象とはなりません。これは「刑事未成年」と呼ばれます。18歳未満の少年であっても、14歳以上であれば捜査の対象となり、家庭裁判所の審判を経て、保護処分や検察官送致(逆送)の対象となることがあります。したがって、「18歳未満」が刑事罰の対象とならないわけではありません。
④【正】
民法では、18歳未満の者(未成年者)が親権者などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、原則として本人または法定代理人が取り消すことができます(未成年者取消権)。これは、取引の経験や知識が乏しい未成年者を保護するための制度です。
問2:正解②
<問題要旨>
選挙制度の違いが選挙結果にどのように影響するかを、具体的なモデルケースを用いて分析する問題です。大選挙区制と小選挙区制それぞれの特徴(特に、得票率と議席獲得率の関係、死票の数)を正確に理解し、計算する能力が求められます。
<選択肢>
まず、変更前の選挙結果(各選挙区で上位2名が当選)を分析します。
・選挙区a:C党(65票)、B党(25票)が当選
・選挙区b:C党(45票)、B党(30票)が当選
・選挙区c:C党(65票)、B党(20票)が当選
・選挙区d:A党(60票)、B党(25票)が当選
・選挙区e:A党(40票)、B党(35票)が当選
この結果、当選者数はA党が2名、B党が5名、C党が3名となります。
各党の合計得票数は、A党150票、B党135票、C党215票です。
得票数の合計が最も少ないB党(135票)が、当選者数では最も多い5議席を獲得しています。したがって、空欄【ア】には「多い」が入ります。
次に、選挙制度が小選挙区制(各選挙区で最多得票の1名が当選)に変更された場合を考えます。
・当選者:a(C党), b(C党), c(C党), d(A党), e(A党)
・当選者数はA党が2名、B党が0名、C党が3名となります。
死票の数を計算します。死票とは、当選者以外に投じられた票のことです。
・変更前の死票数:全投票数500 – 全当選者の得票数合計(65+25+45+30+65+20+60+25+40+35) = 500 – 410 = 90票
・変更後の死票数:全投票数500 – 全当選者の得票数合計(65+45+65+60+40) = 500 – 275 = 225票
死票の数は90票から225票に増加します。したがって、空欄【イ】には「増加」が入ります。
最後に、変更後の得票数と当選者数の関係を見ます。
得票数の合計が最も少ないB党(135票)の当選者数は0名となり、最も少なくなっています。したがって、空欄【ウ】には「少ない」が入ります。
以上の分析から、ア:多い、イ:増加、ウ:少ないの組み合わせである②が正解となります。
問3:正解⑦
<問題要旨>
地方自治における住民の政治参加の仕組みについて、直接請求権と請願権の違いを理解しているかを問う問題です。それぞれの制度の目的、要件、根拠法規についての正確な知識が必要です。
<選択肢>
①【誤】
ア:条例の制定を求める手続きは「直接請求」の一つです。「情報公開」は行政情報の開示を求める制度であり、異なります。
②【誤】
アが誤りです。
③【誤】
アが誤りです。
④【誤】
アが誤りです。
⑤【誤】
イ:条例の制定・改廃を請求するために必要な署名の数は、地方自治法に基づき、その地方公共団体の有権者の「50分の1」以上と定められています。「3分の1」は、議会の解散請求や、議員・首長の解職請求(リコール)に必要な署名数です。
⑥【誤】
イが誤りです。
⑦【正】
ア:住民が一定数の署名を集めて条例の制定・改廃や議会の解散などを請求する権利を「直接請求」といいます。
イ:そのうち、条例の制定・改廃請求に必要な署名数は、有権者の「50分の1」以上です。
ウ:憲法第16条は「請願権」を保障しており、これに基づき誰でも国や地方公共団体に対して要望を述べることができます。直接請求のような法的拘束力はありませんが、年齢などに関係なく行える簡易な意思表示手段です。
以上のことから、すべての組み合わせが正しいです。
⑧【誤】
イが誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
日本の裁判員制度について、アメリカの陪審制度やドイツの参審制度と比較しながら、その特徴を正確に理解しているかを問う問題です。裁判員の選任方法、評議への参加範囲(事実認定と量刑判断)がポイントとなります。
<選択肢>
①【誤】
イ、ウが誤りです。日本の裁判員は有罪・無罪の判断だけでなく、量刑の判断にも加わります。
②【誤】
イが誤りです。日本の裁判員制度では、有罪・無罪の判断は裁判官との合議で行います。
③【正】
ア:日本の裁判員は、アメリカの陪審員と同様に、特定の刑事事件ごとに、裁判員候補者名簿の中からくじなどで選ばれます。
イ:有罪か無罪かの判断(事実認定)は、裁判員と裁判官が共同で評議を行って決定します。
ウ:どのような刑罰を科すかという量刑の判断にも、裁判員は裁判官とともに加わります。
以上の説明はすべて日本の裁判員制度の特徴と合致しています。
④【誤】
ウが誤りです。日本の裁判員は量刑の判断に加わります。
⑤【誤】
ア、イ、ウすべてが誤りです。
⑥【誤】
ア、イが誤りです。
⑦【誤】
ア、ウが誤りです。
⑧【誤】
アが誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
複数の資料(グラフ、表)から日本の労働市場の状況を読み取り、分析する問題です。有効求人倍率、完全失業率、雇用のミスマッチといった基本的な労働経済の用語を理解し、資料と結びつけて考察する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。資料2で「事務的職業」の有効求人倍率は1を下回っており、求職者数に対して求人数(労働力の需要量)が不足している状況です。したがって「過剰になって」は誤りです。
②【誤】
イ、ウが誤りです。ウについて、資料3を見ると、2002年~2006年にかけて有効求人倍率が低迷しているのは「フルタイム」であり、これが就職を難しくした要因と考えられます。
③【正】
ア:資料1を見ると、2014年以降、有効求人倍率は1.0倍を常に「上回って」います。これは、求職者数を求人数が上回っている状態(売り手市場)を示します。
イ:資料2から、職種によるミスマッチが読み取れます。「事務的職業」は求人数が少なく(労働力の需要が不足)、一方で「輸送・機械運転の職業」は求職者数が少なく(労働力の供給が不足)なっています。会話文の「職種によるミスマッチ」という文脈から、両方の空欄に「不足して」が入るのが適切です。
ウ:資料1で2002~2006年は完全失業率が高水準です。資料3を見ると、この期間、パートタイムの有効求人倍率は比較的高い一方、「フルタイム」の有効求人倍率は1倍を大きく下回り、低い水準で推移しています。このことから、フルタイム雇用の需要が不足していたことが、当時の高い失業率の一因と分析できます。
④【誤】
イが誤りです。ウについて、資料3で低迷しているのは「フルタイム」の有効求人倍率です。
⑤【誤】
ア、イが誤りです。
⑥【誤】
ア、イ、ウすべてが誤りです。
⑦【誤】
アが誤りです。
⑧【誤】
ア、ウが誤りです。
問6:正解②
<問題要旨>
家計に関するデータから、可処分所得、平均消費性向、エンゲル係数を計算し、比較する問題です。それぞれの指標の定義を正確に理解し、表の数値を正しく用いて計算する能力が求められます。
<選択肢>
まず、各指標の計算式を確認します。
・可処分所得 = 実収入 – 非消費支出
・平均消費性向 = 消費支出 ÷ 可処分所得
・エンゲル係数(%) = (食料費 ÷ 消費支出) × 100
空欄【ア】について、例aと例bの平均消費性向を計算して比較します。
・例aの可処分所得 = 550 – 150 = 400(千円)
・例aの平均消費性向 = 300 ÷ 400 = 0.75
・例bの可処分所得 = 310 – 60 = 250(千円)
・例bの平均消費性向 = 180 ÷ 250 = 0.72
比較すると、0.75 > 0.72 なので、「例a」の方が高くなります。
空欄【イ】について、例cのエンゲル係数を計算します。
・例cのエンゲル係数 = (30 ÷ 100) × 100 = 30 (%)
したがって、アには「例a」、イには「30%」が入る組み合わせが正解です。
①【誤】
イの計算が誤っています。
②【正】
上記の計算結果と一致します。
③【誤】
アの判断とイの計算が誤っています。
④【誤】
アの判断が誤っています。
問7:正解⑤
<問題要旨>
日本の社会保障制度の4つの柱のうち、社会保険、公的扶助、社会福祉について、それぞれの制度の目的、財源、対象者の基本的な特徴を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
ア【正】
社会保険制度(医療保険、年金保険、雇用保険など)は、加入者(被保険者)や事業主が事前に保険料を拠出し、病気、高齢、失業といった保険事故が発生した際に、保険給付を行う仕組みです。記述の内容は正しいです。
イ【誤】
公的扶助制度(生活保護制度など)は、生活に困窮する人々に対して、最低限度の生活を保障するための制度です。その財源は、保険料ではなく、国や地方公共団体が負担する**税金(公費)**でまかなわれます。したがって、「保険料から」という部分が誤りです。
ウ【正】
社会福祉制度は、高齢者、障害者、児童など、社会生活を送る上で支援を必要とする人々(社会的弱者)に対して、施設サービスや在宅サービスなどを提供する制度です。記述の内容は正しいです。
以上のことから、正しい記述はアとウの組み合わせとなります。
問8:正解④
<問題要旨>
近年に新設された日本の行政機関について、その設置目的と所属する府省を正しく理解しているかを問う問題です。比較的新しい時事的な知識が求められます。
<選択肢>
①【正】
消費者庁は、食品表示偽装問題などを受けて消費者行政を一元化するため、2009年に内閣府の外局として設置されました。
②【正】
復興庁は、東日本大震災からの復興を強力に推進するため、2012年に内閣に設置された時限的な組織です。
③【正】
デジタル庁は、日本の行政のデジタル化を推進する司令塔として、2021年に内閣に設置されました。
④【誤】
こども家庭庁は、子ども政策の司令塔として、2023年4月に内閣府の外局として設置されました。厚生労働省や内閣府などに分散していた子ども関連の部署を統合したものですが、組織としては厚生労働省ではなく内閣府に置かれています。したがって、この記述は誤りです。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
社会学者マックス・ヴェーバーが『職業としての政治』で述べた、近代国家の本質的な特徴についての文章を読解する問題です。国家を「正当な物理的暴力行使の独占」という観点から定義した彼の思想を、文章から正確に読み取る力が求められます。
<選択-肢>
①【誤】
本文には「もちろん暴力行使は、国家にとってノーマルな手段でもまた唯一の手段でもない」と明記されており、暴力行使が国家の通常かつ唯一の手段であるという記述とは矛盾します。
②【誤】
本文には「過去においては、氏族(ジッペ)を始めとする多種多様な団体が、物理的暴力をまったくノーマルな手段として認めていた」とあり、国家誕生以前にも暴力行使が認められていた団体があったことが示されています。
③【正】
本文の核心部分である「国家とは、ある一定の領域の内部で・・・(略)・・・正当な物理的暴力行使の独占を(実効的に)要求する人間共同体である」「国家が暴力行使への『権利』の唯一の源泉とみなされている」という記述と合致しており、本文から読み取れる内容として最も適当です。
④【誤】
「国家の許容した範囲内でのみ」暴力行使が認められるのは、「今日では」「現代に特有な現象」と述べられており、「過去」の話ではありません。
問2:正解④
<問題要旨>
日本の社会保険制度のうち、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)について、それぞれの保険料の負担者が誰であるか、またその理由を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
ア(雇用保険):
雇用保険は、労働者の失業時の生活安定や再就職促進を目的としています。失業の原因は、個々の企業の経営判断や労働者自身の都合だけでなく、景気変動といった社会経済的な要因も大きく関わります。そのため、そのリスクは当事者である事業主と労働者だけでなく、国(政府)も一体となって負担すべきという考え方に基づいています。したがって、財源は**事業主、労働者、政府(国庫)**の三者が負担します。この趣旨を説明しているのは記述bです。
イ(労災保険):
労災保険は、業務上または通勤中の災害による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して給付を行う制度です。業務災害の責任は、労働者を使用して利益を得ている事業主にあるという「使用者責任」の考え方に基づき、保険料は全額事業主が負担することになっています。この趣旨を説明しているのは記述dです。
したがって、アにb、イにdが入る組み合わせが正解となります。
問3:正解⑤
<問題要旨>
日本の公務員の労働基本権が制約されていることについて、その根拠となった最高裁判例(全農林警職法事件)と、制約の代償措置とされる制度を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
ア:判例で禁止の対象として言及されているのは、ストライキなどの「争議行為」です。労働者の団結を妨げるなどの使用者の行為は「不当労働行為」と呼ばれ、文脈に合いません。よって【b 争議行為】が当てはまります。
イ:公務員の労働基本権制約の代償措置として、国家公務員の給与水準などを国会および内閣に勧告する権限を持つ中立的な第三者機関は「人事院」です。内閣人事局は、幹部人事の一元管理などを行う機関です。よって【c 人事院】が当てはまります。
ウ:Xの発言は、判決を肯定する立場からのものです。日本の現行法では、一般職の国家公務員は、団結権(職員団体を結成する権利)と団体交渉権(ただし交渉のみで協約締結権はない)は認められていますが、争議権は認められていません。記述eは、この現状を「やむをえない」とする内容であり、Xの発言の趣旨と合致しています。記述fの「職員団体をつくることができない」は、団結権が認められている現状と異なるため誤りです。よって【e】が当てはまります。
以上のことから、ア:b、イ:c、ウ:eの組み合わせである⑤が正解です。
問4:正解②
<問題要旨>
地方自治の基本原則である「地方自治の本旨」と、国と地方の役割分担について定めた地方自治法の条文の趣旨を理解しているかを問う問題です。団体自治と住民自治の違い、補完性の原則の理解がポイントです。
<選択肢>
ア:地方自治の本旨は、「住民自治」と「団体自治」の二つの要素からなります。このうち、国から独立した法人格を持つ地方公共団体が、その地域の行政を自主的に行うべきという考え方を「団体自治」といいます。「住民自治」は、その地域の住民が地方自治に参加し、その意思に基づいて運営されるべきという考え方です。したがって、【a 団体自治】が当てはまります。
イ:地方分権一括法による改正後の地方自治法第1条の2は、国と地方公共団体の役割分担について定めています。その内容は、「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本」とし、国は「地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない」というものです。これは、まず基礎的な自治体が行政を担い、それで対応できない部分をより広域の自治体や国が補うという「補完性(補充性)の原則」を示しています。この趣旨を説明しているのは記述dです。記述cは、国が主導する中央集権的な考え方であり、この条文の趣旨とは逆です。
したがって、アにa、イにdが入る組み合わせが正解となります。
問5:正解⑤
<問題要旨>
日本国憲法第20条が保障する「信教の自由」と、その中に含まれる「政教分離原則」について、その内容を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
ア【正】
信教の自由には、①内心における信仰の自由、②礼拝や布教などを行う宗教的行為の自由、③宗教団体を設立・加入する宗教的結社の自由、の3つの側面が含まれると解されています。したがって、この記述は正しいです。
イ【誤】
憲法第20条第1項後段には「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と明確に規定されています。したがって、この記述は誤りです。
ウ【正】
憲法第20条第3項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定されています。これは、国や地方公共団体が特定の宗教と結びつくことを禁じる政教分離原則の核心部分です。したがって、この記述は正しいです。
以上のことから、正しい記述はアとウの組み合わせとなります。
問6:正解④
<問題要旨>
消費者保護の仕組みの一つである「消費者団体訴訟制度」について、その制度が導入された背景やねらいを、与えられたメモから正確に読み取る問題です。文章の趣旨を正しく把握する読解力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
メモの「2. 改正の背景」には、「行政規制だけでは、被害の未然防止や拡大防止が十分にできなかった」とあり、行政規制の「限界」が背景として挙げられています。「過剰」であったわけではありません。
②【誤】
この制度は、事業者の不当な行為を差し止めるためのものであり、事業者に対する規制を強化するものです。したがって、「規制緩和の一環」という記述は正反対であり、誤りです。
③【誤】
メモの「1. 改正の内容」には、「従来の行政による規制(行政規制)に加え、・・・(略)・・・制度を導入する」とあります。つまり、行政規制がなくなったわけではなく、適格消費者団体が「のみ」が取り組むことになったわけではありません。
④【正】
メモの「3. 消費者団体訴訟制度を導入するねらい」に、「行政機関の人員や予算などの資源(行政資源)を、より迅速な対応が求められる重大な消費者被害に集中させることが可能になるという副次的な効果も期待できる」と明記されています。記述の内容は本文と完全に一致します。
問7:正解②
<問題要旨>
株式会社を中心とした会社形態における出資者の責任の範囲と、現代企業に求められる社会的責任(CSR)についての理解を問う問題です。有限責任と無限責任の違い、合同会社と合名会社の区別、企業の社会的責任の概念がポイントです。
<選択肢>
ア:株式会社の株主は、会社が倒産するなどして債務を負った場合でも、自分が出資した金額(株式の引受価額)の範囲内でしか責任を負いません。これを「有限責任」といいます。したがって、【a 出資額をこえた責任は負わない】が当てはまります。
イ:会社形態のうち、株式会社と同様に、すべての出資者(社員)が有限責任であるのは「合同会社」です。「合名会社」の社員は、会社の債務に対して無限に責任を負う「無限責任社員」で構成されます。したがって、【c 合同会社】が当てはまります。
ウ:株主の利益(株価の上昇や配当)のみを優先する経営が、環境破壊や劣悪な労働環境など、社会にとって望ましくない事態を引き起こす可能性があります。こうした事態を避けるために、企業が株主だけでなく、従業員、取引先、消費者、地域社会といった幅広い利害関係者(ステークホルダー)の利益を考慮し、社会的な責任を果たすべきだという考え方が「企業の社会的責任(CSR)」です。この考え方を導入することは、会話文中の問題意識に対する有効な対策となります。記述fはこの内容を説明しています。記述eの「株主代表訴訟」は、株主が会社に代わって経営陣の責任を追及する制度であり、文脈が異なります。したがって、【f】が当てはまります。
以上のことから、ア:a、イ:c、ウ:fの組み合わせである②が正解です。
問8:正解④
<問題要旨>
2009年に改正された臓器移植法について、改正前と改正後の制度内容を正確に比較し、読み取る問題です。特に、本人の意思表示と家族の承諾の関係がどのように変化したかを注意深く読み解く必要があります。
<選択肢>
ア【正】
改正前の制度では、本人が臓器提供の意思を表示していても家族が拒めば提供できません。つまり、臓器を提供しないという意思は(表示がなくても家族の拒否によって)尊重されます。改正後の制度では、本人が「臓器を提供しない意思」を表示している場合についての記述はありませんが、これは提供しない意思が最優先されることを前提としています。したがって、改正の前後を通じて、本人が臓器を提供しないと明確に意思表示していれば、その自己決定は家族の意思にかかわらず尊重される仕組みであると読み取れます。
イ【正】
改正後の制度では、「本人の臓器提供の意思は不明」なときでも、「家族が書面で臓器提供を承諾するとき」に臓器摘出が可能になりました。これは年齢にかかわりません(ただし15歳未満の場合は、本人が提供しない意思を表示していないことが条件)。そして、アで確認したように、本人が提供しない意思を表示している場合は摘出できません。したがって、この記述は正しいです。
ウ【誤】
改正後の制度でも、臓器を摘出できる条件は「本人が書面で臓器を提供する意思を表示しており家族が拒まないとき」とされています。つまり、本人が提供の意思を示していても、家族が反対(拒否)すれば臓器摘出はできません。したがって、本人の自己決定が家族の意思にかかわらず実現されるわけではなく、この記述は誤りです。
以上のことから、正しい記述はアとイの組み合わせとなります。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
一国の経済規模を示す指標であるGDP(国内総生産)が、各生産段階で生み出される「付加価値」の合計であることを、具体的なモデルケースを通じて計算する問題です。付加価値の計算方法(生産総額 – 中間投入額)を理解しているかが問われます。
<選択肢>
まず、表の空欄ア、イ、ウを埋めます。
・ア(製粉会社の中間投入物):製粉会社は農家から50万円で小麦を購入しているので、中間投入物の額は50万円です。
・イ(製パン会社の中間投入物):製パン会社は製粉会社から150万円で小麦粉を購入しているので、中間投入物の額は150万円です。
・ウ(製粉会社の付加価値額):生産総額150万円 – 中間投入物50万円 = 100万円です。
次に、問題で問われている空欄エとオを計算します。
・エ(製パン会社の付加価値額):生産総額400万円 – 中間投入物150万円 = 250万円です。
・オ(この国のGDP):GDPは、国内で生み出された付加価値の合計額です。
GDP = 農家の付加価値 + 製粉会社の付加価値 + 製パン会社の付加価値
GDP = 50万円 + 100万円 + 250万円 = 400万円です。
(別解として、GDPは最終生産物(この場合は消費者に販売されたパン)の総額とも等しくなるため、400万円と計算することもできます。)
したがって、エが250、オが400となる組み合わせが正解です。
問2:正解⑥
<問題要旨>
国民所得(NI)の概念と、国民経済計算の基本的な考え方である「三面等価の原則」についての理解を問う問題です。GDP、GNI、NIといった各指標の関係性と、生産・分配・支出の各側面からの捉え方がポイントです。
<選択肢>
ア:GDPに「海外からの純所得」を加えるとGNI(国民総所得)になります。そこから「固定資本減耗」を引くとNNP(国民純生産)となり、さらに「間接税を差し引き、補助金を加え」たものがNI(国民所得)です。したがって、【b NI(国民所得)】が当てはまります。
イ:国民所得は、①どれだけ生産されたか(生産面)、②誰に分配されたか(分配面)、③何に使われたか(支出面)という3つの側面から捉えることができます。会話の流れから、生産、分配と並ぶもう一つの側面を問うているため、【c 支出】が当てはまります。「投資」は支出の一部です。
ウ:生産面から捉えた国民所得(生産国民所得)、分配面から捉えた国民所得(分配国民所得)、支出面から捉えた国民所得(支出国民所得)は、事後的に見れば必ず等しくなります。これを「三面等価の原則」といいます。したがって、【f どの面からみた総額もすべて等しい】が正しい記述です。
以上のことから、ア:b、イ:c、ウ:fの組み合わせである⑥が正解です。
問3:正解④
<問題要旨>
市場メカニズムがうまく機能せず、資源配分が効率的でなくなる「市場の失敗」の具体例を正しく選択する問題です。独占・寡占、外部不経済、情報の非対称性などが代表的な例です。
<選択肢>
ア【正】
市場で特定の企業による独占や少数の企業による寡占が進むと、価格競争が働かなくなり、企業が自由に価格を設定できる(価格支配力をもつ)ようになります。その結果、価格が高止まりしたり、生産量が過少になったりするため、これは「市場の失敗」の典型例です。
イ【正】
ある経済主体の活動が、市場での取引を介さずに、他の経済主体に影響を及ぼすことを「外部性」といいます。特に、公害のように不利益を与える場合は「外部不経済」と呼ばれ、社会全体で見た場合の最適な生産量よりも過大に生産されてしまうため、「市場の失敗」の一例です。
ウ【誤】
市場で取引を行う売り手と買い手が、取引対象に関する情報を等しく持っている状態は、「情報の対称性」と呼ばれ、市場メカニズムが効率的に機能するための理想的な条件の一つです。逆に、売り手だけが商品の欠陥を知っている場合のように、情報が一方に偏っている「情報の非対称性」が、「市場の失敗」を引き起こす原因となります。したがって、この記述は市場が成功している状態を示しており、誤りです。
以上のことから、正しい記述はアとイの組み合わせとなります。
問4:正解⑦
<問題要旨>
名目GDPと実質GDPの関係から、物価変動の指標であるGDPデフレーターを計算し、その結果から物価の動向を判断する問題です。GDPデフレーターの計算式を正しく理解し、適用できるかが問われます。
<選択肢>
GDPデフレーターの計算式は以下の通りです。
GDPデフレーター = (名目GDP ÷ 実質GDP) × 100
問題で与えられた数値を用いて、2020年のGDPデフレーターを計算します。
・ア:(2020年の名目GDP 540兆円 ÷ 2020年の実質GDP 360兆円) × 100
= 1.5 × 100 = 150
したがって、アには数値dの150が入ります。
次に、物価の動向を判断します。
GDPデフレーターは基準年を100として物価水準を示します。
・基準年である2010年のGDPデフレーターは、(名目400兆円 ÷ 実質400兆円) × 100 = 100 です。
・2020年のGDPデフレーターが150ということは、基準年である2010年と比較して物価が1.5倍に上昇したことを意味します。
したがって、イには語句eの「上昇」が入ります。
よって、ア:d、イ:eの組み合わせである⑦が正解です。
問5:正解③
<問題要旨>
企業の排出する汚染物質の総量を確実に削減するための規制内容を、論理的に考察する問題です。汚染物質の総量が「排出量 × 濃度」で計算されることを踏まえ、いかなる状況でも規制前の総量を下回る選択肢を見つけ出す必要があります。
<選択肢>
まず、規制導入前の汚染物質の総量を計算します。
・企業A:100トン × 1% (0.01) = 1トン
・企業B:500トン × 2% (0.02) = 10トン
・合計:1 + 10 = 11トン
この11トンを「確実に」下回る規制を探します。
① 汚染水の濃度を0.1%に制限しても、排出量が制限されていないため、例えば企業Bが12,000トン排出すれば、汚染物質は12トンとなり、規制前を上回る可能性があります。不確実です。
② 汚染水の排出量を制限しても、濃度が制限されていないため、例えば企業Aが濃度を10%にすれば汚染物質は5トン、企業Bが濃度を5%にすれば10トンとなり、合計15トンで規制前を上回る可能性があります。不確実です。
③ 濃度と排出量の両方に上限を設けています。この規制下で排出されうる最大の汚染物質量を計算します。
・企業Aの最大値:120トン × 1.5% (0.015) = 1.8トン
・企業Bの最大値:600トン × 1.5% (0.015) = 9.0トン
・合計の最大値:1.8 + 9.0 = 10.8トン
この規制下では、汚染物質の総量は最大でも10.8トンにしかならず、いかなる場合でも規制前の11トンを確実に下回ります。
④ 濃度と排出量の両方に上限を設けています。この規制下で排出されうる最大の汚染物質量を計算します。
・企業Aの最大値:300トン × 1% (0.01) = 3トン
・企業Bの最大値:400トン × 2% (0.02) = 8トン
・合計の最大値:3 + 8 = 11トン
この場合、汚染物質の総量が規制前と同じ11トンになる可能性があるため、「確実に減少させる」という条件を満たしません。
したがって、③が正解です。
問6:正解④
<問題要旨>
景気循環の過程におけるGDP、民間設備投資、民間部門の在庫の動きの特徴を理解し、それぞれの対前年増減額を示すグラフを正しく対応させる問題です。景気変動に対する各指標の感応度や変動幅の違いに着目することがポイントです。
<選択肢>
景気循環における各指標の一般的な動きは以下の通りです。
・民間部門の在庫:景気後退の初期に意図せざる在庫増(売れ残り)が起こり、不況期には生産調整によって在庫が減少(在庫調整)します。変動のサイクルが比較的短く、景気の先行指標となることがあります。
・民間設備投資:企業の景況感に大きく左右されるため、景気変動に対して非常に敏感に反応し、増減の振れ幅が最も大きくなる傾向があります。
・GDP:個人消費や政府支出など比較的安定した項目も含むため、設備投資などに比べると変動は緩やかになります。
グラフの特徴と照らし合わせます。
・資料4:縦軸の目盛りが最も大きく(-10兆円~+25兆円)、変動の振れ幅が非常に大きいことから、これは景気に敏感な民間設備投資と判断できます。
・資料2:縦軸の目盛りが最も小さく(-1兆円~+3兆円)、変動幅が小さいことから、これは民間部門の在庫と判断できます。1991年のバブル崩壊後の景気後退局面で、在庫の増加額が減少し、1994年にはマイナス(在庫が取り崩されている)になっている点も特徴と合致します。
・資料3:変動幅が資料2と4の中間であり、経済全体の動きを反映するGDPと判断するのが最も妥当です。
以上の分析から、ア:民間部門の在庫、イ:民間設備投資、ウ:GDPの組み合わせである④が正解となります。
問7:正解⑥
<問題要旨>
国際貿易の理論である「比較優位」について、生産に必要な労働力の量(生産性)の変化によって、どちらの国が比較優位を持つかが変わる条件を計算する問題です。機会費用の概念を正しく理解し、計算できるかが問われます。
<選択肢>
比較優位は、ある財を生産する際の「機会費用」(その財を1単位生産するために諦めなければならない別の財の量)が他国より小さい場合に存在します。
まず、自動車1単位を生産するための機会費用を、オレンジの単位で計算します。
機会費用 = (自動車1単位の生産に必要な労働力) ÷ (オレンジ1単位の生産に必要な労働力) で計算される生産比の逆数、つまり、(オレンジ1単位生産に必要な労働力) ÷ (自動車1単位生産に必要な労働力) となります。
技術革新以前:
・A国の機会費用:5人 ÷ 20人 = 0.25単位のオレンジ
・B国の機会費用:4人 ÷ 10人 = 0.4単位のオレンジ
A国の方が機会費用が小さい(0.25 < 0.4)ため、A国が自動車生産に比較優位を持っています。
技術革新以後:
問題は「自動車生産に比較優位をもつ国が変わる」場合を問うています。つまり、B国がA国よりも機会費用が小さくなる(B国が比較優位を持つ)条件を探します。
・A国の機会費用 > B国の機会費用
・(5人 ÷ ア人) > 0.4
この不等式を解くと、
・5 > 0.4 × ア
・12.5 > ア
つまり、アが12.5人未満のときに、A国の機会費用がB国を上回り、比較優位がB国に移ります。
選択肢の数値を検討します。
・a (15):12.5より大きいので、比較優位は変わらない。
・b (10):12.5より小さいので、比較優位はB国に変わる。
・c (5) :12.5より小さいので、比較優位はB国に変わる。
したがって、当てはまる数値はbとcの組み合わせです。
問8:正解②
<問題要旨>
ある財(生鮮野菜)の代替財(冷凍野菜)が市場に登場した場合、元の財の需要曲線がどのように変化するかを考察する問題です。代替効果と需要曲線のシフト、そして価格弾力性の変化に関する理解が問われます。
<選択肢>
・安価な冷凍野菜(代替財)の輸入が解禁されると、消費者は価格の高い生鮮野菜の代わりに冷凍野菜を購入するようになります。これにより、どの価格帯においても生鮮野菜を買おうとする量は減少します。その結果、生鮮野菜の需要曲線は全体として左にシフトします。この時点で、右にシフトしている③と④は誤りです。
・次に、①と②のどちらがより適当かを考えます。問題文には「消費者は、生鮮野菜の価格が高いほど、生鮮野菜より冷凍野菜を好んで購入する傾向にある」とあります。これは、生鮮野菜の価格が高いときほど、代替財である冷凍野菜への需要の流出が大きくなることを意味します。
・つまり、需要曲線が左にシフトする幅は、価格が低いときよりも高いときの方が大きくなります。
・この結果、シフト後の需要曲線は、シフト前の曲線に比べて傾きがより緩やかになります。(同じ価格の変化に対して、需要量の変化がより大きくなるため、価格弾力性が大きくなる)
・①のグラフでは、シフト後の曲線は傾きが急になっており、価格が高いほど需要の減少幅が小さいことを示しているため、問題の条件と合いません。
・②のグラフでは、シフト後の曲線は傾きが緩やかになっており、価格が高い領域でより大きく左にシフトしていることを示しています。これは問題の条件と合致しています。
したがって、②が最も適当な図となります。
第4問
問1:正解⑥
<問題要旨>
社会契約説を唱えた思想家(グロティウス、ホッブズ、ロック)と、それぞれの思想を説明した文章とを正しく結びつける問題です。各思想家が想定した「自然状態」や「自然法」の捉え方の違いを正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
ア:この文章は、人間は生まれながらにして「生命、健康、自由、所有物」といった権利(自然権)を持ち、理性的で平和な「自然状態」を想定しています。これはロックの思想の核心です。
イ:この文章は、人々を統制する共通の権力がない「自然状態」を、「万人の万人に対する闘争」と表現されるような、絶え間ない恐怖と危険に満ちた状態として描いています。これはホッブズの思想です。
ウ:この文章は、国家間の戦争状態においても、それを規律する共通の法(自然法や万民の合意に基づく法)が存在すると主張しています。これは、国際社会にも法的な秩序があるべきだと説き、「国際法の父」と呼ばれるグロティウスの思想です。
以上のことから、アはc(ロック)、イはb(ホッブズ)、ウはa(グロティウス)の組み合わせが正しくなります。
問2:正解⑤
<問題要旨>
アジア3か国の人口ピラミッドを比較し、将来の人口動態(高齢化)を予測するとともに、「人口オーナス」という概念を正しく理解しているかを問う問題です。人口ピラミッドの形状から少子高齢化の進行度を読み取る力が求められます。
<選択肢>
ア:2050年時点での高齢化の進行度を予測します。
・インドとインドネシアの人口ピラミッドは、若年層が厚い「富士山型」に近く、今後も生産年齢人口(15~64歳)の増加が見込めます。
・一方、中国の人口ピラミッドは、過去の一人っ子政策の影響で若年層が細く、生産年齢人口の層が厚い「つぼ型」に近い形状になっています。この厚い層が30年後(2050年)には高齢者層へと移行するため、生産年齢人口の割合が最も大きく落ち込み、高齢化が急激に進むと予測されます。
イ:総人口に占める生産年齢人口の割合が低下し、社会全体で子どもや高齢者を支える負担が重くなる状態を「人口オーナス(人口の重荷)」と呼びます。逆に、生産年齢人口の割合が高く、経済成長を後押しする状態は「人口ボーナス」です。会話文は、生産年齢人口の割合が低下する状態を指しているため、「人口オーナス」が当てはまります。
したがって、アに中国、イに人口オーナスが入る組み合わせが正解です。
問3:正解③
<問題要旨>
アジアにおける開発援助(ODA)やインフラ開発に関連する国際的な動向について、正確な知識を問う問題です。一帯一路構想、アジアインフラ投資銀行(AIIB)、国際収支、開発協力大綱など、幅広い時事知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
中国が提唱する「一帯一路」構想は、中国から中央アジア、ヨーロッパへと続く陸路の「シルクロード経済ベルト」と、中国沿岸部から東南アジア、インド洋、アフリカ、ヨーロッパへと続く海路の「21世紀海上シルクロード」の二つから構成されています。陸路のみではありません。
②【誤】
中国が主導して設立されたアジアインフラ投資銀行(AIIB)には、アジアの国々だけでなく、イギリス、フランス、ドイツといったヨーロッパの国々や、カナダ、ブラジルなど、アジア以外の多くの国も参加しています。
③【正】
国際収支統計において、ODAによる無償資金協力や食料援助のように、対価の受け取りを伴わない一方的な資産の提供(贈与)は、「第二次所得収支」(かつては経常移転収支と呼ばれた)に計上されます。
④【誤】
日本のODAの基本方針を定めた「開発協力大綱」では、日本の平和と安全、繁栄といった「国益の確保に貢献する」ことが、ODAの目的の一つとして明記されています。したがって、国益を全く考慮しないわけではありません。
問4:正解①
<問題要旨>
日米欧の家計における金融資産構成のデータから、各地域の資産運用の特徴を読み取り、金融資産のリスクとリターンの一般的な関係についての理解を問う問題です。
<選択肢>
ア:一般的に、金融資産の「収益性」(リターン)と「安全性」(リスクの低さ)はトレードオフの関係にあります。株式や投資信託のように高い収益性が期待できる資産は、価格変動が大きく元本割れの可能性もあるため、安全性は低いとされます。逆に、預金のように安全性が高い資産は、得られる収益(利息)は低い傾向にあります。
イ:会話文中のYさんは「資産が減る可能性を最も低くしたい」と述べており、安全性を最優先するリスク回避的な考え方を持っています。資料を見ると、日本の家計は「現金・預金」の割合が54.3%と突出して高く、アメリカ(13.3%)やユーロエリア(34.3%)に比べて、安全資産への偏りが顕著です。したがって、Yさんの考え方に最も近いのは日本の金融資産構成です。
以上のことから、アに「低い」、イに「日本」が入る組み合わせが正解です。
問5:正解⑦
<問題要旨>
宇宙の平和利用を定めた「宇宙条約」の条文を読み解き、その規定に違反する具体的な事例を判断する問題です。条文の禁止事項(領有の禁止、大量破壊兵器の配備禁止)や国家責任の原則を正確に読み取る読解力が求められます。
<選択肢>
ア【正】
第4条には「核兵器および他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないこと」を約束すると明記されています。したがって、核兵器を搭載した人工衛星を軌道に乗せる行為は、明確な条約違反です。
イ【正】
第2条には「月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用もしくは占拠またはその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない」と規定されています。したがって、月面を自国の領土であると主張し占拠する行為は、条約違反です。
ウ【正】
第6条では、自国の活動について「それが政府機関によって行なわれるか非政府団体によって行なわれるかを問わず、国際的責任を有する」と定められています。また、第7条では、自国から打ち上げた物体が他国に与えた損害について国際的な責任を負うとされています。したがって、自国の企業の活動が原因であっても、国家としての責任を免れることはできず、責任をとらないと主張することは条約違反となります。
以上のことから、ア、イ、ウのすべてが宇宙条約違反の事例として正しいです。
問6:正解⑤
<問題要旨>
科学技術の発展がもたらす便益とリスクについて、エネルギー問題、プライバシー権、経済安全保障という3つのテーマを通じて議論する会話文の空欄を補充する問題です。それぞれの分野に関する正確な用語と知識が求められます。
<選択肢>
ア:発電する際に発生する排熱を、捨てるのではなく暖房や給湯などの熱源として有効利用するシステムを「コージェネレーション(熱電併給)」といいます。「スマートグリッド」は、IT技術を活用して電力の需給を最適化する次世代送電網のことです。したがって、【b コージェネレーション】が当てはまります。
イ:プライバシーの権利は、当初「私生活をみだりに公開されない権利」と解されていましたが、情報化社会の進展に伴い、個人情報が大量に収集・利用されるようになったことから、「自分に関する情報を自らコントロールする権利(自己情報コントロール権)」という側面が重要視されるようになりました。記述cはこの現代的な理解を正しく説明しています。記述dの「憲法第13条は、・・・(略)・・・明文で保障している」という部分は誤りです。プライバシー権は憲法に明文規定がなく、第13条の幸福追求権から導き出されると解釈されています。したがって、【c】が当てはまります。
ウ:AIや半導体などの先端技術が、他国によって軍事転用されたり、サプライチェーンが断絶したりするリスクに対応するため、近年、経済的な手段を用いて国家の安全保障を図る「経済安全保障」という考え方が重要になっています。日本では「経済安全保障推進法」が制定され、重要な先端技術の流出防止やサプライチェーンの強化が進められています。記述eはこの状況を正しく説明しています。記述fは1980年代の日米貿易摩擦に関するもので、文脈に合いません。したがって、【e】が当てはまります。
以上のことから、ア:b、イ:c、ウ:eの組み合わせである⑤が正解です。