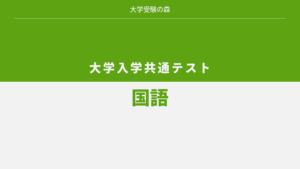解答
解説
第1問
この文章は、江戸時代以降における「妖怪」観の変遷を、フーコーの「アルケオロジー」の概念を参照しながら論じたものです。鬼や天狗といった歴史的・伝統的イメージをもつ妖怪が、近世に入るとさまざまな芸能や絵画の題材として盛んに描かれた結果、現実を超えたフィクションの対象として機能していく過程が示されています。さらに近代になると、妖怪は単なる超自然的存在ではなく、人間の不安や未知の領域を象徴する「内面」を映すものへと変容していきます。
文章では、こうした妖怪認識の変化が「表象」や「記号」という観点でどのように整理されてきたかを分析し、同時に近代特有の「私」の観念が妖怪とどのように結びつくかを明らかにしようとしています。要するに、妖怪が古来より受け継がれた民間伝承の姿から、人間の不安や空想を映すフィクショナルな存在へと変貌する「ストーリー」を、歴史的・思想的背景を踏まえて解明する試みとなっています。
第2問
この文章は、語り手である「私」と同僚のW君とのあいだに生じる、贈り物(羽織)をめぐる微妙な心情の動きを中心に描いた作品である。W君は病気療養中のため休職をしており、語り手は見舞いや雑誌の仕事上のやりとりなどを通じて彼と交流を続ける。あるときW君は、羽織という大切な品を語り手に贈るが、語り手は「なぜ自分に?」という疑問や、その羽織を身に着けることへの戸惑い・後ろめたさを抱くようになる。さらにW君の妻の存在や、互いの立場の変化(仕事の移動やW君の退職など)が重なり、語り手はW君との関係をどう捉えるべきか悩む。
しかし同時に、語り手にとってこの羽織は、W君の思いを感じさせる特別な品でもある。語り手はたびたびその羽織を着用するたびにW君を思い出し、過去のやりとりや感謝の気持ちを回想する。一方で、W君の負担になりたくない、あるいはW君の妻に気を遣うといった理由から、語り手はW君の家や店に足を運ぶことをためらい続ける。こうした「贈り物」という行為が引き起こす繊細な感情のやり取りと、距離感の取り方に戸惑う人間模様が、作品全体の大きなテーマとなっている。
第3問
この文章(『栄花物語』の一節)は、中納言殿の妻の死後、親族や周囲の人々が寺へ移り集まってくる場面を描いています。亡き妻への深い悲しみが重々しく漂うなか、登場人物たちはさまざまに“あはれ”を感じ、涙をこぼしつつも弔いや法事の準備を進めていきます。特に、目に見えて切ない様子を見せる「大北の方」や「斎信(大納言殿)」の嘆きや、周囲がそれをいたわり慰めようとする様子が強調されており、“思し残す”ことの多いままに人々が集まる様子が細やかに描かれています。
要するに、本段は亡き妻を失った悲嘆の中での人々のしめやかな振る舞い・涙・気遣いなどを通して、当時の宮廷社会における「哀しみと供養」の姿を映し出しているといえます。
第4問
この設問文は、いずれも古代中国における「馬車を操縦する技術(御術)」と「馬の性能・操り方」について述べたものです。
問題文Ⅰ(詩)では、
- 馬の持つ速力や力強さを称えつつ、
- その力を引き出すには適切な調整(調和)や扱いが必要である
といった主張が、漢詩の形式で詠まれています。
問題文Ⅱ(散文)では、
- 名手「王良」とその主君が馬車競走をする場面を通して、
- 良い馬がいても、それを扱う御者の技術や心構えが伴わなければ馬の能力を十分に発揮できない
という考え方が示されます。
両方の文章を通して、「馬の優れた性能」と「御者の的確な操縦技術」の双方があってこそ、はじめて馬車の速さや安定を得られるのだという思想が浮き彫りにされています。