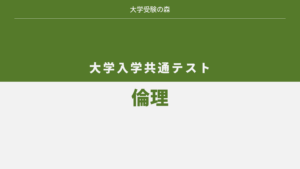解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
様々な思想や宗教で用いられる比喩やたとえについて、その内容を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イエスが「善きサマリア人」のたとえで説いたのは、隣人愛の対象をユダヤ人の同胞に限定せず、助けを必要とする全ての人に及ぼすべきだということです。これは同胞愛を否定するものではなく、むしろその範囲を普遍的に拡大する教えです。
②【誤】
孟子は、幼子が井戸に落ちそうになっているのを見れば、誰もがとっさに「惻隠の心(あわれみいたむ心)」から助けようとする、と述べました。これは人間が生まれながらに持つ道徳的感情(四端)の例であり、「助けないのは恥ずかしい(羞悪の心)」という後発的な感情や計算から行動する、と説明したわけではありません。
③【誤】
プラトンが太陽にたとえたのは「正義のイデア」ではなく「善のイデア」です。太陽が現実世界の事物を見えるように照らすように、善のイデアが他の全てのイデアを真に存在させ、私たちがそれを認識できるようにする根拠であると説きました。
④【正】
仏教では、人間を苦しめる根本的な煩悩として、貪欲・瞋恚(怒り)・愚癡(愚かさ)の三つを挙げ、これらが人の善性を毒すことから、毒にたとえて「三毒」と呼びます。したがって、この記述は正しいです。
問2:正解②
<問題要旨>
古代ギリシアのソフィストおよびソクラテスの、言葉や対話に関する思想や活動についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ソフィストが教えた弁論術の主な目的は、民会や法廷などで聴衆を説得し、自分の主張を通すことでした。「見掛けの背後にある真実を見いだすこと」を探究したのは、ソクラテスやプラトンです。
②【正】
ソフィストは、絶対的な真理の存在を疑問視する相対主義的な立場から、状況に応じて言葉を巧みに用いて人々を説得する技術(弁論術)を教えました。これは、真理の探究そのものよりも、社会的成功を目的としたものでした。したがって、この記述は正しいです。
③【誤】
ソクラテスは、対話(問答法)を通じて、相手が善や美といった事柄について何も知らないということを自覚させようとしました。彼が対話相手に対して一方的な尊敬の念を抱いたわけではなく、むしろ相手の「無知」を自覚させることに主眼がありました。
④【誤】
ソクラテスは「無知の知」を自覚しましたが、それは真理の探究が無益であるという結論には至りません。むしろ、知らないからこそ、より善く生きるために知を愛し求め続けるべきだ(愛知=フィロソフィア)と説きました。
問3:正解①
<問題要旨>
イスラームにおける啓示のあり方や、信仰の基本についての理解を問う問題です。ムハンマドへの最初の啓示に関する伝承(ハディース)の内容を正しく把握できているかがポイントとなります。
<選択肢>
①【正】
前半の「天使はイスラームにおいて信じることが義務とされる存在である」という記述は、アッラー、天使、啓典、預言者、来世、天命を信じる「六信」の内容と合致しており、正しいです。後半の「天使がムハンマドに神の言葉を受け取ることを強要している」という記述は、最初の啓示の際に、天使ジブリールが「読め」と命じ、返答に窮するムハンマドを激しく抱きしめて繰り返し迫った、という伝承の内容に合致します。この様子は「強要」と表現でき、正しい記述です。
②【誤】
ムハンマドが最初の啓示を受けた場所がヒラー山の洞窟であるという点は正しいです。しかし、天使が「巻物を手渡した」という記述は伝承と異なります。啓示は口頭で伝えられたものであり、物理的な巻物が手渡されたわけではありません。
③【誤】
「スンナとはムハンマドが受け取った神の言葉をまとめたもの」という記述が根本的に誤りです。神の言葉をまとめたものは「クルアーン」であり、「スンナ」は預言者ムハンマドの言行や慣行を指します。
④【誤】
イスラームの教えは、当初メッカの支配者層から迫害されており、彼らを通じて広められたわけではありません。また、啓示はムハンマドが求めたものではなく、神から一方的に与えられたものであり、この記述は史実と異なります。
問4:正解⑥
<問題要旨>
道家思想、ユダヤ教、イスラーム、仏教という様々な思想・宗教における「言葉」の役割や位置づけについての知識を問う、正誤組合せ問題です。
<選択肢>
ア【正】
老子の思想の中心である「道(タオ)」は、万物の根源でありながら、特定の形を持たず、人間の言葉で定義したり名付けたりすることができない超越的な存在です。そのため、「無」とも呼ばれます。
イ【正】
古代イスラエルにおいて、イザヤに代表される預言者たちは、神の言葉を預かり、民衆に伝える役割を担いました。彼らは、民が神との契約に背いたことがバビロン捕囚のような国難の原因であると批判し、神への回心を促しました。
ウ【誤】
イスラームの信仰告白(シャハーダ)は、「五行」と呼ばれる五つの信者の義務(信仰行為)の一つです。「六信」は信じるべき対象(神、天使、啓典など)を定めたものであり、信仰告白は含まれません。
エ【正】
ブッダは快楽と苦行の両極端を避ける「中道」の実践として「八正道」を説きました。その中の一つである「正語」は、嘘や悪口などを避け、真実で穏やかな言葉を語ることを意味します。
以上より、正しい記述はア、イ、エであり、その組合せは⑥です。
問5:正解⑥
<問題要旨>
旧約聖書と新約聖書における「羊」と「羊飼い」の比喩を読み解き、ユダヤ教の神とキリスト教のイエスについての神学的理解を問う問題です。
<選択肢>
空欄aには、資料1の旧約聖書「詩編」の文脈から、イスラエルの民を導く羊飼いにたとえられる「主」、すなわち唯一神ヤハウェが入ります。したがって、「神」が適切です。
空欄bには、資料2でイエスが「世の罪を取り除く神の小羊」と呼ばれていることから、キリスト教の贖罪思想が入ります。これは、ユダヤ教の過越祭でいけにえとして捧げられた羊にイエスをなぞらえ、イエスが十字架上で死ぬことによって、全人類の原罪が贖われた(代わりに償われた)とする考え方です。
したがって、aに「神」、bに「その死によって人間の原罪を代わりに償った」が入る⑥が正解です。
問6:正解③
<問題要旨>
荘子の思想を示す二つの逸話を読み、それぞれが「逍遥遊」「無用の用」といったどの思想概念を説明しているかを判断する問題です。
<選択肢>
資料1は、足元だけの有用な土地も、その周りの一見「無用」に見える広大な土地がなければ意味をなさない、という話です。これは、世間的な価値基準で役に立たないと見なされるものが、実は重要な役割を果たしているという「無用の用」の思想を示しています。
資料2は、大きすぎて使い物にならない木も、何もない広野に植えれば、その下でのんびりと過ごすことができる、という話です。これは、人為的な有用性の基準から解放され、あるがままの自然な姿で自由な境地に至る「逍遥遊」の考え方を示しています。
したがって、資料1がイ(無用の用)、資料2がア(逍遥遊)となる③が正解です。
問7:正解①
<問題要旨>
キリスト教の「神の国」と仏教の「涅槃」について、それぞれを説明したたとえ話を読み解き、その思想内容と表現方法を理解する問題です。
<選択肢>
①【正】
a:資料1の「からし種のたとえ」は、神の国がやがて大きく成長し、人々を救いに導くという「福音(良い知らせ)」であることを示しています。この記述は正しいです。
b:資料1の「からし種」、資料2の「(激流の中の)洲」は、いずれも当時の人々にとって身近なものでした。このような比喩を用いることで、捉えがたい宗教的な概念を具体的にイメージさせ、理解を促すことができます。この記述は両資料の表現方法を的確に捉えています。したがって、①が最も適当です。
②【誤】
aの「試練の場」やbの「自然の脅威に抵抗する」という解釈は、資料の文脈とは合致しません。
③【誤】
aの涅槃の説明は正しいですが、bの記述が、比喩の働きという点に触れている①のbに比べて、やや一般的すぎます。
④【誤】
aの「ブラフマン(梵)と合一」するのはウパニシャッド哲学(バラモン教)の思想であり、ブッダが説いた無我の立場からの涅槃とは異なります。
問8:正解②
<問題要旨>
古代ギリシア哲学における比喩の例を正しく選択し、かつ本文の会話の流れを踏まえて、比喩が持つ価値についての記述として最も適切なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
a(比喩の例):
②のプラトンが魂を「二頭の馬と御者」からなる馬車にたとえた、というのは『パイドロス』で語られる有名な比喩であり、正しい記述です。①のゼノンのパラドックスは運動を否定するもの、③の大乗・小乗の比喩は上座部の説明として不適切、④の初転法輪は正しいですが、他の選択肢との組合せを考える必要があります。
b(比喩の価値):
本文の会話では、Bが荘子のたとえについて「分かりやすく表されているとは言えないと思う。でも、意味をあれこれ考えてみることができるのは面白い」と述べています。これは、比喩が必ずしも物事を単純化・平易化するものではなく、むしろ多義的であるからこそ、受け手に思索を促すきっかけを与えるという価値を示唆しています。②のb「伝達される内容を必ずしも分かりやすくするわけではないけれど、だからこそ自分で考えるきっかけを与えてくれる」という記述は、この会話の趣旨と完全に合致しています。
したがって、a、bともに適切な記述である②が正解です。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
近世日本の儒学者である藤原惺窩、熊沢蕃山、林羅山、新井白石の思想や業績について、正確な知識を持っているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
藤原惺窩は近世儒学の祖であり、儒教の道徳に基づく身分秩序の重要性を説きました。「身分的な秩序を超えて」という部分は彼の思想とは異なります。
②【誤】
陽明学者であった熊沢蕃山は、むしろ無計画な新田開発が治水上の問題を引き起こすとして批判し、山林の保護など、自然と調和した政策の重要性を説きました。
③【誤】
林羅山は江戸幕府の教学の基礎を築いた朱子学者であり、彼が朱子学を批判した事実はありません。朱子学を形式的だと批判したのは、伊藤仁斎や荻生徂徠などの古学者です。
④【正】
新井白石は朱子学者として合理主義的な思考を持ち、その知識を幕政改革(正徳の治)に活かしました。彼は西洋事情にも通じていましたが、キリスト教の教義(天地創造説など)に対しては、儒教的な合理主義の立場から批判的でした。したがって、この記述は正しいです。
問2:正解②
<問題要旨>
日本の神話や古代信仰における自然観や世界観についての正誤を判断する問題です。
<選択肢>
ア【正】
日本の伝統的な世界観では、里山や海辺などは、人が住む現世と、神々や死者の霊が住む他界とが接する境界領域と見なされることがありました。これらは単なる自然ではなく、信仰上の意味を持つ空間でした。
イ【誤】
日本神話における天上の世界「高天原」は、神々の住居や田畑、機織り小屋などがあり、地上世界と類似した生活の場として描かれています。「田畑や家屋などが見られず」という記述は誤りです。
したがって、アが正、イが誤である②が正解です。
問3:正解⑤
<問題要旨>
鎌倉時代の仏教者である日蓮の思想と行動について、複数の記述から正しいものを全て選ぶ問題です。
<選択肢>
ア【正】
日蓮は、蒙古襲来といった国難は、国が正法である『法華経』に背いているために起こると考えました。そして、国を救い仏国土を現世に実現するためには、『法華経』の題目を唱えること(唱題)が唯一の道であると主張しました。
イ【誤】
日蓮は他宗派に対して極めて批判的であり、「四箇格言」で浄土宗、禅宗、真言宗、律宗を厳しく排撃しました。「各宗派の融和」を説いたというのは、彼の立場とは正反対です。
ウ【正】
日蓮は、数ある経典の中で『法華経』こそが釈迦の究極の教えであると確信し、これを広めることが国家を安泰にし、人々を救済する道であると考え、生涯をかけて布教活動を行いました。
以上より、正しい記述はアとウであり、その組合せは⑤です。
問4:正解④
<問題要旨>
二宮尊徳の「天理(天道)」と「人道」に関する文章を読み、その思想内容を的確に把握しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
bの報徳思想の説明が不十分です。恩に報いる対象は天・地・人すべてに及びます。
②【誤】
aの「互いに反することはない」は、資料で「天理と人道はまったく別のもの」とされ、人道が天理(自然の荒廃作用)に抗うものであるという趣旨と矛盾します。
③【誤】
bの「武士も含めた全ての人が、直接、農業に携わる社会」は尊徳の思想ではありません。彼は身分秩序を前提として、それぞれの分に応じた勤労(分度)を説きました。
④【正】
aの「人道は、天理による荒廃に抗いつつ、人の手を加えて暮らしを保つ」は、田畑の草を取り、堤を築くという資料の内容を正しく要約しています。また、bの「勤勉で節度ある生活をし、余剰を他者に譲ることで、社会に貢献することを説いた」は、尊徳の報徳思想の中心である「分度推譲」の考えを的確に説明しています。したがって、④が正解です。
問5:正解①
<問題要旨>
室町時代の水墨画(雪舟筆)を題材に、この時代の美意識と、絵画の具体的な表現を結びつけて理解する問題です。
<選択肢>
①【正】
a:室町時代の禅宗文化の中で育まれた美意識には、簡素で静かな味わいの中に、奥深い精神性を感じ取る「わび」「さび」や「枯淡」の境地があります。この記述は、この時代の美意識を正しく説明しています。
b:雪舟に代表される水墨画は、墨一色の濃淡やかすれ、筆致の強弱によって、自然の雄大さや奥深さ、深い精神性を表現します。この記述は、絵の具体的な表現を的確に捉えています。aとbの組合せは適切です。
②【誤】
「幽玄」はより平安時代や鎌倉時代の和歌などに見られる、奥深く神秘的な美を指すことが多く、またbの「写実的な表現」は、精神性を重視する水墨画の表現とは異なります。
③【誤】
aの「さび」の説明は正しいですが、bの「明瞭な輪郭線」は、この絵の表現とは異なります。
④【誤】
aの「わび」の境地を満開の桜のような「華やかな自然美」と結びつけるのは不適切です。わびはむしろ質素で静かなものに見出される美意識です。
問6:正解②
<問題要旨>
近代日本のキリスト者である内村鑑三の思想についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
内村鑑三は、教会制度や儀式を介さず、聖書を通じて直接神と向き合う「無教会主義」を提唱しました。したがって、教会組織を重視したという記述は誤りです。
②【正】
内村鑑三は、その著書『代表的日本人』の中で、西郷隆盛や中江藤樹などを取り上げ、彼らが体現した武士道精神こそが、日本におけるキリスト教の「接ぎ木」の土台となりうると考えました。したがって、この記述は正しいです。
③【誤】
「二つのJ」に身を捧げたと述べたのは内村鑑三ですが、その「J」はイエス(Jesus)と日本(Japan)であり、正義(Justice)ではありません。彼は神と日本に生涯を捧げると述べました。
④【誤】
内村鑑三はキリスト教徒としての非戦論の立場から、日露戦争に反対しました。積極的に支持したという記述は誤りです。
問7:正解④
<問題要旨>
近代日本の思想家である河上肇と吉野作造の思想や主張を、それぞれの説明文と正しく結びつける問題です。
<選択肢>
アは、経済学者として貧困問題を研究し、当初は人道主義的な立場でしたが、やがてマルクス主義に傾倒していった河上肇の説明です。代表的な著作に『貧乏物語』があります。
イは、大正デモクラシーの理論的指導者であり、天皇主権の明治憲法の枠内で、実質的な民主主義(民本主義)を主張し、普通選挙の実現に尽力した吉野作造の説明です。
したがって、アが河上肇、イが吉野作造となる④が正解です。
問8:正解①
<問題要旨>
中井正一の文章を読み解き、会話文中の空欄a~dに、文章中の下線部ア~エのどの部分が入るかを正しく判断する問題です。
<問題要旨>
会話と資料を丁寧に対照し、意味の通る組合せを探します。
D「a の箇所だけれど、これは逆に言えば、宇宙の秩序は完璧だってことだよね?」:完璧な秩序について述べられているのは、下線部ウ「自然の星の軌道のように、寸分の狂いも謬りもないものではない」の部分(の否定形)です。つまり、人間の創る秩序は完璧ではないが、宇宙の秩序は完璧だ、という対比です。よってaはウ。
C「私は、b の箇所と c の箇所の違いが気になっているんだ」:Cは「既に存在する秩序を人間が取り入れている」部分と、「人間が独自に秩序を生み出している」部分の違いを指摘しています。前者に当たるのがア「宇宙の秩序を、一人一人自分の中にうつしとることができる」であり、後者に当たるのがイ「みずからを創造したのである」です。よってbはア、cはイ。
D「d の箇所が手掛かりになるんじゃない?」:この二つの関係性を説明する手掛かりとして、Dは試行錯誤の必要性を指摘しています。これはエ「常に謬りつつ、その謬りをふみしめることが、真実へのただ一つの道しるべとなる」という部分が該当します。
以上から、a-ウ、b-ア、c-イ、d-エとなる①が正解です。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
フランシス・ベーコンが提唱した、正しい認識を妨げる偏見や先入観である「イドラ」の4分類(種族、洞窟、市場、劇場)について、具体例と正しく結びつけているか問う問題です。
<選択肢>
①【正】
新しいもの好きなど、個人の性格、環境、教育などによって生じる個人的な偏見を「洞窟のイドラ」と呼びます。したがって、この記述は正しいです。
②【誤】
信頼する友人の言うことを無批判に信じるのは、特定の個人との関係から生じるものであり、人間という種に共通する本性から生じる「種族のイドラ」の例としては不適切です。「種族のイドラ」は、例えば物事を擬人化して捉えたり、都合の良い事例だけを信じたりするような、人間に共通する感覚の誤りを指します。
③【誤】
皆が言っているからという理由で信じるのは、人々の交わりや言語の不適切な使用から生じる「市場のイドラ」の一例です。「権威に無批判に従う」のは、次に述べる「劇場のイドラ」に分類されます。
④【誤】
占いが当たったという一面的な事実から全体を正しいと信じ込むのは、人間の本性に根差す「種族のイドラ」の例です。伝統的な学説や権威を無批判に受け入れてしまう偏見が「劇場のイドラ」です。
問2:正解④
<問題要旨>
実存主義の先駆者であるキルケゴールの思想について、その内容を正しく説明しているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
キルケゴールが示した実存の三段階は、「美的実存」→「倫理的実存」→「宗教的実存」の順です。選択肢では倫理的実存と宗教的実存の順序が逆になっています。
②【誤】
「生きられた身体」をキーワードに、身体を通した世界との関わりを分析したのは、フランスの現象学者メルロ=ポンティの思想です。
③【誤】
限界状況(死、罪責など)における絶望からの超越や、「愛しながらの戦い」といった実存的交わりを説いたのは、ドイツの実存主義者ヤスパースです。
④【正】
キルケゴールは、ヘーゲルのような客観的で普遍的な真理を批判し、この「私」が情熱をもって生きるための主体的真理こそが重要であると説きました。「私にとって真理であるような真理」という表現は、彼の思想を的確に表しています。したがって、この記述は正しいです。
問3:正解②
<問題要旨>
フランクフルト学派の中心人物であるホルクハイマーとアドルノの思想(批判理論)について、その内容を正しく説明している記述を判断する問題です。
<選択肢>
ア【正】
ホルクハイマーとアドルノは、その主著『啓蒙の弁証法』において、理性の行使による自然支配が、逆説的に人間自身を管理社会のシステムに隷属させ、主体性を奪う結果になったと分析しました。
イ【誤】
科学の歴史が、ある時代の「パラダイム(理論的枠組み)」の転換によって革命的に進歩すると主張したのは、科学哲学者のクーンです。
ウ【正】
彼らは、近代の理性が、目的を問わずに効率のみを追求する「道具的理性」へと堕落したと批判しました。この道具的理性が社会全体を覆い、人間を支配するようになっていると考えました。
以上より、正しい記述はアとウであり、その組合せは②です。
問4:正解②
<問題要旨>
プラグマティズムの思想家パースの文章と、哲学対話に関する説明文を読み解き、それぞれの内容を正しく要約している選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
a(パースの思想):
資料1でパースは、人間の思考が「自分自身との対話」であるとし、さらに人間集団は対話を通じて「もっと高次の人格」になると述べています。アの「人間は個人として思考するときにも自分自身と対話するものであり、さらに集団としては対話を通してより高次の人格を備える」という記述は、この内容を正確に要約しています。イは「一人だけでは思考できない」と断定しており、パースの趣旨とは少し異なります。
b(哲学対話の目的):
資料2(省略されているが文脈から推測)とTの発言から、哲学対話が多様な意見に耳を傾け、探求する場であることがわかります。エの「民主的社会でよく生きるために、異なる声に耳を傾け、それらを受けとめ、考える姿勢を持って、相互に理解し合える力を身に付ける」という記述は、哲学対話の教育的目的を的確に説明しています。ウの「他者の観点を優先して」や、オ、カの記述は、対話の趣旨から外れます。
したがって、aにア、bにエが入る②が正解です。
問5:正解④
<問題要旨>
近代哲学の父と称されるデカルトの思想や生涯について、正しい説明を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
デカルトが遂行した「方法的懐疑」は、少しでも疑わしいものを全て偽として退ける徹底的なものであり、「穏健な意見に従う」という態度とは正反対です。
②【誤】
デカルトは精神と身体を独立した実体と考える物心二元論を唱えましたが、両者が松果体において相互作用すると考え、その関係性を考察しました。「連動を認めないとした」という記述は誤りです。
③【誤】
全ての観念は経験から得られるとするのは、ロックに代表されるイギリス経験論の立場です。デカルトは、神や精神といった観念は生まれつき備わっているとする生得観念説(大陸合理論)を採りました。
④【正】
デカルトは、青年期に伝統的なスコラ哲学に飽き足らず、学問の世界を離れてヨーロッパ各地を旅し、「世間という大きな書物」から学ぶことを決意しました。その経験を通じて、彼は自身の哲学の基礎となる確実な真理を探究するに至りました。したがって、この記述は正しいです。
問6:正解③
<問題要旨>
精神分析家フロムの思想と、彼が述べた「討論」「会話」「対話」の違いに関する文章の内容を正しく結びつけている選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
「集合的無意識」を提唱したのはユングです。フロムの思想ではありません。
②【誤】
自己保存欲求を自然権として論じたのは、ホッブズなどの近代思想家です。フロムの思想ではありません。
③【正】
フロムは、近代人が「自由からの逃走」として権威主義に陥る心理を分析し、生産的に生きることの重要性を説きました。資料で述べられている、所有(have)の様式に縛られた討論や会話と、存在(be)の様式に基づき、ありのままの自己で臨む対話の区別は、まさに彼の思想を反映したものです。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
「積極的な自由」の重要性を説いたのはフロムですが、資料の趣旨は、他者を変容させることよりも、まずありのままの自己で対話に臨むことの意義を述べています。
問7:正解①
<問題要旨>
ドイツ観念論を大成したヘーゲルの「絶対精神」という概念について、その説明として最も適切なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
ヘーゲルによれば、歴史は「絶対精神」が自由を自覚していく過程です。絶対精神は、個々の時代や民族の精神(世界精神)として現れ、英雄などの行為(理性の狡知)を通じて、最終的に全ての人間が自由であるという段階へと自己を展開させていきます。この記述はヘーゲルの歴史哲学を的確に説明しています。
②【誤】
人間は、歴史の法則にただ従うのではなく、国家や人倫といった共同体の中で能動的に自由を実現していく存在とされます。「個人の自由を制限して」という表現は不適切です。
③【誤】
歴史を発展させる根本的な力は、個人の主体性を超えた「絶対精神」にあります。個人の主体性が絶対精神と呼ばれるわけではありません。
④【誤】
「理性の狡知」とは、絶対精神が、個人の情熱や意図を利用して、歴史全体の目的を実現していく働きのことであり、人間の行為が絶対精神の支配を覆す可能性を指すものではありません。
問8:正解②
<問題要旨>
本文の会話の流れを踏まえ、哲学対話を経験したEの「主体性」に対する考えの変化を最もよく表している記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
会話の中でEは、主体性について「まだ分からないんだけど」「問いが増えて、今後何をどう考えればいいのか、その地図を手に入れたような感じ」と述べています。「答えも明確に分かるようになる」という断定的な表現は、このEの心境とは異なります。
②【正】
Eは、対話の場に「『私たち』っていう共同の主体」が現れるのを感じつつも、「『私』っていう個人の主体性は消えてしまうわけじゃなくて、むしろ私らしく存在してた」と述べています。これは、共同的な探究(共同的な主体性)の中で、個々の主体もまた活性化するという発見です。この記述は、Eの発見をバランスよく表現しており、最も適切です。
③【誤】
Eは「『私』っていう個人の主体性は消えてしまうわけじゃなくて」と明確に述べており、「共同的な次元に宿るものだ」と限定するのは、彼女の考えとは異なります。
④【誤】
Eは、自分自身のあり方について「聴くのが好きな自分をいつも以上に実感できた」と述べています。これは、主体的なあり方が「積極的に表現すること」だけに限られないことを示唆しています。この選択肢は、Eの発見の一側面を捉えていません。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
心理学における欲求不満(フラストレーション)への対処の仕方(防衛機制など)について、具体例と用語を正しく結びつけているか問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
自分の嫌いという感情を、相手が自分を嫌っているのだと思い込むのは「投射(投影)」と呼ばれる防衛機制です。「昇華」は、社会的に認められない欲求を、学問や芸術など価値のあるものへ向けることです。
②【正】
欲求不満の状態において、その原因となった対象とは別の、攻撃しやすい対象に八つ当たりするなどの衝動的な行動を「近道反応」と呼びます。したがって、この記述は正しいです。
③【誤】
社会的に価値のあるものへ欲求の対象を置き換えるのは「昇華」です。「投射」は、自分の認めがたい感情や欲求を、他人が持っているかのように思い込むことです。
④【誤】
「失敗反応」という用語は一般的ではありません。子どものように激しく抵抗するのは「退行」の一種と考えられます。
問2:正解⑦
<問題要旨>
環境倫理の分野で重要な業績を残したボールディングとレイチェル・カーソンの思想や主張を、それぞれの説明文と正しく結びつける問題です。
<選択肢>
アは、地球を、外部との物質のやり取りがない閉鎖的な宇宙船にたとえ(「宇宙船地球号」)、資源の有限性と環境問題の深刻さを訴えた経済学者ボールディングの説明です。
イは、その著書『沈黙の春』の中で、DDTなどの化学農薬の無分別な使用が生態系に深刻なダメージを与えていると警告し、環境問題への社会的な関心を喚起した生物学者レイチェル・カーソンの説明です。
したがって、アがボールディング、イがカーソンとなる⑦が正解です。
問3:正解③
<問題要旨>
サイードが批判した「オリエンタリズム」の具体例として、適当でないものを選ぶ問題です。オリエンタリズムとは、西洋(オクシデント)が、自らを優位に置くために、東洋(オリエント)に対して作り上げた、固定的で偏見に満ちたイメージのことを指します。
<選択肢>
①【該当する】
西洋の音楽を基準とし、日本の伝統音楽を劣ったものと見なす態度は、西洋中心主義的なオリエンタリズムの一例です。
②【該当する】
アジアの中で日本を「西洋的」であるとして特別視し、他のアジア諸国を見下す態度は、西洋を価値基準の中心に置き、アジア内部に序列をつけるという、オリエンタリズムの変形と言えます。
③【該当しない】
イスラーム圏の文化への知的関心を持ち、図書館で調べるという行為自体は、オリエンタリズム的な偏見とは直接結びつきません。単に個人の関心の対象が西洋よりもイスラーム圏に向いているというだけであり、そこには西洋を優位とする価値判断は含まれていません。
④【該当する】
東南アジアを、西洋にはない「エキゾティックでミステリアスな」場所として捉える見方は、東洋を非合理的で神秘的な他者として表象する、典型的なオリエンタリズムのステレオタイプです。
問4:正解②
<問題要旨>
終末期医療(ターミナルケア)に関連するホスピス、リヴィング・ウィル、安楽死といった制度や考え方について、正誤を判断する問題です。
<選択肢>
ア【正】
ホスピスは、治癒を目指す治療が困難になった患者に対し、身体的・精神的苦痛を和らげる緩和ケアを中心に行う施設です。
イ【正】
リヴィング・ウィル(尊厳死の宣言書)は、将来、自分が意思表示できなくなった場合に備えて、延命治療の希望の有無など、終末期における医療への希望をあらかじめ文書で示しておくものです。
ウ【誤】
患者の要請に基づき、医師が致死薬などを投与して死に至らせる積極的安楽死は、オランダ、ベルギー、カナダなど、世界の一部の国や地域では法的に認められています。「認めている国や地域はない」という記述は誤りです。
したがって、アが正、イが正、ウが誤である②が正解です。
問5:正解③
<問題要旨>
生命をテーマに哲学的な思索を展開したベルクソンとシュヴァイツァーの思想について、正しい説明を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
ベルクソンが説いた「エラン・ヴィタール(生命の躍動)」は、生命が多様な方向に進化・分岐していく創造的な力のことであり、「一直線に進歩していく」というものではありません。また、「開かれた社会」という概念も彼の思想ですが、この文脈での結びつきは不正確です。
②【誤】
福祉国家における生命の管理(生権力)を分析し、権力構造を考察したのは、フランスの思想家ミシェル・フーコーです。
③【正】
シュヴァイツァーは、「生きようとする生命に囲まれた、生きようとする生命」であるという自覚から、「生命への畏敬」を倫理の根本に据えました。そして、人間は他の生命を犠牲にしなければ生きていけないという現実の中で、その葛藤を引き受けつつ、生命を尊重する責任があると説きました。この記述は彼の思想を的確に表しています。
④【誤】
工場での労働体験を通じて、機械文明における人間の疎外を考察したのは、フランスの女性哲学者シモーヌ・ヴェイユです。
問6:正解③
<問題要旨>
パーソナリティ心理学における主要な理論である「ビッグファイブ(五因子モデル)」について、その内容を正しく説明しているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
価値観から性格を6つの類型(理論型、経済型、審美型、社会型、権力型、宗教型)に分類したのは、ドイツの心理学者シュプランガーの類型論です。
②【誤】
①と同様、シュプランガーの類型論の説明です。
③【正】
ビッグファイブ理論は、人間の性格が主に「開放性」「誠実性」「外向性」「協調性」「神経質傾向」という五つの特性(因子)の強弱の組み合わせで記述できるとする特性論的アプローチです。この記述は、ビッグファイブの内容を正しく説明しています。
④【誤】
ビッグファイブは、人を特定のタイプに分類する「類型論」ではなく、個々の特性の程度を測定する「特性論」です。
問7:正解③
<問題要旨>
「意図」と「結果」が人の行為に対する道徳的評価にどう影響するかを調査したグラフを読み解き、考察文の空欄を正しく埋める問題です。
<問題要旨>
グラフを丁寧に読み取ります。
a:「意図なし・危害あり」の場面を見ると、テロリストの評価得点(約2.2)は、犯罪者(約3.8)や一般市民(約3.9)よりも低くなっています。得点が低いほど「許されない」という評価なので、一般市民や犯罪者はテロリストよりも「道徳的に許されると評価していた」ことになります。よってaはア。
b:「意図あり・危害なし」の場面では、テロリストの評価得点(約4.1)は、犯罪者(約2.2)や一般市民(約2.0)よりも高くなっています。つまり、犯罪者や一般市民はテロリストよりも、この行為を「道徳的に許されないと評価していた」ことになります。よってbはエ。
c:以上のことから、テロリストは「意図」よりも「危害があったかどうか」という「結果」を重視して判断していることが分かります(意図があっても危害がなければ評価が高く、意図がなくても危害があれば評価が低い)。一方、一般市民や犯罪者は、「危害」がなくても「意図」があっただけで評価を厳しくしており、「結果」よりも「意図」を重視しています。考察文はテロリストの判断基準を問うているので、「意図よりも結果」を重視していると言えます。よってcはオ。
以上から、a-ア、b-エ、c-オとなる③が正解です。
問8:正解④
<問題要旨>
哲学者アンスコムの「意図」に関する文章を読み、その内容を正しく説明している記述を全て選ぶ問題です。
<選択肢>
ア【正】
資料でアンスコムは、「意図というものは、人が自由に、心の中で向けたり逸らしたりできるようなものではない」と述べています。これは、人が自分の意図を都合よく変えたり偽ったりできるという考え方を否定するものです。
イ【正】
資料では、デカルト的な心理学(意図は内的な精神状態である)と「行いの善悪は意図次第だ」という考えが結びつくと、「召し使いは、主人の犯罪に加担するあらゆる行為をしても、自分はただ生計を立てることを意図していただけだ、と言うことで正当化できてしまう」と述べられています。これは、この組合せがどんな行為でも正当化できてしまう危険性を指摘するものです。
ウ【誤】
アンスコムは、召し使いの例を、そのような正当化がまかり通ってしまうことの問題点として挙げています。彼女がこの召し使いの行為を「正当化される」と述べているわけではありません。むしろ批判的に例示しています。
したがって、正しい記述はアとイであり、その組合せは④です。
問9:正解③
<問題要旨>
これまでの会話や板書で示された「二重結果原則」を踏まえて、行為の是非と意図に関する記述として、全体の趣旨に最も合致するものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
二重結果原則は、たとえ結果が同じでも、「意図」が異なれば、一方の行為は許され、他方の行為は許されない、という場合があることを説明する原則です。この記述は原則の趣旨と正反対です。
②【誤】
二重結果原則は、あくまで「悪い結果を意図していない」場合にのみ適用される可能性があります。「悪い結果が意図されていたとしても」正当化できる、というものではありません。
③【正】
Gの発言にあるように、二重結果原則が適用されるには、【条件1】(悪い結果を意図しないこと)に加えて、【条件2】「良い結果が、悪い結果を埋め合わせられるほど望ましいものであること」が必要です。終末期医療の差し控えの場合、「つらい治療を避けられる」という良い結果が、「死期が早まる」という悪い結果を上回るかどうかが問われることになります。この記述は、原則の適用を正しく説明しています。
④【誤】
Hが「人が何かしているときにどんな意図を持っているのかなんて、はっきり分かることでしょうか」と疑問を呈しているように、会話全体を通じて、意図を基準とすることの難しさも示唆されています。「疑いの余地がない」という断定的な表現は、会話の趣旨に合致しません。