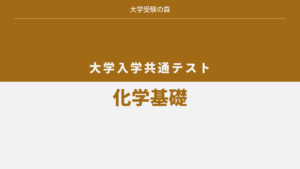解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
原子の構造(陽子、中性子、電子の数)に関する問題です。原子は原子核と電子から構成され、原子核は陽子と中性子からできています。原子番号は陽子の数、質量数は(陽子の数+中性子の数)を表します。中性子の数は「質量数 ー 原子番号(陽子の数)」で計算できます。
この問題では、比較対象となる原子の表記が欠落しているようですが、解答から判断すると、中性子の数が10個の原子と比較する問題であると推測されます。ここでは、各選択肢の原子が持つ中性子の数を計算し、比較します。元素の原子番号は、H(1), C(6), N(7), O(8), F(9), Ne(10)を使用します。
<選択肢>
①【誤】
¹⁵N(窒素)は、原子番号が7、質量数が15です。中性子の数は 15 – 7 = 8個です。
②【誤】
¹⁶O(酸素)は、原子番号が8、質量数が16です。中性子の数は 16 – 8 = 8個です。
③【正】
¹⁹F(フッ素)は、原子番号が9、質量数が19です。中性子の数は 19 – 9 = 10個です。
④【誤】
²²Ne(ネオン)は、原子番号が10、質量数が22です。中性子の数は 22 – 10 = 12個です。
問2:正解④
<問題要旨>
物質の性質を利用した分離・識別の問題です。炭酸水素ナトリウム(NaHCO₃)と塩化ナトリウム(NaCl)の性質の違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
炭酸水素ナトリウムは加熱すると熱分解し、二酸化炭素と水が発生して固体の質量が減少します(2NaHCO₃ → Na₂CO₃ + H₂O + CO₂)。一方、塩化ナトリウムは融点が高い安定な物質であり、加熱しても質量は変化しません。この質量の変化によって両者を区別できます。
②【誤】
炭酸水素ナトリウムは弱酸(炭酸)の塩であり、強酸である希硫酸と反応して二酸化炭素の気体を発生します(2NaHCO₃ + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + 2H₂O + 2CO₂)。一方、塩化ナトリウムは強酸の塩であり、希硫酸とは反応しません。気体の発生の有無によって両者を区別できます。
③【誤】
炭酸水素ナトリウムは、水に溶かすと加水分解により水酸化物イオン(OH⁻)を生じるため、水溶液は弱塩基性を示します。一方、塩化ナトリウムは強酸と強塩基からなる塩なので、水溶液は中性です。pHメーターや指示薬でpHを調べることで両者を区別できます。
④【正】
炎色反応は、特定の元素が含まれていることを調べるための操作です。炭酸水素ナトリウムも塩化ナトリウムも、どちらもナトリウム(Na)原子を含んでいます。そのため、どちらの水溶液を白金線につけて加熱しても、ナトリウム原子に由来する黄色の炎色反応を示します。したがって、この操作では両者を区別することはできません。
問3:正解②
<問題要旨>
元素の周期的性質、特にイオン化エネルギーと電子親和力についての理解を問う問題です。これらの用語の定義と、周期表における傾向を正しく把握しているかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
イオン化エネルギーは、原子から電子を1個取り去って陽イオンにするのに必要なエネルギーです。同族の元素では、原子番号が大きくなるほど原子核と最外殻電子の間の距離が大きくなり、電子を引き付ける力が弱まるため、イオン化エネルギーは小さくなる傾向があります。これは正しい記述です。
②【誤】
イオン化エネルギーは、同じ周期の元素では、原子番号が大きくなるほど大きくなる傾向があります。ただし、最大となるのは最も右に位置する希ガス元素です。第2周期の元素(Li〜Ne)の中で、イオン化エネルギーが最も大きいのはフッ素(F)ではなく、ネオン(Ne)です。したがって、この記述は誤りです。
③【正】
電子親和力は、原子が電子を1個受け取って1価の陰イオンになるときに放出されるエネルギーのことです。これは電子親和力の正しい定義です。
④【正】
電子親和力は、周期表の右上に位置する元素ほど大きい傾向があります(希ガスを除く)。塩素(Cl)は第17族のハロゲン元素、ナトリウム(Na)は第1族のアルカリ金属元素です。したがって、電子親和力はClの方がNaよりも大きくなります。これは正しい記述です。
問4:正解①
<問題要旨>
物質を構成する原子間の結合(化学結合)の種類についての問題です。金属元素と非金属元素の間の結合はイオン結合、非金属元素間の結合は共有結合が基本となります。
<選択肢>
①【誤】
塩素(Cl₂)は、非金属元素である塩素原子2つが電子を共有してできている分子です。非金属元素間の結合なので、共有結合です。「イオン結合」という記述は誤りです。
②【正】
ヨウ化カリウム(KI)は、金属元素であるカリウム(K)と非金属元素であるヨウ素(I)からなる化合物です。カリウムイオン(K⁺)とヨウ化物イオン(I⁻)が静電気的な引力で結合したイオン結合性の物質です。これは正しい組み合わせです。
③【正】
アンモニア(NH₃)は、非金属元素である窒素(N)と水素(H)が共有結合によって結びついた分子です。これは正しい組み合わせです。
④【正】
ポリエチレンは、多数のエチレン(C₂H₄)分子が重合してできた高分子化合物です。炭素原子同士、および炭素原子と水素原子が共有結合によって鎖状につながっています。これは正しい組み合わせです。
問5:正解②
<問題要旨>
物質量と気体の体積に関する計算問題です。固体の質量を物質量に変換し、標準状態(0℃, 1.013×10⁵ Pa)における気体の体積(モル体積: 22.4 L/mol)を用いて体積を求めます。
<選択肢>
ドライアイスは二酸化炭素(CO₂)の固体です。
まず、ドライアイスの質量を計算します。
質量 = 密度 × 体積 = 1.60 g/cm³ × 1.10 cm³ = 1.76 g
次に、この質量のCO₂の物質量を求めます。CO₂の分子量は、原子量C=12, O=16を用いると、12 + 16 × 2 = 44です。したがって、モル質量は44 g/molです。
物質量 (mol) = 質量 (g) / モル質量 (g/mol) = 1.76 g / 44 g/mol = 0.040 mol
最後に、標準状態における気体の体積を計算します。標準状態では、気体1 molあたりの体積は22.4 Lです。
体積 (L) = 物質量 (mol) × モル体積 (L/mol) = 0.040 mol × 22.4 L/mol = 0.896 L
したがって、正解は②の0.896 Lです。
問6:正解④
<問題要旨>
弱酸を強塩基で滴定した際の中和滴定曲線を選ぶ問題です。滴定前のpH、中和点の滴下量、中和点のpH、曲線の形状がポイントになります。
<選択肢>
まず、中和点を求めます。
滴定される酢酸の物質量は、0.10 mol/L × (10/1000) L = 0.0010 mol です。
(注:希釈しても酢酸の物質量は変わりません)
これを中和するために必要な水酸化ナトリウムの物質量も0.0010 molです。
滴下する水酸化ナトリウム水溶液の濃度は0.10 mol/Lなので、必要な体積V(mL)は、
0.10 mol/L × (V/1000) L = 0.0010 mol
V = 10 mL
よって、中和点は滴下量が10 mLのところです。この時点で選択肢は②か④に絞られます。
次に、滴定の開始点と中和点のpHを考えます。
・滴定前:酢酸は弱酸なので、pHは7よりかなり低く、2〜3程度の値から始まります。
・中和点:弱酸(酢酸)と強塩基(水酸化ナトリウム)の中和なので、生成した塩(酢酸ナトリウム)が加水分解し、水溶液は塩基性を示します。したがって、中和点のpHは7より大きくなります。
②と④のグラフはどちらも中和点が10mLで、開始pHが約3、中和点pHが8〜9付近となっており、これらの条件を満たします。しかし、曲線の形を詳細に見ると、弱酸の滴定曲線は、中和点に近づくにつれて緩やかにpHが上昇し、中和点付近で急激に変化(pHジャンプ)します。④のグラフは、この典型的な弱酸の滴定曲線の形状をより正確に表しています。したがって、④が最も適当なグラフです。
問7:正解①
<問題要旨>
ブレンステッド・ローリーの酸・塩基の定義に関する問題です。この定義では、相手に陽子(H⁺)を与える物質が「酸」、相手から陽子(H⁺)を受け取る物質が「塩基」とされます。水(H₂O)が酸として働いている、つまりH⁺を他に与えている反応式を選びます。
<選択肢>
①【正】
NH₃ + H₂O → NH₄⁺ + OH⁻
この反応では、H₂OがNH₃にH⁺を与えて、自身はOH⁻になっています。したがって、H₂Oは酸として働いています。(NH₃は塩基)
②【誤】
NH₄⁺ + H₂O → NH₃ + H₃O⁺
この反応では、H₂OはNH₄⁺からH⁺を受け取って、H₃O⁺になっています。したがって、H₂Oは塩基として働いています。(NH₄⁺は酸)
③【誤】
HF + H₂O → H₃O⁺ + F⁻
この反応では、H₂OはHFからH⁺を受け取って、H₃O⁺になっています。したがって、H₂Oは塩基として働いています。(HFは酸)
④【誤】
2H₂O → 2H₂ + O₂
これは水の電気分解(または熱分解)を表す反応式で、酸化還元反応です。ブレンステッド・ローリーの定義における酸塩基反応ではありません。
問8:正解①
<問題要旨>
化学反応の中から、酸化還元反応を選ぶ問題です。酸化還元反応とは、反応の前後で原子の酸化数が変化する反応のことです。単体が含まれる反応や、酸化剤・還元剤が関与する反応は酸化還元反応です。
<選択肢>
ア:塩酸を電気分解する。(2HCl → H₂ + Cl₂)
反応前はHの酸化数が+1、Clが-1ですが、反応後は単体であるH₂とCl₂になり、酸化数はともに0に変化します。酸化数が変化しているので、酸化還元反応です。
イ:亜鉛に塩酸を加える。(Zn + 2HCl → ZnCl₂ + H₂)
反応前は単体のZnの酸化数が0ですが、反応後はZn²⁺になり酸化数は+2に変化します。また、H⁺(酸化数+1)がH₂(酸化数0)に変化します。酸化数が変化しているので、酸化還元反応です。
ウ:石灰石に塩酸を加える。(CaCO₃ + 2HCl → CaCl₂ + H₂O + CO₂)
この反応は弱酸の塩と強酸の反応(酸塩基反応、中和反応)です。すべての原子について反応の前後で酸化数に変化はありません。
エ:硫化鉄(II)に塩酸を加える。(FeS + 2HCl → FeCl₂ + H₂S)
この反応も弱酸の塩と強酸の反応です。すべての原子について反応の前後で酸化数に変化はありません。
以上より、酸化還元反応が起こるのはアとイです。したがって、①が正解です。
問9a:正解②
<問題要旨>
化学反応の量的関係(質量比)を問う計算問題です。反応式における係数比(モル比)と各物質のモル質量から、生成物の質量比を算出します。
<選択肢>
与えられた燃焼反応式は次の通りです。
C₆H₁₀O₅ + 6O₂ → 6CO₂ + 5H₂O
この式から、生成する二酸化炭素(CO₂)と水(H₂O)の物質量の比は 6 : 5 であることがわかります。
次に、CO₂とH₂Oのモル質量を計算します。原子量はH=1.0, C=12, O=16を用います。
・CO₂のモル質量 = 12 + 16 × 2 = 44 g/mol
・H₂Oのモル質量 = 1.0 × 2 + 16 = 18 g/mol
したがって、生成するCO₂とH₂Oの質量の比は、
(CO₂の質量) : (H₂Oの質量) = (物質量比 × モル質量)の比
= (6 mol × 44 g/mol) : (5 mol × 18 g/mol)
= 264 : 90
この比を最も簡単な整数比に直します。両辺を6で割ると、
= 44 : 15
よって、正解は②です。
問9b:正解③
<問題要旨>
混合物の燃焼に関する計算問題です。ジャガイモが「炭水化物」と「水」のみからなると仮定し、燃焼で発生した水の総量から、元々ジャガイモに含まれていた水の質量を求めます。
<選択肢>
ジャガイモ1.00g中の炭水化物の質量を x (g)とすると、水分の質量は (1.00 – x) g となります。
燃焼で発生した水の総量 (0.89 g) は、以下の二つの合計です。
(1) 元々ジャガイモに含まれていた水の質量: (1.00 – x) g
(2) 炭水化物 x (g) の燃焼によって生成した水の質量
(2)の質量を求めます。問9aより、炭水化物(C₆H₁₀O₅、式量162)と生成する水(H₂O、分子量18)の質量比は、
(C₆H₁₀O₅の質量) : (生成するH₂Oの質量)
= (1 mol × 162 g/mol) : (5 mol × 18 g/mol)
= 162 : 90
= 9 : 5
つまり、炭水化物が y (g) 燃焼すると、水は (5/9)y (g) 生成します。
今、炭水化物の質量は x (g) なので、生成する水の質量は (5/9)x (g) です。
したがって、以下の関係式が成り立ちます。
(元々あった水の質量) + (燃焼で生じた水の質量) = (発生した水の総質量)
(1.00 – x) + (5/9)x = 0.89
この方程式を x について解きます。
1.00 – (4/9)x = 0.89
(4/9)x = 1.00 – 0.89
(4/9)x = 0.11
x = 0.11 × (9/4) = 0.99 / 4 = 0.2475 g
これは炭水化物の質量です。
求めたいのは燃焼前のジャガイモに含まれていた水の質量、つまり (1.00 – x) g です。
1.00 – 0.2475 = 0.7525 g
選択肢の中で最も近い値は③の0.75です。
第2問
問1a:(111)正解④ (112)正解④ (113)正解②
<問題要旨>
化学反応式の係数を決定する問題です。反応式の前後で各原子の数が等しくなるように係数を合わせます(未定係数法)。
<選択肢>
反応式: a HNO₃ → b NO₂ + c O₂ + d H₂O
反応の前後で、H, N, O原子の数がそれぞれ等しくなるように、a, b, c, dを決めます。
・H原子: a = 2d —(i)
・N原子: a = b —(ii)
・O原子: 3a = 2b + 2c + d —(iii)
まず、a=4と仮定してみます。(aを偶数にするとdが整数になり計算しやすい)
(ii)より、b = 4
(i)より、4 = 2d なので d = 2
これらの値を(iii)に代入します。
3 × 4 = 2 × 4 + 2c + 2
12 = 8 + 2c + 2
12 = 10 + 2c
2c = 2
c = 1
よって、係数は a=4, b=4, c=1, d=2 となります。
反応式は 4HNO₃ → 4NO₂ + O₂ + 2H₂O となります。
したがって、
111 (aに相当) は ④の4
112 (bに相当) は ④の4
113 (dに相当) は ②の2
となります。
問1b:正解③
<問題要旨>
酸素(O₂)の性質や製法に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
浄水場で水の殺菌・消毒に用いられるのは、オゾン(O₃)です。酸素にも殺菌作用はありますが、一般的にこの用途で使われるのはオゾンです。
②【誤】
空気の体積組成は、約78%が窒素(N₂)、約21%が酸素(O₂)、約0.93%がアルゴン(Ar)です。したがって、酸素は体積比で2番目に多い気体です。3番目に多いのはアルゴンです。
③【正】
酸化マンガン(IV)(MnO₂)を触媒として、過酸化水素水(H₂O₂)を分解すると酸素が発生します。これは実験室における酸素の代表的な製法です。(2H₂O₂ → 2H₂O + O₂)
④【誤】
発泡入浴剤がお湯に溶けると発生する気体は、主に炭酸水素ナトリウムとフマル酸などの有機酸が反応して生じる二酸化炭素(CO₂)です。
⑤【誤】
スナック菓子の袋には、中身の酸化を防ぐ目的で、化学的に不活性な窒素(N₂)ガスが充填されています。
問2a:正解①
<問題要旨>
化学反応の量的関係から、反応物の量を計算する問題です。生成物の質量から物質量を求め、反応式の係数比を使って、反応した気体の体積を算出します。
<選択肢>
水銀と酸素が反応して酸化水銀(II)ができる反応式は次の通りです。
2Hg + O₂ → 2HgO
生成した酸化水銀(HgO)は2.17g、HgOの式量は217です。
まず、生成したHgOの物質量を計算します。
物質量 = 質量 / 式量 = 2.17 g / 217 g/mol = 0.0100 mol
反応式の係数比より、(消費されたO₂の物質量) : (生成したHgOの物質量) = 1 : 2 です。
したがって、消費されたO₂の物質量は、HgOの物質量の1/2です。
消費されたO₂の物質量 = 0.0100 mol × (1/2) = 0.00500 mol
問題は、このO₂の体積を標準状態(0℃, 1.013×10⁵ Pa)で求めているので、モル体積 22.4 L/mol を使って計算します。
O₂の体積 = 物質量 × モル体積 = 0.00500 mol × 22.4 L/mol = 0.112 L
よって、正解は①です。
問2b:正解③
<問題要旨>
金属元素の単体およびその酸化物の反応性に関する知識を問う問題です。金属のイオン化傾向や、酸化物の安定性がポイントになります。
<選択肢>
①【正】
カルシウム(Ca)はアルカリ土類金属で、イオン化傾向が非常に大きく反応性が高いです。そのため、乾燥した空気中でも容易に酸化されて酸化カルシウム(CaO)になります。
②【正】
アルミニウム(Al)はイオン化傾向が大きい金属ですが、空気中に放置すると表面に緻密で安定な酸化アルミニウム(Al₂O₃)の薄い膜(酸化被膜)が生成します。この被膜が内部を保護するため、それ以上酸化が進みにくくなります。
③【誤】
鉄(Fe)は、湿った空気中(酸素と水が存在する環境)で容易に酸化され、赤さび(主成分:酸化鉄(III)水和物 Fe₂O₃・nH₂O)を生じます。「酸化されない」という記述は誤りです。
④【正】
酸化銀(I)(Ag₂O)は、比較的イオン化傾向が小さい銀の酸化物であり、不安定です。加熱すると容易に分解して、単体の銀(Ag)と酸素(O₂)になります。
⑤【正】
酸化銅(II)(CuO)は、水素(H₂)のような還元剤とともに加熱すると、還元されて単体の銅(Cu)と水(H₂O)が生じます。
問3a:正解③
<問題要旨>
化学反応の量的関係に関する問題です。実験データ(表)を読み取り、どちらの反応物が不足しているか(律速段階)を判断し、反応物の量を決定します。
<選択肢>
反応式: NaNO₂ + NH₄Cl → N₂ + 2H₂O + NaCl
この反応式の係数から、NaNO₂, NH₄Cl, N₂は、1 : 1 : 1 の物質量比で反応・生成することがわかります。
表1を見ると、加えるNaNO₂の物質量を増やしていくと、生成するN₂の体積も増加していますが、NaNO₂が12.0×10⁻³ molを超えると、N₂の生成量は224 mLで一定になっています。これは、NaNO₂が12.0×10⁻³ molの時点で、もう一方の反応物であるNH₄Clが全て反応し尽くしてしまったことを意味します。つまり、この水溶液中のNH₄Clと過不足なく反応して生成するN₂の最大量が224 mLであるとわかります。
標準状態で生成したN₂の最大体積 224 mL (= 0.224 L) の物質量を計算します。
N₂の物質量 = 体積 / モル体積 = 0.224 L / 22.4 L/mol = 0.0100 mol
反応式の係数比が 1:1 なので、反応したNH₄Clの物質量も0.0100 molです。
NH₄Clの式量は53.5なので、その質量を計算します。
NH₄Clの質量 = 物質量 × 式量 = 0.0100 mol × 53.5 g/mol = 0.535 g
これは、もとの水溶液100mLに溶けていたNH₄Clの質量です。
よって、正解は③です。
問3b:(118)正解① (119)正解②
<問題要旨>
混合気体の平均分子量と成分気体の体積百分率に関する計算問題です。気体の密度は平均分子量に比例することを利用して解きます。
<選択肢>
気体XはN₂とArの混合気体です。気体の密度は、同温・同圧では平均分子量に比例します。
気体Xの密度が純粋なN₂の密度よりも0.50%大きいので、気体Xの平均分子量M(X)も、N₂の分子量M(N₂)より0.50%大きくなります。
N₂の分子量 M(N₂) = 14 × 2 = 28
Arの原子量 M(Ar) = 40
M(X) = M(N₂) × (1 + 0.50/100) = 28 × 1.005 = 28.14
気体Xに含まれるArの体積百分率を p (%)とすると、N₂の体積百分率は (100 – p) (%)となります。
平均分子量は、各成分気体の(分子量 × 体積分率)の和で表されます。
M(X) = M(Ar) × (p/100) + M(N₂) × ((100-p)/100)
この式に数値を代入して p を求めます。
28.14 = 40 × (p/100) + 28 × ((100-p)/100)
両辺を100倍します。
2814 = 40p + 28(100 – p)
2814 = 40p + 2800 – 28p
2814 – 2800 = 12p
14 = 12p
p = 14 / 12 = 7 / 6 ≒ 1.166…
問題の指示(第2問 問3の訂正内容)に従い、この数値の小数第2位を四捨五入すると、1.2 % となります。
形式「118 . 119 %」に当てはめると、
118 は ①の1
119 は ②の2
となります。