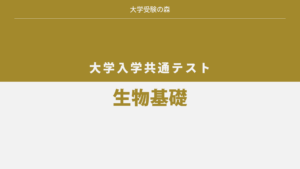解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
真核細胞である繊毛細胞と、原核細胞である細菌の構造や代謝の違いに関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
生物は、単純な物質から複雑な有機物を合成する「同化」と、複雑な有機物を分解してエネルギーを得る「異化」の両方の代謝を行って生命を維持しています。繊毛細胞も細菌も生命活動を行う生物なので、同化と異化の両方を行います。したがって、「細菌は異化のみを行う」という記述は誤りです。
②【誤】
繊毛細胞は真核細胞であり、核膜に包まれた「核」の中に遺伝物質であるDNAをもちます。一方、細菌は原核細胞であり、核膜に包まれた核をもたず、DNAは細胞質基質中の「核様体」と呼ばれる領域に存在します。したがって、「繊毛細胞も細菌も、核の中にDNAを含む」という記述は誤りです。
③【誤】
葉緑体は、光合成を行うための細胞小器官で、植物や藻類などの真核生物の細胞に存在します。繊毛細胞は動物の細胞であり、細菌は原核細胞なので、どちらにも葉緑体は存在しません。したがって、この記述は誤りです。
④【正】
ミトコンドリアは、酸素を用いて有機物を分解し、エネルギー(ATP)を効率よく取り出す「呼吸」の場となる細胞小器官です。真核細胞である繊毛細胞は、活発な運動エネルギーを必要とするため、多数のミトコンドリアをもちます。一方、細菌はミトコンドリアをもたず、呼吸は細胞膜などで行われます。したがって、「ミトコンドリアは、繊毛細胞には存在するが、細菌には存在しない」という記述は正しいです。
問2:正解⑦
<問題要旨>
細胞周期(G1期、S期、G2期、M期)の各段階における、細胞1個あたりのDNA量の変化に関する理解度を問う問題です。
<選択肢>
この問題では、分裂を終えたG1期の細胞のDNA量を「1」としています。
細胞周期は、G1期(DNA合成準備期)→S期(DNA合成期)→G2期(分裂準備期)→M期(分裂期)の順に進みます。
・G1期のDNA量を「1」とすると、
・S期でDNAが複製されるため、DNA量は「1」から「2」へと連続的に増加します。
・G2期ではDNAの複製が完了しているため、DNA量は「2」となります。
・M期(分裂期)でも、細胞分裂が完了するまではDNA量は「2」のままです。
問題の各細胞について見ていきましょう。
・分泌細胞XはG1期なので、DNA量は基準となる「1」です。
・基底細胞YはG2期なので、DNA複製後のためDNA量はG1期の2倍の「2」となります。
・基底細胞ZはM期の中期なので、まだ分裂が完了しておらず、DNA量はG2期と同じ「2」となります。
したがって、基底細胞YのDNA量は2、基底細胞ZのDNA量は2となり、この組合せである⑦が正解です。
問3:正解②
<問題要旨>
DNAの塩基配列から、翻訳されるタンパク質のアミノ酸配列への変換(セントラルドグマ)に関する計算問題です。遺伝子の塩基数とアミノ酸の数の関係、および終止コドンの影響を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
翻訳において、mRNAの連続した3つの塩基(コドン)が1つのアミノ酸を指定します。
・ア:正常なタンパク質のアミノ酸の数を求めます。
アミノ酸配列を指定する塩基対が13500なので、アミノ酸の数は、塩基数を3で割ることで計算できます。
13500塩基 ÷ 3 = 4500個
よって、アには4500が入ります。
・イ:変異体のタンパク質のアミノ酸の数を求めます。
変異体では、3601番目の塩基から始まるコドンが終止コドンに変化しています。終止コドンはアミノ酸を指定せず、そこで翻訳が終了します。つまり、正常に翻訳されるのは、その直前の3600番目の塩基までとなります。
したがって、合成される不完全なタンパク質のアミノ酸の数は、3600個の塩基から指定される数となります。
3600塩基 ÷ 3 = 1200個
よって、イには1200が入ります。
この組合せである②が正解です。
問4:正解②および⑤
<問題要旨>
一度分化した植物の細胞が、再び分裂・分化して完全な個体を再生する能力(分化全能性)について問う問題です。根の細胞がもつ潜在的な能力を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
根の細胞も生きている細胞であり、呼吸によって有機物を分解し、生命活動に必要なエネルギーを取り出しています。したがって、「エネルギーを消費する代謝を行っていない」は誤りです。
②【正】
根の細胞から再生した個体が花を咲かせることができるのは、元の根の細胞が、花の形成に必要な遺伝子を含め、その個体がもつ全ての遺伝情報(ゲノム)を持っているからです。分化した細胞でも、使われていない遺伝子が失われるわけではありません。
③【誤】
根の切断端近くの細胞が「増殖して」芽をつくる、と問題文にあります。細胞が増殖するためには、細胞分裂に先立ってDNAを複製する必要があります。したがって、DNAを複製する能力を失ってはいません。
④【誤】
根の細胞が、葉や茎になる「芽」を形成するということは、根とは異なる種類の細胞に変化したことを意味します。これは、他の細胞に分化する能力を失っていないことを示しています。
⑤【正】
再生してできた地上部には葉があり、光合成を行います。光合成には葉緑体が必要です。このことから、元の根の細胞は、葉緑体をつくる能力(遺伝子)を失っていなかったことがわかります。
⑥【誤】
根は基本的に地中にあり光が当たらないため、光合成を行うための葉緑体をもちません。したがって、光を当てても光合成は行われず、酸素も発生しません。
⑦【誤】
減数分裂は、生殖細胞(精細胞や卵細胞など)を形成する際の特殊な細胞分裂です。芽をつくる際の細胞増殖は、体細胞分裂によって行われます。
問5:正解③
<問題要旨>
「根に蓄えられた有機物を呼吸によって利用して芽をつくる」という仮説を検証するための実験計画の空欄を埋める問題です。対照実験の考え方や、呼吸と光合成に必要な物質についての知識が問われます。
<選択肢>
この実験は、仮説の要素である「呼吸」と「有機物(光合成産物)」が、芽の形成に不可欠であることを証明しようとしています。
・実験1(ウ):仮説の「呼吸によって」エネルギーを取り出す、という部分を検証します。呼吸には酸素(O2)が必要です。そこで、通常の大気下(対照区)と比べて、ウ(=O
2)を除いた条件でどうなるかを調べます。もしO2がないと芽ができなければ、芽の形成に呼吸が必要だという仮説が支持されます。
・実験2(エ):仮説の「葉の光合成で生産された有機物を蓄えており」という部分を検証します。光合成をさせなければ、根に蓄えられる有機物は減少するはずです。光合成を止めるには、一定期間、光をエ(=遮断)する処理を行います。この処理をした根で芽ができなくなれば、光合成産物が芽の形成に必要だという仮説が支持されます。
・実験3(オ):実験2で芽ができなかった原因が、本当に有機物の不足によるものかを確かめる実験です。実験2と同様に光を遮断して有機物の蓄積を妨げた根に、エネルギー源となる有機物であるオ(=グルコース)を与えます。これで芽ができるようになれば、芽の形成には有機物が必要であることがより確実になります。
したがって、ウにはO2、エには遮断、オにはグルコースが入る③が正解です。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
運動時など、身体が活動的・興奮状態にあるときに優位になる自律神経「交感神経」の働きについて問う問題です。交感神経と副交感神経の役割を区別できているかがポイントです。
<選択肢>
運動を開始すると、身体を活動に適した状態にするため、交感神経の働きが活発になります。
①【適当】
交感神経は、より多くの光情報を取り入れるために瞳孔を拡大させる働きがあります。
②【適当】
交感神経は、より多くの酸素を肺に取り込めるように気管支を拡張させる働きがあります。
③【不適当】
胃や腸のぜん動運動といった消化活動を促進するのは、身体がリラックスしているときに優位になる副交感神経の働きです。交感神経が優位なときは、消化活動はむしろ抑制されます。したがって、この記述は適当ではありません。
④【適当】
交感神経は、活動のためのエネルギー源を確保するため、肝臓に蓄えられているグリコーゲンの分解を促進し、血液中のグルコース濃度(血糖値)を上昇させます。
問2:正解②
<問題要旨>
運動時の心拍数と呼吸数の変化を示したグラフを正確に読み取り、そこから導き出せる事柄を判断する問題です。グラフの縦軸・横軸の意味や、線の種類(負荷の大きさ)の違いを丁寧に見ることが重要です。
<選択肢>
a【正】
グラフを見ると、運動中(0~6分)の心拍数は、負荷が大きい(実線)ほど高く、中程度(破線)、小さい(点線)の順に低くなっています。このことから、心拍数が運動の負荷の大きさを示す目安になる、という記述は正しいと言えます。
b【誤】
グラフの傾きは「上昇率」を示します。心拍数、呼吸数ともに、運動開始直後(0~2分)の傾きが最も急であり、その後は傾きが緩やかになっています。したがって、「運動の終了直前に最も大きくなる」という記述は誤りです。
c【正】
運動中は筋肉での酸素消費が増えるため、それを補うために心拍数や呼吸数が増加します。これにより、心臓から送り出される血液量や呼吸による酸素摂取量が増え、結果として単位時間あたりにからだ全体に供給される酸素の総量は、安静時よりも多い状態になります。したがって、この記述は正しいと考えられます。
d【誤】
グラフを見ると、運動終了後(6分以降)は、心拍数、呼吸数ともに減少に転じています。「そのまま上昇し続ける」という記述は明らかに誤りです。
(注:問題文では「a~cのうち」とありますが、実際の記述は4つあります。また、解答は「2」ですが、選択肢の具体的な組み合わせが問題用紙に示されていません。ここでは、各記述の正誤を判断しました。正しい記述はaとcです。)
問3:正解③
<問題要旨>
自律神経系や中枢神経系が関わる、心拍や呼吸の調節メカニズムについての総合的な理解を問う問題です。神経系の分類や、神経と内分泌(ホルモン)による調節の速度の違いなどがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
呼吸運動はある程度、意識的に(大脳の働きで)調節できますが、心臓の拍動や消化管の運動など、自律神経系が支配している多くの働きは、私たちの意識ではコントロールできません。したがって、「自律神経系の働きは意識的に調節できる」という部分は誤りです。
②【誤】
体温が上昇した際、その情報に基づいて心拍などを調節する司令を出すのは、間脳の視床下部などの体温調節中枢です。副腎髄質から分泌されるホルモン(アドレナリン)は交感神経の興奮によって分泌が促進されますが、体温上昇が直接の引き金となって副腎髄質から信号が送られるわけではありません。伝達の経路の記述が不正確です。
③【正】
延髄は脳幹の一部であり、中枢神経系に分類されます。延髄には心拍や呼吸を無意識的に調節する中枢があり、そこからの指令は自律神経系(交感神経・副交感神経)を通じて心臓に伝えられます。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
心拍の調節には、自律神経系による調節と、アドレナリンなどのホルモンによる内分泌系による調節の両方が関わっています。しかし、神経による情報伝達は電気信号なので非常に速いのに対し、ホルモンは血液によって運ばれるため効果が現れるまでに時間がかかります。したがって、「内分泌系による調節のほうが…迅速に伝達される」という記述は誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
獲得免疫(適応免疫)において中心的な役割を担うT細胞(ヘルパーT細胞、キラーT細胞)の機能についての問題です。それぞれのT細胞がどのような働きをするかを正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
活性化の順序が逆です。まず、マクロファージなどの抗原提示細胞から抗原の情報を受け取ったヘルパーT細胞が活性化し、その活性化されたヘルパーT細胞がキラーT細胞を活性化します。
②【正】
キラーT細胞(細胞傷害性T細胞)は、ウイルスに感染してしまった自分の細胞や、がん細胞など、体内で「異常」になった細胞を認識し、直接攻撃して排除する働きをします。これは細胞性免疫と呼ばれます。
③【誤】
B細胞を活性化して、抗体を産生する形質細胞への分化を促すのは、ヘルパーT細胞の役割です。
④【誤】
食作用は、マクロファージや好中球といった食細胞がもつ働きで、体内に侵入した細菌などを直接取り込んで分解する、主に自然免疫で機能する仕組みです。ヘルパーT細胞は食作用を行いません。
⑤【誤】
抗体を産生するのは、B細胞がヘルパーT細胞によって活性化され、分化した「形質細胞(抗体産生細胞)」です。ヘルパーT細胞自身が抗体をつくることはありません。
問5:正解⑥
<問題要旨>
予防接種(ワクチン)によって得られる免疫(二次応答や免疫記憶)の仕組みに関する問題です。どの細胞が関与し、どのような効果があるのかを正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
a【誤】
予防接種によって誘導される二次応答は、一度目の抗原侵入を記憶している「記憶細胞(メモリーB細胞やヘルパーT細胞)」が素早く反応する獲得免疫の仕組みです。好中球は、抗原の種類に関わらず働く自然免疫の食細胞であり、二次応答に直接は関与しません。
b【正】
予防接種は、あらかじめ弱毒化・無毒化した病原体(抗原)を体に入れることで、本格的な感染の前に免疫記憶をつくらせる方法です。これにより、本物の病原体が侵入した際には、記憶細胞がただちに大量の抗体をつくりだすなど、強力な免疫応答(二次応答)が起こり、病原体が体内で増殖して発病するのを防ぐことができます。
c【正】
bで述べたように、予防接種によって記憶細胞が体内に準備された状態になるため、実際に病原体に感染した場合、免疫記憶がない状態(一次応答)に比べて、はるかに速く、そして強く免疫応答が起こります。
したがって、正しい記述であるbとcを過不足なく含んでいる⑥が正解です。
問6:正解③
<問題要旨>
年齢の異なる集団への予防接種の効果を示したグラフを読み取り、その結果の背景にある免疫学的な理由を考察する問題です。特に、一次応答と二次応答の違い、免疫記憶の有無が抗体量の差にどう影響するかを理解しているかが重要です。
<選択肢>
①【誤】
グラフから「7歳以上の<接種前>では、3歳未満の<1回接種後>よりも抗体量が多かった」ことは読み取れます。しかし、その理由が「成長に伴い自然免疫が強くなったから」というのは誤りです。抗体の産生は獲得免疫の働きによるものです。
②【誤】
3歳未満の<接種前>で抗体が検出されたのは、母親由来の抗体が残っているか、あるいは本人が気づかないうちにその病原体に感染(不顕性感染)した経験がある可能性などが考えられます。抗体は獲得免疫によって産生されるものであり、「自然免疫の働きで産生していた」という説明は誤りです。
③【正】
7歳以上の集団は、3歳未満の集団に比べて、これまでの人生で病原体Bに感染したり、予防接種を受けたりした経験を持つ人の割合が高いと考えられます。そのため、接種前からある程度の抗体(免疫記憶)を持っている人が多く、ワクチンの接種が強力な二次応答を引き起こしたと解釈できます。これが、1回の接種で抗体量が爆発的に増加した理由として最も妥当です。
④【誤】
予防接種は、特定の病原体Bの抗原に対して特異的に反応する抗体の産生を促すものです。免疫には特異性があり、関係のない他のすべての抗原に対する抗体の産生が促されるわけではありません。したがって、この記述は誤りです。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
生態系における栄養段階と、生態ピラミッド(個体数ピラミッド)の関係についての基本的な理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
生態系では、生産者(植物など)から一次消費者、二次消費者、高次消費者へと栄養段階が上がるにつれて、利用できるエネルギー量は大きく減少していきます(エネルギー効率は約10%)。そのため、上位の栄養段階の生物を支えるためには、より大量の下位の栄養段階の生物が必要となり、結果として上位の栄養段階にいくほど個体数は少なくなる傾向があります。これを個体数ピラミッドと呼びます。マッコウクジラのような最上位の捕食者は個体数が少なくなります。
②【誤】
キーストーン種は、その生態系における個体数や生物量は少ないにもかかわらず、他の多くの種の存続に大きな影響を与える重要な種のことです。高次消費者がキーストーン種である場合もありますが、高次消費者の特徴として「キーストーン種によって制限されやすい」というのは一般的ではありません。
③【誤】
栄養段階が最上位であるということは、その生物を捕食する天敵が基本的に存在しないことを意味します。したがって、「捕食されやすい」は誤りです。
④【誤】
一般的に、栄養段階が上位の生物ほど、体のサイズは大きくなる傾向があります。マッコウクジラはその典型的な例です。
問2:正解④
<問題要旨>
生物の遺骸が分解される速さに影響を与える要因について、直接的な理由を正しく理解しているかを問う問題です。分解者の活動や、それを取り巻く環境要因についての知識が求められます。
<選択肢>
a【正】
生物の遺骸(有機物)を無機物に分解する中心的な役割を担うのは、細菌や菌類といった分解者です。したがって、これらの分解者の活動が不活発であれば、分解速度は直接的に遅くなります。例えば、深海のような低温・高圧の環境や、酸素が乏しい湿地などでは、分解者の代謝活動が抑制されるため、分解が遅くなります。
b【正】
分解には、細菌や菌類だけでなく、ミミズやダンゴムシのように遺骸を直接消費する生物(デトリタス食者)も関与します。これらの生物が遺骸を細かくすることで、微生物による分解がさらに進みやすくなります。そのため、こうした遺骸を消費する生物の総量が少なければ、分解のプロセス全体が遅くなる直接的な原因となります。
c【誤】
光合成を行う生物(生産者)の総量は、その生態系に供給される有機物の総量に関係しますが、すでに存在する遺骸の「分解速度」そのものに直接影響を与えるわけではありません。分解速度は、遺骸が置かれた環境(温度や水分など)や、それを分解する生物の活動度に依存します。
以上のことから、分解が遅くなる直接的な理由として適当なのはaとbです。したがって、aとbを過不足なく含む選択肢である④が正解となります。
問3:正解①
<問題要旨>
生物の死体が、異なる方法で処理された場合の、生態系におけるエネルギーの流れと物質循環についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
砂浜に埋められた死体は、有機物の塊です。この有機物は、土壌中にいる細菌や菌類などの分解者によって分解されたり、他の動物に食べられたりします。その過程で、死体が持っていた化学エネルギーは、それらの生物の生命活動(呼吸など)のためのエネルギーとして利用されます。これは、生態系における正常なエネルギーの流れと物質循環の一部です。
②【誤】
死体を燃やすと、有機物に含まれる化学エネルギーが熱エネルギーに変換される、という点は正しいです。しかし、生物(生産者)がエネルギーを取り込む「同化」のうち、熱エネルギーを化学エネルギーに変換できるものはありません。光エネルギーを化学エネルギーに変えるのが光合成です。
③【誤】
埋められた死体の有機物は、分解者によって二酸化炭素や水、アンモニウム塩などの無機物にまで分解されます。このうち、分解者の呼吸によって生じた二酸化炭素は、大気中に放出されます。したがって、「大気中へは放出されない」という記述は誤りです。
④【誤】
燃やされた死体から生じた無機物(二酸化炭素など)は、大気中に放出された後、植物の光合成などによって再び生物に取り込まれ、有機物の合成に利用されます。これは物質循環の一環です。したがって、「ほかの生物に利用されない」という記述は誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
世界のバイオーム(生物群系)について、緯度に伴う気候の変化に応じた水平分布の順序と、それぞれの特徴を正しく理解しているかを問う問題です。示されたバイオームの配列から、空欄に当てはまるバイオームの特徴を的確に選び出す必要があります。
<選択肢>
問題文に示されたバイオームの配列は、熱帯多雨林 → ア → サバンナ → 砂漠 → イ → ウ → 針葉樹林 です。この配列と各記述を照らし合わせていきます。
・【ア】について
「ア」は、熱帯多雨林とサバンナの間に位置しています。年間を通して高温な熱帯地域で、森林が成立するほどの降水量があるものの、明瞭な雨季と乾季が存在する気候帯に成立するバイオームは「雨緑樹林」です。これは、乾季に葉を落とす樹木(落葉広葉樹)が特徴です。
したがって、選択肢【a】の「雨季と乾季が明瞭な地域に成立し、チーク類など、乾季に落葉する広葉樹が優占する」という記述が「雨緑樹林」に合致するため、【ア】は【a】となります。
・【イ】と【ウ】について
「イ」と「ウ」は、砂漠と針葉樹林の間に位置します。これは、乾燥した気候から冷涼な気候へと移り変わる温帯に見られるバイオームの配列です。
一般的に、砂漠のような極度に乾燥した地域から、より湿潤な森林地帯へ移行する際には、まず樹木の生育には不十分な降水量の草原地帯が広がります。これが「ステップ(温帯草原)」です。
したがって、【イ】には、選択肢【f】の「年降水量が少なく、イネのなかまが優占する草原が広がり、樹木は少ない」という「ステップ」の記述が当てはまります。
そして、ステップよりも降水量が多く、より冷涼な地域へ進むと、冬の寒さに適応して落葉する広葉樹からなる「夏緑樹林」が広がります。
したがって、【ウ】には、選択肢【e】の「気候は冷涼で、ブナ類やカエデ類など、冬に落葉する広葉樹が優占する」という「夏緑樹林」の記述が当てはまります。
以上のことから、アにはa、イにはf、ウにはeがそれぞれ対応するため、この組合せである③が正解となります。
問5:正解②
<問題要旨>
日本のバイオームについて、緯度による水平分布と標高による垂直分布を組み合わせた、より具体的な分布の知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
針葉樹林は、本州中部の亜高山帯だけでなく、水平分布として、より寒冷な北海道の平地から山地にかけても広く分布しています。しかし、「標高によらず優占する」という表現は不正確で、北海道でも標高が非常に高くなると森林限界を超え、高山植物帯となります。
②【正】
夏緑樹林(ブナ、ミズナラなど)が優占する冷温帯は、南の地域(九州・四国)では標高の高い山地帯に分布しますが、北上して東北地方に行くと、より低い標高の丘陵帯(低地帯)までその分布域が下がってきます。これは、緯度が高くなるほど同じ気温帯の標高が低くなるためで、正しい記述です。
③【誤】
照葉樹林(シイ、カシなど)が優占する暖温帯は、西日本の低地を代表するバイオームですが、関東地方の平野部にも広く分布しています(ただし、多くは人間活動により失われています)。したがって、「関東地方には分布しない」は誤りです。
④【誤】
亜熱帯多雨林は、日本では主に沖縄などの南西諸島に分布します。九州地方の大部分の低地は照葉樹林帯に属し、亜熱帯多雨林は分布しません。