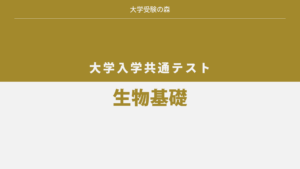解答
解説
第1問
問1:正解⑥
<問題要旨>
問題文と表から、乳酸菌とコウジカビがそれぞれ原核生物と真核生物のどちらに分類され、どのような細胞構造を持つかを判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
コウジカビは真菌類(真核生物)であり、動物や植物と同じくミトコンドリアを持つため、イに分類されます。しかし、乳酸菌は原核生物であり、ア(葉緑体を持つ真核細胞)には分類されません。
②【誤】
乳酸菌は原核生物であり、ア(葉緑体を持つ真核細胞)には分類されません。
③【誤】
乳酸菌はウ(原核細胞)に分類されますが、コウジカビはイ(ミトコンドリアを持つ真核細胞)に分類されるため、アではありません。
④【誤】
乳酸菌はウ(原核細胞)に分類されます。
⑤【誤】
コウジカビはイ(ミトコンドリアを持つ真核細胞)に分類されます。
⑥【正】
問題文より、乳酸菌は核を持たないため原核生物です。原核生物は、細胞膜と細胞壁を持ちますが、ミトコンドリアや葉緑体のような膜構造を持つ細胞小器官は持ちません。したがって、表のウが乳酸菌に相当します。一方、コウジカビは核を持つ真核生物です。真菌類であり、光合成は行わないため葉緑体は持ちませんが、呼吸のためにミトコンドリアは持ちます。したがって、表のイがコウジカビに相当します。よって、この組み合わせは正しいです。
問2:正解①
<問題要旨>
図に示された代謝過程A(同化の例:光合成)とB(異化の例:呼吸)について、両方に共通する特徴ではなく、どちらか一方にのみ当てはまる記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
過程Aは光エネルギーを利用して無機物から有機物を合成する「同化(光合成)」、過程Bは有機物を分解してエネルギーを取り出す「異化(呼吸)」です。従属栄養生物は、自身で有機物を合成できないため過程Aを行わず、外部から取り入れた有機物を分解してエネルギーを得るため過程Bのみを行います。したがって、これは過程Bのみに該当する記述です。
②【誤】
同化(A)も異化(B)も、生体内での化学反応であり、多数の酵素の働きによって円滑に進行します。したがって、両方の過程に該当します。
③【誤】
ATPは、エネルギーを放出してADPとリン酸に分解され、またエネルギーを吸収して合成されます。この性質から「エネルギーの通貨」と呼ばれ、同化(A)と異化(B)の両方の過程でエネルギーの受け渡しに利用されます。したがって、両方の過程に該当します。
④【誤】
過程B(呼吸)の一部である解糖系は細胞質基質で行われます。過程A(光合成)は葉緑体で行われますが、葉緑体も細胞質に存在します。しかし、①が明確に一方の過程のみに該当する記述であるため、これは最も適当な選択肢とは言えません。
問3:正解③
<問題要旨>
酵母(酵母菌)を用いた実験結果から、酸素の有無で数が変動する細胞小器官Xの働きを推測する問題です。細胞小器官Xはミトコンドリアであると同定できます。
<選択肢>
①【誤】
記述a(光合成に関与する)は、葉緑体の働きです。酵母は菌類であり、光合成を行いません。
②【誤】
記述b(染色体の凝縮に関与する)は、細胞分裂の際に核内で起こる現象であり、特定の細胞小器官の働きではありません。
③【正】
問題文から、細胞小器官Xは酸素がある条件下で増え、酸素を消費することから、好気呼吸に関わるミトコンドリアであるとわかります。好気呼吸は、有機物を分解してエネルギーを取り出す「異化」の代表例です。したがって、記述c(異化に関与する)は、ミトコンドリアの主な働きとして適当です。
④【誤】
記述a、bは誤りです。
⑤【誤】
記述aは誤りです。
⑥【誤】
記述bは誤りです。
⑦【誤】
記述a、bは誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
ゲノム、DNA、遺伝子発現に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ゲノムは、ある生物が持つ遺伝情報の1セットのことであり、その大きさ(塩基対数)は細胞周期のどの時期でも変化しません。なお、DNA量はS期に複製されるため、G1期からG2期にかけて2倍になります。
②【誤】
DNAは塩基が対になった二重らせん構造をとっています。したがって、100万「塩基対」のDNAは、100万組の塩基の対からできており、ヌクレオチド(塩基、糖、リン酸からなる単位)の総数はその2倍の200万個になります。
③【誤】
mRNAは一本鎖RNAであり、二本鎖DNAでみられるシャルガフの規則(AとT、GとCの量が等しい)は成り立ちません。そのため、アデニン(A)の割合が30%であっても、グアニン(G)の割合を特定することはできません。
④【正】
同一個体の体細胞は、原則として全て同じゲノム(遺伝情報のセット)を持っています。しかし、細胞が特定の機能を持つように分化する過程で、発現する遺伝子の種類が異なります。これを「遺伝子発現の調節」といい、その結果、細胞の種類によって存在するタンパク質の種類や量は異なります。
問5:正解④
<問題要旨>
タンパク質のアミノ酸数、遺伝子の数、ゲノムに占める遺伝子領域の割合から、ゲノム全体の大きさを計算する問題です。
<選択肢>
①【誤】
計算結果と異なります。
②【誤】
計算結果と異なります。
③【誤】
計算結果と異なります。
④【正】
まず、1つのタンパク質をコードする遺伝子領域の塩基数を求めます。1つのアミノ酸は3つの塩基(1コドン)によって指定されるので、平均270個のアミノ酸からなるタンパク質を作るためには、270 × 3 = 810個の塩基が必要です(終止コドンは計算を簡略化するためここでは無視します)。
次に、ゲノム中の全遺伝子領域の塩基数を計算します。遺伝子は2000個あるので、810塩基 × 2000個 = 1,620,000塩基(162万塩基)となります。
最後に、ゲノム全体の大きさを計算します。遺伝子領域がゲノム全体の90%を占めるので、ゲノム全体の塩基数を G とすると、「G × 0.90 = 162万塩基」という式が成り立ちます。これを解くと、G = 162万 ÷ 0.9 = 180万塩基となります。ゲノムの大きさは通常「塩基対」で表されるため、180万塩基対が答えとなります。
⑤【誤】
計算結果と異なります。
⑥【誤】
計算結果と異なります。
問6:正解⑤
<問題要旨>
大腸菌の遺伝子数、mRNA数、タンパク質数のデータから、遺伝子発現の仕組みについて考察する問題です。
<選択肢>
①【誤】
記述a:ゲノムに存在する遺伝子の数は、生物種に固有のものであり、培養条件によって変化することはありません。
②【誤】
記述a、cは誤りです。
③【誤】
記述c:ゲノムには約4200個の遺伝子がありますが、mRNAの総数は約8000または約3000です。これは、全ての遺伝子が常に転写されているのではなく、状況に応じて必要な遺伝子だけが転写されていることを示しています。
④【誤】
記述a、cは誤りです。
⑤【正】
記述b:遺伝子の総数(約4200)よりもmRNAの総数(約8000)の方が多い条件(条件A)があることから、一つの遺伝子(DNA領域)から複数のmRNAが繰り返し転写されることがあるとわかります。
記述d:遺伝子の総数(約4200)に対して、タンパク質の総数(約300万)は非常に多いです。これは、一つのmRNAから多数のタンパク質が翻訳されること、つまり同じ種類のタンパク質が細胞内に複数個存在することを示しています。したがって、bとdの組み合わせが適当です。
⑥【誤】
記述cは誤りです。
第2問
問1:正解②
<問題要旨>
内分泌系で働くホルモンに関する一般的な記述の中から、適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
ホルモンは内分泌腺でつくられ、毛細血管などの循環系(血液中)に直接分泌されます。そして、血液によって全身に運ばれ、特定の器官(標的器官)にある標的細胞に作用します。
②【誤】
1種類のホルモンであっても、作用する標的細胞の種類によって異なる応答を引き起こすことがあります。例えば、アドレナリンは心筋の細胞に作用すると心拍数を増加させますが、消化管の平滑筋に作用するとその動きを抑制します。したがって、「どの標的器官でも同じ応答を引き起こす」という記述は誤りです。
③【正】
ホルモンが特定の細胞にのみ作用するのは、その細胞(標的細胞)がホルモンと特異的に結合する「受容体」を持っているためです。
④【正】
視床下部に存在する一部の神経細胞(神経分泌細胞)は、他の神経細胞に情報を伝達するのではなく、血管にホルモン(放出ホルモンや放出抑制ホルモンなど)を分泌します。
⑤【正】
自律神経系と内分泌系は互いに連携して恒常性を維持しています。例えば、交感神経は副腎髄質に作用してアドレナリンの分泌を促進します。
問2:正解①
<問題要旨>
運動時の血糖濃度と2種類のホルモン濃度の変化を示したグラフを読み取り、ホルモンの働きを推測する問題です。
<選択肢>
①【正】
運動によって血糖が消費され血糖濃度が低下すると(グラフ左)、それを上昇させるために働くホルモンの分泌が促進されます。グラフ右で運動中に濃度が上昇しているホルモンAは、血糖値を上昇させる働きを持つと考えられます。すい臓から分泌されるホルモンのうち、血糖値を上昇させるのはグルカゴンです。グルカゴンは、肝臓に働きかけてグリコーゲンの分解を促進し、グルコースを血液中に放出させることで血糖値を上げます。したがって、この記述はホルモンAの働きとして適当です。
②【誤】
ホルモンBは運動中に濃度が低下していることから、血糖値を低下させるインスリンだと考えられます。グルカゴン(ホルモンA)とインスリン(ホルモンB)は、血糖濃度に応じてそれぞれ分泌量が調節され、互いに反対の作用(拮抗作用)を示しますが、インスリンがグルカゴンの分泌を直接抑制するわけではありません。
③【誤】
ホルモンB(インスリン)は血糖値を低下させます。一方、アドレナリンは血糖値を上昇させる働きを持つため、両者の働きは逆です。
④【誤】
ホルモンB(インスリン)の分泌は、主に血糖濃度の上昇によって促進され、低下によって抑制されます。心拍数の増加がインスリン分泌を直接抑制するわけではありません(運動に伴い交感神経が優位になることでインスリン分泌は抑制されますが、心拍数そのものが原因ではありません)。
問3:正解⑤
<問題要旨>
インスリン濃度が正常であるにもかかわらず高血糖が続く患者の状態から、インスリンの作用機序のどこに問題があるかを考察する問題です。これは2型糖尿病の典型的な病態です。
<選択肢>
①【誤】
インスリン濃度は健康な人とほぼ同じであるため、「合成」に問題があるとは考えにくいです。
②【誤】
「合成」に問題があるとは考えにくく、またグルコースは細胞で「合成」されるのではなく、取り込まれて利用(分解)されます。
③【誤】
インスリン濃度は正常なので、「分泌」に問題があるとは考えにくいです。
④【誤】
「分泌」に問題があるとは考えにくく、グルコースは「合成」されません。
⑤【正】
Yさんの体内では、インスリンの量は正常であるにもかかわらず血糖値が下がらないことから、インスリンが標的細胞(筋肉や肝臓の細胞)で正常に機能していないと考えられます。これは、標的細胞にあるインスリン受容体の感受性が低下し、インスリンを正常に「ア:受容」できなくなった状態(インスリン抵抗性)が原因と推測されます。インスリンが正常に作用しないと、細胞へのグルコースの「イ:細胞への取り込み」が促進されず、血液中にグルコースが過剰な状態(高血糖)が続きます。その結果、細胞はエネルギー源としてのグルコースを十分に利用できなくなります。
問4:正解③
<問題要旨>
インフルエンザウイルス感染の初期段階で起こる「喉の腫れ」が、どの免疫の働きによるものかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
細胞性免疫は、キラーT細胞などが感染細胞を攻撃する獲得免疫の一種であり、感染から数日経ってから本格的に機能します。初期段階の反応ではありません。
②【誤】
体液性免疫は、B細胞が産生する抗体によって病原体を排除する獲得免疫の一種であり、これも感染初期の反応ではありません。
③【正】
喉の腫れや発赤、痛み、発熱といった症状は「炎症反応」と呼ばれます。これは、病原体などの異物が体内に侵入した際に、マクロファージやマスト細胞などが働き、病原体を排除し、組織の修復を促すための初期の防御反応です。この炎症反応は、病原体の種類を問わず非特異的に働く「自然免疫」に含まれます。
④【誤】
胸腺で成熟する免疫細胞はT細胞であり、獲得免疫を担います。感染初期の反応ではありません。
⑤【誤】
気管の粘膜が分泌する粘液は、病原体の侵入を防ぐ物理的なバリアであり、体内に侵入した後の「腫れ」という炎症反応を直接引き起こす働きではありません。
問5:正解⑧
<問題要旨>
インフルエンザからの回復が早かった母の体質について、獲得免疫が開始される仕組みと関連付けて考察する問題です。
<選択肢>
①~⑦【誤】
理由については⑧で説明します。
⑧【正】
獲得免疫(適応免疫)が効率よく働くためには、まず異物(抗原)の情報をリンパ球に伝える必要があります。この役割を担うのが「ウ:樹状細胞」などの抗原提示細胞です。樹状細胞は、皮膚や粘膜などで病原体を取り込むと、「エ:リンパ節」に移動します。そして、そこで待機している特定の「オ:T細胞」(特にヘルパーT細胞)に抗原の情報を提示し、活性化させます。このT細胞の活性化が、その後のB細胞の活性化(抗体産生)やキラーT細胞の活性化につながるため、獲得免疫全体の司令塔となります。母の回復が早かったのは、この一連のプロセス、特に樹状細胞による抗原提示からT細胞の活性化までが効率よく行われたためではないか、と考えるのが最も論理的です。
問6:正解④
<問題要旨>
アナフィラキシーショックの症状と治療による回復過程を、免疫、循環系、自律神経系の働きと関連付けて解釈する問題です。
<選択肢>
①【誤】
キ:血圧の大幅な低下は血管の「拡張」によって起こります。
②【誤】
キ:血圧の大幅な低下は血管の「拡張」によって起こります。ク:時間帯Ⅱは心拍数が安定に向かって減少しており、副交感神経の働きが優位になっていると考えられます。
③【誤】
ク:時間帯Ⅰでは血圧低下を補うために心拍数が増加しており、交感神経が優位に働いていると考えられます。心拍数が減少に転じている時間帯Ⅱが副交案神経の作用と考えるのが妥当です。
④【正】
カ:アナフィラキシーは、ハチ毒(抗原)に対して体内で過剰に起こる「免疫反応」です。
キ:この免疫反応の結果、マスト細胞などからヒスタミンが大量に放出され、全身の毛細血管が急激に「拡張」します。これにより、血液が末梢に停留し、循環する血液量が相対的に減少するため、血圧が大幅に低下します。
ク:図2を見ると、治療によって血圧が回復する過程で、一時的に上昇していた心拍数が「時間帯Ⅱ」において持続的に低下しています。心拍数を減少させるのは副交感神経の働きです。したがって、時間帯Ⅱにおける心拍数の変化は、興奮状態が収まり、副交感神経の作用が優位になってきた結果と解釈できます。
⑤~⑧【誤】
カ:アナフィラキシーは免疫不全(免疫が働かない状態)ではなく、免疫の過剰反応です。
第3問
問1:正解①、④(順不同)
<問題要旨>
ササの刈り取りの有無が、林床の光環境とそこに生育する草本(種T)の個体数や成長にどう影響するかを、2つのグラフから読み取り、解釈する問題です。
<選択肢>
①【正】
図1を見ると、刈り取り区・対照区のどちらにおいても、3月の光の強さは8月よりも明らかに強い値を示しています。これは、雑木林の優占種であるコナラなどの夏緑樹が、冬から春にかけて(3月)は落葉しており、夏(8月)は葉が茂っているため、林床に届く光の量が変わることを示しています。
②【誤】
図1の3月のデータを比較すると、刈り取り区(ササなし)の方が対照区(ササあり)よりも光が強くなっています。ササは常緑性であるため、冬でも葉があり、その繁茂は春の林床の光を遮ることがわかります。したがって、光の強さは「変わらない」わけではありません。
③【誤】
図1より林床の光環境が明るいのは刈り取り区です。しかし、図2の個体の総数を見ると、刈り取り区(約115個体)よりも対照区(約190個体)の方が多くなっています。
④【正】
図2を見ると、葉の総数は、ササが繁茂している対照区では約500枚であるのに対し、ササを刈り取った区では約1700枚です。このことから、ササが繁茂すると種Tの葉の総数は減少することがわかります。
⑤【誤】
個体当たりの葉の数を計算すると、刈り取り区では約1700枚 ÷ 約115個体 ≒ 14.8枚/個体、対照区では約500枚 ÷ 約190個体 ≒ 2.6枚/個体となります。したがって、ササの刈り取りにより、個体当たりの葉の数は「増加」します。
⑥【誤】
ササの繁茂による影響の度合いを、刈り取り区に対する対照区の割合で比較します。葉の総数は約500/1700≒0.29倍に、花の総数は約40/380≒0.11倍に減少しています。花の総数の方がより大きく減少しているため、花の総数の方がより強く影響を受けていると言えます。
問2:正解②
<問題要旨>
森林の遷移や構造に関連する記述の中から、適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
森林では、樹木の葉が茂る層(林冠)が太陽光を遮るため、その下の林床に届く光は弱くなります。林冠と林床では光環境が大きく異なります。
②【誤】
極相林は、遷移の最終段階に到達した安定した森林で、主に陰樹で構成されます。陰樹の幼木は、親木の下の暗い林床で生育する必要があるため、弱い光でも成長できる「陰生植物」としての性質を持っています。強い光を好む「陽生植物」の性質は持ちません。
③【正】
遷移が進行するにつれて、草本、低木、陽樹、陰樹へと植生が変化し、植物の背が高く、階層構造も複雑になります。その結果、林冠が林床を覆うようになり、林床は暗くなります。
④【正】
ギャップとは、台風などによる倒木で林冠の一部が失われ、林床に直接光が届くようになった場所のことです。そのため、ギャップの林床は周囲より明るくなります。
⑤【正】
遷移が進行すると、光、土壌などの環境が変化します。それに伴い、その環境に適応した植物が生育するようになり、林床に生育する植物種も変化していきます。
問3:正解③
<問題要旨>
3つの異なる森林(地点X, Y, Z)における土壌動物のデータ(表1、図3)と環境データ(表2)を比較し、結果を正しく解釈している記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
「その他の分類群」の「個体数」が最も多いのは、表1から地点Z(84個体)です。スギが優占する地点Yは66個体なので、この記述は誤りです。なお、図3は分類群の「数」であり、個体数ではありません。
②【誤】
落葉や落枝の層・腐植に富む層が厚いのは地点YとZです。表1の個体数の合計を見ると、地点X(27) < 地点Y(193) < 地点Z(357) となっており、この層が厚い方が土壌動物の個体数は多い傾向にあります。記述の内容は逆です。
③【正】
各地点でのカメムシ類の個体数が全体に占める割合を計算します。
・二次林の地点Z:49 ÷ 357 ≒ 13.7%
・人工林の地点X:1 ÷ 27 ≒ 3.7%
・人工林の地点Y:8 ÷ 193 ≒ 4.1%
したがって、二次林の地点Zでは、人工林の地点X, Yよりもカメムシ類の占める割合が大きいと言えます。
④【誤】
下層の植生がよく発達しているのは地点Zです。表1を見ると、ミミズ類の個体数は地点Y(27個体)が最も多く、地点Z(13個体)ではありません。
問4:正解④
<問題要旨>
「土壌動物の分類群の数は、林床の光環境の影響を受ける」という仮説を検証するための実験計画として、最も適切なものを選ぶ問題です。対照実験の基本を押さえることが重要です。
<選択肢>
①【誤】
地点Xでヒノキを伐採すると、光環境だけでなく、リター(落葉落枝)の種類や量、土壌の湿度など、他の多くの環境条件が変わってしまいます。また、比較対象が異なる植生の地点Yであるため、光以外の条件が違いすぎ、光の影響だけを調べることはできません。
②【誤】
この操作は、「落葉や落枝の層・腐植に富む層」という、光環境とは別の条件を変化させるものです。仮説の検証にはなりません。
③【誤】
下層植生を刈り取ると、光環境だけでなく、土壌動物の生息場所や餌も変化させてしまいます。また、条件の異なる地点YとZの調査区間での比較であり、適切な対照実験とは言えません。
④【正】
この計画では、同じ地点Z内で、一部を覆って人為的に「暗い」条件を作り出します。そして、その他の条件(植生、土壌など)が同じである「覆いをしなかった場所(明るい)」と比較します。これにより、「光環境」という条件だけを変化させてその影響を調べることができ、仮説を検証するための対照実験として最も適しています。