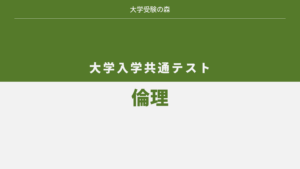解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
この問題は、様々な宗教における正義や規範についての理解を問うものです。それぞれの宗教の基本的な教義や戒律に関する正確な知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
イスラームは、ムハンマドが唯一神アッラーからの啓示を受けて創始した宗教です。そのため、啓示を受ける以前のアラビア社会の多神教的な伝統を否定するところから始まっており、それを遵守するように命じることはありません。
②【誤】
ヒンドゥー教は、古代のバラモン教から発展した宗教であり、ヴァルナ制として知られる身分制度(カースト制度)を否定せず、むしろ社会の根幹として受け継いでいます。したがって、「全ての人が平等とみなされ」という記述は誤りです。
③【正】
仏教において、在家信者には殺生や盗み、嘘などを禁じる五戒が基本的な行為規範として課せられています。一方、世俗を離れて修行に専念する出家信者(僧侶)には、五戒よりもはるかに多くの、より厳格な戒律(具足戒など)が定められていました。
④【誤】
ユダヤ教の十戒には、「わたしのほかに、ほかの神々があってはならない」として唯一神ヤハウェへの信仰が定められていますが、「救世主(メシア)を待望すべきこと」は含まれていません。メシア待望はユダヤ教の重要な思想ですが、モーセが神から授かったとされる十戒の条文には含まれません。
問2:正解④
<問題要旨>
この問題は、様々な宗教や思想における理想的な生き方についての理解を問うものです。それぞれの思想家や宗派が何を重視し、どのような生き方を説いたかを正確に把握しているかが試されます。
<選択肢>
①【誤】
パリサイ(ファリサイ)派は、モーセの律法を厳格に解釈し、日常生活の細部に至るまで遵守することを人々に求めた集団でした。律法を形骸化させると見なした人々を批判したのであり、柔軟な生き方を求めたわけではありません。
②【誤】
アリストテレスは、人間にとっての最高の幸福(エウダイモニア)は、理性を最大限に発揮する観想(テオーリア)的な生活にあると考えました。倫理的徳を実践する政治的生活も優れた生き方としましたが、「最も望ましい」「最高の幸福」としたのは観想的生活です。
③【誤】
ジャイナ教は、徹底した不殺生(アヒンサー)を戒律とします。農業は土を耕す際に多くの生物を殺傷してしまうため、ジャイナ教の信者の多くは、不殺生の戒律を守りやすい商業に従事しました。
④【正】
老子は、人為的な社会制度や道徳(仁義)を否定し、万物の根源である「道(タオ)」に従い、自然のままに(無為自然)生きることを理想としました。そして、小さな国家で質素な生活に満足する「小国寡民」が理想的な社会のあり方であると説いています。
問3:正解①
<問題要旨>
この問題は、イスラームの聖典『クルアーン』の一節を読み解き、そこに示された対人関係のあり方と、イスラーム共同体(ウンマ)の結びつきの根拠を理解するものです。
<選択肢>
①【正】
空欄a:資料には「どの民にも他の民を嘲笑させてはならない。これら(嘲笑される民)はそれら(嘲笑する民)よりもすぐれているかもしれないのだから」とあり、相手の方が優れている可能性を理由に、他者を嘲笑することを禁じています。記述と一致します。
空欄b:イスラームでは、信徒(ムスリム)同士は同胞とされ、相互扶助の精神が重視されます。特に、喜捨(ザカート)は信仰告白、礼拝、断食、巡礼と並ぶ五行の一つであり、貧者を救済することは共同体を結びつける重要な義務です。記述はイスラームの教えと合致しています。
②【誤】
空欄b:「1日に5回、エルサレムに向かって祈ること」は誤りです。イスラームの礼拝は、メッカのカーバ神殿の方角を向いて行われます。
③【誤】
空欄a:「限られた情報を頼りに想像力を駆使して、人を総合的に評価すべきだ」は、資料の「憶測をできるだけ避けよ。ある種の憶測は罪である。互いにさぐりあったり、陰口をたたいたりするではない」という記述と正反対です。
④【誤】
空欄b:「1日に5回、ムハンマドの肖像画を拝むこと」は誤りです。イスラームでは偶像崇拝が厳しく禁じられており、神や預言者を絵や像で表現して崇拝することはありません。
問4:正解②
<問題要旨>
この問題は、キリスト教、墨家、仏教における共存や共生に関する思想の正誤を判断するものです。それぞれの思想の核心的な教えを正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
ア【正】
イエスは、山上の垂訓において「敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」と説きました。これは、愛の対象を仲間や同胞に限定せず、敵対する者にまで広げる「隣人愛」の教えであり、記述は正しいです。
イ【正】
墨家は、血縁や身分にとらわれず、全ての人を差別なく愛する「兼愛」と、互いに利益を与え合う「交利」を説きました。これにより争いをなくし、人々が平和に共存する社会を目指したため、記述は正しいです。
ウ【誤】
ブッダは、人間を苦しめる原因は、不変な実体としての「我(アートマン)」が存在するという誤った考え(我執)にあるとしました。そして、この我執を捨てること(無我)で苦しみから解放されると説きました。他者のアートマンを尊重するのではなく、アートマンという概念そのものを否定したため、記述は誤りです。
問5:正解⑧
<問題要旨>
この問題は、ブッダとパウロの思想、および彼らの言葉を記した資料の内容について、正しい説明を全て選ぶものです。思想家の教えと、提示された資料の読解の両方が求められます。
<選択肢>
ア【誤】
ブッダは、この世のあらゆるものは常に変化し(諸行無常)、不変の実体はなく(諸法無我)、それゆえに人生は本質的に苦である(一切皆苦)と説きました。「苦とも楽とも断定できない」という記述は、一切皆苦の教えと矛盾するため誤りです。
イ【正】
パウロは、イエスが十字架で死んだことを、全人類の罪を代わりに背負って贖う(あがなう)ための犠牲(贖罪)と捉えました。この信仰によってのみ人は義とされる(信仰義認)と考え、キリスト教神学の基礎を築きました。記述は正しいです。
ウ【正】
資料1には「既に生まれたものも、これから生まれようとするものも、全ての生き物は、幸せであれ」と記されています 。これは、現在生きているものだけでなく、未来に生まれてくるものも含めた全ての生命に対する慈悲の心(慈悲)を示しており、記述と一致します。
エ【正】
資料2には「ユダヤ人もギリシア人もありません。奴隷も自由人もありません。男も女もありません。あなたがたは皆、キリスト・イエスにあって一つだからです」とあります 。これは、キリストへの信仰の前では、民族・身分・性別といったあらゆる差異が無効化され、全ての人が神の子として平等であることを示しており、記述と一致します。
問6:正解②
<問題要旨>
この問題は、荀子の思想、特に彼の性悪説と礼治主義について、提示された『荀子』の資料に基づいて最も的確に説明している選択肢を選ぶものです。資料の読解力と荀子・孟子の思想に関する知識が必要となります。
<選択肢>
①【誤】
荀子は、人間の性は悪(欲望)ですが、教育や礼儀(偽)によって矯正することは可能だと考えました。「矯正し得ない」という部分が誤りです。
②【正】
荀子は、人間が生まれつき持つ性質(性)は利己的な欲望であり(性悪説)、善は後天的な努力や学習(偽)によって獲得されると考えました。資料でも、性は学んで得られるものではないとし、「礼義は聖人の偽から生じたものであり、人の性から生じたものではない」と述べています 。この立場から、人間の本性を善とする孟子の性善説を批判しており、選択肢の記述は資料の内容および荀子の思想と完全に一致します。
③【誤】
荀子は、後天的な学習や努力の産物である「偽」(礼義など)を社会秩序の維持に不可欠なものとして重視しました。「偽物にすぎないから不要だ」という記述は、荀子の思想とは正反対です。
④【誤】
荀子は、人間の本性は悪(邪悪)ですが、後天的な学習(偽)によって聖人にもなれる(「普通の人でも、禹のようになることができる」 )と考えました。「善を身に付けることはできない」という記述は誤りです。
問7:正解②
<問題要旨>
この問題は、ソフィストとキケロの思想を記した資料を読み解き、メモの空欄を埋めるものです。ソフィストの自然観(ピュシス)と人為(ノモス)の対立、およびストア派に影響を受けたキケロの自然法思想に関する理解が問われます。
<選択肢>
a:資料1には、ソフィストの思想として、「他人より多く持とうと欲張ること」が「自然本性」であり、それが「法によって力ずくで平等の尊重へと、脇へ逸らされている」とあります 。 これは、法(ノモス)が自然(ピュシス)としての「人間の欲求」を抑圧しているという考え方です。したがって、aには「人間の欲求」が入ります。
b:資料2では、キケロが「他人の不利益によって自分の利益を増すことは自然に反する」と述べています 。 これは、他者を犠牲にした「自己の利益」の追求を問題にしています。したがって、bには「自己の利益」が入ります。
c:ストア派は、理性が支配する自然(宇宙)の法則に従って生きることを理想としました。この思想は、人為的な法を超えた普遍的な法(自然法)が存在するという「自然法思想」の源流となりました。キケロもこの思想に強く影響を受けています。したがって、cには「自然法思想」が入ります。
以上の組み合わせから、②が正解となります。
問8:正解④
<問題要旨>
この問題は、冒頭からの会話全体の文脈を踏まえ、帰宅中のAとBの会話の空欄を埋めるものです。正義の普遍性と相対性、そして真理の探究についての対話の流れを理解する必要があります。
<選択肢>
a:登校中の会話でBは「正義は人間相互の関係の中で必然的に求められる」 、Aは「私たちの共存のために必要なもの」 と話し合っていました。 帰宅中の会話でAが「時代や文化を超えて正義に共通の理解みたいなものがある」と感じている ことから、 「人と人との関わり合いがあれば、そこに不可欠なものとして求められる」という④の記述は、これまでの議論を適切にまとめていると言えます。
b:Aは「自分の都合に応じて事実を捉えたり、規範なんて人間同士の約束事にすぎないものだとしたりする風潮」を危惧し 、Bは「そうした風潮に流されず、それを乗り越えることを目指して、私たちは、本当の正義や真理の探究を続ける必要がある」と応じています 。 この流れに続く具体例として、感覚的な思い込み(ドクサ)を批判し、イデアという事物の真の姿(真理)を理性によって探求すべきだとしたプラトンの思想は、最も文脈に合致しています。
①【誤】
a:「絶対的な正義が存在しているというのは確かだね」は、Aの「共通の理解みたいなものがあるって感じる」 という発見のニュアンスよりも断定的すぎます。
②【誤】
b:プロタゴラスはソフィストであり、「人間は万物の尺度である」と述べ、絶対的な真理を否定しました。これはBの「本当の正義や真理の探究を続ける必要がある」 という主張とは逆の方向性です。
③【誤】
a:「特定の正義概念が、あらゆる社会や文化を超えて全ての人々の生き方を規定している」も断定的であり、会話のニュアンスと異なります。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
この問題は、日本の仏教者である最澄と空也の思想や活動に関する正誤を判断するものです。平安時代の仏教に関する基本的な知識が問われます。
<選択肢>
ア【誤】
最澄は法華経の精神に基づき、全ての人間は成仏できる可能性(仏性)を持つという「一乗思想」を説きました。「成仏できる人とできない人を、悟りの能力により区別する」という記述は、差別なく全ての人が救われるとする最澄の思想とは異なるため誤りです。
イ【正】
空也は平安時代中期の僧で、「市聖(いちのひじり)」と呼ばれました。諸国を遍歴しながら、庶民に「南無阿弥陀仏」と念仏をとなえることを勧め(口称念仏)、橋を架けたり井戸を掘ったりする社会事業にも尽力しました。記述は空也の活動を正しく説明しています。
問2:正解④
<問題要旨>
この問題は、日本神話における神々の性格や行動についての理解を問うものです。『古事記』などに描かれる神々の姿に関する知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
『古事記』によれば、イザナキとイザナミは国生みの際に、天つ神にその方法を問い、その教えに従ってやり直しました。神の命令に「反発して従わなかった」わけではありません 。
②【誤】
日本の神話における神々は、合議(神議り)によって物事を決定することが多く、最上位の神が全てを独断で決めるような絶対的な人格神としては描かれていません。
③【誤】
和辻哲郎は、アマテラスが自身も高天原の神々を祀りつつ、自身もまた天津神として祀られる存在であることから、「祀るとともに祀られる神」と評し、その二重の性格に日本の神の尊貴さの根源を見いだしました。「尊貴さを否定した」という記述は誤りです。
④【正】
日本神話において、スサノヲが高天原へやって来た際、アマテラスはその真意を疑います。そこで、両者は誓約(うけい)を行い、互いの持ち物から子を成すことで心の潔白を証明しようとしました。スサノヲからは女神が生まれたため、彼は自らの「清き明き心」が示されたと宣言しました。記述は神話の内容と一致しています。
問3:正解④
<問題要旨>
この問題は、提示された資料を読み解き、そこに描かれている念仏僧が誰であり、その思想がどのようなものかを特定するものです。鎌倉仏教、特に浄土教の法然と一遍の思想の違いを理解しているかが鍵となります。
<選択肢>
a:資料の念仏僧は、「南無阿弥陀仏と一声となえれば極楽往生できる」と説き、「相手に信ずる気持ちがあろうがなかろうが」区別せず名号札を配るようお告げを受けています 。 これは信心の有無を問わず、念仏そのものによって往生が決定しているとする思想です。④の「南無阿弥陀仏と一声となえるだけで往生が決定すると説く」は、この思想と合致しています。
b:信心の有無や心の状態を問わず、ただ名号(南無阿弥陀仏)をとなえること自体に救済の力があるとし、「賦算(ふさん)」と呼ばれる名号札を配り歩いたのは一遍です。資料に描かれているのは一遍の姿です。
c:「往生の可否は信心と無関係」であり、「信心の起きない人でも」救われるという考えは、阿弥陀仏の本願によって全ての人の往生は既に決定しているとする一遍の思想(他力念仏の徹底)と一致します。法然は信心(三心)を重視した点で一遍と異なります。
以上の組み合わせから、④が正解となります。
問4:正解②
<問題要旨>
この問題は、江戸時代の儒学者、伊藤仁斎の「仁」についての思想を、身近な人間関係に即して説明した選択肢を選ぶものです。仁斎が「仁」をどのように捉えたかを正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
伊藤仁斎は、形式的な礼儀よりも内面的な誠実さや真心(誠)を重視しました。礼儀によって外面を整えることを「仁」とするのは、彼の思想とは異なります。
②【正】
伊藤仁斎は、仁を「愛」と捉え、それが親子や兄弟といった最も身近で日常的な人間関係(「活物」)の中に現れると考えました。偽りを排し、身近な他者へと思いやりの心(誠)を向けることで、相手からも思いやりが返ってくる、そうした具体的な愛情関係こそが「仁」であるとしました 。選択肢の記述は、この仁斎の思想を的確に表現しています。
③【誤】
私利私欲を厳しく戒めるのは朱子学の特徴であり、仁斎は観念的な理を批判しました。「欲望から完全に脱する」といった禁欲的な態度は、仁斎の思想とは異なります。
④【誤】
上下関係の秩序(理)を重んじるのは朱子学の考え方です。伊藤仁斎は、そのような固定的・観念的な「理」ではなく、具体的な人間関係の中にある「仁」を重視しました。
問5:正解①
<問題要旨>
この問題は、吉田松陰の思想と、彼が獄中で記した『講孟余話』の資料を読み解き、スピーチの空欄を埋めるものです。松陰の思想のキーワードと、資料から読み取れる彼の学習観を結びつける必要があります。
<選択肢>
a:吉田松陰は、孟子の「至誠」の思想を重視し、自らの心を偽らない純粋な真心である「誠」を尽くすことを行動の指針としました。したがって、aには「『誠』を掲げて、自己の心情の純粋さを追い求めること」が入ります。
b:資料で松陰は、学問を功利的な目的で行うことを否定し、「人と生まれて人の道を知らず」「士と生まれて士の道を知らないのは、恥の最たるもの」と述べています 。 そして、「もしこれを恥じる心があるならば、書を読み道を学ぶより他に方法はない」と結論づけています 。 つまり、学ぶ動機は「道をわきまえぬことを恥じる心」にあり、その目的は「人としての道を知る」ことなのです。したがって、bには「道をわきまえぬことを恥じる心に基づき、人としての道を知る」が入ります。
以上の組み合わせから、①が正解となります。
問6:正解②
<問題要旨>
この問題は、明治時代の啓蒙思想団体である明六社のメンバー(森有礼、西村茂樹、加藤弘之など)の思想や主張を特定するものです。それぞれの人物が何を問題にし、何を論じたかを正確に記憶しているかが問われます。
<選択肢>
ア:封建的な家父長制や一夫多妻制を批判し、夫婦が対等な権利を持つ一夫一婦制を理想としたのは、森有礼です。彼は『妻妾論』で近代的な契約に基づく婚姻関係を主張しました。
イ:明治期の欧化政策の行き過ぎを懸念し、西洋哲学の知見を取り入れつつも、儒教を基盤とした国民道徳の確立を主張したのは、西村茂樹です。彼は『日本道徳論』を著しました。
以上の組み合わせから、アが森有礼、イが西村茂樹となるため、②が正解となります。
問7:正解③
<問題要旨>
この問題は、日本を代表する哲学者、西田幾多郎の哲学に関する説明として最も適当なものを選ぶものです。「純粋経験」「場所の論理」「絶対矛盾的自己同一」といった彼の哲学のキーワードを正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
西田哲学は、主観と客観が分かれる以前の直接的な経験である「純粋経験」から出発します。「主観と客観の対立から出発し」という部分が誤りです。
②【誤】
西田が提唱した「場所」の論理は、主観的なものを一切含まない純粋な客観的世界ではなく、主観と客観の対立を包み込み、それらを成り立たせる根源的な場を指します。
③【正】
西田は晩年、世界の根源的なあり方を「絶対矛盾的自己同一」という概念で捉えました。これは、例えば「個」と「全」のような、互いに矛盾し対立するものが、対立したまま一つに統一されているという世界の動的な構造を表現したものです。記述は西田哲学の中心概念を正しく説明しています。
④【誤】
西田の言う「絶対矛盾的自己同一」は、歴史の進歩によって矛盾が乗り越えられた(解消された)状態ではなく、矛盾が矛盾として存在したまま統一されているという、現実世界のあり方そのものを指します。
問8:正解①
<問題要旨>
この問題は、Cの日記と三木清の文章を読み、Cの「問い」に対する考えの変化と、三木清の読書論の理解を結びつけて会話の空欄を補充するものです。対話の文脈と資料の読解が求められます。
<選択肢>
a:Cは日記の中で、吉田松陰の問いも、西田幾多郎の問いも、自分の自問自答も、「問いであるという点では同じなんだよな」と気づいています 。 その上で、三木清の読書論に触れています。したがって、aには「他者に向けられた問いも自問自答も問いであることは同じである」という、日記で得た気づきが入るのが最も自然です。
b:先生の「読書中の問いについて、三木は何と言っていますか?」という問いに対し、Cは資料の内容を要約して答えるはずです。資料には「問から答へ、答は更に問を生み、問答は限りなく進展してゆく」とあります 。 これは、問いが次々と新たな問いを生み出すということを示しており、bには「問いは次々に更なる新たな問いを生み出していく」という記述が入るのが適切です。
以上の組み合わせから、①が正解となります。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
この問題は、ルネサンス期の人物(マキャヴェリ、ラファエロ、ペトラルカ)の業績や思想に関する説明の正誤を判断するものです。それぞれの人物を正しく特定し、その活動内容を理解しているかが問われます。
<選択識>
ア【正】
マキャヴェリは『君主論』の中で、国家を維持するためには、宗教や道徳から切り離された現実主義的な政治(権謀術数)が必要であると説きました。目的のためには非道徳的な手段も許されるという彼の思想は、近代政治学の基礎を築きました。記述は正しいです。
イ【誤】
メディチ家の庇護を受け、「ダヴィデ」像を制作したのはミケランジェロです。ラファエロは主に聖母子像などで知られる盛期ルネサンスの画家ですが、「ダヴィデ」の作者ではありません。
ウ【誤】
『デカメロン』を著し、人間のありのままの感情や欲望を描いたのはボッカッチョです 。ペトラルカは古典研究を通じて人間性を探求した人文主義者(ヒューマニスト)として知られますが、『デカメロン』の作者ではありません。
問2:正解②
<問題要旨>
この問題は、近代経済学の父、アダム・スミスの経済思想に関する説明として最も適当なものを選ぶものです。彼の主著『国富論』における「見えざる手」の思想を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
アダム・スミスは、人々が自己の利益(利己心)を追求する自由な経済活動が、結果として社会全体の利益につながると考えました。利己心に基づく自由競争を否定するのではなく、むしろそれを肯定しています。
②【正】
アダム・スミスは、各人が自己の利益を追求して自由に経済活動を行えば、市場メカニズム、すなわち「見えざる手」によって導かれ、意図せずして社会全体の富が増大し、公益が促進されると説きました(予定調和)。記述はこの思想を正しく説明しています。
③【誤】
この記述は、資本主義社会における労働者の疎外を論じたマルクスの思想の説明です。アダム・スミスの思想ではありません。
④【誤】
この記述も、資本主義における労働疎外を論じたマルクスの思想(特に初期の『経済学・哲学草稿』で展開された類的存在からの疎外)の説明です。
問3:正解⑤
<問題要旨>
この問題は、法や規範について考察した思想家(ベンサム、ロック、トマス・アクィナスなど)の主張を特定し、正しい組み合わせを選ぶものです。近代の功利主義、社会契約説、中世のスコラ哲学に関する知識が問われます。
<選択肢>
ア:快楽と苦痛が人間の行動原理であるとし、行為を規制するものとして「四つの制裁(サンクション)」を挙げたのは、功利主義の創始者であるベンサムです。
イ:社会契約によって政府を設立しますが、政府が信託に反して市民の生命、自由、財産を侵害する場合には、人民は政府に抵抗し、新たな政府を樹立する権利(抵抗権・革命権)を持つと説いたのは、ロックです。
ウ:神が定めた普遍的な「永遠法」があり、人間は理性によってその一部である「自然法」を認識できるとしました。このように、神の法(啓示)と理性の法(哲学)は調和すると説いたのは、中世スコラ学を大成したトマス・アクィナスです。
以上の組み合わせから、アがベンサム、イがロック、ウがトマス・アクィナスとなるため、⑤が正解となります。
問4:正解③
<問題要旨>
この問題は、カントの道徳哲学における「自由」と「目的の王国」の概念について、読書ノートの空欄を埋めるものです。カントの自律、道徳法則、人格の尊厳といったキーワードの理解が求められます。
<選択肢>
a:カントにとっての真の「自由」とは、自然的な欲求や傾向性(眠気など)にただ従うことではなく、人間が自らの理性によって立てた普遍的な道徳法則に、自発的に従うこと(自律)です。したがって、aには「自らが立法した道徳法則に自発的に従う」が入ります。
b:カントが構想した「目的の王国」とは、全ての人々が互いを単なる手段としてだけでなく、常に同時に目的として尊重しあうような、理性的存在者からなる理想的な共同体のことです。そこでは各人の人格の尊厳が尊重されます。したがって、bには「各人が全ての人格を決して単に手段としてのみ扱うのではなく、常に同時に目的として尊重し合う」が入ります。
以上の組み合わせから、③が正解となります。
問5:正解④
<問題要旨>
この問題は、パスカルの人間観について、『パンセ』の一節を読み解き、その思想を的確に説明している選択肢を選ぶものです。「考える葦」「中間者」「偉大と悲惨」といったパスカルの思想のキーワードを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
パスカルは、人間の偉大さと惨めさは表裏一体であると考えました。「己の偉大さを深く省みることで、惨めにならずに済む」のではなく、偉大であるからこそ自らの惨めさを認識できるとしました。
②【誤】
パスカルにとって信仰は、人間の惨めさから目を背ける「気晴らし」ではなく、惨めさから救済される唯一の道でした。「信仰は…気晴らしにすぎない」という記述は誤りです。
③【誤】
資料には「惨めさは偉大さから結論され、偉大さは惨めさから結論される」とあり、惨めさの中にこそ偉大さを見いだすことができると述べています 。 「惨めさという不幸の中ではその偉大さを見いだすことはできない」という記述は、資料の内容と矛盾します。
④【正】
パスカルは、人間の真理は理性(幾何学的精神)だけでなく、心(繊細の精神)によって直観されると説きました。資料では、「王座を奪われた王でない限り、一体誰が自分が王でないことを不幸だと思うだろう」という比喩を使い、人間が自らの現状を「惨め」だと感じるのは、かつてはより善い本性を持っていた(偉大であった)ことの証拠である、と論じています 。 記述はパスカルの思想と資料の内容を正しく説明しています。
問6:正解③
<問題要旨>
この問題は、他者論を展開した哲学者レヴィナスの思想に関する説明として、最も適当なものを選ぶものです。彼の思想における「顔」「他者」の非対称的な関係性を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
レヴィナスにとって他者は、具体的な「顔」をもって現れ、私に倫理的な責任を問いかけてくる存在です。「顔を持たない無個性な存在」という記述は正反対です。
②【誤】
レヴィナスは、私と他者の関係を、対等で相互的なものではなく、無限に高い位置から私に「汝、殺すなかれ」と命じる、非対称的な関係として捉えました。「対等なものとして…承認し合う関係」という記述は誤りです。
③【正】
レヴィナスによれば、他者は、私の理解やカテゴリー化を常に超えてしまう異質な存在(無限)として、その「顔」において私に現れます。その他者の顔は、私に対して倫理的な呼びかけ、訴えかけとして働きかけます。記述はレヴィナスの思想を的確に説明しています。
④【誤】
活動の主体として公共空間に現れて発言することを論じたのは、アーレントです。レヴィナスの思想ではありません。
問7:正解①
<問題要旨>
この問題は、シェリングの『人間的自由の本質』からの資料を読み、人間が善と悪に対してどのような存在であるかを理解し、会話の空欄を埋めるものです。資料の読解を通して、自由と選択の関係性を捉えることが求められます。
<選択肢>
①【正】
資料には「人間は、善と悪とに向かう自己運動の源泉を等しく自分の内に持つ」「人間は分岐点に立っている。人間が何を選ぼうとも、それは人間がなしたことになる。しかし、人間は未決定のままでいることはできない」とあります 。 これは、人間が善悪両方への可能性を持ち、そのどちらかを選択せざるを得ない存在として自由であることを示しています。選択肢の記述は資料の内容を正確に要約しています。
②【誤】
資料は、善と悪への可能性を「等しく自分の内に持つ」と述べており 、「等しくは持っておらず、悪へ向かう傾向をより強く持つ」という記述は資料と一致しません。
③【誤】
資料は、人間が「何を選ぼうとも、それは人間がなしたことになる」と述べており 、自ら選び決断する力があることを前提としています。 「決断する力はない」という記述は誤りです。
④【誤】
資料は善悪への可能性を「等しく」持つと述べており 、「悪へ向かう傾向をより強く持つ」という記述は資料と一致しません。
問8:正解①
<問題要旨>
この問題は、「自由」をテーマにした議論全体の流れを踏まえ、D、E、Fが作成したレポートの空欄を埋めるものです。準備段階での自由の捉え方と、ディスカッションを経て深まった自由の捉え方の両方を文脈から読み取る必要があります。
<選択肢>
a:レポート前半は、準備段階での考察をまとめたものです。会話では、自由を単なる「制約からの解放」 だけでなく、「自己決定」 や、他者との共存のための「規範や法」による調整を含むものとして多角的に捉えていました 。 したがって、aには「制約がない状態だけでなく、他者の自己決定との調整をも含むものだ」という記述が入るのが適切です。
b:レポート後半は、ディスカッションでの学びをまとめたものです。ディスカッションでは、自由に伴う不安や迷い、弱さが話題となり、Eが「自分の弱さを素直に認める」「迷いながらも下した選択は…貴重に思える」と述べ 、Fも「自由を手放さず、迷いながら自分で決定していきたい」と応じています 。 これは、弱さや迷いを否定するのではなく、それと向き合いながらも自由を手放さずに自己決定していくことの重要性を示しています。したがって、bには「自らの迷いや弱さと向き合いながら、それらを完全に払拭できなくても、自由を放棄しないこと」という記述が最も合致します。
以上の組み合わせから、①が正解となります。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
この問題は、現代の家族のあり方の多様化と、生活環境に関する用語の知識を問うものです。社会学的なキーワードの正確な理解が求められます。
<選択肢>
a:血縁のない親子や兄弟姉妹を含む家族とは、夫婦の一方または両方が、以前のパートナーとの間にもうけた子を連れて再婚することによって形成される家族のことです。このような家族を「ステップファミリー」と呼びます。
b:生活環境の快適さ、居住性の豊かさを意味する言葉は「アメニティ」です。
「ディンクス(DINKs)」は、子どもを持たない共働きの夫婦を指す言葉です。「ユニバーサルデザイン」は、年齢や障害の有無にかかわらず、全ての人が利用しやすいように製品や環境を設計するという考え方です。
したがって、aにステップファミリー、bにアメニティが入る③が正解となります。
問2:正解②
<問題要旨>
この問題は、青年期における自我の目覚めや自立について論じた人物(シュプランガー、ホリングワースなど)を特定するものです。青年心理学に関する基本的な知識が問われます。
<選択肢>
ア:「青年ほど、深い孤独のうちに、触れ合いと理解を渇望している人間はいない」と述べ、青年期の自我の目覚めを論じたのは、ドイツの哲学者・心理学者であるシュプランガーです。
イ:青年が親への精神的な依存から脱却し、自立していく過程を「心理的離乳」と呼んだのは、アメリカの心理学者であるホリングワースです。
以上の組み合わせから、アがシュプランガー、イがホリングワースとなるため、②が正解となります。
問3:正解②
<問題要旨>
この問題は、「マシュマロ実験」に関する資料を読み、その研究内容と後の追試・批判を正しく理解した上で、資料の趣旨に合致する発言を選ぶものです。科学的な研究報告を客観的に読解する能力が試されます。
<選択肢>
①【誤】
資料の後半では、追試の結果、「家庭の経済状況の方が、将来の成功との関係が深いとされた」と述べられており 、「家庭環境を問わず」という部分が資料の趣旨と合いません。
②【正】
資料には、当初の実験が「親が高学歴である家庭の子どもに限られて」おり 、その後「様々な家庭環境の子どもを参加者として再度実験を行ったところ」、異なる結果が出たと記されています 。 参加者の属性が限定されていたことが、結果に影響を与えた可能性を示唆しており、選択肢の記述は資料の趣旨に合致しています。
③【誤】
この実験は相関関係を示唆するものであり、成功した大人が全員このテストで我慢できたという因果関係を証明するものではありません。過度な一般化であり、資料の趣旨から逸脱しています。
④【誤】
資料の最後には、「将来の成功に対して本人の資質と家庭環境のどちらがより大きく影響するかについては、研究者間での議論が続いている」とあり 、結論が確定したわけではありません。 「全く関係ない」「家庭環境が大事だってことなんだね」と断定しているこの選択肢は、資料の慎重な記述と矛盾します。
問4:正解③
<問題要旨>
この問題は、貧富の差に関連する思想や問題についての説明の正誤を判断するものです。アマルティア・センのケイパビリティ・アプローチと、開発途上国の食糧問題に関する知識が問われます。
<選択肢>
ア【誤】
アマルティア・センが提唱したのは、人々がどのような機能を達成できるかの潜在的な可能性(集合)である「ケイパビリティ(潜在能力)」を拡大させることが豊かさにつながるという考え方です。これを国家の機能の集合とする記述は不正確です。彼が重視したのは個人の自由や選択の可能性です。
イ【正】
開発途上国の中には、自国民の食糧を生産するよりも、先進国に輸出するためのコーヒーやカカオ、バナナといった商品作物(キャッシュクロップ)の生産を優先するモノカルチャー経済に陥っている国があります。これが、国内の食糧不足や飢餓の一因となっています。記述は正しいです。
問5:正解①
<問題要旨>
この問題は、文化や宗教に関する用語や思想(ホモ・レリギオースス、文化相対主義、カルチャー・ショック)についての説明として、適当なものを全て選ぶものです。
<選択肢>
ア【正】
「ホモ・レリギオースス」とは、ルーマニアの宗教学者エリアーデが提唱した概念で、「宗教的人間」を意味します。人間は本性的に宗教的な存在であり、聖なるものを求める営みを通じて世界を意味づける、という人間観を示しています。記述は正しいです。
イ【誤】
文化相対主義は、全ての文化に固有の価値があり、文化間に優劣はないとする考え方です。「自国と他国の文化の優劣を明確にすること」は、自文化中心主義(エスノセントリズム)につながる考え方であり、文化相対主義とは正反対です。
ウ【誤】
西洋とイスラームの対立が不可避であると説いたのは、ハンティントンの「文明の衝突」論です。「カルチャー・ショック」は、異文化に接した際に感じる戸惑いや精神的な衝撃を指す言葉であり、思想の名前ではありません。
問6:正解①
<問題要旨>
この問題は、ジョン・ロールズの正義論、特に才能の分配に関する彼の考え方を、提示された『正義論』の資料に基づいて的確に説明している選択肢を選ぶものです。ロールズの「格差原理」や「無知のヴェール」の思想を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
ロールズは、社会における不平等が許容される条件として、①公正な機会均等の原理と、②最も不遇な人々の利益を最大にするという「格差原理」を挙げました。資料では、才能によって得られる所得は、その人の道徳的な価値を示すものではなく、「共通利益を最大限高めるように能力を向かわせるためのものでもある」と述べています 。 これは、才能ある者の利益が、結果的に最も恵まれない人々を含む社会全体の利益につながる場合にのみ、その格差が正当化されるという格差原理の考え方と一致します。記述はロールズの思想と資料の内容を正しく説明しています。
②【誤】
二項対立的な図式を問い直す(脱構築)のは、デリダなどのポスト構造主義の思想家です。ロールズの思想ではありません。
③【誤】
ロールズは、功利主義が「社会全体の効用」のために個人の権利を犠牲にする可能性があるとして批判し、それに代わる正義の原理を提唱しました。「功利主義の発想に基づいて」という記述は誤りです。
④【誤】
ロールズは、才能やそれによって得られる利益の分配が、道徳的に任意(偶然)のものであると考えました。そのため、「個々人の才能に応じて社会の利益を分配することこそが正義に適う」という考え方(能力主義)を批判しています。
問7:正解③
<問題要旨>
この問題は、「努力が報われるか」に関する二つの意識調査の図を読み解き、GとHの会話の空欄を埋めるものです。グラフから客観的な事実を正確に読み取り、それを言葉で表現する能力が求められます。
<選択肢>
a:図1を見ると、1988年と2013年を比べて、全ての年代・性別において、「いくら努力しても、全く報われないことが多いと思う」と回答した人の割合が増加していることがわかります。 したがって、「男女を問わず、1988年よりも2013年の方が、努力は報われないと考える人の割合が増えているね」という③の記述は、グラフの傾向を正しく読み取っています。
b:図2を見ると、「生活水準10年の変化」が「悪くなった」「やや悪くなった」と回答した人ほど、「いくら努力しても、全く報われないことが多いと思う」という回答(網掛け部分)の割合が高くなっています(悪くなった:54% 、やや悪くなった:32% )。 逆に、「よくなった」「ややよくなった」と回答した人ほど、その割合は低くなっています。したがって、「生活水準が悪化したと感じている人ほど、努力は報われないと考えている傾向が見られるよ」という③の記述は、グラフの傾向を正しく読み取っています。
以上の組み合わせから、③が正解となります。
問8:正解②
<問題要旨>
この問題は、社会の仕組みや構造を論じた現代の思想家(ボードリヤール、マッキンタイア、フーコー、レヴィ=ストロース)の思想を特定するものです。それぞれの思想家のキーワードと主張を正確に結びつける知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
この記述は、ドゥルーズ=ガタリの『アンチ・オイディプス』における欲望機械や社会体の議論を想起させますが、マッキンタイアの思想ではありません。マッキンタイアは、共同体の伝統における「徳」の再生を論じた思想家です。
②【正】
ボードリヤールは、現代の消費社会では、人々はモノをその使用価値のために消費するのではなく、他者との差異を示すための「記号」として消費していると分析しました。この「記号の消費」が現代社会の構造を特徴づけていると説いており、記述は彼の思想を正しく説明しています。
③【誤】
狂気と理性の分離の歴史を分析し、規律訓練による不可視な権力(規律権力)の構造を明らかにしたのは、フーコーです。デューイはプラグマティズムの思想家です。
④【誤】
言語学の知見を応用し、神話や親族関係の分析を通じて、人間の思考の根底にある無意識的な構造(構造主義)を明らかにしたのは、レヴィ=ストロースです。ソシュールはその源流となった言語学者ですが、南米の神話分析を行ったわけではありません。
問9:正解④
<問題要旨>
この問題は、GとHの「運と格差」をめぐる議論の最終的な対話の空欄を埋めるものです。70ページの最初の会話での二人の立場と、最後の会話で明らかになる共通の願いとすれ違いの理由を結びつけて考える必要があります。
<選択肢>
a / b:最初の会話でGは「運の違いが生む格差は、社会が埋め合わせるべきだ」と主張し 、Hは「与えられた環境の中で頑張ることが大事」「最終的には、努力は個人の問題」と、個人の努力を重視する立場でした 。 したがって、Gの立場は a「社会のあり方で変わるものと捉え、社会ができる限り埋め合わせる」、Hの立場は b「社会も無視できないけれど、努力が報われることの方を重視する」と要約するのが最も適切です。
c:Gは「社会は公平であるべきだ」「お互いを尊重する社会」を望んでいます 。 彼が格差を社会で埋め合わせるべきだと考えたのは、そうしないと「自分自身が選んだわけではない家庭環境などで評価が決められてしまう社会になりかね」ず、それでは人々が互いを尊重できなくなると考えたからです 。したがって、cには「埋め合わせなかったら…」という理由が入ります。
d:Hもまた、人々が互いを尊重する社会を望んでいます。彼が個人の努力を重視したのは、もし社会が格差を埋め合わせる中で「努力まで運のおかげだということになると、努力する人は、自身が適切に評価されていないと感じてしまって」人々が互いを尊重できなくなると考えたからです 。したがって、dには「埋め合わせる中で…」という理由が入ります。
以上の組み合わせから、④が正解となります。二人は「互いを尊重する社会」という共通の目標を持ちながら、その実現方法(格差を埋め合わせるべきか否か)について、異なる懸念を抱いていたことがわかります。