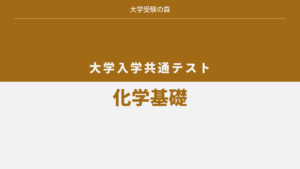解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
純物質と混合物の違いを理解し、正しく分類できるかを問う問題です。純物質は1種類の物質からなるもの(単体、化合物)、混合物は2種類以上の物質が混じり合ったものです。
<選択肢>
①【誤】
酸素(O2)もオゾン(O3)も、酸素原子Oのみからなる単体です。したがって、どちらも純物質に分類されます。
②【誤】
二酸化炭素(CO2)は化合物であり、純物質です。ドライアイスは二酸化炭素の固体であり、状態が違うだけで同じ純物質です。
③【誤】
炭酸水は二酸化炭素と水、過酸化水素水は過酸化水素と水の混合物です。したがって、どちらも混合物に分類されます。
④【正】
水(H2O)は化合物であり、純物質です。食塩水は塩化ナトリウムと水の混合物です。純物質と混合物の正しい組合せです。
⑤【誤】
炭酸ナトリウム(Na2CO3)と炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)は、どちらも化合物であり、純物質です。
問2:正解②
<問題要旨>
原子やイオンの電子配置に関する問題です。貴ガスであるネオン(Ne)原子の電子配置を基準に、それとは異なるものを選びます。
<選択肢>
①【誤】
ネオン(Ne)は原子番号10で、電子配置はK殻に2個、L殻に8個(K(2)L(8))です。ナトリウムイオン(Na+)は、原子番号11のナトリウム原子(Na)が電子を1個失ったイオンです。したがって、電子の数は10個となり、電子配置はNeと同じK(2)L(8)です。
②【正】
カルシウムイオン(Ca2+)は、原子番号20のカルシウム原子(Ca)が電子を2個失ったイオンです。したがって、電子の数は18個となります。その電子配置はK(2)L(8)M(8)となり、これは原子番号18のアルゴン(Ar)と同じです。よって、Neの電子配置とは異なります。
③【誤】
アルミニウムイオン(Al3+)は、原子番号13のアルミニウム原子(Al)が電子を3個失ったイオンです。したがって、電子の数は10個となり、電子配置はNeと同じK(2)L(8)です。
④【誤】
酸化物イオン(O2−)は、原子番号8の酸素原子(O)が電子を2個受け取ったイオンです。したがって、電子の数は10個となり、電子配置はNeと同じK(2)L(8)です。
⑤【誤】
フッ化物イオン(F−)は、原子番号9のフッ素原子(F)が電子を1個受け取ったイオンです。したがって、電子の数は10個となり、電子配置はNeと同じK(2)L(8)です。
問3:正解②
<問題要旨>
水分子の構造や性質についての記述の正誤を判断する問題です。共有結合、非共有電子対、分子の形、電気陰性度、配位結合などの知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
水分子(H2O)の中心にある酸素原子は、最外殻に6個の価電子を持ちます。そのうち2個を2つの水素原子との共有結合に使用し、残りの4個(2組)が非共有電子対として存在します。
②【誤】
水分子では、酸素原子の周りに2つの共有電子対(O-H結合)と2組の非共有電子対が存在します。これらの電子対は互いに反発するため、分子は直線形にはならず、折れ線形の構造をとります。
③【正】
オキソニウムイオン(H3O+)は、水分子の酸素原子が持つ非共有電子対の一方を、電子を持たない水素イオン(H+)に提供して配位結合を形成することによって生じます。
④【正】
酸素原子は水素原子よりも電気陰性度が大きいため、共有電子対を自分の方に引きつけます。その結果、酸素原子はわずかに負の電荷(δ-)を、水素原子はわずかに正の電荷(δ+)を帯び、分子全体として極性を持ちます。
問4:正解①
<問題要旨>
メタン(CH4)の物理的・化学的性質に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
気体の密度は、同温・同圧では分子量に比例します。メタン(CH4)の分子量は16(12 + 1.0×4)です。一方、空気の平均分子量は、窒素(分子量28)と酸素(分子量32)が約4:1の割合で含まれるため、約29となります。メタンの分子量は空気の平均分子量より小さいため、常温・常圧で空気より密度は小さい(軽い)です。
②【正】
メタンは天然ガスの主成分であり、都市ガスなどとして広く利用されています。
③【正】
純粋なメタンは、無色・無臭の気体です。家庭用の都市ガスに匂いがついているのは、ガス漏れに気づきやすくするために人工的に匂いを添加しているためです。
④【正】
メタンが完全燃焼すると、二酸化炭素(CO2)と水(H2O)が生成します(CH4+2O2→CO2+2H2O)。生成した二酸化炭素は、石灰水(水酸化カルシウム水溶液)に通すと、炭酸カルシウムの白色沈殿を生じさせ、白く濁らせます。
問5:正解④
<問題要旨>
物質の三態(固体、液体、気体)と状態変化に関する基本的な理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
温度は、物質を構成する分子や原子の熱運動の激しさを表す指標です。したがって、高温になるほど分子の熱運動は激しくなります。
②【正】
純物質が融解(固体から液体への状態変化)している間は、加えられた熱エネルギーは状態変化のために使われます。そのため、固体がすべて液体になるまで温度は一定(融点)に保たれます。
③【正】
分子には、熱運動によって互いに遠ざかろうとする傾向と、分子間力によって互いに引き合って集まろうとする傾向があります。熱運動の傾向が分子間力よりずっと強いと気体になり、分子間力の影響が強くなると液体や固体になります。
④【誤】
蒸発は、液体の表面から分子が気体となって飛び出していく現象であり、沸点以下のあらゆる温度で起こっています。沸点に達すると、液体の表面からだけでなく内部からも気化(沸騰)が激しく起こるようになります。「沸点に到達したときに初めて蒸発が始まる」という記述は誤りです。
問6:正解⑤
<問題要旨>
標準状態(0℃, 1.013×105Pa)における気体の質量、体積、組成から、分子の数(物質量)を比較する問題です。アボガドロの法則により、同温・同圧では、気体の分子の数は体積に比例し、また物質量に比例します。
<選択肢>
分子の数が多い順に比較するため、各気体の物質量[mol]を計算します。標準状態では、気体1 molの体積は22.4 Lです。原子量はH=1.0, C=12, N=14, O=16, He=4.0, Ne=20を用います。
ア:一酸化炭素CO(分子量 12+16=28)8.4 gの物質量は、 8.4 g/28 g/mol=0.30 mol
イ:アンモニアNH3 5.6 Lの物質量は、 5.6 L/22.4 L/mol=0.25 mol
ウ:ヘリウムHeとネオンNeの体積比1:1の混合気体4.8 g。体積比が1:1なので、物質量比も1:1です。Heをn[mol]、Neをn[mol]とすると、質量の合計は、 (4.0×n)+(20×n)=4.8 g 24n=4.8 n=0.20 mol 混合気体の全物質量は、n+n=2n=0.40 mol です。
各気体の物質量を比較すると、ウ(0.40 mol) > ア(0.30 mol) > イ(0.25 mol)となります。したがって、分子の数もこの順に多くなります。
①【誤】 ②【誤】 ③【誤】 ④【誤】 ⑤【正】 ⑥【誤】
問7:正解①
<問題要旨>
実験室で気体を発生させ、捕集するための適切な装置を選ぶ問題です。反応物の状態(固体・液体)、発生する気体の性質(空気との密度の比較、水への溶解性)を考慮して判断します。
<問題の分析>
・発生反応:大理石(主成分:炭酸カルシウム CaCO3、固体)に希塩酸(HCl、液体)を加えて二酸化炭素(CO2)を発生させます。これは常温で起こる反応です。
・発生装置:固体と液体の反応なので、三角フラスコや試験管に液体を滴下する装置が適しています。このとき、加えた液体を伝って気体が逆流して漏れ出ないように、長頸漏斗の先端は液面より下にある必要があります。
・捕集する気体:二酸化炭素(CO2、分子量44)は、空気の平均分子量(約29)より大きいため、空気より重い気体です。また、水に少し溶けます。
・捕集方法:空気より重い気体なので、集気びんの口を上に向け、びんの底から気体をためていく下方置換法が適しています。
<選択肢>
①【正】
発生装置は長頸漏斗の先端が液面下にあり、適切です。捕集方法は下方置換法であり、空気より重い二酸化炭素の捕集に適しています。
②【誤】
捕集方法が上方置換法になっています。これは空気より軽い気体(アンモニアなど)の捕集に用いる方法であり、二酸化炭素の捕集には不適切です。
③【誤】
発生装置の長頸漏斗の先端が液面より上にあります。これでは発生した二酸化炭素が長頸漏斗から逃げてしまい、捕集できません。
④【誤】
発生装置が③と同様に不適切です。また、捕集方法も②と同様に不適切です。
問8:正解②
<問題要旨>
同濃度・同体積の酸と塩基を混合した後の水溶液の性質(水素イオン濃度 [H+])を比較する問題です。酸と塩基の強弱と、中和によって生成する塩の性質(加水分解)を理解しているかが問われます。H+が最も高くなるのは、最も酸性が強くなる組合せです。
<選択肢>
いずれの組合せも、酸と塩基の価数は1価で、モル濃度と体積が等しいため、過不足なく中和反応が起こります。したがって、反応後の液性は生成した塩の性質によって決まります。
①【誤】
塩酸(強酸)と水酸化ナトリウム(強塩基)の反応です。強酸と強塩基からなる塩(NaCl)は加水分解せず、水溶液は中性になります。
②【正】
塩酸(強酸)とアンモニア(弱塩基)の反応です。強酸と弱塩基からなる塩(NH4Cl)が生成します。この塩の陽イオンであるアンモニウムイオン(NH4+)が水と反応(加水分解)して水素イオン(H+)を生じるため、水溶液は酸性になります。(NH4+⇌NH3+H+)
③【誤】
酢酸(弱酸)と水酸化ナトリウム(強塩基)の反応です。弱酸と強塩基からなる塩(CH3COONa)が生成します。この塩の陰イオンである酢酸イオン(CH3COO−)が加水分解して水酸化物イオン(OH−)を生じるため、水溶液は塩基性になります。(CH3COO−+H2O⇌CH3COOH+OH−)
④【誤】
酢酸(弱酸)とアンモニア(弱塩基)の反応です。弱酸と弱塩基からなる塩(CH3COONH4)が生成します。この場合、液性は酸と塩基の強さの程度によりますが、酢酸とアンモニアの酸解離定数と塩基解離定数は近いため、水溶液はほぼ中性になります。
以上の比較から、反応後の水溶液が最も強い酸性を示し、$[H^+]$が最も高くなるのは②の組合せです。
問9:正解③
<問題要旨>
二つの実験結果から、3種類の金属ア、イ、ウのイオン化傾向の大小関係を決定する問題です。
<イオン化傾向の基本>
・電池において、負極になる金属の方がイオン化傾向が大きい。
・金属の単体を他の金属イオンの水溶液に浸したとき、単体が溶けて水溶液中の金属イオンが析出すれば、単体の金属の方がイオン化傾向が大きい。
<選択肢>
実験Ⅰ:アの板とイの板を導線でつなぎ食塩水に浸すと、電流がアからイに流れました。電池において、電流は正極から負極に流れます(電子の流れは逆)。したがって、アが正極、イが負極となります。負極になる金属の方がイオン化傾向が大きいため、「イオン化傾向:イ > ア」となります。
実験Ⅱ:ウの硫酸塩の水溶液にアの板を浸したところ、ウが析出しました。これは、アが溶けてイオンになり、水溶液中のウのイオンが電子を受け取って単体として析出したことを意味します。イオン化傾向が大きい金属ほど陽イオンになりやすいので、「イオン化傾向:ア > ウ」となります。
ⅠとⅡの結果をまとめると、イオン化傾向の大きい順に「イ > ア > ウ」となります。
①【誤】 ②【誤】 ③【正】 ④【誤】 ⑤【誤】 ⑥【誤】
問10:正解⑤
<問題要旨>
亜鉛と酸の反応における量的関係をグラフから読み取り、酸の種類を変えた場合の反応の様子を予測する問題です。化学反応の量的関係(モル計算)が重要になります。
<問題の分析>
・反応式:
亜鉛と希硫酸の反応:Zn+H2SO4→ZnSO4+H2
亜鉛と塩酸の反応:Zn+2HCl→ZnCl2+H2
・図1のグラフの読取り:
同じ質量の亜鉛に希硫酸を加えていくと、発生する水素の体積は最大で100 mLになります。これは、用意した亜鉛が全て反応すると100 mLの水素が発生することを意味します。また、希硫酸を6 mL加えた時点で、水素の発生が最大量に達して一定になっています。つまり、亜鉛を全て反応させるのに、この濃度の希硫酸が6 mL必要だったことがわかります。
・塩酸に変えた場合:
① 発生する水素の最大量:用いる亜鉛の質量は同じなので、発生する水素の最大量も同じ100 mLです。
② 反応に必要な酸の体積:反応式を見ると、1 molの亜鉛と反応して水素を発生させるのに、硫酸(H2SO4)は1 mol必要なのに対し、塩酸(HCl)は2 mol必要です。つまり、同じ物質量の亜鉛を完全に反応させるには、塩酸は硫酸の2倍の物質量が必要です。問題文より、希硫酸と塩酸のモル濃度は同じなので、塩酸は硫酸の2倍の体積が必要となります。 希硫酸が6 mLで反応が完了したので、塩酸の場合は 6 mL×2=12 mL が必要になります。
・結論:
塩酸を用いた場合、加えた塩酸の体積が12 mLに達するまでは体積に比例して水素が発生し、12 mLで発生量が100 mLに達した後は、それ以上塩酸を加えても水素の発生量は変わらず100 mLで一定となります。この関係を示すグラフは⑤です。
<選択肢>
①〜⑥のグラフのうち、横軸が12 mLのところで縦軸が100 mLに達し、その後一定になっているグラフは⑤です。
第2問
問1a:正解③
<問題要旨>
示された操作が、どの分離操作に分類されるかを答える問題です。
<選択肢>
①【誤】
蒸留は、沸点の差を利用して液体の混合物を分離する操作です。
②【誤】
昇華法は、固体が液体を経ずに直接気体になる性質(昇華性)を利用して物質を分離・精製する操作です。
③【正】
ホウレンソウをゆでることで、目的の成分であるシュウ酸を溶媒である水に溶かし出して分離しています。このように、特定の溶媒に物質を溶かして分離する操作を抽出といいます。
④【誤】
再結晶は、温度による溶解度の差を利用して、固体物質の純度を高める操作です。
問1b:正解④
<問題要旨>
熱分解反応における質量変化から、生成した気体の物質量を計算する問題です。化学反応式と質量保存の法則、または物質量の計算を用います。
<問題の分析>
シュウ酸カルシウム(CaC2O4)が熱分解し、炭酸カルシウム(CaCO3)と一酸化炭素(CO)が生成する反応です。
反応式:CaC2O4→CaCO3+CO
図1より、反応前のCaC2O4の質量は5.12 g、反応後のCaCO3の質量は4.00 gです。
<解法1:質量保存の法則を用いる>
質量保存の法則より、発生したCOの質量は、反応前の質量と反応後の質量の差に等しくなります。 発生したCOの質量 = 5.12 g−4.00 g=1.12 g COの分子量は28(C:12, O:16)なので、発生したCOの物質量は、 物質量 = 質量 / 分子量 = 1.12 g/28 g/mol=0.0400 mol これは、4.00×10−2 mol となります。
<解法2:出発物質から計算する>
最初のシュウ酸カルシウム一水和物(CaC2O4⋅H2O、式量146)は5.84 gです。 この物質量は、5.84 g/146 g/mol=0.0400 mol です。 これが全て反応して、CaC2O4 になり、さらに分解してCOを放出します。 CaC2O4⋅H2O→CaC2O4→CaCO3+CO 反応式の係数比から、CaC2O4⋅H2O 1 mol から CO は 1 mol 生成します。 したがって、生成するCOの物質量は、出発物質の物質量と同じ0.0400 molです。
<選択肢>
①【誤】 ②【誤】 ③【誤】 ④【正】 ⑤【誤】 ⑥【誤】
問2a:正解①
<問題要旨>
正確な濃度の溶液(標準溶液)を調製する際に、溶液の体積を正確に定めるために用いる実験器具を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
メスフラスコは、標線まで液体を入れることで、極めて正確な体積の溶液を調製するために用いられるガラス器具です。問題文のように「正確に100mLになるまで水を加えて」調製するのに適しています。
②【誤】
メスシリンダーは、おおよその体積を量り取るための器具であり、メスフラスコほどの正確さはありません。
③【誤】
ビュレットは、滴定の際に、滴下した液体の体積を正確に読み取るための器具です。
④【誤】
コニカルビーカーは、滴定の際の反応容器として用いられる器具で、目盛りは目安であり、体積を正確に量るのには適していません。
問2b:正解③
<問題要旨>
溶解した溶質の質量と溶液の体積から、モル濃度を計算する問題です。
<問題の分析>
・溶質:シュウ酸二水和物 (COOH)2⋅2H2O (式量 126)
・溶質の質量:0.630 g ・溶液の体積:100 mL = 0.100 L
<計算>
- 溶質の物質量を求めます。 物質量[mol] = 質量[g] / 式量[g/mol] =0.630 g/126 g/mol=0.00500 mol
- モル濃度を求めます。 モル濃度[mol/L] = 溶質の物質量[mol] / 溶液の体積[L] =0.00500 mol/0.100 L=0.0500 mol/L
- 指数表記に直します。 0.0500 mol/L=5.00×10−2 mol/L
<選択肢>
①【誤】 ②【誤】 ③【正】 ④【誤】
問3:正解①
<問題要旨>
水酸化ナトリウムと塩酸が、質量や体積から直接正確な濃度の標準溶液を調製するのに適さない理由を問う問題です。
<選択肢>
・水酸化ナトリウム(NaOH):固体の水酸化ナトリウムには、空気中の水蒸気を吸収して自ら溶ける性質(潮解性)があります。そのため、秤量中に空気中の水分を吸って質量が増加してしまい、正確な質量をはかり取ることが困難です。また、空気中の二酸化炭素(CO2)を吸収して炭酸ナトリウム(Na2CO3)に変化する性質もあります(2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O)。
・塩酸(HCl):塩酸は、塩化水素という気体が水に溶けた水溶液です。特に濃塩酸は、溶質である塩化水素が蒸発(揮発)しやすく、保存している間に濃度が変化してしまうため、正確な濃度を保つことが困難です。
したがって、空欄には ア:水(水蒸気)、イ:二酸化炭素、ウ:蒸発(揮発) が入ります。 ①【正】 ②〜⑧【誤】
問4a:正解②⓪③
<問題要旨>
酸化還元滴定の実験結果から、未知試料である過マンガン酸カリウム(KMnO4)水溶液の濃度を計算する問題です。
<問題の分析>
・反応式:2MnO4−+5(COOH)2+6H+→2Mn2++10CO2+8H2O
・還元剤:シュウ酸((COOH)2)水溶液
・濃度 c′=5.0×10−3 mol/L ・体積 V′=10 mL
・酸化剤:過マンガン酸カリウム(KMnO4)水溶液
・濃度 c=? [mol/L]
・滴下量 V=10.00 mL
<計算>
化還元滴定の量的関係は、「酸化剤が受け取る電子の物質量 = 還元剤が放出する電子の物質量」で表されます。
・MnO4− は Mn2+ に変化 → Mnの酸化数が+7から+2に変化 → 1分子あたり5個の電子を受け取る。
・(COOH)2 は 2CO2 に変化 → Cの酸化数が+3から+4に変化 → 1分子あたり2個の電子(1×2)を放出する。
(酸化剤の価数)×(濃度)×(体積)=(還元剤の価数)×(濃度)×(体積) 5×c [mol/L]×100010.00 [L]=2×(5.0×10−3 mol/L)×100010 [L]
両辺の 100010 を消去して、 5×c×10.00=2×5.0×10−3×10 50c=10×10−2 50c=0.1 c=500.1=5001=0.0020 mol/L
これを問題の形式に当てはめると、 c=2.0×10−3 mol/L よって、116には2、117には0、118には3が入ります。
問4b:正解⑥
<問題要旨>
滴定実験において、理論値よりも滴下量が少なくなった原因を考察する問題です。滴下量が少なくなるのは、「(A) 滴定する溶液(ビュレット側)の濃度が意図せず濃くなった」または「(B) 滴定される溶液(コニカルビーカー側)の物質量が意図せず少なくなった」場合です。
<選択肢>
①【誤】
ビュレットをこれから入れるKMnO4水溶液で共洗いするのは、内部に残った水で溶液が薄まるのを防ぐための正しい操作です。滴定値に誤差は生じません。
②【誤】
ビュレットが水でぬれたままだと、KMnO4水溶液が薄まります。薄まった溶液で滴定すると、終点までに必要な体積は理論値より多くなります。
③【誤】
コニカルビーカーを$(COOH)_2水溶液で共洗いすると、はかり取った10mLに加えて、壁面に付着した分の(COOH)_2も反応してしまいます。つまり、反応する(COOH)_2$の物質量が多くなるため、滴下量は理論値より多くなります。
④【誤】
コニカルビーカーが水でぬれていても、ホールピペットで正確に10mLはかり取った$(COOH)_2$の物質量は変化しません。溶液全体の体積が増えて濃度は薄まりますが、物質量が変わらないため、滴定値には影響しません。
⑤【誤】
ホールピペットをこれから用いる$(COOH)_2$水溶液で共洗いするのは、内部の水で溶液が薄まるのを防ぐための正しい操作です。滴定値に誤差は生じません。
⑥【正】
ホールピペットが水でぬれたままだと、はかり取る$(COOH)_2水溶液が水で薄まってしまいます。その結果、10mLはかり取っても、そこに含まれる(COOH)_2$の物質量は本来より少なくなります。反応する相手が少ないため、滴下量は理論値より少なくなります。これは(B)のケースに該当します。