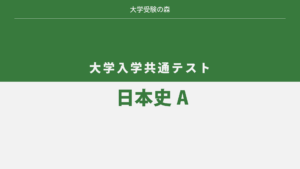解答
解説
第1問
問1:正解①
<問題要旨>
明治政府が導入した新しい制度や政策に対して、19世紀後半の民衆がどのような反応を示したかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
地租改正は、土地の所有者に地価の3%を現金で納めさせる税制改革でした。しかし、これは従来の米で納める年貢よりも農民の負担が重くなる場合が多く、全国各地で大規模な反対一揆(地租改正反対一揆)が起こりました。この記述は史実と一致します。
②【誤】
松方財政によるデフレ政策で農民が困窮し、各地で自由民権運動と結びついた激化事件(例:秩父事件)が起こりましたが、「全国的な農民組合」が結成されたのは1922年の日本農民組合であり、時期が異なります。
③【誤】
鉄道国有法は1906年に公布された法律で、民衆の暴動が起きたという史実はありません。日露戦争後の日比谷焼打事件などと混同しないよう注意が必要です。
④【誤】
「血税」とは、国民皆兵を目指した徴兵令に対する民衆の反発から生まれた言葉です。徴兵令に反対する一揆(血税一揆)が起こったのは1873年であり、西南戦争が起きた1877年とは時期が異なります。
問2:正解③
<問題要旨>
史料1(三遊亭円朝の落語『椿説蝦夷訛』の一部)を読み解き、1880年代までの北海道における開拓の様子に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
X【誤】
史料1には、飛蝗(バッタ)の被害対策について、「開拓使様で毎年雪の解けかかる時分大勢の人手を出して地の中にある虫の卵を取って焼き棄てました」と書かれています。対策を主導したのは「開拓使」という政府機関であり、「民間の有力な開拓民」ではありません。
Y【正】
史料1には、虫害がなくなった後、「屯田兵などは五穀の外に桑を仕立て養蚕も致し、麻や藍を作り(中略)大きな身代(財産)になったものが沢山おります」と書かれています。屯田兵は、北海道の開拓と防備を担った兵士で、多くは士族(旧武士)でした。したがって、北海道に移住した士族の中に財産を築いた者が多くいたという記述は、史料の内容と合致します。
問3:正解②
<問題要旨>
明治時代の文学における坪内逍遙の主張と、二葉亭四迷が確立した文体について問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アの坪内逍遙の主張は正しいですが、イの二葉亭四迷の文体は「話し言葉に近い文体(言文一致体)」です。「話し言葉とは異なる文体」という記述が誤りです。
②【正】
ア:坪内逍遙は『小説神髄』において、それまでの勧善懲悪的な物語を批判し、小説は人間の内面や世相をありのままに描くべきだとする写実主義を提唱しました。イ:二葉亭四迷は、坪内逍遙から三遊亭円朝の落語を参考にするよう助言を受け、話し言葉に近い「言文一致体」で小説『浮雲』を執筆しました。両方とも正しい組み合わせです。
③【誤】
アの坪内逍遙の主張が誤りです。「社会の理想の姿を描く」のではなく、ありのままの現実を描くことを主張しました。
④【誤】
アの坪内逍遙の主張が誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
日中戦争期の思想・文化統制に関する史料と歴史的事実について、正しい記述の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【誤】
史料2には、「事変ニュースが(中略)村人達を寄せつけた」「この中には初めて映画というものを見る人々も大分混っている」「序に娯楽映画も見る」とあります。これは、戦争ニュースをきっかけに初めて映画に触れた人が、娯楽映画も見るようになったという流れを示しており、「娯楽映画を見ていた人々がニュース映画に引き付けられるように」なったという記述とは順序が逆です。
b【正】
史料3には、「他の娯楽機関の取締強化により彼等(労務者)の自然的な要求が映画に走らしめた」とあります。これは、映画以外の娯
楽が規制されたため、労働者の需要が映画に集中し、映画館が盛況になったという分析であり、記述と一致します。
c【誤】
中国戦線での日本軍兵士の実態を描いて発禁処分となったのは、石川達三の『生きている兵隊』です。『麦と兵隊』は火野葦平の作品で、戦争文学のベストセラーとなりました。作品名が異なります。
d【正】
東京帝国大学教授であった矢内原忠雄は、その植民地政策研究が国家的見地から批判され、1937年に大学を辞職に追い込まれました(矢内原事件)。この記述は史実と一致します。
問5:正解③
<問題要旨>
古川ロッパの日記の断片 I~III を、書かれた時期の古いものから順に正しく配列する問題です。太平洋戦争中の出来事の発生時期を特定する必要があります。
<選択肢>
I:「サイパン全滅」とは、サイパン島の日本軍守備隊が玉砕したことを指します。これは1944年7月の出来事です。
II:「二千六百年奉祝日」とは、神武天皇即位から2600年を記念する式典のことで、1940年(昭和15年)に行われました。日記中の「近衛首相」は第2次近衛文麿内閣(1940年7月~)の首相であり、時期が一致します。
III:「わが軍沖縄の戦果」とあることから、沖縄戦についての日記とわかります。沖縄戦は1945年3月末から6月にかけての出来事です。
したがって、古い順に並べると II (1940年) → I (1944年) → III (1945年) となります。
問6:正解②
<問題要旨>
喜劇役者・古川ロッパの日記(1934年~1960年)を使って、「戦後の社会状況の変化が娯楽に与えた影響」を調べるというテーマに最も適した選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
工場法が制定されたのは1911年であり、「戦後」のテーマとは合致しません。
②【正】
テレビの本格的な放送が開始されたのは1953年で、戦後の新しい娯楽メディアとして急速に普及しました。これは映画や演劇といった既存の娯楽に大きな影響を与えたため、映画・演劇界で活躍したロッパの日記から、その影響を調べることはテーマとして非常に適しています。
③【誤】
映画の有声化(トーキー)が普及したのは1930年代前半です。ロッパの日記が始まる1934年にはすでに進行しており、「戦後の変化」というテーマには当てはまりません。
④【誤】
東海道新幹線が開通したのは1964年です。古川ロッパは1961年に亡くなっているため、日記から新幹線の影響を調べることはできません。
問7:正解①
<問題要旨>
戦中から戦後にわたる食糧事情に関する法律(食糧管理法)に関するメモの空欄を補充する問題です。
<選択肢>
ウ:1942年に制定された食糧管理法は、戦争遂行のための食糧確保、つまり深刻な「食糧不足」に対処することを目的としていました。政府が米や麦などの主要食糧を管理し、国民に配給する制度の根拠となりました。
エ:戦後、食糧生産が増加し、特に1960年代後半になると米が余るようになりました。政府による米の買い上げ(食管会計)が大きな財政負担となったため、1970年代から米の生産量を調整する「減反」政策が本格的に行われました。
したがって、ウには「食糧不足」、エには「減反」が入ります。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
明治初期の西洋文明の導入に関する文章の空欄を補充する問題です。アは開港場、イは洋服を率先して着用した階層を問うています。
<選択肢>
ア:1858年の日米修好通商条約により開港が約束され、翌1859年に実際に開港したのは横浜・長崎・箱館の3港でした。兵庫(神戸)が開港したのは1868年です。したがって、アには「箱館」が入ります。
イ:明治政府は、近代化政策の一環として、まず官吏(役人)や軍人に制服として洋服の着用を義務付けました。これが一般に洋服が広まるきっかけとなりました。したがって、イには「官吏や軍人」が入ります。
両方の組み合わせが正しいのは④です。
問2:正解②
<問題要旨>
幕末の1865年と1867年の輸入品に関する2つのグラフを比較し、そこから読み取れる内容に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
X【正】
1865年(グラフ1)では武器類と艦船の合計は13.31%、1867年(グラフ2)では合計21.11%と割合が増加しています。輸入総額も増えているため、輸入額は大幅に増加しています。これは、幕府や雄藩が軍備の近代化を競っていた幕末の国内情勢を反映しており、記述は正しいです。
Y【誤】
1866年に結ばれた改税約書により、日本の輸入関税は一律従価5%へと大幅に引き下げられました。関税率の引き下げは輸入を促進する要因であり、「関税率が引き上げられた」という記述は史実と逆です。
問3:正解④
<問題要旨>
明治初期の国立銀行に関する史料を読み、その内容と合致する記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
1872年に制定された当初の国立銀行条例では、アメリカの制度を参考に、発行する銀行券と正貨(金貨)との交換(兌換)を義務付けていました。しかし、この兌換義務が銀行設立の妨げとなったため、1876年の条例改正で不換紙幣の発行が認められました。
②【誤】
国立銀行条例では、条件を満たした各銀行がそれぞれ紙幣を発行する権限を持っていました。紙幣発行権が日本銀行に一元化されるのは1882年以降のことです。
③【誤】
史料には「政府の命令同様の慫慂(しょうよう)にて、三井組、小野組発起し」第一国立銀行が設立されたとあります。政府が設立を勧めており、「対抗するため」ではありません。
④【正】
史料には、秩禄処分で交付された「金禄公債証書をもって、国立銀行設立を申請する者夥(おびただ)しく」とあります。これは、現金収入の道を断たれた華族や士族が、公債を資本金として銀行を設立し、事業家へ転身しようとしたことを示しており、記述の内容と一致します。
問4:正解②
<問題要旨>
明治時代の文化における、西洋文明の受容と日本の伝統との関係について述べた文の中から、正しいものの組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】
アメリカから来日した美術史家フェノロサは、岡倉天心らとともに、当時軽視されがちだった日本の伝統美術の価値を高く評価し、その復興と保存に尽力しました。
b【誤】
政教社を結成したのは、三宅雪嶺、志賀重昂、陸羯南らです。彼らは国粋主義の立場から政府の極端な欧化政策を批判しました。洋学者の加藤弘之は社会進化論を唱えた人物で、政教社のメンバーではありません。
c【誤】
1890年に公布された民法(旧民法)は、フランス民法を主な手本としていました。これに対し、日本の伝統的な家族制度を損なうという批判(民法典論争)が起こり、施行が延期されました。その後、ドイツ民法を参考に新しい民法が作られました。
d【正】
明治政府は1872年に太陽暦を採用しましたが、農作業のサイクルなどと深く結びついていた旧暦(太陰太陽暦)は、特に農村部ではその後も長く慣習として使われ続けました。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
明治時代の教育制度に関する文章の空欄を補充する問題です。アはお雇い外国人の名前、イは官営八幡製鉄所の鉄鉱石の主な輸入元を問うています。
<選択肢>
ア:鹿鳴館を設計し、工部大学校で辰野金吾など多くの日本人建築家を育てたのは、イギリス人建築家のジョサイア・コンドルです。モッセは地方自治制度の整備などに貢献したドイツ人顧問です。
イ:1901年に操業を開始した官営八幡製鉄所は、原料となる鉄鉱石を中国(当時の清)のターイエ(大冶)鉄山から、石炭を近くの筑豊炭田から供給することを前提に建設されました。
したがって、アにコンドル、イに清が入る③が正解です。
問2:正解④
<問題要旨>
1900年から1940年にかけての学校数の推移を示した表を読み解き、教育制度の変遷に関する記述として最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
1900年から1910年にかけて小学校数が減少していますが、この時期は就学率が向上した時期(1907年に義務教育6年制が確立)であり、小規模校の統廃合が進んだことが原因と考えられます。「就学率の低下と関係している」という記述は誤りです。
②【誤】
中学校は義務教育ではありません。また、義務教育が6年に延長されたのは1907年であり、1920年代から30年代の出来事ではありません。
③【誤】
表を見ると、1900年から1940年まで一貫して、中学校の数が高等女学校の数を上回っています。「高等女学校の数が中学校の数を常に上回って」いるという記述は誤りです。
④【正】
1910年から1930年にかけて大学の数が8校から46校へと急増しています。これは1918年に公布された大学令により、帝国大学以外にも官立・公立・私立の大学設立が認められたためで、記述は表の変化の背景を正しく説明しています。
問3:正解③
<問題要旨>
明治時代以降の教育に関する出来事について、正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
教育勅語が発布されたのは1890年です。日露戦争(1904年~1905年)よりも前の出来事です。
②【誤】
明治時代、小学校教育に西洋音楽が取り入れられ、唱歌として教えられました。政府が西洋音楽を禁止した事実はありません。
③【正】
日中戦争が長期化する中、戦時体制を強化するため、1941年に小学校は国民学校と改称され、皇国精神を養うための軍国主義的な教育が行われました。この記述は正しいです。
④【誤】
敗戦後、GHQは戦前の軍国主義教育の中心とされた修身・日本歴史・地理の授業を一時停止するよう指令しました。「奨励した」という記述は全くの逆です。
問4:正解④
<問題要旨>
1872年に出された学制に関する太政官布告(史料1)を読み解き、その内容に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
X【誤】
史料1は、学問の目的を「人々自ら其身を立て、其産を治め、其業を昌にして、以て其生を遂る」こと、つまり個人の立身出世や生活の安定にあると説いています。そして、これまでの学問が「国家の為にす」と唱えながら実生活に役立たない「空理虚談」に陥っていると批判しています。したがって、「国家のために学ぶことにある」という記述は史料の趣旨とは逆です。
Y【誤】
学制は「邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん」ことを理想に掲げ、すべての国民(男女の区別なく)に小学校教育を受けさせることを目指しました。「男子のみに義務づけた」という記述は誤りです。
問5:正解①
<問題要旨>
1899年の文官任用令改正に関する新聞記事(史料2)を読み、その背景や関連事項に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
a【正】
史料2には「昨年憲政党内閣の際、むやみに在野の党員を任用せしに」とあり、日本初の政党内閣である第1次大隈重信内閣(隈板内閣)が、党員を官僚に登用しようとする猟官運動で混乱したことを問題視しています。この記述は史料の内容と一致します。
b【誤】
文官任用令改正は、政党の介入を排して官僚の身分を保障し、試験による任用を厳格化するものでした。これにより、官僚は政党から独立した存在となり、公平な任用が困難になったわけではありません。
c【正】
この文官任用令改正を行ったのは、藩閥勢力を基盤とする第2次山県有朋内閣です。この内閣は、政党の影響力を抑えるため、1899年に文官任用令改正を、翌1900年には軍部大臣現役武官制を定めました。
d【誤】
憲政党は、第1次大隈内閣の総辞職後に分裂し、旧自由党系の勢力は1900年に伊藤博文を総裁とする立憲政友会を結成しました。つまり、憲政党が立憲政友会の母体の一部となったのであり、両者が対立したわけではありません。
問6:正解⑥
<問題要旨>
明治時代以降の学問に関する出来事 I~III を、古いものから年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:滝川事件は、京都帝国大学教授の滝川幸辰の刑法学説が自由主義的とされ、1933年に休職処分にされた思想弾圧事件です。
II:北里柴三郎が香港でペスト菌を発見し、高峰譲吉が消化酵素タカジアスターゼを創製したのは、ともに1894年のことです。
III:福沢諭吉が個人の自立と実学の重要性を説いた『学問のすゝめ』を出版したのは、1872年から1876年にかけてです。
したがって、古い順に並べると III (1870年代) → II (1890年代) → I (1930年代) となります。
問7:正解②
<問題要旨>
近現代の日本の教育と社会について述べた文の中から、誤っているものを一つ選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
明治政府は、文明開化・殖産興業を推進するため、お雇い外国人から直接技術や知識を学んだり、欧米へ留学生を派遣したりして、西洋の文化や技術を積極的に導入しました。
②【誤】
明治時代の女子教育は、1899年の高等女学校令などで示されたように、「良妻賢母(よい妻、賢い母)」を育成することを主な目的としていました。「良妻賢母の理念を批判し」という部分が史実と異なります。
③【正】
大正デモクラシーの風潮の中、画一的な詰め込み教育への批判から、児童の個性や自主性を尊重する新しい教育(大正自由教育)が、沢柳政太郎らによって提唱・実践されました。
④【正】
敗戦後の教育改革で1947年に学校教育法が制定され、小学校6年・中学校3年・高等学校3年・大学4年を基本とする、六・三・三・四制の新しい学校制度が発足しました。
第4問
問1:正解⑤
<問題要旨>
ワシントン会議(1921~22年)で「調印された条約」と「廃棄された条約」を、史料1~3の中から正しく特定する問題です。
<選択肢>
史料1:「両締盟国」が共同で戦闘にあたるという内容は、軍事同盟を定めたものです。これは1902年に締結された日英同盟の内容に合致します。日英同盟はワシントン会議で調印された四か国条約によって発展的に解消(事実上の廃棄)されました。よって、これは「廃棄された条約」(Y)にあたります。
史料2:「国際連盟規約」と明記されている通り、これは第一次世界大戦後のパリ講和会議で設立が決まった国際連盟の規約であり、ワシントン会議とは直接関係ありません。
史料3:「主力艦建造計画を廃止」「新しい主力艦を建造したり取得したりできない」という内容は、海軍の軍備を制限するものです。これはワシントン会議で調印された海軍軍備制限条約の内容です。よって、これは「調印された条約」(X)にあたります。
したがって、Xが史料3、Yが史料1の組み合わせになります。
問2:正解④
<問題要旨>
不戦条約(1928年)に調印したときの内閣について述べた文として、正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
不戦条約に調印したのは、田中義一内閣です。
①【誤】
幣原喜重郎を外相に起用して協調外交を進め、ソ連と国交を樹立したのは加藤高明内閣(1924年~1926年)です。
②【誤】
虎の門事件(1923年)の責任をとって総辞職したのは第2次山本権兵衛内閣です。
③【誤】
シベリア出兵を決定したのは寺内正毅内閣(1918年)です。
④【正】
1925年に制定された普通選挙法(25歳以上のすべての男子に選挙権)に基づく、最初の衆議院議員総選挙が1928年に行われました。これを実施したのが田中義一内閣です。
問3:正解③
<問題要旨>
満州事変(1931年)後の中国問題に関する日本政府内の方針を示した史料4を読み解き、記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
X【誤】
史料4には「満蒙の治安維持及び満鉄以外の鉄道保護は、主として中国側の警察ないし警察的軍隊に当たらせる」とあります。「満鉄の警備」ではなく「満鉄以外の」鉄道保護を中国側に任せるとしており、記述は史料の内容と異なります。
Y【正】
史料4の末尾に、「つとめて国際法ないし国際条約抵触を避け」「九力国条約などの関係上、できる限り中国側の自主的発意に基づいたような形式にする」とあります。これは、満州に独立国を建国するにあたり、中国の主権尊重・領土保全を定めた九か国条約などに違反していると国際社会から非難されるのを避けるための方策を検討していたことを示しています。記述は史料の内容と合致します。
問4:正解①
<問題要旨>
満州事変後から太平洋戦争期にかけての日本の外交について述べた文の中から、正しいものの組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】
日本は、国際連盟を脱退(1933年)して国際的に孤立する中、同じくヴェルサイユ体制に不満を持つドイツ・イタリアに接近し、日独防共協定(1936年)、日独伊三国同盟(1940年)を結び、枢軸国としての関係を強めました。
b【誤】
1938年、第1次近衛文麿内閣は「国民政府を対手とせず」声明を発表し、蔣介石の国民政府との和平交渉を打ち切りました。これは日中関係を改善するどころか、戦争を泥沼化させるものでした。
c【正】
ドイツがソ連に侵攻する可能性が高まる中、日本は南方(東南アジア)への進出(南進政策)を本格化させるため、北方の脅威であるソ連との衝突を避ける必要がありました。そのために1941年、日ソ中立条約を締結しました。
d【誤】
日米関係が悪化する中、1939年に日米通商航海条約の廃棄を通告したのはアメリカ側です。日本側ではありません。
問5:正解③
<問題要旨>
第二次世界大戦後、連合国軍(主にアメリカ軍)の占領下にあった時期(1945年~1952年)の日本の社会や文化に関する説明として、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
GHQの指令により、戦前の軍国主義を指導・推進した軍人・政治家・官僚・財界人などが公職から追放されました(公職追放)。
②【正】
1946年のアメリカ教育使節団の報告書に基づき、教育基本法や学校教育法が制定され、教育の機会均等や男女共学など、戦後の民主主義教育の基本が定められました。
③【誤】
戦時中の厳しい統制から解放され、戦後の人々は自由で明るい文化を求めました。並木路子の「リンゴの唄」などの明るい歌謡曲が大ヒットし、人々を元気づけました。「日本政府によって規制された」という記述は全くの逆です。
④【正】
占領下では、プレス=コードなどによってGHQや占領政策への批判は厳しく禁じられましたが、それ以外のテーマについては言論の自由が大幅に認められ、政治や社会に対する活発な議論が行われました。
問6:正解④
<問題要旨>
敗戦後に日本がアメリカとの間で結んだ条約や協定 I~III を、古いものから年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:アメリカが「琉球諸島」の権利を放棄する協定とは、沖縄返還協定のことです。1971年に調印され、1972年に沖縄が日本に復帰しました。
II:アメリカからの経済援助と引き換えに、日本の自衛力増強義務を定めた協定は、MSA協定(日米相互防衛援助協定)です。1954年に締結されました。
III:「極東」での軍事行動に関する事前協議を定めた条約は、1960年に改定された新日米安全保障条約(60年安保)です。
したがって、古い順に並べると II (1954年) → III (1960年) → I (1971年) となります。
問7:正解②
<問題要旨>
サンフランシスコ平和条約以降の日本の外交に関するメモの空欄を補充する問題です。
<選択肢>
ア:1951年のサンフランシスコ講和会議には、ソ連などの社会主義国は参加したものの、条約の内容に反対して調印を拒否しました。インドは、会議そのものに参加しませんでした。したがって、アには「ソ連」が入ります。
イ:1972年、田中角栄首相が中国を訪問し、日中国交正常化をうたった日中共同声明に調印しました。これにより、日本と中華人民共和国との間の「不正常な状態」が終結しました。日中平和友好条約が結ばれるのは、その後の1978年です。したがって、イには「日中共同声明」が入ります。
両方の組み合わせが正しいのは②です。
第5問
問1:正解①
<問題要旨>
第一次世界大戦を挟む1910年代から20年代にかけての日本の工業化について、正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
第一次世界大戦中から戦後にかけて、日本の大手紡績会社は、国内より賃金の安い中国に工場(在華紡)を建設し、現地生産を拡大することで国際競争力を維持しようとしました。
②【誤】
この時期は、労働者の権利意識が高まり、友愛会などが主導する労働争議が活発化した時代です。「大規模な労働争議は見られなくなった」という記述は誤りです。
③【誤】
この時期、重化学工業も発展しましたが、財閥は軽工業から重化学工業、金融へと事業を多角化し、その支配力を一層強めました。「影響力が低下した」という記述は誤りです。
④【誤】
日本の造船業が飛躍的に発展したのは第一次世界大戦中です。大戦終了後は、世界的に船舶が過剰となり、日本の造船業は深刻な不況に陥りました。「終了後に需要が増えた」という記述は誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
関東大震災後に問題となった「震災手形」の救済策に関する史料を読み解き、語句と説明文の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
X:史料には、「震災手形と詐称」された手形について、「政商は震災以前の累積的損害により支払い困難となっていた手形」を偽ったとあります。つまり、これは「震災前から経営困難に陥っていた企業が発行した」手形です。よって、Xとaが結びつきます。
Y:史料には、「市中有力金融機関」について、「震災打撃の甚だしい企業の発行した手形は危険なものとして、震災手形としての割引を拒否した」とあります。これは、リスクの高い手形を避け、より安全な(=震災による損害が軽微な企業の)手形を優先的に買い取ったことを意味します。よって、Yとdが結びつきます。
したがって、X-a、Y-dの組み合わせが正しくなります。
問3:正解③
<問題要旨>
高度経済成長期に関するメモの空欄を補充する問題です。アは「所得倍増」を掲げた内閣、イは田中角栄内閣の時期に悪化した経済現象を問うています。
<選択肢>
ア:1960年に発足し、「所得倍増計画」をスローガンに掲げて高度経済成長を推進したのは、池田勇人内閣です。鳩山一郎内閣は1950年代の内閣です。
イ:1973年の第一次石油危機(オイルショック)をきっかけに、世界的に物価が急騰しました。田中角栄内閣の日本列島改造論に基づく公共事業の拡大もこれに拍車をかけ、「狂乱物価」と呼ばれるほどの激しいインフレーション(物価上昇)が発生しました。デフレーションは物価が下落する現象で、逆です。
したがって、アに池田勇人、イにインフレーションが入る③が正解です。
問4:正解④
<問題要旨>
敗戦直後から1960年代までの日本経済に関する出来事 I~III を、古いものから年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:東京オリンピックが開催され、それに伴い東海道新幹線や首都高速道路などのインフラ整備が進んだのは1964年です。
II:敗戦直後の生産力低下に対応するため、石炭・鉄鋼といった基幹産業に資材や資金を重点的に配分する傾斜生産方式が打ち出されたのは、1946年末からのことです。
III:朝鮮戦争(1950年~1953年)に伴い、日本が国連軍(主にアメリカ軍)への物資供給基地となったことで生まれた好景気は「朝鮮特需」と呼ばれます。
したがって、古い順に並べると II (1946年~) → III (1950年~) → I (1964年) となります。
問5:正解②
<問題要旨>
戦後の経済成長に関する表と史料2を読み解き、そこから導かれる記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
X【正】
表を見ると、1955年から72年の日本の年平均成長率(10.0%)は、第二次世界大戦の戦勝国であるアメリカ(2.6%)やイギリス(1.3%)の成長率を大幅に上回っています。この記述は表から正しく読み取れます。
Y【誤】
史料2は1956年の経済白書の一節で、「もはや戦後ではない」と述べ、復興による成長が終わったことを指摘しています。一方、1ドル=360円の固定相場制から円の価値を切り上げる(変動相場制へ移行する)のは、1971年のニクソン・ショック以降の出来事です。史料2の時点では円の切り上げは行われていません。
問6:正解①
<問題要旨>
日本の産業別就業者数の推移を示したグラフを読み解き、その背景に関する記述の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】
グラフを見ると、1920年、1930年、1940年のいずれの時点でも、第3次産業(点線の棒)の就業者数が第2次産業(斜線の棒)の就業者数を上回っています。この記述は正しいです。
b【誤】
昭和恐慌が始まったのは1930年頃です。グラフを見ると、1950年の第2次産業の就業者数は、1930年時点よりも大幅に増加しており、「落ち込んだ」という記述は誤りです。
c【正】
グラフを見ると、第1次産業(黒い棒)の就業者数は、1960年には第3次産業の就業者数を下回り、1970年には第2次産業の就業者数も下回っています。したがって、第1次産業の就業者数が他の2つの産業を初めて両方とも下回ったのは、1950年から70年の間です。この記述は正しいです。
d【誤】
高度経済成長期を通じて、日本の主要エネルギーは石炭から石油へと転換しました(エネルギー革命)。そのため、国内の炭田は相次いで閉山に追い込まれており、「国内炭田の再開発が進んだ」という記述は史実と全く逆です。
問7:正解②
<問題要旨>
近現代の日本経済について述べた文の中から、誤っているものを一つ選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
第一次世界大戦期には、工業化の進展とともに水力発電が普及し、工場の動力源は従来の蒸気力から電力へと転換していきました。
②【誤】
1927年の金融恐慌の際、台湾銀行から巨額の融資を受けていた鈴木商店は、融資の継続が困難になったことで経営が行き詰まり、破産に追い込まれました。「経営は回復した」という記述が誤りです。
③【正】
敗戦後の激しいインフレーションを収束させるため、GHQの指導で実施されたドッジ・ライン(緊縮財政政策)は、インフレ抑制には成功したものの、多くの企業が倒産する深刻な不況(安定恐慌)を引き起こしました。
④【正】
高度経済成長期、政府は農業基本法(1961年)を制定して農家の所得向上を目指しましたが、工業部門の発展に伴い、賃金の高い都市部の工場へ若者を中心とした労働力が流出する傾向は続きました。