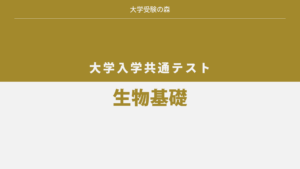解答
解説
第1問
問1:正解⑤
<問題要旨>
全ての生物の基本単位である細胞について、原核細胞と真核細胞に共通する特徴と相違点を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
ATP(アデノシン三リン酸)は、全ての生物においてエネルギーの貯蔵・供給を担う物質であり、「エネルギーの通貨」と呼ばれます。原核細胞も真核細胞も、生命活動に必要なエネルギーをATPを介して利用します。
②【正】
酵素は生体触媒として、細胞内で行われる様々な化学反応(代謝)を促進します。代謝は生命活動の根幹であり、原核細胞・真核細胞を問わず全ての細胞で行われています。
③【正】
異化とは、呼吸に代表されるように、有機物を分解してエネルギーを取り出す働きのことです。同化(光合成など)と合わせて代謝と呼ばれ、全ての生物が自身の生命活動を維持するために行っています。
④【正】
細胞膜は、細胞の内部と外部を隔てる膜構造であり、物質の出入りを調節する重要な役割を持ちます。細胞膜は、全ての細胞に共通して存在する構造です。
⑤【誤】
ミトコンドリアや葉緑体は、内部に独自のDNAや膜構造を持つ細胞小器官です。これらの細胞小器官は真核細胞にのみ存在し、原核細胞には存在しません。したがって、これは両者に共通する特徴ではありません。
問2:正解②
<問題要旨>
生物が持つ遺伝情報全体であるゲノムと、その一部である遺伝子に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
二本鎖DNAにおいて、塩基の相補性からアデニン(A)とチミン(T)の数、グアニン(G)とシトシン(C)の数がそれぞれ等しくなります(シャルガフの規則)。しかし、アデニンとグアニンの数が等しいとは限りません。
②【正】
ゲノムのDNAには、タンパク質の設計図となる遺伝子領域だけでなく、遺伝子ではない領域も広大に存在します。これらの領域は、RNAに転写もされず、タンパク質に翻訳もされない部分を多く含んでいます。
③【誤】
同一個体の体細胞は、すべて一つの受精卵が体細胞分裂を繰り返してできたものです。そのため、皮膚の細胞とすい臓の細胞が持つゲノムの情報は、原則として同一です。細胞の種類によって働きが違うのは、ゲノムの中のどの遺伝子が使われるか(発現するか)が異なるためです。
④【誤】
分裂は、親の遺伝情報をそのまま受け継ぐ無性生殖です。したがって、分裂によって生じた2個体の細胞は、突然変異が起きない限り、全く同じ種類の遺伝子を持っています。
⑤【誤】
卵や精子などの生殖細胞が作られる際の減数分裂では、相同染色体が対ごとに分かれるため、染色体の数が半分(2n→n)になります。これにより遺伝子の「セット」が半分になりますが、生物が生きていくために必要な遺伝子の「種類」が半分になるわけではありません。
問3:正解④
<問題要旨>
遺伝子の本体がDNAであることを証明したエイブリーらの実験に関する問題です。肺炎双球菌の形質転換を引き起こす物質が何かを、酵素処理の結果から考察する力が求められます。
<選択肢>
この問題は、S型菌の抽出液を様々な酵素で処理した後、R型菌に混ぜて培養し、「S型菌が見つかった(=形質転換が起こった)処理はどれか」を問うています。形質転換が起こるということは、形質転換を引き起こす原因物質(遺伝物質)が、その酵素処理で分解されなかったことを意味します。
ア:タンパク質を分解する酵素で処理した。
もし遺伝物質がタンパク質ならば、この処理で分解されて形質転換は起こりません。しかし、実際には形質転換が起こります。これは、遺伝物質がタンパク質ではないことを示しています。
イ:RNAを分解する酵素で処理した。
もし遺伝物質がRNAならば、この処理で分解されて形質転換は起こりません。しかし、実際には形質転換が起こります。これは、遺伝物質がRNAではないことを示しています。
ウ:DNAを分解する酵素で処理した。
もし遺伝物質がDNAならば、この処理で分解されて形質転換は起こりません。実際、この処理を行うと形質転換は起こらなくなります。
設問では「S型菌が見つかった処理」、つまり「形質転換が起こった処理」を問われているため、アとイが該当します。したがって、アとイを過不足なく含む④が正解です。
問4:正解①
<問題要旨>
細胞周期の各時期におけるDNA量の変化をグラフから読み取り、紫外線照射によって細胞周期がどの段階で停止したかを特定する問題です。
<問題要旨>
図1のグラフから、この培養細胞の細胞周期を読み取ります。細胞1個当たりのDNA量を相対値で1とすると、DNAを複製して2になり、細胞分裂を経て再び1に戻るというサイクルを繰り返しています。
・DNA量が1の時期:G1期(DNA合成準備期)
・DNA量が1から2へ増加する時期:S期(DNA合成期)
・DNA量が2の時期:G2期(分裂準備期)およびM期(分裂期)
・DNA量が2から1へ減少する部分:M期(分裂期)の終わり
図2を見ると、培養時間16時間の時点で紫外線を照射しています。このとき、細胞のDNA量は1なので、G1期であることがわかります。照射後、細胞はS期に移行せず、DNA量が1のまま36時間後まで維持されています。これは、紫外線によるDNAの損傷を修復するために、G
1期で細胞周期が一時的に停止していることを示しています。このような細胞周期のチェックポイント機能は、異常な細胞が増えるのを防ぐために重要です。
<選択肢>
①【正】
紫外線照射時、細胞はDNA量が1のG1期にあり、照射後もS期に進まずDNA量1のままで停止しているため、正解です。
②【誤】
G2期はDNA量が2の時期であり、グラフと一致しません。
③【誤】
S期はDNA量が増加している時期であり、グラフと一致しません。
④【誤】
M期はDNA量が2の時期であり、グラフと一致しません。
問5:正解④
<問題要旨>
実験結果のグラフと模式図を統合的に解釈し、化合物Zが細胞周期のどの過程を阻害するのかを考察する問題です。
<問題要旨>
図3のグラフを見ると、化合物Zを添加した後、細胞のDNA量は1から2へと正常に増加しています。これは、G1期からS期を経てG2期へと細胞周期が進行したことを示します。しかし、その後DNA量は2のままで一定となり、分裂後のDNA量1の細胞が現れていません。これは、細胞がM期(分裂期)を完了できず、細胞分裂が止まっていることを示唆しています。
次に図4の模式図を見ると、化合物Z添加後の26時間後や40時間後の時点では、核内に太く凝縮した染色体が見られます。これは細胞がM期に入っている状態を示しています。
以上のグラフと模式図の結果から、化合物Zは、細胞をM期で停止させ、染色体が娘細胞へ正常に分配される過程を阻害していると結論付けられます。
<選択肢>
①【誤】
S期に進行しているため、G1期の進行は阻害されていません。
②【誤】
M期に入っている様子が観察されるため、G2期の進行は阻害されていません。
③【誤】
DNA量が1から2へ増加しているため、DNAの複製は阻害されていません。
④【正】
DNA量が2のままで、凝縮した染色体を持つ細胞が蓄積していることから、M期における染色体の分配が阻害され、細胞分裂が完了できない状態と考えられます。
⑤【誤】
図4から明らかなように、染色体は凝縮しているため、染色体の凝縮は阻害されていません。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
血液を構成する成分(血球、血しょう)と、その働きについての基本的な知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
血液は、有形成分である血球(赤血球、白血球、血小板)と、液体成分である血しょうから構成されます。血清は、血しょうから血液凝固に関わるタンパク質であるフィブリノーゲンを取り除いたものです。
②【誤】
血液1mm
3
あたりに含まれる血球の数は、赤血球が約450万~500万個、血小板が約15万~40万個、白血球が約4000~8000個です。したがって、最も数が多いのは赤血球です。
③【誤】
血液の液体成分である血しょうの約90%は水です。それに溶けている物質の中で最も質量が多いのは、アルブミンやグロブリンなどのタンパク質(約7%)です。無機塩類は約0.9%を占めるにすぎません。
④【正】
酸素の大部分は、赤血球に含まれるヘモグロビンと結合して運ばれます。ヘモグロビン1分子は最大4分子の酸素と結合でき、これにより血液はただの水よりもはるかに効率よく酸素を運搬できます。
⑤【誤】
白血球の主な働きは、食作用や抗体産生による免疫作用です。二酸化炭素や尿素などの老廃物は、主に血しょうに溶け込んで運搬されます。
問2:正解⑤
<問題要旨>
血管が損傷した際に起こる血液凝固の一連の流れを、正しい順序で理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
血管が傷つくと、出血を止めるために以下のステップで血液凝固が起こります。
傷ついた血管のコラーゲン繊維が露出すると、そこに血小板が集まって塊を作り、一時的な止血栓となります。(ウ)
血小板や組織から放出される血液凝固因子が働き、血しょう中のタンパク質であるフィブリノーゲンが、不溶性の繊維状の物質であるフィブリンに変化します。(ア)
このフィブリンが網目状の構造を作り、そこに赤血球などを絡め取って丈夫な血ぺい(血餅)を形成し、傷口を完全に塞ぎます。(イ)
したがって、正しい順序はウ→ア→イとなります。この順序に合致する選択肢は⑤です。
問3:正解③
<問題要旨>
病原体が体内に侵入した際に、まず初めに働く防御機構である「自然免疫」に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
病原体などを細胞内に取り込んで処理する食作用を持つのは、マクロファージや好中球といった白血球です。血小板は血液凝固には関わりますが、食作用は持ちません。
②【誤】
角質層は皮膚の表面を覆う構造で、病原体の侵入を防ぐ物理的なバリアです。傷ができた直後に、傷口を塞ぐために角質層が新たに形成されるわけではありません。傷口はまず血ぺいで塞がれます。
③【正】
マクロファージは、自然免疫の中心的な役割を担う食細胞です。組織中に広く存在し、傷口などから病原体が侵入すると、いち早くそれを認識して食作用により取り込み、分解します。これは侵入直後に起こる重要な初期防御反応です。
④【誤】
ナチュラルキラー(NK)細胞は、ウイルスに感染した細胞やがん細胞など、自己の異常な細胞を認識して攻撃するリンパ球です。細菌などの病原体そのものを直接攻撃する役割は主ではありません。
⑤【誤】
抗体を放出する抗体産生細胞(形質細胞)が働くのは、獲得免疫の仕組みです。獲得免疫は、特定の病原体を記憶し、それに対して特異的に反応する強力な免疫ですが、反応が起こるまでには数日間の時間が必要です。侵入直後の反応ではありません。
問4:正解⑤
<問題要旨>
人体の器官の位置関係(特に腎臓)と、動脈と静脈の構造的な違いについての理解を組み合わせる問題です。
<選択肢>
・空欄アの特定:
問題文に「管Aの血管壁は管Bの血管壁よりも厚かった」とあります。心臓から高い圧力で送り出される血液が流れる動脈は、その圧力に耐えるために血管壁が厚く、弾力性に富んでいます。一方、心臓へ戻る血液が流れる静脈は、血圧が低いため血管壁が比較的薄くなっています。したがって、管Aが腎動脈、管Bが腎静脈と判断できます。問題文では「管アを血管の模型の静脈に接続し」とあるため、アにはBが入ります。
・空欄イの特定:
腎臓は、腹部の背中側に左右一対ある臓器です。図1は人体を腹側から見た図で、横隔膜を境に上が胸部(部位X)、下が腹部(部位Y、Z)です。腎臓は横隔膜のすぐ下、腰の高さに位置するため、部位Yが最も適切な場所となります。
以上のことから、アがB、イがYの組み合わせである⑤が正解です。
問5:正解②
<問題要旨>
腎臓における尿の生成過程、特に「ろ過」と「再吸収」の仕組みを理解し、最終的に尿として排出される物質を特定する問題です。
<選択肢>
腎臓では、血液が糸球体でろ過されて原尿が作られ、それが細尿管と集合管を通過する間に再吸収と濃縮が行われて尿が完成します。
・ろ過:糸球体からボーマンのうへ、血球やタンパク質などの大きなものを除く血しょう成分がこし出されます。この時点の原尿には、水、無機塩類(a)、グルコース(糖)(b)、尿素(d)、アミノ酸(c)などが含まれます。
・再吸収:原尿が細尿管を通る間に、からだに必要な物質が選択的に血液中へ回収されます。健康なヒトの場合、グルコース(糖)とアミノ酸は100%再吸収されるため、尿中には排出されません。水や無機塩類も大部分が再吸収されます。
・尿の成分:再吸収されずに残った尿素や、過剰な水、無機塩類などが尿として排出されます。
したがって、管C(輸尿管)を流れる尿中には、主に**無機塩類(a)と尿素(d)**が含まれます。この組み合わせを示しているのは②です。
問6:正解③
<問題要旨>
腎臓の内部構造と、血液がろ過される場所(糸球体)の分布を結びつけて考察する問題です。
<選択肢>
腎臓の断面は、外側の皮質と内側の髄質に分けられます。血液をろ過する糸球体とボーマンのうからなる腎小体は、主に皮質に分布しています。
この実験では、腎動脈から墨汁を注入しています。墨汁の黒い成分は「タンパク質」であるため、血球と同様に分子量が大きく、糸球体でろ過されません。したがって、墨汁の成分は糸球体を含む毛細血管の中に留まります。
結果として、墨汁の黒い成分は、糸球体が密集している皮質に沿って分布することになります。髄質には細尿管や集合管が多く、糸球体はほとんどないため、墨汁は分布しません。
図の中で、腎臓の外側である皮質にのみ黒い成分が分布している様子を示しているのは③です。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
日本のバイオーム(生物群系)の分布を決定づける気候要因と、緯度や標高による森林限界の変化についての知識を問う問題です。
<選択肢>
・空欄アの特定:
バイオームの分布は、主にその地域の気候、特に気温と降水量によって決まります。日本列島は南北に長く、どの地域でも森林が成立するには十分な降水量があります。そのため、南の亜熱帯多雨林から、照葉樹林、夏緑樹林、北の針葉樹林へとバイオームが変化する最も大きな要因は、年平均気温の違いです。
・空欄イの特定:
森林限界とは、高木が生育できなくなる限界線(標高)のことです。これは主に低温によって決まります。緯度が高い地域ほど、同じ標高でも気温が低くなるため、より低い標高で高木が生育できなくなります。したがって、高緯度に位置する北海道の森林限界の標高は、それより低緯度にある本州中部地方の森林限界よりもより低いです。
以上のことから、アが年平均気温、イがより低いの組み合わせである④が正解です。
問2:正解⑤
<問題要旨>
湖沼における生態系、特に植生の分布(遷移)や生態系における生産者についての理解を問う問題です。
<選択肢>
a【正】
湖沼では、岸辺から沖に向かって水深が深くなるにつれて、光の届き方が変化します。これに応じて、生育する植物の種類が異なり、岸辺から順に抽水植物(ヨシなど)、浮葉植物(ヒシなど)、沈水植物(クロモなど)といった帯状の植生分布(植物群落の帯状配列)が見られます。
b【誤】
生態系における生産者とは、光合成などによって無機物から有機物を合成する独立栄養生物のことです。湖沼では、植物プランクトンやaで述べたような水生植物が生産者に該当します。動物プランクトンは、植物プランクトンなどを捕食する消費者です。
c【正】
湖沼は、河川からの土砂の流入や、植物の遺骸などが長年にわたって堆積することで、次第に浅くなり、湿原へと変化します。さらに乾燥化が進むと、草原を経て、やがては森林へと移り変わっていきます(遷移)。これを湿性遷移と呼びます。
したがって、正しい記述はaとcであり、この両方を含む⑤が正解です。
問3:正解③
<問題要旨>
草原の維持管理の方法と、そこに生育する植物の種数(多様性)との関係について、表とグラフのデータを正確に読み取り、比較検討する力が問われています。
<選択肢>
①【誤】
「火入れと刈取りの両方を毎年(区域II)」と「どちらかのみを毎年(区域III, IV)」の希少な草本の割合を比較します。
・区域IIの割合:約3.8種 / 約28種 ≒ 13.6%
・区域IIIの割合:約5.0種 / 約25種 = 20%
区域IIの割合は区域IIIよりも小さいため、この記述は誤りです。
②【誤】
「火入れを毎年(区域IV)」と「管理を放棄(区域V)」を比較します。
・区域IV:全種数 約25種、希少種数 約4.0種
・区域V:全種数 約23種、希少種数 約4.5種
区域IVは区域Vに比べて「希少な草本の種数」が少ないため、この記述は誤りです。
③【正】
「伝統的管理(区域I)」と「火入れと刈取りの両方を毎年(区域II)」を比較します。
・区域I:全種数 約36種、希少種数 約8.2種
・区域II:全種数 約28種、希少種数 約3.8種
区域Iは、区域IIに比べて「全ての植物の種数」も「希少な草本の種数」も、両方とも多くなっています。したがって、この記述はグラフから読み取れる事実として正しいです。
④【誤】
「管理を放棄(区域V)」と「伝統的管理(区域I)」の希少な草本の割合を比較します。
・区域Vの割合:約4.5種 / 約23種 ≒ 19.6%
・区域Iの割合:約8.2種 / 約36種 ≒ 22.8%
区域Vの割合は区域Iよりも小さいため、この記述は誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
外来生物が関わる生態系の問題について、その定義を正しく理解し、該当しない事例を特定する問題です。「外来生物」とは、本来の生息・生育地から、人間活動によって意図的・非意図的に別の地域へ導入された生物種を指します。
<選択肢>
①【外来生物が関わる】
アジア原産のクズが、人間の手によって北米に持ち込まれた結果、在来の生態系に影響を与えている典型的な外来生物の問題です。
②【外来生物が関わらない】
サクラマスを捕獲した川と同じ川に放流しています。これは、生物を本来の生息地ではない「別の地域」へ移動させているわけではないため、外来生物の問題ではありません。ただし、同じ地域内であっても、飼育によって特定の遺伝子を持つ個体が増えすぎると、その地域の個体群全体の遺伝的な多様性が損なわれる「遺伝的攪乱」という問題を引き起こす可能性があります。
③【外来生物が関わる】
元々イタチがいなかった島へ、本州から人間がイタチを持ち込んだ結果、在来のトカゲが捕食されて減少したという、外来生物による捕食の問題です。
④【外来生物が関わる】
外国産の魚に付着していた「外国由来の細菌」が、人間による飼育を介して日本の水路に持ち込まれ、在来の魚に感染したという問題です。病原体も外来生物に含まれ、在来種に病気をもたらす深刻な影響を与えることがあります。
問5:正解①
<問題要旨>
生態系に影響を与える外来生物について、その科学的な管理方法に関する適切な考え方を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
一度定着してしまった外来生物を完全に根絶することは、技術的にもコスト的にも非常に困難な場合があります。そのような場合でも、生態系への悪影響をできるだけ小さくするために、定期的に駆除を行うなどして個体数を低いレベルに抑える「低密度管理」は、現実的で有効な対策の一つです。
②【誤】
家畜であっても、野生化して自然の生態系に定着すれば、在来の草食動物との競合や植生破壊などを引き起こす深刻な外来生物問題となります。世界の島々で野生化したヤギが植生を破壊した例などがあり、放置せずに適切に管理する必要があります。
③【誤】
ある外来生物を駆除するために、その天敵となる別の外来生物を導入する「生物的防除」は、予期せぬ新たな生態系の破壊を引き起こす危険性が非常に高い方法です。沖縄でハブを駆除するために導入されたマングースが、ヤンバルクイナなどの希少な在来種を捕食してしまった例が有名です。
④【誤】
外来生物の駆除は、侵入が確認された直後の、個体数が少なく分布域も限られている段階で集中的に行うことが最も効果的であり、根絶の可能性も高まります。「早期発見・早期駆除」が基本原則です。増殖して分布が広がってからでは、駆除は極めて困難になります。