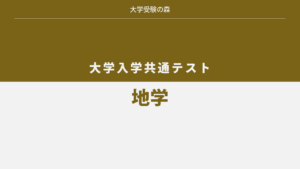解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
グラフから海洋底の拡大速度を読み取り、2つの海嶺の速度を比較する問題です。グラフの傾きが海洋底の移動速度に対応します。
<選択肢>
①【誤】
海嶺bの速さは海嶺aの速さよりも遅いため、1倍より大きくなることはありません。
②【誤】
海嶺aの速さが海嶺bの速さの約2倍です。問題では「海嶺bの速さは、海嶺aの速さの何倍か」と問われているため、逆の関係になります。
③【正】
グラフの横軸は年代、縦軸は海嶺からの距離を示しているため、その傾き(距離÷年代)が海洋底の移動の速さを表します。
海嶺a(●の点)について、80百万年前の点で考えると、距離は約3300kmです。したがって、速さは約 3300km / 80百万年 = 41.25 km/百万年 です。
海嶺b(☆の点)について、80百万年前の点で考えると、距離は約1600kmです。したがって、速さは 1600km / 80百万年 = 20 km/百万年 です。
よって、海嶺bの速さが海嶺aの速さの何倍かを計算すると、20 / 41.25 ≒ 0.48 となり、約1/2倍であることがわかります。
④【誤】
計算結果から、速さの比は約1/2であり、1/3ではありません。
問2:正解②
<問題要旨>
ハッブルの法則に関するグラフを読み取り、与えられた後退速度から銀河までの距離を推定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
30メガパーセクの距離にある銀河の後退速度は、グラフの直線関係からおよそ2100km/sと推定され、3500km/sにはなりません。
②【正】
グラフには2つの銀河のデータ(20メガパーセクで約1400km/s、40メガパーセクで約2800km/s)が示されています。ハッブルの法則では、銀河の後退速度vは距離dに比例し (v = H₀d)、グラフは原点を通る直線となります。
グラフの2点から、この直線の傾きであるハッブル定数H₀は、2800km/s / 40メガパーセク = 70 km/s/メガパーセク と求められます。
後退速度が3500km/sの銀河までの距離dは、d = v / H₀ = 3500 / 70 = 50メガパーセクと計算できます。
③【誤】
70メガパーセクの距離にある銀河の後退速度は、グラフの直線関係からおよそ4900km/sと推定され、3500km/sにはなりません。
④【誤】
90メガパーセクの距離にある銀河の後退速度は、グラフの直線関係からおよそ6300km/sと推定され、3500km/sにはなりません。
問3:正解③
<問題要旨>
マントル物質の融解曲線のグラフを読み取り、特定の温度・圧力条件下での物質の状態を判断する問題です。物質の温度・圧力が融解曲線より下側(低温側)にあれば固体、上側(高温側)にあれば液体(融解)状態となります。
<選択肢>
①【誤】
点Aの条件(圧力4.5×10⁹ Pa, 温度1400℃)は、無水の場合の融解曲線(実線)より下側(低温側)にあるため、融解していません。
②【誤】
無水の場合は融解しておらず、水に飽和している場合は融解しています。記述が逆です。
③【正】
点Aの条件は、圧力4.5×10⁹ Pa、温度1400℃です。
・無水の場合:グラフの実線を見ると、圧力4.5×10⁹ Paでの融解温度は1600℃程度です。点Aの温度1400℃はこれより低いため、融解しておらず固体状態です。
・水に飽和している場合:表1のデータをプロットして破線を延長すると、圧力4.5×10⁹ Paでの融解温度は、1190℃(4×10⁹ Pa)と1300℃(5×10⁹ Pa)の間、およそ1250℃になります。点Aの温度1400℃はこれより高いため、融解して液体(マグマ)状態です。
したがって、「無水の場合は融解していないが、水に飽和している場合は融解している」という記述が正しいです。
④【誤】
点Aの条件は、水に飽和している場合の融解曲線(破線)より上側(高温側)にあるため、融解しています。
問4:正解③
<問題要旨>
日本南岸の海域における、夏季と冬季の水温の鉛直分布の特徴を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
曲線aは、夏季(灰色の太線)よりも全体的に水温が低いものの、表層に顕著な水温躍層が見られます。冬季は表層の冷却と風による混合で水温がほぼ一定の層(混合層)が発達するため、この分布は冬季としては不適当です。
②【誤】
曲線bは、夏季よりも表層水温が高くなっています。冬季は夏季に比べて日射が弱く、気温も低いため、表層水温は低くなるはずです。
③【正】
冬季の日本南岸では、海面の冷却と季節風による鉛直混合が活発になるため、水深100m程度まで水温がほぼ一定の「混合層」が形成されます。曲線cは、夏季(灰色の太線)に比べて表層水温が低く、深い混合層が形成されており、冬季の典型的な水温分布を示しています。
④【誤】
曲線dは、表層から深層まで水温が非常に低く、ほぼ一定です。これは極域の海で見られる水温分布であり、黒潮が流れる日本南岸の分布としては不適当です。
問5:正解⑤
<問題要旨>
地層の走向・傾斜の情報を用いて、地形図上の特定の地層(鍵層)が地表に現れる位置を推定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
地点aの標高は約195mです。走向線からの距離を考えると、この地点での鍵層の標高は200m程度と計算され、地表には現れません。
②【誤】
地点bの標高は180mです。走向線からの距離を考えると、この地点での鍵層の標高は180mと計算されますが、より正確な作図や他の地点との比較から、解答としてはeが最も適当と判断されます。
③【誤】
地点cの標高は160mです。走向線からの距離を考えると、この地点での鍵層の標高は150m程度と計算され、地表には現れません。
④【誤】
地点dの標高は120mです。走向線からの距離を考えると、この地点での鍵層の標高は125m程度と計算され、地表には現れません。
⑤【正】
この問題では、地層面と地形面(等高線)が交わる場所(露頭)を探します。
地点Xの標高を読み取ります。Xは150mの等高線から2本分高い位置にあるため、等高線間隔が10mであることから、標高は170mです。
鍵層の走向はN45°Wなので、地点Xを通り北西-南東方向の直線(走向線)を引きます。この線上では鍵層の標高はどこでも170mです。
傾斜は45°SWなので、走向線から南西方向に離れると鍵層の標高は低くなり、北東方向に離れると高くなります。傾斜が45°なので、tan(45°)=1となり、走向線からの水平距離がそのまま標高差になります。
地点eの標高は100mです。地点eが鍵層の露頭であると仮定すると、鍵層の標高も100mであるはずです。
地点X(鍵層標高170m)と地点e(鍵層標高100m)の標高差は70mです。したがって、地点eはXを通る走向線から南西方向に水平距離で70m離れた場所にあるはずです。
地図の縮尺(20mのスケール)を使って確認すると、地点eはXを通る走向線から南西方向に約70m(スケールの3.5倍)離れており、計算と一致します。よって、地点eで鍵層が見られると判断できます。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
アイソスタシーの原理に基づき、大陸氷床が融解した後の地殻の変動を問う問題です。アイソスタシーとは、地殻とマントルの間の重さのバランスが保たれている状態を指します。
<選択肢>
①【正】
図1の状態では、氷の重さによって中央部の地殻がマントルに沈み込んでいます。この氷が融けて失われると、中央部にかかっていた荷重が取り除かれるため、地殻は軽くなります。アイソスタシーを回復しようとする働きにより、マントルから浮力を受けて中央部は隆起します。これを氷河性地殻隆起(ポストグレイシャルリバウンド)と呼びます。
②【誤】
中央部は荷重が減少するため、隆起します。沈降は、逆に氷床が形成されるなどして荷重が増加した場合に起こります。
③【誤】
変動の主な原因は中央部の荷重の減少であるため、最も大きく変動するのは中央部です。周辺部が隆起することはありません。
④【誤】
中央部の隆起に伴い、マントル物質が中央部へ移動するため、周辺部ではわずかに沈降が起こる可能性はありますが、最も主たる現象は中央部の隆起です。
問2:正解②
<問題要旨>
地磁気の逆転がオーロラの発生場所や海洋底の残留磁気に与える影響についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
文章bが誤りです。
②【正】
a【正】:オーロラは、太陽からの荷電粒子が地球の磁力線に沿って侵入し、極域の超高層大気と衝突して発光する現象です。地磁気の向きが逆転しても、磁力線が集中する磁極が地理的な極付近にあることに変わりはないため、オーロラは現在と同様に高緯度地方で発生します。
b【誤】:中央海嶺で生成される海洋地殻の残留磁気は、その時代の地磁気の向きを記録します。もし地磁気の向きが現在と正反対であれば、新たに生成される海洋地殻には、現在とは逆向きの残留磁気が記録されます。「現在と同じ向き」という記述が誤りです。
③【誤】
文章aが正しく、文章bが誤りです。
④【誤】
文章aが正しいです。
問3:正解④
<問題要旨>
日本周辺のプレートの沈み込みと火山の分布を示した図を解釈し、記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
図を見ると、東北地方や北海道に分布する活動的な火山(▲)は、太平洋プレート上面の深さを示す等深線(実線)の100kmの線に沿うように分布しています。この火山の列を火山フロントと呼びます。
②【正】
等深線の間隔が狭いほど、プレートの沈み込む角度が急であることを示します。図を見ると、東北地方の地下よりも、伊豆・小笠原諸島の地下の方が等深線の間隔が明らかに狭くなっています。これは、伊豆・小笠原諸島の地下で太平洋プレートがより急な角度で沈み込んでいることを意味します。
③【正】
関東地方の地下には、南東からフィリピン海プレートが沈み込み(破線の等深線)、そのさらに下には東から太平洋プレートが沈み込んでいる(実線の等深線)ことがわかります。このように2つのプレートが重なって沈み込んでいる複雑な構造になっています。
④【誤】
図を見ると、四国地方の地下にはフィリピン海プレートが存在しており、その上面の深さを示す等深線(破線)が描かれています。したがって、「フィリピン海プレートが存在しないからである」という理由が誤りです。(四国地方に火山がないのは、沈み込むフィリピン海プレートが比較的高温で、火山活動を引き起こすほどの深さに達していないためとされています。)
問4:正解①
<問題要旨>
震央分布とP波初動分布から、横ずれ断層のタイプと特定の観測点での初動を推定する問題です。
<選択肢>
①【正】
断層面の推定:本震(☆)とその余震(○)の分布は、北北西-南南東方向に直線状に並んでおり、これが断層面の走向を示していると考えられます。
P波初動の分布:P波初動は、断層運動によって観測点が「押される」か「引かれる」かを示します。観測点A(北西)とB(南東)で「引き」が観測されています。横ずれ断層の初動分布は、断層面とそれに直交する補助面によって4つの象限に分けられ、対角の象限が同じ動き(押し/引き)になります。
断層のずれの向きの決定:A(北西)とB(南東)が「引き」の領域なので、それと対角の位置にある北東(Cの方向)と南西の領域は「押し」の領域となります。断層を挟んで西側のブロックが南へ、東側のブロックが北へ動くと、このような初動分布が生まれます。これは、断層を挟んで相手側のブロックが左にずれる「左横ずれ断層」です。
地点Cの初動:地点Cは北東の象限に位置しており、この領域は「押し」となります。
したがって、「左横ずれ」で地点Cの初動は「押し」の組み合わせが正しいです。
②【誤】
地点Cは「押し」の領域です。
③【誤】
断層のずれは「左横ずれ」です。
④【誤】
断層のずれは「左横ずれ」であり、地点Cの初動は「押し」です。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
おもな造岩鉱物の特徴(色、へき開、産状)に基づいて、分類の基準と図を正しく対応させる問題です。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが異なります。
②【誤】
組み合わせが異なります。
③【正】
各鉱物の特徴は以下の通りです。
・輝石:有色鉱物、へき開あり、斑れい岩の主成分
・黒雲母:有色鉱物、へき開あり(顕著)、斑れい岩にはあまり含まれない
・石英:無色鉱物、へき開なし、斑れい岩には含まれない
・かんらん石:有色鉱物、へき開なし、斑れい岩の主成分
各基準で分類すると、以下のようになります。
a. 有色鉱物か、無色鉱物か
・有色鉱物:輝石、黒雲母、かんらん石
・無色鉱物:石英
→これは図Yの分類(左に有色鉱物3つ、右に無色鉱物1つ)と一致します。
b. へき開がよく見られるか、そうでないか
・へき開あり:輝石、黒雲母
・へき開なし:石英、かんらん石
→これは図Xの分類と一致します。
c. 斑れい岩のおもな構成鉱物であるか、そうでないか
・斑れい岩の主成分:輝石、かんらん石
・そうでない:石英、黒雲母
→これは図Zの分類と一致します。
以上のことから、Xはb、Yはa、Zはcの基準で分類したものだとわかります。
④【誤】
組み合わせが異なります。
⑤【誤】
組み合わせが異なります。
⑥【誤】
組み合わせが異なります。
問2:正解⑤
<問題要旨>
会話文を読み、マグマの性質と火山地形に関する知識を問う問題です。イエローストーンが流紋岩質のマグマ活動でできたカルデラであることを理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
流紋岩質マグマはSiO₂が多く、粘性が高いです。また、大規模な陥没地形はカルデラです。
②【誤】
流紋岩質マグマはSiO₂が多いです。
③【誤】
流紋岩質マグマはSiO₂が多く、粘性が高いです。
④【誤】
流紋岩質マグマは粘性が高いです。また、大規模な陥没地形はカルデラです。
⑤【正】
会話文に出てくる「流紋岩質マグマ」は、富士山などの「玄武岩質マグマ」に比べて【ア:多く】のSiO₂を含んでいます。SiO₂が多いマグマは、ケイ酸塩の結びつきが強くなるため、粘性が【イ:高く】なります。
また、地下のマグマだまりから非常に大量のマグマが噴出すると、その上が空洞化し、大規模な陥没地形が形成されます。これを【ウ:カルデラ】と呼びます。イエローストーンは巨大なカルデラで知られています。
⑥【誤】
流紋岩質マグマは粘性が高いです。
問3:正解④
<問題要旨>
沈み込み帯の温度構造図(図4)から特定の地点の温度と圧力(深さ)を読み取り、Al₂SiO₅鉱物の相図(図3)と照らし合わせて、その地点で安定に存在する鉱物を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
地点Aで安定なのは珪線石です。
②【誤】
地点Aで安定なのは珪線石、地点Bで安定なのはらん晶石です。
③【誤】
地点Aで安定なのは珪線石、地点Bで安定なのはらん晶石です。
④【正】
まず、図4から地点Aと地点Bの温度と深さを読み取ります。
・地点A:深さは20km。等温線を見ると、600℃と800℃の線の間に位置しているため、温度は約700℃と推定できます。
・地点B:深さは40km。400℃と600℃の等温線の間に位置しているため、温度は約500℃と推定できます。
次に、この(深さ、温度)の条件を図3の相図に当てはめます。
・地点A(深さ20km, 温度700℃):この条件は「珪線石」が安定な領域に含まれます。
・地点B(深さ40km, 温度500℃):この条件は「らん晶石」が安定な領域に含まれます。
したがって、Aでは珪線石、Bではらん晶石が安定に存在します。
⑤【誤】
地点Aで安定なのは珪線石、地点Bで安定なのはらん晶石です。
⑥【誤】
地点Bで安定なのはらん晶石です。
問4:正解③
<問題要旨>
化石の種類(示相化石と示準化石)と、代表的な示準化石の活動時代に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
過去の環境を示す化石は示相化石です。
②【誤】
過去の環境を示す化石は示相化石です。また、デスモスチルスは第四紀の示準化石ではありません。
③【正】
【エ】:文章中に「過去の環境を推定するために有効な化石」とあるため、これは示相化石を指します。示相化石は、地層が堆積した当時の環境(気候、水深、塩分濃度など)を知る手がかりとなる化石です。
【オ】:問題文に「第四紀の地層から」「同じ時期に生息していた」とあるため、第四紀の示準化石を選ぶ必要があります。示準化石は、その化石が含まれる地層の年代を決めるのに役立つ化石です。選択肢のうち、マンモスは第四紀(特に更新世)を代表する示準化石です。一方、デスモスチルスは新生代第三紀中新世の示準化石です。
したがって、エに「示相化石」、オに「マンモス」が入るのが適当です。
④【誤】
デスモスチルスは第四紀の示準化石ではありません。
問5:正解③
<問題要旨>
複数の示相化石が同じ地層から産出した場合に、それらの生息水深の共通範囲を求めることで、地層の堆積環境を推定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
この範囲では、二枚貝B(〜50m)やC(〜100m)が生息できません。
②【誤】
この範囲では、二枚貝B(〜50m)が生息できません。
③【正】
4種類の二枚貝の化石が同じ場所で生息していた(原地性)ということなので、地層が堆積した水深は、4種類すべての生息水深が重なる範囲であると考えられます。
・Aの生息水深:5m 〜 70m
・Bの生息水深:10m 〜 50m
・Cの生息水深:10m 〜 100m
・Dの生息水深:20m 〜 200m
これらの共通範囲を求めます。最も浅い限界は、Dの「20m」より浅くなることはありません。最も深い限界は、Bの「50m」より深くなることはありません。
したがって、4種類すべてが生息できる水深の範囲は、20m〜50mとなります。
④【誤】
この範囲では、二枚貝B(〜50m)やD(20m〜)が生息できません。
問6:正解②⑥(順不同)
<問題要旨>
地質図から地質構造(走向・傾斜、褶曲)を読み取り、この地域の地史や特徴について正しく述べている文を選択する問題です。
<選択肢>
①【誤】
地質図の北西側に示されている走向・傾斜の記号は、南東への傾斜を示しています。南東側の記号は北西への傾斜を示しているため、「すべての地層は北西に傾斜している」は誤りです。
②【正】
地質図の中央部を軸として、両側の地層が互いに向かい合うように傾斜しています(翼が中心に向かって傾いている)。これは向斜構造の特徴です。また、地層の分布を見ると、中央の泥岩が最も新しく、外側に向かって砂岩、礫岩、凝灰岩の順に古くなっており、これも向斜構造を示しています。
③【誤】
北東-南西走向の褶曲(向斜)構造は、北西-南東方向からの圧縮の力によって形成されます。記述は圧縮方向が誤っています。
④【誤】
地質図からは、凝灰岩を形成した火山灰がどちらの風向で運ばれてきたかを判断することはできません。
⑤【誤】
地質図からは、砂岩を形成した砂がどちらの方向から運ばれてきたか(古流向)を判断することはできません。
⑥【正】
この地域は向斜構造であり、地層の逆転はないため、褶曲の中心部に位置する地層ほど新しくなります。地点Aは中央部の泥岩層に、地点Bは外側の礫岩層に位置しています。したがって、地点Aの地層は地点Bの地層よりも新しいと言えます。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
気圧と水銀柱の高さの関係(トリチェリの実験)について、高度や気圧の変化が及ぼす影響を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
文章aが誤りです。
②【誤】
文章aが誤り、文章bが正しいです。
③【正】
a【誤】:水銀柱の高さは、外の大気圧とつり合っています。低気圧が近づくと、大気圧は通常よりも低くなります。したがって、水銀柱を押し上げる力が弱まるため、高さはHより低くなります。「高くなる」という記述は誤りです。
b【正】:標高が高くなるほど、その上にある大気の量が少なくなるため、気圧は低くなります。富士山の山頂(標高3776m)は海抜0mの地点より気圧が大幅に低いため、実験を行うと水銀柱の高さはHより低くなります。
④【誤】
文章bが正しいです。
問2:正解②
<問題要旨>
地球大気の温度の鉛直分布とその要因(温室効果、オゾンによる紫外線吸収)に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
文章dが誤りです。
②【正】
c【正】:水蒸気や二酸化炭素などの温室効果ガスは、地球から放射される赤外線を吸収し、その一部を再び地表に向かって放射することで、地上付近(対流圏)の大気を暖める働きがあります。これを温室効果と呼びます。
d【誤】:成層圏上部(高度20〜50km)の気温が高い主な原因は、成層圏に存在するオゾン層が、太陽からの有害な紫外線を吸収するためです。オゾンによる温室効果もわずかにありますが、気温を高くしている主な要因は紫外線吸収による加熱です。「オゾンによる温室効果」という記述は、主たる原因として不適切です。
③【誤】
文章cが正しく、文章dが誤りです。
④【誤】
文章cが正しいです。
問3:正解④
<問題要旨>
雲粒が形成される際の凝結核・昇華核となる物質についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【適当】
土壌粒子は風によって大気中に巻き上げられ、凝結核として働きます。黄砂などがその例です。
②【適当】
波しぶきなどによって大気中に放出された海塩粒子は、吸湿性が高く、主要な凝結核となります。
③【適当】
燃焼によって生じる煙やすすの粒子(エアロゾル)も、凝結核として働きます。
④【不適当】
オゾンはO₃の分子であり、雲粒を形成するための核となるような粒子ではありません。凝結や昇華の核となるのは、大気中に浮遊する微小な固体や液体の粒子(エアロゾル)です。
問4:正解①
<問題要旨>
氷晶と過冷却水滴が共存する雲の中での氷晶の成長メカニズム(ライスター・ベルシェロン過程)を、飽和水蒸気圧の概念から理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
図2を見ると、同じ温度(0℃以下)では、氷に対する飽和水蒸気圧(破線)よりも、過冷却水に対する飽和水蒸気圧(実線)の方が常に【ア:高い】ことがわかります。
このため、氷晶と過冷却水滴が共存する環境では、水蒸気圧が両者の飽和水蒸気圧の間にある場合、過冷却水滴にとっては未飽和、氷晶にとっては過飽和の状態になります。その結果、過冷却【イ:水滴】は蒸発し、その水蒸気が【ウ:氷晶】の表面に昇華・付着して氷晶が成長していきます。
②【誤】
水滴が蒸発し、氷晶が成長します。
③【誤】
過冷却水に対する飽和水蒸気圧の方が高いです。
④【誤】
過冷却水に対する飽和水蒸気圧の方が高く、水滴が蒸発して氷晶が成長します。
問5:正解①
<問題要旨>
黒潮を含む海洋の循環に関する基本的な用語(西岸強化、地衡流)の知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
【エ】:北太平洋の亜熱帯循環では、地球自転の効果(コリオリ力の緯度変化)により、還流の西側で流れが強く、狭くなります。この現象を西岸強化と呼びます。黒潮はまさにこの西岸強化によって生じている強流です。
【オ】:流れの方向に対して右向きに働くコリオリの力と、左向きに働く圧力傾度力(水圧の差による力)がつり合って流れる海流を地衡流と呼びます。黒潮のような大規模な海流は、地衡流としてよく近似できます。
②【誤】
エクマン吹送流は、風とコリオリの力がつり合った流れを指し、黒潮の力学的な説明としては不適切です。
③【誤】
エクマン輸送は、風によって海水が運ばれる現象を指し、流れが速くなる原因ではありません。
④【誤】
両方の語句が不適切です。
問6:正解①
<問題要旨>
黒潮が地衡流であることを踏まえ、蛇行部分における海面高度の分布を推定する問題です。
<選択肢>
①【正】
黒潮は地衡流であり、北半球では流れの方向を見て右側にコリオリの力が働きます。この力とつり合うためには、圧力傾度力が左向きに働く必要があります。圧力傾度力は、圧力(海面高度)が高い方から低い方へと働くため、流れの方向を見て左側の海面高度が低く、右側の海面高度が高くなければなりません。
図3の蛇行部では、黒潮はAからBの方向へカーブしながら流れています。この流れに沿って考えると、A側が流れの右側、B側が流れの左側に対応する部分が多くなります。全体として、黒潮の流路の中心(暖水域)は周囲より海水温が高く、熱膨張により海面高度が高くなっています。蛇行によって南に張り出した部分では、遠心力も考慮すると、中心部で海面が低くなる冷水渦が形成されます。線分A-Bは、この冷水渦を横切っています。したがって、AとBの岸に近い側が高く、中央部が低くなるような海面高度分布となります。
②【誤】
中央部が高くなるのは暖水渦の場合であり、黒潮大蛇行の内側の冷水域とは逆の分布です。
③【誤】
AからBに向かって単調に高くなる分布ではありません。
④【誤】
AからBに向かって単調に低くなる分布ではありません。
第5問
問1:正解④
<問題要旨>
星図上の惑星の動きを読み取り、その視運動(順行・逆行)と名称を正しく判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
惑星Aの動きは順行です。また、動きの速さから木星と判断されます。
②【誤】
惑星Aの動きは順行です。
③【誤】
惑星Aは木星です。
④【正】
・視運動の判断:恒星は天球に固定されていると考えると、惑星が恒星に対して東から西へ動くように見えるのが「逆行」、西から東へ動くように見えるのが「順行」です。図1では、日付が進むにつれて惑星A、Bともに西から東(図の右から左)へ動いています。したがって、両惑星とも順行運動をしています。
・惑星の名称の判断:火星と木星では、地球から遠い木星の方が、恒星に対する見かけの動き(年周運動)が遅くなります。図を見ると、同じ期間(5月7日から6月26日)で惑星Bの方が惑星Aよりも大きく移動しています。したがって、動きの遅い惑星Aが木星、動きの速い惑星Bが火星であると判断できます。
よって、惑星Aは「順行」しており、その名称は「木星」です。
問2:正解③
<問題要旨>
天体の観察結果から、どのような事実が確認できるかを考察する問題です。
<選択肢>
①【誤】
惑星が楕円軌道であることは、見かけの明るさや速度の年周変化などを精密に観測しないとわかりません。この図の観察だけでは公転軌道の形までは断定できません。
②【誤】
惑星の自転は、表面の模様の動きなどを望遠鏡で長期間観測して初めてわかることであり、この図の観察からは確認できません。
③【正】
火星と木星は、図1に示されるように、ほぼ同じ経路(黄道)に沿って動いています。黄道は地球の公転面が天球と交わる線です。惑星が黄道近くを動くということは、それらの惑星の公転面が地球の公転面とほぼ一致していることを示しています。この観察結果は、この事実を裏付けています。
④【誤】
衝(地球を挟んで太陽と反対側に来る位置)や合(太陽と同じ方向に来る位置)は、惑星と太陽と地球の位置関係で決まります。この観察だけでは、惑星が衝や合にあるかどうかは判断できません。
問3:正解⑤
<問題要旨>
火星と木星の物理的特徴(大気、内部構造、密度)に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
文章aが誤りです。
②【誤】
文章aとcが誤りです。
③【誤】
文章aが誤りです。
④【誤】
文章cが誤りです。
⑤【正】
a【誤】:火星の大気の主成分は二酸化炭素ですが、木星の大気の主成分は水素とヘリウムです。
b【正】:火星は地球型惑星であり、中心部に金属核、その周りを岩石質のマントルと地殻が覆っています。木星は木星型惑星ですが、その中心部には岩石や氷からなる固体核が存在すると考えられています。
c【誤】:金属水素の層は、巨大な圧力によって水素が金属的な性質を示す層で、木星や土星の内部に存在すると考えられています。火星のような地球型惑星の内部には存在しません。
d【正】:木星は巨大なガス惑星であり、その平均密度は約1.33 g/cm³です。一方、火星は岩石質の地球型惑星であり、平均密度は約3.93 g/cm³です。したがって、木星の平均密度は火星よりも小さいです。
よって、正しい文はbとdです。
⑥【誤】
文章cが誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
HR図上での恒星の進化の経路と、質量の大きな恒星の末期の姿に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
恒星Pは太陽よりはるかに明るく高温なので、超新星爆発を起こします。
②【正】
恒星Pは、スペクトル型がB0、絶対等級が-5程度と、HR図の左上に位置する、質量が非常に大きく高温で明るい主系列星です。
【ア】:このような大質量の恒星は、主系列星の段階を終えると、核での核融合が進み、温度をあまり変えずに光度を増しながら、赤色超巨星へと進化します。HR図上では、右(低温)かつ上(明かるい)方向へ移動します。矢印Xがこの進化の向きを表しています。
【イ】:質量が太陽の8倍以上ある大質量の恒星は、最終的に中心核が崩壊し、超新星爆発を起こしてその一生を終えます。
白色矮星になるのは、太陽程度の質量の恒星の末期の姿です。
③【誤】
進化の向き(ア)が異なります。
④【誤】
進化の向き(ア)が異なります。
⑤【誤】
進化の向き(ア)が異なります。
⑥【誤】
進化の向き(ア)が異なり、恒星Pは超新星爆発を起こします。
問5:正解②
<問題要旨>
恒星の見かけの等級、年周視差、色という観測データから、HR図上での位置を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
Aは絶対等級が0等、スペクトル型がA0型(白色)の星です。
②【正】
絶対等級を求める:年周視差 p (秒) と絶対等級 M、見かけの等級 m の間には、M = m + 5 + 5 log₁₀p という関係があります。
年周視差 p = 0.10秒、見かけの等級 m = 1.0等なので、
M = 1.0 + 5 + 5 log₁₀(0.10)
M = 6 + 5 * (-1)
M = 1
この恒星の絶対等級は1.0等です。
スペクトル型を推定する:恒星の色は表面温度に対応しており、スペクトル型で分類されます。問題の恒星は橙色なので、スペクトル型はK型に分類されます。スペクトル型はO-B-A-F-G-K-Mの順に高温(青白い)から低温(赤い)になります。太陽(G型)が黄色なので、橙色はそれより低温なK型です。
HR図上の位置を特定する:絶対等級が1.0等、スペクトル型がK型という条件に合う恒星を探します。図2を見ると、点Bがスペクトル型K0、絶対等級約1.0等に位置しており、これらの条件と一致します。点Bは主系列から少し外れた巨星です。
③【誤】
Cは絶対等級が6等、スペクトル型がA0型(白色)の白色矮星です。
④【誤】
Dは絶対等級が6等、スペクトル型がK0型(橙色)の主系列星です。