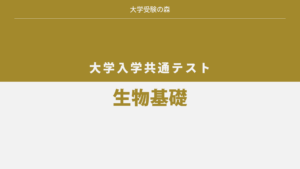解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
原核細胞と真核細胞の構造や機能に関する基本的な違いについて問う問題です。それぞれの細胞が持つ特徴を正確に理解しているかがポイントとなります。
<選択肢>
①【誤】
核酸(DNAやRNA)を構成する塩基は、アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)(RNAではウラシル(U))であり、これは原核細胞と真核細胞で共通です。塩基の種類に違いはありません。
②【誤】
酵素は、代謝(生命活動に伴う化学反応)を触媒するタンパク質であり、あらゆる生物の細胞に存在します。原核細胞も代謝を行っており、そのための酵素を持っています。
③【正】
ATPは、すべての生物がエネルギーを必要とする生命活動に用いる「エネルギーの通貨」であり、原核細胞でも真核細胞でも合成されます。しかし、ATP合成の主要な場であるミトコンドリアは、真核細胞に特有の細胞小器官であり、原核細胞には存在しません。原核細胞は細胞膜などに存在する酵素によってATPを合成します。
④【誤】
一般的に、真核細胞(約10~100μm)は原核細胞(約1~10μm)よりも大きい傾向があります。しかし、アメーバやゾウリムシなどの単細胞の真核生物や、ニワトリの卵(卵黄)のように、肉眼で観察できる大きさの真核細胞も存在します。
⑤【誤】
呼吸は、有機物を分解してエネルギーを取り出す、多くの生物に共通の仕組みです。酸素を用いて有機物を分解する好気呼吸は、真核細胞だけでなく、多くの原核細胞(好気性細菌など)も行います。
問2:正解⑤
<問題要旨>
細胞内共生の関係が成立する過程で、共生する藻類と動物細胞の代謝や遺伝子発現がどのように変化するかを考察する問題です。生物間の相互作用と、それに伴う適応的な変化を理解する力が問われます。
<選択肢>
ア:藻類は光合成を行い、有機物を生産します。したがって、共生する動物細胞に対しては、エネルギー源となる糖などの有機物を供給すると考えられます。二酸化炭素は光合成の材料であり、むしろ動物細胞の呼吸によって供給される側です。
イ:共生関係が長くなると、藻類はこれまで自ら合成していたアミノ酸などを、宿主である動物細胞から安定的に供給されるようになります。その結果、動物細胞から栄養分を効率よく取り込むためのタンパク質(輸送体など)の必要性が高まり、その遺伝子の発現は上昇すると考えられます。
ウ:動物細胞は、共生する藻類にアミノ酸などを供給する役割を担うことになります。藻類という供給先ができたことで、そのアミノ酸などをより多く生産する必要が生じる可能性があります。共生関係を維持するために、その栄養分を生成するために働くタンパク質の遺伝子発現は上昇すると考えるのが妥当です。
以上のことから、アに「糖」、イに「上昇」、ウに「上昇」が入る⑤の組み合わせが最も適当です。
問3:正解④
問3:正解④
<問題要旨>
ヒトの体細胞に含まれるDNAの総量と、DNA複製の仕組みに基づいて、複製が開始される場所の数を計算する問題です。生物の知識と基本的な計算能力が求められます。
<選択肢>
1,ヒトの体細胞の全DNA量を計算する
問題文より、ヒトの精子(配偶子、核相はn)の核には 3×109塩基対のDNAが含まれます。体細胞は核相が2nなので、そのDNA量は精子の2倍となります。
2,複製を開始する場所の数を計算する
問題文では「DNAの一つの場所で 1×105塩基対のDNAが複製される」とあります。この「場所」を複製起点と解釈し、必要な数を計算します。
- 必要な場所の数 = (全DNA量) ÷ (一つの場所で複製されるDNA量)
- (6×109) ÷ (1×105) = 60,000
3,選択肢との比較と考察
上記で計算した60,000という数値は、選択肢のいずれとも一致しません。これは、問題文の数値設定に誤植があった可能性が非常に高いと考えられます。もし、「一つの場所で複製されるDNA量」が 1×106塩基対であったと仮定して再計算すると、以下のようになります。
- (6×109)÷(1×106)=6×103=6,000この結果は選択肢④と一致します。
- したがって、問題の数値に誤植があったと想定し、計算から導かれる④が正解となります。
問4:正解①
<問題要旨>
細胞周期の各時期と、それに同調して発現量が変化するタンパク質XおよびYの情報とを結びつけ、特定の細胞がどの時期にあるかを特定する問題です。細胞周期の各段階の特徴を理解しているかが問われます。
<選択肢>
細胞周期は、分裂が終わった直後のG1期(DNA合成準備期)、S期(DNA複製期)、G2期(分裂準備期)、M期(分裂期)の順に進行します。間期はG1期、S期、G2期を合わせた期間です。
- タンパク質X: 分裂終了直後(=G1期の開始)に発現を開始し、DNAの複製中(S期)に減少します。したがって、タンパク質XはG1期に最も多く存在すると考えられます。
- タンパク質Y: DNAの複製が始まる(=S期の開始)と発現を開始し、分裂終了直後(=G1期の開始)に急速に減少します。したがって、タンパク質YはS期、G2期、M期に多く存在し、G1期にはほとんど存在しないと考えられます。
問題の細胞は、ペトリ皿に貼り付いている扁平な細胞(間期の細胞)であり、「タンパク質Xのみを発現し、タンパク質Yを発現していなかった」とあります。この条件(Xは発現するがYは発現しない)に合致する細胞周期の時期はG1期です。
問5:正解⑧
<問題要旨>
細胞周期の進行度合いが異なる細胞集団について、細胞あたりの全DNA量と、DNA複製中に取り込まれる物質Aの量を測定したグラフを解釈する問題です。細胞周期とDNA量の関係を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
グラフの横軸は全DNA量、縦軸は物質A(DNA複製中に取り込まれる)の量を示しています。
細胞周期におけるDNA量の変化は以下の通りです。
- G1期: DNA複製前の時期。DNA量は2(相対値)。
- S期: DNA複製中の時期。DNA量は2から4へ連続的に増加(相対値)。
- G2期・M期: DNA複製後の時期。DNA量は4(相対値)。
この問題では、オの細胞集団の平均DNA量を1としているため、G1期のDNA量を1、G2期・M期のDNA量を2と読み替えます。
- 細胞集団オ: 全DNA量が1で、物質Aの量が少ない。これはDNA複製前のG1期の細胞集団です。
- 細胞集団エ: 全DNA量が1から2の間に分布し、物質Aの量が多い。これはDNAを活発に複製しているS期の細胞集団です。
- 細胞集団カ: 全DNA量が2で、物質Aの量が少ない。これはDNAの複製を終えた後の細胞集団であり、G2期と**M期(分裂期)**の両方の細胞を含みます。
したがって、カの細胞集団はG2期とM期の細胞から構成されるため、⑧が最も適当です。
第2問
問1:正解⑥⑧⓪
<問題要旨>
消化酵素の働きを調べる実験において、特定の結論を導くために比較すべき実験区の組み合わせを答える問題です。科学実験の基本である「対照実験」の考え方を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
この実験では、リパーゼによって脂肪が分解されると脂肪酸が生成し、リトマスミルクが酸性(赤色)に傾くことを利用しています。
結論1:リパーゼには、脂肪を分解する作用がある。
この結論を導くには、「リパーゼがある場合」と「リパーゼがない場合(他の条件は同じ)」を比較する必要があります。
- 試験管ⓓ:リパーゼ溶液を加えた(リパーゼあり)。
- 試験管ⓑ:リパーゼ溶液の代わりに蒸留水を加えた(リパーゼなし)。
ⓓでは赤色に変化し、ⓑでは変化がほとんどないことから、リパーゼの作用が確認できます。よって、比較すべきはⓑとⓓ(選択肢⑥)です。
結論2:リパーゼは、高温で処理すると、作用しなくなる。
この結論を導くには、「通常のリパーゼ」と「高温で処理したリパーゼ」の働きを比較する必要があります。
- 試験管ⓓ:通常のリパーゼ溶液を加えた。
- 試験管ⓒ:100℃で処理したリパーゼ溶液を加えた。
ⓓでは赤色に変化し、ⓒでは変化がほとんどないことから、リパーゼが高温で失活(作用を失うこと)したことがわかります。よって、比較すべきはⓒとⓓ(選択肢⑧)です。
結論3:胆汁には、リパーゼによる脂肪の分解を助ける作用がある。
この結論を導くには、「リパーゼのみの場合」と「リパーゼと胆汁を加えた場合」を比較する必要があります。
- 試験管ⓓ:リパーゼ溶液のみを加えた。
- 試験管ⓔ:リパーゼ溶液と胆汁の粉末を加えた。
ⓔがⓓよりも濃い赤色になっていることから、胆汁がリパーゼの働きを促進したことがわかります。よって、比較すべきはⓓとⓔ(選択肢⓪)です。
問2:正解④
<問題要旨>
「胆汁の乳化作用がリパーゼの働きを促進する」という仮説を検証するための実験計画を立案する問題です。仮説を検証するために、どのような条件を設定して比較すべきかを論理的に考える力が求められます。
<選択肢>
実験2の結果から、各層が何であるかを理解します。
- 試験管①:食用油(層X)と水(層Y)が分離している。
- 試験管⑧:胆汁の働きで食用油が水中に微粒子として分散(乳化)した層Zと、乳化しきれなかった油(層X)、水(層Y)に分かれている。
仮説を検証するためには、「乳化された脂肪」と「乳化されていない脂肪」に対するリパーゼの作用を比較する必要があります。
- 乳化されていない脂肪:試験管①から採取できる層X(食用油そのもの)が適しています。
- 乳化された脂肪:試験管⑧から採取できる層Z(胆汁によって乳化された食用油)が適しています。
したがって、検証実験では 層X と 層Z を比較します(アとイに該当)。
仮説が正しければ、乳化された脂肪の方がリパーゼの作用を受けやすいため、分解が速く進みます。つまり、層Zを入れた試験管の方が、層Xを入れた試験管よりも多くの脂肪酸が生成され、より濃い赤色になると予想されます(ウに該当)。
以上のことから、アに「X」、イに「Z」、ウに「Z」が入る④の組み合わせが最も適当です。
問3:正解②
<問題要旨>
病原体の侵入を初期段階で防ぐ「自然免疫」に関する記述の中から、誤っているものを選ぶ問題です。自然免疫に関わる細胞や物質の機能を正確に覚えているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
マクロファージは、アメーバ様の運動で体内を移動し、細菌などの異物を発見すると細胞内に取り込んで消化・分解する「食作用」を持つ、自然免疫の中心的役割を担う細胞です。
②【誤】
ナチュラルキラー(NK)細胞は、ウイルス感染細胞やがん細胞を認識して攻撃するリンパ球の一種です。しかし、その攻撃方法は食作用ではなく、細胞に接触して細胞死(アポトーシス)を引き起こす物質を放出することによるものです。
③【正】
リゾチームは、唾液、涙、鼻水などに含まれる酵素で、細菌の細胞壁を分解する働きがあります。これにより、細菌の増殖を抑える化学的な防御を担っています。
④【正】
皮膚の表面を覆う角質層や、気管の表面を覆う粘液は、ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入するのを防ぐ物理的な障壁として機能します。
⑤【正】
汗に含まれる乳酸などにより、皮膚の表面は弱酸性に保たれています。多くの細菌は弱酸性の環境では増殖しにくいため、これも化学的な防御の一つです。
問4:正解④
<問題要旨>
獲得免疫(適応免疫)のうち、抗体が作られる仕組み(液性免疫)において、中心的な役割を果たす細胞間の相互作用とその場所について問う問題です。
<選択肢>
抗体産生は以下の流れで進みます。
- 体内に侵入した抗原(ウイルスなど)は、まず樹状細胞などの抗原提示細胞に取り込まれます。
- 抗原提示細胞は、リンパ液の流れに乗って最寄りのリンパ節に移動します。
- リンパ節内で、抗原提示細胞は取り込んだ抗原の断片を、ヘルパーT細胞に提示します(抗原提示)。
- 抗原提示を受けて活性化したヘルパーT細胞は、同じ抗原を認識したB細胞を活性化させ、その結果、B細胞が抗体を産生する細胞(形質細胞)へと分化します。
この一連の流れの中で、免疫応答の司令塔であるヘルパーT細胞を活性化させる「抗原提示細胞(樹状細胞)とヘルパーT細胞の接触」が極めて重要です。そして、この主要な反応が起こる場所はリンパ節です。
胸腺はT細胞が成熟する器官であり、キラーT細胞は細胞性免疫で働く細胞です。したがって、④が正解となります。
問5:正解⑥
<問題要旨>
免疫に関する3つの異なる実験の結果について、その現象を正しく説明している記述の組み合わせを選ぶ問題です。二次応答、受動免疫、細胞性免疫といった獲得免疫の多様な仕組みを総合的に理解している必要があります。
<選択肢>
まず、各マウスの状態と実験内容を整理します。
- マウスR:事前に無毒化ウイルスを注射済み。→ ウイルスWに対する記憶細胞ができており、二次応答が可能。
- マウスS:好中球がない。→ 自然免疫の一部が機能不全。
- マウスT:B細胞がない。→ 抗体を産生できず液性免疫は機能しないが、細胞性免疫(キラーT細胞などが働く)は機能する。
次に、各実験の説明を吟味します。
- 実験1:マウスRが生存できたのは、体内に作られていた記憶細胞(記憶B細胞と記憶ヘルパーT細胞)がウイルスWに素早く反応し、強力な免疫応答(二次応答)を起こしてウイルスを排除したためです。→ ⑤が適当。
- 実験2:マウスSが生存できたのは、マウスRから注射された血清中に含まれる抗体が、マウスSの体内でウイルスWを中和・排除したためです。これは、他個体で作られた抗体によって免疫を得る「受動免疫」の一例です。→ ②が適当。(記憶細胞は血球成分であり、血清には含まれません)
- 実験3:マウスTはB細胞がないため抗体を作れません。しかし、無毒化ウイルスの注射によってT細胞が活性化され、ウイルスWの抗原を認識する記憶T細胞が作られます。再度ウイルスWに感染した際、この記憶T細胞から分化したキラーT細胞が、ウイルスに感染した自己の細胞を破壊することでウイルスを排除したと考えられます(細胞性免疫)。→ ⑥が適当。
したがって、実験1、2、3を正しく説明しているのは、それぞれ⑤、②、⑥の記述です。この組み合わせを持つ⑥が正解となります。
第3問
問1:正解⑤
<問題要旨>
光合成におけるエネルギー変換の種類と、生物の体内で行われる「同化」に分類される化学反応を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
ア: 光合成は、生物が光エネルギーを、有機物中の結合エネルギーという形の化学エネルギーに変換する過程です。熱エネルギーではありません。
イ: 同化とは、単純な物質から、より複雑な物質を合成する反応のことです。この過程ではエネルギーが吸収・貯蔵されます。グルコース(単糖類)を多数つなぎ合わせてグリコーゲン(多糖類)を合成する反応は、同化の典型例です。一方、グリコーゲンをグルコースに分解するのは異化です。
ウ: ATP(アデノシン三リン酸)は「エネルギーの通貨」と呼ばれます。ADP(アデノシン二リン酸)とリン酸からATPが合成される反応は、エネルギーを蓄える反応であり、同化に分類されます。光合成や呼吸の過程でこの反応が起こります。一方、ATPがADPとリン酸に分解される反応は、エネルギーを放出する反応です。
したがって、ア「化学」、イ「グルコースからグリコーゲン」、ウ「ADP から ATP」となる⑤が正解です。
問2:正解①
<問題要旨>
水槽のような生態系における窒素循環のプロセス、特に有機窒素化合物が水草に利用されるまでの変化の順序を問う問題です 。
<選択肢>
水槽内での窒素循環は、主に以下の順で進みます。
- 餌の残りかすなどの有機窒素化合物は、微生物によって分解され、アンモニウムイオンに変わります。
- アンモニウムイオンは、硝化菌の働きによって硝酸イオンへと酸化されます。
- 水草は、この硝酸イオンなどを吸収して利用します。 この流れを正しく示しているのは、①「有機窒素 → アンモニウムイオン → 硝酸イオン → 水草」です 。
問3:正解①
<問題要旨>
水槽という閉鎖的な生態系から、物質循環の輪に入っている「窒素」を系外へ取り除くための有効な操作はどれかを考える問題です。
<選択肢>
水槽内に入った窒素は、様々な形に変化しながら生態系内を循環します。この窒素を水槽の「外」へ取り除くためには、窒素を体内に多く含んでいる生物そのものを水槽から取り出すのが最も直接的で有効な方法です。
- a: 水草は、水中の窒素化合物(硝酸イオンなど)を吸収して成長します。つまり、水草の体には多くの窒素が固定されています。したがって、茂った水草を切り取って水槽から取り除くことは、系内の窒素を系外へ排出する有効な操作です。
- b: 水草を魚に食べさせても、窒素は水草から魚の体へ移動するだけで、水槽内にとどまります。魚が排泄をすれば、窒素は再び水中へ戻ります。魚自体を水槽から取り出さない限り、窒素の除去にはなりません。
- c: 光の量を減らすと水草の成長が抑制され、水中の窒素化合物の吸収量が減ってしまいます。これは窒素を除去するどころか、水中に窒素が溜まりやすくなる原因となりえます。
したがって、窒素を取り除くための操作として適当なものはaのみであり、正解は①です。
問4:正解⑤
<問題要旨>
世界の陸上バイオーム(生物群系)の分布を示した図を読み解き、各バイオームの特徴に関する記述の正誤を判断する問題です。気候と植生の関係を理解しているかが問われます。
<選択肢>
まず、図中のアルファベットが示すバイオームを推定します。
- A: 寒冷・乾燥 → ツンドラ
- B: 亜寒帯 → 針葉樹林
- D: 温暖・湿潤 → 照葉樹林
- I: 高温・やや乾燥 → サバンナ
①【誤】
バイオームA(ツンドラ)には、夏の間、コケ植物や地衣類、草本、低木などが生育します。植物が生育できないわけではありません。
②【誤】
バイオームBは亜寒帯に分布する針葉樹林(タイガ)であり、マツやモミなどの針葉樹が優占します。低木が優占するわけではありません。
③【誤】
バイオームDは、西日本などの暖温帯に成立する照葉樹林です。日本では、本州から北海道の太平洋沿岸にかけては、主に夏緑樹林や針葉樹林が分布します。
④【誤】
バイオームFが示す気候区(温帯のステップと森林の移行帯など)は、ユーラシア大陸だけでなく他の大陸にも存在し、同様の気候条件下では似た植生が成立します。特定の大陸に特有なバイオームではありません。
⑤【正】
バイオームIは、年平均気温が高く、降水量が森林が成立するにはやや少ない地域に分布するサバンナに該当します。サバンナは、イネ科などの草本植物が優占する草原に、樹木がまばらに点在する景観が特徴です。
問5:正解③①
<問題要旨>
衛星データから得られる「緑葉の量を示す指標N」の年間を通した変化のグラフが、どのバイオームのものかを特定する問題です。各バイオームの植生の季節による変化を理解しているかが問われます。
<選択肢>
指標Nは緑葉が多いほど1に近づきます。グラフは北半球のものです。
- バイオームC(夏緑樹林): 温帯に成立し、ブナやナラなどの落葉広葉樹が優占します。夏には葉を豊かに茂らせますが、冬には落葉するため、緑葉の量は大きく季節変動します。つまり、夏(6月頃)に指標Nがピークに達し、冬にはほぼ0に近くなると考えられます。このパターンに最も合致するのはグラフ③です。
- バイオームE(熱帯多雨林): 年間を通して高温多湿な地域に成立します。常緑広葉樹がうっそうと茂り、特定の落葉期はありません。そのため、一年中、緑葉の量が非常に多く、指標Nは高い値で安定していると考えられます。このパターンに最も合致するのはグラフ①です。