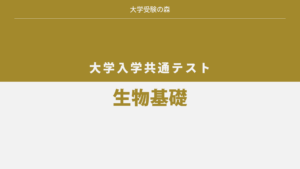解答
解説
第1問
問1:正解①
<問題要旨>
実験1・2の結果から、細胞小器官A(葉緑体)と細胞小器官B(ミトコンドリア)の働きを特定し、それぞれの特徴に関する知識を問う問題です。問1では、細胞小器官Aの働きについて問われています。
<選択肢>
①【正】
実験1で、細胞小器官Aは二酸化炭素を取り込んで酸素を発生させていることから、光合成を行う葉緑体であると判断できます。 光合成は、光エネルギーを利用してATPを合成する「光化学系」の反応と、そのATPを利用して二酸化炭素から有機物を合成する「カルビン・ベンソン回路」の反応からなります。したがって、光エネルギーを用いてATPを合成する反応に関わるという本選択肢は正しい記述です。
②【誤】
細胞小器官A(葉緑体)が行う光合成は、光エネルギーを用いて有機物を「合成」する反応であり、「分解」する反応ではありません。有機物を分解するのは呼吸です。
③【誤】
「有機物を分解して得たエネルギー」を利用するのは呼吸の働きです。また、呼吸では二酸化炭素を「放出」します。細胞小器官A(葉緑体)の働きとは異なります。
④【誤】
「有機物を分解して得たエネルギーを用いて、ATPを合成する反応」は、実験2で示された細胞小器官B(ミトコンドリア)が行う呼吸の働きです。
問2:正解④
<問題要旨>
細胞小器官A(葉緑体)と細胞小器官B(ミトコンドリア)に共通する特徴を問う問題です。実験2では、細胞小器官Bが有機物を加えてATPを合成していることから、呼吸を行うミトコンドリアであると判断できます。
<選択肢>
①【誤】
細胞小器官A(葉緑体)は植物細胞などに存在し、動物細胞には含まれません。しかし、細胞小器官B(ミトコンドリア)は、エネルギーを必要とする多くの真核細胞に共通して存在するため、植物細胞だけでなく動物細胞にも含まれます。
②【誤】
葉緑体とミトコンドリアは、どちらも細胞の核とは別に独自のDNAを持っています。これは、これらの細胞小器官がもともと独立した生物(シアノバクテリアや好気性細菌)であり、細胞内共生によって真核細胞に取り込まれたとする「細胞内共生説」の根拠の一つです。
③【誤】
葉緑体とミトコンドリアは、真核生物の細胞内に見られる細胞小器官です。原核生物の細胞内には、膜で包まれた構造を持つこれらの細胞小器官は存在しません。
④【正】
葉緑体とミトコンドリアは、どちらも独自のDNAを持ち、細胞の分裂とは独立して分裂によって増殖する能力を持っています(半自律的増殖)。これは細胞内共生説を支持する特徴の一つです。したがって、本選択肢は共通する特徴として正しい記述です。
問3:正解③
<問題要旨>
湖における水草の光合成と呼吸が、水中の溶存酸素量とpHにどのような影響を与えるかを考察する問題です。細胞小器官Aは葉緑体(光合成)、細胞小器官Bはミトコンドリア(呼吸)の働きを指します。
<選択肢>
①【誤】
アが呼吸、イが光合成という点が誤りです。昼に速度が大きくなるのは光合成です。
②【誤】
アが呼吸、イが光合成という点が誤りです。
③【正】
ア:溶存酸素量のグラフを見ると、昼間(光がある時間帯)に酸素量が増加しています。 これは、光合成によって酸素が放出されるためです。したがって、昼に速度が大きくなるアは「光合成」です。
イ:生物は昼夜を問わず常に呼吸をしています。光合成の速度は光の強さに大きく依存して変動しますが、呼吸の速度はそれに比べて大きな変動はありません。したがって、イは「呼吸」です。
ウ:pHの変動について考えます。光合成は水中の二酸化炭素(CO2)を消費し、呼吸はCO2を放出します。CO2が水に溶けると炭酸(H2CO3)を生じ、水は酸性(pHが低い)になります。昼間は光合成が呼吸を上回り、CO2が大量に消費されるため、水中のCO2濃度が低下し、pHは上昇します(アルカリ性に傾く)。夜間は呼吸のみが行われるため、CO2が水中に放出され、pHは低下します(酸性に傾く)。この変動パターンを示すのはグラフaです。
アに光合成、イに呼吸、ウにグラフaが入る選択肢は③です。
④【誤】
ウがグラフbという点が、指定された正解と異なります。
問4:正解④
<問題要旨>
生物の遺伝情報(DNA)に関する基本的な理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
生物の種が異なれば、遺伝情報であるDNAの全塩基配列も異なります。ブロッコリーとキュウリは異なる種なので、塩基配列は同一ではありません。
②【誤】
肝臓の細胞は体細胞であり、核相は複相(2n)です。一方、精子は生殖細胞であり、減数分裂によって作られるため核相は単相(n)です。したがって、精子に含まれるDNA量は、肝臓の細胞の半分になります。
③【誤】
体細胞分裂は、もとの細胞(母細胞)と全く同じ遺伝情報を持つ細胞(娘細胞)を2つ作る分裂です。そのため、分裂が起こるたびに遺伝子の種類が変化することはありません。
④【正】
一個体を構成する細胞は、もとは一つの受精卵であり、その体細胞分裂によって増殖したものです。そのため、葉や根など、からだのどの部分の細胞であっても、基本的に全く同じ遺伝情報(遺伝子のセット)を持っています。ただし、細胞の場所や役割に応じて、使われる遺伝子(発現する遺伝子)の種類が異なるため、葉や根のような形態や機能の違いが生じます。
問5:正解②
<問題要旨>
真核生物の体細胞分裂における染色体とDNAの変化に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
体細胞分裂の間期は、G1期(DNA合成準備期)、S期(DNA合成期)、G2期(分裂準備期)に分けられます。このうち、DNAの複製が行われるのはS期のみです。間期の全期間を通して行われるわけではありません。
②【正】
間期には、DNAは核内でクロマチンとして分散して存在しますが、分裂期(M期)に入ると、クロマチンが凝縮して太く短い染色体の形になります。染色体は分裂期にのみ光学顕微鏡で観察可能な形態をとります。
③【誤】
体細胞分裂では、母細胞が持つDNAを複製して2倍にした後、それを二つの娘細胞に均等に分配します。その結果、生じた娘細胞が持つDNA量は、分裂前の母細胞(G1期)のDNA量と同じになります。
④【誤】
DNAのヌクレオチド鎖は、ヌクレオチドの「リン酸」と「糖(デオキシリボース)」が交互に結合(リン酸ジエステル結合)することで形成されます。塩基は糖に結合しており、ヌクレオチド鎖の形成には直接関与しません。
問6:正解④
<問題要旨>
DNAからmRNAが合成される転写の過程を正しく図示したものを選択する問題です。転写の基本的なルールを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
図中のDNAの鎖に、DNAを構成しないはずの塩基であるウラシル(U)が含まれています。DNAはアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類の塩基からなります。
②【誤】
合成されているmRNAの鎖に、RNAを構成しないはずの塩基であるチミン(T)が含まれています。RNAはアデニン(A)、ウラシル(U)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類の塩基からなります。
③【誤】
図中のDNAの鎖にウラシル(U)が、mRNAの鎖にチミン(T)が含まれており、どちらも誤りです。
④【正】
DNAの鎖にはチミン(T)が含まれ、mRNAの鎖にはウラシル(U)が含まれており、塩基の種類は正しいです。また、転写の際の塩基の相補性を確認します。鋳型となるDNA鎖(下側)の塩基配列「CTTAAGAG」に対して、相補的なmRNAの塩基配列「GAAUUCUC」が正しく合成されています(CはGと、TはAと、AはUと対合)。したがって、この図は転写の過程を正しく示しています。
⑤【誤】
mRNAの鎖にチミン(T)が含まれており、誤りです。
⑥【誤】
DNAの鎖にウラシル(U)が含まれており、誤りです。
第2問
問1(1):正解⑤
<問題要旨>
酸素解離曲線を用いて、肺胞から組織へ酸素を供給する際に、全ヘモグロビンのうち何%が酸素を解離(放出)するかを読み取る問題です。
<選択肢>
【正・誤】
計算過程は以下の通りです。
1.肺胞での酸素ヘモグロビンの割合を読み取る。
組織にCO2を供給する前の血液は、肺胞で酸素を受け取ります。問題文のグラフの注釈から、肺胞の酸素濃度は100です。また、肺胞では組織から運ばれてきた二酸化炭素を放出するため、二酸化炭素濃度は低くなります。したがって、「二酸化炭素濃度が低いときの曲線」を用います。グラフから、酸素濃度100のときの酸素ヘモグロビンの割合は96%であることがわかります。
2.組織での酸素ヘモグロビンの割合を読み取る。
組織では細胞の呼吸によって二酸化炭素が放出されるため、二酸化炭素濃度は高くなります。したがって、「二酸化炭素濃度が高いときの曲線」を用います。問題文の注釈から、組織での酸素濃度は30とされています。グラフから、酸素濃度30のときの酸素ヘモグロビンの割合は30%であることがわかります。
3.酸素を解離したヘモグロビンの割合を計算する。
組織で酸素を解離するヘモグロビンの割合は、肺胞での割合と組織での割合の差で求められます。
96%(肺胞) – 30%(組織) = 66%
したがって、アに入る数値として最も適当なものは⑤の66です。
問1(2):正解③
<問題要旨>
問7に続き、酸素解離曲線と問題文の情報を用いて、1分間に全身の組織が受け取る酸素の総量を計算する式を完成させる問題です。
<選択肢>
【正・誤】
計算式「H × (ア/100) × イ × ウ」が「1分間に全身の組織が受け取ることのできる酸素の量(mL)」となるように、イとウを考えます。
・Hは「血液1L中に含まれるヘモグロビン量(g)」です。
・アは問7で求めた「組織で酸素を解離するヘモグロビンの割合(%)」です。
・H × (ア/100) は、「血液1Lあたり、酸素を解離するヘモグロビンの量(g)」を意味します。
ウ:次に、このヘモグロビンの量が何mLの酸素に相当するかを考えます。問題文に「1gのヘモグロビンは最大1.4mLの酸素と結合できる」とあるので、酸素を解離したヘモグロビンの量(g)に1.4を掛けることで、放出された酸素の量(mL)が計算できます。したがって、ウには「1.4」が入ります。
・H × (ア/100) × 1.4 で、「血液1Lが組織に供給する酸素の量(mL)」が計算できます。
イ:最後に、1分間あたり全身の組織が受け取る総量を求めます。そのためには、「血液1Lあたりの酸素供給量」に「1分間に組織に送り出される血液の総量(L)」を掛ける必要があります。問題文に「安静時には、1分間当たり約5Lの血液が、体循環として心臓から全身の組織に送り出される」とあります。したがって、イには「1分間に心臓から全身の組織に送り出される血液量(L)」が入ります。
以上より、イに「1分間に心臓から全身の組織に送り出される血液量(L)」、ウに「1.4」が入る③が正解です。
問2:正解④
<問題要旨>
ヘモグロビンによる酸素運搬に関する記述の中から、適当でないものを選択する問題です。
<選択肢>
①【正】
運動時は、安静時よりも組織での呼吸が活発になり、酸素消費量が増え、二酸化炭素濃度が高まります。二酸化炭素濃度が高まると、酸素解離曲線が右下にシフトし(ボーア効果)、より多くの酸素がヘモグロビンから解離しやすくなります。その結果、組織に送り出される酸素の量は多くなります。
②【正】
肺胞における酸素の供給量、すなわち肺胞の酸素濃度が低下すれば、ヘモグロビンと結合する酸素の量も減少し、血液が運搬できる酸素の最大量が低下します。
③【正】
酸素解離曲線を見ると、通常の酸素濃度(相対値100)では酸素ヘモグロビンの割合は96%です。大気中よりも高い濃度の酸素を吸入すると、肺胞の酸素濃度がさらに上昇し、酸素ヘモグロビンの割合を100%に近づけることができます。
④【誤】
問7の計算で見たように、組織を通過した後の血液(静脈血)でも、ヘモグロビンの30%はまだ酸素と結合しています。つまり、ヘモグロビンは組織で必要な分の酸素を放出した後も、ある程度の酸素と結合したまま肺胞に戻ります。酸素を一度全て解離するわけではありません。
⑤【正】
酸素解離曲線が示すように、組織における酸素濃度が同じであっても、二酸化炭素濃度が高い方が曲線は右下に位置します。これは、同じ酸素濃度でも酸素ヘモグロビンの割合が低いことを意味し、ヘモグロビンが酸素を解離しやすくなっていることを示しています。
問3:正解②
<問題要旨>
暑い時の体温調節の仕組み、特に発汗に関する神経や中枢の働きを正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
カが誤りです。発汗は、汗が蒸発する際の気化熱によって体表から熱を奪うことで、熱の「放散を促進」する働きです。
②【正】
エ:体温調節の中枢は、間脳の「視床下部」にあります。視床下部が体温の変化を感知します。
オ:発汗を指令する自律神経は「交感神経」です。交感神経が興奮すると、皮膚にある汗腺(エクリン腺)からの発汗が促進されます。
カ:発汗による汗の蒸発は、体から熱を奪う(気化熱)ため、熱の「放散を促進」し、体温の上昇を防ぎます。
したがって、この組合せは正しいです。
③【誤】
オとカが誤りです。発汗を指令するのは交感神経であり、汗の蒸発は熱の放散を促進します。
④【誤】
オが誤りです。発汗を指令するのは交感神経です。
⑤【誤】
エとカが誤りです。体温調節の中枢は視床下部であり、発汗は熱の放散を促進します。
⑥【誤】
エが誤りです。体温調節の中枢は視床下部です。
⑦【誤】
エ、オ、カの全てが誤りです。
⑧【誤】
エとオが誤りです。体温調節の中枢は視床下部、発汗の指令は交感神経です。
問4:正解①
<問題要旨>
寒い時の体温調節として、ホルモンが関わる仕組みについて、誤っている記述を選択する問題です。
<選択肢>
①【誤】
寒い時、体温調節中枢である視床下部からの指令は、交感神経を通じて副腎髄質に伝えられ、アドレナリンの分泌を促進します。また、視床下部は脳下垂体前葉を刺激するホルモンを分泌します。脳下垂体後葉は、副腎髄質を刺激するホルモンを分泌しません。脳下垂体後葉から分泌されるホルモンはバソプレシン(抗利尿ホルモン)とオキシトシンです。したがって、この記述は誤りです。
②【正】
寒い時、視床下部から放出ホルモンが分泌され、これが脳下垂体前葉を刺激します。刺激を受けた脳下垂体前葉は、甲状腺刺激ホルモン(TSH)を分泌し、これが血流に乗って甲状腺を刺激します。
③【正】
交感神経の末端から放出される神経伝達物質や、視床下部からの指令で興奮した交感神経によって、副腎髄質からアドレナリンが分泌されます。アドレナリンは心拍数を増加させたり、肝臓でのグリコーゲンの分解を促進したりして血糖濃度を上げ、細胞の代謝を促進します。
④【正】
脳下垂体前葉から分泌された甲状腺刺激ホルモンによって刺激された甲状腺は、チロキシンというホルモンを分泌します。チロキシンは、全身の細胞の代謝を促進する(熱産生量を増やす)働きがあります。
問5:正解②
<問題要旨>
寒い時に起こる反応のうち、「熱の産生を促進する反応」に分類されるものを正しく選択する問題です。「熱の放散を抑制する反応」と区別することがポイントです。
<選択肢>
【正・誤】
a. 皮膚の血管が収縮する:皮膚の血管が収縮すると、体表近くを流れる血液の量が減ります。これにより、体内の熱が外に逃げるのを防ぎます。これは「熱の放散を抑制する」反応です。
b. 立毛筋が収縮する(鳥肌が立つ):立毛筋が収縮すると、体毛が逆立ちます。毛の多い動物では、毛の間に空気の層ができて断熱効果が高まります。これも「熱の放散を抑制する」反応です。
c. 心拍数が上昇する:寒い時には、アドレナリンやチロキシンの働きで全身の代謝が促進され、熱の産生量が増加します。心拍数の上昇は、この代謝促進に伴う反応の一つであり、全身の細胞へ酸素や栄養分を効率よく供給することで、熱産生を支えます。したがって、これは「熱の産生を促進する」反応に関連する現象です。
以上より、熱の産生を促進する反応はcのみです。したがって②が正解です。
第3問
問1:正解①⑤(順不同)
<問題要旨>
極相林の優占種(ミズナラ)と、農耕地の雑草(シロザ)の種子の性質に関する実験結果を読み取り、正しく考察している記述を二つ選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
実験1で、ミズナラの種子は光の届かない土の中に埋めてから1か月でほとんどが発芽しています。これは、発芽に適した条件であればすぐに発芽し、長期間土壌中で休眠状態で残る(埋土種子となる)ことが少ない性質を示しています。したがって、この記述は正しいです。
②【誤】
実験1では、ミズナラの種子は「光の届かない土の中」で発芽しています。このことから、ミズナラの種子発芽に光は必須ではないと考えられます。したがって、「暗い林床では発芽できない」という記述は実験結果と矛盾します。
③【誤】
実験2で、シロザの種子の発芽率を比較すると、土の中に埋めていた期間が1か月の場合は10%ですが、15か月後には40%に上昇しています。したがって、「期間が短いほど、発芽率が高い」という記述は誤りです。
④【誤】
実験2から、シロザの種子は「湿った明るい場所」で発芽が促進されることがわかります。したがって、発芽させないためには、この条件を避けるべきです。この記述は目的と手段が逆になっており、誤りです。
⑤【正】
実験1・2から、シロザの種子は土の中(暗い場所)では発芽せずに長期間生存し、地表面(明るい場所)に出ると発芽することがわかります。農地を耕す(耕作)行為は、土中の種子を地表面に移動させることになります。したがって、この記述は実験結果に基づく正しい考察です。
⑥【誤】
実験1で、シロザの種子は27か月(2年以上)経過しても発芽せずに生存していることが示されています。したがって、2年間除草したとしても、土の中にはまだ発芽能力のある埋土種子が残っていると考えられます。この記述は誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
二次遷移の初期段階における植生や環境の特徴について、適当でない記述を選択する問題です。一次遷移との違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
遷移の初期に侵入・定着する種は、日当たりの良い裸地などを好む陽生植物(パイオニア植物)が中心です。二次遷移でも、森林伐採跡地などの明るい場所から遷移が始まるため、陽生植物が優占します。
②【誤】
二次遷移は、例えば山火事や森林伐採の跡地など、土壌や埋土種子、有機物などがすでに存在する場所から始まります。一方、「水分や栄養塩類の乏しい環境」というのは、溶岩台地や岩場など、土壌が全くない状態から始まる一次遷移の初期段階の特徴です。したがって、この記述は二次遷移の説明としては適当ではありません。
③【正】
二次遷移の場には、前の植生に由来する落葉や落枝などの有機物が土壌中に豊富に存在します。これらは分解者(細菌や菌類など)の働きによって分解され、植物が利用できる無機物となり、植生の速やかな回復を支えます。
④【正】
二次遷移は、土壌や種子などがすでに存在する状態から始まるため、土壌形成から始まる一次遷移に比べて、植生の変化(遷移)の進行速度が速いという特徴があります。
問3:正解①⑤(順不同)
<問題要旨>
生態系における物質循環とエネルギーの流れに関する基本的な原則について、正しい記述を二つ選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
物質は生態系内を循環します。例えば、水は蒸発、降水、河川などを通じて陸上と水界(海洋、湖沼など)の間を循環します。炭素や窒素なども、様々な形で両生態系間を移動し、地球規模で循環しています。
②【誤】
動物は、体外から取り入れた無機窒素化合物(アンモニウムイオンや硝酸イオンなど)から、アミノ酸やタンパク質などの有機窒素化合物を合成することはできません。動物は、他の生物(植物や他の動物)を食べることによって有機窒素化合物を摂取します。
③【誤】
炭素は、生物間の「食う―食われる」の関係だけでなく、生物の呼吸による大気中への放出や、植物の光合成による大気からの吸収など、生物と非生物的環境(大気、水、土壌など)との間でも循環しています。
④【誤】
エネルギーは生態系内を一方向に流れ、循環はしません。生物が有機物を分解して得たエネルギーの一部は熱エネルギーとして放出されます。この熱エネルギーが、再び光合成などで化学エネルギーに変換されて利用されることはありません。
⑤【正】
生態系に投入されるエネルギーの源は、主に太陽の光エネルギーです。このエネルギーは、生産者から各次の消費者へと食物連鎖を通じて移動しますが、各段階で呼吸によって熱エネルギーとして失われ、最終的には生態系外(宇宙空間)へ放出されていきます。
⑥【誤】
生態系に入ってきた太陽の光エネルギーのうち、生産者である植物が光合成によって化学エネルギーに変換できるのは、ごく一部(1%程度)です。大部分は反射されたり、熱として失われたりします。
問4:正解⑧
<問題要旨>
キーストーン種であるヒトデと、そうではないトキの生態系への影響の違いを、食物網の図から読み取り、文章の空欄を埋める問題です。
<選択肢>
【正・誤】
ア:ヒトデもトキも、他の動物を食べる消費者です。植物などを食べる一次消費者ではなく、他の動物を捕食するため、「二次以上の消費者」となります。
イ:図を見ると、トキはドジョウ(水田)、陸上性昆虫(陸上)、ミミズ(土中)など、異なる環境に生息する多様な動物を食べています。一方、ヒトデが食べるカサガイ類、イガイ、フジツボ類は、いずれも岩礁という限られた環境に生息しています。したがって、トキは採餌する環境が「多様な」といえます。
ウ:トキが食べる動物種は、それぞれ生息環境が異なるため、お互いの種間での競争などの関わりは比較的「弱い」と考えられます。一方、ヒトデが食べる動物種は、同じ岩礁の表面という場所をめぐって激しく競争しています。特にイガイは競争力が強く、ヒトデがいないと他の種を排除して独占してしまいます。このような強い競争関係がある環境では、捕食者であるヒトデの役割が大きくなります。
以上のことから、アに「二次以上の消費者」、イに「多様な」、ウに「弱い」が入る⑧が最も適当です。