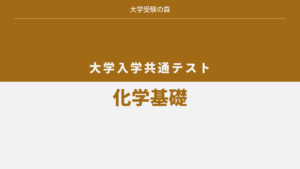解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
原子の構造、特に原子番号、質量数、中性子の数の関係を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
11はナトリウム(Na)の原子番号であり、陽子の数(または電子の数)を示します。
②【正】
ナトリウム(Na)の原子量は23です。原子量(質量数)は陽子の数と中性子の数の和です。原子番号(陽子の数)は11なので、中性子の数は 23 (質量数) – 11 (陽子の数) = 12 となります。
③【誤】
23はナトリウム(Na)の原子量(質量数)であり、陽子の数と中性子の数の和を示します。
④【誤】
34は、質量数(23)と原子番号(11)を足した数 (23 + 11 = 34) であり、中性子の数ではありません。
問2:正解③
<問題要旨>
分子の極性について理解しているかを問う問題です。分子の形と、各結合の極性の打ち消し合いを考えます。
<選択肢>
①【誤】
アンモニア(NH3)は三角錐形の分子構造をとります。N-H結合には極性があり、分子全体として極性が打ち消されず、窒素(N)原子側が負、水素(H)原子側が正に帯電する極性分子です。
②【誤】
硫化水素(H2S)は水(H2O)と同様の折れ線形の分子構造をとります。H-S結合には極性があり、分子全体として極性が打ち消されず、硫黄(S)原子側が負、水素(H)原子側が正に帯電する極性分子です。
③【正】
酸素(O2)は、同じ酸素原子同士が結合した直線形の二原子分子です。同じ原子間の結合(O=O)であるため、電子の偏りがなく、結合自体に極性がありません。したがって、無極性分子です。
④【誤】
エタノール(C2H5OH)は、分子内に電気陰性度の大きい酸素原子(O)を含むヒドロキシ基(-OH)を持っています。C-O結合およびO-H結合の極性が非常に大きいため、分子全体として強い極性を持つ極性分子です。
問3:正解④
<問題要旨>
ハロゲン(17族元素)の性質に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
ハロゲンはすべて17族元素であり、属する周期(原子番号)に関わらず、価電子の数は常に7個です。
②【誤】
イオン化エネルギーは、同族元素では原子番号が大きいほど(周期表の下にいくほど)、原子半径が大きくなるため、原子核と価電子の引力が弱まり、小さくなる傾向があります。
③【誤】
塩化水素(HCl)分子では、電気陰性度は水素(H)よりも塩素(Cl)の方が大きいため、共有電子対は塩素原子の方に強く引き付けられ、偏っています。
④【正】
ヨウ素(I2)と硫化水素(H2S)が反応すると、 I2+H2S→2HI+S という反応が起こります。この反応で、ヨウ素(I2)の酸化数は0から-1に減少し(還元され)、硫化水素(H2S)中の硫黄(S)の酸化数は-2から0に増加しています(酸化されています)。相手(H2S)を酸化する物質は酸化剤と呼ばれるため、I2は酸化剤としてはたらいています。
問4:正解⑥
<問題要旨>
純物質を加熱したときの状態変化と温度変化のグラフ(加熱曲線)の各領域における物質の状態を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
Aは固体状態であり、温度が上昇しています。絶対零度でない限り、物質を構成する粒子(分子)は常に熱運動(固体では格子振動)をしています。
イ【正】
Bは温度が一定の区間で、融解が起こっています。ここでは固体と液体が共存しています。
ウ【誤】
Cは液体状態であり、温度が上昇しています。液体状態では、分子は規則正しい配列を失い、流動性を持っています。規則正しい配列を維持しているのは固体状態(A)です。
エ【正】
Dは温度が一定の区間で、沸騰が起こっています。沸騰とは、液体の表面からだけでなく、内部からも気化が激しく起こる現象です。
オ【誤】
Eは気体状態、Cは液体状態です。一般に、気体状態の分子間平均距離は、液体状態や固体状態に比べてはるかに大きくなります。
したがって、正しい記述はイとエの組合せである⑥です。
問5:正解④
<問題要旨>
二酸化炭素(CO2)とメタン(CH4)という基本的な分子の構造、結合、性質に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
二酸化炭素(CO2)は、C原子が両側のO原子と二重結合した O=C=O という直線形分子です。
②【正】
メタン(CH4)は、C原子を中心に4つのH原子が正四面体の頂点方向に結合した、正四面体形の分子構造をとります。
③【正】
二酸化炭素(CO2)は非金属元素のCとO、メタン(CH4)は非金属元素のCとHが結合しており、どちらも共有結合によって形成される分子です。
④【誤】
常温・常圧(同温・同圧)において、気体の密度はモル質量(分子量)に比例します。
CO2の分子量 = 12 + 16×2 = 44
CH4の分子量 = 12 + 1.0×4 = 16
CO2の方が分子量が大きいため、密度はCO2の方がCH4より大きくなります。したがって、「二酸化炭素の方がメタンより小さい」という記述は誤りです。
問6:正解④
<問題要旨>
混合気体の平均分子量(または全物質量と全質量)から、成分気体の物質量の割合を計算する問題です。
<選択肢>
ヘリウム(He)の原子量は 4.0 、窒素(N2)の分子量は 14×2 = 28.0 です。
混合気体 1.00 mol のうち、He の物質量を x (mol) とすると、N2 の物質量は (1.00−x) (mol) となります。
混合気体の全体の質量は 10.0 g なので、以下の式が成り立ちます。
(He の質量) + (N2 の質量) = (全体の質量)
4.0×x+28.0×(1.00−x)=10.0
4.0x+28.0−28.0x=10.0
−24.0x=10.0−28.0
−24.0x=−18.0
x=18.0/24.0=3/4=0.75 (mol)
混合気体 1.00 mol 中に He は 0.75 mol 含まれるため、その物質量の割合は 75 % です。
① 30
② 40
③ 67
④ 75
⑤ 90
問7:正解③
<問題要旨>
アルミニウム(Al)とその化合物に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
ジュラルミンは、アルミニウムを主成分とする合金で、軽量かつ高強度であるため、航空機の機体材料などに広く利用されています。
②【正】
アルミニウムの製錬(ボーキサイトからアルミナを経て、融解塩電解で単体を得る)は、非常に多くの電力を消費します。一方、アルミニウム缶をリサイクルして再生する(溶かして再利用する)方が、必要なエネルギーははるかに少なくて済みます。
③【誤】
アルミナ(Al2O3)は酸化アルミニウムです。化合物中の酸素原子(O)の酸化数は通常 -2 です。Al2O3 全体での酸化数の総和は 0 となるため、アルミニウム原子(Al)の酸化数を x とすると、
2x+3×(−2)=0
2x−6=0
2x=6
x=+3
したがって、Alの酸化数は +3 です。「+2である」という記述 は誤りです。
④【正】
アルミニウム(Al)、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)などの金属は、濃硝酸に触れると表面に緻密な酸化物の被膜(不動態)を形成します。この被膜が内部を保護するため、それ以上は溶解しなくなります。
問8:正解③
<問題要旨>
金属のイオン化傾向の大小関係を理解し、水溶液中の金属イオンと単体金属の間で酸化還元反応(金属の析出)が起こるかどうかを判断する問題です。
<選択肢>
金属が析出する反応は、水溶液中の金属イオンよりも、浸した金属片の金属原子の方がイオン化傾向が大きい場合に起こります。
主な金属のイオン化傾向は、(大) Zn > Sn > Pb > Cu > Ag (小) です。
① 塩化スズ(II) (Sn²⁺) + 亜鉛 (Zn)
イオン化傾向は Zn > Sn です。Znが溶け出し(Zn → Zn²⁺)、Sn²⁺が還元されてSnが析出します。
② 硫酸銅(II) (Cu²⁺) + 亜鉛 (Zn)
イオン化傾向は Zn > Cu です。Znが溶け出し(Zn → Zn²⁺)、Cu²⁺が還元されてCuが析出します。
③ 酢酸鉛(II) (Pb²⁺) + 銅 (Cu)
イオン化傾向は Pb > Cu です。浸した金属(Cu)の方がイオン化傾向が小さいため、Cuは溶け出さず、Pb²⁺も還元されません。したがって、金属は析出しません。
④ 硝酸銀 (Ag⁺) + 銅 (Cu)
イオン化傾向は Cu > Ag です。Cuが溶け出し(Cu → Cu²⁺)、Ag⁺が還元されてAgが析出します。
したがって、金属が析出「しない」のは③です。
問9:正解②
<問題要旨>
酸と塩基の中和滴定における量的関係から、未知の溶液のモル濃度を求める計算式を導出する問題です。
<選択肢>
中和反応では、酸が出す H+ の物質量と、塩基が出す OH− の物質量が等しくなります。
公式: a×C×V=a′×C′×V′
a:酸の価数
C:酸のモル濃度 (mol/L)
V:酸の体積 (L または mL)
a′:塩基の価数
C′:塩基のモル濃度 (mol/L)
V′:塩基の体積 (L または mL)
問題文 より、
a=2 (2価の強酸)
C=? (求めたい値) (mol/L)
V=5 (mL) (ホールピペットではかり取った体積)
a′=1 (水酸化ナトリウム NaOH は1価の塩基)
C′=x (mol/L)
V′=y (mL) (中和に要した体積)
(途中で加えた水 30mL は、コニカルビーカー内の酸の「物質量」には影響しないため、計算には用いません)
値を代入します。
2×C×5=1×x×y
10×C=xy
C=10xy (mol/L)
① 5xy
② 10xy
③ 35xy
④ 5+yxy
⑤ 70xy
⑥ 35+yxy
⑦ 2(5+y)xy
⑧ 2(35+y)xy
第2問
問1:(a)正解②②①(b)正解④
<問題要旨>
a. 化学反応式の係数を決定する問題です。
b. 反応前後でのクロム(Cr)原子の酸化数の変化を問う問題です。
<選択肢>
a (ア, イ, ウ)
与えられた反応式:ア CrO42-+ イ H+→ ウ Cr2O72-+ H2O
反応式の右辺 H2O の係数を 1 と仮定し、反応の前後で原子の数が等しくなるように係数を合わせます。
- H原子: 右辺は H2Oに 2個。左辺はH+にイ個。よって、イ = 2。
- Cr原子: 左辺はCrO42-にア個。右辺はCr2O72-に2ウ個。よって、ア = 2ウ。(2)
- O原子: 左辺はCrO42-に 4ア 個。右辺はCr2O72-に 7ウ 個とH2Oに 1個。よって、4ア = 7ウ + 1。(3)
(2)の ア = 2ウ を(3)に代入します。
4(2ウ)=7ウ+1
8ウ=7ウ+1
ウ=1
これを(2)に代入して ア を求めます。
ア = 2 × (1) = 2
したがって、ア=2、イ=2、ウ=1となります。
b (エ)
反応前後のCrの酸化数を求めます。酸素(O)の酸化数を -2 とします。
・ CrO42- (クロム酸イオン)
Crの酸化数を x とすると、イオン全体の電荷が -2 なので、
x+4×(−2)=−2
x−8=−2
x=+6
・ Cr2O72- (ニクロム酸イオン)
Crの酸化数を x とすると、イオン全体の電荷が -2 なので、
2x+7×(−2)=−2
2x−14=−2
2x=12
x=+6
酸化数は反応前後で +6 から +6 へと変化していません。
問2:正解②
<問題要旨>
実験操作IV(滴下)で用いる適切な実験器具を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
メスフラスコ は、一定体積の溶液を正確に調製(希釈)するために用いる器具です(操作I で使用)。
②【誤】
ホールピペット は、一定体積の液体を正確にはかり取るために用いる器具です(操作I 、操作II で使用)。
③【誤】
コニカルビーカー は、滴定を受ける溶液を入れるために用いる器具です(操作II で使用)。
④【正】
ビュレット は、滴下した溶液の体積を正確に読み取るために用いる器具であり、滴定操作(操作IV )で滴下する側に用います。
問3:正解②⑤
<問題要旨>
実験操作全体および実験結果に関する記述の正誤を判断し、誤りを含むものを二つ選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
操作Iでメスフラスコを用いて希釈する際、どうせ標線まで純水を加えるため、使用前にメスフラスコが純水でぬれていても、はかり取ったしょうゆ(5.00mL)中のCI⁻の物質量は変わらず、最終的に調製される希釈溶液の濃度にも影響しません。
②【誤】
この実験は、CI⁻(分析対象)をAg⁺(滴定液)で滴定し、CrO4²⁻(指示薬)で終点を検出するものです。Ag2CrO4(クロム酸銀)は指示薬ではなく沈殿物であり、KNO3(硝酸カリウム)はAg⁺を含まないためCI⁻と反応しません。これらを用いても滴定は行えません。
③【正】
この実験で求まるのは、しょうゆに含まれるすべての塩化物イオン(CI⁻)のモル濃度です。もししょうゆにNaClの他にKCIが含まれていた場合、求めたCI⁻濃度は(NaCl由来のCI⁻ + KCI由来のCI⁻)の合計値となります。この合計値をすべてNaCl由来として計算すると、実際のNaCl濃度よりも高い値が算出されます。
④【正】
元のしょうゆのCI⁻濃度を Corig、希釈溶液の体積を Vdil、AgNO3の滴下量を VAg とすると、希釈操作(5.00mLを250mLへ、50倍希釈 )と中和点の関係 Cdil×Vdil=CAg×VAg (CAg=0.0200 ) および Corig=Cdil×50 から、
Corig=CAg×VAg ×50 / Vdil=0.0200×VAg×50 / Vdil = VAg / Vdil
という関係が導かれます。(単位がmLのままで計算可能)
しょうゆB: CB=15.95 mL/5.00 mL=3.19 (mol/L)
しょうゆC: CC=13.70 mL/10.00 mL=1.37 (mol/L)
しょうゆBの濃度の半分は 3.19/2=1.595 (mol/L) です。
Cの濃度(1.37)はBの濃度の半分(1.595)以下であるため、この記述は正しいです。
⑤【誤】
④の計算と同様に、しょうゆAの濃度を計算します。
しょうゆA: CA=14.25 mL/5.00 mL=2.85 (mol/L)
A(2.85), B(3.19), C(1.37)を比較すると、CI⁻のモル濃度が最も高いのは しょうゆB です。「最も高いものは、しょうゆAである」という記述は誤りです。
問4:正解①
<問題要旨>
硝酸銀水溶液の滴下量と、生成する塩化銀(AgCl)沈殿の質量の関係を示すグラフを選ぶ問題です。
<選択肢>
滴定開始から終点(滴下量 a )までは、加えた銀イオン(Ag⁺)はすべて試料中の塩化物イオン(CI⁻)と反応し、AgClの沈殿を生成します。 Ag++Cl-→AgCl↓
この区間では、加えたAgNO3水溶液の体積(滴下量)に比例して、AgCl沈殿の質量は直線的に増加します。
終点(a)に達すると、試料中のCI⁻がすべて消費されます。そのため、それ以上AgNO3水溶液を加えても新たなAgCl沈殿は生成せず、AgClの沈殿質量は一定になります。(加えたAg⁺は指示薬のCrO4²⁻と反応し始めます )
この関係を示すグラフは、原点(0,0)から点(a, y)まで直線的に増加し、その後は水平(一定)になる① です。
問5:正解⑤②⑤
<問題要旨>
a. 実験結果から、しょうゆAのCI⁻モル濃度を計算する問題。
b. aで求めたモル濃度を用い、一定体積のしょうゆに含まれるNaClの質量を計算する問題。
<選択肢>
a (解答番号 18)
問3の④⑤の解説で計算した通り、元のしょうゆのCI⁻濃度 Corig は Corig=VdilVAg で求められます。
しょうゆAについて、操作IIではかり取った希釈溶液の体積 Vdil=5.00 (mL)、操作Vで記録したAgNO3水溶液の滴下量 VAg=14.25 (mL) です。
CA=14.25 mL/5.00 mL=2.85 (mol/L)
選択肢⑤ 2.85 が正解です。
b (解答番号 19, 20)
15mL (0.015 L) のしょうゆAに含まれるNaClの質量を求めます。
- CI⁻の物質量 (mol)
nCl=CA×V=2.85 mol/L×0.015 L=0.04275 (mol) - NaClの物質量 (mol)
CI⁻はすべてNaCl由来と仮定する ため、nNaCl=nCl=0.04275 (mol) - NaClの質量 (g)
NaClの式量は 58.5 です。
m=nNaCl×(式量)=0.04275 mol×58.5 g/mol
m=2.500875 (g) - 解答形式
数値を小数第1位まで で表すため、小数第2位を四捨五入して 2.5 (g) となります。
形式 19.20 g に当てはめると、
19 = ②
20 = ⑤
となります。